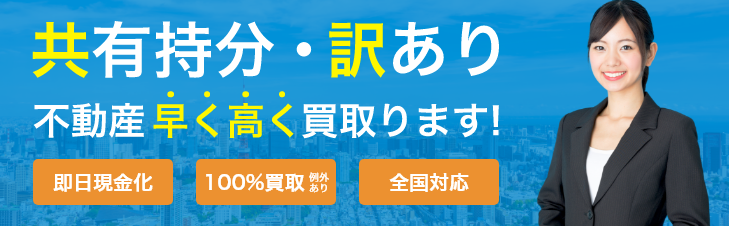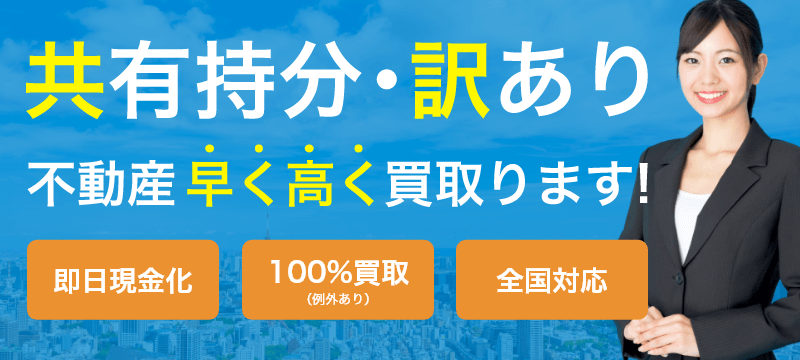マイホームを夫婦共有の名義で購入してたにも関わらず離婚になってしまった場合、 原則として、共有持分についても「離婚調停」を行なった上で財産分与を行い、再分配することになります。
一方で、このようなケースでは双方が納得する形で分配しようと思っても、上手くいかないケースは多々あることでしょう。
今回は、そのような場合に備えて、知っておくべき「離婚調停における共有不動産の扱い方」について解説します。
目次
離婚時に共有持分の売却が不利な理由
共有持分の売却自体は離婚調停中であっても行えますが、一般的には不利になりやすいといえます。その主な理由は、離婚時の財産分与で共有不動産を1/2ずつ分割する必要があるからです。
以下より、詳細を解説していきます。
財産分与において共有不動産は1/2で配分しなければならない
共有名義で購入したマイホームは離婚時に財産分与の対象となります。民法によれば、「夫婦が婚姻中に築いた財産は原則として1/2ずつ分ける」とのこと。したがって、マイホームも同様に分割する必要があります。
ただし、特殊な技能や資格に基づいて財産が築かれた場合、分与割合が変わる可能性も考えられます。双方が合意すれば自由に分与割合を決めることができます。
夫婦間で共有物分割請求をしたほうが良いケースとは?
共有物分割請求とは、もう一方の共有者に対して、当該物件を物理的、あるいは金銭的に分割して再分配する手続きです。
以下のようなケースでは、離婚前であっても共有物分割請求が検討できるでしょう。
- マイホーム購入時の出資額に大きな差がある
- 相手が離婚届に印を押さない
- 離婚調停が長引き、固定資産税などの負担が心配
共有者は分割請求の申し立てがあれば、協議に応じなければなりません。ただし、夫婦間の共有物分割請求に関しては、経済事情や離婚後の住居確保などから認められないこともあります。
これは、分割請求権の行使によって他方に不当な損害が発生する場合、「権利濫用」と判断されるため。権利濫用の適用はケースバイケースですので、専門家に相談しましょう。
共有持分はどのタイミングから自由に売却できる?
財産分与が確定し、離婚調停が終了した後、自分に分与された持分を売却することが可能です。財産分与を行わないまま離婚した場合でも、後から相手に対して財産分与を請求できることが民法で定められています。
ただし、離婚後2年が経過すると、財産分与請求権は消滅します。そのため、期間内に財産分与を行い、自分の持分を確定させることが重要です。
離婚時にマイホームの共有状態を解消する方法
離婚が決まった際、マイホームの共有状態を解消することで、後々のトラブルを防げます。共有状態の解消方法は、マイホームの売却や単独名義への変更が考えられます。
解消方法は、離婚後もどちらかが物件に住むか、ローンの残債状況によって異なるため、詳細をみていきましょう。
マイホームを売却する
離婚後にマイホームに住む予定がなければ、売却を検討することが一般的です。住宅ローンを利用している場合、残債状況によって対応が変わります。
ローンが完済済みであれば、売却益を財産分与で分割することが通例で、売却前に譲渡所得税の支払いが必要です。ローン残債があり、売却価格が残債を上回る場合(アンダーローン)状態でも、売却益でローン返済が可能です。
ただし、ローンの残債を下回るオーバーローンの場合は、任意売却が必要になります。任意売却は、金融機関の承認を得て行う売却方法。オーバーローン状態では、通常マイホームは財産分与の対象にならないものの、協議次第で分与対象となることもあります。
単独名義に変更する
離婚後もどちらかがマイホームに住む場合、ローンが完済していれば、法務局で名義変更手続きが必要です。ただし、登録免許税や不動産取得税がかかりますので注意しましょう。
残債がある場合、金融機関から契約違反とされ、名義変更ができないこともあります。そのような場合、金融機関から残債の一括請求がある恐れがあるため、専門家への事前相談が重要です。
離婚時に共有関係を解消しないとどうなる?
共有名義のままだと、売却やリフォームの際に共有者の同意が必要となります。さらに、固定資産税も基本的に折半する必要があるため注意しましょう。
離婚後の売却が難しくなる
共有名義のマイホームを売却する際、全体の売却には共有者の同意が必要です。そのため、意見が割れた場合、売却ができません。
共有持分だけの売却も、一部権利であるため買い手が見つかりにくく、市場価格より低くなるケースが考えられます。訳あり物件の買取専門業者に相談すれば、短期間で売却が可能です。
固定資産税を支払い続けることになる
物件に住んでいない共有者は、他方の共有者に家賃を請求することができます。その場合、得た家賃を固定資産税に充てるか、「家賃請求をしない代わりに固定資産税も支払わない」と交渉することが考えられます。
まとめ
婚調停の際、共有不動産の扱いは注意が必要です。共有持分の扱いに悩む場合は、財産分与や名義変更の手続きを適切に行い、将来的なトラブルを避けることが求められます。
また、共有関係を解消しないと、売却やリフォームが難しくなるだけでなく、固定資産税の支払いも継続されることになります。不安があるなら、早い段階で専門家への相談も検討しましょう。
本ブログで情報発信を行っている当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり物件の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。
共有持分であっても最短1日の買取が可能で、法的な手続きについては丸投げしていただけます。共有持分にお悩みの方は、ぜひ下記よりご相談ください。