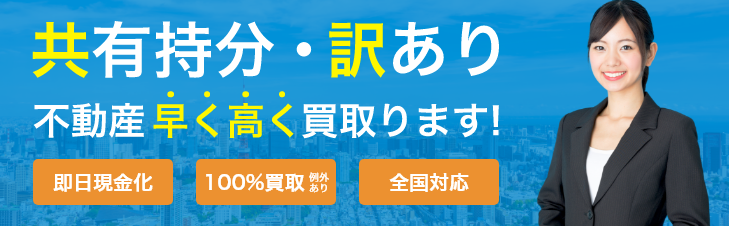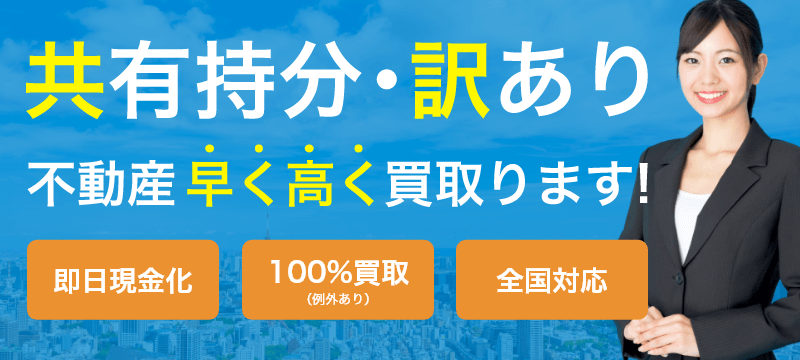マンションや住宅・土地などを他の人と共有していると、管理や権利関係トラブルに発展するケースがあります。その煩わしさから「共有状態を解消したい」と考えることがあるでしょう。
しかし、そこで自分の共有持分を売却しようと思っても、スムーズに進まない可能性も大いに考えられます。。今回は、そういった場合に有効な「共有物分割請求」について詳しく解説しますので、ぜひお役立てください。
目次
共有物分割請求とは
共有物分割請求とは、共有者に認められた「共有物の分割を請求する権利」のことです。「五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない」と、民法上で定められています。
共有者が話し合いに応じない場合でも、裁判所を通せば分割請求を行うことが可能です。不動産を2人以上の名義で登記する「共有」状態の場合、自分1人で大きな決断ができないことが大きなデメリットですが、共有物分割請求を活用すれば、共有状態を解消できます。
例えば「共有不動産を売りたい」と思ったとしても、他の共有者の合意と協力を得られなければ売却することはできません。売却以外にも、解体や増改築・大規模な修繕・長期賃貸借・建て替えなどにも全員の合意が必要となります。
共有物分割請求は「どうしても共有状態を解消したい」と考えた場合に有効な解決方法といえるでしょう。
共有物分割訴訟が起こればどうなる?
共有物分割訴訟が起こると、裁判所で当事者の主張を確認し、最終的に判決によって分割方法などが決定されます。
裁判所側は、共有持分権者それぞれの主張内容や持分割合・共有物の経済的価値や持分権者の資力などを考慮して、総合的に判断します。
共有物分割請求の3つの方法
共有物分割請求をおkなう方法としては、次の3とおりです。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
以下より、それぞれについてみていきましょう。
現物分割
現物分割とは「不動産を物理的に分ける」方法です。実際は、建物を2つに分けることは難しいでしょう。そのため、この方法は建築物が建っていない土地のみの場合に適用されることがほとんど。
例えば、AとBで共有持分が2分の1の土地の場合、その土地を半分ずつで分けるのが一般的でしょう。この分割行為は「分筆」といいます。
しかし、ただ分けただけではAとBそれぞれの「単有」にはなりません。そのため、自分の共有持分を相手に譲り合うことで、登記上2つに分配することができます。
代償分割
代償分割とは共有者の誰か1人がすべての持分を買い取り「他の共有者に代償金を支払う方法」です。
裁判所で「代償分割すべき」と判断されるケースは、下記のような場合です。
- 現物分割が不可能な場合
- 取得者に資力がある場合
- その他、価格賠償が相当だと判断した場合
建物など物理的に分割することが不可能なものの場合や、土地であっても分筆することが難しい場合は、価格賠償が相当であると判断されるケースがあります。
共有者の取得者に視力がある場合、価格賠償すべきと判断される可能性が高いでしょう。逆に言えば、資力がない人に対して、「借金してでも買い取るように」という要求をすることはありません。
換価分割
換価分割とは、共有不動産を第三者に売却し「利益を共有持分の割合に応じて共有者全員に分配する方法」を指します。
現物分割も物理的に不可能で、代償分割も資力がないため選択できない場合、換価分割が裁判所によって判断されるのが一般的。
その際の訃報は、「競売」となりますが、以下のような懸念点があります。
- 売却益が少なくなる
- プライバシーが侵害されるおそれがある
競売では市場価格よりも低い金額で売却されてしまいます。8割やそれ以下の金額で売られてしまうことも珍しくありません。
さらに、競売では自分たちで手続きをするのではなく、裁判所が強制的に売却を進めていくため、第三者が不動産調査や撮影などを行います。そのため、プライバシー上の問題が発生する可能性も懸念されるでしょう。
共有物分割請求の流れ
共有物分割請求を行う流れは、主に以下の3ステップに分けられます。
- Step1.共有分割協議
- Step2.共有分割調停
- Step3.共有分割訴訟
各手順について、それぞれ個別にみていきましょう。
Step1.共有分割協議
まずは分割方法についての協議を行います。裁判をするためにも協議は必要であり、「現物分割」「代償分割」「換価分割」のうち、どの方法にするのかを話し合うことが必要です。
意見がまとまれば、その方法で話の分割を進めれば問題ありません。しかし、協議が難航する状態であるならば、次のステップである「調停」へと進みます。
Step2.共有分割調停
裁判所で「共有物分割調停」を申し立てることで「調停」を行えます。
調停では裁判所の調停員が交渉の間に入って進めてくれるため、スムーズに決まる場合があるでしょう。調停によって和解が成立すれば、和解調書も作成されます。
ここでも決着がつかなければ、次の「訴訟」へと進みます。なお、調停は必須ではないため、いきなり訴訟を起こすことも可能です。
Step3.共有分割訴訟
協議や調停で解決しない場合、最終段階である訴訟となります。訴訟では、裁判所側が客観的に判断した上で共有物の分割方法を決定します。どのような判決になるかは案件によって異なりますが、優先順位は下記のとおりです。
- 優先順位1:代償分割
- 優先順位2:現物分割
- 優先順位3:換価分割
なお、以前は現物分割が優先されていたときもありましたが、今では現物分割が可能な場合であっても、共有者のうち誰か1人が価格賠償の条件を満たすのであれば、価格賠償が選択されるケースが多くなっています。
共有物分割請求ができないケース
共有者全員が「共有物分割請求をしない」という取り決めをしている場合、共有物分割請求ができません。不分割の合意の期間は5年を超えることはできないため、約束後でも5年を経過していれば共有物分割請求することも可能。
なお、組合が所有する不動産の場合は、組合の清算前に共有物分割請求することは基本的には認められていません。
共有分割訴訟に必要な費用
共有物分割請求は、案件内容によってかかる時間は異なりますが、調停であれば3ヶ月~半年程度、訴訟となれば判決までに半年以上かかります。その間は、以下のような費用が必要。
- 交渉費用
- 弁護士費用
- 訴訟費用
- 登記費用
- 不動産鑑定費用
前述したように、共有物分割訴訟は裁判所が判決を下すため「いつ、どのような結果になるか」がわかりません。結果が出るまで時間や費用がかかり、精神的な負担も大きくなることが考えられます。
訴訟で競売命令を下されれば、手元に残るお金も少なくなってしまうでしょう。
そのため、できる限り共有物分割訴訟になる前に、共有持分に関する問題を解決するのがおすすめです。例えば、競売発生前に買取専門業者に売却した方が高く売れて手元に残るお金も多くなるため、共有者全員にとってメリットがあるといえます。
まとめ
「共有者と話し合いができない」「連絡が取れない」といったケースでは、共有持分に関する問題を話し合いで解決することが難しい場合があります。その場合、共有物分割請求が選択肢としてあがることでしょう。
しかし、不動産の取り扱いは難しく、共有者が身内であっても協議の中で衝突する場合があります。トラブルを防いだり早めに解決したりするためにも、知識が豊富な専門家に相談してみましょう。
本ブログで情報発信を行っている当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり物件の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。
共有持分であっても最短1日の買取が可能で、法的な手続きについては丸投げしていただけます。共有持分にお悩みの方は、ぜひ下記よりご相談ください。