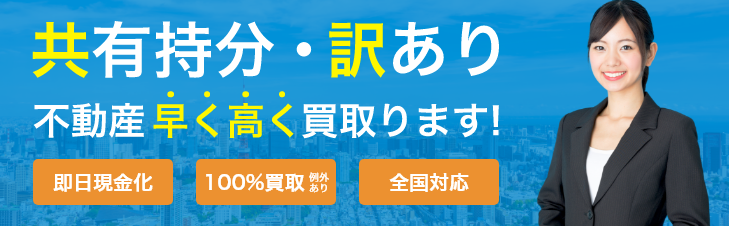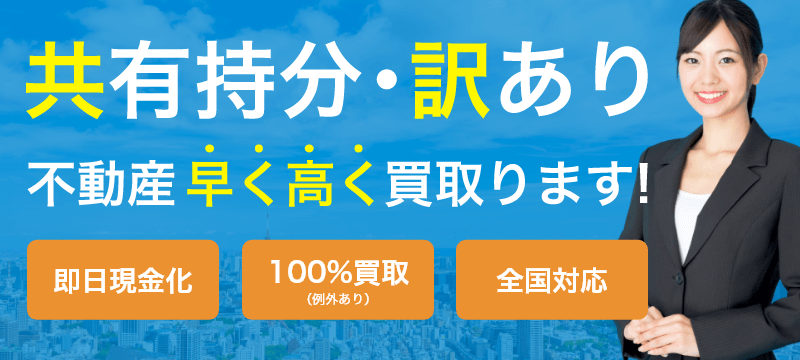不動産を所有していると、たとえ住んでいなかったとしても「固定資産税」を支払わなければならず、それは共有名義の不動産においても同様です。
今回は、共有名義の不動産にかかる固定資産税の支払い方についてご紹介します。なるべく損をしないための必要知識をお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
共有名義の不動産とは?
「夫婦共同で土地家屋を購入した」「兄弟が共有名義で土地を相続した」などのケースでは、権利上は複数人で不動産を共有している状態になります。このように複数の名義人が共有している不動産が「共有名義不動産」です。
共有している不動産の権利の割合を「共有持分」といいます。相続で等分するときは「法定権利分」が持分。共同で出資した場合には出資金の割合がそのまま持分になるケースが多々あります。
不動産が共有名義になっている場合には、登記簿謄本の権利部に「持分」「所有者名」が記されることになります。
固定資産税とは?
固定資産税とは、土地や家屋・建物・設備などの固定資産を所有している人にかかる市町村税です。
毎年1月1日に所有している人に納付義務があり、税額は不動産の「固定資産税評価額」に対して、土地・建物ともに1.4%の税率をかけて算出されます。
なお、自治体によっては、1.4%以上の税率に定められている場合もあるため留意しましょう。
土地の評価額について
「土地」とは、田畑や山林なども含まれ、用途によって地目と呼ばれる区分があります。評価額は、地目が宅地の場合は、「路線価方式」などを基にして算出。固定資産税路線価は各自治体のホームページなどで確認することが可能です。
家屋の評価額について
固定資産税における「家屋」とは、新築住宅や中古住宅などの住家や、店舗・倉庫など土地に定着した構造物のことを指します。家屋の評価額は、「同じ建物を同じ土地に建てた場合にいくらになるか」を算出した後、経年劣化分を減価することで決められるのが一般的です。
固定資産税の支払い時期
固定資産税や都市計画税の納付書は、4~6月に送付されることが通例です。自治体によって納付期限はさまざまですが、年4回が原則です。
一括払いを選択することも可能ですが、割引などはありません。手持ち資金に余裕が持てることから分割払いにメリットはありますが、納付期限を忘れやすいよう注意しましょう。
固定資産税の支払い方法
自治体によって異なりますが、固定資産税の支払いは、下記のような手段で行えます。
| 現金で支払う | 納付書を、コンビニや銀行・郵便局などの金融機関、または市区町村の窓口に持っていき現金で支払う方法。 |
|---|---|
| 口座振替で支払う | 銀行や郵便局などの口座から、自動的に支払ってくれる方法。 |
| クレジットカードで支払う | クレジットカード支払いはWEB専用サイトで支払う方法とYahoo公金支払いで支払う2つの方法。 |
| ペイジーで支払う | 納付書にペイジーマークが付いている場合は、インターネットバンキング(モバイルバンキング含む)やATMで納付が可能 。 |
場合によっては「都市計画税」の支払いも必要
都市計画税とは、所有する不動産が、都市計画法による市街化区域に位置する場合に必要となる税金です。各地方自治体が、道路や公園・下水道整備など土地区画整理事業に必要な費用にあてることを目的としており、固定資産税と一緒に課税されます。
税額は「固定資産税評価額 × 0.3%」の計算式を用いるのが一般的です。
共有名義の固定資産税は「代表者」が支払う
共有名義の不動産にかかる固定資産税は、共有者が「自分の持分に応じた費用」を負担し、代表者が支払う仕組みです。
例えば、A・Bの2人で不動産を共有しており「Aの共有持分が2/3」「Bの共有持分が1/3」で30万円の固定資産税納付書が届いたとしたら「Aは20万円」「Bは10万円」を支払う必要があリマス。
固定資産税や都市計画税の納付書は、共有者に分割して送られてくるわけではなく、代表者一人に送付されます。自治体は登記されている中から誰に請求してもよいことになっています。
そのため、納付書が送られてきた代表者が全額支払い、その後共有持分に応じて他の共有者に請求する……、という流れが一般的。
自治体が代表者を選ぶ場合は、下記の要素を考慮して決められます。
- 共有持分が一番多い人
- 不動産がある場所に住んでいる人
- 登記簿に記載している順番が早い人
つまり、自治体は「いかに未回収を防ぐか」を基準に判断するため、実際に住んでいる人や共有持分が多い人に納付書を送ることが多いのだとわかるでしょう。
なお、共有者全員で話し合い、代表者を決めて自治体に申し出ることも可能。
その場合、「共有資産代表者選定届(自治体により名前は異なる)」を、不動産が所在している自治体の役所に提出しましょう。届け出の締め切りが自治体ごとに異なりますが、提出すれば代表者を変更可能です。
共有名義の固定資産税には「連帯納付義務」がある
固定資産税は、共有持分権者全員が全額の支払い義務を負う「連帯債務」を負っています。これは、持分割合とは関係なく支払う必要があるということです。
なお、前述のように各共有者は共有持分に応じて費用を負担する必要がありますが、共有者の中の誰か一人が全額支払えば租税債務は消滅します。
その場合、固定資産税や都市計画税を支払った「代表者」から、他の共有者へ持分に応じた金額を求償することも可能です。
代表者以外が固定資産税額を確認する方法
場合によっては、代表者以外の共有者が税額を知りたいというケースもあるでしょう。そのような場合は、共有不動産を管轄する自治体の役所で「固定資産税評価証明書」を取得すれば確認可能。
証明書を取得する際には、身分証明書や戸籍なども必要になってくるため、事前に準備しておきましょう。
代表者は変更も可能
共有名義の不動産の代表者を変更することも可能ですが、提出書類には新旧それぞれの代表者の署名捺印が必要です。
当然ながら代表者が変更されたからといって、共有名義人の持分割合に応じた連帯納税義務が免除されるわけではない点には留意しましょう。
共有名義の固定資産税を滞納したらどうなる?
ここからは共有不動産の固定資産税を滞納した場合、どうなるのかについて解説します。リスクを避ける意味でも、正確に把握しておきましょう。
延滞税がかかる
一括支払い・年4回払いのいずれのケースでも、固定資産税の支払いには期限が設けられています。
その期日を過ぎても納税しない場合に発生するのは「延滞税」です。延滞金の税率は、納付期限の翌日から1ヶ月を超えると割合が大きく変わるため留意が必要です。
督促状が届く
固定資産税・都市計画税を滞納すると、督促状が届きます。地方税法第329条で「納期限から20日以内に督促状を発しなければならない」とされているとおりですので、督促状が届いた段階ですぐに支払いをしましょう。
もし、自分で支払えない場合は、他の共有者に相談するのが賢明。納税が遅くなるほど延滞税がかさんでしまうためです。
他の共有者も差し押さえ対象に
督促状が届いても納税をしない場合、財産を差し押さえられてしまいます。
共有名義の不動産の場合、滞納すると代表者だけではなく、他の共有者の財産も差し押さえ対象になるため、より注意しなければなりません。
これは、前述したように「連帯債務」によるものであり、代表者以外の共有者も全額支払う義務があるからです。
猶予や減額・免除などが認められる場合
やむをえない事情があり固定資産税を納付できない場合、条件を満たすことで1年の猶予や減額・免除などが認められるケースがあります。
一例としては、以下のとおりです。
- 震災や火災などの災害を受けた場合
- 本人または生計を共にする親族が病気または負傷した場合
- 営んでいる事業が廃止または休止した場合
など
上記以外でも、固定資産税などの減免を受けられる場合があるため、支払えない際には滞納せず、まずは専門家に相談してみるといいでしょう。
固定資産税を支払いたくない場合の売却方法
「共有不動産の固定資産税を支払いたくない」と、考える場合もあるでしょう。確かに、不動産を売却し手放せば、固定資産税や都市計画税を支払う必要がなくなります。
しかし、共有名義の不動産を売るためには共有者全員の合意が必要。共有者のうち誰か1人でも反対の状態であれば売却できません。
そのような場合の対処法としては、以下のとおりです。
- 他の共有者への売却
- 買取専門業者への売却
ここからは、それぞれ個別に解説します。
他の共有者への売却
不動産全体を売却できないのであれば、共有状態を解消することで不動産の所有権を手放すことが可能です。その方法の一つが、自分の持分を他の共有者に買い取ってもらうこと。
特に共有者が親族であるなら、一度打診してみるとよいでしょう。
買取専門業者への売却
他の共有者が自分の持分買い取りに乗り気ではない場合、自分の持分のみの買取専門業者への売却が推奨されます。不動産全体の売却には共有者全員の合意が必要ですが、自分の共有持分のみの売却であれば自分1人の判断で実施可能。
共有持分を売却できれば、固定資産税や都市計画税の支払いがなくなるだけでなく、厄介な共有関係に巻き込まれることもなくなるため、悩み多い共有不動産を抱えている方にはおすすめです。
まとめ
共有名義の不動産であっても、固定資産税の支払いは必須です。しかし、「登記はしているけれど、不動産を活用できていない」「他の共有者が独占しており、得をすることがない」などの理由から、固定資産税の支払いが負担になっているケースも多々あるでしょう。
支払いに応じない場合、差し押さえなどによって自分の財産を失うリスクが生じてしまいます。それを避けるためにも、早いタイミングでの売却が推奨されます。
専門業者なら、他の共有者とトラブルになることなく、スムーズに共有不動産を売却可能。固定資産税の支払いに悩んでいるなら、まずは相談してみましょう。
本ブログで情報発信を行っている当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり物件の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。
共有持分であっても最短1日の買取が可能で、法的な手続きについては丸投げしていただけます。共有持分にお悩みの方は、ぜひ下記よりご相談ください。