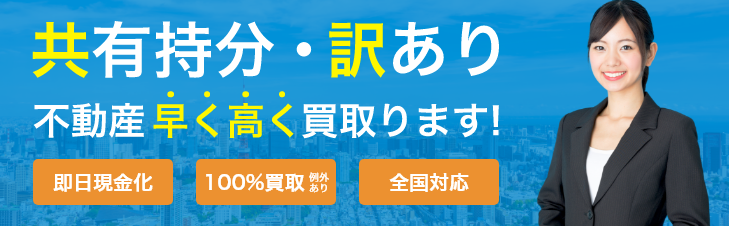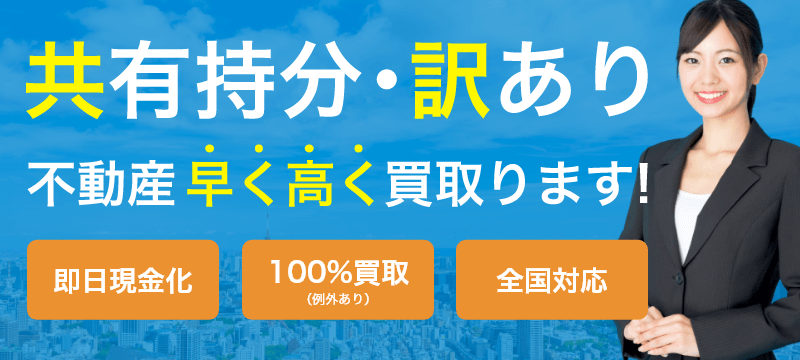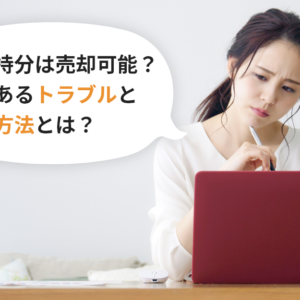「共有不動産をどのようにして活用するのか?」について考えた際、「売却 vs 賃貸」のいずれかの判断軸が発生することでしょう。「どちらを選択するべきなのか」については、物件の状態や他の共有者の意見次第で異なってきます。
今回は、共有不動産を売却。もしくは賃貸活用する際に、どちらを選択するべきかの判断基準について解説します。共有不動産についてお悩みの方は、ぜひお役立てください。
目次
共有不動産を売却・賃貸がそれぞれ有効なケース
共有不動産の売却や賃貸を検討する際には、以下の基準に基づいて判断しましょう。
<売却が有効なケース>
- 共有不動産を手放したい
- 早急にまとまったお金が欲しい
<賃貸が有効なケース>
- 共有不動産を保有し続けたい
- 安定した副収入が欲しい
次項より、それぞれについて解説します。
共有不動産の売却が有効なケース
共有不動産が不要である場合や、短期間で資金が必要な場合は売却が適切です。売却により固定資産税の負担も解消されます。
利活用が難しい共有不動産では、単に所有しているだけの状態が続く可能性もあります。固定資産税の支払いや共有者間のトラブルが負担となる場合、売却によりこれらの悩みから解放されるといえるでしょう。
共有不動産を売却すれば、所有権を手放せるため、それ以降は税負担や共有者同士のトラブルなどの悩みからは開放されます。
さらに、「早急にまとまった資金が必要である」場合も、共有不動産の売却を検討しましょう。
共有持分を積極的に買い取っている専門業者も存在しますので、そういった業者に依頼すれば、最短即日から1週間で売却することも可能です。
関連記事:共有持分はどのタイミングで売却するべき?高く売るための勘所も紹介
共有不動産の賃貸活用が有効なケース
「共有不動産を継続的に保有したい」「長期的な家賃収入を得たい」といった場合は、賃貸活用が適切です。売却では所有権が移転するため利用が制限されますが、賃貸では所有権を維持し、将来的な利用が可能。
共有不動産が生まれ育った実家のため思い入れがある場合は、売主から買主に所有権が移ることでm以降の利用が一切できなくなる売却は特に選択しづらいのではないでしょうか。
一方で、賃貸物件として貸し出すなら、物件の所有権を保有し続けられますので、将来的に自分で住む。あるいは別の形で利活用する余地を残せます。
一度にまとまった売却益を得るのではなく、毎月小額ずつでも家賃収入を得て、安定的な副収入の基盤を築いておきたい……、というケースでも賃貸活用は有用な選択肢です。
何を基準にして共有不動産の売却 ・賃貸を決めればいいのか?
共有不動産の売却・賃貸のどちらを選べばいいのかについて悩んだ場合、以下の観点から判断しましょう。
- 自分にとって共有不動産は必要か?
- どのタイミングで資金がいるのか?
共有不動産の扱い方について考える上では、自分や他共有者の意見を尊重するだけでなく、どのタイミングで利益が得られるのかについても検討することが必要です。
①:自分にとって共有不動産は必要か?
共有不動産の全体売却や賃貸活用には、以下のように他の共有者の同意が必要です。
- 売却…共有者全員の同意
- 賃貸…過半数の同意
自分にとって共有不動産が必要かどうかを検討し、他の共有者と意見を調整しましょう。
ただし自分だけの持分の売却は、他共有者の同意がなくても可能。「賃貸活用を希望するが他共有者が手放したい」という場合、他共有者の持分を買い取り、賃貸活用を検討することもできます。
共有不動産の扱い方については他の共有者の意見を聞き、その上で「はたして自分にとって共有不動産は必要であるのかどうか」について判断するのがベターといえます。
②:どのタイミングで資金がいるのか?
共有不動産をどのように利用するかは、収益のタイミングにも影響します。短期的に利益が欲しい場合は売却を。長期的に安定した収入を得たい場合は賃貸活用を選びましょう。
- 短期で利益が欲しい…物件を売却する
- 長期間にわたって安定収入にしたい…物件を貸し出す
ただし、不動産の資産価値は経過時間と共に減少し、売却価格も下がります。利活用の予定がない場合、早期に売却を検討することが賢明です。
将来の利活用や資金調達の予定に応じて、適切な対応が求められます。こうした観点から共有不動産の売却・賃貸を検討し、最適な選択を行いましょう。
共有不動産を売却するメリットとデメリット
共有不動産を売却する際に考えられるメリット・デメリットとしては、以下のようなものが考えられます。
<売却のメリット>
- 自分の持分だけなら自由に売却できる
- 他共有者とのトラブルから開放
<売却デメリット>
- 全体売却には共有者全員の同意が必要
ここからは、それぞれについて個別にみていきましょう。
共有不動産売却のメリット
共有不動産の持分のみであれば、他の共有者の同意がなくても自由に売却できるだけでなく、そのことを事前に報告する義務もありません。
共有不動産を売却すれば、他の共有者との関係も解消できますので、物件の処遇に関する話し合いといった煩わしさからも開放されるでしょう。
共有不動産売却のデメリット
前述のとおり、共有状態にある物件のすべてを売却するなら、共有者全員の同意が必要です。共有不動産そのものを売ることに対して積極的なのが自分だけであった場合、他の共有者から反対されてしまえば、売却できません。
もし、自分の共有持分のみを売却することになった場合、得られる売却益も全体売却に比べて割安になってしまいます。
共有不動産を賃貸活用するメリット・デメリット
共有不動産を賃貸する場合のメリット・デメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
<賃貸活用のメリット>
- 継続的な家賃収入が得られる
<賃貸活用のデメリット>
- 一方的に賃貸契約を解除できない
- 共有者同士でトラブルになりやすい
次項より、個別に見ていきましょう。
共有不動産を賃貸活用するメリット
共有不動産を賃貸物件として活用すれば、継続的な家賃収入が得られます。
所有物件が戸建て物件であるなら、入居者が長く借り続ける傾向にあるため、長い間にわたって安定的に不動産収益を得ることが可能。最終的な収益は売却したときに比べて多くなる可能性もあります。
共有不動産を賃貸活用するデメリット
一方で、賃貸物件として貸し出し、賃貸契約を締結すれば一方的に契約を解除できなくなる点がネックです。一度、入居者が賃貸物件の利用をはじめると、特殊な事情がない限り、一方的な契約解除は行えません。
共有不動産の場合は賃貸契約を解除するにも、不動産の持分割合における過半数の同意が必要であると「借地借家法第28条」で規定されています。通常の普段に比べ、さらに契約解除が難しいといえるでしょう。
さらに、賃貸物件として貸し出すためにリフォームが必要であった場合でも、共有者全員の同意が必要。家賃収入の取り分について全員の意見を一致させておかなければなりません。
共有者全員で意見を揃えることは難易度は高く、共有不動産の賃貸活用の際には大きなハードルになると予測されます。
共有不動産を売却する方法
共有不動産の売却を考えた場合、一般的な不動産仲介会社を利用するスキームでは、以下の手順が必要です。
【共有不動産を売却する手順】
- Step1:売却価格の決定
- Step2:共有者全員の合意形成
- Step3:不動産会社と媒介契約の締結
- Step4:買い手探し
- Step5:買主との売買契約の締結
- Step6:物件の引き渡し
これらの手続きは時間がかかり、通常の不動産でも3ヶ月から半年ほど必要。共有不動産の場合、さらに時間を要することが多い点については把握しておきましょう。
なるべく短期で売却したいなら、前述のように訳あり物件専門の買取業者への依頼が有効といえます。
関連記事:共有持分を高く売るためには買取業者の選び方とは?価格査定の要点も解説!
共有不動産を売却する場合、費用はいくら?
共有不動産を売却する際にかかる費用は、次のようなものです。
- 譲渡所得税
- 印紙税
- 登記費用
- 仲介手数料(仲介業者を利用した場合)
譲渡所得税や印紙税、登記費用などの税金は必ず支払うことが必要。一方で、仲介手数料は共有者間で売却や専門業者への売却を行う場合は不要です。
共有不動産の賃貸活用をする手順
共有不動産を賃貸物件として活用する場合、以下の手順で実施します。
【共有不動産を賃貸活用するする手順】
- Step1:家賃相場の調査
- Step2:他の共有者の過半数の同意を得る
- Step3:管理会社との契約(管理委託する場合)
- Step4:入居者の募集
- Step5:借主と賃貸契約の締結
賃貸活用においては、入居者探し以上に共有者間の意見の一致が課題となることがあります。その場合、自ら他の共有者の持分を買い取る選択肢も考えられるでしょう。
共有不動産を貸し出す場合の費用は?
共有不動産を賃貸活用する際に考慮すべき費用は、以下のようになります。
- 宣伝広告費
- 管理費用
- リフォーム費用
賃貸物件として貸し出すにあたっては、不動産会社に宣伝広告を依頼し、管理を委託するのが一般的です。そのため、これらの費用が必要となります。また、物件の老朽化が進んでいる場合には、リフォーム費用も考慮する必要があります。
まとめ
共有不動産の扱いについて、売却・賃貸のいずれかで悩んだ場合は、基本的には売却を選択すれば手間がかかりません。売却なら、賃貸活用に比べて手間が少なく、自分の共有持分飲みなら自由に売りに出せるためです。
一方で、思い入れのある物件を残したいなら、賃貸活用でも十分に収益を得られる余地はあります。さらには、共有不動産を利活用する場合には、他の共有者となるべく禍根を残さないような落としどころを見つける努力も大切だといえます。
本ブログで情報発信を行っている当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり物件の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。
共有持分であっても最短1日の買取が可能で、法的な手続きについては丸投げしていただけます。共有持分にお悩みの方は、ぜひ下記よりご相談ください。