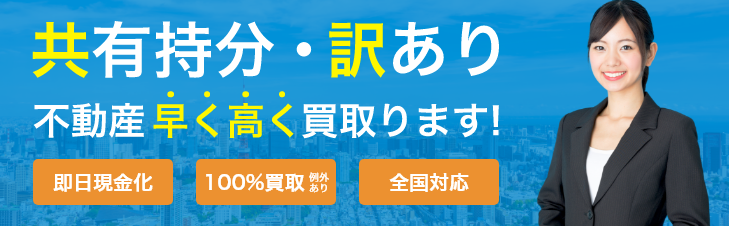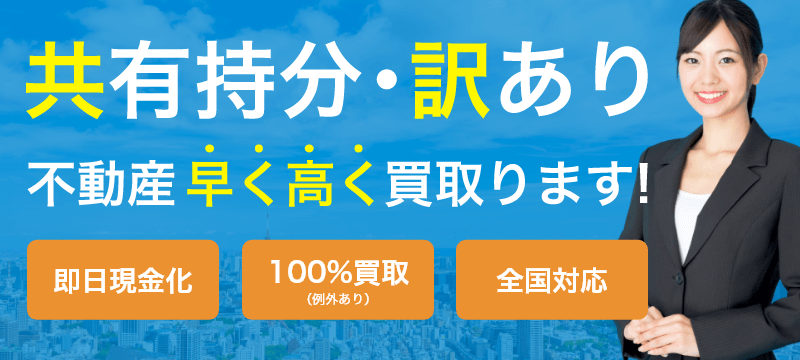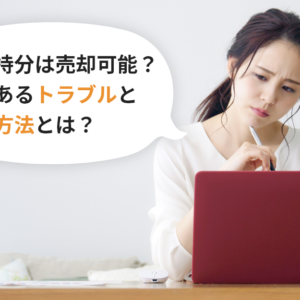複数人で権利関係を分割している「共有不動産」は利活用が難しいため、“自分の持分のみ”の売却を検討するケースも存在するでしょう。
しかし、共有持分は通常の不動産よりも売却が難しいため、適切なタイミングを把握しておかなければなりません。今回は、共有持分をなるべく高く売却するために求められるタイミングの見定め方を紹介します。
共有持分について悩みをお抱えの方は、ぜひお役立てください。
目次
共有持分を売却する4つのタイミング
共有持分の売却タイミングとしては、主に以下のシチュエーションで行うのが一般的です。
- 相続発生時
- 離婚が決定したとき
- アンダーローン状態になったとき
次項より、個別にみていきましょう。
相続発生時
実家などを相続する際、兄弟姉妹がいる場合は、複数人で共有持分として実家の権利を分割承継するケースは多いでしょう。しかし、共有持分を持っていても共有者単独では物件を自由に使えません。
もし、他の相続人が実家を活用したいと考えているなら、共有持分の売却が適切な選択肢となります。
離婚が決定したとき
離婚時にマイホームを所有している場合、財産分与の結果として共有持分となります。離婚後も共有持分を保持すると、固定資産税の負担が続きかねません。
共有状態を解消しないと、以下のようなトラブルが生じる可能性があります。
- 他方の共有持分をが売却されて第三者と共有関係になる
- 他方が再婚すると権利関係が複雑になる
- 離婚時に取り決めた家賃や固定資産税の支払いが行われない
上記のようなトラブルを避けるため、離婚後は共有持分を売却するのがよいでしょう。
関連記事:離婚調停が発生した場合、共有不動産の扱いはどうなるの?
アンダーローン状態になったとき
アンダーローンは、物件の売却価格が住宅ローン残債を超える状態を指します。住宅ローン完済前の場合、抵当権を持つ金融機関が物件売却を認めないことも。
アンダーローン状態ならば、物件売却が許可されるケースもあります。共有持分だけを売却するか、物件全体を売却するかに関わらず、自分の共有持分を手放すのに適したタイミングといえるでしょう。
共有持分をなるべく高く売却する方法
共有持分は利活用が難しいため、不動産業者に仲介を依頼しても買取希望者が見つかりにくく、高額売却も期待できません。そこで、以下の方法を検討しましょう。
- 共有者全員で物件をまるごと売却する
- 他の共有者の持分を買い取って売却する
- 訳あり物件買取業者へ相談する
次項より、個別に解説します。
共有者全員で物件をまるごと売却する
共有持分を売却する際の買取価格の相場感は、「共有不動産全体の価格 × 持分割合 × 1/2」程度です。
例えば、市場価格が2,000万円の物件の共有持分1/2を売却する場合、買取価格はおおよそ500万円になります。
そのため、共有持分を単独で売却するよりも、共有不動産を一括売却し、共有者全員で売却益を分配する方が賢明といえるでしょう。
他の共有者の持分を買い取って売却する
他の共有者の持分を自分で買い取り、物件をまるごと売却する……、という方法もあります。
この手法は、共有者が売却に反対する理由として「遠方に住んでいるから立ち会いが難しい」「単純に手続きが億劫である」などのケースでは特に有効でしょう。
他の共有者の持分を取得し、持分割合を大きくしてから売却することで、自分の共有持分だけを売却するよりも収益が大きくなる可能性があります。
ただし、贈与税が課税されることがあるため注意が必要です。共有者間での売買価格が市場相場よりも大幅に低い場合、贈与とみなされる可能性があります。
贈与税は、年間の贈与額が110万円以下であれば控除を受けられます。そのため、支出を抑えるように調整しましょう。
訳あり物件買取業者へ相談する
共有持分のみの売却は買取相場が低いだけでなく、買い手探しが難しい点もネックです。一方で、共有持分や訳あり物件を積極的に買取っている専門業者へ相談すれば、問題解決を図れる可能性があります。
専門業者は共有持分のような特殊な物件の扱いに長けているため、短期間で買取まで完了させることが可能。やはり市場相場よりは低い見積もり金額とはなるものの、自分で買い手を探すよりは高額売却も実現しやすいでしょう。
売却以外で共有持分を手放す方法
共有持分を所有し続けていると、それだけで毎年の固定資産税や管理費を支払わなければなりません。そのため、売却は難しいものの、どうしても手放したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、共有持分の「生前贈与」「放棄」を行って問題解決を図ります。
共有持分を他者に生前贈与する
将来、配偶者や子どもに共有持分を相続させる予定であれば、生前贈与が選択肢になるでしょう。生前贈与を行うことで、贈与税がかかる可能性はありますが、控除を利用して課税額を抑えることができ、相続税対策にもつながります。
生前贈与は他の共有者の同意が不要で、持分を分割して贈ることも可能です。
共有持分の放棄を行う
共有持分の放棄が可能であり、民法255条により放棄分が他の共有者に帰属することになります。
ただし、放棄したことを法的に証明するためには、不動産登記手続きが必要で、他の共有者の協力も求められます。
まとめ
共有持分を所有し続けると固定資産税や管理費の支払い義務が生じるため、利用予定がなければ売却が望ましいといえます。ただし、一部の共有持分のみの売却では、市場相場よりも売却益が少なくなることが懸念点。
このため、共有持分を売却する場合は、全体売却を行うか、他の共有者の持分をできるだけ集めてから売却することが賢明です。
共有持分に関する問題に対処するには、専門業者への相談や他の共有者との協力が不可欠。さまざまな選択肢を検討し、最適な解決策をみつけましょう。
本ブログで情報発信を行っている当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり物件の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。
共有持分であっても最短1日の買取が可能で、法的な手続きについては丸投げしていただけます。共有持分にお悩みの方は、ぜひ下記よりご相談ください。