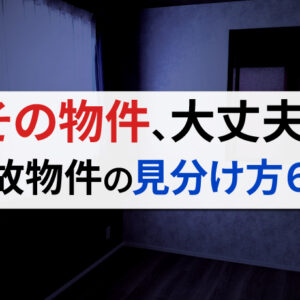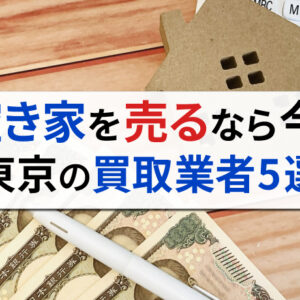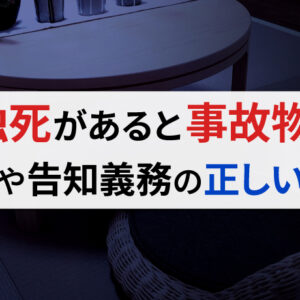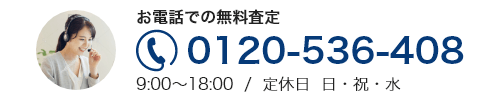について今すぐご相談できます。
お電話する
相続人が複数いる場合や遺産の内容が複雑なケースでは、誰がどれだけの割合で遺産を相続できるのかという問題が発生します。その際に重要となるのが法定相続分です。
法定相続分とは、民法で定められた相続における基本的な取り分の割合のこと。遺言書がない場合の遺産分割の基準となるだけでなく、遺留分の計算や相続税の算出にも関わる重要な概念です。
適切な理解がないと、相続手続きの長期化や相続人間の対立を招くリスクがあります。本記事では、法定相続分の基本的な考え方から計算方法、適用される場面まで、実践的な知識を詳しく解説します。
目次
法定相続分とは
民法第900条に定められた法定相続分は、配偶者や子供、両親、兄弟姉妹など、それぞれの立場によって定められた遺産の取り分を示す割合を指します。
この割合は、遺言書がない場合の遺産分割の際に、特に重要な意味を持ちます。
遺産分割において法定相続分が基準とされる理由は、被相続人との関係性に応じて、公平な分配を実現するためです。
例えば、配偶者と子供が相続人の場合、配偶者が2分の1、子供が残りの2分の1を均等に分けることになります。このように、法定相続分は相続人それぞれの権利を明確にする役割を担っています。
遺産分割協議の目安として活用可能
遺産分割協議では、法定相続分を目安としながら、相続人同士で話し合いを進めていきます。ただし、この割合に厳密にこだわる必要はなく、相続人全員の合意があれば、異なる割合での分割も可能です。
例えば、介護などで被相続人の生前に貢献した相続人がいる場合は、その人により多くの遺産を渡すといった柔軟な対応も認められています。このように、法定相続分は話し合いのスタートラインとして機能し、実情に応じた調整が可能な仕組みとなっています。
具体的な相続分との違い
相続における実際の取り分を示す「具体的相続分」は、法定相続分をベースとしながらも、さまざまな要素を加味して算出されます。
具体的な例として、被相続人から生前に多額の贈与を受けていた場合や、被相続人の介護に尽力した場合などが挙げられます。
このような特別な事情がある場合、それらを「特別受益」や「寄与分」として計算に反映させることで、より公平な遺産分割が可能となります。法定相続分が基本的な割合を示すのに対し、具体的相続分は現実の状況を反映した実質的な取り分といえます。
ただし、これらの調整には相続人全員の合意が必要となるため、話し合いの過程では法定相続分が重要な指針となります。
法定相続人とは
法定相続人は、民法によって定められた相続権を持つ人々を指します。被相続人との血縁や婚姻などの関係性により、一定の条件を満たした人が法定相続人となります。
この制度は、被相続人の財産を適切に引き継ぎ、遺族の生活を守るという重要な役割を担っています。
法定相続人の定義と役割
法定相続人は、原則として被相続人の配偶者と、一定範囲の血族で構成されます。
配偶者は常に法定相続人となる一方、血族については第1順位から第3順位まで優先順位が設けられており、上位の順位に該当者がいる場合、下位の人は法定相続人とはなりません。
法定相続人となることで、遺産分割協議への参加権や、遺留分請求権などの重要な権利が発生します。相続税の計算においても、法定相続人の数は基礎控除額に影響を与える重要な要素となります。
法定相続人の種類と該当条件
相続順位は以下のように定められています。
- 第1順位:子(代襲相続人としての孫、ひ孫を含む)
- 第2順位:父母(代襲相続人としての祖父母を含む)
- 第3順位:兄弟姉妹(代襲相続人としての甥姪を含む)
ここで重要なのは、上位の順位に一人でも該当者がいれば、下位の順位の人は法定相続人とはならないという点です。
例えば、子供が一人でもいれば、被相続人の父母や兄弟姉妹は法定相続人とはなりません。
法定相続人がいない場合の対応
法定相続人が全くいない場合、その財産は最終的に国庫に帰属します。ただし、そうなる前に、特別縁故者からの請求により、家庭裁判所が相続財産の全部または一部を与える可能性もあります。
特別縁故者とは、被相続人と生計を共にしていた人や、療養看護に努めた人などを指します。
内縁関係や養子は法定相続人に含まれるのか?
内縁関係にある人は、たとえ長年の同居があったとしても、法定相続人とはなりません。ただし、内縁関係にある人との間に生まれた子供は、認知がなされていれば法定相続人となります。
一方、養子については、普通養子も特別養子も実子と同様に法定相続人となります。ただし、相続税法上は養子の数に制限が設けられており、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが相続税の計算上考慮される養子の上限となります。
これは、養子縁組による相続税の節税を防ぐための規定です。
なお、養子の実の親子関係は養子縁組によって切れることはないため、実父母の相続においても法定相続人となる点には注意が必要です。
法定相続分が重要になってくる場面
相続手続きにおいて法定相続分は、単なる遺産分割の目安としてだけでなく、以下のような相続に関する多くの場面で基準として用いられます。
- ①:遺産分割協議を進める際の基準として
- ②:遺言書がない場合の相続手続き
- ③:相続税の計算に必要なケース
- ④:特別受益や寄与分が問題となる場合
- ⑤:家庭裁判所での調停や審判の際
次項より、詳しく解説します。
①:遺産分割協議を進める際の基準として
遺産分割協議では、法定相続分が話し合いの出発点となります。相続人全員が集まり、誰がどの財産をどれだけ相続するかを決める際、この法定相続分を基準に話し合いを進めていくのが一般的です。
相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で分割することも可能ですが、話し合いの土台として法定相続分は重要な意味を持ちます。
②:遺言書がない場合の相続手続き
遺言書がない場合、法定相続分は最も重要な基準となります。不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなど、さまざまな相続手続きにおいて、法定相続分に基づいた権利関係の証明が必要です。
特に、相続開始後すぐに必要となる預貯金の払い戻しでは、法定相続分に応じた払い戻しが行われることが一般的です。
③:相続税の計算に必要なケース
相続税の計算では、法定相続分が「法定相続分課税方式」という計算方法の基礎となります。
この方式では、まず法定相続人の数と法定相続分に基づいて相続税の総額を計算し、その後、実際の取得割合に応じて各相続人の納付税額を算出します。基礎控除額の計算においても、法定相続人の数が重要な要素となります。
④:特別受益や寄与分が問題となる場合
生前贈与を受けた相続人がいる場合や、被相続人の介護などに特別な寄与があった場合、法定相続分を基準としつつ、それらの事情を加味して具体的な相続分を算出します。
特別受益の計算では、まず相続財産に生前贈与の価額を加えた金額に法定相続分を掛け、その後、特別受益の価額を控除するという方法で計算されます。
⑤:家庭裁判所での調停や審判の際
遺産分割の話し合いが難航し、家庭裁判所での調停や審判となった場合、法定相続分は重要な判断基準となります。
特に審判では、特別な事情がない限り、法定相続分に従った分割が原則とされます。ただし、特別受益や寄与分が認められる場合には、それらを考慮した上で具体的な相続分が定められることになります。
このように、法的な場面では法定相続分が基本的な判断基準として扱われます。
遺言書で指定されていても法定相続分には従う必要がある!
遺言書があれば、原則としてその内容が優先されますが、法定相続分が全く意味を持たなくなるわけではありません。
特に重要となるのが「遺留分」という制度です。遺留分とは、法定相続分をベースに計算される最低限保障される相続分のことで、遺言書の内容がこれを下回る場合、法定相続人は遺留分侵害額請求権を行使できます。
例えば、配偶者と子がいる場合の遺留分は、配偶者が法定相続分の2分の1、子が法定相続分の2分の1となります。
仮に遺言書で「全財産を長男に相続させる」と書かれていても、配偶者や他の子供たちは、この遺留分を請求することが可能です。
法定相続分の計算例
相続における法定相続分の計算は、相続人の組み合わせによって変わってきます。実際の計算例を見ていくことで、より具体的な理解を深めていきましょう。
配偶者と子供の相続割合の計算例
遺産総額が1億円で、相続人が配偶者と子供3人という一般的なケースを考えてみましょう。
まず、配偶者は2分の1の権利を持つため、5,000万円が配偶者の取り分となります。残りの5,000万円を3人の子供で均等に分けることになるため、子供1人あたりの取り分は約1,667万円となります。
このように、配偶者と子供がいる場合は、まず大きく二分した後、子供の人数で均等に分けるという手順で計算していきます。
実際の遺産分割では、この金額を目安に、現預金や不動産などの具体的な財産の分け方を検討していきます。
代襲相続が発生した場合の計算例
次に、遺産総額1億円で、配偶者と2人の子供がいたものの、そのうち1人の子供が既に死亡しており、その子供(被相続人から見て孫)が2人いるケースを考えてみましょう。
この場合、まず配偶者の取り分が5,000万円となります。残りの5,000万円のうち、生存している子供の取り分が2,500万円となります。
そして、既に死亡している子供の取り分2,500万円は、その子供(孫)2人で均等に分けることになるため、孫1人あたりの取り分は1,250万円となります。
このように代襲相続の場合は、亡くなった人の取り分を、その子供たちで均等に分けるという計算方法を取ります。ただし、相続放棄をした人の子供には代襲相続の権利は発生しない点には注意が必要です。
これらの計算例は、あくまでも法定相続分による基本的な計算方法です。実際の相続では、遺言書の有無や特別受益、寄与分などの要素によって、具体的な相続分が変わってくる可能性があります。
法定相続分が適用されないケース
法定相続分は相続における基本的な取り分を定めた規定ですが、さまざまな事情により修正や調整が必要となるケースがあります。
- 遺言書による分割指定がある場合
- 特別受益が認められる場合
- 寄与分が考慮される場合
- 相続放棄が行われた場合
それぞれ個別にみていきましょう。
遺言書による分割指定がある場合
遺言書は被相続人の最終的な意思を示すものとして、法定相続分よりも優先されます。例えば、「不動産は長男に相続させる」「預貯金は次男に相続させる」といった具体的な指定がある場合、原則としてその内容に従って相続が進められます。
ただし、遺言の内容が著しく不公平で、遺留分を侵害するような場合には、法定相続人は遺留分侵害額請求権を行使することができます。これは法定相続分を基準に計算される最低限の相続分を保障する制度です。
特別受益が認められる場合
被相続人から生前に多額の贈与や援助を受けていた相続人がいる場合、それを「特別受益」として考慮する必要があります。
具体例を挙げると、ある相続人が既に住宅資金として3,000万円の贈与を受けていた場合、その金額を相続財産に加算した上で各人の相続分を計算し、特別受益を受けた人の相続分からその金額を控除します。
この調整により、生前の贈与を受けていない相続人との公平性が保たれます。
特別受益の対象となる典型的な例としては、結婚・養子縁組における贈与や、教育・生活費の援助で通常の範囲を超えるものなどが挙げられます。
寄与分が考慮される場合
被相続人の介護や事業の手伝いなどで、特別な貢献をした相続人がいる場合、その行いは「寄与分」として評価されます。
例えば、他の相続人が仕事や家庭の都合で関われない中、一人の相続人が長年にわたって無償で介護を行っていた場合、その貢献度に応じて相続分を増やすことができます。
寄与分の金額は、貢献の期間や内容、程度などを総合的に判断して決定されます。ただし、日常的な家事や介護は、原則として寄与分としては認められないため、特別な事情があったことを示す必要があります。
相続放棄が行われた場合
相続人の中に相続放棄をする人がいると、法定相続分の計算にも影響が出ます。相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、残りの相続人の間で法定相続分が再計算されます。
さらに、相続放棄をした人の子供には代襲相続の権利は発生しません。例えば、被相続人に子供が3人いて、そのうち1人が相続放棄をした場合、残りの2人で相続することになり、それぞれの法定相続分は3分の1から2分の1に増加します。
このように相続放棄は、他の相続人の相続分に直接的な影響を与えます。
法定相続分を侵害すると「遺留分侵害請求」を受ける可能性がある
遺言書によって法定相続分を大きく下回る相続分が指定されたり、生前贈与で特定の相続人が著しく優遇された場合、遺留分侵害請求(正式には「遺留分侵害額請求」)が行われることがあります。
遺留分侵害請求とは、遺留分を侵害された相続人が、その不足分に相当する金銭の支払いを他の相続人や受贈者に対して求める権利です。この請求は、遺産分割が完了した後でも行うことが可能であり、相続トラブルの原因となることも少なくありません。
遺留分侵害請求が認められる場合の影響
遺留分侵害請求が認められた場合、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いが必要となります。支払いは原則として現金で行うため、不動産など現物資産が中心の相続では、資産の売却や分割が必要になるケースもあります。
このような事態は、遺産分割後の財産状況や相続人間の関係に大きな影響を与える可能性があり、新たな相続トラブルの火種となることもあります。
遺留分侵害請求を避けるためのポイント
遺留分侵害請求を避けるためには、遺留分を侵害しない範囲で遺産分割の内容を決める。または遺留分を侵害する場合は、相続人との事前の話し合いで合意形成を図ることが重要です。
相続人ごとの遺留分を正確に把握し、それを下回らないよう財産を配分すれば、請求リスクを減らすことができます。
なお、生前贈与も遺留分の対象となるため、将来の遺留分侵害請求を見据えた適切な贈与額の設定が求められます。
法定相続分でトラブルになったら弁護士に相談しよう
法定相続分をめぐるトラブルは、法律的な複雑さと感情的な対立が絡み合うことで、解決が長期化する傾向にあります。特に、遺産分割協議がまとまらない場合や、遺留分侵害請求、特別受益や寄与分をめぐる争いでは、当事者同士の話し合いだけでは解決が難しいことが少なくありません。
このような状況では、弁護士に相談することが最も効果的な対処法です。弁護士は法的な知識だけでなく、第三者として冷静な視点からアドバイスを提供し、感情的な対立の緩和にも寄与します。
また、調停や裁判に発展した場合も、適切な主張と証拠の整理を行い、依頼者の権利を守る重要な役割を果たします。
弁護士費用の目安
弁護士に依頼する際の費用は、事案の複雑さや争う金額によって異なりますが、一般的な相場は以下のとおりです。
- 初回相談料: 30分5,000円~1万円程度。
- 着手金: 経済的利益(争う遺産額)の3~5%が目安。
- 報酬金: 成果に応じて、着手金と同程度またはそれ以上になることもある。
場合によっては相続財産から弁護士費用を支出できることもあるため、費用面の不安から依頼を躊躇せずに、まずは相談してみましょう。
「ワケガイ」なら訳あり物件も短期で買取可能!
当社(株式会社ネクスウィル)は、相続や共有持分など、訳ありの不動産を買い取る「ワケガイ」サービスを提供しています。
相続で取得した不動産の処分に悩む方からのご相談を多数いただいており、法定相続分の問題で困っているケースにも対応しています。
相続で取得した不動産は、法定相続分の計算が複雑であったり、相続人間の調整が難しかったりと、さまざまな理由で売却が進まないことがあります。
そのような場合でも、ワケガイは独自のノウハウと提携する専門家のネットワークを活用し、適切な解決策をご提案します。
法務、税務の専門家と連携しながら、共有持分の買取や相続に関する課題の解決をサポートしますので、お気軽に無料相談をご利用ください。
まとめ
法定相続分は相続における重要な基準ですが、これを絶対的なものと考える必要はありません。相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合での遺産分割も可能です。
重要なのは、被相続人の意思を尊重しつつ、相続人それぞれの事情や貢献を考慮した、公平で円満な遺産分割を実現することです。
相続に関する問題は、早期に専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることで、スムーズな解決につながります。法定相続分の知識を基礎としながら、各々の状況に応じた最適な解決策を見出していきましょう。