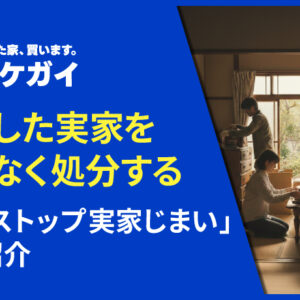について今すぐご相談できます。
お電話する
借地権付きの不動産を所有していると、契約更新の際に更新料を請求されるケースがあります。更新料の金額が高額で支払いが困難な場合や、そもそも支払う義務があるのか分からないといった悩みを抱えることも少なくありません。
その際に正しく理解しておくべきなのが借地権の更新料です。借地権の更新料とは、借地契約を継続するために地主へ支払う費用のことを指します。
ただし、法律上の義務ではなく、契約内容や地域の慣習によって異なるため、適正な金額かどうかを判断することが重要です。
更新料が高額すぎる場合は交渉の余地があるほか、支払いが難しい場合には別の選択肢も考えられます。
本記事では、借地権の更新料の相場や計算方法、支払い義務の有無、支払えない場合の対処法について詳しく解説します。
目次
借地権の更新料とは
借地権の更新料は、契約を更新する際に地主へ支払う費用です。法律上の義務ではありませんが、多くの契約で設定されており、地主が土地の使用継続に伴う利益の調整や、契約の更新に関する合意を得るために請求することが一般的。
また、地価の変動や地域の慣習が影響することもあり、特に地価の上昇が著しい地域では、更新料の負担が大きくなるケースもあります。契約書を確認し、支払い義務があるかどうかを把握することが重要です。
借地権の更新料を減額・免除してもらうことは可能?
更新料は交渉次第で減額や免除が可能な場合があります。
契約書に明確な規定がなく「過去に支払った実績がない」「地域の慣習で更新料の支払いが一般的でない」場合は、支払い義務がない可能性も懸念されます。
交渉の際には、地域の相場や契約内容を確認し、地主に合理的な根拠を示すことが有効です。分割払いの提案や地代の増額と引き換えに更新料の減額を求めるなど、柔軟な対応を検討すると交渉が成立しやすくなります。
借地権の更新料を払わないとどうなる?
では、借地権の更新料を支払わないとどうなるのでしょうか。具体的には、以下のような事態に陥る可能性があります。
- 契約を更新できずに借地権を失う
- 地主との関係が悪化し、交渉が難しくなる
- 裁判を起こされ、法的責任を問われる
- 未払いが続くと立ち退きを求められる
- 過去の判例から未払いのリスクを知る
時効より、個別に解説します。
契約を更新できずに借地権を失う
借地権の契約が更新されなければ、借地人はその土地を利用し続けることができません。
借地借家法により、借地権には一定の更新権が認められていますが、更新料の支払いが契約の前提条件となっている場合、それを拒否すると契約が更新されず、結果的に借地権を失う可能性があります。
特に、契約内容に「更新料の支払いが必要」と明記されている場合、支払いを拒否すれば更新の申し出自体が無効とみなされるケースも存在します。地主が更新を拒否し、契約満了後に土地の明け渡しを求めることも考えられます。
これに対抗するには、契約書を確認し、更新料の支払い義務の有無を正確に把握することが大切です。
(参考:e-Gov 法令検索「借地借家法」)
地主との関係が悪化し、交渉が難しくなる
借地契約は、地主との信頼関係のもとに成り立っています。そのため、更新料を一方的に拒否すると、地主との関係が悪化し、将来的な交渉が難しくなる可能性があります。
例えば、地代の値上げや建て替えの許可、契約更新時の条件変更など、借地人は地主と協議しなければならない場面が何度も訪れます。更新料を巡って関係がこじれると、そうした場面で地主の対応が厳しくなることも考えられます。
裁判を起こされ、法的責任を問われる
更新料の支払いを拒否し続けると、最悪の場合、地主が裁判を起こし、法的な責任を問われる可能性があります。
更新料は法律上の義務ではないものの、契約書に明記されている場合は「契約不履行」として訴訟に発展しかねません。
裁判になった場合、過去の判例では更新料の支払い義務を否定するものもあれば、契約内容を根拠に地主側の主張が認められたケースもあります。
借地借家法は借地人を保護する趣旨の法律ですが、契約内容や地域の慣習が影響するため、一概にどちらが有利とはいえません。
未払いが続くと立ち退きを求められる
更新料の支払いを拒否し続けると、地主から立ち退きを求められるリスクが高まります。特に、契約の更新そのものが無効と判断されると、地主側から「契約満了に伴う退去」を要求されるケースが出てきます。
通常、借地契約には正当事由がない限り、地主が一方的に借地人を立ち退かせることは難しいとされています。
しかし、更新料の未払いが契約違反とみなされると、地主は「正当事由のひとつ」として立ち退きを請求する可能性があります。
過去の判例から未払いのリスクを知る
更新料の支払いを拒否した場合、実際の裁判ではどのような判断が下されているのでしょうか。過去の判例を調べることで、リスクをより具体的に把握できます。
例えば、最高裁の判例では、「更新料が法的に当然に発生する義務ではない」としつつも、「契約の内容や地域の慣習によっては支払い義務が生じる場合もある」と判断しています。
そのため、地主が裁判を起こした場合、契約書に更新料の明確な記載があれば、借地人に支払いを命じる判決が出ることもあります。
借地権の更新料の金額交渉は可能?
借地権の更新料は、契約書に定められている場合でも交渉の余地があるケースも存在します。なぜなら、更新料の支払いは法律で義務付けられているわけではなく、地主と借地人の合意によって決まるからです。
そのため、提示された金額が高いと感じた場合や、支払いが困難な場合は、減額や分割払いを交渉することが可能。
交渉を有利に進めるためには、まず契約書を確認し、更新料の金額や支払い義務について明確に理解しておく必要があります。もし契約書に具体的な金額の記載がなく、「慣習に従う」などの曖昧な表現が使われている場合は、相場を調べたうえで地主と話し合う余地があるでしょう。
借地権更新料の相場感はどのくらい?
借地権の更新料は、地域や契約の内容によって異なりますが、一般的には借地権価格の5%程度が目安とされています。
これは、過去の取引事例や不動産業界の慣習から導き出された相場であり、多くの借地契約で採用されています。
ただし、地域によってはこの相場が変動するケースも見受けられます。例えば、都心部の商業地など地価が高いエリアでは、更新料の相場が3~5%に抑えられる傾向があります。
一方、地方では土地の流動性が低いため、更新料がやや高めに設定されることもあります。
更新料の計算例
借地権の更新料は、一般的に次の計算式を用いて算出されます。
- 更新料 = 更地価格 × 借地権割合 × 5%(または契約で定められた割合)
例えば、以下のようなケースを考えてみます。
- 更地価格:1,000万円
- 借地権割合:60%
- 更新料の割合:5%
この場合、更新料の計算式は以下のようになります。
- 1,000万円 × 60% × 5% = 30万円
このように、土地の価格と借地権割合によって更新料の金額が決まるため、契約の前に土地の評価額を確認しておくことが重要です。
借地権の更新料が支払えない場合の対処法
借地権の更新料が支払えない場合は、以下のような対処法を採りましょう。
- 地主に支払い条件の交渉をする
- 弁護士に相談して法的な選択肢を確認する
- 借地権を売却して解決する
次項より、詳しく解説します。
地主に支払い条件の交渉をする
借地権の更新料が高額で支払えない場合、まず検討すべきなのは、地主との交渉です。更新料の支払いは契約上の義務として定められているケースもありますが、必ずしも一括で支払わなければならないわけではありません。
地主も、借地人が契約を継続してくれる方が安定した収入につながるため、柔軟な対応をしてくれる可能性があります。
弁護士に相談して法的な選択肢を確認する
交渉が難航した場合や、そもそも更新料の支払い義務があるのか不明な場合は、弁護士に相談するのも有効な手段です。
特に、契約書の内容が不明確だったり、地主から過去の相場を大きく超える金額を請求されていたりする場合は、法的な観点からアドバイスを受けることで、適切な対応が可能になります。
弁護士に相談することで、以下のような選択肢を検討できます。
- 更新料の支払い義務があるかどうかの確認
- 更新料の減額交渉を進める際の法的根拠の整理
- 裁判になった場合の見通しの把握
また、過去の判例を参考に、更新料を巡るトラブルがどのような形で解決されているのかを知ることもできます。
借地権を売却して解決する
更新料の支払いが難しく、地主との交渉も進まない場合は、借地権を売却するという選択肢もあります。借地権は、土地を所有していなくても一定の価値があるため、不動産市場で売却することが可能です。
売却を検討する際には、まず借地権の市場価値を把握することが重要です。借地権の価格は、更地価格や借地権割合によって決まるため、不動産会社に査定を依頼するのが一般的。
また、売却には地主の承諾が必要なケースが多いため、事前に確認しておく必要があります。
借地権を売却した場合に発生する諸経費
借地権を売却した場合、次のような費用が発生します。
- 譲渡所得税
- 測量費・登記費用
- 契約解除に伴う違約金
- 仲介手数料(※仲介による売却の場合)
- その他の諸費用
これら諸費用についても、以下より解説します。
譲渡所得税
借地権を売却すると、売却益に対して譲渡所得税が発生します。これは、購入時の価格と売却価格の差額に対して課税されるもので、売却益が大きいほど税負担も増えます。
譲渡所得税の税率は、所有期間によって異なります。売却するまでに5年を超えて保有していた場合は長期譲渡所得として20.315%(所得税+住民税+復興特別所得税)が課税され、5年以下の場合は短期譲渡所得として39.63%が課税されます。
長期保有の方が税率が低いため、売却のタイミングを検討することも大切です。
(参考:国税庁「短期譲渡所得の税額の計算/長期譲渡所得の税額の計算」)
測量費・登記費用
借地権を売却する際、土地の境界を明確にするために測量が必要になる場合があります。
特に、境界線が曖昧な場合や、過去に正式な測量が行われていない場合、買主から測量を求められるケースも存在します
測量費用は土地の広さや条件によって異なりますが、数十万円程度かかることが一般的です。
また、売却に伴い登記の変更が必要になることもあります。例えば、借地権の名義変更や、抵当権の抹消などが必要になる場合、司法書士に依頼して手続きを進めることになります。
登記費用は手続きの内容によりますが、数万円~十数万円程度が目安となります。
契約解除に伴う違約金
借地契約の内容によっては、売却に際して契約解除が必要になる場合があり、その際に違約金が発生する可能性があります。
特に、契約書に「解約時には〇〇円の違約金を支払う」と明記されている場合は、その金額を負担しなければなりません。
ただし、地主と交渉することで、違約金を減額してもらえるケースもあります。売却前に契約書を確認し、違約金が発生するかどうかをチェックしておくことが重要です。
仲介手数料(※仲介による売却の場合)
不動産会社を通じて借地権を売却する場合、仲介手数料が発生します。仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格に応じて次のように計算されます。
- 200万円以下の部分:5%+消費税
- 200万~400万円の部分:4%+消費税
- 400万円以上の部分:3%+消費税
例えば、1,000万円で借地権を売却した場合、仲介手数料の上限は36万円+消費税となります。
その他の諸費用
その他の諸費用として、売却に伴う書類作成費用や、土地所有者への承諾料がかかることがあります。地主の承諾が必要な場合、承諾料として売却価格の数%を求められることもあるため、事前に確認しておくことが大切です。
売却をスムーズに進めるためには、これらの諸経費を事前に把握し、想定される費用を考慮したうえで売却計画を立てることが重要になります。
「ワケガイ」なら借地権付き物件も短期で買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり不動産の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。借地権付きの物件は、通常の不動産市場では買い手がつきにくく、売却までに時間がかかるケースが多いですが、ワケガイならスピーディな取引が可能です。
借地権は、土地の所有権がなく第三者への売却時に地主の承諾が必要な場合があるため、売却が難航することがあります。また、更新料の支払いや契約条件の調整が必要なこともあり、一般的な不動産会社では対応が難しいケースも少なくありません。
ワケガイでは、借地権の取り扱いに精通した専門チームが、売却のハードルをひとつひとつクリアしながら、最適な解決策を提案いたします。お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
借地権の更新料は、契約更新時に求められる費用ですが、その支払い義務や金額の適正性は契約内容や地域の慣習によって異なります。契約書を確認し、支払い義務が明記されているかを把握することが第一歩です。
更新料が相場よりも高額である場合や、支払いが困難な場合は、地主との交渉を検討しましょう。
分割払いの提案や地代の調整を申し出ることで、負担を軽減できる可能性があります。また、契約内容によっては法的に支払いの必要がないケースもあるため、不安がある場合は弁護士に相談するのも有効な手段です。
それでも支払いが難しい場合、借地権の売却という選択肢もあります。借地権には市場価値があり、適切な方法で売却することで資金を確保できます。契約条件や自身の状況に応じて、最適な対策を検討しましょう。
運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |