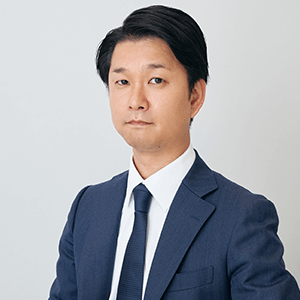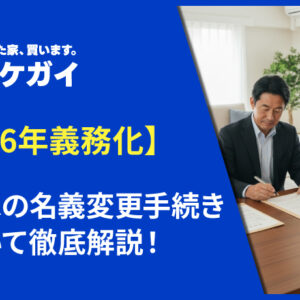について今すぐご相談できます。
お電話する
不動産売却では、契約内容の認識違いや物件の瑕疵をめぐるトラブル、不動産会社との手数料や媒介契約に関する問題など、さまざまな紛争が発生します。
売主の知識不足や手続きの不備により、予期せぬトラブルに発展するケースも少なくありません。一方で、不動産売却時のトラブルは、事前の対策と正しい知識があれば、その多くを未然に防ぐことができます。
本記事では、不動産売却時に発生しやすいトラブルの具体的な事例と、その予防策や解決方法について、法改正の内容も含めて詳しく解説します。
目次
不動産売却時に発生する主なトラブルとは
不動産売却時のトラブルは、売主・買主・不動産会社の三者間で発生することが一般的です。
買主や不動産会社との契約内容の認識違い、売却物件の瑕疵に関する問題、仲介手数料の取り扱いなど、多岐にわたる紛争が報告されています。
発生するトラブルは多様ですが、適切な事前準備と正確な情報共有を行うことで、未然に防げるケースが多くなります。
特に重要事項説明や契約条件に関する十分な確認、物件状態の正確な把握と開示などが重要となります。
不動産の取引は一般的に高額で、一度トラブルが発生すると解決までに時間と労力がかかります。安全な取引を実現するためにも、トラブルの種類と対策について理解を深めておきましょう。
特に訳あり物件の売却では要注意!
不動産売却において、特に注意すべきなのが「訳あり物件」の取引です。これは、一般的な物件に比べてトラブルのリスクが高く、慎重な対応が求められます。訳あり物件とは、物件の状態や環境、過去の経緯に何らかの問題がある不動産を指します。
例えば、雨漏りやシロアリ被害などの物理的な問題、騒音や悪臭といった環境面での課題、過去に事故や事件があった心理的な要素などが該当します。
こうした問題がある場合、売却時には買主への正確な情報開示が不可欠です。
不動産会社との間に発生し得るトラブル
不動産売却において、仲介会社との関係は非常に重要な要素となります。具体的に発生し得るトラブルとしては、以下のものが考えられます。
- 仲介手数料の不明瞭さが発生した
- 媒介契約の内容を見落とした
- 売却活動の不備が起こった
次項より、詳しく解説します。
仲介手数料の不明瞭さが発生した
仲介手数料の上限は宅地建物取引業法で定められており、売買価格が400万円を超える場合は「(売買価格×3%+6万円)+消費税」となります。
ところが、この上限額を法定の金額として説明したり、別途広告費用などを請求したりする悪質な業者も存在します。
手数料の支払時期についても、売買契約時と決済時の分割払いが一般的ですが、事前に取り決めがないと認識の違いでトラブルになることも。
(参考:e-Gov 法令検索「宅地建物取引業法」)
媒介契約の内容を見落とした
媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれ売主の権利や不動産会社の義務が異なります。
契約内容を十分理解しないまま締結すると、後々トラブルの原因となりかねません。特に「囲い込み」と呼ばれる、不動産会社が物件情報を他社に公開せず、自社で買主を見つけようとする行為には注意が必要です。
売却活動の不備が起こった
不動産会社による売却活動の不備も深刻な問題となっています。具体的には、適切な価格査定を行わない、広告活動が不十分、内見対応が杜撰といったケースが挙げられます。
レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録状況や、実際の広告出稿状況を定期的に確認することで、このようなトラブルを防ぐことが可能です。なお、売却活動の進捗状況は必ず記録に残し、不動産会社と共有するようにしましょう。
買主との間に発生し得るトラブル
不動産売買では、売主と買主の間でもトラブルが発生します。具体例を挙げると、以下のとおり。
- 物件状況の開示が不十分だった
- 価格交渉が難航した
- 契約条件の曖昧さが問題になった
それぞれ個別にみていきましょう。
物件状況の開示が不十分だった
物件状況の開示不足は、売買契約後に大きなトラブルへと発展するケースが多くあります。例えば、雨漏りの履歴や過去の修繕状況、騒音や日照の問題など、売主にとっては些細に思える情報でも、買主の購入判断に大きく影響する可能性があります。
そのため、「告知書」には物件に関する情報を漏れなく記載し、不動産会社を通じて買主に正確に伝える必要があります。
価格交渉が難航した
価格交渉でのトラブルは、主に物件価格の相場観の違いから生じます。
売主は高く売りたい、買主は安く買いたいという基本的な利害の対立だけでなく「リフォーム費用の負担」「設備の評価額をめぐる認識の違い」なども、交渉を複雑にする要因となっています。
このような場合には、不動産会社を通じて近隣相場や取引事例を具体的に示しながら、互いが納得できる落としどころを探ることが重要です。
契約条件の曖昧さが問題になった
売買契約書の条件があいまいだと、引き渡し後に深刻なトラブルとなることがあります。
特に多いのが、残置物の取り扱いや、修繕箇所の負担範囲、住宅ローン特約の適用条件などです。
売買契約書には、これらの条件を明確に記載し、売主・買主の双方が内容を十分に理解したうえで契約を締結する必要があります。
物件に関するトラブル
ここからは、物件そのもので発生するトラブルをみていきましょう。
- 瑕疵の内容を理解しなかった
- 補償や保険の手続きを怠った
次項より、詳しく解説します。
瑕疵の内容を理解しなかった
物件の瑕疵は、その種類によって対応方法が異なります。主な瑕疵の種類は以下のとおりです。
- 物理的瑕疵:建物の強度不足、雨漏り、シロアリ被害など
- 心理的瑕疵:自殺や事故死、暴力団員の居住歴など
- 法的瑕疵:建築基準法違反、接道義務違反など
- 環境的瑕疵:日照、騒音、悪臭など
特に2020年4月の民法改正により従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと変更されました。この改正により、売主は単に瑕疵の有無ではなく、契約内容に適合しているかどうかで責任を問われるようになっています。
つまり、事前に問題を把握していたかどうかに関わらず、契約内容と異なる点があれば売主の責任となる可能性があるのです。
(参考:e-Gov 法令検索「民法等の一部を改正する法律について」)
補償や保険の手続きを怠った
不動産売却後に発覚する欠陥や不具合(瑕疵)によるトラブルを防ぐためには「既存住宅売買瑕疵保険」への加入が有効です。この保険は、引き渡し後に発見された瑕疵の修補費用を最大1,000万円まで補償しています。
(参考:国土交通省「既存住宅売買瑕疵保険について」)
保証期間は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について2年間または5年間とされ、予期せぬトラブルによる経済的負担を軽減できます。特に中古住宅の売却時には、取引後の責任を明確にする手段として有効です。
既存住宅売買瑕疵保険に加入するためには、事前に専門の建物検査(インスペクション)を受ける必要があります。
この検査によって物件の状態が客観的に評価され、万が一の瑕疵が発見された場合でも、適切な修繕や対策を講じたうえで売買契約を進められます。結果として、買主の不安を解消できるだけでなく、売主にとっても価格交渉を有利に進める材料となるでしょう。
法的なトラブル
不動産売却において、法的なトラブルは最も深刻な問題に発展する可能性があります。売買契約は取引金額が大きく、契約書の内容や重要事項説明、告知義務など、法律に基づく手続きが多岐にわたります。
基本的には不動産会社の担当者などがチェックしてくれますが、オーナーとして以下のポイントを意識しておきましょう。
- 契約書の確認を怠った
- 重要事項説明を見落とした
- 適切な告知をしなかった
それぞれ個別にみていきましょう。
契約書の確認を怠った
売買契約書は、取引の根幹を定める重要な書類です。特に注意が必要なのは、住宅ローン特約や手付金の取り扱い、契約解除の条件などです。
契約書の内容をよく理解しないまま契約を締結すると、後になって取り返しのつかない事態を招くことがあります。
例えば、住宅ローン特約の期限設定が不明確な場合、ローン審査が通らなかった際の手付金の返還について争いが生じる可能性があります。
重要事項説明を見落とした
重要事項説明は、物件の権利関係や法的な制限、設備の状況など、買主の意思決定に重要な影響を与える事項を説明する機会です。
重要事項説明の内容は、売買契約前に十分に確認し、不明点があればその場で質問することが重要です。特に、土地の用途制限や法的規制については慎重に確認しましょう。
適切な告知をしなかった
告知義務違反は、売買契約後に大きなトラブルとなるケースが多発しています。売主は、物件の瑕疵や修繕履歴、事故の有無など、知り得る範囲の情報を買主に告知する義務があります。
これらの情報を意図的に隠したり、あいまいな説明をしたりすると、引き渡し後に損害賠償請求を受ける可能性があります。
不動産トラブルを相談すべき専門家
トラブルの内容によって、相談すべき専門家は異なります。早期の段階で適切な専門家に相談することで、問題の拡大を防ぐことが可能です。
契約トラブル→不動産会社
売買契約に関するトラブルは、まず仲介を担当した不動産会社に相談します。取引の経緯を把握している不動産会社であれば、円滑な解決に向けた助言や対応が期待できます。
ただし、不動産会社の対応に不満がある場合は、所属する協会の相談窓口を利用することも検討しましょう。
法的紛争→弁護士
損害賠償請求や契約解除など、法的な判断が必要なトラブルは、弁護士への相談が不可欠です。特に「金銭的な損失が大きい」「当事者間での話し合いが難しい」といった場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は法的な観点から解決策を提示し、必要に応じて訴訟対応もサポートしてくれます。
書類や登記の不備→司法書士
登記手続きの不備や、売買に必要な書類の不足は、司法書士に相談するのが最適です。司法書士は不動産登記の専門家として、必要な書類の確認や手続きの助言を行います。
特に相続絡みの物件売却では、権利関係が複雑になりがちなため、早めの段階での相談が望ましいでしょう。
法的手段を取る前に使えるADR(裁判外紛争解決機関)の活用方法
ADR(裁判外紛争解決機関)とは、裁判に比べて費用や時間の負担が少なく、柔軟な解決が期待できる制度です。
不動産取引のトラブルを法的手段に頼らず解決する方法として、各都道府県の宅建協会が運営する「不動産無料相談所」や、不動産公正取引協議会の「苦情相談窓口」などのADR機関が利用できます。
(参考:日本弁護士連合会「ADRの拡充」)
これらの機関では、専門的な知識を持った相談員が中立的な立場から、トラブル解決に向けたアドバイスや調停を行います。ADRを利用する際は、トラブルの経緯や証拠となる書類を整理して臨むことが大切です。
「ワケガイ」の買取サービスならトラブルなく現金化が可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり物件の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。
共有持分や再建築不可物件、空き家、事故物件など、一般的な不動産市場では売却が難しい物件でも、適切な価格での買取が可能です。
売主様の状況に応じて、最短1日での買取や最大3億円までの一括支払いにも対応しており、不動産に関するさまざまなお悩みを解決してきた実績があります。
特に、他社で買取を断られた物件や、相続などで権利関係が複雑な物件についても、提携する専門家と連携しながら丁寧にサポートいたします。
また、物件調査や査定は無料で実施していますので、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
不動産売却のトラブルを防ぐためには、売却前の準備が何より重要です。まずは物件の状態を正確に把握し、瑕疵の有無や修繕履歴などを整理しましょう。必要に応じて建物検査(インスペクション)を実施し、客観的な調査結果を得ることも検討する必要があります。
また、不動産会社との媒介契約を結ぶ際は、仲介手数料の金額や支払時期、売却活動の具体的な内容について、書面で明確に取り決めることが大切です。
売買契約の締結時には、契約書の内容を慎重に確認し、特に契約解除の条件や瑕疵担保責任の範囲について、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |