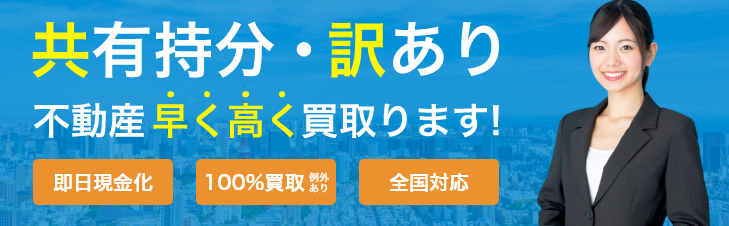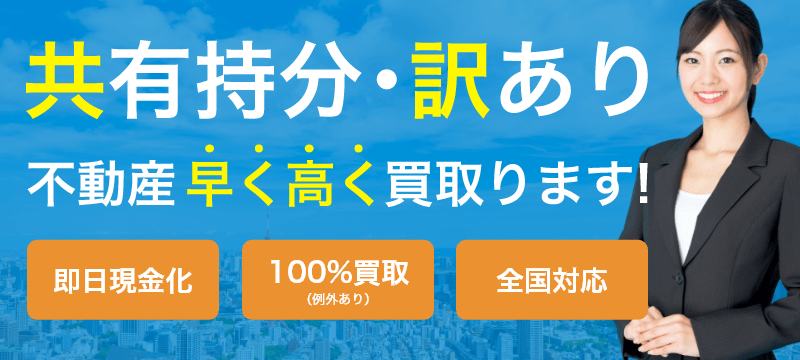こんにちは。ワケガイ編集部です。
住宅の購入資金を親子で分担するケースでは、「どのようにローンを組むか」「不動産の名義をどう分けるか」で悩まれる方が少なくありません。その際に検討されるのが親子リレーローンです。
親子リレーローンとは、親と子で住宅ローンの返済をリレー方式で引き継ぐ仕組みで、単独では借入が難しいケースでも希望の物件が取得しやすくなるという利点があります。
しかし、名義や持分の設定を誤ると、贈与税の課税リスクや将来的な相続・売却時のトラブルに発展しかねません。また、親が高齢となり判断能力を失った場合、持分の処分ができなくなるおそれもあります。
そこで本記事では、親子リレーローンの仕組みやメリット・デメリットなど、利用にあたって押さえておくべきポイントを詳しく解説します。
目次
親子リレーローンとは
親子リレーローンは、親と子供が共同で住宅ローンを契約し、世代をまたいで返済を引き継いでいく仕組みの住宅ローンです。金融機関では「親子継承型ローン」などと呼ばれることもあります。
この制度は、親子のいずれか一方では住宅ローンの審査が難しい場合でも、両者の収入を合算することで融資を受けやすくなるというメリットがあります。特に、親が高齢で単独では長期ローンが組めない場合でも、子供の年齢を基準に返済期間を延ばすことができるため、高額になりがちな二世帯住宅の建築資金などに適しています。
具体例を挙げると、親が65歳であっても、子供が35歳であれば、子供を基準にして35年ローンを組むことが可能です。このように、返済期間を確保しながら、親の年金収入や子供の給与収入などを組み合わせて資金計画を立てることができます。
ただし、親が先に亡くなった場合は、以後の返済を子供がすべて引き継ぐことになります。また、親子で同居していないと利用できない金融機関もあるため、事前に各行の条件を確認する必要があります。
親子リレーローンの「持分割合」は出資額の比率で設定する
親子で住宅を共有する場合、所有権の「持分割合」は、それぞれの出資額に応じて決めるのが原則です。たとえば、住宅取得費用が3,000万円で、親が2,000万円、子供が1,000万円を負担した場合、持分は「親3分の2:子供3分の1」とするのが適正です。
登記上は法的拘束なく任意の割合で設定できますが、実際の負担額と持分が一致していないと、税務上は「みなし贈与」として贈与税の課税対象になるおそれがあります。特に注意すべきは以下のようなケースです。
- 実際の負担額に差があるのに「親1:子供1」など均等に登記した
- 持分変更を行ったが、金銭の授受や契約書が伴っていない
- 親が一方的に多く支払い、子供の名義にしている
このような場合、税務署は差額分を「無償の経済的利益」とみなして贈与税を課すことがあります。仮に親から子供への贈与額が年間110万円を超えると、基礎控除を超える分に対して課税されるため、意図せぬ納税義務が生じかねません。
さらに、親子リレーローンを利用中でも、持分割合は「売買」や「贈与」によって変更が可能です。ただし、持分の移転登記には登録免許税がかかり、贈与であれば贈与税、売買であれば譲渡所得課税の対象になるため、変更時には税理士など専門家の助言を受けるのが望ましいでしょう。
関連記事:共有持分の割合の決め方や計算方法をケース別に徹底解説!
持分割合はローン返済中でも変更できるが、課税リスクには注意
住宅ローンの返済期間中であっても、不動産の持分割合を変更することは可能です。たとえば、将来的に贈与や売買を通じて持分を移転するケースも珍しくありません。ただし、持分割合の変更は、税務上のリスクと隣り合わせです。
特に注意すべきなのは、実際の出資割合と登記上の持分割合が一致していない場合です。このようなケースでは、税務署から「贈与」とみなされ、贈与税が課される可能性があります。
たとえば、住宅購入費1,000万円のうち、親が750万円、子供が250万円を負担して購入した場合、本来の持分割合は「親4分の3:子供4分の1」となるのが自然です。しかし、登記を「親2分の1:子供2分の1」とした場合、次のような不整合が生じます。
- 子供が本来負担すべき持分取得額:1,000万円 × 2分の1 = 500万円
- 実際の子供の出資額:250万円
この差額250万円は、親から子供への「みなし贈与」として扱われる可能性があります。課税対象額から基礎控除(年間110万円)を差し引いた140万円について、贈与税の申告・納付が必要になる場合があります。
さらに、親子間の不動産持分の移転が「売買」として扱われる場合には、親に譲渡所得税が課される可能性があります。そのため、売買契約書や代金の振込記録など、適正な対価の授受を証明できる書類を整えておく必要があります。
親から子供への資金援助で、子供の持分を多く設定すること自体は違法ではありませんが、贈与税のリスクを把握したうえで、正しい登記と資金の流れを記録に残しておきましょう。
関連記事:共有持分を取得した場合にかかる「取得税」とは?節税対策もセットで解説
親子リレーローンのメリット
親子リレーローンのメリットとしては、以下のものが挙げられます。
- メリット①:親子の収入が合算して審査される
- メリット②:返済期間を長期に設定できる
それぞれ詳しくみていきましょう。
メリット①:親子の収入が合算して審査される
親子リレーローンの大きな特長のひとつが、親と子供の収入を合算して審査を受けられる点にあります。特に、二世帯住宅のように建築費が高額になりがちなケースでは、単独でのローン審査では希望額に届かないこともありますが、収入を合算することで審査通過の可能性が高まります。
この点は、親子で住む大きな家を計画している世帯にとって、大きなメリットといえるでしょう。
また、「フラット35」などの住宅ローンプログラムでは、年金収入も安定収入とみなされます。通常であれば、年金生活者だけで住宅ローンを組むのは難しいところですが、子供と収入を合算することで、年金収入が返済能力として評価され、借入のハードルが下がります。
メリット②:返済期間を長期に設定できる
通常の住宅ローンでは、借入時の年齢によって返済期間が制限されます。たとえば65歳でローンを組む場合、完済年齢が80歳とされている金融機関では、15年ローンが上限です。
しかし、親子リレーローンなら、子供の年齢を基準に返済期間を設定できるため、より長期のローンが組めます。たとえば子供が30歳であれば、35年ローンの設定も可能です。これにより、月々の返済負担が軽減され、家計への影響を抑えることができます。
長期ローンにより資金計画の自由度が増し、家族のライフステージに応じた柔軟な設計が可能になります。
親子リレーローンのデメリット
一方で、親子リレーローンには次のようなデメリットも存在します。
- デメリット①:持分次第では贈与とみなされかねない
- デメリット②:相続時に遺産分割で揉めるリスクがある
以下より個別に解説します。
デメリット①:持分次第では贈与とみなされかねない
親子リレーローンを利用する際には、返済負担と所有権(持分)の割合を一致させる必要があります。たとえば、親が6割、子供が4割の割合でローンを返済する場合は、不動産の所有割合も同じにしておくのが原則です。
もし、返済割合に比して持分が少ない側が存在すると、税務上「贈与」とみなされる可能性があります。特に、親がもともと住宅を所有しており、子供とリレーローンを組むことで所有権を分けるようなケースでは、持分の設定と税務処理に慎重な対応が必要です。
適切な登記手続きと税務上の確認を怠ると、想定外の贈与税が発生するおそれがあります。
デメリット②:相続時に遺産分割で揉めるリスクがある
親子でローンを返済しながら共同所有している住宅は、相続時にトラブルの火種となることがあります。住宅の所有権を持つ子供が相続するケースが多いものの、それが他の相続人との間で「不公平」と捉えられれば、遺産分割協議が難航する原因になりかねません。
とくに現金や預貯金など分けやすい資産が少ない場合、住宅の評価額が相続の配分に大きな影響を及ぼすため、事前の取り決めや対話が重要です。
また、子供が独身で将来的に住宅に住み続ける保証がない場合、配偶者の意向などによって同居が困難になることもあります。そうしたケースでは、子供が実際には住まない住宅のローンを返済し続けることになり、新たな住宅ローンを組めなくなるリスクも生じます。
親子リレーローンにおける経済負担を減らすための方法
親子リレーローンを利用する際には、経済的な負担を軽減するためにも以下の点に留意しましょう。
- 住宅ローン控除を利用する
- 団体信用生命保険に加入する
- 返済が苦しくなったら売却も検討する
それぞれ詳しく解説します。
住宅ローン控除を利用する
住宅ローン控除は、住宅ローンの返済による負担を軽くするための制度で、条件を満たせば所得税や住民税から最大年間40万円が控除されます。通常は10年間、長期優良住宅などでは13年間に延長される場合もあります。
(参考:国税庁「認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」)
ただし、控除を受けるには、対象の住宅に実際に居住していることが条件です。親子リレーローンを利用していても、住んでいない側には適用されず、必ずしも両者が控除を受けられるとは限りません。
なかでも二世帯住宅で親子が同居している場合は、双方が控除の対象になることがあります。居住実態や登記状況によっては、親と子供の両方が控除を受け、合計で最大80万円が適用されるケースもあるため、事前の確認が重要です。を受けることが可能で、最大で合計80万円の控除を受けることができる場合もあります。
団体信用生命保険に加入する
団体信用生命保険(通称:団信)は、住宅ローンの返済中に債務者が死亡または高度障害状態になった場合、残債が免除される保険制度です。加入しておけば、万が一の際にも家族に返済の負担を残すことなく、安心して住宅ローンを利用できます。
親子リレーローンでは、金融機関によって親子のどちらが団信に加入できるかが異なります。多くの場合、子供側のみが加入対象となっており、親が亡くなっても残債が免除されないケースがあります。そのため、親子ともに団信に加入できる仕組みを選ぶことが大切です。
たとえば「フラット35」などは親子双方の加入が可能な商品があり、リスクに備えやすいといえるでしょう。また、団信は死亡時だけでなく、がんや脳卒中、急性心筋梗塞などを含む高度障害にも対応した特約が付加できる場合もあります。
ただし、保証期間は通常80歳までであり、それ以降に債務が残っていると遺族が返済義務を負う点には注意が必要です。長期のローン計画では、完済時期と年齢のバランスも見極めておきましょう。
返済が苦しくなったら売却も検討する
親子リレーローンは長期間にわたる返済が前提となるため「途中で住宅が老朽化する」「収入状況が変化したりする」こともあります。親から子供へ返済が移るタイミングで「今の家に住み続けることが難しい」と感じたら、売却を選択肢に入れるのも現実的です。
特に、親子リレーローンが残っている限り、子供は原則として新たな住宅ローンを組むことができません。既存の住宅を売却し、ローンを完済すれば、新しい住宅の購入資金に充てることが可能になります。
ローン残高が残っている状態でも、金融機関の同意を得て抵当権を外すことで、物件を売却することは可能です。売却代金で残債を完済できれば問題はありませんが、売却価格がローン残高を下回る場合には、差額を自己資金で補填する必要があります。
このようなリスクを踏まえ、売却時の査定額や残債を事前に確認し、返済計画を見直しておく必要があります。状況によっては、早めの売却判断が次の住まいへの移行をスムーズにする助けとなるでしょう。
関連記事:共有持分の不動産を売却する方法とは?売却費用やよくあるトラブルを紹介!
関連記事:共有名義不動産の売却価格の決まり方とは?基準についてわかりやすく解説
親がローン完済前に認知症や要介護状態になりそうな場合の対応
親子リレーローンでは、返済の一部を親が担っていることも多く、親が認知症や要介護状態になると、ローン返済や不動産管理の面で支障が生じます。こうした事態に備えるには、法的な手続きを含めた、以下のような対策が有効です。
- 成年後見制度の準備をしておく
- 事前に家族信託契約を結んでおく
それぞれ個別に解説します。
成年後見制度の準備をしておく
親の判断能力が低下した場合、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任する手続きが必要になります。
成年後見人とは、認知症などで判断能力を失った本人に代わって、財産管理や法律行為を行う法的な代理人です。金融機関との契約や不動産の売却手続きも、後見人を通じて進めることができます。
ただし、成年後見制度の運用には制約もあります。後見人の選任までには数カ月を要することが多く、不動産の処分など重要な判断には家庭裁判所の許可が必要です。そのため、ローン返済や名義変更を迅速に進めたい場合には、対応が遅れる懸念もあります。
関連記事:共有名義人が認知症になったら、不動産は売却可能?成年後見人制度とセットで解説
事前に家族信託を結んでおく
親が健康なうちに「家族信託契約」を結んでおく方法もあります。家族信託とは、財産の所有者(親)が、特定の目的にしたがって財産管理を第三者(通常は子供)に託す仕組みであり、信託契約に基づいて財産の管理・処分を受託者が行います。
家族信託は、裁判所の監督下に置かれないぶん、対応の自由度が高く、柔軟な資産管理を行える点が利点です。ただし、契約の内容設計には法的な専門知識が求められるため、早い段階での準備と専門家への相談が推奨されます。
関連記事:共有持分の家族信託にメリットはある?トラブル防止に繋がる必要知識を解説
出口戦略を検討されている方は「ワケガイ」にご相談ください!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や高齢者名義の不動産など、売却に課題を抱える物件の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。
親子リレーローンは親の年齢や体調に左右される側面があり、「もし親に何かあったら」と不安を感じながら返済を続けている方も少なくありません。
そうした場合の「出口戦略」として、不動産の早期売却や持分整理を検討することも選択肢の一つです。
ワケガイでは、共有名義や高齢者名義、再建築不可といった事情を抱える物件でも、法務や税務に精通した専門家と連携しながらスムーズに対応可能です。
ご家族の状況が変化する前に、あらかじめ方向性を整理しておくことで、将来のリスクを軽減できますので、お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
親子リレーローンは、親子で協力して住宅を取得する有効な手段ですが、メリットばかりに注目してしまうと、後々思わぬ落とし穴にはまるリスクもあります。特に不動産の名義や持分割合の設定は、贈与税や譲渡所得税など税務上の影響を及ぼすため、安易な判断は禁物です。
さらに、親がローン返済途中に認知症や要介護状態となる可能性も踏まえ、成年後見制度や家族信託などの備えを早めに講じておくことが、将来的な柔軟な対応につながります。
本記事で紹介したようなリスクとその対策を踏まえた上で、親子リレーローンを選択肢の一つとして検討しましょう。