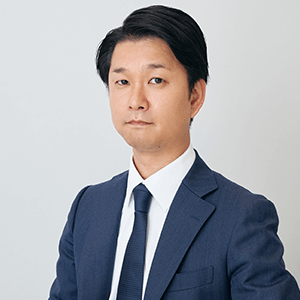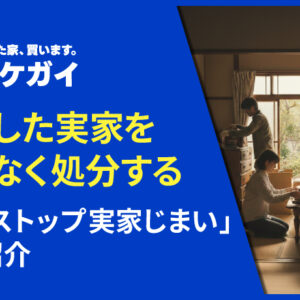について今すぐご相談できます。
お電話する
市街化調整区域にある土地を売却したいと考えても、思うように買い手がみつからないことがあります。建築制限や住宅ローンの審査の厳しさ、インフラの未整備などが障壁となり、通常の不動産市場では流動性が低くなるためです。
そのため、市街化調整区域の不動産売却には、一般の住宅地とは異なる注意点や手続きが求められます。
市街化調整区域とは、都市計画法によって無秩序な開発を防ぐために指定されたエリアのことです。住宅や商業施設の建築が制限されており、不動産の売却や活用にも影響を与えます。
規制を正しく理解していないと、売却がスムーズに進まなかったり、思わぬトラブルに発展することもあります。
本記事では、市街化調整区域の基本的な仕組みや売却が難しい理由、売却を成功させるための策について詳しく解説します。
目次
市街化調整区域とは?
市街化調整区域とは、都市計画法に基づき、市街化を抑制するために指定された区域のことです。簡単にいえば、「原則として新たな建物を建てることができないエリア」と考えられます。多くの市街地では住宅や商業施設が立ち並んでいますが、市街化調整区域では無秩序な開発を防ぐため、行政の許可なく建築することが制限されています。
市街化区域と市街化調整区域の違い
市街化区域と市街化調整区域は、都市計画における役割が異なっています。
市街化区域は、すでに多くの建物が立ち並び、今後も計画的に発展させていくエリアを指します。
道路や上下水道といったインフラが整備されており、住宅や商業施設の建設が可能です。一般的に「街」としてイメージされるのはこの市街化区域に該当します。
一方、市街化調整区域は、無秩序な開発を防ぐために新たな建物の建設が制限されているエリアです。農地や山林が多く、インフラ整備が進んでいないことも珍しくありません。原則として住宅の新築は許可されず、開発には厳しい条件が課せられます。
ただし、すでに建っている建物の改築や、一部の例外的な開発は認められることもあります。
市街化調整区域の不動産が売れにくい理由
市街化調整区域の不動産は、市街化区域に比べて売却が難しいとされます。その理由はいくつかありますが、特に影響が大きいのが以下のものです。
- 建築制限があるため需要が低いから
- 住宅ローン審査が厳しいため購入者が限られるから
- インフラ整備が不十分で生活が不便であるから
それぞれ個別にみていきましょう。
建築制限があるため需要が低いから
市街化調整区域では、基本的に新築住宅を建てることが認められていません。
一部例外として、既存の住宅を改築したり、特定の条件を満たせば新築が許可される場合もありますが、そのハードルは高いものです。
一般的な住宅地であれば、購入後に自由に家を建てられるため、幅広い層の購入希望者が集まります。
しかし、市街化調整区域ではその自由度が低く、「購入しても好きな用途で活用できない」という理由で、多くの人が購入を避けてしまうのです。
住宅ローン審査が厳しいため購入者が限られるから
住宅ローンを利用する際、金融機関はその土地の資産価値を評価し、融資の可否を決定します。
市街化調整区域の土地は、建築制限の影響もあり「資産価値が低い」とみなされることが多く、住宅ローンの審査が厳しくなります。
特に、新築が難しい土地では担保価値が低いと判断され、ローンが組めないことも少なくありません。
インフラ整備が不十分で生活が不便であるから
市街化調整区域は、市街化を抑える目的で設定されているため、上下水道やガス、道路といったインフラが整備されていないことがあります。
例えば、上下水道が整っていない場合、井戸水や浄化槽を利用する必要があり、購入希望者にとって大きな負担になります。
また、公共交通機関が少ないエリアも多く、車がなければ生活が成り立たないというケースも少なくありません。
市街化調整区域の不動産を売却するためのポイント
売れにくいとされる市街化調整区域の不動産ですが、売却が不可能というわけではありません。具体的には、以下のポイントを抑えるのが有効です。
- 売却しやすい物件を見極める
- 売却しにくい物件の特徴を把握する
- 適切な売却戦略を立てる
それぞれ個別に解説します。
売却しやすい物件を見極める
市街化調整区域の中でも、比較的売却しやすい物件にはいくつかの共通点があります。例えば、「すでに住宅や建物が建っている物件」は、新築制限の影響を受けにくいため、比較的需要が高くなります。
既存の住宅を活用することができれば、買い手にとってのメリットも大きく、売却の可能性が高まります。
また、市街化区域に隣接している土地や、将来的に市街化区域へ編入される可能性がある土地は、今後の価値上昇が期待されるため、投資目的での需要も見込めます。
自治体の都市計画を確認し、将来の開発予定があるエリアの物件は、適切なタイミングで売却すれば有利に取引ができることもあります。
売却しにくい物件の特徴を把握する
逆に、売却が難しい物件には、「インフラが未整備」「土地が狭小または変形している」「市街化区域から離れている」といった特徴があります。
特に、上下水道が整備されていない土地は、購入後に追加の設備投資が必要となるため、買い手にとっての負担が大きくなります。
また、市街化調整区域の中でも、周囲に開発の可能性がまったくないエリアは、今後の価値向上が見込めず、買い手がつきにくくなります。
適切な売却戦略を立てる
市街化調整区域の不動産を売却する際には、通常の不動産売却とは異なり売却が難しいのが実情です。そのため、まずは物件の特徴を正確に把握し、適正な価格を設定する必要があります。
市場価格を把握しないまま高値で売り出すと、売却までに時間がかかり、結果的に値下げを余儀なくされることもあります。
そのため、周辺の類似物件の売却事例を参考にしながら、適正価格を見極めることが求められます。
また、市街化調整区域の不動産は、通常の不動産会社では扱いにくいこともあるため、専門の業者を活用するのもひとつの手段です。
特に、市街化調整区域の買取を得意とする不動産会社に相談することで、スムーズな売却が期待できます。こ
市街化調整区域の不動産を売却する手順
市街化調整区域の不動産を売却するには、通常の不動産売却とは異なるプロセスを踏む必要があります。その手順は、大きく分けると6つのステップに大別されます。
- 手順①:市街化調整区域の規制を確認する
- 手順②:役所に相談し、必要な手続きを把握する
- 手順③:売却の目的に応じて方法を選ぶ(仲介 or 買取)
- 手順④:適正な売却価格を設定する
- 手順⑤:売却活動を開始し、買い手を探す
- 手順⑥:契約・引き渡しの流れを確認し、スムーズに進める
それぞれ個別に解説します。
手順①:市街化調整区域の規制を確認する
最初に行うべきことは、対象となる不動産がどのような規制を受けているのかを確認することです。市街化調整区域では、一般的に建築が制限されており、新築や用途変更には自治体の許可が必要となるケースが多くあります。
例えば、すでに建物がある場合でも、その建物を解体すると再建築が認められないことがあります。このような規制を事前に把握しておかないと、売却時にトラブルが発生しかねません。
規制を調べる方法としては、自治体の都市計画課や建築指導課に問い合わせるのが一般的です。また、不動産業者に相談すれば、過去の売却事例をもとにアドバイスをもらえることもあります。
手順②:役所に相談し、必要な手続きを把握する
市街化調整区域の不動産を売却する際には、事前に役所に相談して必要な手続きを確認しておくことが必要です。
特に、売却後に新しい所有者がどのようにその土地を利用できるのかを明確にするため、都市計画課や建築指導課に問い合わせておくとよいでしょう。
例えば、特定の条件を満たせば住宅を建築できる「開発許可」や、既存の建物をそのまま利用できる「既存宅地確認」など、土地の利用制限を緩和するための手続きがある場合もあります。
これらの許可が得られれば、売却のハードルが下がり、より多くの買い手を見つけやすくなります。
手順③:売却の目的に応じて方法を選ぶ(仲介 or 買取)
市街化調整区域の不動産を売却する際には、主に「仲介」と「買取」の2つの方法があります。
どちらを選ぶかによって、売却までのスピードや価格に違いが出るため、売却の目的に応じて適切な方法を選択することが重要です。
仲介による売却 は、不動産会社を通じて一般の買い手を探す方法。市場価格で売れる可能性があるため、売却価格を重視する場合に向いています。
ただし、市街化調整区域の物件は買い手が見つかりにくいため、売却までに時間がかかることもあります。
一方で、買取業者による売却 は、不動産会社や専門の業者が直接物件を買い取る方法です。市場価格よりは低い金額になることが多いですが、短期間で確実に売却できるというメリットがあります。
手順④:適正な売却価格を設定する
市街化調整区域の不動産は、市街化区域に比べて需要が低いため、適正な価格を設定しないと売却が長引いてしまいます。
市場価格を知るためには、周辺の類似物件の売却価格を調べたり、不動産会社に査定を依頼したりする方法があります。
査定を受ける際には、複数の不動産会社に依頼するのが望ましいです。市街化調整区域の物件を扱った経験がある業者であれば、適正な価格を見極めるためのアドバイスを受けることができます。
手順⑤:売却活動を開始し、買い手を探す
売却価格を決めたら、不動産会社を通じて売却活動を開始します。市街化調整区域の不動産は、一般的な住宅用地と比べて買い手が少ないため、売却のターゲットを明確にすることが重要です。
例えば、隣接する土地の所有者や、事業用地として利用したい企業・農家など、特定の需要がある層に向けてアプローチを行うと、スムーズに売却が進む可能性があります。
手順⑥:契約・引き渡しの流れを確認し、スムーズに進める
買い手が見つかったら、売買契約を締結し、引き渡しの準備を進めます。この際、契約条件や必要な書類をしっかり確認しておくことが重要です。
特に、市街化調整区域の不動産は利用制限があるため、契約内容に制約事項を明記し、トラブルを防ぐ工夫が必要です。
契約が完了し、買い手へ引き渡しが行われれば、売却の手続きは完了です。
市街化調整区域の不動産売却で発生する費用
市街化調整区域の不動産を売却する際には、以下のような費用が発生します。
- 登記関連費用
- 測量費用
- 譲渡所得税
- 印紙税
- 仲介手数料
- 解体費用・整地費用(必要な場合)
- その他の諸費用
それぞれ個別に確認していきましょう。
登記関連費用
不動産の売却時には、登記手続きが必要になります。売主が負担する可能性がある登記費用としては、「抵当権抹消登記費用」と「住所変更登記費用」が挙げられます。
もし売却する土地や建物に住宅ローンの抵当権が設定されている場合、売却前に抵当権を抹消しなければなりません。
その際に必要なのが抵当権抹消登記費用で、通常は司法書士に依頼して手続きを行います。
費用の相場は 1件あたり1〜2万円程度ですが、抵当権が複数設定されている場合にはその分だけ費用がかかります。
また、登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合は、住所変更登記が必要になります。例えば、引っ越しをして住所が変わっている場合や、結婚により姓が変わった場合などが該当します。住所変更登記の費用は 数千円〜1万円程度 が一般的です。
測量費用
売却する土地の境界が不明確な場合や、土地の一部を分筆して売却する場合には、測量を行う必要があります。
特に、市街化調整区域の土地は、都市部に比べて境界が曖昧になっていることが多く、測量が必須となるケースが少なくありません。
測量には、現況測量と確定測量の2種類が存在します。現況測量は簡易的な測量で、費用の相場は 10万円〜30万円 程度です。
一方、隣接地の所有者との立ち会いを行い、境界を正式に確定する確定測量は 50万円〜100万円 ほどかかることもあります。確定測量を実施すると、売却後の境界トラブルを防ぐことができるため、できるだけ早めに行っておくのが望ましいでしょう。
譲渡所得税
不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生すると、譲渡所得税が課されます。譲渡所得は「売却価格 −(購入価格 + 売却にかかった諸費用)」で計算され、この金額に税率をかけたものが課税額となります。
譲渡所得税の税率は、所有期間によって異なります。所有期間が5年以下(短期譲渡所得) の場合、税率は 39.63%(所得税30.63%+住民税9%) となり、高額な税負担になります。
一方、所有期間が5年を超える(長期譲渡所得) 場合は、税率が 20.315%(所得税15.315%+住民税5%) に軽減されます。そのため、売却のタイミングによっては税負担を大きく軽減できる可能性があります。
| 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計 | |
| 短期譲渡所得(5年以内) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期譲渡所得(5年超) | 15% | 5% | 0.32% | 20.32% |
(参考:国税庁「短期譲渡所得の税額の計算/長期譲渡所得の税額の計算」)
また、マイホームとして利用していた場合、「3,000万円特別控除」 を適用することで譲渡所得税をゼロにできるケースもあります。ただし、市街化調整区域の不動産の場合、条件を満たさないこともあるため、事前に税理士や不動産会社に確認するとよいでしょう。
印紙税
売買契約書を作成する際には、印紙税がかかります。印紙税は契約書に「収入印紙」を貼り付けて納める税金です。印紙税の金額は、売買金額に応じて以下のように決まります。
| 契約金額 | 印紙代 |
| 1〜10万円 | 200円 |
| 10〜50万円 | 400円 |
| 50〜100万円 | 1,000円 |
| 100〜500万円 | 2,000円 |
| 500〜1,000万円 | 1万円 |
| 1,000〜5,000万円 | 2万円 |
| 5,000万〜1億円 | 6万円 |
| 1億〜5億円 | 10万円 |
| 5億〜10億円 | 20万円 |
| 10億〜50億円 | 40万円 |
| 50億〜 | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
(参考:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」)
売却価格が高くなるほど印紙税も増えるため、事前に必要な額を確認しておくとスムーズに手続きを進められます。
仲介手数料
不動産会社に売却を依頼する場合、成功報酬として仲介手数料が発生します。仲介手数料は 売却価格の3% + 6万円(税別) が上限とされており、例えば1,000万円で売却した場合は 36万円(税別) の手数料がかかります。
仲介手数料は売却が成立した際にのみ発生するため、売れなければ支払う必要はありません。ただし、広告費用や測量費用を別途請求されることがあるため、契約前にしっかり確認しておくことが大切です。
解体費用・整地費用(必要な場合)
売却前に古い建物を解体し、更地にする必要がある場合は、解体費用が発生します。解体費用の相場は、建物の構造によって異なりますが、以下が目安となります。
<解体費用の目安(1坪あたり)>
- 木造住宅:3〜5万円
- 鉄骨造住宅:5〜7万円
- RC(鉄筋コンクリート)造:7〜10万円
また、土地をそのまま売却する場合でも、雑草の除去や地盤の均し作業など、最低限の整地費用が必要になることがあります。
その他の諸費用
その他に発生する可能性のある費用としては、司法書士報酬や税理士報酬があります。
特に、譲渡所得税の計算や申告が必要な場合、税理士に依頼すると 5万円〜10万円程度 の費用がかかるのが一般的です。
また、隣地との境界に関するトラブルが発生した場合には、弁護士費用が発生することも考えられます。
市街化調整区域の不動産を売却する際には、こうした諸費用を事前に把握し、資金計画を立てておくことが重要です。予想外の出費が発生しないよう、売却前にしっかりと準備しておきましょう。
「ワケガイ」なら市街化調整区域の物件も買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり不動産の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。
市街化調整区域の土地や建物は、通常の市場で買い手がつきにくく、売却に時間がかかるケースが多いですが、ワケガイではこれまで多くの取引実績を積み重ね、迅速な買取を実現しています。
市街化調整区域の不動産は、建築制限や住宅ローンの審査の厳しさ、インフラ未整備といった理由から売却が難しくなる傾向があります。加えて、一般の不動産会社では取り扱いを敬遠されることも少なくありません。
しかし、ワケガイではこうした特殊な物件の売却に精通し、独自のネットワークを活かして買い手を見つけることが可能です。お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
市街化調整区域の不動産を売却する際には、通常の不動産売却とは異なる規制や手続きが伴います。まずは、市街化調整区域の特性を理解し、自治体での確認を怠らないことが重要です。
規制によって売却の可否が大きく左右されるため、事前に役所へ相談し、どのような用途で売れるのかを確認しておきましょう。
また、市街化調整区域の不動産は、一般の買い手が見つかりにくいため、売却方法の選定も慎重に行う必要があります。
仲介と買取のどちらが適しているのか、適正価格をどう設定すべきかを考え、不動産会社と十分に相談しながら進めることが求められます。売却が難しい場合には、土地活用や賃貸、寄付といった選択肢を検討するのもひとつの手です。
適切な情報をもとに準備を整え、最適な売却方法を見極めることで、市街化調整区域の不動産でもスムーズな売却が可能になります。まずは、所有している土地の現状を把握し、売却の選択肢を広げることから始めましょう。