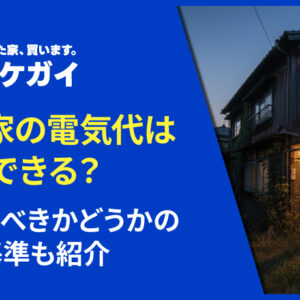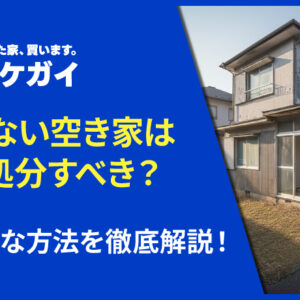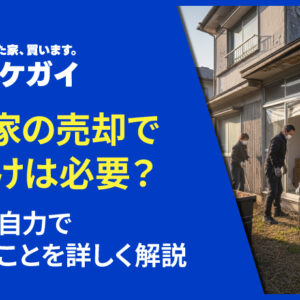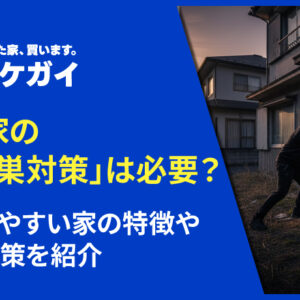について今すぐご相談できます。
お電話する
賃貸物件で入居者が亡くなると、オーナーは突然の対応を迫られます。事故物件として扱われるのか、家賃相場はどの程度下がるのか、賃貸活用は可能なのかなど、多くの疑問が生じます。その際に知っておくべきなのが「事故物件の取り扱い」です。
事故物件とは、物件内で人が亡くなった経緯や影響の度合いによって、心理的瑕疵物件として扱われる可能性がある不動産のことです。このような物件は通常の市場では敬遠されやすく、賃貸や売却に慎重な判断が求められます。
本記事では、事故物件の定義や家賃相場、賃貸活用時のリスクや工夫、売却の可能性について詳しく解説します。事故物件を所有するオーナーが、適切な判断をするために役立つ知識を提供します。
目次
事故物件とは何か?
事故物件とは、一般的に「過去に何らかの理由で人が亡くなった履歴がある物件」を指します。ただし、すべての死亡ケースが事故物件とみなされるわけではありません。
孤独死や病死のように、自然な経緯で亡くなった場合は、基本的には事故物件とはされません。一方で、事件性のある死亡や、発見までに時間がかかった孤独死などは、事故物件として扱われることが多くなります。
特に、特殊清掃が必要になったケースでは、次の入居者が心理的負担を感じる可能性があるため、事故物件とみなされることが一般的です。
また、火災や災害によって亡くなった場合も、一定の条件下では事故物件と見なされることがあります。
事故物件には告知義務がある
事故物件であることを借り手に告知する義務は、国土交通省が定めるガイドラインによって一定の基準が示されています。
2021年に公表された「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸物件の場合、事件・事故による死亡は原則として告知が必要 となっています。ただし、自然死や日常的な病死の場合は告知義務がないとされています。
また、告知義務が必要な期間についてもガイドラインが定められています。原則として事故発生から3年間は告知が必要 ですが、それ以降は特に説明する義務はないとされています。
ただし、新たな入居者が「心理的瑕疵がある」と判断する可能性がある場合は、3年を経過していても告知すべきケースがあります。
例えば、死亡事故が報道されて広く知られている場合や、建物に大きな損傷が残っている場合などです。
(参考:国土交通省「『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』を策定しました」)
所有物件で入居者が亡くなった場合の対応方法
賃貸物件で入居者が亡くなってしまった場合、オーナーとしては冷静に適切な対応を取ることが求められます。少し多いですが、以下の対応方法を把握しておきましょう。
- 警察・関係機関への連絡と現場確認を行う
- 管理会社・保証人・遺族と連携して対応を決める
- 賃貸契約の解約手続きを進める
- 部屋の原状回復や特殊清掃の手配をする
- 事故物件としての告知義務を確認する
- 今後の賃貸継続または売却の選択肢を検討する
次項より、個別に解説します。
警察・関係機関への連絡と現場確認を行う
入居者が物件内で亡くなった場合、まず警察が現場検証を行います。事故や事件性の有無を確認するため、オーナーが最初にするべきことは、警察や関係機関の指示に従いながら状況を把握することです。
一般的に、警察が現場を調査し、必要な場合は検視を行います。その間、オーナーは室内に立ち入ることができませんが、現場の状況について警察から説明を受けることは可能です。
この際、どのような経緯で亡くなったのか、発見時の状況はどうだったのかを確認し、今後の対応に備えます。特に事件性がある場合や、発見が遅れて遺体の損傷が激しい場合は、後の手続きや原状回復に影響するため、しっかり情報を把握しておくことが重要です。
管理会社・保証人・遺族と連携して対応を決める
警察の調査が終わると、次に管理会社や遺族、保証人と連携して具体的な対応を決めていきます。
まず、管理会社がいる場合は、物件の今後の管理について相談します。管理会社が間に入ることで、遺族や保証人とのやり取りをスムーズに進めることができます。
遺族がいる場合、亡くなった方の荷物の処分や契約の整理について協議が必要になります。遺族が遠方にいるケースでは、すぐに対応できないこともあるため、どのように進めるか事前に確認しておくと良いでしょう。
賃貸契約の解約手続きを進める
入居者が亡くなった場合、賃貸契約は当然に終了するわけではなく、正式な解約手続きが必要です。
遺族や保証人がいる場合、まずは契約書を確認し、誰が解約手続きを進めるべきかを明確にします。
通常、連帯保証人や遺族が解約手続きを行うことになりますが、保証人がいない場合や遺族が手続きを拒否した場合は、オーナー側が対応を進める必要があります。
部屋の原状回復や特殊清掃の手配をする
入居者の死亡後、物件を再び貸し出すためには、適切な原状回復が必要になります。特に、孤独死や事件が関わる場合、通常の清掃では対応しきれないケースがあるため、特殊清掃の手配が必要になることもあります。
特殊清掃では、血液や体液の除去、消臭作業、害虫駆除などが行われます。
発見が遅れた場合は、通常のリフォームでは済まないことが多く、床や壁の張替えが必要になることもあります。そのため、清掃費用や原状回復の見積もりを早めに取ることが重要です。
事故物件としての告知義務を確認する
前述のように、事故物件には一定の告知義務があります。オーナーとしては、入居希望者に対してどこまで情報を開示すべきかを確認し、適切な対応を取ることが求められます。
国土交通省のガイドラインによれば、事故発生から3年間は新しい入居者に告知する義務があります。
ただし、期間が過ぎたとしても、心理的瑕疵が残る場合には、告知が必要になることも。特に、事件性のあるケースやメディアで報道された事故の場合は、長期間にわたって影響を受ける可能性があるため、慎重に判断することが大切です。
今後の賃貸継続または売却の選択肢を検討する
物件を再び賃貸に出すか、それとも売却するかを決めることも、オーナーにとって重要な判断のひとつです。
事故物件は一般的な物件よりも入居者が集まりにくく、家賃を下げなければならないことが多いですが、立地や条件によっては十分に貸し出せるケースもあります。
事故物件専門の不動産会社に相談し、実際にどの程度の家賃であれば需要があるのかを確認することが重要です。
事故物件の家賃相場はどのくらい?
事故物件は、一般的な賃貸物件と比べて家賃が低く設定される傾向があります。しかし、どの程度下がるのかは、立地や事故の内容によって異なります。
オーナーとしては、適正な家賃設定をすることで、空室リスクを抑えながら収益を確保することが重要になります。
事故物件の家賃相場は、通常の物件と比べて 20~30%程度安くなるケースが多いとされています。例えば、同じエリア・同じ間取りの物件が月額10万円で貸し出されている場合、事故物件であれば7万円〜8万円程度が相場になることが一般的です。
ただし、事件性のあるケースや、長期間発見されなかった孤独死などは、さらに値下げしないと入居者が決まりにくくなることもあります。
また、告知義務の期間が過ぎた後は、家賃を相場に戻すことも可能です。国土交通省のガイドラインでは、死亡事故が発生して 3年が経過すれば、新たな入居者に対する告知義務は基本的に不要 とされています。
そのため、この期間を過ぎた後に家賃を再調整することも選択肢のひとつです。
事故物件を賃貸活用するリスク
事故物件を賃貸として運用する際、通常の物件とは異なるリスクが伴います。具体的には、以下のようなものです。
- 入居者が集まりにくい
- 家賃を下げても空室が続く
- 告知義務違反によるトラブル
- 周辺住民の風評被害
- 短期退去や契約解除が増える
- 物件価値が下がり売却しにくくなる
トラブルを回避するためにも、しっかりと把握しておきましょう。
入居者が集まりにくい
事故物件に対して心理的な抵抗を感じる人は多く、一般的な賃貸物件よりも入居者を確保するのが難しい傾向にあります。
特に、事件性のある死亡や長期間放置された孤独死などのケースでは、告知義務がある期間中は敬遠されやすくなります。
ただし、事故物件を気にしない層も一定数存在します。例えば、家賃の安さを重視する人や、留学生・外国人など、日本の事故物件に対する考え方に影響されにくい層をターゲットにすることで、入居者の確保につながる場合もあります。
家賃を下げても空室が続く
家賃を下げれば入居者が見つかりやすくなると考えがちですが、それでも空室が続くことがあります。
特に、近隣に同じような間取りや設備の通常の物件が多い場合、事故物件を選ぶ理由が少なくなり、競争力が落ちる可能性が高まります。
告知義務違反によるトラブル
事故物件であることを入居希望者に適切に伝えなかった場合、契約後にトラブルになるケースがあります。
国土交通省のガイドラインでは、「心理的瑕疵のある物件は、一定期間告知する義務がある」とされており、これを怠ると後に契約解除や損害賠償を求められる可能性があります。
周辺住民の風評被害
事故物件は、オーナーだけでなく周辺の住民にも影響を及ぼしかねません。特に、事件性のある死亡事故が発生した場合、近隣の住民が不安を感じたり、物件に対してネガティブな印象を持つことがあります。
短期退去や契約解除が増える
事故物件は、入居者が途中で心理的な違和感を覚え、短期間で退去してしまうケースもあります。
入居時には気にしなかったとしても、実際に住んでみて不安を感じる人もいるため、結果的に契約解除が増える可能性が懸念されます。
物件価値が下がり売却しにくくなる
事故物件は、一般的な物件と比べて売却が難しくなります。心理的瑕疵があるため、通常の市場では買い手が見つかりにくく、価格も大幅に下がる傾向があります。
売却を検討する場合、事故物件を専門に扱う買取業者に相談するのが有効です。一般の不動産市場よりも安くなることが多いですが、早期に現金化できる点がメリット。
また、リノベーションを施し、物件の印象を変えることで売却しやすくなる場合もあります。
事故物件を賃貸活用する際の工夫
事故物件は心理的瑕疵があるため、一般の物件よりも入居者を見つけるのが難しい傾向が見受けられます。しかし、適切な工夫をすることで、賃貸運用を成功させることも可能です。
ここでは、入居者の心理的ハードルを下げる方法や、家賃設定、長期空室への対策について解説します。
入居者の心理的ハードルを下げる工夫をする
事故物件の最大の課題は、心理的な抵抗感です。これを和らげるために、まずは室内の雰囲気を一新することが重要です。
リフォームやリノベーションを施し、事故を感じさせない空間作りを行うと、入居希望者の印象が大きく変わります。
特に、クロスや床の張り替え、照明の変更は手軽にできるため、見た目の印象を改善しやすい方法です。
家賃設定のバランスを考える
事故物件は、一般の物件よりも家賃を下げる必要がありますが、どこまで下げるべきかが難しいポイントです。家賃を大幅に下げすぎると収益性が悪化しますし、逆に下げ幅が少なすぎると入居者が見つかりません。
長期空室リスクに備える
事故物件は、通常の物件よりも空室期間が長くなる傾向が見受けられます。そのため、収益が不安定にならないよう、空室リスクに備えておくことが大切です。
まず、事故物件に特化した不動産会社や、訳あり物件を専門に扱う賃貸業者と提携することで、通常の募集よりもスムーズに入居者を見つけられる可能性があります。
賃貸活用を諦めた場合、事故物件の売却は可能?
事故物件を賃貸に出すのが難しいと判断した場合、売却を検討することになります。ただし、通常の物件よりも売却が難しく、価格も安くなりやすいため、慎重な判断が求められます。
事故物件でも売却自体は可能ですが、一般的な市場では買い手がつきにくいのが実情です。特に、心理的瑕疵が強い物件は、個人の購入希望者が避けるため、売却までに時間がかかることがあります。
しかし、事故物件専門の買取業者や投資家向けの市場では、通常の不動産市場とは異なる基準で取引されるため、売却が成立しやすくなります。売却先の選択肢を広げることが重要になります。
売却価格の相場はどのくらい?
事故物件の売却価格は、一般の相場よりも30~50%程度安くなることが多いとされています。ただし、事故の内容や立地によって価格の下落幅は異なります。
例えば、事故の発生から時間が経過し、告知義務の期間(3年以上)が過ぎている場合、影響は軽減され、比較的高値で売却できる可能性があります。
一方で、事件性のある事故や、広く報道されたケースでは、価格が大きく下がることが一般的です。
売却時の告知義務はどうなる?
事故物件を売却する場合、買主に対して過去の事故の事実を告知する義務があります。賃貸の告知義務と同様に、売却時も 事故から3年間は原則として告知が必要 ですが、事故の影響が長引く場合は、3年を過ぎても告知が求められるケースも存在します。
また、売却後に「告知されていなかった」としてトラブルになるケースもあるため、不動産会社と相談しながら、適切に情報を開示することが大切です。
事故なら訳あり物件専門の買取業者がおすすめ!
通常の不動産市場で売却が難しい場合は、事故物件専門の買取業者 に相談するのが有効です。
こうした業者は、事故物件をリノベーションして再販したり、賃貸用に転用するノウハウを持っているため、一般市場よりもスムーズに売却できる可能性があります。
また、売却までのスピードが速く、早急に現金化したい場合にも適しています。ただし、一般市場で売るよりも価格が低くなることが多いため、複数の業者に査定を依頼し、最も条件の良いところを選ぶことが重要です。
「ワケガイ」なら訳あり物件も短期で買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり物件の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。市場での売却が難しい事故物件でも、豊富な実績をもとに、スピーディかつ適正な価格で買取を実施しています。
事故物件は、通常の不動産市場では買い手がつきにくく、売却までに時間がかかることが一般的です。さらに、告知義務の有無や価格の設定、周辺住民の風評リスクなど、慎重な対応が求められます。
そのため、売却を検討しているものの、手続きの煩雑さや買い手探しに悩むオーナー様も少なくありません。
ワケガイでは、こうした課題を解決するため、専門スタッフが物件の状況を的確に把握し、迅速な査定と買取を行っています。最短1日での契約完了も可能ですので、お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
事故物件を所有すると、家賃相場の下落や入居者が集まりにくいなどの課題に直面します。賃貸活用する場合は、適切なリフォームや家賃設定、ターゲット層の見極めが重要です。
一方、賃貸が難しい場合は売却も検討すべき選択肢となります。
売却を考える際は、事故物件の市場価値や告知義務の期間を確認し、適正な価格で売却できる方法を選ぶことが求められます。特に、専門の買取業者を活用すると、スムーズに取引が進む可能性があります。
事故物件の取り扱いは、慎重かつ戦略的に進める必要があります。賃貸か売却か、自身の状況に合わせた最適な選択を行いましょう。
運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |