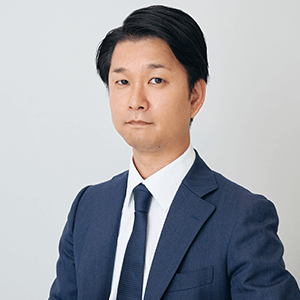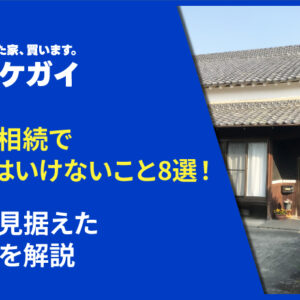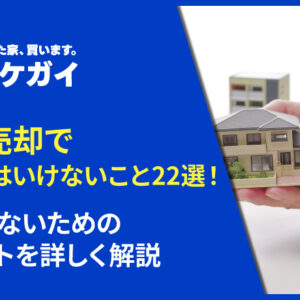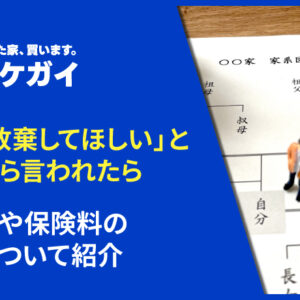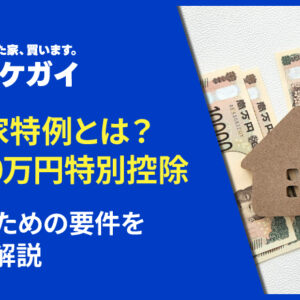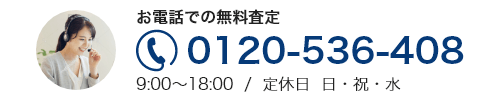について今すぐご相談できます。
お電話する
築50年以上の古民家を売却するケースでは、建物の老朽化や耐震性の問題から、一般の買い手がつきにくく、売却が難航するといった問題が発生します。
その際に直面するのが、建物の資産価値の低下や住宅ローンが通りにくいといった課題です。
古民家の売却は、建物の状態や立地条件、売却方法によって価格や期間が大きく変わってきます。適切な方法を選択しないと、必要以上に時間がかかったり、予想以上の費用負担が生じたりするリスクがあります。
そこで本記事では、古民家を売却する際の具体的な方法や注意点、活用できる制度などについて詳しく解説します。
目次
古民家の売却が難しい理由
築50年以上の古民家は、建物の老朽化や耐震性の問題により、通常の中古住宅と比べて売却が難しくなります。その理由としては、以下が挙げられます。
- 建物の評価が低くなりやすい
- 住宅ローンが利用しにくい
- 解体費用が発生する可能性がある
それぞれ個別に解説します。
建物の評価が低くなりやすい
古民家の場合、建物の資産価値はほぼゼロとみなされがちです。国税庁が定める木造住宅の耐用年数は22年で、この期間を超えると減価償却が進み、固定資産税評価額が低くなります。
ただし、市場価値が完全にゼロになるわけではなく、地域の需要や建物の状態によっては一定の価値が認められるケースもあります。
特に、観光地や移住希望者向けの市場では、リノベーション前提で購入を検討する買主も存在するため、価格設定の際にはこうした需要を考慮することが重要です。
(参考:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」)
住宅ローンが利用しにくい
金融機関は古民家の購入に対して、住宅ローンの貸し出しに慎重な姿勢を見せる傾向があります。築年数が古い建物は、将来的な耐久性や安全性に不安があるためです。
住宅ローンを利用する際、購入する不動産は担保として設定されます。しかし、古民家は建物の資産価値が低いため、担保評価が低くなり、一般的な住宅ローンでは審査が通りにくいことがあります。
ただし、一部の地方銀行や信用金庫では「古民家再生ローン」や「リノベーションローン」を提供している場合があり、住宅ローンと併用することで資金調達が可能なケースもあります。
そのため、買主に対しては、こうしたローンを利用できる可能性についても案内しておくとよいでしょう。
解体費用が発生する可能性がある
古民家は建物の老朽化が進んでいることが多く、解体を検討しなければならないこともあります。一般的な木造住宅の解体費用は、30坪で150万円前後。これに加えて、建物内の家財道具の処分費用も必要になってきます。
さらに、建物を解体して更地にすると、固定資産税の住宅用地特例(小規模住宅用地の特例)が適用されなくなり、税負担が増える可能性があります。
具体的には、固定資産税の課税標準額が、住宅用地では最大1/6に軽減される仕組みになっています。そのため、更地にすると課税標準額が上昇し、税負担が最大で6倍に増えるケースもあります。
ただし、土地の面積や用途地域によって負担増加の度合いは異なるため、事前に自治体の税務課などでシミュレーションを行い、売却戦略を検討することが重要です。
古民家の効果的な売却方法
古民家の売却方法は大きく分けて3つあります。
- 不動産会社の仲介を利用
- 専門業者への直接買取の依頼
- 空き家バンクの活用
それぞれの特徴を理解し、物件の状態や希望する売却時期に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。次項より、順番に解説します。
不動産会社の仲介を利用
不動産会社による仲介は、一般的な売却方法といえます。立地が良好で、リノベーション済みの古民家であれば、市場価格での売却が期待できます。
また、不動産会社のネットワークを活用して、幅広く買い手を募ることができる点も魅力です。
仲介での売却手順
仲介での売却は、複数の不動産会社に査定を依頼することから始まります。査定額や提案内容を比較し、信頼できる会社を選定します。その後、媒介契約を結び、物件の広告掲載や内覧対応などの販売活動がスタートします。
買い手が見つかれば、価格交渉を経て、売買契約の締結へと進みます。一連の流れには通常3〜6か月ほどの期間を要します。
専門業者への直接買取の依頼
老朽化が進んでいたり、立地条件が良くない古民家の場合は、買取専門業者への売却がおすすめです。
買取業者は自社で物件を購入するため、仲介のように買い手を探す必要がありません。残置物の処分や修繕の必要もなく、現状のままでの売却が可能です。
直接買取での売却手順
買取専門業者への売却は、最短で1週間程度で完了します。まずは買取業者に査定を依頼し、提示された金額に納得できれば、売買契約を締結します。
仲介手数料が不要な点も特徴的です。ただし、買取価格は市場価格より低めになる傾向があります。
空き家バンクの活用
自治体が運営する空き家バンクへの登録も、古民家売却の選択肢の1つです。地方移住を考える人々へ向けて、物件情報を広く発信できます。
また、空き家バンクに登録することで、自治体の補助金制度を利用できる可能性も出てきます。
空き家バンクでの売却手順
空き家バンクに登録するには、まず自治体の担当窓口へ相談します。登録が認められると、自治体のウェブサイトなどで物件情報が公開されます。
購入希望者との交渉や契約は、提携する地元の不動産会社が仲介役となって進められます。なお、空き家バンクは地域によって運営方法が異なるため、詳細は各自治体へ確認が必要です。
古民家売却で損をしないためのポイント
古民家を少しでも高く売却する上では、以下のポイントを意識しましょう。
- 売却前に建物調査を実施する
- 耐震診断で信頼性を高める
- 適切な売却価格を設定する
次項より、詳しく解説します。
売却前に建物調査を実施する
建物調査(ホームインスペクション)の実施は、売却後のトラブルを防ぐだけでなく、調査結果を買主に提示することで、信頼性を高め、売却価格の維持にも繋がります。
築年数が経過した建物には、目視では確認できない劣化や損傷が潜んでいることがあります。
建物調査では、建築士などの専門家が基礎や外壁、屋根裏などを細かくチェックします。調査費用は5〜10万円程度ですが、この投資には大きな意味があります。
調査結果をもとに補修の必要性を判断できるだけでなく、買主に対して建物の状態を明確に説明することが可能になります。売却後のトラブルを防ぐ効果も期待できるでしょう。
耐震診断で信頼性を高める
1981年の建築基準法改正以前に建てられた古民家は、現行の耐震基準を満たしていない可能性が高くなります。耐震診断を実施することで、建物の安全性に関する具体的なデータを示すことができます。
耐震診断の費用は10万円前後。診断の結果、耐震性に問題があると判明した場合は、耐震補強工事を検討することも選択肢の1つです。
自治体によっては、耐震診断や耐震補強工事への補助金制度を設けているケースもあり、これらを活用することで費用負担を軽減できます。
適切な売却価格を設定する
古民家の価格設定では、建物の資産価値はほぼゼロとして考える必要があります。
価格の中心となるのは土地の評価額です。近隣の取引事例や地価の推移を参考にしながら、実勢相場を見極めましょう。
建物調査や耐震診断の結果が良好であれば、それらを価格に反映させることも可能です。ただし、必要以上に高額な価格設定は、買い手がつかない原因となります。
売却にかかる諸費用も考慮しながら、市場に受け入れられる価格帯を見極めることが重要です。買取業者への相談や、複数の不動産会社による査定を参考にするのも有効な方法といえます。
古民家売却で発生する費用/税金
古民家の売却では、さまざまな費用や税金が発生します。具体的には、次のとおり。
- 登記関連費用
- 譲渡所得税
- 印紙税
- 仲介手数料(※仲介を利用した場合)
- 解体費用(※解体して売却する場合)
以下より、個別にみていきましょう。
登記関連費用
不動産を売却する際、売主が負担する登記関連費用として、主に以下の2つが挙げられます。
①:抵当権抹消登記
住宅ローンを完済している場合、売却時には抵当権を抹消する登記手続きが必要です。
- 登録免許税:不動産1件につき1,000円
- 司法書士報酬:依頼する場合は1万〜2万円前後
自分で法務局に申請する場合は、登録免許税のみ(1件1,000円)で済ませることが可能です。
(参考:国税庁「登録免許税のあらまし」)
②:相続登記(相続した不動産を売却する場合)
相続によって取得した不動産を売却する際には、事前に相続登記を行う必要があります。2024年4月1日から相続登記が義務化され、過去の相続分も含めて適用対象となります。
相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため、相続が発生したらできるだけ早めに登記を行いましょう。
- 登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
- 司法書士報酬:5万円〜10万円前後
また、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書の作成や追加費用が発生する場合があります。
(参考:国税庁「登録免許税のあらまし」)
譲渡所得税
古民家を売却して利益が出た場合、譲渡所得税の納付が必要となります。税額は「売却価格−(取得費+譲渡費用)」で計算される譲渡所得に対して課されます。所有期間が5年を超える場合は20%、5年以下の場合は39%の税率が適用されます。
譲渡所得税を軽減できる特例制度も用意されています。例えば、相続した古民家であれば「相続空き家の3,000万円特別控除」により、最大3,000万円までの控除を受けられる可能性があります。
ただし、適用条件として「1981年5月31日以前に建築されたこと」「相続開始直前に被相続人が居住していたこと」「相続後、賃貸などに使用されていないこと」などの要件を満たす必要があります。
また、売却後に確定申告を行わないと特例を受けられないため、注意が必要です。
(参考:国税庁「短期譲渡所得の税額の計算/長期譲渡所得の税額の計算」)
印紙税
不動産売買契約書に貼付する収入印紙にかかる税金です。売却価格に応じて税額が定められており、売主・買主がそれぞれ負担します。
例えば、売却価格が5,000万円の場合、印紙税は6万円(2024年3月31日までの軽減税率が適用される場合は3万円)となります。
(参考:国税庁「印紙税」)
仲介手数料(※仲介を利用した場合)
不動産会社による仲介売却の場合、仲介手数料が発生します。手数料は売却価格によって法律で上限が定められています。
一般的な計算式は「売却価格×3%+6万円(税別)」です。売却価格が400万円以下の場合は、一律18万円(税別)が上限となります。
解体費用(※解体して売却する場合)
古民家を解体して更地にして売却する場合は、解体費用が必要です。木造住宅の解体費用は一般的に1坪あたり3〜5万円。
30坪の古民家であれば、90万円〜150万円程度の費用が見込まれます。さらに、家財道具などの残置物がある場合は、その処分費用も別途必要となってきます。
古民家売却で使える補助制度
古民家の売却時には、自治体が提供するさまざまな補助制度を活用できます。
特に解体や耐震改修に関する支援制度は、売却時の費用負担を大きく軽減できる可能性がありますので、個別にみていきましょう。
解体費用に対する補助金
自治体によって、老朽化した空き家の解体に対する補助金制度を設けています。例えば、東京都板橋区では住宅の除却に要する費用に対して最大200万円が支給されます。
補助金の交付には「倒壊の危険がある」「周辺環境に悪影響を及ぼす」といった条件を満たす必要があり、事前に建築士による調査が求められます。
耐震改修を支援する制度
1981年以前に建てられた木造住宅を対象に、耐震診断や耐震改修工事の費用を補助する制度があります。
耐震診断は費用の3分の2程度、耐震改修工事では工事費用の23%(上限100万円)が補助される例が多く見られます。
売却時に利用できる税制優遇
古民家を売却する際には、いくつかの税制優遇制度を利用できます。例えば、相続した古民家を売却する場合、「空き家の3,000万円特別控除」を利用可能です。
また、自身が居住していた古民家であれば「居住用財産の3,000万円特別控除」の適用を検討できます。
古民家売却で起こりやすいトラブル例
ここからは、古民家売却で発生しやすいトラブル例を紹介します。
- 例①:購入者との価格交渉が難航する
- 例②:境界線や土地権利で揉める
- 例③:契約後に新たに瑕疵が発見される
それぞれ個別に解説します。
例①:購入者との価格交渉が難航する
古民家の場合、建物の価値評価が難しく、売主と買主の価格に対する認識の差が大きくなりがちです。特に解体を前提とした購入者からは、解体費用の負担を理由に大幅な値引きを要求されることがあります。
このような事態を避けるため、事前に建物調査を実施し、客観的なデータに基づいた価格設定を心がけましょう。
例②:境界線や土地権利で揉める
古い建物の場合、正確な境界が不明確なケースが多くあります。売却時に隣地との境界確認を行うと、これまで使用していた土地の一部が隣地の所有であることが判明するなど、予期せぬトラブルが発生することがあります。
土地家屋調査士による境界確定作業を事前に行うことで、このようなリスクを回避できます。
例③:契約後に新たに瑕疵が発見される
売買契約後に雨漏りや白アリ被害といった瑕疵が発見されると、買主から補修費用の請求や契約解除を求められる可能性があります。売主は「契約不適合責任」として、これらの要求に対応しなければなりません。
トラブル防止のためにも、事前に建物調査を実施し、発見された不具合は買主に説明しておくことが重要です。
相続した古民家を売却する際の注意点
相続した古民家を売却する場合、以下の点に留意しましょう。
- 名義変更の手続きには期限がある
- 遺産分割協議を適切に進める
- 相続税対策を行っておく
- 売却後は確定申告が必要
次項より、詳しく解説します。
名義変更の手続きには期限がある
相続した古民家を売却するには、まず不動産登記簿上の名義を被相続人から相続人に変更する必要があります。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の手続きは、法務局で行います。必要書類として、戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書などを準備する必要があります。
手続きは司法書士に依頼することもでき、その場合の費用は10万円前後となります。
(参考:東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !~」)
遺産分割協議を適切に進める
複数の相続人がいる場合、古民家の売却には全員の同意が必要です。相続人の中に行方不明者がいたり、意見が対立したりすると、売却手続きが進まなくなる可能性があります。
遺産分割協議書の作成は、できるだけ早い段階で進めることが賢明です。特に古民家の場合、時間の経過とともに建物の価値が下がり続けるため、迅速な対応が重要となってきます。
相続税対策を行っておく
相続税の申告期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内です。この期限内に適切な申告と納税を済ませていないと、古民家を売却する際にトラブルになる可能性があります。
なお、相続した古民家を売却する際には「相続した空き家の3,000万円特別控除」などの税制優遇を受けられる場合があります。税理士に相談しながら、適切な対策を講じることをおすすめします。
(参考:国税庁「相続税の申告と納税」)
売却後は確定申告が必要
古民家を売却した際には、翌年の確定申告で譲渡所得の申告が必要です。申告期間は売却した翌年の2月16日から3月15日までとなっています。
申告書類には、売買契約書のほか、仲介手数料の領収書や建物の登記事項証明書など、取引に関連する書類を添付します。
申告手続きは税理士に依頼することも可能で、費用は10万円前後が一般的です。なお、3,000万円特別控除などの特例を利用する場合は、必要書類が追加されるため、早めの準備が重要となります。
(参考:国税庁「土地や建物を売ったとき」)
売却以外の古民家を活用する方法
売却以外にも、古民家の価値を活かした活用方法があります。地域の特性や建物の状態に応じて、最適な活用方法を検討してみましょう。
- 賃貸物件として運用する
- リノベーションして活用する
- 地域活性化プロジェクトに提供する
- 観光施設や宿泊施設として利用する
- 空き家バンクで登録する
それぞれ個別に解説します。
賃貸物件として運用する
古民家をリノベーションし、賃貸物件として運用する方法があります。昨今では、古民家ならではの魅力を求める入居者も増えています。ただし、賃貸向けのリノベーション費用は相応にかかるため、収支計画の慎重な検討が欠かせません。
リノベーションして活用する
古民家カフェやアトリエ、シェアオフィスなど、用途を変更して活用する方法も注目されています。築年数を重ねた建物ならではの風情が、新たな価値を生み出すケースも少なくありません。
地域活性化プロジェクトに提供する
自治体や地域団体が進める地域活性化プロジェクトに古民家を提供する方法もあります。地域の交流拠点やコミュニティスペースとして活用されることで、地域貢献にもつながります。
観光施設や宿泊施設として利用する
古民家を民宿やゲストハウスとして活用する例も増えています。日本の伝統的な暮らしを体験したい観光客のニーズと合致し、インバウンド需要の受け皿としても期待されています。
「ワケガイ」なら古民家も短期で買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり物件の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。古民家の売却でお困りの方に向けて、スピーディーな対応と適正価格での買取を実現しています。
特に、老朽化が進んだ古民家や、相続した古民家の処分にお悩みの方からのご相談が増えています。当社では、建物の状態や立地に関わらず、最短即日での査定が可能です。また、建物に家財が残ったままでも、現状のまま買い取らせていただきます。
古民家は一般的な不動産売買では、建物の評価額が低く見積もられがちです。しかし当社では、豊富な買取実績とノウハウを活かし、適正価格での買取をお約束します。
古民家の売却についてお悩みの方は、お気軽に無料相談をご利用ください。全国どこでも無料で査定いたします。
まとめ
古民家の売却では、建物調査や耐震診断を実施し、物件の状態を正確に把握することから始めましょう。その結果をもとに、仲介・買取・空き家バンクなど、最適な売却方法を選択します。
また、解体費用の補助金や税制優遇など、活用できる制度は積極的に利用することをおすすめします。
相続した古民家の場合は、名義変更や遺産分割協議など、必要な手続きを計画的に進めることが重要です。売却以外の活用方法も視野に入れ、物件の価値を最大限に引き出す方法を検討しましょう。
運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |