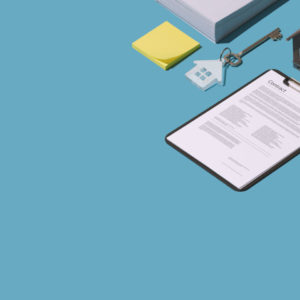夫婦や親子で住宅を購入する場合や、複数人で相続を受ける場合、不動産を共有名義にすることがあります。
しかし、この共有名義、不動産の売却や活用の際に「全員の同意が必要」といった制約があり、思わぬトラブルにつながることがあります。こうした場面で問題解決の鍵となるのが「不動産の共有名義」に関する正しい知識です。
共有名義とは、不動産を複数人で共同所有する形態のことで、それぞれの「持分」に基づいて権利や義務が分配されます。
共有名義は一見便利に見えても、管理や処分の場面では思わぬ障壁となることもあるため、あらかじめ仕組みやリスク、解消手段を理解しておくことが重要です。
本記事では、不動産の共有名義の基本から、メリット・デメリット、トラブルの回避策、解消の方法までを詳しく解説します。
目次
不動産の共有名義とは
不動産の「共有名義」とは、一つの物件を複数人で所有する形態を指します。それぞれの所有者は「持分(もちぶん)」という割合で権利を持ちます。
例えば、夫婦で住宅を購入し、夫が6割・妻が4割というように出資額に応じて名義を分ける場合がこれにあたります。
共有名義には主に以下3つの種類があります。
<共有名義の種類>
- 法定共有
- 準共有
- 共有
「法定共有」は、相続などによって法的に分割されるケース。「準共有」は、実体は個別の権利でも、法律上は共同所有と見なされる形。
そしてもっとも一般的なのが「共有」で、これは任意に持分を決めて不動産を共同所有する形態です。共有名義の不動産は、所有者全員の合意がなければ売却や大規模な改築ができません。
そのため、特に将来的な処分や相続を見据えると、メリットだけでなくトラブルの可能性も考慮する必要があります。便利さの裏にリスクもある。それが共有名義の不動産の特徴です。
不動産を共有名義にすることで得られるメリット
共有名義には制約もありますが、状況によっては有効に機能する場面もあります。代表的なメリットとしては、以下が挙げられます。
- 購入時の資金負担を分散できる
- 特定の相続人に偏らず財産を分配できる
次項より、個別に解説します。
購入時の資金負担を分散できる
住宅購入時に共有名義を選ぶ最大の理由のひとつが、資金面での負担軽減です。例えば夫婦や親子で住宅を共同購入する際、それぞれがローンを組むことで個人では手が届かない物件を取得できるケースがあります。
共有名義にすることで、出資割合に応じた住宅ローン控除もそれぞれが受けることが可能です(※一定の条件あり)。
加えて、持分に応じた費用分担が明確になるため、将来的な固定資産税や修繕費などの費用負担についてもトラブルを防ぎやすくなります。
資金面の連携が前提になる分、単独名義では得られない柔軟性が生まれるのが共有名義の特徴です。
ただし、収入状況やライフプランに変化があった場合、どちらか一方がローン返済を継続できなくなるリスクもあるため、あくまで慎重な設計が必要です。
特定の相続人に偏らず財産を分配できる
相続を見据えて不動産を共有名義にしておくことには、財産の公平な分配という観点で利点があります。
例えば親が亡くなった後、特定の子だけが不動産を単独相続する形だと、他の相続人との間で不満や争いが生じることがあります。
その点、あらかじめ持分を明示して共有名義にしておくと、それぞれが権利を主張しやすく、感情的なもつれを避けやすくなります。
また、法定相続分と異なる割合で持分を設定することで、生前贈与などの意思を反映させることも可能です。特に土地や建物といった分割が難しい不動産では、こうした工夫がのちの相続トラブルの予防につながります。
ただし、共有状態のまま相続が繰り返されると、共有者が増えすぎて管理が困難になるおそれもあります。そのため、共有名義にしたあとの見直しや解消も視野に入れることが現実的です。
不動産を共有名義にすることで生じる課題
共有名義は資金負担を分散できたり、相続時の公平性を保ったりするうえで有効ですが、日常の管理や将来の活用においてはさまざまな制約が伴います。
ここでは特に多くの人が悩みやすい3つの問題を取り上げて解説します。
売却や大規模修繕で「全員の同意」が必要になる
共有名義の不動産を売却したり、大規模なリフォームや建替えを行ったりする場合には、原則として共有者全員の同意が必要になります。
これは民法第251条に定められている「変更行為」に該当するためで、たとえ1%しか持分を持たない共有者が反対しても、その意思を無視して実行することはできません。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)
このルールは、親族間や夫婦間であっても例外ではありません。例えば、ある親子が持分を分けて家を所有していたとして、子どもが家を売却して現金化したいと望んでも、親が首を縦に振らなければ手続きは進みません。
また、修繕のように早急な対応が求められる場面でも、誰か一人でも反対すれば全体が止まってしまうという非効率な状況に陥る可能性があります。
共有名義を選ぶ際には、こうした「足並みを揃える必要性」が思った以上に大きな負担になることを理解しておくべきでしょう。
使用・収益行為では「過半数の同意」が求められる
不動産を賃貸に出す、第三者に一時的に使用させるといった行為は「使用・収益行為」と呼ばれます。これらを実施するには、持分の過半数による同意が必要です。
民法第252条で定められており、例えば3人の共有者がいれば、持分の合計が51%を超えるグループの賛成がなければ成立しません。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)
このルールは一見、少数派の意見を切り捨てられるようにも見えますが、実際には持分の比率によって影響力が大きく異なります。
例えば、Aが70%、BとCがそれぞれ15%を持っている場合、Aの一存で賃貸が決定されることになります。
過半数の同意で進められるとはいえ、話し合いや関係性がこじれていれば、手続きに支障をきたすこともあります。
特に共有者同士の距離感が遠くなりがちな相続後などは、収益化したくても動かせないという問題に直面する例が多く見られます。
共有者の死亡により相続関係が複雑化する
共有名義のまま共有者の一人が亡くなると、その人の持分は相続人に引き継がれます。
これは当然の権利ですが、実際には相続人が複数人いた場合に、その持分がさらに細かく分かれてしまうため、不動産の管理や処分が一層困難になります。
例えば3人の共有者のうち1人が亡くなり、その人に子どもが3人いた場合、ひとつの持分がさらに3分割され、全体では5人の共有状態になります。
しかも、その新しい相続人たちが不動産に興味がない、連絡が取れない、あるいは関係が悪化しているといった事情があれば、名義変更や売却の話が前に進まなくなります。
このような「名義の分散」が数世代にわたって続くと、事実上、誰も自由に動かせない“塩漬け不動産”になってしまうこともあります。特に地方や相続対策をしていない家庭では、深刻な社会問題にもなりつつあるテーマです。
共有名義の場合、固定資産税は誰が払う?
共有名義の不動産にかかる固定資産税は、各共有者が持分に応じて負担するのが原則です。ただし、納税通知書は基本的に1通しか発行されず、代表者として指定された人にまとめて届きます。
このため、実務上はその代表者がいったん全額を支払い、のちに他の共有者に持分割合に応じて請求する形が一般的です。
例えば、3人で不動産を共有しており、持分がそれぞれ50%・30%・20%だった場合、代表者が10万円の固定資産税を立て替えて支払ったとすると、後日それぞれに5万円、3万円、2万円ずつを請求する流れになります。
問題となるのは、この「立て替え→精算」のプロセスが、共有者間の信頼関係に依存している点です。
関係がこじれていたり、他の共有者が費用負担に非協力的だったりする場合、代表者が一方的に負担を抱えることになります。
また、もし代表者が滞納した場合、地方自治体は他の共有者にも納税を請求できるため、「自分の持分しか関係ない」という考え方では済まされないのが現実です。
固定資産税の支払いについては、共有名義のメリットとセットでしっかり話し合っておく必要があります。
共有名義人の片方が死亡した場合はどうなる?
共有名義の不動産を所有している人のうち、どちらかが亡くなった場合、その持分は自動的に残った共有者に移るわけではありません。亡くなった方の「持分」は、その人の相続人が引き継ぐことになります。
例えば、夫婦でそれぞれ50%ずつ所有していた家で夫が亡くなった場合、夫の50%分は妻のものにはならず、原則として法定相続人(この場合は妻や子どもなど)に相続されます。
ここで問題となるのは、相続人が複数いる場合や、その相続人と連絡が取りにくい、あるいは関係性が薄い場合です。
例えば夫の相続人が妻と3人の子であれば、その50%はさらに4等分され、それぞれ12.5%ずつの共有持分となります。
もとの持分が分割されることで、共有者が一気に増え、意思決定が難しくなるのです。
こうした状態が放置されると、不動産の売却や建て替えといった判断が進まず、いわゆる「塩漬け不動産」になりかねません。名義変更や持分の整理には相続登記が必要であり、相続人全員の協力が求められます。
共有名義を単独名義にする手順
共有名義で持っている不動産を単独名義に変更するには、いくつかのステップを経る必要があります。
簡単な手続きではないため、相手との関係や費用面の調整も含めて慎重に進める必要があります。ここでは、基本的な3つのステップに分けて流れを解説します。
- 手順①:共有者と交渉し、持分の譲渡について合意を得る
- 手順②:持分の売買契約を締結し、必要な書類を準備する
- 手順③:名義変更の登記を行い、単独名義にする
それぞれ個別にみていきましょう。
手順①:共有者と交渉し、持分の譲渡について合意を得る
最初のステップは、他の共有者と話し合い、その人の持分を譲ってもらうことについて合意を取り付けることです。
ここで重要なのは、相手にとっても納得できる条件を提示することです。「譲渡」といっても、無償で渡してもらえるわけではなく、多くの場合は金銭のやり取り、つまり持分の「買取」が必要になります。
相手の希望額と自分の支払い可能額がかけ離れていると、交渉が難航することもあります。感情的なもつれや相続トラブルを避けるためにも、あくまで冷静に、第三者の専門家(司法書士や不動産会社など)を交えて進めるとスムーズです。
手順②:持分の売買契約を締結し、必要な書類を準備する
持分譲渡の合意が取れたら、次に進むのが売買契約の締結です。一般的な不動産売買と同様に、持分を売る側と買う側の双方で契約書を作成し、押印します。加えて、名義変更の登記に必要な書類も事前に揃えておく必要があります。
主に必要となるのは以下のような書類です。
| 書類名 | 提出者 |
| 登記原因証明情報(売買契約書など) | 両者 |
| 登記識別情報(権利証) | 売主(持分を手放す側) |
| 印鑑証明書 | 売主(3か月以内) |
| 住民票 | 買主(名義人となる側) |
また、売買代金の支払いと引き換えに書類の受け渡しを行う「決済」も必要です。実務上は司法書士が立ち会うことが多く、登記に漏れがないかの確認もここで行います。
手順③:名義変更の登記を行い、単独名義にする
契約書と必要書類が揃ったら、最終的に法務局で名義変更の登記を行います。これにより、不動産の登記簿上の所有者が「単独名義」となり、法的にも完全な所有者となるわけです。
詳しくは後述しますが、この手続きでは登録免許税が発生します。
このステップが完了すると、名義上も実質上も、他の人の影響を受けることなく不動産を管理・処分できるようになります。
ただし、書類の不備や登記漏れがあると、あとでトラブルになる可能性があるため、手続きは専門家に依頼するのが一般的です。
共有名義を単独名義にした場合に発生する費用
共有名義を単独名義に変更するには、書類のやり取りや登記の手続きだけでなく、さまざまな費用がかかります。
意外と見落とされがちなのが、持分の買取代金以外のコストです。主には、以下4つが挙げられます。
- 費用①:持分の買取費用
- 費用②:登記変更にかかる登録免許税
- 費用③:司法書士や専門家への依頼費用
- 費用④:贈与とみなされた場合の贈与税
それぞれ個別にみていきましょう。
費用①:持分の買取費用
共有者から持分を譲り受ける場合、その分の代金を支払う必要があります。これは単なる手続きではなく、不動産の一部を買い取る「売買契約」となるため、市場価格をベースにした金額が発生します。
例えば、対象の不動産が3,000万円で、共有者が30%の持分を持っている場合、その買取費用は概ね900万円程度になります。もちろん、実際の価格は不動産の立地や状態、双方の合意によって変わります。
注意すべきなのは、買取価格を大幅に下げてもらった場合、税務署に「贈与」と見なされるリスクがある点です。この場合、後述する贈与税が別途課される可能性もあるため、適正価格の設定には慎重になる必要があります。
費用②:登記変更にかかる登録免許税
共有名義を単独名義に変更するには、法務局で登記の変更を行わなければなりません。この際に必要となるのが登録免許税で、不動産の名義を移すための国への手数料です。
税額の計算式は次のとおりです。
- 不動産評価額 × 2.0%(売買の場合)
例えば、譲り受ける持分の評価額が1,000万円であれば、登録免許税は20万円となります。この評価額は、固定資産税評価証明書に記載された金額を基に計算されます。
また、相続や贈与による名義変更の場合には税率が異なります(相続:0.4%、贈与:2.0%など)。売買と贈与ではコストに大きな差が出るため、どの方法を選ぶかで費用感が変わります。
(参考:国税庁「登録免許税の税額表」)
費用③:司法書士や専門家への依頼費用
名義変更の登記手続きは、自分で行うことも可能ですが、多くの場合は司法書士に依頼するのが一般的です。特に複雑な共有関係や書類の不備を避けたい場合は、専門家のサポートが不可欠です。
司法書士報酬の相場は、次のとおりです。
| 項目 | 費用の目安(税別) |
| 登記申請手続き | 3万〜7万円程度 |
| 売買契約書の作成・立会い | 2万〜5万円程度 |
依頼先によって金額は前後しますが、全体で5万〜10万円程度を見込んでおくと安心です。また、不動産会社や税理士が関与するケースでは、別途コンサルティング料が発生することもあります。
費用④:贈与とみなされた場合の贈与税
共有者から無償、または極端に安い金額で持分を譲り受けた場合、税務上は「贈与」とみなされる可能性があります。この場合、贈与税が課税されることになり、場合によってはかなり高額になります。
贈与税の基礎控除は年間110万円までです。それを超える部分については、以下の累進課税が適用されます。
| 課税価格(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
| ~200万円 | 10% | なし |
| ~400万円 | 15% | 10万円 |
| ~600万円 | 20% | 30万円 |
(参考:国税庁「贈与税がかかる場合」)
仮に市場価値500万円の持分を100万円で取得したとすると、差額の400万円が「贈与」として課税対象となる可能性があります。この場合、15%の税率がかかり、贈与税額は50万円前後になる計算です。
価格設定に不自然な点がないよう、持分の時価を意識して譲渡価格を決めることが、税務リスクの回避につながります。
共有名義のままで不動産を手放す方法
共有名義の不動産は単独では自由に処分しにくい一方で、名義を整理せずとも「持分」を手放すことは可能です。
ここでは、共有名義を維持したまま不動産を売却または整理する代表的な3つの方法を紹介します。
- 共有者全員での売却
- 共有者間での持分売買
- 自身の持分のみの第三者への売却
次項より、個別に解説します。
共有者全員での売却
もっともオーソドックスな方法は、共有者全員が合意して不動産を一括で売却するパターンです。この場合、共有名義のままでも物件全体として市場に出すことができるため、通常の不動産売買と同じように高値での売却が期待できます。
ただし、ここでの鍵は「全員の合意」です。共有者のうち一人でも反対する人がいれば、売却は成立しません。また、誰がどの程度の価格で納得するのか、売却益をどのように分配するのかなど、事前の調整が欠かせません。
不動産会社を介して売却を進める場合は、以下のような流れになります
- Step1.共有者全員で売却の意思を確認
- Step2.査定を依頼し、売却価格を決定
- Step3.売買契約を締結し、代金を持分に応じて分配
売却が完了すれば、名義ごとの処理は不要になり、共有関係も解消されます。
共有者間での持分売買
もう一つの選択肢は、共有者同士で持分を売買する方法です。例えば「兄弟で共有していたが、自分は家に住む予定がないので、他の兄弟に持分を売る」といったケースがこれにあたります。
この方法であれば、不動産全体を市場に出さずに手放すことができるため、比較的スムーズに進めやすい特徴があります。売買に必要な手続きは通常の持分譲渡と同じで、売買契約の締結や登記の変更が必要になります。
注意点として、持分の評価額や売買価格の妥当性を共有者同士で納得しておく必要があります。
極端に安い金額にすると、税務上「贈与」と見なされるリスクもあるため、評価証明書などで根拠を明示しておくと安心です。
この方法のメリットは、相手が既にその不動産に関わっている人物であるため、交渉や意思疎通が比較的取りやすい点にあります。
自身の持分のみの第三者への売却
共有者全員の同意が得られない場合でも、自分の持分だけを第三者に売却することは法律上可能です。これは「持分売却」と呼ばれ、不動産全体ではなく、所有権の一部のみを他人に譲るという形になります。
この方法にはメリットもありますが、実務上はかなりハードルが高い点に注意が必要です。なぜなら、持分だけを購入しても不動産全体を自由に使えないため、買い手が非常に限られてしまうからです。
特に問題になるのが、売却先が不動産業者や共有トラブルを目的とした「持分買い取り業者」である場合です。
そのような業者が入ることで、他の共有者との関係性が悪化し、最終的に強制分割の訴訟に発展することもあります。
リスクを避けるためには、できる限り共有者間での合意を模索し、それでも難しい場合にのみこの選択肢を検討すべきでしょう。
共有名義の不動産売却、トラブルになる前に「ワケガイ」にご相談ください!

当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり不動産の専門買取サービス「ワケガイ」を提供しています。
ワケガイでは、通常の不動産会社では扱いづらい「共有名義」「共有持分」の不動産についても、独自のノウハウで買取を実施しています。共有者との話し合いが難航して売却の見通しが立たない、相続で持分だけを取得したが活用できず困っている、といったケースにも対応可能です。
売主様おひとりの持分のみでも買取対象となりますので、全員の同意が得られない状況でもあきらめる必要はありません。複雑な手続きも、当社提携の専門家がサポートいたします。
お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
共有名義の不動産は、一見公平で柔軟な所有形態に見えますが、実際には売却や賃貸などでの合意形成が難しく、トラブルの火種になりやすい性質があります。
特に相続後や時間の経過とともに共有者が増えていくケースでは、管理や活用が事実上不可能になることも少なくありません。
そのため、共有名義のまま放置せず、持分の整理や単独名義化、売却といった選択肢を早めに検討することが現実的です。
自分がどのような立場にあり、どのような制約や権利があるのかを明確に理解した上で、将来的なリスクを回避する判断を心がけましょう。共有者との関係性が良好なうちに動き出すことが、最も円滑な解決への近道です。