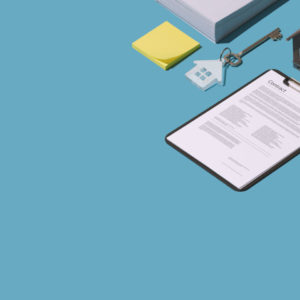共有名義の不動産を相続したり、夫婦で住宅を購入したりする際、各人が所有する割合として「共有持分」が発生します。しかし、共有者同士で意見が食い違えば、思うように売却や修繕が進まないといった問題が生じやすくなります。
その際に正しく理解しておきたいのが「共有持分でできること」です。共有持分とは、不動産の一部に対して持つ明確な所有権であり、その持分に応じて可能な行為と制限が法律で定められています。
何が単独でできて、どこまで共有者の合意が必要なのかを理解していないと、後々トラブルや損失につながりかねません。
そこで今回の記事では、共有持分をめぐってできること・できないことを整理し、典型的なトラブル事例や対応策とあわせて詳しく解説します。
共有持分とは何か
不動産を複数人で所有する場合、それぞれの所有割合を「共有持分」と呼びます。
例えば、兄弟が親の家を相続し、それぞれ2分の1ずつ登記したとすれば、その家は2人の「共有」であり、それぞれの持ち分が「共有持分」として存在することになります。
この共有持分は、単に「何割持っているか」を示すだけでなく、法律的に明確な権利として扱われます。
共有者は、物件全体に対して共同で所有しているものの、各自の持分に応じて行使できる権利は異なります。
自分の持分を売ることは原則自由ですが、不動産全体を売却したり、改築したりといった行為には、他の共有者の同意が必要になる場面が多くあります。つまり、単独では自由に動かせない制約もあるのが特徴です。
共有持分が発生する主なケース
共有持分は、複数人が不動産を共同で所有する際に生じます。特に相続や共同購入といった日常的な場面で発生することが多く、当事者の意思とは無関係に共有状態になるケースも珍しくありません。以下に代表的なケースを挙げます。
- 相続による共有:親の不動産を子どもたちが法定相続分で引き継いだ場合、共有名義となり、それぞれが持分を持つことになります。
- 夫婦や親族による共同購入:住宅を購入する際に、夫婦や親子が出資比率に応じて名義を分けると、それぞれの出資割合に応じた共有持分が登記されます。
- 離婚や贈与による名義変更:夫婦間の財産分与や、親から子への贈与の一環で名義を一部変更した場合にも、共有持分が生じます。
こうしたケースでは、将来的な管理や処分を円滑に進めるためにも、共有状態のうちに整理方法を検討しておくことが重要です。
共有持分でできること
共有持分を持っている人は、たとえ不動産全体の所有者でなくても、一定の権利を行使することが可能です。
特に、自分の「持分」に関しては、他の共有者の同意を必要とせず、比較的自由に扱うことが認められています。ここでは、そのなかでも単独で行える代表的な行為について見ていきましょう。
単独でできること
共有持分を持っている場合、自分の持分に関しては他の共有者の同意なく行える行為があります。ここでは、法律上認められている「単独でできること」の代表例をご紹介します。
自分の持分を売却する
共有不動産における自分の持分は、基本的に単独で第三者に売却することが可能です。つまり、共有者の同意がなくても、自分の持っている「割合」だけを他人に譲り渡すことができます。
これは民法で認められている権利であり、共有状態であっても持分は明確に個人の財産とされているためです。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)
自分の持分を賃貸に出す
意外に思われるかもしれませんが、自分の持分を「賃貸物件として貸す」ことも理論上は可能です。
例えば、自分が持っている2分の1の共有持分だけを第三者に貸すという形式です。これは、民法上、各共有者が自己の持分について「単独で処分・使用できる」と定められていることに基づきます。
自分の持分を担保にしてローンを組む
金融機関によっては、共有持分を担保に融資を行うケースもあります。つまり、自分が持っている割合の持分を「抵当に入れる」ことができるということです。
これも他の共有者の同意を必要としない、単独で可能な行為のひとつです。
共有物の保存行為(修繕・維持管理など)
共有不動産の修繕や清掃といった「保存行為」は、共有者の一人が単独で行うことができます。
これは、共有物の現状を維持するための最低限の措置とされ、他の共有者の同意を得なくても問題ありません。例を挙げると「屋根の雨漏りを直す」「壊れた門扉を補修する」といった日常的な維持作業がこれに該当します。
過半数の同意があればできること
共有不動産に関する管理行為の多くは、すべての共有者の合意を必要とせず、持分の過半数で決定することができます。以下では、過半数の同意で進められる行為を具体的に見ていきます。
共有物の通常の管理(清掃・修繕・設備の維持など)
建物の清掃や簡単な修繕、共用設備の保守など、日常的な維持管理に関する判断は、共有者全員の合意ではなく、持分の過半数で決めることができます。
例えば、共有住宅の共用廊下の電球交換や、外壁の一部補修といった比較的軽微な作業がこれにあたります。
共有不動産の用途変更(居住用→賃貸用など)
共有不動産の用途を変更する場合も、原則として過半数の同意で実行可能とされています。具体的には、親から相続した空き家を、住居用から賃貸物件として貸し出すようなケースが該当します。
このような変更は、日常の使用方法を調整する「管理行為」として扱われるのが一般的です。
共有物の収益化(駐車場として貸し出すなど)
空き地や利用されていない土地部分を有料駐車場として貸し出すといった収益化も、過半数の同意で行える範囲です。
日常の使用方法を変えずに、利益を得ることを目的とする場合には「管理」に分類されるためです。
共有名義の不動産を担保に入れる
共有者が不動産全体を担保に入れる場合、これは通常の管理行為とはやや異なりますが、民法上は「共有物の管理」に含まれると解されることが多く、過半数の同意があれば実行できる場合があります。
ただし、金融機関側が実際に担保として受け入れるかどうかは、また別の判断になります。
全員の同意が必要なこと
共有状態の不動産において、物件の性質を大きく変えるような行為には、すべての共有者の同意が求められます。どのような行為が該当するのか、注意が必要なポイントを整理します。
共有不動産の売却
不動産全体を売却する場合、共有者全員の合意が必要です。たとえ9割の持分を持つ人がいたとしても、残り1割の共有者が反対すれば売ることはできません。これは、売却が共有物の性質を根本的に変える「変更行為」とみなされるためです。
この要件があるがゆえに、不動産の共有状態は「身動きが取りづらい」と言われることが多いのです。
大規模な改築・増築
共有物に大がかりな手を加える、例えば建物の構造を変えるような増築工事なども、全員一致でなければ進められません。わずかでも反対意見が出れば、着工は不可能になります。
小さな修繕と違って、建物の構造や価値に影響を与えるため、これも「変更」として扱われます。将来的な資産価値を上げる目的であっても、共有者全員が納得していなければ実行に移せない点に注意が必要です。
共有物の解体や用途の大幅変更
建物の取り壊しや、住宅から店舗への転用といった抜本的な変更も、当然ながら全員の同意がなければ実施できません。これらの行為は、物理的・法的に不動産の性質を変えるものであり、ひとりの意思で決めることはできません。
共有持分の放棄(法的手続きが必要)
自分の持分を「いらない」と放棄する場合も、形式的には自由にできそうに思えますが、法的には全員に影響を与える行為となり、扱いは慎重になります。放棄によってその持分がどう扱われるか、誰に移転するのかを明確にする必要があるためです。
共有持分で発生するトラブル例
共有不動産は、複数人が同じ物件を所有するという性質上、関係者の意見の食い違いや、権利行使の衝突が起きやすいものです。
特に、日常の利用や処分の場面で「誰かの行動が他の共有者に影響を与える」構造があるため、些細なすれ違いが深刻なトラブルに発展することも珍しくありません。
例えば、以下のようなトラブルが発生するリスクがあります。
- 例①:共有者が持分を勝手に売却し、知らない第三者が共有者になった
- 例②:共有者の一人が不動産を独占して住み続けている
- 例③:相続で共有者が増え、意思決定が困難になった
- 例④:共有者の意見が合わず、リフォームや修繕が進まない
次項より、詳しく解説します。
例①:共有者が持分を勝手に売却し、知らない第三者が共有者になった
共有者の一人が、自分の持分だけを第三者に売却し、その事実を事後的に知らされるというケースは決して少なくありません。民法上、自分の持分を売ることは自由に認められているため、他の共有者に無断で売却が成立してしまうことがあります。
問題は、その結果として、まったく面識のない人間が新たに共有者として権利を持つことになる点です。
例えば、相続で取得した家に兄弟で共有名義を設定していた場合、一方が持分を外部に売却し、その相手が不動産業者だったとすれば、以後の交渉はその業者との間で行わなければならなくなります。
例②:共有者の一人が不動産を独占して住み続けている
共有不動産には、原則として共有者全員が等しく利用できるというルールがあります。にもかかわらず、実際には「一人が居住して出ていこうとしない」「他の共有者の立ち入りを拒む」といった事例が後を絶ちません。
このような占有状態が長く続くと、他の共有者との間で不公平感が高まり、損害賠償請求や使用料相当額の請求といった法的対応に発展することもあります。
例③:相続で共有者が増え、意思決定が困難になった
相続を経て共有者が増えると、ひとつの物件に対して関与する人が多くなり、意思決定のハードルが一気に上がります。特に、一次相続に続く二次相続によって孫世代まで共有者が広がると、物件に対する関心や価値観もバラバラになっていくのが現実です。
例④:共有者の意見が合わず、リフォームや修繕が進まない
老朽化した建物を適切に維持するには、定期的な修繕やリフォームが不可欠ですが、共有者間で意見が分かれると、その実施すら困難になります。例えば、屋根の葺き替えや水回りの更新など、一定の費用がかかる工事について、誰がどこまで負担するのかという点で対立が生まれやすくなります。
こうした修繕は「管理行為」や「変更行為」に該当することがあり、過半数、あるいは全員の同意が必要になることもあります。
共有持分だけ相続放棄することは可能?
相続にあたって、特定の財産だけを放棄したいという希望を持つ人は少なくありません。特に不動産の共有持分については、管理の煩雑さや将来的なトラブルを懸念して「この物件だけ相続したくない」と考えるケースもあります。しかし、結論からいえば、共有持分だけを選んで相続放棄することはできません。
相続放棄は、民法において「相続人としての地位そのものを最初からなかったものとする手続き」とされています。そのため、特定の財産だけを受け取らずに、ほかの財産は引き継ぐといった「部分的な相続放棄」は認められていないのです。
現実的な対応としては、相続を受けた後に持分を他の相続人へ譲渡する、あるいは売却や分割請求を行うといった方法が考えられます。
共有不動産は手間のかかる資産であるため、相続前の段階で遺産分割協議において取り扱いを明確にしておくことが、もっとも望ましい対処といえるでしょう。
共有持分を手放す・整理する方法
共有状態を続けていると、日常の管理や意思決定の煩雑さに悩まされることが少なくありません。特に自分が利用していない不動産の場合、「できれば関わりたくない」「早く整理したい」と感じるのは自然なことです。
そうしたときには、共有持分の整理を検討する価値があります。代表的な方法としては、次の4つです。
- 他の共有者に売却する
- 第三者に売却する
- 裁判所に共有物分割請求をする
- 共有持分の放棄を行う
それぞれ個別にみていきましょう。
他の共有者に売却する
最も現実的で穏便な方法は、他の共有者に自分の持分を買い取ってもらうことです。すでに不動産に関わっている相手であるため、利用や将来の方針について話が通じやすく、売却交渉もスムーズに進みやすい傾向があります。
特にその共有者が現地に住んでいる場合や、不動産の管理を担っている場合には、買い取ってもらえる可能性が高くなります。
第三者に売却する
他の共有者が買い取ってくれない場合には、外部の第三者に売却するという選択肢もあります。近年では、共有持分の買取を専門に行う不動産業者も増えており、共有状態のままでも一定の価格で現金化することが可能になっています。
もっとも、買い手が業者である場合、その後の共有関係がより複雑になることもあります。
共有者間での協議がしづらくなったり、売却や解体を強く求められるなど、摩擦が生じることも想定されます。
裁判所に共有物分割請求をする
共有者間での話し合いがまとまらない場合には、法的手段として「共有物分割請求訴訟」を行うことが可能です。これは、共有状態を解消するために裁判所の判断を仰ぐもので、判決によって物件の分割や競売が命じられることもあります。
例えば、土地を物理的に分けられる場合には現物分割、分けられない場合には売却して代金を分け合う代金分割が選択されます。
ただし、訴訟には時間と費用がかかるうえ、関係がさらに悪化するおそれもあります。最後の手段として考えるべき選択肢です。
共有持分の放棄を行う
「もう関わりたくない」という強い意思のもとで、共有持分を放棄することも理論上は可能です。
ただし、法律上の「放棄」には明確な定義がなく、実務的には持分の無償譲渡として処理されることがほとんどです。したがって、放棄する相手が受け取りを拒否すれば成立しません。
また、固定資産税や管理責任から逃れたいという動機で放棄を選んだとしても、受け取り手がいなければ法的には自動的に自治体が取得するわけではなく、結局は所有者として残ってしまう可能性があります。
意図的な整理であれば、放棄よりも売却や譲渡のほうが現実的です。
(参考:総務省「固定資産税」)
共有持分の売却でお悩みなら「ワケガイ」にご相談ください!

当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり不動産に特化した買取サービス「ワケガイ」を提供しています。
共有持分の不動産は、売却に全員の同意が必要だったり、買い手が見つからなかったりと、一般的な不動産とは異なる難しさがあります。相続や離婚をきっかけに共有者間の関係が複雑化し、売却や管理に支障をきたすケースも少なくありません。
ワケガイでは、そうした共有持分を単独で買い取る体制を整えており、これまでにも数多くの案件に対応してきました。スピーディかつ確実な対応で、煩わしい手続きを代行し、手元に現金を届けます。
共有状態にお悩みの方は、お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
共有持分を持っている場合、自分ひとりでできることと、他の共有者の同意が必要なことを正しく見極める必要があります。特に売却や賃貸、リフォームなどは、相手の同意や法的手続きを伴うケースが多いため、単独判断では進められません。
誤った理解のまま行動すれば、他の共有者との関係悪化や、思わぬ損失に発展するリスクがあります。また、共有者が増えれば増えるほど、意思決定は難しくなり、管理や処分のハードルも高まります。
共有持分は一見シンプルに見えて、実務上は極めて繊細な取り扱いが求められる制度です。だからこそ、自分が何をできるのか、何ができないのかを把握し、対応策をあらかじめ準備しておくことが肝心です。