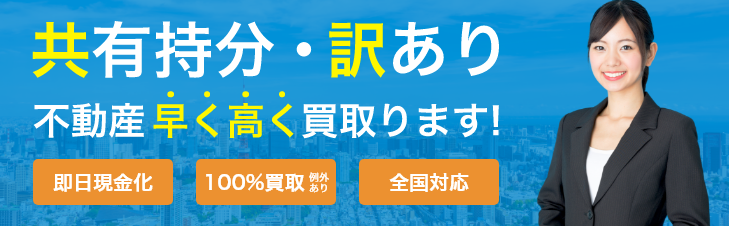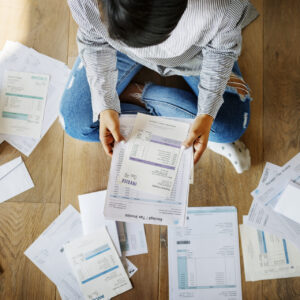再建築や売却の際、前面道路が「私道」だったことで思わぬ支障を受けるケースがあります。特にその私道が他人と「共有」されている場合には、通行や掘削に制限があったり、共有者の同意が必要となる場面も少なくありません。
そのようなときに正しく把握しておきたいのが、「私道の共有」にまつわる権利関係です。私道は、公道とは異なり、個人または複数人で所有される道路状の土地を指し、自由な利用には法的な前提があります。
本記事では、私道の共有状態で発生する権利関係の基礎知識から、売却時に押さえておきたい実務面での留意点まで、わかりやすく解説します。
目次
私道とは
「私道」とは、公共ではなく個人が所有、または共有している土地で、道路の形で整備され、交通する目的で使用されているものを指します。
建築基準法では、道路の幅は最低4m必要とされています。住宅などの建築物の敷地は、建築基準法の道路に2m以上接している必要があります。
敷地がこの義務を満たしていない場合、建物の再建築ができなくなり、深刻な問題となります。
ただし、この規制が施行される前にすでに4m未満の道路が存在していた場合には、「みなし道路」とされ、特に制限なく使用することが可能です。
4m以上が必要な理由は、住民の安全と利便性のために、緊急時に消防車などが進入でき、車両同士がすれ違うことができるように、規定されたものです。
私道の所有形態
私道については、「共有型私道」「持合型私道」の2つの所有形態があります。それぞれ個別に解説します。
【共有型私道】1つの道路を「共有」した私道
分譲地によく見られるパターンで、道路を囲むように何軒かの家があり、真ん中の道路を所有者全員で共有している状態です。
これは一例で、他の形も考えられます。このような場合、真ん中の道路は「共有者としての使用収益権」を行使することで、所有者全員が使用することができます。
また、各共有者は、他の共有者の権利を不当に侵害してはならないという意味で、同時に「負担」を負うことになります。
関連記事:私道持分とは?トラブルや税金、売却のリアルな実情を紹介
【持合型私道】道路を「分筆」した私道
道路そのものの土地が分筆されている状態です。
外見上は1本の道路のように見えますが、実際には別々の土地に分かれていて、それぞれの土地は1人の所有者が所有しています。これは不動産登記法上の「共有」には該当しませんが、実際には道路を共有しているのと同じことになります。
所有権が分かれていると、ある人は他人の土地を通らないと公道に出られないことがあります。
そのため、通行権や地役権などをそれぞれが所有者と締結し、通行できるようにしておく必要があります。また、それぞれが「単独所有」なので、自分の所有物として自由に「売却」や「掘削」をすることが可能です。
但し、勝手に売却や掘削すれば、他の土地に影響を与える可能性もあるので、契約書に何らかの制限を設けることも考えられます。
私道の種類
私道は、建築基準法の規定により以下のように分類されます。
これらの種類は再建築の可否や建築確認申請の審査に直接影響するため、購入や売却の前に自分の土地が接している道路の種類を正確に把握しておくことが大切です。
1項3号道路(既存道路)
都市計画区域に指定される前からすでに存在していた、幅員4m以上の道路を指します。市区町村の管理下にある場合も多く、公道と私道のいずれにも該当し得ます。建築基準法上の「道路」として問題なく扱われるため、再建築に支障はありません。
1項5号道路(位置指定道路)
特定行政庁の許可を得て、「建築基準法上の道路」として指定された私道です。幅員4m以上など一定の条件を満たすことで、建築基準法上の道路として認められます。袋小路の場合は幅6m以上、または長さが35m未満などの制限があります。建物の建築が可能である一方、管理責任は基本的に私有者にあります。
2項道路(みなし道路)
建築基準法の適用以前から建物が立ち並んでいた幅員1.8m以上4m未満の道路です。現在では基準を満たさないため、新たに建物を建てる際は「セットバック」が求められます。道路の中心線から2m後退した部分が道路とみなされ、そこには建築ができません。実質的に敷地の一部が制限される点に注意が必要です。
私道に関する例外措置「43条但し書き道路」とは
建築基準法では、建物を建てるためには原則として「道路に2m以上接していること」が必要とされています。
しかし、なかにはこの条件を満たしていなくても、安全上の支障がないと認められれば建築が可能となる特例があります。それが、いわゆる「43条但し書き道路」に関する措置です。
この制度は、道路に面していない、あるいは建築基準法上の道路とみなされない通路に接している土地であっても、一定の基準を満たせば建築を許可できるようにしたものです。具体的には、建築審査会の許可を得ることで、例外的に建築が認められます。
対象となるのは、幅員が狭い小路や、通行実態はあるが法的には道路と認められていない通路など。行政ごとに判断基準は異なる場合がありますが、たとえば隣地に十分な避難経路が確保されている、あるいは周辺住民との同意がある、といった事情が考慮されます。
ただし、43条但し書き道路に該当する土地は、建築の自由度や再建築の可否に制限があるため、売買時には注意が必要です。購入を検討する際は、行政への事前確認や、専門家のサポートを受けておくと安心です。
私道にまつわる2つの権利
私道が第三者と共有されている場合、自分の敷地であっても自由に使えるとは限りません。そういった問題を解決する上で重要になってくるのが以下2つの権利です。
- 通行権
- 掘削権
それぞれの権利について詳しくみていきましょう。
①:通行権
通行権とは、他人の土地の上を通って移動できる権利のことです。特に私道を利用しなければ公道に出られない場合、この権利があるかどうかは死活問題となります。
ただし、通行権と一口にいっても、その成り立ちや効力の範囲にはいくつかの種類があります。
それぞれの特徴を理解することで、自分の立場に合った適切な対応がしやすくなるでしょう。以下に代表的な通行権の種類をご紹介します。
①-1:囲繞地通行権(袋地通行権)
土地が四方を他人の土地に囲まれており、公道に出るために私道を通らなければならない場合には、「囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)」が認められます。これは民法第210条に基づくもので、特別な契約を結ばなくても、当然に発生する法的権利です。
ただし、どの範囲まで通行できるか、どの経路を使うかには合理性が求められます。たとえば、他の通路があっても利便性が著しく劣る場合などは、この権利が争点になることもあります。
①-2:通行地役権
通行地役権とは、他人の土地を通る権利を契約により取得するものです。これは任意の合意に基づく権利で、囲繞地でなくても設定することができます。民法第280条に規定があり、登記を行うことで第三者に対しても効力を持ちます。
たとえば「公道に面していないが、Bさんの私道を通ればすぐに出られる」という場合に、AさんとBさんが話し合って通行を認める契約を結び、登記することで権利関係が明確になります。
通行地役権は、契約ではなく「時効」によっても取得可能です。他人の土地を長年にわたって継続的に通行していた場合、その事実をもとに通行権を主張できるケースがあります。民法第283条に基づき、一定期間(通常は10年または20年)通行を続ける必要があります。
①-3:使用貸借・賃貸借による通行
もっとも身近な方法が、通行のために契約を結ぶケースです。対価を支払って通行を認めてもらう「賃貸借契約」、あるいは無償で認めてもらう「使用貸借契約」があります。
これらはあくまで当事者間の約束であり、登記をしなければ第三者に対しては主張できません。また、契約期間が終了すれば通行も認められなくなるため、将来的な安定性には欠ける面があります。
②削権
もう1つ重要なのが、私道を掘って設備を通すための「掘削権」です。たとえば、新築時に水道や下水道、ガス管などのインフラを敷設するためには、私道の地下に工事を行う必要があります。しかし、たとえ自宅前の道路であっても、自分が単独で所有していない限り勝手に掘ることはできません。
掘削には、道路の所有者すべての同意が原則必要です。共有私道であれば、共有者全員の署名や印鑑証明を取り、書面で同意を得るケースが一般的です。これは、水道局などに提出する際の必須書類となることも多く、整備の遅れに直結しかねません。
また、掘削後の復旧や通行制限、第三者への影響などについても、事前に丁寧な取り決めを行うことがトラブル防止につながります。
私道が共有であることを知らずに掘削工事を進めてしまい、後から近隣と紛争になる例も少なくありません。掘削権も通行権と同様、法的な裏付けと合意形成が求められる権利なのです。
私道に面した不動産を売却する際の注意点
もし、私道に面した不動産を売却する際には以下の点に留意しましょう。
- 私道の権利関係を事前に整理しておく
- 買主への説明義務と重要事項の開示を行う
- 私道の共有者がいる場合は事前に相談しておく
次項より、詳しく解説します。
私道の権利関係を事前に整理しておく
私道に面した不動産を売却する際、まず確認すべきなのが「その私道にどのような権利を持っているか」です。
たとえば、自分が私道の一部を所有しているのか、他人の土地を通行する契約があるのか、あるいは通行権が登記されていないのかによって、買主に伝えるべき情報も大きく異なります。
また、共有持分を持っている場合には、共有者が誰か、持分の割合はどうなっているのか、登記内容と現況が一致しているかなども確認しておく必要があります。こうした権利関係が不明確なままでは、売却後にトラブルが生じる恐れがあり、取引自体が成立しないこともあり得ます。
関連記事:私道の共有持分で発生するトラブルとは?対処法もセットで詳しく解説
買主への説明義務と重要事項の開示を行う
売主には、物件の現況や権利関係について正確に買主へ伝える義務があります。特に私道が絡む場合、通行権の有無や、共有であるかどうか、掘削に制限があるかといった点は、購入後の生活に直結するため、重要事項説明書での明示が不可欠です。
また、通行権が法的に根拠のあるものか、ただ慣習的に通れているだけなのか、といった違いも買主にとっては大きな判断材料になります。こうした情報を伝えずに売却を進めた場合、契約後に損害賠償や契約解除といったトラブルに発展する可能性も否定できません。
関連記事:私道持分がない不動産を売る3つの方法とは?スムーズに売却するコツも紹介
私道の共有者がいる場合は事前に相談しておく
私道が共有状態にある場合、たとえ自分の敷地の前にある道路でも、単独で自由に売却や掘削を進めることはできません。通行権があっても、インフラ整備や道路の舗装工事といった利用については、他の共有者の同意が必要となる場合があります。
売却にあたっては、共有者とあらかじめ連絡を取り合い、自分の共有持分の売却について理解を得ておくとスムーズです。
共有者との関係性が良好であれば、契約書の準備や手続きも進めやすくなりますし、買主にとっても安心材料となるでしょう。
「ワケガイ」なら訳あり物件も短期で買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分などの複雑な不動産にも対応する買取サービス「ワケガイ」を提供しています。
私道の共有持分が絡む物件は、通行権の整理や他の共有者との関係などが障壁となり、一般市場では売却が難しいケースも少なくありません。特に、持分だけを売りたい場合や、登記があいまいなまま相続されたケースでは、買い手が見つからず長期間放置されることもあります。
ワケガイでは、こうした背景を踏まえた専門的な査定と、必要に応じた士業との連携を通じて、買取対応しています。
物件ごとに最適な対応を行うことで、共有状態にある私道でも円滑な現金化が可能ですので、お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
私道が共有されている場合、その利用や処分には制約が課せられています。特に、通行権や掘削権の有無を確認せずに工事や売却を進めると、後から共有者との対立や法的トラブルに発展するリスクもあります。
売却を検討しているなら、まずは私道の権利関係を登記簿や契約書で明確にし、必要に応じて通行・掘削の同意を得ておく必要があります。
買主にとっても、私道の取り扱いは物件選びの重要な判断材料となるため、誤解のない説明を心がけましょう。
私道の共有は扱いが複雑ですが、早い段階で状況を整理し、専門家の助言も取り入れながら対応することで、円滑な売却や活用に繋げられます。