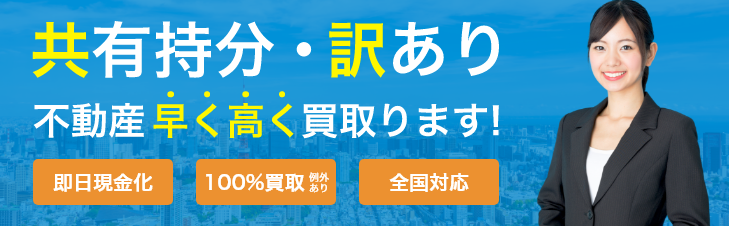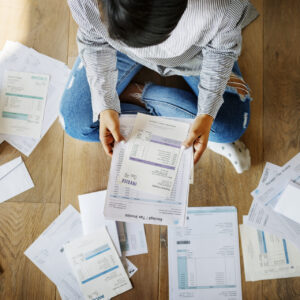こんにちは。ワケガイ編集部です。
「長年他の共有者が不在で連絡が取れない」「誰も使用していない共有不動産を単独で管理している」といったケースでは、「いつの間にか自分の所有になるのでは?」といった疑問や期待を持つ方も少なくありません。
そのような状況で問題となるのが、共有持分の時効取得です。共有持分の時効取得とは、特定の条件を満たしたとき、他の共有者の持分を法的に取得できるとされる制度です。
ただし、要件は厳格で、自己判断で進めるとトラブルに発展するおそれもあります。そこで本記事では、共有持分の時効取得が認められる要件に加え、具体的な手続き手順を詳しく解説します。
目次
共有持分の時効取得とは
時効取得とは、他人の物を所有の意思を持って公然と占有し続けることで、最終的にその物件の所有権を獲得する法的な手続きです。日本の民法では、時効取得は特定の条件下で認められています。
“20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する”
引用:民法162条
一見すると、10年や20年の所有の意思があれば時効取得が可能に思えますが、実際には5つの厳格な要件を満たす必要があります。
共有持分の時効取得で得られる恩恵
共有不動産の持分を時効によって取得できれば、法律上、正式に単独所有者となることが可能です。これは共有状態にあった不動産について、他の共有者の同意を得ずに使用・処分できる権利を確立できることを意味します。
また、共有不動産の売却を検討していた場合には、単独所有者として一括売却が可能になるため、より高い価格での売却交渉がしやすくなる点も見逃せません。共有関係の煩雑さを解消し、資産活用の自由度を高めるうえで、時効取得が成立すれば非常に大きなメリットを得られるでしょう。
共有持分の時効取得で必要な5つの要件
共有持分の時効取得が成立する条件としては、以下のとおりです。
- 要件①:占有期間が一定以上ある
- 要件②:平穏かつ公然な占有である
- 要件③:所有の意思がある
- 要件④:他主占有ではない
- 要件⑤:占有開始時に善意無過失である
次項より、詳しく解説します。
要件①:占有期間が一定以上ある
時効取得に必要な占有期間について、法律では10年または20年以上の期間が定められています。10年の占有期間が適用されるのは、「他人のものであると知らずに占有していた」という場合です。
一方で、占有開始時に物件が他人のものであることを知っていた場合は、20年以上の占有が必要となります。この期間は、所有権の時効取得を主張する上での基礎的な条件です。
要件②:平穏かつ公然な占有である
時効取得のためには、平穏かつ公然とした占有が必須です。つまり、所有者に対する高圧的な態度や暴力、脅迫等を伴う占有は、時効取得の対象とはなりません。
占有が長期に渡るだけでなく、その占有が第三者からも明白に認識できる形でなければなりません。例えば「長期間その場所に居住し、自分の家を建てている」といった行動は、「公然な占有」の証左となります。
要件③:所有の意思がある
時効取得には「自分が所有者である」という意識、すなわち所有の意思が必要です。他人が所有していると認識している場合は、時効取得は成立しません。
この所有の意思は感情的な側面だけでなく、具体的な行動、例えば固定資産税の支払いや、登記上の所有者としての認識などを通じて示されることが望ましいでしょう。
要件④:他主占有ではない
時効取得において、他主占有の状態では取得が認められません。例えば、賃貸人として他人の物件を占有している場合、その不動産が大家の所有であることが明らかなら、「他主占有」に該当します。時効取得には、占有者自身がその不動産を所有しているとの認識が必須です。
要件⑤:占有開始時に善意無過失である
時効取得においては、占有開始時にその物件が自分のものだと信じている「善意無過失」が条件となります。
この状態で10年間占有すれば時効取得が認められます。しかし、途中で他人の物であることが判明した場合、時効取得の要件は満たされません。
共有持分の時効取得が難しい理由
不動産の共有状況下で他の共有者の持分を時効取得することは非常に難しいのが実情です。大きくは、次の2つがその理由です。
- 理由①:単独所有の意思が認められにくいため
- 理由②:「平穏かつ公然」の占有が成立しにくいため
それぞれ個別に解説します。
理由①:単独所有の意思が認められにくいため
時効取得の成立には、「その不動産を自分のものとして占有していた」という意思が必要です。これは法律上「所有の意思(自主占有)」と呼ばれ、客観的にも確認できる必要があります。
しかし、共有不動産を相続したようなケースでは、本人も「共有物を相続した」という認識を持っていることが多く、外部からも「共有の一部を使っているだけ」と見なされやすいのが実情です。こうした状況では、自己の所有物として扱っていたという意思を証明するのはきわめて困難です。
特に、名義が共有のままであれば、所有の意思の存在を立証するには、継続的かつ一貫した単独管理の実態が求められます。
理由②:「平穏かつ公然」の占有が成立しにくいため
もう一つの理由は、「平穏かつ公然に占有していたか」という点です。これは、他人の権利を侵害するような方法でなく、かつ隠れることなく堂々と使用していたかが問われる要件です。
例えば、他の共有者の同意を得ずに居住を始めた場合、争いの火種になることが多く、「平穏な占有」とは評価されにくくなります。また、単独で住んでいたとしても、固定資産税の支払いや物件の管理状況などを通じて、継続的に自らが所有していると外部に明示していた実態がなければ、「公然性」が否定される可能性もあります。
特に収益物件では、家賃収入を単独で受け取っていても他の共有者の異議があると、占有の平穏性が損なわれたと見なされやすいのが実態です。
共有持分の時効取得の手順
共有不動産の中で自分だけが長年住み続けていると、「他の共有者の持分も自分のものにできるのでは」と考える方もいるかもしれません。
一方で、時効取得の成立には厳格な要件があり、共有状態にある不動産では特にハードルが高くなります。以下に、法律に基づいた3つのステップを紹介します。
- 手順①:時効取得の要件を満たしているか確認する
- 手順②:時効の援用を行う
- 手順③:所有者移転登記をする
それぞれ詳しく解説します。
手順①:時効取得の要件を満たしているか確認する
大前提、時効取得が認められるには、民法上の以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 所有の意思をもって占有していたこと(自分のものだと思っていたこと)
- 平穏かつ公然と占有していたこと(暴力や隠ぺいなく、表立って使用していたこと)
- 一定の期間、継続して占有していたこと(通常20年、一定条件下では10年)
まずは、これらの要件を実際に満たしているかを一つずつ確認しましょう。
特に共有不動産では、「この家は共有である」という意識のもとで住んでいた場合、「所有の意思」が認められません。そのため、実際に時効取得が成立するのは、「相続当初から単独所有だと信じており、他の共有者も一切異議を唱えていない」といった特殊なケースに限られます。
手順②:時効の援用を行う
時効取得の要件を満たしている場合でも、自動的に所有権が得られるわけではありません。自らその取得を主張しなければならず、これを「時効の援用」といいます。
これは、時効が成立していることを自分から明確に主張する行為であり、民法第145条に以下のように定められています。
民法第145条には、時効を援用する必要があることが明記されています。これは、裁判所が時効を理由に判断を下すためには、当事者が時効を主張しなければならないという規定です。
つまり、黙っていても所有権は自動的に移りません。時効を理由に権利を主張したいのであれば、他の共有者に対して通知することが必須です。
通知は書面で行うのが原則で、後の証拠とするためにも「内容証明郵便」での送付が推奨されます。
手順③:所有者移転登記をする
時効の援用を終えたら、最後に「所有権移転登記」を行います。これは法務局で登記名義を変更する手続きであり、時効取得の実効性を担保する上で不可欠です。
ただし、相手方(他の共有者)が死亡している、または所在不明で連絡がつかないといった場合には、援用通知や登記申請の前提として「不在者財産管理人」を選任しなければならないケースもあります。
この点について、民法第25条では以下のように定められています。
“第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする”
引用:民法第25条
つまり、他の共有者が不在であるときは、家庭裁判所に申し立てを行い、代理人を通して法的手続きを進める必要があるのです。
関連記事:持分移転登記とは?手続き方法や費用、リスクについて解説
共有持分の時効取得で発生する可能性のある費用・税金
共有持分を時効取得する場合、登記や手続きの過程でさまざまな費用・税金が発生します。ここでは主な項目を整理して紹介します。
登録免許税
時効取得によって自分名義の登記を行う場合、「登録免許税」という税金が必要です。これは不動産の名義変更にかかる税金で、固定資産評価額に対して2.0%の税率で計算されます。
たとえば、固定資産評価額が1,000万円の不動産であれば、登録免許税は20万円となります。
登録免許税の税額は、不動産の価格ではなくあくまで評価額に基づいて決まる点に注意が必要です。評価額は、市区町村役場で発行される固定資産税課税明細書や評価証明書などで確認できます。
また、税金は登記の申請時に原則として現金一括で納める必要があるため、あらかじめ用意しておくと手続きがスムーズです。
不在者財産管理人の選任費用
共有者がすでに死亡していたり、連絡がつかない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる必要があります。これに伴う費用として、以下が発生する可能性があります。
- 申立費用(収入印紙代):800円
- 郵便切手代:数千円程度
- 予納金(管理人の報酬原資):10万~20万円前後
不在者財産管理人の報酬は、財産の規模や管理期間によっても変動します。特に相手方が複数名いる場合には、費用総額が上がる傾向にあります。
専門家への依頼費用
登記手続きや家庭裁判所への申立て、あるいは共有者とのやりとりをスムーズに進めるため、司法書士や弁護士に依頼するケースも少なくありません。その場合、以下のような報酬がかかる可能性があります。
- 司法書士(登記代行):5万〜10万円
- 弁護士(交渉・申立支援):10万〜30万円
- 内容証明郵便の作成・送付:5,000円〜1万円
報酬額は業務範囲や依頼内容によって変わりますが、早期に相談することで不要なトラブルや追加費用を避けやすくなります。
共有持分の時効取得ができない場合の対処法
共有不動産に長く住んでいても、共有状態のままでは持分を時効で取得するのは難しいのが実情です。では、時効取得ができない場合にはどのような選択肢があるのでしょうか。
ここでは、不動産を「手放したい人」と「単独所有を目指す人」それぞれのケースに分けて、実務的な対処法をご紹介します。
不動産を手放したい場合の対処法
他の共有者に自分の持分を買い取ってもらう
共有不動産の利用を希望しない場合には、自身の持分を他の共有者に買い取ってもらう方法があります。この際は、価格設定に注意が必要です。相場よりも大幅に低い価格で売却すると、贈与とみなされて贈与税が課されるおそれがあります。
贈与税の基礎控除は年間110万円です。この範囲内であれば課税を避けられる可能性があるため、金額設定は慎重に行いましょう。また、共有者が買取に応じない場合には、後述する第三者売却や共有物分割請求といった選択肢も検討できます。
第三者に自分の持分を買い取ってもらう
共有者間での交渉が難しい場合は、共有持分専門の買取業者に売却する方法があります。共有状態のままでも買い取ってくれる業者は、持分の活用ノウハウを持っており、一般市場よりも高値で買い取られるケースもあります。
特に、共有者間でトラブルがある、持分の評価額が不明確、といった状況では、専門業者の査定を受けて適正価格を把握することから始めると良いでしょう。売却までの手続きもスピーディに進められることが多く、実務的な解決策となりえます。
単独所有を目指す場合の対処法
他の共有者の持分を買い取る
自分だけで不動産を自由に活用したい場合には、他の共有者から持分を買い取る方法が有効です。共有不動産の単独所有を実現すれば、売却や建て替え、担保設定などの処分もスムーズに行えます。
買い取りには共有者全員の同意が必要ですが、現に自分だけが住んでいるなどの状況であれば、交渉の余地がある場合もあります。なお、話し合いがまとまらない場合には、「共有物分割請求」という法的手段を通じて単独所有に近づける方法も存在します。
時効取得すら難しい共有持分は「ワケガイ」にご相談ください!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や再建築不可物件などの訳あり不動産を専門に扱う買取サービス「ワケガイ」を提供しています。一般的な不動産会社では敬遠されがちな物件でも、私たちは多数の取引実績をもとに、全国どこでも柔軟に対応可能です。
「共有者との交渉が難航している」「時効取得できずに悩んでいる」といったケースでも、状況に応じた最適なご提案をいたします。物件の状態にかかわらず、まずはお気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
共有持分の時効取得は、不在の共有者や連絡の取れない相続人がいる場合に、所有関係を整理する一つの手段となりえます。しかし、単独所有の意思を継続して示し、排他的に管理・使用していたことを証明しなければならず、ハードルは決して低くありません。
また、時効取得が認められた場合でも、その後には登記申請や登録免許税、場合によっては譲渡所得税の申告なども必要になります。
自己判断で進めてしまうと、他の共有者との紛争や申立ての棄却といったリスクもあるため、まずは自身の状況が取得要件に該当するかどうかを慎重に確認しましょう。その上で、必要に応じて専門家の支援を得ながら、現実的な選択肢を見極めていくことが大切です。