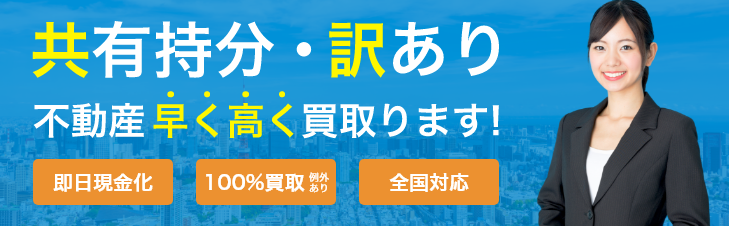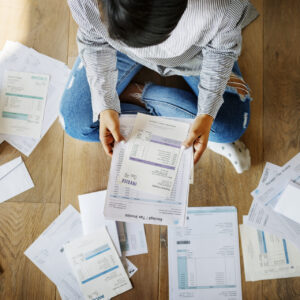こんにちは。ワケガイ編集部です。
共有持分とは、1つの不動産を複数人で共有している際に、それぞれが「割合的に所有している権利」のことを指し、共有者単独ではできること・できないことがあるのが特徴です。そのうちの1つが「保存行為」と呼ばれる行為です。
不動産の保存行為とは、現状を維持・保全する目的で行う行為で、共有者の合意なく単独で実行できるという特徴があります。
共有持分として不動産を所有している方のなかには、「老朽化した家を勝手に修理してもいいのか」「無断で使っている共有者に何か対応できないか」といった悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際問題として、保存行為と見なされず「変更行為」などと判断されると、他の共有者とのトラブルになるおそれがあります。
そこで本稿では、共有持分の保存行為の概要や注意点について詳しく解説します。
目次
共有持分でできること・できないこと
そもそも共有持分権とは「財産(不動産)を複数の人で共有している際、その共有持分やそれに伴って発生するさまざまな権利」のことです。
不動産の共有持分権者は、共有持分に応じた権利を有しますが、「共有持分が1/2だから、建物の半分が自分のもの」というわけではありません。「不動産全体に対して1/2の割合の権利を持っている」という考え方となります。
夫婦や兄弟、または他人同士であっても共有することは可能。単有の不動産であれば、売却や抵当権設定など名義人の判断で何でも行うことができますが、共有状態の不動産はそうではありません。
共有持分権者は何ができる?
不動産の所有権を持つ人には、使用・収益する権利のほかに、「保存行為」「変更(処分)行為」「管理行為」をする権利が与えられています。
- 保存行為:単独で可能
- 変更(処分):行為単独では不可能
- 管理行為」:共有持分割合の過半数の合意が必要
このように、それぞれ単独でできるかどうかが異なるため、注意しましょう。
関連記事:共有持分の管理行為とは?できること・できないことと対処法をわかりやすく解説
「保存行為」の具体例
不動産を共有している場合、単独では判断できないこともあるため「各共有者がお互いに権利を制限し合っている状態」だといえます。
「保存行為」は、共有者に制限されることなく独断で行うことができると、前述しました。では、具体的にどのような行為なのでしょうか。保存行為とは、「不動産の現状を維持するための行為」を指します。
保存行為をすることで他の共有持分権者の利益にもなるため、合意が必要なく単独で行えます。保存行為の具体例については、以下のとおりです。
- 例①:不動産の修理や修繕
- 例②:不法占拠している人への明け渡し請求
- 例③:法定相続登記
- 例④:地役権設定登記請求
それぞれ個別に解説します。
例①:不動産の修理や修繕
壊れたり老朽化したりした不動産を修理・修繕する行為は「不動産の価値を保つための行為」にあたるので、「保存行為」となります。
ただし、壊れているわけではなく「オシャレにしたいから」「こうした方が見栄えが良くなるから」などといった理由で手を加えることにはなりません。この場合は、「変更行為」とみなされ、共有者の合意が必要になるケースがあります。
さらに、「家が古くなったから、家全体を修繕しよう」とする行為は「大規模修繕」となり、「変更行為」とみなされる可能性が懸念されます。そうなると、共有者全員の合意が必要になるため、留意しましょう。
例②:不法占拠している人への明け渡し請求
第三者が不法に不動産を占拠している場合、単独での明け渡し請求が認められます。そのままの状態にしておくと、共有者全員にとって不利益になるため、しっかりと対処しましょう。
ただし、占拠している人が共有者の場合、明け渡し請求はできません。共有持分を少しでも持っていれば、使用する権利があるとが理由。
この場合、自分の持分に応じた使用が妨げられている場合は、その分の金銭を請求(不当利得返還請求)することは可能です。
関連記事:共有不動産を単独使用された場合「明け渡し請求」は可能?
例③:法定相続登記
不動産の相続が発生した際、法定相続分に従った共有登記をするなら、法定相続人であれば1人で申請を行えます。法定相続登記の一種だといわれています。
ただし、2つの注意点がありますので、以下より解説します。
「とりあえず法定相続登記」はNG
共有状態はデメリットが多く、後々トラブルとなるケースがあるため、できる限り単有で登記するようにしましょう。
「法定相続分での共有登記は1人で申請できるから、とりあえずしておこう」と、安易に行うと、あとから遺産分割協議で1人に決まった際に、登記し直す手間や費用がかかってしまいかねません。
相続登記放置も避けるべき
「相続人が決まらない」「決まったにも関わらず、登記を放置している」といった状況では、法定相続人全員の共有状態とみなされるため、1人の判断で不動産売却などができません。
さらに、年月を経てまた相続が発生し、共有者が増えることで、権利関係が複雑化することも想定できます。
関連記事:共有名義での相続登記はしても大丈夫?メリット・デメリットを詳しく解説
例④:地役権設定登記請求
地役権とは「自分の土地を利用するために、一定の範囲で他人の土地を使わせてもらうことができる」権利です。
例えば、道路に面していない土地(袋地)を所有している場合、道路へ出るために他人の土地を使わせてもらう必要があるでしょう。他にも、水道を引くために他人の土地を使用したいケース(用水地役権)などで地役権が行使されるケースがあります。
登記をすることで第三者に主張できるため、単独で行うことができる「保存行為」に当たるのです。
共有持分の保存行為に関する注意点
前述のように、不動産の価値を維持するための保存行為は単独で行えます。しかし、実際には他の行為との境界線があやふやなケースも珍しくありません。
自己判断で「保存行為だろう」と思って行ったことがそうではなく、他の共有持分権者の利益を侵害してしまったという状況もあり得るのです。
もし「これは保存行為なのか、それとも変更行為なのか」と迷ったら、決行する前に専門家に相談するようにしましょう。
万が一、保存行為ではなかった場合、他の共有者に損害賠償請求をされる。あるいは元の状態に戻すよう原状回復請求をされたりしてしまうリスクもあります。
共有状態の解消方法
不動産を2人以上の名義で所有していると、あらゆる行為に対して共有者の確認・合意が必要になります。独断で行える「保存行為」も、自己判断を誤れば共有者の怒りを買ってしまうかもしれません。
このような煩わしさから「共有関係を解消したい」と考えた場合、どのようにしたら解消できるのでしょうか。考えられる対処法には、次のようなものがあります。
- 不動産を売却する
- 持分放棄をする
- 共有物分割請求をする
以下より、それぞれみていきましょう。
不動産を売却する
不動産を手放すことで、共有関係を解消することができます。ただし、売却は「変更(処分)行為」に当たるため、共有者全員の合意が必要。共有者の中に1人でも非協力的な人がいれば売却は難しくなる点については留意しましょう。
さらには、自分の共有持分を他の共有者に買い取ってもらうという選択肢も有効です。自分の所有権はなくなりますが、共有関係を解消できます。
共有持分の買い取り金額は「不動産の時価 × 持分割合」で算出できますが、交渉で決めるため、この限りではありません。 それでも売却が難しい場合、自分の共有持分のみを専門の買取業者に売却することもひとつの方法です。
市場価格の売却額よりは低くなりますが、訴訟となって弁護士費用がかさんだり競売で売却益が低くなる可能性が憂慮されるなら、有用な選択肢といえるでしょう。
関連記事:共有持分はどのタイミングで売却するべき?高く売るための勘所も紹介
自分が相手の共有持分を買い取る
売却するのとは逆に、相手の共有持分を買い取るという方法もあります。単有にすることで、売却や抵当権設定・増改築など、不動産を大幅に変更する行為も自分1人の判断で行うことができるようになります。
この方法を採るなら「持分を買い取る費用」「固定資産税」「管理費などの維持費用」が必要となるため、資力があることが前提となります。
持分放棄をする
共有者が話し合いに応じない場合などで所有権を手放したいときには「持分放棄」を検討しましょう。
この権利は、民法第255条において「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する」と定められています。
例えば、AとBが共有名義で持っている不動産をAが持分放棄した場合、自動的にBにその権利が移行します。ただし、Bの同意なしに持分放棄をすることはできますが、登記手続きの際にはBの協力が必要になります。
関連記事:共有持分は放棄できる?具体的な手順や発生する費用をチェック!
共有物分割請求をする
共有物分割請求とは、共有持分権者に法的に認められた権利です。共有状態を解消するために、共有者同士で話しがまとまらない場合は訴訟を起こすことが可能。
調停によって解決しなければ、裁判所が客観的に分割の方法やその内容などを決めます。分割の方法には以下の3つがあります。
- 現物分割:不動産を物理的に分ける方法で、建築物が建っていない土地のみの場合に適用される。
- 価格賠償(代償分割):共有者の誰か1人がすべての持分を買い取り、他の共有者に代償金を支払う方法。
- 換価分割:第三者に売却して、経費を差し引いて残ったお金を共有持分に応じて共有者全員に分配する方法。
上記のうち、現物分割も物理的に不可能で、代償分割は資力がなく難しいと判断された場合、換価分割が選択されるという流れが一般的です。
とくに共有者間での協議が決裂した場合は、裁判所の判断に委ねる必要が出てきます。いずれにせよ、分割の方法によっては希望どおりの結果にならない可能性もあるため、慎重に進めましょう。
共有持分でお悩みの方は「ワケガイ」の買取サービスをご利用ください!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有名義や再建築不可、事故物件など“訳あり物件”の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。共有状態の不動産は、他の共有者の同意が得られず売却や管理に困るケースが多く、トラブルの火種になりやすいのが実情です。
ワケガイでは、そうした煩雑な事情にも柔軟に対応し、単独名義では売れない不動産でも、共有持分だけを買取することが可能です。全国対応でスピーディな査定・契約を実現しており、最短1日で現金化できる実績も多数ございます。
共有名義にまつわるお悩みを抱えている方は、ぜひお気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
共有名義の不動産では、たとえ自分の持分であっても、すべてを自由に扱えるわけではありません。修繕や登記などの「保存行為」は単独で可能ですが、リフォームや売却などの行為は他の共有者の同意が必要です。この線引きを誤ると、損害賠償請求や関係悪化を招くリスクもあります。
とくに、保存行為と変更行為の判断が難しいケースでは、事前に専門家へ相談することが重要です。また、共有状態を根本から解消する手段としては、持分売却や持分放棄、共有物分割請求などがあります。
煩雑な手続きを回避するためにも、共有不動産を保有している方は、日頃から「自分にできる行為」と「できない行為」を整理し、適切な対応を心がけましょう。