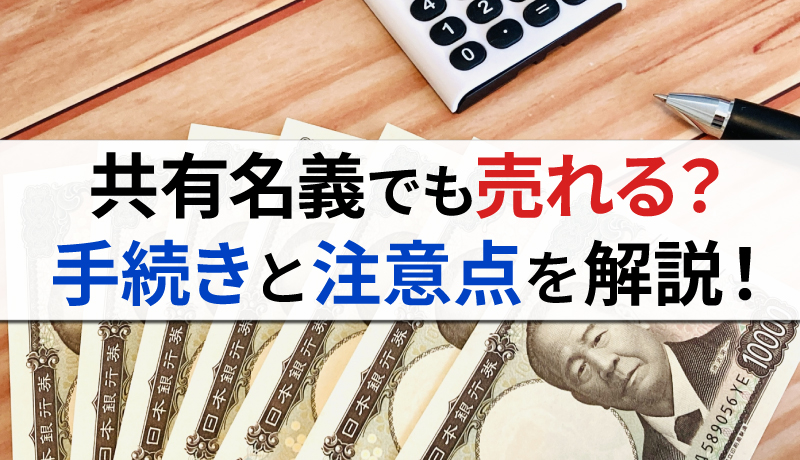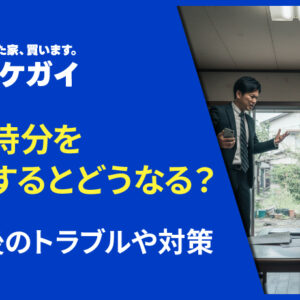こんにちは。ワケガイ編集部です。
共有名義の不動産では、売却や活用を進める際に、共有者全員の同意が必要になるため手続きが滞る、持分のみの売却で関係が悪化するなどの問題が発生します。その際に重要なのが、共有名義の「基礎知識」を正しく理解することです。
共有名義不動産とは、複数人で所有権を持つ不動産のことで、権利割合や使用方法、売却の可否が法律で決まっています。これらを理解せずに行動すると、売却価格の低下や法的トラブルにつながる可能性があります。
そこで本記事では、共有名義不動産の基本的な仕組みや権利関係、売却時の注意点、共有状態を解消する方法までを解説します。
目次
共有名義不動産の「基礎知識」をおさらい
共有名義不動産は、相続や共同購入などで複数人が権利を持つ形で成立します。正しく理解していないと、売却や活用の場面で思わぬトラブルにつながりやすいため、まずは基本的な仕組みを整理しておきましょう。
ここからは「共有持分とは何か」「自分の持分だけを売却できるのか」という点を中心に解説します。
共有持分とは
共有持分とは、不動産を複数人で所有している場合に、それぞれが保有する「所有権の割合」のことを指します。例えば、兄弟2人が土地を相続して「2分の1ずつ」登記した場合、それぞれがその不動産全体について半分の権利を持っているという状態になります。
持分割合は登記簿謄本に明記され、売却や担保設定といった法的行為を行う際の基準になります。持分は「土地の特定部分」ではなく「不動産全体に対する抽象的な割合」である点が特徴です。
このため「自分の持分が庭の一角」などと物理的に切り分けるものではなく、あくまで登記上の権利として扱われます。
関連記事:共有持分の不動産を売却する方法とは?売却費用やよくあるトラブルを紹介!
共有名義の不動産は「自分の持分だけ」なら自由に売却可能
共有名義不動産では、共有者全員の同意がないと物件全体を売却できません。しかし、自分が持っている「共有持分」だけを第三者に売却することは法律上可能とされています。
つまり、他の共有者に承諾を得なくても、自分の権利分だけを売れるのです。
ただし、実務的には注意点が多くあります。持分だけを購入する買主は限られており、通常よりも価格が低くなる傾向があります。また、第三者が新たに共有者として加わることで、利用や管理をめぐるトラブルが発生しやすくなることもあります。
そのため、持分を売却する場合は、他の共有者への持分譲渡を優先的に検討するか、共有持分専門の不動産買取業者を利用するのが現実的な選択肢となります。
共有名義の不動産を売却する5つの方法
共有名義の不動産を売却するには、状況に応じていくつかの選択肢があります。方法ごとにメリットとデメリットが異なるため、事前に整理して理解しておくことが大切です。
ここからは代表的な5つの方法を紹介します。
- 方法①:共有者全員で売却する
- 方法②:自分の持分だけを売却する
- 方法③:共有持分を他の共有者に売る
- 方法④:共有状態を解消してから売る
- 方法⑤:共有持分の買取専門業者に売る
それぞれ個別にみていきましょう。
方法①:共有者全員で売却する
最も理想的なのが、共有者全員の合意を得て不動産全体を一括で売却する方法です。この形であれば、通常の単独名義物件と同じように取引できるため、市場での買い手もみつかりやすく、価格も相場に近づきやすいのが大きな利点です。
また、売却後の代金は持分割合に応じて分配されるため、権利関係もシンプルに整理できます。
一方でデメリットは、共有者全員の意思統一が必要になる点です。相続した兄弟姉妹の間で意見が食い違ったり、誰かが売却に反対したりすると、話が進まなくなる恐れがあります。したがって、全員で売却を目指す場合は、事前の十分な話し合いと合意形成が不可欠です。
方法②:自分の持分だけを売却する
共有者全員の同意を得られない場合でも、自分の持分のみを売却することは法律上可能です。相続人の一人が早期に現金化したい場合や、他の共有者と関係が悪化して協力が見込めない場合には有効な選択肢となります。
ただし、自分の持分だけを購入したいと考える一般の買主は限られており、取引相手は投資家や共有持分専門の業者に偏る傾向があります。
そのため、価格は相場よりも下がることが多く、希望どおりの金額で売れない可能性が高いです。また、第三者が新たな共有者として加わることで、利用や管理に関するトラブルがさらに複雑化する懸念もあります。
方法③:共有持分を他の共有者に売る
自分の持分を他の共有者に買い取ってもらう方法です。第三者が新たに介入しないため、権利関係が複雑にならず、売却後のトラブルも少ないのが大きな特徴です。また、共有者同士の取引であれば市場価格に近い水準で売れる可能性も高いでしょう。
ただし、相手に十分な資金力がなければ成立しない点には注意が必要です。契約を進める際には、贈与と誤解されないように売買契約書や登記の手続きを正しく行うことが求められます。
方法④:共有状態を解消してから売る
分筆登記や代償分割などを行い、単独名義にした上で売却する方法となっています。単独所有にすれば、通常の不動産と同じ条件で市場に出せるため、買い手が見つかりやすく、高値で売却できる可能性が高まります。
ただし、測量費や登記費用、司法書士への報酬といった費用が発生し、共有者間での合意形成も必要です。売却価格をできるだけ高くしたい場合や資産を整理しておきたい場合には、有効な選択肢となります。
方法⑤:共有持分の買取専門業者に売る
共有持分の取り扱いに慣れた専門業者に直接売却する方法です。一般の市場では買い手が限られてしまう共有持分でも、専門業者ならスピーディに現金化でき、最短数日での売却も可能です。
手続きもシンプルで、共有者間で合意が得られない場合や、早期に資金化したい場合に適しています。ただし、市場価格よりは低めの金額になりやすい傾向があるため、スピードや確実性を優先したい人に向いた方法といえます。
共有名義不動産を売却する際の必要書類
共有名義の不動産を売却するには、権利関係を明確にし、契約を正しく進めるための書類が必須です。必要書類が揃っていないと売却手続きが進まなかったり、思わぬトラブルにつながることもあるため、早めに準備しておく必要があります。
ここからは、実際に必要となる書類について個別にみていきましょう。
登記済権利証または登記識別情報
不動産の所有者であることを証明する最も重要な書類です。過去に登記を行った際に発行された「登記済権利証」や、現在主流となっている「登記識別情報(12桁の符号)」のいずれかが必要になります。
これがないと所有権移転登記ができず、売買契約を完了させることができません。紛失している場合は再発行ができないため、司法書士による本人確認情報制度を利用するなど、別の手続きを経る必要があります。
本人確認書類
売主本人であることを確認するために必要な書類です。一般的には運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどが使われます。
登記簿上の住所や氏名と本人確認書類に記載された内容が一致していない場合は、住民票や戸籍謄本を追加提出することもあります。特に相続や結婚による改姓がある場合は、不一致が起こりやすいため注意が必要です。
印鑑証明書
売却契約や登記申請に実印を使用するため、その実印が市区町村に正式に登録されていることを証明する書類です。通常は発行から3か月以内のものが有効とされます。
共有者が複数いる場合は全員分の印鑑証明書が必要となるため、事前に手配を依頼しておかないと手続きが遅れる原因になります。
共有者全員の同意書または委任状
共有名義不動産を売却する際、物件全体を売却する場合には共有者全員の同意が必須となっています。その意思確認を明文化するのが「同意書」です。全員が署名・押印することで、後で「合意していない」といったトラブルを防ぐことができます。
共有者が遠方に住んでいて直接署名が難しい場合は「委任状」を利用し、代表者に売却手続きを任せることも可能です。委任状には対象不動産や権限の範囲を明確に記載することが求められます。
固定資産税納税通知書
毎年、市区町村から送付される「固定資産税納税通知書」も必要な書類です。この書類には不動産の課税標準額や所在情報が記載されており、売買契約書の作成や税額清算に活用されます。
通常、売却時には固定資産税を日割りで清算するため、正確な税額確認に不可欠です。通知書を紛失している場合は、市区町村役場で再発行を依頼することができます。
その他必要に応じて求められる書類
不動産の来歴や売却方法によって、追加で求められる書類があります。たとえば、相続で取得した不動産の場合は「遺産分割協議書」や「戸籍謄本」が必要です。また、代理人を立てて手続きを進める場合は「代理権限証書」や「委任状」が必須となります。
さらに、住宅ローンが残っている物件なら「抵当権抹消に必要な金融機関の書類」が求められるケースもあります。売却する物件の状況に応じて必要書類は変わるため、事前に司法書士や不動産会社へ確認しておくと安心です。
共有名義不動産の売却で発生する費用・税金
共有名義の不動産を売却すると、売却益に対する税金や契約手続きに伴うコストが発生します。
特に共有の場合は持分ごとに税金を計算・負担する必要があるため、どのような費用がかかるのかを事前に把握しておくことが大切です。
売却により発生する費用・税金としては、以下のものが挙げられます。
- 譲渡所得税・住民税
- 印紙税
- 登記関連費用
- 測量費用
- 仲介手数料
- その他の費用
次項より、個別に解説します。
譲渡所得税・住民税
売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合に課される税金です。計算式は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で、所有期間が5年以下の「短期譲渡」は税率が高く、5年を超える「長期譲渡」は低い税率となります。
| 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計 | |
| 短期譲渡所得(5年以内) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期譲渡所得(5年超) | 15% | 5% | 0.32% | 20.32% |
(参考:国税庁「短期譲渡所得の税額の計算」/「長期譲渡所得の税額の計算」)
さらに居住用であれば「3,000万円特別控除」などの特例を利用できるケースもあり、条件を満たすかどうかが納税額に大きく影響します。共有不動産の場合、各共有者が持分に応じて所得を分けて申告する必要がある点にも留意しましょう。
印紙税
不動産の売買契約書を紙で作成・署名する場合、契約金額に応じた印紙税が課されます。課税対象は「課税文書」(売買契約書そのもの)で、原本ごとに課税される点が実務上の留意事項です。通常は売主・買主が各1通ずつ原本を保有するため、それぞれに印紙を貼付し、消印(割印)して無効化します。
(参考:国税庁「印紙税」)
誰が負担するかは法律で固定されておらず、契約書の特約で定めるのが一般的(折半・買主負担など地域慣行あり)です。
なお、電子契約(クラウド署名等)なら印紙税は非課税のため、コスト削減を目的に電子化を選ぶケースが増えています。税額は契約金額の区分表で決まり、国の軽減措置の適用期間により変動する場合があります。
貼り忘れや消印漏れは追徴(過怠税)の対象となるため、契約締結時に「金額区分の確認 → 所要額の印紙貼付 → 消印 → 写しは写しとして保存(コピーに印紙不要)」の順でチェックすることが実務上のポイントです。
登記関連費用
売却に伴う各種登記(所有権移転、抵当権抹消、住所氏名変更、場合によっては分筆等)に要する費用の総称です。内訳は大きく「登録免許税(国税)」「司法書士報酬(専門家費用)」「③実費(証明書の取得料・郵送費・交通費 等)」に分かれます。
登録免許税
不動産の登記を行う際には、法律で定められた「登録免許税」を納める必要があります。所有権の移転、抵当権の抹消、土地の分筆など、手続きごとに税率や計算方法が異なり、課税の仕組みを理解しておかないと想定外の負担になります。
| 内容 | 税率 |
|---|---|
| 所有権の保存 | 0.4% |
| 売買または競売による所有権の移転 | 2% |
| 相続または法人の合併による所有権の移転 | 0.4% |
| その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) | 2% |
(参考:国税庁「登録免許税の税額表」)
所有権移転登記は売買の際に必ず必要で、固定資産税評価額を基準に計算されるため、物件価格が高いほど税額も大きくなります。
一方で、抵当権抹消登記や分筆登記は定額のため、件数が多いかどうかで負担が左右されます。
このように、登録免許税は登記の種類ごとに計算方式が異なるため、「どの登記が必要か」を売却前に整理しておく必要があります。
司法書士報酬
司法書士に登記申請を依頼する際に支払う報酬です。依頼内容によって数万円〜十数万円程度が相場であり、登記の種類や地域によって差があります。
複雑なケースでは費用が増えることもあるため、複数の事務所に見積もりを依頼するのがおすすめです。
測量費用
土地を売却する際、境界が曖昧だと買主が安心して購入できません。そのため「境界確定測量」や「分筆登記のための測量」が必要になるケースがあります。
測量は土地家屋調査士に依頼し、現地調査・測量図作成・隣地所有者との立会いを経て、法務局に図面を提出します。
費用の目安は数十万円程度ですが、土地の広さや形状、隣地が何筆あるか、過去に境界標が残っているかどうかで大きく変動します。
山林や irregular な形状の土地は費用が膨らみやすい傾向です。また、売却直前に急いで行うと隣地所有者との日程調整が難しくなるため、余裕をもって依頼することがスムーズな売却につながります。
仲介手数料
不動産会社に仲介を依頼して売却した場合に発生する報酬で、成功報酬制であるのが一般的です。上限は宅地建物取引業法で決められており、次の計算式で算出されます。
- 仲介手数料(上限)= 売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税
例えば、売却価格が2,000万円なら、約72万円(税抜)が上限額です。売却金額が高いほど比例して手数料も大きくなるため、事前に計算して資金計画に組み込んでおく必要があります。なお、手数料は分割払い(契約時・引渡時)に分けて支払うのが一般的であり、不動産会社によってはディスカウントやサービス込みで調整できる場合もあります。
その他の費用
不動産の売却に伴い、次のような追加費用が発生する場合があります。
- 修繕費:雨漏りや壁の亀裂など、最低限の補修を求められるケース
- ハウスクリーニング費用:空き家や居住跡を整えるための清掃費
- 残置物撤去費用:家具や家電、ゴミの処分費用(数万円~数十万円)
- 解体費用:老朽化が激しく、現状のままでは売却困難な建物の場合に必要
これらはすべて必須ではなく、物件の状態や買主との交渉次第で負担の有無が変わります。「現況有姿(現状のまま)」での売却契約にすれば売主の負担を抑えられますが、その分価格が下がる可能性があります。
状況を踏まえて、事前にどこまで対応するかを決めておきましょう。
共有名義不動産を売却する際のトラブル例と対処法
共有名義の不動産を売却する際には、権利関係が複雑なためトラブルに発展しやすい傾向があります。
特に「共有者間の意見対立」や「一部の共有者が持分だけを売却するケース」では、話し合いが難航しやすく、感情面のもつれから解決が長期化することも少なくありません。
代表的なトラブル例としては、次のものが挙げられます。
- 共有者間で意見が対立する
- 持分のみ売却して関係が悪化する
- 契約内容を曖昧にして揉める
- 費用負担を巡って争う
- 税金の見落としで負担が増える
それぞれ詳しく解説します。
共有者間で意見が対立する
共有名義不動産を売却する場合、もっとも多いのが共有者同士の意見対立です。売却価格や時期、仲介にするか買取にするかといった判断は、それぞれの事情によって希望が異なりやすく、合意に至らないことも珍しくありません。
特に相続で複数の兄弟姉妹が共有者となった場合、感情的な対立が背景にあることもあります。これを防ぐには、口頭だけの話し合いではなく、合意した内容をきちんと文書に残しておく必要があります。明文化によって誤解が避けられ、長期化するリスクを大きく減らせます。
持分のみ売却して関係が悪化する
共有者の一人が自分の持分だけを第三者に売却すると、残りの共有者との関係が悪化するケースは珍しくありません。新たな共有者が投資目的の業者などであれば、利用や管理の協力が得られず、話し合いが一層困難になる恐れがあります。
たとえ法的には認められた行為でも、人間関係をこじらせやすいのが実情です。こうした事態を避けるには、まず他の共有者に対して持分の買取を打診することが現実的です。既存の共有者間で権利を整理できれば、新たな火種を生まずに済みます。
契約内容を曖昧にして揉める
売却の際に作成する契約書に不備があると、後から解釈を巡って紛争になる危険性があります。一例を挙げると、雨漏りや設備不良といった瑕疵への対応を「現状有姿」としか書かず具体的に定めなければ、買主が修繕費の負担を求めて争いになることがあります。
契約条件を明確に記載しておけば、後の誤解や責任の押し付け合いを避けられます。専門家に内容を確認してもらうことで、曖昧さのない契約を整えることができ、余計なトラブルを防ぐことにつながります。
費用負担を巡って争う
測量費・修繕費・税金といった付随費用の負担割合を決めないまま売却を進めると、後から「誰がどれだけ払うのか」で争いになりかねません。特に共有者の経済状況が異なる場合は、負担感の不公平が表面化しやすいです。
売却に着手する前に必要となる費用を洗い出し、持分割合に応じて分担する。あるいは代表者が一時立替するなど、具体的なルールを合意書に残しておくことが安定した取引につながります。
税金の見落としで負担が増える
前述のように、不動産売却では譲渡所得税や住民税、登録免許税など複数の税金が発生するため、事前に把握しておかないと「想定外の税額」に悩まされることがあります。
とりわけ譲渡所得税は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益に課される仕組みで、事前に計算していないと翌年の確定申告時に大きな負担が判明することもあります。
売却前に税額をシミュレーションし、特例の適用可否を確認することが、こうしたトラブルを避ける上では求められます。
共有名義不動産を売却した後の確定申告の流れ
共有名義不動産を売却した場合、売却益(譲渡所得)が出れば確定申告が必要になります。特に共有の場合は、各共有者が持分割合に応じて申告を行う必要があり、通常の単独売却より手続きが複雑になりがちです。
確定申告の流れは、主に以下の5ステップに分けられます。
- 手順①:譲渡所得を計算する
- 手順②:必要書類を揃える
- 手順③:申告書を作成する
- 手順④:税務署に提出する
- 手順⑤:税金を納付する
各手順について、個別にみていきましょう。
手順①:譲渡所得を計算する
まずは、売却によって得た利益=譲渡所得を算出します。計算式は以下のとおりです。
- 譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
なお、上記の費用の定義については、次のようになっています。
- 売却価格:実際に買主から受け取った金額
- 取得費:購入時の代金や相続時の評価額、購入時の仲介手数料・登録免許税など
- 譲渡費用:売却時にかかった仲介手数料、印紙税、測量費、解体費用など
所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり税率が高く、5年を超えると「長期譲渡所得」として税率が下がります。
さらに、居住用不動産であれば「3,000万円特別控除」などの特例を利用できるケースもあります。共有の場合は、持分割合に応じて計算を分ける必要があるため、早めに確認しておくことが大切です。
手順②:必要書類を揃える
譲渡所得の計算ができたら、確定申告に必要な書類を準備します。代表的なものは以下のとおりです。
- 売買契約書(売却価格の証明)
- 登記簿謄本(不動産の権利確認)
- 仲介手数料の領収書(譲渡費用の証明)
- 取得時の契約書や領収書(取得費の証明)
- 共有割合を示す資料(登記簿や遺産分割協議書など)
これらの書類が不足していると、正確に譲渡所得を算出できず、税務署から確認を求められる可能性があります。
特に相続で取得した不動産の場合は、被相続人の購入時の資料を探す必要があるため、時間に余裕を持って準備しておくことが大切です。
手順③:申告書を作成する
譲渡所得の計算と必要書類の準備が整ったら、確定申告書を作成します。不動産売却の申告には「申告書B」「第三表(分離課税用)」が必要です。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、自宅からでも簡単に作成できます。共有名義不動産の場合は、売却代金や費用を持分割合に応じて按分し、それぞれが別々に申告する必要があります。
全員で1通まとめて提出するのではなく、各自の持分を正確に記載する点に注意が必要です。
手順④:税務署に提出する
作成した申告書と添付書類を、売却した翌年の 2月16日から3月15日 の申告期間内に税務署へ提出します。
提出方法には、直接税務署に持参する方法、郵送、そして「e-Tax」を使ったオンライン申告があります。
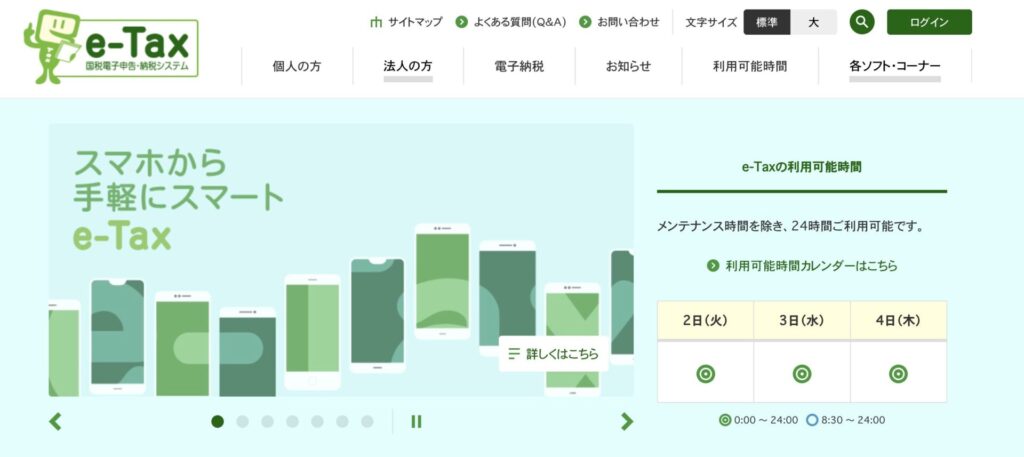
(出典:e-Tax)
e-Taxを利用すれば、還付金の振込が早まるなどのメリットもあります。期限を過ぎると延滞税や加算税が発生するため、余裕を持ったスケジュールでの提出が大切です。
手順⑤:税金を納付する
申告が終わると、算出された税額を納める必要があります。納付期限は確定申告の提出期限と同じ 3月15日 です。納付方法には以下の選択肢があります。
- 金融機関の窓口で現金納付
- コンビニでの納付(バーコード付き納付書)
- インターネットバンキングやクレジットカード納付
- 口座振替(事前手続きが必要)
納付資金を確保していないと延滞税が課されるため、売却代金の一部を納税用に確保しておきましょう。場合によっては還付になることもあるため、正しく申告することが負担軽減につながります。
売却が難しい共有不動産も「ワケガイ」なら買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有名義不動産や再建築不可物件、事故物件、空き家やゴミ屋敷といった訳あり不動産の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。
通常の市場では売却が難しく、長期化しやすい物件でも、最短1日での現金化や最大3億円の一括買取といったスピーディな対応が可能です。
全国47都道府県で豊富な実績を持ち、複雑な権利関係や老朽化が進んだ物件であっても、現状のまま買取することができます。
所有者の方が抱える「売れない」「管理負担が大きい」といった悩みに、安心して活用いただける仕組みを整えています。お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
共有名義不動産を円滑に扱うためには、権利割合や売却条件などの基礎知識を押さえた上で、事前に共有者間の合意形成をきちんと行いましょう。
持分のみの売却は価格低下や関係悪化のリスクがあるため、可能であれば全員で協力して売却を進めるのが望ましいといえます。
また、共有状態を解消して単独名義にすることで、市場での売却や活用の選択肢が広がります。
税金や費用の負担も事前に把握し、契約内容は書面で明確に残しておくことが大切です。こうした準備と理解が、売却の成功とトラブル回避につながります。