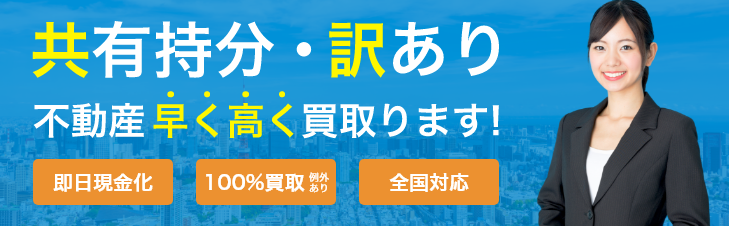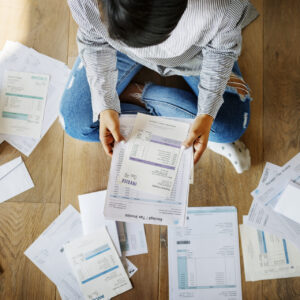こんにちは。ワケガイ編集部です。
親が亡くなった後、兄弟姉妹で実家を共有名義で相続するケースは少なくありません。しかし、「名義をどうするか」を曖昧なまま進めてしまうと、後々の管理や売却時にトラブルが発生しがちです。
その際に理解しておくべきなのが、共有名義で実家を相続するための具体的な手続きです。共有名義とは、複数の相続人がそれぞれの持分を有する形で名義登記をする方法であり、誰が何をどの割合で相続するのかを明確にする必要があります。
本記事では、実家を共有名義で相続する可能性がある方が把握しておくべき必要知識と、実際の手続きの進め方を解説します。
目次
不動産の共有名義とは?
共有名義の不動産とは、「複数人が権利を持っている不動産」のことです。
具体的に、親名義の実家を兄弟で相続するケースで考えてみましょう。この場合、兄と弟の2分の1ずつ相続登記をすることになり、その不動産は共有状態となります。その後、物件に対して半分ずつの権利を持つことになるというのが共有不動産の特徴です。
ここでいう2分の1とは、「建物の西側が兄、東側が弟のもの」という物理的な考えではなく、あくまでも「概念的な権利を有している」状態を意味します。
近年は、夫婦で住宅を購入する際にペアローンを組んで購入するケースも多々あります。この場合も、夫婦で登記をすれば共有名義の不動産になります。
共有不動産はお互いに権利を「制限している」状態
不動産を共有する場合、各共有者は不動産の一部を使用するのではなく、不動産の全てについて使用することが可能。これを「共有物の使用収益権」といいます。
ただし、共有不動産は他の共有者の持分権利もあるため「特定の共有者だけが好きに使う」ことはできません。共有不動産について、以下の民法では3つの制限を定めています。
| 行為の分類 | 必要な同意 | 具体的な行為例 |
| 変更(処分)行為 | 共有者全員の合意が必要 | 売却/贈与/長期賃貸借/増築・改築/大規模修繕/抵当権の設定/解体/建て替え/分筆・合筆 |
| 管理行為 | 共有持分割合の過半数の合意が必要 | 短期賃貸借/共有物の使用方法決定/賃料の減額/賃貸借契約の解除 |
| 保存行為 | 単独で実行可能 | 修繕/無権利者への明け渡し請求/抹消登記請求/法定相続による所有権移転登記 |
上記のとおり、共有不動産を所有している場合、共有持分権者はこれらを単独では決行できない場合があるのです。一例を挙げると、相続した実家を売却したいと弟が提案しても、兄が反対の場合は実行できません。
つまり、各共有者がお互いに権利を制限し合っている状態で、重大な事項であるほど制限が厳しくなっていきます。
実家を共有名義で相続する場合の手続き手順
兄弟姉妹で実家を共有名義として相続する場合、「登記さえすれば完了」と思われがちですが、実際には複数の手続きを段階的に進める必要があります。ここからは、実家を共有名義で相続する場合の手順を3つに分けて解説します。
- 手順①:法定相続人を確定し、相続分を確認する
- 手順②:遺産分割協議を行い、共有名義とすることに合意する
- 手順③:共有名義で相続登記を行う
それぞれ個別にみていきましょう。
手順①:法定相続人を確定し、相続分を確認する
はじめに必要なのは、相続人が誰なのかを明らかにし、それぞれが取得すべき持分割合を確認することです。被相続人が再婚していた場合や、認知された子どもがいる場合などは特に、戸籍調査に時間がかかることがあります。
持分割合は、法定相続分に従うのが基本ですが、遺言書が存在する場合にはその内容が優先されます。実家のような不動産を複数人で共有する場合には、登記に記載される「割合」そのものが、後々の売却や管理に影響するため、初期段階から正確に把握しましょう。
手順②:遺産分割協議を行い、共有名義とすることに合意する
相続人が確定したら、次は遺産分割協議を行い、誰が何を相続するかを話し合います。実家を共有名義にするには、相続人全員が「不動産を共同で所有すること」に同意する必要があります。
この際、協議内容を文書化した「遺産分割協議書」を作成します。この書面は、登記や税務など後続手続きの基礎となるため、個人間の口約束で済ませることなく、全員が署名・押印した正式な書面として残すことが求められます。共有割合や管理ルールを協議書に明記しておくことで、将来的なトラブルの予防にもつながります。
関連記事:遺産分割協議書とは?共有持分を遺言書なしで相続する場合に必要な理由
手順③:共有名義で相続登記を行う
協議の内容が固まったら、法務局で不動産の名義変更手続きを行います。共有名義とする場合には、各相続人の名前と持分割合を登記簿に記載します。
相続登記に必要な書類は以下のとおりです。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産の固定資産評価証明書
- 登記申請書
登記申請は、相続人自身で行うことも可能ですが、記載ミスや書類不備があると却下されてしまいます。司法書士に依頼すれば、専門的なアドバイスを受けながらスムーズに進めることができるため、不安がある場合は専門家への依頼も検討しましょう。
関連記事:共有名義での相続登記はしても大丈夫?メリット・デメリットを詳しく解説
共有名義不動産で発生しやすい5つのトラブル例
実家を兄弟などと共有名義で相続した場合、後々さまざまな問題に発展するリスクがあります。代表的なものとしては、以下5つが挙げられます。
- 例①:単独で売却できない
- 例②:管理・費用の負担が一部共有者に偏りかねない
- 例③:責任の所在がわからなくなる
- 例④:立ち退きを要求できない
- 例⑤:相続により権利関係が複雑化する
次項より、個別に解説します。
例①:単独で売却できない
共有の実家をすべてを売却するためには、共有者全員の合意が必要です。前述のとおり、弟が「売りたい」と思っても、兄が「売りたくない」と反対すれば、売却できません。売却だけでなく「改築」「大規模修繕」など、不動産の形を変えることや処分行為は共有者全員の合意が必須となります。
抵当権設定も処分行為にあたるため、銀行からお金を借りる際に、相続した実家を担保に入れたいと思っても、独断では行えないこともあわせて理解しておきましょう。
例②:管理・費用の負担が一部共有者に偏りかねない
実家などを共有名義で相続すると、管理や費用の負担が一部の共有者に偏りやすいという問題があります。よくあるのは、空き家の草取りや掃除などの日常的な管理は、近くに住む親族に押しつけられることなどで、こうなってしまうと精神的・物理的な負担が大きくなりがちです。
また、固定資産税や修繕費といった費用も、納付書が届いた人が一時的に全額を支払うことになり、あとから他の共有者に精算を求める必要があります。しかし、その際に支払いを渋られたり、減額を要求されたりすれば、結果として金銭面でも不公平な状態になりかねません。
このように、共有状態では「労力」「金銭」の両面で負担が偏り、親族間の不満やトラブルに発展しやすい点に注意が必要です。
例③:責任の所在がわからなくなる
賃料収入を得られる不動産を共有した場合、賃料や必要経費などの分配についてトラブルになることがあります。借主と争いが起きたときや赤字になってしまった時など、共有状態にしていると誰が責任を負うのかが不明確なため、責任の押し付け合いになってしまうこともあり得るでしょう。
例④:立ち退きを要求できない
共有持分をわずかでも持っていれば、実家を「使用する権利」があります。そのため「兄と弟で共有している実家を兄が占有し、弟が使用できない状況」であったとしても、無理やり立ち退きを要求することはできないのです。
「裁判によって持分に応じた金銭を請求する」「悪質な場合であれば、明渡請求をする」ことなどは不可能ではありませんが、精神的にも多大な負担になってしまうでしょう。
例⑤:相続により権利関係が複雑化する
不動産を共有名義で相続すると、相続を繰り返すたびに共有者の人数が増え、権利関係が複雑になっていきます。具体的には、、兄弟で共有していた実家をそれぞれが子に相続すれば、次世代では4人、6人と共有者が増えることになります。
その結果、管理や費用に関する意思決定がしにくくなり、対応可能な一部の共有者に実務負担が集中するケースが多発します。具体的には、空き家の管理を近隣に住む人が任される、固定資産税を納付書を受け取った人が立て替えるといった事例が典型です。
こうした負担の偏りは、他の共有者との関係悪化や支払いトラブルにつながることもあります。権利関係が複雑化するほど話し合いは難航するため、共有状態のまま放置すべきではありません。
共有名義で相続してしまった実家を処分する方法
共有名義で実家を相続したものの、利用予定がない、他の共有者との協議が難航しているといった悩みを抱えている方も少なくありません。ここからは、そのような場合に実家を処分するための具体的な5つの方法を解説します。
- 方法①:共有者全員で合意し、実家を売却する
- 方法②:自分の共有持分だけを第三者に売却する
- 方法③:家庭裁判所に共有物分割請求をする
- 方法④:共有持分を放棄して共有関係から離脱する
- 方法⑤:自治体や団体に寄付・寄贈を申し出る
それぞれ個別にみていきましょう。
方法①:共有者全員で合意し、実家を売却する
共有名義の不動産を処分する最も合理的な方法は、共有者全員が合意し、第三者に売却するケースです。不動産売買契約には所有者全員の同意が必要なため、誰か一人でも反対すれば売却は進められませんが、全員が「手放したい」という意志を持っていれば、最もスムーズに進む方法です。
この方法の利点は、売却価格が市場に近い金額になることと、売却代金を持分に応じて分配できる点にあります。加えて、共有状態が完全に解消されるため、将来的な関係悪化やトラブルの心配もなくなります。
関連記事:共有持分も売却できる!4つの方法とトラブル例を解説
方法②:自分の共有持分だけを第三者に売却する
他の共有者が売却に応じてくれない場合でも、自分の持分だけを売却することは法律上可能です。買い手の多くは、共有持分の取引に慣れた不動産買取業者や投資家になりますが、こうした取引は通常の不動産売買に比べて流通性が低く、価格も割安になる傾向があります。
それでも、資産を凍結したまま抱え込むより、現金化して責任を手放したいというニーズには合致します。共有関係が悪化していて今後の見通しも立たないような場合には、割り切った判断が求められることもあるでしょう。
方法③:家庭裁判所に共有物分割請求をする
どうしても話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に共有物分割請求を申し立てる方法もあります。この手続きではまず調停が行われ、合意に至らなければ審判に進み、裁判所が不動産の分け方を判断します。
オーソドックスなのは「換価分割」と呼ばれる手続きで、実家を売却し、その代金を各共有者に分ける形です。現物を分け合うことが難しく、特定の共有者に買い取る資力もない場合、最終的にこの方法が選ばれやすくなります。
裁判所が関与することで、長年進まなかった共有問題が強制的に解決へと進む一方、時間や費用の負担が大きく、関係性が決定的に悪化するケースもあるため、慎重な判断が必要です。それでも、共有の膠着状態を打破する最後の選択肢として覚えておくべき制度といえます
関連記事:共有物分割請求とは?請求方法や流れを解説
方法④:共有持分を放棄して共有関係から離脱する
共有状態の煩雑さや管理の負担から解放されたい場合、自身の持分を放棄するという選択肢もあります。ただし、ここでいう「放棄」は、民法上の権利を手放す意思表示をするだけではなく、実際には他の共有者への無償譲渡を意味します。
単独で「もういらない」と宣言しても法的には無効で、他の共有者に登記を移転しなければ真の意味で放棄したことにはなりません。この場合、持分を受け取る側が贈与を受けたとみなされ、贈与税が発生する可能性もある点には注意が必要です。
実務的には、他の共有者がその負担を受け入れることが前提となるため、事前の話し合いや合意形成が求められます。誰も引き取り手がいない場合には、放棄は成立しません。制度的な選択肢としては存在しても、実行までのハードルは意外と高い方法です。
関連記事:共有持分は放棄できる?具体的な手順や発生する費用をチェック!
ワケガイなら共有名義や複雑な相続物件もスピード対応可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり不動産の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。
ワケガイでは、相続によって共有名義になってしまった実家や、親族間で意見がまとまらず放置された不動産など、一般的な不動産会社では対応が難しいケースにも柔軟に対応しています。
共有者全員の同意が得られないケースでも、持分のみの買取や、専門家との連携による法的整理を通じて、早期の問題解決をサポートいたします。
複雑な権利関係や相続登記が未了の状態でも、当社がワンストップで対応し、最短1日での現金化も可能ですので、まずはお気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
実家を共有名義で相続する場合、感情的な問題だけでなく、実務面でも慎重な対応が求められます。「誰が相続人となるか」「どのように持分を分けるか」といった基本的な点から、登記に必要な書類の収集、手続きの正確さまで、1つでも誤ればトラブルの火種になりかねません。
特に、今後その実家を売却したり、貸し出したりする可能性があるなら、登記に記載される「持分割合」の意味や、後々の意思決定への影響も意識しておくべきです。
将来の紛争を防ぐためにも、早い段階から相続人間で協議を行い、必要な書類をそろえて手続きを進めていくことが大切です。共有名義の相続は一見シンプルように思えて思えて、意外と複雑です。専門家の力を借りながら、確実に対応することを心がけましょう