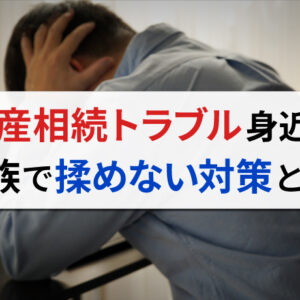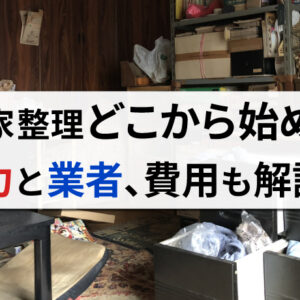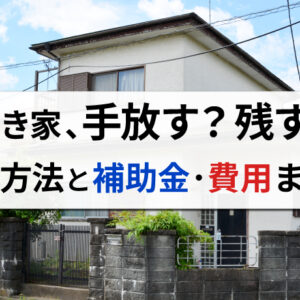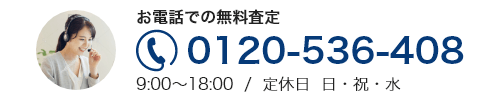について今すぐご相談できます。
お電話する
事故や自殺などの痛ましい出来事が発生した事故物件は、そのままでは売却や利活用が難しいだけでなく、物件に起きた出来事の告知義務が発生します。
もし告知義務を怠った場合、不動産契約における重大な違反行為となってしまいかねません。
そこで今回は、事故物件を取り扱う際には必須となる告知義務について解説します。
目次
事故物件には瑕疵(かし)の告知義務がある
「瑕疵(かし)」という用語は、「普通ならば有していると考えられる機能や条件が欠如している状態」を指します。この瑕疵には、事故や事件などが発生した不動産物件も含まれます。
法律により、瑕疵が存在する物件を保有するオーナーは、その物件を売ったり賃貸する際に、瑕疵の詳細を買い手や入居希望者に正確に伝える責任があります。この点について、宅地建物取引業法第47条で規定されています。
心理的瑕疵物件とは?
事故や自殺が原因となった瑕疵は、「心理的瑕疵」として扱われます。こうした物件は、事故物件として認識されることが多いです。心理的瑕疵とは、物件自体には物理的なダメージはないものの、その歴史や背景から潜在的なネガティブなイメージを持つ物件を指します。
しかし、心理的瑕疵の認識や影響は人それぞれ異なります。すなわち、どのような事件や事故を「心理的瑕疵物件」として扱うかには、明確な基準が存在しないのです。このため、その基準を設定する際は、専門家の意見を求めることが望ましいといえます。
告知義務はいつまで発生するのか?
事故や事件が物件で発生すると、その事実は消え去ることがありません。従って、心理的瑕疵の告知義務も消失することはないのです。
例えば、事故が起きてから数年が経過していたとしても、告知せずに物件を取引すると、後に瑕疵に関する情報を知った人々との間でトラブルが発生するリスクがあります。告知義務は絶えず続くものであるという認識が必要です。
「入退去があれば告知義務はない」は間違い
「事故物件に後続の入居者が存在すれば、心理的瑕疵が解消される」という主張が一部で存在しますが、これは必ずしも正確ではありません。
最も重要な点は「将来の利用者がどのように物件を受け取るか」です。確かに、一度別の入居者が居住した後であれば、心理的瑕疵に対して懸念を抱く人が減るかもしれません。しかし、その逆のケースも十分考えられます。
前述のように、心理的瑕疵の基準はあいまいです。したがって、物件オーナーは常に告知義務を続けることで、後のトラブルを避けるためのリスクヘッジとするべきです。
今後は心理的瑕疵の判断基準が明確化される
国土交通省が発表した「不動産業ビジョン2030~令和時代の『不動産最適活用』への取り組み」では、近未来の課題として挙げられています。
すでに「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」を設置し、具体的なガイドライン策定の方向性が模索されているため、近い将来、事故物件に関する判断基準や対応が変化する可能性があります。
告知義務に関するガイドラインが制定された背景
国土交通省は、2021年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表しました。
このガイドライン策定の背景には、事故物件に関するトラブルが頻発していた事実があります。
これまでの不動産取引の現場では、自殺や事故が発生した物件に関する告知の基準が一貫していませんでした。宅地建物取引業者がどこまで調査し、どの情報を開示するべきかについてのガイドラインが存在しなかったことが、取引上の紛争の要因となっていました。
その結果、不動産の取引が混乱し、買主や賃借人が後から事実を知って損害賠償を求める事例が増加。また、貸主が高齢者の孤独死を懸念して入居を拒否するような問題も発生していました。
このガイドラインの導入により、死亡事故や事件が発生した住宅用不動産の取引時に、どの情報を宅地建物取引業者が開示すべきかの明確な基準が提供され、不動産取引の透明性と安全性が向上することが期待されています。
関連記事:瑕疵担保責任の代わりに定められた「契約不適合責任」とは?
告知義務ガイドラインで明示された「調査義務」とは
告知義務ガイドラインにより、宅地建物取引業者に求められる調査と告知の義務が明文化されました。このガイドラインは過去の裁判例や業界の取引実務を参考に、一般的に受け入れられる形でまとめられています。
この範囲内で対象とされる不動産は居住用限定となり、オフィスや事業用施設は該当しません。調査義務の部分では、売主や貸主からの告知書への記載を確認することが「調査義務を果たした」と位置づけられています。
物件の周辺住民への取材やオンライン上の情報探索等は必須とされていないので、オーナーから提供された情報が主要な確認源となります。
しかし、オーナーが意図的に情報を隠した場合、損害賠償を求められるリスクが存在するため、告知書の内容は正確に記載されるべきでしょう。
瑕疵の内容はどのタイミングで告知するべき?
事故物件に関連する心理的瑕疵の告知の適切なタイミングは、基本的に物件の売却や賃貸利用に関する契約の前です。
具体的には、売却の際には心理的瑕疵の情報を売買契約書に明記し、事前に伝える必要があります。賃貸の場合、入居する前に告知を行う必要があるとされています。
売買において告知義務を怠った場合
心理的瑕疵に関する告知を省略して不動産売買を行った場合、後日この情報が発覚すれば、宅地建物取引業法に違反する恐れがあり、その結果トラブルが生じるリスクが高まります。
こうした状況では、購入者から損害賠償請求や契約解除の要求がなされることも考えられます。心理的瑕疵の認識や許容度は人それぞれ異なるので、明確な告知は取引の安全を確保するために必須です。
関連記事:瑕疵のある物件を売却するには?事故物件の売り方を徹底解説
賃貸利用で告知義務を怠った場合
賃貸物件においても、心理的瑕疵の告知を怠ると、入居者からの損害賠償請求のリスクが高まります。
例として、平成26年に大阪地裁で裁定されたケースがあり、入居直後に自殺事故があったことを知った入居者が、退去費用等を貸主に請求。この事件では、告知義務の違反と判断され、貸主は104万円の支払いを命じられました。
まとめ
事故物件が抱える心理的な瑕疵については、告知義務が切れることはなく、その後も残り続けます。物件に発生した他の損傷と違い、心理的瑕疵については解消することは難しいのが実情。
これを怠ると、法的なリスクだけでなく、信頼の失墜といった重大な影響が発生する可能性があります。特に、心理的瑕疵の許容度は人それぞれ異なるため、明確な告知は取引の安全を確保するために必須といえるでしょう。
物件が抱える瑕疵については、売却や賃貸活用を行う際に告知する義務がある一方で、心理的瑕疵の判断基準については判断基準が不明瞭である点がネックです。そのため、どの内容について告知を行うのかについては、外部専門家の判断も仰ぐようにしましょう。
本ブログで情報発信を行っている「ワケガイ」は、訳あり物件を積極的に買い取っている専門業者です。所有物件についてお悩みの方は、訳あり物件の買取に特化したワケガイに、ぜひお問い合わせください。
| 運営団体 株式会社ネクスウィル 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 |