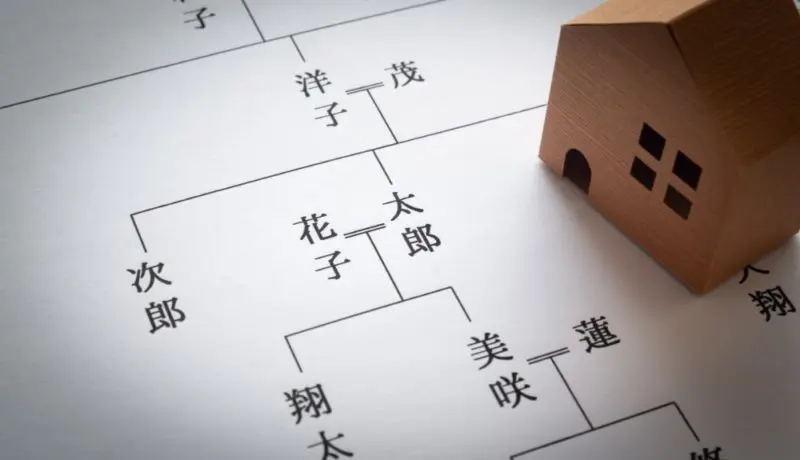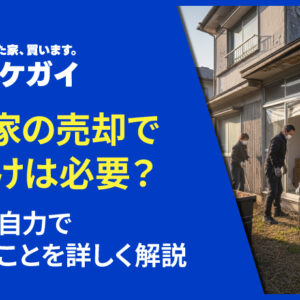について今すぐご相談できます。
お電話する
遺産の大部分を特定の相続人に譲る遺言や、多額の生前贈与が行われたケースでは、他の相続人の遺産取り分が著しく少なくなるという問題が発生します。
このような事態に備えて民法で定められているのが遺留分です。遺留分とは、配偶者や子どもなど一定範囲の相続人に保障された最低限の遺産取得分のこと。
遺言や贈与によって遺留分を下回る遺産しか受け取れない場合、遺留分権利者として請求することができます。
本記事では、遺留分権利者の範囲や請求方法、計算方法について詳しく解説します。
目次
遺留分権利者とは
民法では、一定の相続人に対して最低限の遺産を保障する「遺留分」という権利を定めています。この遺留分を請求できる資格を持つ人を「遺留分権利者」と呼びます。
遺言書の有無にかかわらず、遺留分権利者には法律で定められた割合の遺産を相続する権利が認められています。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)
遺留分権利者の法的根拠
遺留分制度は民法第1042条に規定されており、「兄弟姉妹以外の相続人」に遺留分が認められています。この制度が設けられた背景には、相続人の生活保障という目的があります。
例えば、被相続人が遺言で全財産を第三者に譲るとしても、配偶者や子どもには一定の遺産を相続する権利が保障されるべきという考え方に基づいています。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1と定められています。この割合は強行規定であり、被相続人の意思でも変更できません。
遺留分権利者になれる人・なれない人
遺留分が認められるのは、配偶者、子ども(直系卑属)、直系尊属(両親や祖父母)の3種類に限られます。配偶者と子どもは常に遺留分権利者となりますが、直系尊属は子どもがいない場合にのみ遺留分権利者となります。これは相続の順位に従った規定です。
一方、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。また、相続放棄をした人や相続欠格者、相続廃除された人も遺留分権利者にはなれません。ただし、子どもが相続欠格や相続廃除に該当した場合、その子ども(被相続人からみて孫)は代襲相続人として遺留分権利者になります。
相続人ごとの遺留分権利者の要件
遺留分権利者の要件は相続人によって異なります。それぞれの立場で認められる権利の内容や、遺留分が発生する条件を理解しておくと、円滑な遺産分割に繋がるでしょう。
配偶者の場合
配偶者は最も手厚く保護された遺留分権利者です。法律上の婚姻関係にある配偶者には、常に遺留分が認められます。
その割合は、子どもがいる場合は遺産の4分の1、子どもがおらず被相続人の親が生存している場合は3分の1、配偶者のみの場合は2分の1となります。
ただし、内縁関係にある事実婚の配偶者には遺留分は認められません。離婚が成立していない別居中の配偶者であれば、法律上の婚姻関係が継続しているため遺留分権利者となります。
子供の場合
子どもは実子、養子を問わず、すべての子どもに遺留分が認められます。婚外子も、認知されていれば婚内子と同じ割合の遺留分が保障されます。
子どもが複数いる場合は、遺留分として認められた財産を人数で均等に分けることになります。例えば子どもが3人いる場合、遺産の2分の1が子どもたちの遺留分総額となり、それぞれが6分の1ずつ受け取る権利を持ちます。
直系尊属の場合
父母や祖父母などの直系尊属は、被相続人に子どもがいない場合にのみ遺留分権利者となります。これは相続の順位に基づく規定で、第一順位である子どもが存在する場合、直系尊属には遺留分が認められません。
直系尊属のみが相続人となる場合の遺留分割合は、法定相続分の3分の1と定められています。両親がともに生存している場合は、この3分の1を両親で分けることになります。
代襲相続人の場合
代襲相続は、本来の相続人が相続開始前に死亡したり、相続欠格や廃除に該当したりした場合に、その人に代わって子どもが相続人となる制度です。この代襲相続人にも遺留分は認められます。
具体例として、被相続人の子どもが相続開始前に死亡していた場合、その子ども(被相続人からみて孫)が代襲相続人として遺留分権利者となります。このとき代襲相続人である孫は、死亡した親と同じ割合の遺留分を受け取る権利を持ちます。
代襲相続は再代襲まで認められており、孫が死亡している場合はひ孫が遺留分権利者となることもあります。
遺留分侵害の具体的な事例と対策
遺留分侵害は、主に遺言や生前贈与によって発生します。典型的なケースは、被相続人が特定の相続人や第三者に財産の大部分を与えようとした場合です。
例えば、「すべての財産を長男に相続させる」という遺言が残されていた場合、配偶者や他の子どもの遺留分が侵害されます。また、生前に多額の財産を特定の相続人に贈与していた場合も、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
こうした侵害に対しては、遺留分侵害額請求という手段で対応できます。侵害額の計算を正確に行い、まずは当事者間での話し合いを試みるのが望ましい方法です。話し合いで解決できない場合は、調停や訴訟という法的手段も検討します。
遺留分の計算方法と割合
被相続人の遺産から遺留分を算出するには、特定の計算方法に従う必要があります。これは民法で定められた計算方式で、すべての遺留分権利者に統一的に適用されます。
遺留分を計算する際の基礎となる財産は、相続開始時の積極財産から消極財産を差し引いた正味の遺産に、一定期間内の贈与財産を加えた金額です。具体的な計算式は以下のとおり。
- 遺留分の基礎財産 = 相続開始時の積極財産(不動産・預貯金など)- 相続開始時の消極財産(借金・税金など)+ 相続人に対する相続開始前10年以内の贈与+ 第三者に対する相続開始前1年以内の贈与
特に生前贈与については、相続人への贈与は10年以内、第三者への贈与は1年以内のものが基礎財産に含まれる点に注意が必要です。ただし、遺留分権利者に損害を与える意図で行われた贈与については、期間の制限なく基礎財産に含まれます。
各相続人の遺留分割合の計算方法
遺留分の割合は、法定相続分を基準に計算されます。配偶者と子どもがいる場合の具体例を見てみましょう。
<例:遺産が1億円で配偶者と子ども2人がいる場合>
- 基礎財産総額:1億円
- 遺留分総額:1億円×1/2=5,000万円
- 配偶者の遺留分:5,000万円×1/2=2,500万円
- 子ども1人あたりの遺留分:5,000万円×1/4=1,250万円
このように、まず全体の遺留分(基礎財産の2分の1)を算出し、それを法定相続分に応じて各相続人に配分します。直系尊属のみが相続人の場合は、基礎財産の3分の1が遺留分総額となります。
遺留分の計算は複雑で、財産の評価額や贈与の時期なども考慮する必要があります。具体的な計算に際しては、不動産や事業用資産の評価方法など、専門的な知識が求められる場合も少なくありません。
遺留分侵害額請求の手順
遺留分侵害額請求は段階を追って進めていく必要があります。具体的には、以下の6段階に分けられます。
- 手順1:遺留分の基礎となる財産額を確定する
- 手順2:遺留分侵害額を計算する
- 手順3:遺留分を侵害している相手と話し合う
- 手順4:内容証明郵便で請求する
- 手順5:調停申立てを行う
- 手順6:訴訟を提起する
それぞれ個別に解説します。
手順1:遺留分の基礎となる財産額を確定する
まずは、相続財産目録を作成し、不動産や預貯金などの積極財産から借金などの消極財産を差し引きます。ここでは、相続開始前10年以内の相続人への贈与や、1年以内の第三者への贈与も考慮に入れます。財産の評価は相続開始時の価額を基準とします。
手順2:遺留分侵害額を計算する
基礎財産が確定したら、具体的な遺留分侵害額を算出します。まず遺産全体の2分の1(直系尊属のみの場合は3分の1)を計算し、それを法定相続分に応じて按分します。その金額から実際に取得した財産額を差し引いた金額が、遺留分侵害額となります。
手順3:遺留分を侵害している相手と話し合う
計算結果に基づき、遺留分を侵害している相手方と話し合いの場を持ちます。この段階では、請求金額や支払方法について柔軟に協議することが可能です。分割払いや代物弁済など、双方が納得できる解決方法を探ります。
手順4:内容証明郵便で請求する
話し合いが難しい場合は、内容証明郵便で正式に請求します。手紙には遺留分侵害の事実と具体的な請求金額、支払期限などを明記します。この時点で請求権の行使を明確にすることで、時効の完成を防ぐことができます。
手順5:調停申立てを行う
内容証明郵便による請求でも解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では裁判所の調停委員が間に入り、両者の主張を聞きながら合意形成を目指します。費用も比較的安価で、当事者の関係性も維持しやすい方法です。
手順6:訴訟を提起する
調停で合意に至らない場合の最終手段が訴訟です。地方裁判所に訴状を提出し、裁判所の判断を仰ぎます。訴訟では、遺留分侵害の事実や計算根拠について、より厳密な立証が求められます。ただし、判決が出れば強制執行も可能となるため、確実な権利実現が期待できます。
遺留分侵害額請求を行う際の注意点
遺留分侵害額請求には厳格な要件と期限が定められています。権利を適切に行使する上でも、以下の点に留意しましょう。
- 相続開始から1年で時効となる
- 生前贈与から10年超は請求できない
- 請求額の計算を間違えると後から修正できない
- 請求相手の選択を誤ると権利を失う
- 相手の支払能力がないと回収不能となる
次項より、詳しく解説します。
相続開始から1年で時効となる
遺留分侵害額請求権には厳格な時効期間が設けられています。相続開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈の事実を知った時から1年以内に請求権を行使する必要があります。この期間を経過すると、請求権は時効により消滅し、行使することができなくなります。
生前贈与から10年超は請求できない
遺留分算定の基礎となる贈与財産には期間制限があります。相続人に対する贈与は相続開始前10年以内、第三者に対する贈与は1年以内のものに限られます。
10年を超える生前贈与は、原則として遺留分の計算対象から外れるため、請求の対象とはなりません。
請求額の計算を間違えると後から修正できない
遺留分侵害額の請求は、一度行うと原則として金額の訂正が認められません。過少な金額で請求すると、後から不足分を追加請求することはできません。
正確な財産評価と慎重な計算が求められます。
請求相手の選択を誤ると権利を失う
遺留分侵害額の請求は、法定の順序に従って行う必要があります。まず遺贈や特定財産承継を受けた人に請求し、不足分がある場合に生前贈与を受けた人へ請求することになります。この順序を誤ると、請求権を失う可能性が懸念されます。
相手の支払能力がないと回収不能となる
遺留分侵害額請求が認められても、相手に支払能力がない場合は実質的な回収が困難となります。民法では、受遺者や受贈者の無資力によって生じた損失は遺留分権利者の負担となると定めています。
事業承継する場合は遺留分放棄も検討しよう
円滑な事業承継を実現するためには、遺留分への対応が必要です。特に、事業用資産が遺産の大部分を占める場合、遺留分による制約が事業の継続性を脅かす可能性があります。
例えば、後継者に事業用資産を集中的に承継させたい場合、他の相続人の遺留分との調整が必要となります。この際、遺留分権利者が遺留分を放棄することで、スムーズな事業承継が可能となる場合があります。
遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要ですが、事業承継を目的とする場合は比較的許可を得やすいとされています。ただし、放棄する側への適切な補償を用意するなど、家族間での十分な話し合いと合意形成が前提となります。
将来の事業承継を見据えて、早い段階から遺留分に関する家族間の協議を始めることをおすすめします。
「ワケガイ」なら訳あり物件も短期で買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は共有持分をはじめとする訳あり不動産の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。
遺留分を巡る相続トラブルでは、財産の分割や換価が難しく、当事者間の対立が長期化することも少なくありません。
特に不動産が遺産の大部分を占める場合、遺留分侵害額の支払いのために不動産の売却が必要となるケースがあります。しかし、相続問題を抱える不動産は一般的な不動産市場での売却が困難です。
ワケガイでは、遺留分による制約がある物件でも、現状のままスピーディーな買取が可能です。相続専門の提携士業と連携しながら、適正価格での買取を実現しますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
遺留分に関する問題は、適切な知識と冷静な判断が必要です。遺留分侵害額請求を行う場合は、まず自身が遺留分権利者に該当するか、請求可能な期間内かを確認しましょう。
その上で、具体的な遺留分額を慎重に計算し、当事者間での話し合いを優先することをおすすめします。話し合いで解決できない場合は、調停など法的手続きの活用を検討します。ただし、相手の支払能力も考慮に入れ、実効性のある解決方法を選択することが、交渉を長引かせないようにする上では大切です。
運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |