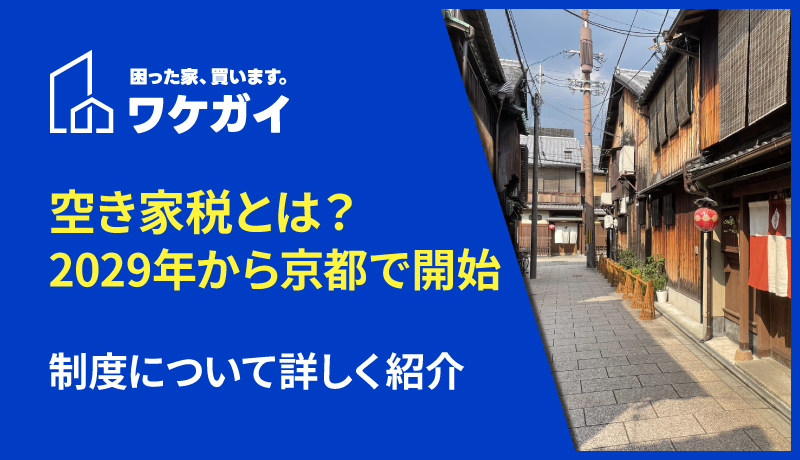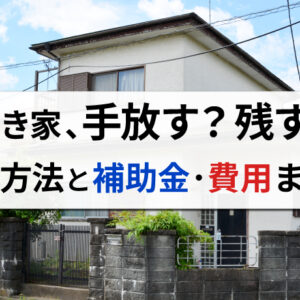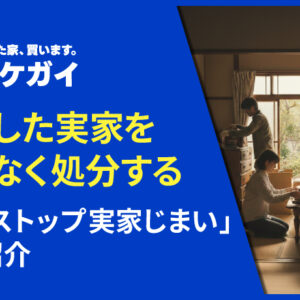こんにちは。ワケガイ編集部です。
空き家を長期間放置していると、景観悪化や防犯上の問題、近隣トラブルなどが発生します。その際に注目されるのが、京都市が創設する「空き家税」です。空き家税とは、一定期間利用されずに放置された住宅や土地に対し、所有者へ追加課税する制度です。
老朽化や治安悪化を防ぎ、地域の空き家対策を促す狙いがあります。しかし、対象や課税額、回避方法を知らないままでは、不必要な負担を抱える恐れがあります。
そこで本記事では、京都市の空き家税の仕組み、課税対象や計算方法、回避・軽減するための現実的な方法まで詳しく解説します。
について今すぐご相談できます。
お電話する
目次
京都市が創設する空き家税とは
まずは、「京都市が創設する空き家税とは何か」「なぜ導入されるのか」といった基本をおさえましょう。これにより、制度の狙いや背景を理解したうえで、具体的な仕組みをスムーズに把握できるようになります。
制度の概要と導入の背景
京都市が創設する「空き家税」の正式名称は「非居住住宅利活用促進税」であり、2026年度から本格的に導入される予定です。これは、市街化区域内にある居住実態のない住宅を対象に課税される仕組みになっています。
導入の目的は、空き家の増加による景観の悪化や防犯上の不安、住宅供給の停滞といった社会問題を解消することにあります。
空き家かどうかの判断は、住民票の有無ではなく「実際に生活の本拠として使用しているか」に基づきます。つまり、所有していても実際に居住していない場合は課税対象となる可能性があります。
ただし、制度設計の段階で「免除」や「猶予」の仕組みも設けられており、固定資産税評価額が一定額未満の物件や、やむを得ない事情で利用できないケースは対象外となる場合があります。これにより、一律に全ての空き家を課税するのではなく、一定の配慮を行いながら制度が運用される見通しです。
固定資産税との違い
空き家税と固定資産税の違いは、課税される対象と目的にあります。固定資産税は、土地や建物を所有している限り必ず課せられる税金であり、住んでいる家でも例外なく課税されます。
(参考:総務省「固定資産税」)
一方、空き家税は「居住実態がなく、使われていない住宅」を対象に追加で課税するものです。つまり、所有しているだけではなく「放置している状態」が課税の根拠となります。
税額の算定方法も特徴的です。空き家税は、家屋そのものの評価額に基づく「家屋価値割」と、土地の評価額に基づき延べ床面積を掛け合わせる「立地床面積割」を合算して計算されます。
一般的には、既存の固定資産税の半額程度を追加で負担するイメージで、結果としてトータルの負担は固定資産税の1.5倍前後になるケースが想定されています。
| 項目 | 固定資産税 | 空き家税 |
| 課税対象 | 所有する全ての土地・建物 | 居住実態がなく放置されている住宅 |
| 課税目的 | 公共サービスのための一般財源 | 空き家の放置抑制と活用促進 |
| 税額の目安 | 評価額 × 1.4%前後 | 固定資産税に加え、さらに0.7%+立地割 |
空き家税の課税対象と条件
空き家税は「すべての空き家」に課税されるわけではありません。京都市が定める要件に基づき、課税対象となる物件と、対象外とされる物件が明確に区分されています。
まず「特定空き家」に指定される基準を押さえ、その上で課税対象となるケースと免除されるケースをみていきましょう。
特定空き家に指定される基準
特定空き家とは、単に「人が住んでいない」だけでなく、周囲に悪影響を及ぼすと判断される住宅を指します。具体的には、以下のものを指します。
- 建物の老朽化が著しく、倒壊や崩落の危険があるもの
- ゴミの放置や害虫の発生など、衛生環境を著しく損なうもの
- 雑草や樹木が繁茂し、景観を悪化させているもの
- 不審者の侵入や火災の恐れがあり、防犯・防災上問題があるもの
といった状態です。これらに該当すると、自治体から「特定空き家」に指定され、所有者に改善を求める勧告が出されます。この指定を受けると、固定資産税の住宅用地特例が外れ、加えて新設される空き家税の課税対象にもなり得ます。
(参考:空き家ワンストップ相談窓口「特定空家とは」)
課税対象になるケースと免除されるケース
課税対象となるのは、京都市内の市街化区域にあり、実際に居住の用に供されていない住宅です。一例を挙げると、長年空き家として放置され、売却や賃貸の予定もなく利用されていない場合は課税対象となります。一方で、すべての空き家が一律に課税されるわけではありません。
免除される代表的なケースは以下のとおりです。
- 遠方に住む所有者が定期的に管理を行っている
- 改修工事や建替えのため、一時的に非居住状態になっている
- 医療・介護などやむを得ない事情で居住できないと認められる
- 評価額が一定額未満の小規模物件
このように、所有者が積極的に管理や活用の意思を示している住宅や、合理的な理由がある住宅は課税対象から除外されます。
制度の狙いは「ただ放置されている空き家」を減らすことにあるため、実態に応じて柔軟に運用される仕組みになっています。
空き家税の税額と計算方法
空き家税は、単に「固定資産税に上乗せされる」というだけではなく、独自の計算方法を持っています。ここからは、課税標準や税率の仕組みを整理したうえで、自治体ごとに想定される税額の差についても解説します。
課税標準と税率の仕組み
京都市の空き家税は、「家屋価値割」と「立地床面積割」という二つの要素で構成されています。
- 家屋価値割
- 建物の固定資産税評価額に対して 0.7% を課す。
- 例:評価額1,000万円の家屋 → 1,000万円 × 0.7% = 7万円。
- 立地床面積割
- 土地1㎡あたりの固定資産税評価額に、建物の延べ床面積を掛け合わせ、そこに税率(0.15〜0.6%)を乗じる。
最終的な税額は、この 「家屋価値割+立地床面積割」 の合計で算出されます。多くの場合、既存の固定資産税に加えて「その半額程度」が追加で課されるイメージです。そのため、実際の負担は固定資産税の 1.5倍前後 になると想定されています。
自治体ごとの税額の差
空き家税は、国の一律制度ではなく、各自治体が独自に条例を定めて導入する仕組みです。京都市が全国で初めて本格的に導入する予定ですが、今後は他の都市にも広がる可能性があります。
自治体によって異なるのは、以下の部分です。
- 課税対象の判定基準(どこまでを「非居住」とみなすか)
- 課税標準額の下限(小規模な家屋を免除するかどうか)
- 税率設定(家屋価値割や立地床面積割の割合)
特に税率は自治体の裁量が大きく、都市部では高めに設定される可能性があります。一方、過疎地や人口減少が進むエリアでは、過度な負担を避けるため低めに抑えられるケースも考えられます。
つまり「同じ規模・評価額の空き家」であっても、どの自治体に所在しているかによって税額が変わる可能性があるということです。京都市に続いて制度を検討する他の自治体の動向にも注目しておく必要があります。
空き家税がもたらす影響
空き家税は、所有者の経済面だけでなく、地域社会や不動産市場にも多面的な影響を与えます。ここからは、具体的に想定される3要素から整理していきましょう。
所有者の経済的負担が増える
空き家税が導入されると、固定資産税に加えて新たな税が課されるため、所有者の負担は確実に増加します。
特定空き家に指定されると、住宅用地特例が外れることで固定資産税が数倍になる場合があり、さらに空き家税まで上乗せされるため、合計で相当な額に達することもあります。
これにより、長期間空き家を維持し続けることが経済的に困難となり、売却や賃貸への転用、あるいは解体といった具体的な判断を迫られるケースが増えるでしょう。
特に、相続などで思いがけず空き家を引き継いだ所有者にとっては、税負担の重さが大きな問題となりやすく、事前に対策を講じておくことが不可欠です。
地域の空き家対策が進む
一方で、空き家税の狙いは単に税収を得ることではなく、地域全体の空き家問題を解消する点にあります。放置された住宅は、景観を損ねるだけでなく、防犯や防災の観点からも危険をもたらします。
税負担というペナルティを設けることで、所有者に管理や活用を促し、結果的に危険な建物の除却や、地域住民が安心して生活できる環境の整備が進むことが期待されています。空き家が有効活用されれば、地域交流の場や移住者向け住宅などに転用される可能性もあり、長期的には地域の活性化につながる効果が見込まれます。
市場に物件が増える可能性がある
税負担を回避するために、多くの所有者が空き家を売却または賃貸に出す動きが強まると考えられます。その結果、不動産市場に流通する物件の数が増え、需給バランスに変化が生じる可能性があるのです。
短期的には売却希望が集中して価格が下がるリスクもありますが、中長期的には市場の流動性が高まり、若年層や移住希望者が住宅を得やすくなるなどの好影響もあり得ます。地域によっては、これまで市場に出にくかった住宅が新たな需要層に利用される契機となり、社会的にプラスの効果をもたらすでしょう。
空き家税を回避・軽減する方法
空き家税の課税を避けるには、「放置しない」ことが大切です。所有する意思がない場合や利用方法が定まらない場合でも、早めに具体的な対応を取ることで税負担を回避・軽減できます。
具体的な方法としては、以下のとおり。
- 方法①:空き家を売却する
- 方法②:空き家を賃貸に出す
- 方法③:空き家をリフォーム・改修して居住可能にする
- 方法④:空き家を解体して更地にする
- 方法⑤:相続放棄をする
それぞれ個別にみていきましょう。
方法①:空き家を売却する
空き家を活用する予定がない場合、最も確実な回避策は売却です。課税が始まる前に売却を進めれば、所有権を手放すことで税負担を完全に避けられます。
特に、特定空き家に指定されると固定資産税の軽減特例が外れ、税額が大幅に跳ね上がるため、指定前に売却することが経済的に有利です。
売却方法には「時間をかけて高値を狙う仲介」「早期に現金化できる買取」の二種類があります。立地や建物の状態によっては仲介で売れにくい場合もあるため、複数の不動産会社に査定を依頼し、相場感を掴んでから判断するのが安心です。
売却益に課税される譲渡所得税についても考慮し、必要なら専門家に相談するとよいでしょう。
関連記事:空き家を売却する方法とは?売却の流れや費用を徹底解説!
方法②:空き家を賃貸に出す
居住実態のある建物として利用されていれば空き家税の対象外となるため、第三者に貸し出すことも有効な回避策です。賃貸に出すことで、単に課税を免れるだけでなく、家賃収入を得ながら建物の利用状態を維持できます。
ただし、老朽化が進んでいる建物は修繕やリフォームが必要となる場合があり、初期投資がかかる点に注意が必要です。また、貸主としての管理責任も発生するため、入居者とのトラブルを避けるために管理会社へ委託するケースも少なくありません。
とはいえ、適切に整備すれば安定した収益につながり、将来的な売却価値も維持しやすくなるため、長期的に見て現実的な選択肢となります。
方法③:空き家をリフォーム・改修して居住可能にする
空き家を放置せず、リフォームや改修を行って再び住める状態にする方法です。自ら住む場合はもちろん、子どもや親族に利用してもらえば「居住実態がある」と判断され、空き家税の対象外となります。
改修には費用がかかりますが、長期的に見れば税負担や管理コストよりも安く済む可能性があります。実際に、老朽化した屋根や水回りを修繕すれば、安全性が高まり、再度住宅として機能するでしょう。
さらに、リフォーム費用の一部は補助金や自治体の助成制度を活用できる場合があり、金銭的な負担を軽減することも可能です。活用を前提に整備することで、将来的に賃貸や売却にもつながりやすくなるため、資産価値の維持にも役立ちます。
関連記事:家のリフォームには費用はどのくらいかかる?利用できる補助制度もセットで紹介!
方法④:空き家を解体して更地にする
建物を取り壊し、更地にしてしまえば「空き家」として扱われなくなるため、空き家税の対象外となります。ただし注意すべきは、住宅が存在することで適用されていた固定資産税の軽減特例が外れる点です。
住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分について固定資産税が最大6分の1に軽減されますが、更地にするとこの優遇がなくなり、税額が高くなる可能性があります。
したがって、空き家税を避けられる一方で固定資産税が増えるため、トータルの負担を比較して判断することが大切です。
また、解体費用自体も数百万円規模になることがあり、自治体の補助金を活用できるかどうかを事前に確認する必要があります。維持が難しい老朽家屋を手放す手段としては有効ですが、費用対効果を慎重に検討すべき方法といえます。
方法⑤:相続放棄をする
相続によって空き家を取得する場合、使い道がなく税負担だけが重くなる見込みなら「相続放棄」を検討するのも一つの手です。相続放棄とは、故人の財産や不動産、借金を含むすべての相続を受け継がない手続きのことです。
これにより、将来その空き家にかかる空き家税や維持費を負担せずに済みます。
ただし、相続放棄は家庭裁判所での正式な手続きが必要で、相続開始から3か月以内という期限があります。期限を過ぎると放棄ができなくなり、自動的に相続人としての責任を負うことになるため、早めに判断することが求められます。
空き家の活用や売却が難しい場合には、相続放棄が最も現実的な回避策となることも少なくありません。
空き家税以外の空き家を放置するリスクとは?
空き家を持つと「使っていないだけだから大きな問題はない」と考えがちですが、実際には税金以外にも数多くのリスクが存在します。放置すれば資産価値は下がり、近隣トラブルや法的責任に発展することも少なくありません。
代表的なリスクとしては、次の5つが挙げられます。
- リスク①:資産価値が大幅に下がる
- リスク②:老朽化による倒壊や損壊の危険が高まる
- リスク③:不法侵入や放火などの犯罪被害に遭いやすくなる
- リスク④:近隣とのトラブルや景観悪化につながる
- リスク⑤:固定資産税の軽減特例が外れる可能性がある
以下より、詳しく解説します。
リスク①:資産価値が大幅に下がる
住宅は人が住み、定期的に手入れをすることで資産価値が維持されます。しかし、空き家を放置すると建物の劣化が加速し、売却や賃貸に出す際に大きなマイナス評価となります。
外壁や屋根の傷み、内部のカビやシロアリ被害は修繕に多額の費用を要し、その分売却価格が下がるか、最悪の場合「買い手がつかない」という事態も起こります。
結果として、資産であるはずの不動産がいわゆる「負動産」となり、所有していること自体が負担になる危険性が高まります。
リスク②:老朽化による倒壊や損壊の危険が高まる
空き家は換気や清掃がされないため湿気がこもり、木材や鉄部の腐食が進みます。そのまま放置すれば、台風や地震といった自然災害時に倒壊や屋根瓦の落下などが起こりやすくなります。
これにより通行人や隣家に被害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。実際に、老朽化した空き家の外壁が崩れ落ちて隣家を破損させたケースも報告されています。建物を維持するには、定期的な点検と修繕が不可欠です。
リスク③:不法侵入や放火などの犯罪被害に遭いやすくなる
人が住んでいない空き家は防犯上の弱点となります。不審者が侵入して不法に使用したり、ゴミを投棄したりするケースが少なくありません。さらに深刻なのは放火被害です。
人気のない住宅は「人目につかない場所」として犯罪者に狙われやすく、火災が発生すれば所有者だけでなく近隣住民にも甚大な被害を及ぼす危険性があります。
所有者は、定期的に巡回したり防犯設備を導入したりして対策を講じる必要があります。
リスク④:近隣とのトラブルや景観悪化につながる
庭や敷地に雑草が繁茂し、ゴミが溜まれば悪臭や害虫の発生源となり、周囲の生活環境に悪影響を与えます。また、外壁や屋根の破損によって落下物が発生すれば、隣家や通行人に危害を加える恐れがあります。
これらは直接的な被害だけでなく「見た目の悪さ」による景観悪化も招き、地域の不動産価値全体を下げる要因となります。近隣住民からの苦情やトラブルに発展すれば、精神的な負担も避けられません。
リスク⑤:固定資産税の軽減特例が外れる可能性がある
通常、住宅が建っている土地には「住宅用地特例」が適用され、固定資産税が大幅に軽減されています。しかし、管理不足で老朽化が進み、自治体から「特定空き家」に指定されるとこの特例が外れます。
すると固定資産税が最大で6倍に跳ね上がり、さらに空き家税まで課されれば、維持するだけで大きな負担となります。つまり、放置することで「税の優遇を失う」という二次的なリスクまで発生するのです。
負担の大きい空き家は「ワケガイ」にご相談ください!

当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり不動産の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。共有持分や再建築不可の土地、長年放置された空き家やゴミ屋敷、さらには事故物件など、一般的な市場では売却が難しい物件でも迅速に対応可能です。
通常の仲介では買い手が見つからず時間やコストがかかるケースも少なくありませんが、ワケガイでは最短即日で現金化まで進められる体制を整えています。
全国対応の実績があり、他社で断られた物件でもご相談いただけますので、処分に困っている不動産をお持ちの方はお気軽に無料査定をご活用ください。
空き家税に関するQ&A
ここからは、空き家税に関して寄せられる代表的な疑問について整理します。制度の開始時期や対象物件、免除ケース、他の税金との関係などを押さえておくことで、自分の状況に当てはまるかどうかを判断しやすくなります。
空き家税はいつ導入されますか?
京都市で空き家税が導入されるのは2026年度からの予定です。すでに条例が可決されており、課税の対象となる物件は2025年度から順次調査が行われる見込みです。
実際に課税通知が届くのは2026年度以降になるため、今から2~3年の準備期間が残されています。ただし、放置状態が続いている空き家は事前調査の段階で把握されやすくなるため、導入前のタイミングで売却や活用を検討しておくことが現実的な対応となります。
京都の空き家税の対象となる物件は?
京都市の空き家税は、市街化区域に存在し、かつ実際に居住の用に供されていない住宅が対象となります。ポイントは「住民票の有無」ではなく「実際に生活しているかどうか」で判断される点です。
別荘やセカンドハウスなど、日常的に使用していない住宅も課税対象に含まれる可能性があります。さらに、管理が不十分で危険性や景観への悪影響がある場合には「特定空き家」として扱われ、固定資産税の優遇が外れる上、空き家税の課税対象にもなります。
空き家税の対象外となるケースは?
すべての空き家が課税されるわけではありません。免除の対象となるのは、やむを得ない事情や一定の条件を満たす場合です。
具体的には、改修工事や建替えのため一時的に非居住状態になっている住宅、遠方に住んでいても定期的に管理されている住宅、病気や介護など特別な事情で居住できない場合などが該当します。
さらに、評価額が一定基準を下回る小規模住宅も免除される仕組みがあります。つまり「放置されている」ことが課税の前提であり、管理や活用の意思が確認できれば対象外となるケースも少なくありません。
空き家税は「固定資産税」や「都市計画税」と同時に課税されることはある?
空き家税は独立した新たな税制であり、固定資産税や都市計画税に加えて上乗せで課税される仕組みです。つまり、固定資産税や都市計画税をすでに支払っている場合でも、空き家と判断されれば別途「空き家税」が課されます。
結果として税負担が1.5倍以上になるケースもあり、所有者にとっては大きな負担増となり得ます。この重複課税は制度の大きな特徴であり、「固定資産税を払っているから大丈夫」とは言えない点に注意が必要です。
まとめ
京都市の空き家税は、放置された空き家に対し、所有者へ追加の税負担を課す仕組みです。負担を避けるためには、単に制度を知るだけではなく、自分の物件が対象になるかを早期に確認し、売却・賃貸・活用・解体・相続放棄など、状況に応じた対応を検討しましょう。
特定空き家に指定される前に動くことで、税負担の軽減だけでなく、地域の防犯や景観改善にもつながります。放置によるリスクは税金だけではなく、倒壊や近隣被害など現実的な問題にも直結します。
空き家を所有しているなら、先延ばしにせず、今から具体的な対応策を実行することが大切です。
運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |