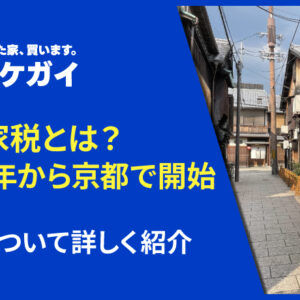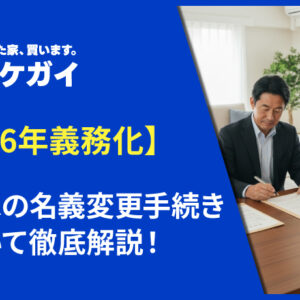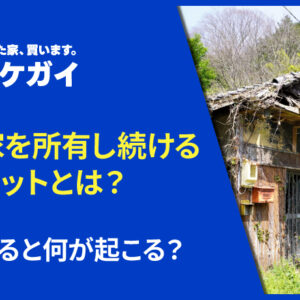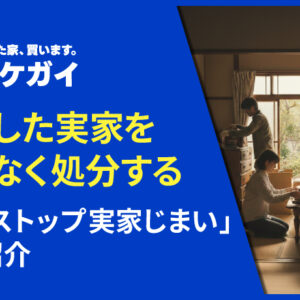こんにちは。ワケガイ編集部です。
空き家をそのまま放置しておくと、老朽化や防犯リスクが高まるだけでなく、固定資産税などの維持費が重くのしかかってきます。その際に有効な選択肢となるのが「空き家の民泊活用」です。
民泊活用とは、空き家を宿泊施設として運用し、観光客や旅行者に提供することで収益を得る方法のことを指します。空き家の維持費を軽減しながら収益化を実現できる一方で、法律や近隣との関係、運営の手間など気をつけるべき点も多く存在します。
そこで本記事では、空き家民泊の仕組みや収益性、必要な手続き、メリット・デメリット、リスクや活用条件について詳しく解説します。
について今すぐご相談できます。
お電話する
目次
空き家の民泊活用とは?
空き家をそのままにしておくと、維持費や防犯面での不安が積み重なり、所有者にとって大きな負担になりかねません。その解決策のひとつとして注目されているのが「民泊」です。
観光需要の高まりと制度の整備を背景に、空き家を民泊施設として運営する動きが広がっています。ここからは、まず民泊の基本的な仕組みと種類について整理していきます。
民泊とは
民泊とは、個人が所有する住宅や空き家の一部または全部を、旅行者に宿泊場所として提供する仕組みを指します。ホテルや旅館と比べると、生活感のある空間で過ごせるのが特徴で、訪日外国人を中心に利用者が増えてきました。
観光庁の統計によると、短期滞在者が増加した2010年代後半に急速に広まり、現在では法制度のもとで営業されるケースが一般的になっています。
民泊が広がった背景には、インターネットを通じた予約サイトの普及があります。誰でも簡単に宿泊施設を探し、予約できる環境が整ったことで、従来は埋もれていた空き家や住宅が旅行者にとって新しい選択肢になりました。
さらに、民泊は地域経済に波及効果をもたらすと期待され、行政も一定の条件下で普及を後押ししています。
民泊の種類
民泊にはいくつかの形態があり、制度によって認められる条件や運営方法が異なります。代表的なものが「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づくものです。
(参考:e-Gov 法令検索「住宅宿泊事業法」)
詳しくは後述しますが、年間の営業日数が180日以内と制限される一方で、届出を行えば比較的スムーズに始められる点が特徴です。空き家を持つ個人にとっては最も現実的な方法といえるでしょう。
もう一つは「特区民泊」です。これは国家戦略特区に指定された地域で認められる制度で、旅館業法の許可を得る代わりに2泊3日以上の宿泊を条件に運営できる仕組みです。
対象エリアが限定される反面、年間を通じて営業できるため、需要が見込める地域では有力な選択肢となります。
さらに、旅館業法に基づく「簡易宿所」として営業する形もあります。この場合はホテルや旅館と同様に許可を取得する必要があり、消防設備や衛生基準などを満たさなければなりません。ハードルは高いものの、長期的に安定した運営を目指す人には適しています。
(参考:e-Gov 法令検索「旅館業法」)
空き家を使った民泊の収益性はどのくらい?
空き家を民泊として運営したときにどの程度の収益が見込めるのかは、多くの方が気になる点です。基本的には「宿泊単価 ×稼働率」が収入の柱になります。
仮に1泊1万円で貸し出し、年間の稼働率が50%だったとすると、単純計算で約180万円の売上が立ちます。ただし、そこから清掃費や管理委託料、光熱費などが差し引かれるため、手元に残る額はさらに少なくなります。
費用と収益の関係をイメージしやすいよう、シンプルな試算例を以下に作成しました。
| 項目 | 金額(年間目安) |
| 売上(1泊1万円×稼働180日) | 180万円 |
| 管理委託料・清掃費 | 50万円 |
| 光熱費・消耗品費 | 20万円 |
| 固定資産税など | 10万円 |
| 残り(概算利益) | 100万円 |
このように、数字だけを見ると魅力的に映りますが、稼働率はシーズンや立地によって大きく変動します。観光地や駅近であれば安定して稼働する可能性がありますが、郊外や需要が乏しい地域では半分以下に落ち込むこともあります。
また、初期費用としてリフォームや家具購入に数十万円から百万円単位の出費が必要になる点も注視すべきポイントです。
民泊新法とは
2018年に施行された住宅宿泊事業法、通称「民泊新法」は、空き家や自宅を旅行者に貸し出す仕組みを正式に位置づけるためにつくられました。
これにより、従来はグレーゾーンとされていた民泊が法律のもとで運営できるようになり、所有者にとっても利用者にとっても安心感のある仕組みが整いました。ここからは、その背景や具体的な制度の内容を見ていきましょう。
民泊新法ができた背景
民泊新法が制定された大きな理由は、訪日外国人観光客の急増にありました。都市部や観光地でホテルの客室が不足し、多くの旅行者が宿泊場所を確保できない状況が続いたのです。その一方で、法的な許可を得ずに営業する違法民泊が急増し、近隣トラブルや安全性の問題が社会的な課題となっていました。
こうした背景を受け、国は一定のルールを整えることで健全な民泊市場を育成しようとしました。民泊新法は、需要に応えつつ地域社会との調和を図るための制度として施行されたのです。
年間営業日数の上限
民泊新法の大きな特徴のひとつに「年間180日以内」という営業日数の上限があります。これは、民泊が旅館やホテルと同じように無制限に営業することを防ぎ、既存の宿泊業との競合を緩和する狙いがあります。
(参考:e-Gov 法令検索「住宅宿泊事業法」)
空き家をフルタイムで民泊として貸し出すことはできず、あくまで副次的な活用として位置づけられているのです。この規制により、民泊は地域に新しい選択肢を提供しながらも、宿泊業全体のバランスを保つ仕組みになっています。
届出の手続き方法
民泊新法の下で営業を始めるには、まず自治体に「住宅宿泊事業届出書」を提出する必要があります。提出時には、物件の間取り図や登記事項証明書、管理体制を示す書類などを添付します。書類に不備がなければ受理され、事業者として登録されてから営業が可能となります。
届出自体は旅館業法の許可よりも簡易ですが、事前に必要書類を揃え、自治体が求める要件を満たしているかを確認する必要があります。これらをクリアして初めて、空き家を民泊として活用できるのです。
管理者の義務とルール
届出を済ませた後も、事業者や管理者にはさまざまな義務が課されています。代表的なものに、宿泊者名簿の作成と保存、苦情窓口の設置、定期的な清掃や衛生管理があります。
また、宿泊者の安全を守るため、防火対策やゴミ処理の体制も整える必要があります。
これらを怠ると、行政からの立入検査や業務改善命令、最悪の場合は営業停止命令が下されることもあります。民泊新法は「始めやすい制度」である一方で、「運営を続けるための責任」も明確にしているのです。
特区民泊とは
民泊には複数の制度がありますが、そのなかでも「特区民泊」と呼ばれるものは、国家戦略特区に指定された地域だけで認められる仕組みです。民泊新法よりも自由度が高い一方で、利用できるエリアが限られているという特徴があります。
ここからは、特区民泊の制度概要と最低宿泊日数の条件について整理してみましょう。
特区民泊の制度概要
特区民泊は、国が定めた国家戦略特区の一環として導入された制度です。自治体が国から特区としての認定を受けることで、旅館業法の規制を一部緩和し、一定の条件下で空き家や住宅を宿泊施設として運営できるようになります。
(参考:e-Gov 法令検索「旅館業法」)
この制度の目的は、観光需要の増加に対応するために柔軟な宿泊施設を確保することにあります。ホテルや旅館の新設には時間とコストがかかりますが、特区民泊であれば既存の住宅を活用できるため、地域の受け入れ能力を短期間で拡大できます。
特区民泊は、都市部の宿泊施設不足を補う手段として位置づけられ、地域活性化の一助としても期待されています。
最低宿泊日数の条件
特区民泊の特徴のひとつが「最低2泊3日以上」という宿泊日数の条件です。これは短期の宿泊を制限し、近隣住民との摩擦を減らす目的で設けられています。1泊だけの利用だと入れ替わりが激しく、騒音やゴミ出しのトラブルが増える恐れがあるためです。
逆に、2泊以上であれば滞在者が落ち着いて過ごしやすく、地域に馴染みやすいと考えられています。
利用者にとっては、気軽に1泊だけ泊まることができないという制約になりますが、安定した滞在が確保されることで、周囲の住環境を守る効果があります。
空き家を民泊として使いたいと考える場合、この最低宿泊日数のルールは事業計画に大きく関わってくるため、あらかじめ理解しておく必要があります。
対象となるエリア
特区民泊は、全国どこでも利用できる制度ではなく、国家戦略特区に指定された一部の地域に限定されています。
代表的なエリアとしては、東京都大田区や大阪市があります。大田区は羽田空港を抱えることから訪日観光客の需要が特に高く、早い段階で特区民泊が導入されました。
大阪市も同様に観光都市として宿泊需要が旺盛で、ホテル不足を補う形で特区民泊が活用されています。
(参考:一般社団法人民泊民宿協会「民泊特区」)
その他にも、京都市や北九州市など、自治体によっては特区民泊制度を取り入れている例がありますが、全国的に見れば対象エリアはまだ限られています。制度の性質上、特区民泊を利用できるかどうかは「その空き家が立地する自治体が特区に指定されているかどうか」で決まります。
つまり、空き家を持つ場所によっては、制度自体を利用できないケースもあるということです。
手続きと必要書類
特区民泊を始めるためには、旅館業法に基づく「簡易宿所営業」の許可を取得しなければなりません。その際には建築基準法や消防法の条件を満たしていることが必須です。
具体的には、非常用照明や火災報知設備の設置、避難経路の確保といった安全対策が必要。これらは宿泊者の安全を守るための最低限の基準であり、通常の住宅をそのまま利用するだけでは基準を満たせない場合も少なくありません。
申請時には、施設の平面図や配置図、避難経路図といった図面類、さらに管理体制や利用ルールを明記した誓約書などを提出します。
こうした書類は自治体ごとに細かい指定があるため、事前に確認して準備する必要があります。許可が下りるまでには一定の期間がかかることが多く、工事や設備の改修が必要になる場合もあります。
空き家を民泊活用するメリット
空き家を民泊に転用することには、所有者にとっては維持費や防犯上の不安を和らげる効果があり、地域社会にとってもプラスの影響をもたらします。
空き家を民泊活用する代表的なメリットとしては、以下の3つが挙げられます。
- メリット①:収益化ができる
- メリット②:空き家の維持管理につながる
- メリット③:地域活性化に貢献できる
それぞれ個別にみていきましょう。
メリット①:収益化ができる
空き家を民泊として運営する大きな魅力は、収益化の可能性にあります。通常の賃貸契約では毎月の家賃が一定ですが、民泊は一泊単位で料金を設定できるため、立地条件やシーズン次第では賃貸より高い収入を得ることが可能です。
例えば、観光地に近い一戸建てであれば、一泊1万円前後の料金でも需要があり、稼働率が安定すれば年間で100万円以上の利益につながることも珍しくありません。
さらに、固定資産税や修繕費といった維持コストを民泊収入でまかなえる点も所有者にとって大きな利点です。特に「空き家はあるが使い道がない」と悩んでいる人にとって、収益化できる可能性は実行する価値を高める要因といえます。
メリット②:空き家の維持管理につながる
空き家を放置すると、湿気による腐食や害虫の発生、空き巣の侵入といったリスクが高まります。民泊として人が出入りすることで、自然に換気や掃除が行われ、こうしたリスクを減らすことができます。
定期的に利用されることで建物の劣化スピードが抑えられ、修繕費の急増を防ぐ効果も期待できます。
また、人の気配がある住宅は犯罪の抑止効果が働きやすい点も見逃せません。灯りが点いたり人の声がするだけで、周囲からは「管理されている家」と認識され、放置された空き家に比べて安全性が高まります。
所有者にとっては「使われていない資産」から「適度に利用されている資産」へと性格が変わるのです。
メリット③:地域活性化に貢献できる
空き家の民泊活用は、所有者だけでなく地域社会にも恩恵をもたらします。
旅行者が地域に滞在することで、飲食店や小売店、交通機関など周辺産業の利用が増え、経済循環が生まれるのです。特に都市部以外の観光地では、宿泊施設不足を補いながら地域全体の集客力を高める効果があります。さらに、民泊は利用者と地域住民との交流を促す場にもなります。
地元の飲食店を紹介したり、地域イベントに参加してもらうことで、旅行者はその土地の魅力をより深く知ることができます。こうした体験はリピーターの増加にもつながり、結果的に地方創生や観光促進の一助となります。
空き家が単なる負担ではなく、地域を支える資源に変わる点が、民泊活用の意義といえるでしょう。
空き家を民泊活用するデメリット
空き家を民泊に転用することで収益や維持管理の面で利点がある一方、見逃せないリスクも存在します。運営を始めてから「思っていた以上に負担が大きい」となるケースも少なくありません。
特に、以下3つのデメリットには注意が必要です。
- デメリット①:近隣トラブルのリスクがある
- デメリット②:運営コストや手間がかかる
- デメリット③:法規制や行政指導を受けかねない
- デメリット④:建物や設備の損耗が進みかねない
- デメリット⑤:衛生・安全管理の問題が生じかねない
- デメリット⑥:収益が安定しないことも珍しくない
それぞれ個別に解説します。
デメリット①:近隣トラブルのリスクがある
民泊にもっとも多いトラブルは、利用者と近隣住民との摩擦です。短期滞在者の入れ替わりが激しいと、夜間の騒音や不適切なゴミ出し、路上喫煙など生活マナーをめぐる問題が起こりやすくなります。
治安悪化を懸念する声が出ることもあり、苦情が積み重なれば地域社会との関係が悪化しかねません。
特に住宅街や集合住宅では、住民の生活環境に直結するため反発が強く、管理組合の規約で禁止されている場合もあります。
空き家を民泊として運営するなら、利用者にルールを周知徹底するだけでなく、苦情に迅速に対応できる体制を整えておく必要があります。
デメリット②:運営コストや手間がかかる
民泊は単に空き家を貸し出せば終わりではありません。具体的には「予約の管理」「宿泊者とのやり取り」「清掃やリネン交換」「鍵の受け渡し」など、日常的な業務が数多く発生します。短期間で利用者が入れ替わるため、そのたびに清掃を徹底しなければならず、想像以上の手間がかかるものです。
こうした作業を外部業者に委託することも可能ですが、その場合は委託料が発生します。特に清掃代や管理代行費は収益を圧迫しやすく、稼働率が低い時期には赤字になってしまう恐れもあります。
民泊は収益性が魅力とされがちですが、同時に「運営コストをどのようにコントロールするか」という課題も避けて通れません。
デメリット③:法規制や行政指導を受けかねない
民泊を合法的に運営するには、民泊新法や各自治体の条例に従う必要があります。届出や管理義務を怠れば、営業停止命令や罰金といった行政処分を受けるリスクがあります。
さらに、民泊をめぐる制度は社会状況に応じて改正されることが多く、ルールが厳しくなる可能性も懸念されます。
実際に、住民からの苦情が相次いだ地域では、営業日数の制限や申請条件の強化が検討されることがあります。こうした制度変更に柔軟に対応できなければ、事業自体が続けられなくなりかねません。
空き家を民泊に活用する際は、規制の動向を把握し、常に法令を遵守できる体制を整えておきましょう。
デメリット④:建物や設備の損耗が進みかねない
空き家は利用されることで維持につながる面もありますが、民泊として頻繁に人が出入りすれば、建物や設備の消耗は確実に進みます。
例えば、ドアノブや水回りの設備は宿泊者が入れ替わるたびに使われるため、通常よりも早く劣化しやすい傾向があります。加えて、家具や家電が壊れる、壁紙が汚れるといった破損が起きる可能性も高まるでしょう。
デメリット⑤:衛生・安全管理の問題が生じかねない
民泊では宿泊者の入れ替わりが頻繁に起こるため、清掃や衛生管理を怠るとすぐに問題が表面化します。例えば、使用済みの寝具を交換せずに次の宿泊者を受け入れれば、不衛生な環境を提供することになり、クレームにつながります。
また、キッチンや浴室の掃除が不十分であれば、カビや害虫の発生を招き、口コミで評価を落とす原因にもなります。こうした衛生上の不備は、利用者離れを引き起こすだけでなく、所有者に責任が及ぶこともあります。
デメリット⑥:収益が安定しないことも珍しくない
民泊は稼働率に大きく左右されるビジネスであり、常に安定した収益を得られるとは限りません。観光シーズンや連休のように需要が集中する時期は予約が入りやすい一方で、閑散期には稼働率が落ち込み、収益がほとんど出ないこともあります。
また、立地条件によっても差は大きく、駅や観光地に近い物件なら安定した利用が見込めますが、郊外の住宅地では期待したほどの稼働率が得られない場合もあります。
民泊が向いている空き家の条件
すべての空き家が民泊に適しているわけではありません。立地や建物の状態、設備の整備状況などによって、運営のしやすさや収益性は大きく変わります。
民泊に向いている条件としては、以下のとおりです。
- 観光地や駅に近い立地である
- 建物の状態が良好である
- 宿泊に必要な設備が整っている
- 周辺環境との調和がとれる
それぞれ個別に解説します。
観光地や駅に近い立地である
旅行者にとって宿泊施設を選ぶ際の大きな基準は「アクセスの良さ」です。観光地や主要駅に近い空き家は需要が見込めるため、稼働率が高まりやすい傾向があります。
一例を挙げると、観光スポットまで徒歩圏内であれば、宿泊者は移動の負担を軽減できるため予約に結びつきやすいのです。
逆に、交通の便が悪い場所では、価格を下げても利用者が集まりにくく、期待した収益が得られない可能性が高まります。民泊に活用する際は、まず立地条件を冷静に評価しましょう。
建物の状態が良好である
老朽化が進んでいる空き家は、安全面や快適性の面で宿泊施設には向きません。雨漏りやシロアリ被害がある家屋では改修に大きな費用がかかり、結局は収益を圧迫してしまいます。耐震性に不安がある建物も、災害時に宿泊者を危険にさらす恐れがあります。
逆に、基本的な構造がしっかりしている空き家であれば、多少の修繕やリフォームで民泊に転用しやすく、長期的に見ても安定した運営がしやすくなります。
宿泊に必要な設備が整っている
民泊では「住める空間」であることが前提です。浴室、トイレ、台所といった水回りの設備が整っていなければ宿泊施設として利用できません。
また、ベッドや寝具、基本的な家具や家電も必要です。これらが揃っていない場合は初期投資が大きく膨らみ、収益化まで時間がかかることになります。
反対に、既に設備がある程度整っている空き家であれば、比較的少ない投資で運営を始められる可能性があるため、留意しましょう。
周辺環境との調和がとれる
民泊は宿泊者と地域住民が共存することで成り立ちます。住宅街や集合住宅にある空き家を民泊にする場合、近隣住民の理解を得られなければトラブルが起こりやすくなります。
騒音やゴミの問題が顕在化すれば、住民の不満が強まり、最悪の場合は運営を続けられなくなるリスクがますます高まります。
地域のルールやマンション管理規約を事前に確認し、周囲の環境に配慮できるかどうかを検討しましょう。民泊の成功は、宿泊者の満足度だけでなく、地域との調和に支えられています。
活用が難しい空き家は「ワケガイ」にご相談ください!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や再建築不可の土地、空き家や事故物件など、通常の不動産市場では売却が難しい物件に特化した買取サービス「ワケガイ」を提供しています。
長年の取引実績を通じて、全国各地の多様なケースに対応してきました。現状のままでは売却が困難な物件でも、煩雑な手続きを一括して進められる体制を整えており、最短で即日の現金化も可能です。
市場で敬遠されがちな不動産を抱えてお悩みの方に、迅速かつ安心できる出口を提供いたします。まずはお気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
空き家の民泊活用は、収益を得ながら建物を維持できる有効な手段ですが、近隣とのトラブルや法規制、収益の不安定さといったリスクも伴います。
大切なのはメリットとデメリットを冷静に比較し、自分の物件や生活スタイルに合った方法を選ぶことです。立地条件や建物の状態を丁寧に見極め、必要に応じて管理委託や保険加入などの備えをしておくと安心です。
民泊だけでなく、賃貸や売却といった代替案も含めて検討し、将来的に負担のない形で空き家を活用していきましょう。