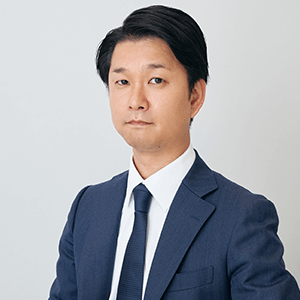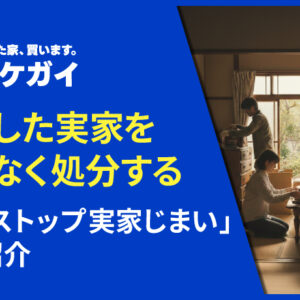こんにちは。ワケガイ編集部です。
相続した実家が空き家のまま放置されているケースや、転勤などで長期的に使わない住宅をそのままにしているケースでは、老朽化や固定資産税の負担、治安悪化といった問題が発生します。その際に検討すべきなのが空き家活用です。
空き家活用とは、使われていない住宅を賃貸や民泊、地域拠点など多様な形で再生し、価値を生み出す方法です。活用によって収益化や地域貢献、防犯効果も期待できます。
本記事では、空き家活用の具体的なアイデアやメリット・デメリット、失敗しないための注意点まで詳しく解説します。
について今すぐご相談できます。
お電話する
空き家活用のアイデア24選
空き家をそのまま放置していると、固定資産税の負担が続く上に老朽化が進み、いざ売却や活用を考えたときに余計な費用がかかることも少なくありません。
しかし見方を変えれば、空き家は自由度の高い資産でもあります。住宅として再利用する方法、商業施設や地域拠点に変える方法など、用途自体は多くあるのです。
ここからは、空き家を「住まい」として生かすパターンを中心に紹介していきます。
①「住まい」としての活用
空き家活用の基本は、やはり住まいとして使うことです。人口減少が進む地方では、移住者や学生を受け入れる住宅が不足している地域もあり、都心部でも、安価に住める物件は常にニーズがあります。
空き家を再生して住宅として提供することは、所有者にとって収益を得る手段であると同時に、地域にとっても新しい住民を呼び込むことに繋がります。
賃貸住宅
最もオーソドックスなのが、空き家を賃貸住宅として貸し出す方法です。改修後に入居者を募れば、家賃収入が得られるだけでなく、空き家が人の出入りによって自然に管理されるようになります。
築年数が古い場合でも、内装を整えれば需要は十分にあります。特に単身者向けや高齢者向けの住宅は常に一定の需要が見込めるため、立地や間取りに応じてターゲットを設定することがポイントです。
移住者・留学生向け住居
地方では空き家を移住者向け住宅に転用することでも活用可能です。自治体によっては移住促進の補助制度を用意しており、改修費用の一部を助成してくれるケースもあります。
移住希望者にとって「住まいが確保できること」は安心材料となり、地域への定着を後押しするでしょう。また、大学や専門学校の周辺では留学生向けの住居として需要も見込めます。
コンテナハウス併用住宅
一風変わった形として、空き家とコンテナハウスを組み合わせて活用する事例も見られます。母屋を改修しつつ、庭や敷地にコンテナを設置して住居や作業スペースとして利用する方法です。
コンテナは低コストで導入でき、工期も短いため、柔軟な住環境を整えられ、シェアハウスのように複数人が暮らすスタイルにすることも可能です。
ただし、コンテナは断熱性や耐久性の面で課題があるため、適切な施工や地域の建築基準を確認する必要があります。
ライダーハウス
ライダーハウスとは、バイクで旅をする人々が気軽に宿泊できる簡易宿泊施設のこと。北海道をはじめ、観光地では昔から親しまれてきたスタイルで、ライダーにとっては安価で便利な休憩場所として重宝されています。
空き家を改修してライダーハウスとして提供すれば、地域の観光資源を活かしつつ利用者を呼び込めるため、特に地方の道の駅や観光ルートに近い立地であれば、安定した需要が見込めるでしょう。
LGBTフレンドリー住宅
性的マイノリティの人々が安心して暮らせる住宅として空き家を提供することで、多様な人々のニーズに応えるという方法もあります。
例えば、同性カップルが入居を断られるケースはいまも存在しており、そうした背景から「誰でも安心して契約できる住まい」の需要は確実にあります。
バリアフリー住宅
高齢化が進む日本では、バリアフリー住宅の需要が年々高まっています。段差の解消や手すりの設置、車椅子対応の通路やトイレなどを整えた空き家は、高齢者や障害を持つ人々にとって非常に住みやすい環境となります。
既存の空き家をそのままでは利用できなくても、リフォームを通じて安全で快適な住居に再生することが可能です。
特に地方では、高齢者が住み慣れた地域に留まりたいと考えていても、適切な住宅が見つからないケースが多くあります。
民泊・ゲストハウス
観光需要が高いエリアでは、空き家を民泊やゲストハウスとして再生することで、集客を見込めます。特に、近年は、ホテルや旅館代が高騰していますので、価格面での差別化も図りやすいでしょう。
特に古民家風の物件は「日本らしい体験」を求める訪日客に好まれる傾向があります。
民泊として運営する場合、旅館業法や消防法などの法規制を守ることが必須です。また、近隣住民との関係も大切で、騒音やゴミ出しのルールを徹底しなければトラブルにつながります。
②「商業・サービス」としての活用
資金調達が前提にはなりますが、住宅としての利用に加えて、空き家を商業目的で利用すると収益性はさらに高まります。立地によっては住まいとしての需要よりも、店舗やサービス拠点として活用したほうが効果的な場合があります。
観光地や駅近など人通りの多い場所であれば、飲食や小売りの場としての展開が期待でき、地域住民にとっても新しい利便性を提供することになります。ここからは代表的な飲食系とサービス拠点の活用事例を取り上げます。
カフェ(ブックカフェ・コミュニティカフェ含む)
空き家をカフェに改装する事例は全国的に広がっています。古民家や町家をリノベーションしたカフェは、特に若い世代や観光客に受け入れられやすい特徴があります。
空き家特有の趣ある外観を活かせば、通常の店舗以上に話題性を持たせることが可能です。
さらに、ブックカフェやコミュニティカフェといった形態を選べば、単なる飲食の場以上の価値を提供できます。ブックカフェなら静かな読書スペースとして、コミュニティカフェなら地域住民の交流拠点として機能します。
軽飲食店(コーヒースタンドなど)
空き家を小規模な飲食店に改装する方法もあります。大規模な厨房や広い席数を必要としない軽飲食業態(例:コーヒースタンドやベーカリーなど)は、比較的低コストで始められるのが利点です。
通勤客が多いエリアや商店街の一角にある空き家であれば、立ち寄りやすい店舗として日常的に利用されやすいでしょう。
移動販売拠点
移動販売の拠点として空き家を利用する方法も有効です。キッチンカーや移動販売は柔軟に営業場所を変えられるメリットがありますが、調理や仕込み、保管を行う拠点が必要になります。そのベースとして空き家を改修すれば、コストを抑えつつ事業を展開することが可能です。
レンタルスペース(ヨガ・イベントなど)
空き家をレンタルスペースとして提供する方法は、利用者に合わせて柔軟に活用できるのが大きな魅力です。
例えば、ヨガ教室やダンスレッスン、料理教室など定期的な利用に向けて貸し出せば、安定した収益につながります。単発のイベントやセミナー、ワークショップにも使えるため、幅広い層に需要があります。
サウナ施設
近年の「サウナブーム」を背景に、空き家をサウナ施設へと改装する事例も増えています。特に郊外や自然に近い環境の空き家は、プライベート感のあるサウナとして人気を集めやすい傾向があります。
既存の浴室や庭を活用すれば比較的低コストで導入できる場合もあり、他の宿泊や飲食と組み合わせることで付加価値を高められます。
シェアサイクル拠点
都市部では自転車を共有して使う「シェアサイクル」が増えています。空き家をその拠点として活用すれば、駐輪場やメンテナンススペースとして提供可能です。
特に駅から少し離れた住宅街や観光地周辺では、シェアサイクルのニーズが高く、利便性の観点から地域貢献にも繋がるでしょう。
③「地域・コミュニティ拠点」としての活用
空き家は個人の住まいや商業施設だけでなく、地域のコミュニティを支える拠点としても役立ちます。
少子高齢化や人付き合いの希薄化が進むなか、住民同士がつながれる場所の需要は高まっています。ここからは、地域社会を豊かにする活用方法をいくつか紹介します。
アートスペース
古い建物の趣をそのまま活かし、ギャラリーやアトリエとして利用することで、他にはない個性を演出できます。若手アーティストにとっては発表の場を得られる機会となり、地域住民にとっても芸術に触れるキッカケとなります。
アートイベントを定期的に開催すれば、地元や観光客を呼び込む効果も期待できます。こうした活動は文化的な価値を高めるだけでなく、地域全体の活性化にも繋がるでしょう。
採算性は高くなくとも、文化的意義や話題性を軸に持続できれば、空き家を地域に開かれた空間へと再生することが可能です。
学習塾・教室(語学・専門教室含む)
空き家を学習塾や教室に活用することでも収益化できます。少人数制の学習塾、英会話やプログラミングといった専門教室など、地域のニーズに合わせて形態を変えられるのが強みです。
住宅の間取りをそのまま使えるため、机やホワイトボードを設置すれば十分に学習環境として機能します。
自習室・コワーキングスペース
テレワークや資格取得の勉強が一般化したことで、自習室やコワーキングスペースの需要は増加しているでしょう。
空き家を改修してネット環境や机、照明を整えれば、集中できる作業場として利用可能です。特に、カフェでは落ち着いて作業できない人や、在宅勤務に限界を感じている人にとって魅力的な場所となります。
ミニ図書館
空き家を小さな図書館に変える取り組みなら、地域住民から寄贈された本を並べ、自由に貸し借りできる形にすれば、大きな投資をせずに始められます。
特に子どもや高齢者にとって、徒歩圏内に利用できる図書館があれば、大いに助かるはずです。
子ども食堂
子どもの貧困や孤食の問題を背景に、子ども食堂の必要性は高まっています。空き家を子ども食堂に改装すれば、食事を提供するだけでなく、地域の人々が交流する場所としても機能します。
料理が得意な住民が協力するなど、地域単位で運営される例も少なくありません。
フリースクール
学校に通いにくい子どもたちに学びの場を提供するフリースクールは、教室として必要なのは広いスペースや机、ホワイトボード程度であり、大がかりな設備を整えなくても始められるのが特徴です。
住宅街の一軒家をそのまま使えば、子どもにとって家庭的で落ち着ける環境となりやすく、学習や交流を安心して行える雰囲気をつくれます。
放課後デイサービス施設
子どもたちが放課後や休日に安心して過ごせる場として、放課後デイサービスの需要は増え続けています。空き家を改修して施設として提供すれば、家庭と学校の間を支える存在になり、保護者の負担軽減にも大きく貢献します。
動物保護施設
犬や猫などの動物を保護し、空き家を新しい飼い主に引き渡すための拠点にすれば、動物たちが一時的に安心して過ごせる環境を整えられます。
敷地に余裕がある住宅であれば、ケージや運動スペースを設けることも可能で、地域のボランティアが集まりやすい場所として機能します。
コミュニティスペース
地域住民が集まれるコミュニティスペースとしての活用は、空き家活用の手法としても手軽な部類です。会議や交流イベント、趣味の集まりなどに利用できる場を整えることで、地域に新しいつながりを生み出せるため、そこから新たなビジネス機会の創出に繋がるでしょう。
特に公共施設が少ない地域では、こうした小規模な拠点の存在は大きな意味を持ちます。
空き家活用のメリット
空き家を放置すれば税金や維持管理の負担ばかりが発生しますが、使い方を工夫すれば以下のような恩恵も得られます。
- メリット①:収益が得られる
- メリット②:地域の活性化につながる
- メリット③:防犯・防災面で安心できる
次項より、個別にみていきましょう。
メリット①:収益が得られる
空き家を賃貸住宅や民泊に再生すれば、家賃収入や宿泊料といった形で安定した収益を生み出せます。特に都市部では住宅需要が根強く、築年数が古い物件でも家賃を抑えれば借り手が見つかる可能性も高まるでしょう。
地方であっても、移住希望者や長期滞在する旅行者をターゲットにすれば需要は十分にあります。自治体四季報が公開しているランキングからも明らかなように、決して日本で人口が増加しているのは東京都だけではありません。

(出典:自治体四季報「人口増減率ランキング」)
空き家を活用して収益を得る最大の意義は、維持コストをカバーできる点にあります。放置していれば固定資産税や管理費が出ていくだけですが、活用すれば収入と支出のバランスが逆転し、資産としての価値を保てます。
メリット②:地域の活性化につながる
空き家をカフェやコミュニティスペースに改装すれば、子ども連れの家族や高齢者が気軽に集まれる場となり、普段顔を合わせない住民同士が交流するきっかけが生まれます。
例えば、住宅地の中に小さな飲食店ができれば、買い物帰りに立ち寄る人が増え、地域の人間関係が日常的に深まります。
商店街の一角で空き家を再生すれば、従来は素通りしていた買い物客が立ち寄るようになり、近隣の店舗での購買機会も増えます。結果として商店街全体の売上が底上げされ、地元経済に直接的な効果が表れます。
メリット③:防犯・防災面で安心できる
空き家を放置すると、建物の劣化による倒壊や火災のリスクが高まるだけでなく、不法侵入や不審火といった治安面の不安も増します。雑草やゴミが放置された空き家は「管理されていない場所」と見なされ、近隣住民の安心感を大きく損ないます。
しかし、人が出入りする形で活用されていれば、こうしたリスクは大きく減少します。定期的に利用者がいることで建物の状態が自然とチェックされ、破損や老朽化も早めに対処できます。
空き家活用のデメリット
空き家を活用することには数多くの利点がありますが、現実的な課題も存在します。収益や地域貢献といった成果を得るためには、費用や規制、運営体制といった壁を乗り越える必要があるのです。
代表的なデメリットとしては、以下のものが挙げられます。
- デメリット①:初期費用や維持費がかかる
- デメリット②:法律や許認可の制約がある
- デメリット③:運営や管理の手間が増える
それぞれ個別にみていきましょう。
デメリット①:初期費用や維持費がかかる
空き家を活用するにあたり、避けて通れないのが改修費用です。長年放置されていた建物は、外から見て問題がなくても水回りや配管、屋根や基礎部分が傷んでいることが少なくありません。
住居として貸し出す場合には耐震補強が必要になることもあり、場合によっては数百万円単位の工事費がかかるケースもあります。
さらに、活用を始めた後も費用は発生し続けます。一例を挙げると、賃貸や民泊にした場合、定期的な清掃や修繕、害虫駆除などの維持管理を怠ると、すぐに住環境の質が落ちてしまいます。収益を得られるようになったとしても、その裏には一定の支出が伴うという現実があるのです。
空き家活用を考える際には、初期費用とランニングコストを冷静に見積もり、無理のない計画を立てるようにしましょう。
デメリット②:法律や許認可の制約がある
空き家を商業目的で活用する場合、さまざまな法律や許認可がハードルとして存在します。民泊であれば旅館業法や消防法、飲食店であれば食品衛生法や建築基準法といった規制に従う必要があります。
これらを無視して運営を始めてしまうと、行政からの指導や営業停止といった事態に発展しかねません。法規制は地域によっても異なり、都市部と地方で必要な手続きが大きく変わることもあります。
さらに、建物の用途変更や耐震基準への適合など、専門知識がなければ判断が難しい部分も多いのが実情です。事前に十分な調査を行わずに進めてしまうと、後から想定外の費用や時間がかかり、計画そのものが破綻しかねません。
デメリット③:運営や管理の手間が増える
空き家を活用して収益を上げるには、運営や管理の仕事が必ず発生します。賃貸であれば入居者の募集や契約管理、民泊なら予約対応や鍵の受け渡し、さらには清掃や設備のチェックが必要です。
こうした作業は一度きりではなく継続的に発生するため、想像以上の手間がかかります。
また、利用者からの問い合わせやトラブル対応も避けて通れません。水道や電気の不具合、近隣住民との摩擦など、オーナーが直接対応するのは負担が大きいでしょう。そのため管理会社や代行業者に委託する方法が現実的ですが、その分コストも増えます。
空き家活用の失敗パターン
ここまで空き家活用の手法についてみてきましたが、当然失敗パターンも存在します。その多くは事前の準備不足や見通しの甘さに起因しています。
特に起こりやすい失敗のケースとしては、以下のものが挙げられます。
- 失敗パターン①:需要を見誤る
- 失敗パターン②:改修費用が予想以上にかかる
- 失敗パターン③:管理・運営体制を整えていない
- 失敗パターン④:収益性ばかりを重視する
それぞれ個別にみていきましょう。
失敗パターン①:需要を見誤る
空き家活用で最も多い失敗は、需要を十分に検討せずに事業を始めてしまうことです。観光地でもない場所で民泊を始めても宿泊客は思うように集まりませんし、住宅街の奥まった立地でカフェを開いても、来店者数は限られてしまいます。
結果として固定費ばかりが膨らみ、赤字経営に陥ることになります。
需要を誤る背景には、「空き家があるから何かに使いたい」という所有者の発想だけで進めてしまう点があります。しかし、利用者の視点に立てば、交通の便や周辺環境、地域の人口動態が利用の可否を大きく左右します。
特に地方では人口減少が進んでいるため、数年前に需要があった事業も現在は難しい場合があります。空き家を活用する前には、地域特性や利用者層を丁寧に分析することが不可欠です。
失敗パターン②:改修費用が予想以上にかかる
古い空き家を改修する際、想定以上の出費に悩まされるケースも非常に多いのが実情です。外観はきれいに見えても、基礎や屋根、配管といった見えない部分が劣化していることが少なくありません。耐震基準を満たすための補強や水回りの入れ替えは費用が高額になりがちで、見積もりが当初の倍以上になることもあります。
こうした出費が発生すると、事業計画で想定していた利回りは一気に崩れ、採算が取れなくなります。さらに、改修工事に時間がかかれば、その間の収益はゼロで、管理費や固定資産税だけが積み重なっていくでしょう。
失敗パターン③:管理・運営体制を整えていない
空き家活用は改修して終わりではありません。利用者を受け入れる以上、日常的な管理や運営が必須。予約管理や問い合わせ対応、設備の清掃や点検を怠れば、すぐに苦情やトラブルにつながります。
特に民泊やレンタルスペースでは清掃不備が原因で利用者の不満が広がり、口コミの低評価によって利用者が減少するケースも多いのです。
さらに、所有者が遠方に住んでいる場合、自分で管理しようとすると対応が遅れがちになり、結果的に破綻することがあります。管理体制を軽視すれば、せっかくの空き家活用も継続できなくなってしまいます。
失敗パターン⑤:収益性ばかりを重視する
空き家活用で陥りがちな落とし穴の一つが、収益だけに目を奪われてしまうことです。短期間で利益を得ようとすると、利用者の満足度や地域との調和がおろそかになります。
実際問題として、観光客相手の民泊にばかり力を入れれば、近隣住民との関係が悪化し、苦情や反発を招きます。その結果、運営自体が難しくなることも少なくありません。
活用が難しい空き家を売却する際の選択肢
どの空き家も必ずしも活用できるわけではありません。老朽化が進みすぎて改修費用がかさむ場合や、立地条件が需要に合わない場合は、思い切って売却するのが現実的な解決策となります。
空き家を売却する方法には大きく分けて「仲介による売却」と「買取専門業者への売却」があり、それぞれに特徴があります。
仲介での売却
不動産会社に仲介を依頼して市場に出す方法は、もっとも一般的な売却手段です。仲介の強みは、市場価格に近い金額で売却できる可能性が高いことにあります。立地や状態が良ければ購入希望者が現れ、相場以上の価格で売れるケースもあります。
ただし、仲介には時間がかかるのが難点です。買い手が見つかるまで数か月から1年以上かかることもあり、その間も固定資産税や維持管理の負担は続きます。また、老朽化が進んだ空き家は買い手がつきにくく、価格を大幅に下げないと売れないこともあります。
買取専門業者への売却
もう一つの選択肢が、買取専門業者に直接売却する方法です。最大のメリットは、売却までのスピードです。業者が直接買い取るため、早ければ数日から数週間で現金化できます。急いで空き家を手放したい場合や、相続後に維持管理が難しい場合には適した方法です。
一方で、買取価格は市場価格よりも低くなるのが一般的です。業者は買い取った物件を再販するため、その分の利益を差し引いた価格での提示となります。それでも、売れ残りのリスクや管理コストを考えれば、早期に現金化できる点は大きな利点です。
関連記事:空き家の固定資産税は無料にならない?支払額が6倍になる仕組みとは
活用が難しい空き家は「ワケガイ」が買い取ります!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や再建築不可物件、事故物件など市場での売却が難しい不動産をスピーディに現金化できる買取サービス「ワケガイ」を提供しています。
一般的な仲介では買い手が見つかりにくいケースでも、最短1日で買取を実現できる体制を整えており、全国対応の実績も豊富です。
老朽化が進んだ空き家や管理負担が大きい物件でも現状のまま査定が可能で、オーナー様の状況に応じた柔軟な対応を心がけています。他社で断られた物件でも諦める必要はありません。まずはお気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
空き家を活用する方法は多岐にわたり、賃貸や民泊による収益化から、カフェやコミュニティスペースによる地域貢献まで幅広い可能性があります。しかし成功のためには、立地や需要を正しく見極め、改修費用や法律面を事前に確認することが大切です。
活用を始める前に目的を明確にし、資金計画や管理体制を整えることで、継続的に価値を生み出す空き家へと変えられます。
放置すればリスクが増す一方であるからこそ、適切な形で空き家を再活用し、自分や地域にとってプラスとなる選択を実行していきましょう。