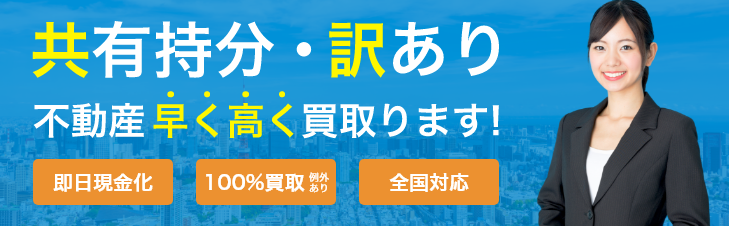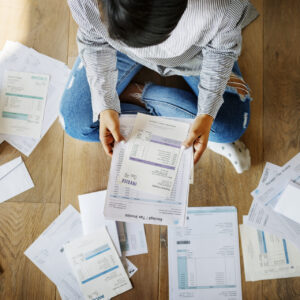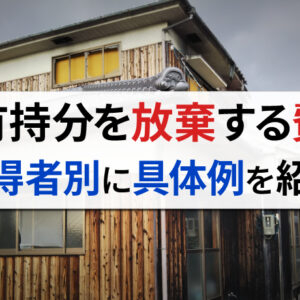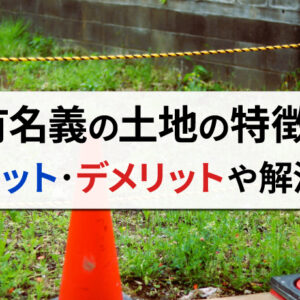不動産の共有持分を売却しようとした際、「思ったよりも安い金額でしか売れない」と感じることがあります。特に、他の共有者が不動産全体を活用している場合や、単独での売却が難しい状況では、希望価格での売却が難しくなることが少なくありません。
その際に重要なのが共有持分の買取相場が市場価格より低くなりやすい理由を理解することです。
共有持分とは、不動産の一部分の所有権を指し、単独で売却できるものの、通常の不動産とは異なる特性があります。そのため、市場での売却価格が制限され、一般の不動産よりも低い価格で取引されるケースが多くなります。
そこで本記事では、共有持分の買取相場が低くなりやすい理由を詳しく解説し、売却を成功させるために知っておくべきポイントを紹介します。
目次
共有持分の売却相場は「市場価格より低い」が基本
共有持分とは、1つの不動産を複数人で所有する際に、それぞれが持つ権利のことを指します。
共有者は持分の範囲で権利を主張できますが、不動産全体を自由に使えるわけではなく、売却や賃貸などの重要な判断には他の共有者の同意が必要になることが多いのが特徴です。
こうした制約があるため、共有持分を売却する際の価格は、市場価格よりも低くなるのが一般的です。
通常の不動産と異なり、持分だけでは不動産を単独で活用できず、買い手が限られるため、売却価格が抑えられる傾向があります。特に、単独での売却を希望する場合、相場よりも大幅に低い価格での取引になるケースも少なくありません。
関連記事:共有持分の家を高く売る方法とは?具体的な手順をわかりやすく紹介
共有持分の売却相場が低くなりやすい理由とは?
共有持分の売却相場が低くなりやすい理由としては、大きくは以下の2点が挙げられます。
- 理由①:権利だけでは活用できず、売却しづらいため
- 理由②:共有者との対立が起こりやすく、リスクが高いから
それぞれ個別にみていきましょう。
理由①:権利だけでは活用できず、売却しづらいため
共有持分は「不動産の権利」ですが、それだけでは不動産全体を自由に活用することができません。持分所有者が単独でできることは限られており、売却もしづらくなります。
例えば、以下のような行為は、他の共有者全員の同意が必要になります。
<共有者の同意が必要な行為>
- 不動産全体の売却
- 長期賃貸借契約の締結
- 建物の解体、新築、大規模修繕
- 抵当権の設定
- 土地の分筆や加筆
このように、共有持分を持っていても自由に不動産を活用できないため、買い手がつきにくく、売却相場も低くなりやすいのです。さらに、売れずに放置すると固定資産税の負担が続くため、早期売却を検討する人も多いのが実情です。
理由②:共有者との対立が起こりやすく、リスクが高いから
共有不動産では、共有者間で意見の対立が起こることが珍しくありません。例えば、売却や活用の方針について意見が割れたり、一部の共有者が協力を拒んだりするケースもあります。
第三者が共有持分を購入する場合、以下のようなリスクを考慮する必要があります。
- 他の共有者が売却に反対し、交渉が進まない
- 使用や管理に関する意見が合わず、トラブルに発展する
- 共有者の一人が居住しており、立ち退きを求めにくい
こうしたリスクを避けるため、共有持分の買い手は慎重になりがちです。その結果、売却の難易度が高まり、価格が下がる要因となります。
関連記事:共有持分は売却可能?よくあるトラブルと対策方法とは?
共有持分の査定のポイント
では、共有持分の価格はどのように決まるのでしょうか。主な査定のポイントとしては、以下が挙げられます。
- 査定ポイント①:共有者の数
- 査定ポイント②:立地条件や周辺状況
- 査定ポイント③:土地と建物がセットかどうか
- 査定ポイント④:ローンの残債や抵当権
- 査定ポイント⑤:隣接する土地との境界の有無
次項より、個別に解説します。
査定ポイント①:共有者の数
共有者の人数が少ないほど、売却時に高値で買い取ってもらえる可能性も高まるでしょう。
なぜなら、買取業者が他の共有者との交渉を行う手間が減るためです。
具体的には、売主を含めて共有者が3~4人程度であれば、比較的査定額も高くなる傾向があります。
査定ポイント②:立地条件や周辺状況
不動産の「状態」「立地」も査定のポイントとなります。良好な条件や立地を持つ不動産はニーズが高く、買取業者も再活用しやすいためです。
具体的には、以下のような要素が重要です。
- 駅やバス停までの距離
- 周辺に商業施設や病院、学校などはあるか
- 建物の劣化具合や築年数
特に、建物の劣化や築年数については、経年とともにどんどん悪化していきます。共有持分の売却を検討しているなら、早い段階で対応しましょう。
査定ポイント③:土地と建物がセットかどうか
土地と建物両方の共有持分を持つ場合、それらを一緒に売却すると買取価格が高くなる可能性があります。土地だけ、あるいは建物だけの共有持分でも売却は可能ですが、査定額は低くなる傾向があります。
査定ポイント④:ローンの残債や抵当権
「共有名義不動産にローンなどの残債」があると、査定以前に売却自体が難しくなる可能性が高いでしょう
共有名義不動産とは「不動産に関する全ての権利をそれぞれの共有持分の所有者が持つ」という前提があります。そのため、ローンなどの残債や借金などによる抵当権も例外ではありません。
共有持分を売却したい場合は、まずローンなどの残債や抵当権を解消しましょう。
査定ポイント⑤:隣接する土地との境界の有無
「隣接する土地との境界標の有無」も共有持分の査定に関わってきます。境界が不明瞭な土地を売却すると、後で境界に関するトラブルが起こり、訴訟に発展する可能性があるのです。
そういったケースを考慮して、買取業者は境界が設定されていない土地の査定額を、低く見積もることが懸念されます。
これは、共有名義不動産(共有持分)に限らず通常の不動産でも基本の査定ポイントとなっておりますので覚えておきましょう。
売却相場は売却先によって変わる
共有持分の売却価格は、市場価格そのままにはならず、売却先によって大きく変わるのが特徴です。売却先には主に「他の共有者」と「第3者」の2択があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
他の共有者に売却するなら市場価格に近づく可能性が高い
他の共有者に持分を売却する場合、その共有者は持分割合を増やすことができるため、市場価格に近い価格で売却できる可能性があります。
例えば、共有不動産の市場価格が5,000万円で、自分の持分が2分の1なら、2,500万円で売れる可能性があるという計算になります。
しかし、他の共有者への売却にはデメリットもあります。
まず、売却には相手の合意が必要なため、共有者が持分を買い取る意思がない場合、売却自体が進まない可能性があります。また、共有者との関係性が悪化している場合、交渉が難航することも考えられます。
さらに、相手に買取の資金力がない場合、支払い能力の問題で取引が成立しないこともあります。市場価格に近い金額で売れる可能性がある一方で、売却のハードルが高いことを理解しておく必要があります。
第三者に売却すると市場価格の3〜6割が一般的
共有持分を第三者に売却する場合、市場価格の3〜6割程度になることが一般的です。これは、共有持分のみでは不動産全体を自由に活用できず、買い手にとってリスクが高いためです。
第三者が共有持分を購入した場合、他の共有者と交渉しながら不動産を運用する必要があります。しかし、共有者との意見が合わず、思うように売却や活用ができないケースも多いため、買い手側は慎重にならざるを得ません。
その結果、買取価格は通常の不動産市場と比べて大幅に低くなりやすいのです。
共有持分の売却は「専門の買取業者」がおすすめ
共有持分の買取を専門とする不動産業者は、「特殊な状況の物件」を専門に取り扱っています。
一般的な不動産業者に共有持分の買取を依頼しても、進行がスムーズにいかないことがあります。その理由は、前述のとおり共有持分の権利関係が複雑で、一般的な利用が難しいからです。
しかし、専門の買取業者に依頼すれば、他の共有者とは関わることなく持分を現金化し、共有名義から離脱することができます。
専門の買取業者は共有持分を買取るためのノウハウが豊富で、専門家と連携して共有者間の調停も行うことができるため、共有不動産をスピーディーに買い取ってくれるでしょう。
「共有者との交渉を避けたい」「迅速かつ労力を使わずに持分を放棄したい」とお考えの方は、共有持分を扱う不動産買取業者に依頼し、買い取ってもらうことを検討しましょう。
関連記事:【2025年版】共有持分の買取業者のおすすめ厳選5社!今買取をお願いするべき専門業者とは?
関連記事:共有持分の売却は「買取」「仲介」のどちらにするべき?
共有持分の買取業者の選定のコツ
共有持分をスムーズに売却するためには、適切な買取業者を選ぶことが重要です。ここでは、共有持分の買取業者を選ぶ際に押さえておきたいポイントを詳しく解説します。
- コツ①:買取実績が豊富かを確認する
- コツ②:買取価格の適正性を比較する
- コツ③:売却手続きのスピードと柔軟性を確認する
- コツ④:共有持分買取のトラブル対応力をチェックする
- コツ⑤:口コミ・評判を確認する
以下より、個別にみていきましょう。
コツ①:買取実績が豊富かを確認する
共有持分の売却は、一般的な不動産売却とは異なり、専門的な知識や交渉力が求められます。特に、他の共有者がいる状態での取引は通常の不動産売買よりも複雑になりがちです。
そのため、共有持分の買取実績が豊富な業者を選ぶことが、スムーズな取引につながります。
✅チェックポイント:
- 公式サイトに過去の買取事例を掲載しているか
- 相談時に具体的な取引実績を提示してくれるか
- 共有持分買取の専門業者かどうか
コツ②:買取価格の適正性を比較する
共有持分の買取価格は、業者によって査定基準が異なるため、一社の査定だけで即決するのは避け、必ず複数の業者から見積もりを取ることが重要です。
共有持分の売却価格は、不動産全体の価格の2分の1~3分の1程度になることが多いですが、業者によってはさらに低く査定される場合もあります。
そのため、適正価格を把握するために、最低でも2~3社の査定額を比較することが大切です。
✅チェックポイント:
- 1社だけではなく、複数の業者の査定額を比較する
- 査定額の根拠を明確に説明してくれるか
- 「相場より極端に安い」査定を提示する業者は避ける
- 「すぐ契約を迫る」業者は慎重に検討する
コツ③:売却手続きのスピードと柔軟性を確認する
共有持分を売却する理由の中には、「すぐに現金化したい」「トラブルを早期解決したい」というケースも少なくありません。
そのため、売却手続きのスピードも重要なポイントになります。
買取業者によっては、最短即日で契約・現金化できる業者もあれば、手続きに1ヶ月以上かかる業者もあります。事前にスケジュールを確認し、希望の期間内で売却が可能かどうかをチェックしましょう。
✅チェックポイント:
- 相談からどのくらいの期間で買取が完了するか
- 即日対応や最短での入金が可能か
- 共有者との交渉サポートがあるか
コツ④:共有持分買取のトラブル対応力をチェックする
共有持分の売却には、他の共有者とのトラブルや法的な問題が発生することがあります。
例えば、買取業者が弁護士や司法書士と連携している場合、売却に必要な手続きや交渉をスムーズに進めやすくなります。共有者とのトラブルに巻き込まれるリスクを避けるためにも、法的なサポート体制がしっかりしている業者を選ぶと安心です。
✅チェックポイント:
- 他の共有者との交渉サポートがあるか
- 弁護士や司法書士と提携しているか
- 過去のトラブル事例と解決策を提示してくれるか
コツ⑤:口コミ・評判を確認する
買取業者を選ぶ際には、実際に取引した人の口コミや評判をチェックすることも大切です。
インターネット上には、不動産買取業者の口コミサイトやGoogleレビューなどがあり、実際の利用者の評価を確認できます。
特に、「契約を急かされた」「買取価格が最初の提示額と違った」「対応が遅い」などのネガティブな口コミが多い業者は避けた方が無難です。
✅チェックポイント:
- Googleレビューや不動産専門サイトの口コミを確認する
- 「対応が丁寧」「説明が分かりやすい」という評価が多いか
- 契約時の強引な営業やトラブルがないか
関連記事:共有持分を高く売るためには買取業者の選び方とは?価格査定の要点も解説!
買取業者に共有持分を売却する流れ
共有持分を買取業者に売却する際は、いくつかの手順を踏む必要があります。具体的には、以下のとおり。
- STEP1. 売却の目的を整理する
- STEP2. 必要書類を準備する
- STEP3. 買取業者に査定を依頼する
- STEP4. 買取業者と条件交渉を行う
- STEP5. 売買契約の締結と手続き
- STEP6. 所有権移転登記の手続き
スムーズな取引を進めるために、各ステップのポイントを押さえておきましょう。
STEP1. 売却の目的を整理する
まず、売却の目的を明確にしましょう。早期に現金化したいのか、高値で売りたいのか、共有状態を解消したいのかによって、適切な業者の選び方が変わります。目的を整理することで、売却の進め方がスムーズになります。
STEP2. 必要書類を準備する
売却には登記簿謄本や固定資産税納税通知書、本人確認書類などが必要になります。事前に揃えておくことで、査定や契約がスムーズに進みます。
書類が不足していると手続きが遅れることがあるため、早めに準備を進めましょう。
STEP3. 買取業者に査定を依頼する
買取業者によって査定額が異なるため、複数の業者に依頼し、比較することが重要です。価格だけでなく、実績や対応の丁寧さも確認しましょう。
買取実績が豊富な業者を選ぶことで、売却後のトラブルを避けられます。
STEP4. 買取業者と条件交渉を行う
査定額をもとに、買取価格や支払い方法、手続きのサポート内容を確認します。契約条件に納得できるまで交渉を進めましょう。売却を急ぐ場合は、即日対応可能な業者を選ぶとスムーズです。
STEP5. 売買契約の締結と手続き
契約内容を確認し、問題がなければ売買契約を締結します。契約後、業者側で所有権移転の手続きが進められます。署名・捺印の前に、契約書の内容をしっかり確認しましょう。
STEP6. 所有権移転登記の手続き
売却が完了すると、所有権移転登記が行われます。登記手続きは通常、業者が司法書士と連携して進めるため、売主側の負担はほとんどありません。登記が完了すると、正式に売却が成立し、代金が支払われます。
関連記事:共有持分を売却する際の注意点とは?税金関連の知識も交えて網羅的に解説
「ワケガイ」なら訳あり物件も短期で買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」を提供しています。ワケガイは、共有持分や再建築不可物件など、一般市場では売却が難しい不動産の買取に特化した専門サービスです。
ワケガイでは独自の査定基準と買取ネットワークを活かし、単独での持分売却にも対応。最短1日で買取を実施し、迅速な資金化をサポートします。また、共有者との交渉が難しい場合や、権利関係が複雑なケースにも、提携する専門家と連携しながらスムーズな売却を実現します。
「他社で断られた」「長年売れずに困っている」共有持分でも対応可能です。お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
共有持分の買取相場は、市場価格より低くなりやすい傾向があります。その理由として、単独での活用が難しいこと、買い手が限定されること、共有者との調整が必要になることなどが挙げられます。
これらの要因が影響し、共有持分の売却価格は通常の不動産取引よりも下がりやすくなっています。
こうした状況の中で、できるだけ有利な条件で売却するためには、複数の買取業者に査定を依頼し、適正価格を把握することが重要です。
また、共有者と事前に協議し、売却の方向性を調整することで、スムーズな取引が可能になります。売却の際は、契約条件や支払いのタイミングを十分に確認し、納得のいく取引を進めましょう。