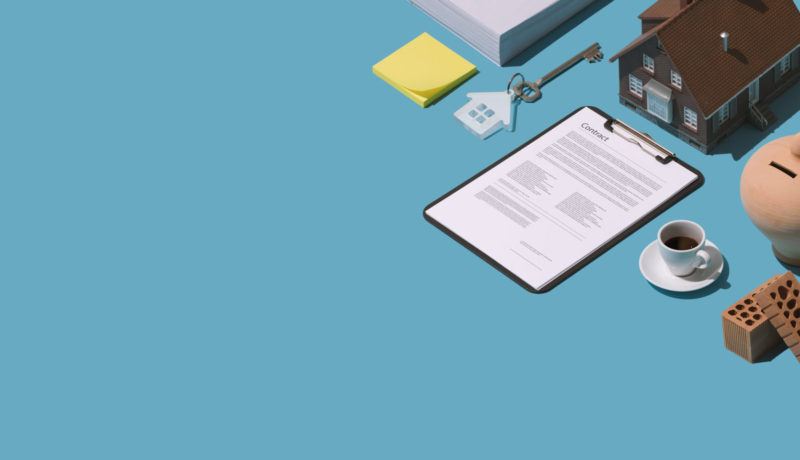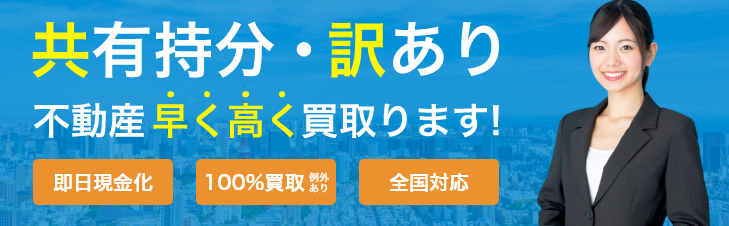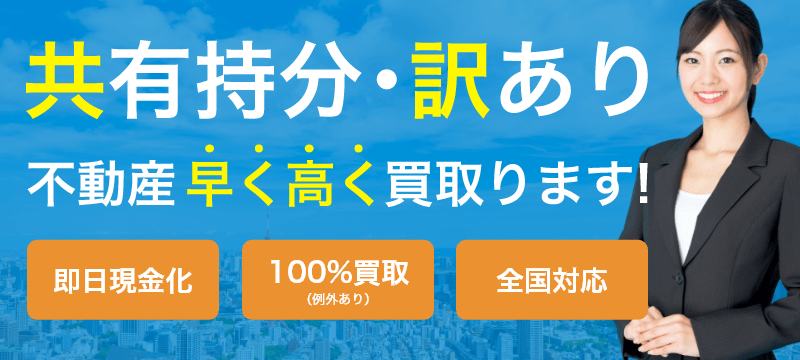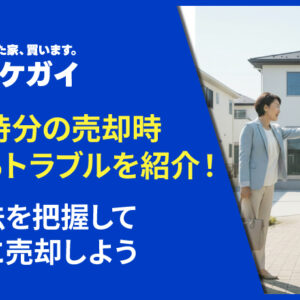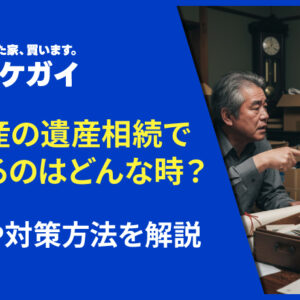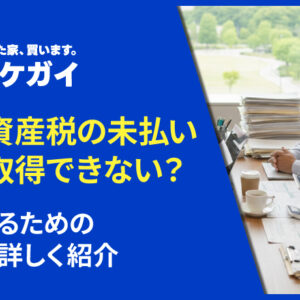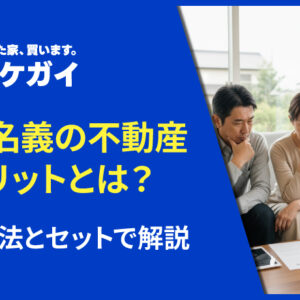こんにちは。ワケガイ編集部です。
共有名義の不動産をめぐって、他の共有者と意見が合わずトラブルに発展したり、負担ばかりが増えてしまったりするケースは少なくありません。こうした場面で検討されるのが「共有持分の放棄」です。
とりわけ、複数人で共有している場合、「共有持分の放棄は早い者勝ち」といった話を耳にしたことがある方も多いでしょう。確かに、最後の1人になると放棄自体ができなくなるケースもあるため、実際に「先に動いた方が有利」になる状況は存在します。
しかし、共有持分の放棄には法的な手続きや費用、他者の協力が必要となるなど、注意点も多くあります。本記事では、そんな「早い者勝ち」の意味を正しく解説した上で、共有持分を放棄するか否かの実務的なポイントを整理します。
目次
共有持分の放棄とは?
共有持分放棄は、複数の共有者と一緒に所有する不動産の一部を手放し、それを他の共有者へ移譲する手続きを指します。一般的な共有持分の移転(例:贈与や売買)では、受取人の同意が必要。しかし、共有持分放棄の場合、放棄する側の意志だけで進行可能というのが特色です。そのため、新たな受取人を探す手間が省け、より迅速に共有状態を解消できるともいえます。
放棄された持分はその後どうなる?
民法第255条によれば、放棄された持分は自動的に他の共有者に帰属します。つまり、共有者が2名であれば、1人が放棄するともう1人が全体を所有することになるのです。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)
しかし、3人以上の共有者がいて、1人が放棄する場合は、放棄された部分が残りの共有者間で持分比率に従い分割されます。
関連記事:共有持分は放棄できる?具体的な手順や発生する費用をチェック!
持分放棄と「贈与」の違い
贈与は、贈り手と受け手双方の合意に基づく法的な手続きです。両者の同意が無いと成立しません。
一方、持分放棄は、放棄者の意思だけで可能で、他の共有者の了承は必要ありません。ただし、持分放棄に関連する不動産の登記をする際には、放棄者と受益者双方の申請が必要。これにより、登記の手続きでは他の共有者の協力が求められます。
贈与では、共有者外の第三者にも贈ることができますが、持分放棄の場合、受益者は必ず共有者となります。
持分放棄は予期せぬトラブルの原因となることも。一例を挙げると、一部の共有者が放棄することで、他の共有者が意図しない中で不動産の持分を増やすことになるため、それが歓迎されない場合もあるからです。
なぜ共有持分の放棄は「早いもの勝ち」といわれるのか?
共有不動産をめぐる人間関係が悪化していると、「一刻も早くこの関係から抜け出したい」と感じる方は少なくありません。とくに物件に住んでもいなければ、収益性も低い共有持分を手放したいと考えるのは自然です。
その際によく耳にするのが「共有持分放棄は早い者勝ち」という言葉ですが、これは本当に正しいのでしょうか。
実際には、共有持分の放棄には法的な制約があり、単に「先に申し出た者が勝ち」という単純な話ではありません。本項では、その背景と注意点を詳しく解説します。
放棄は「他の共有者」がいなければ行えないことが主な理由
共有持分の放棄は、あくまで共有関係にある他の誰かに引き取ってもらうことを前提としています。つまり、最後の一人になってしまうと、放棄先が存在しないため放棄そのものができなくなります。
この構造により、「先に放棄すれば、残った人に押しつけられるのでは?」という心理が働きやすくなり、結果として「早い者勝ち」といわれるのです。ただし、これはあくまで実務的な順番の話であり、実際には放棄先の共有者が登記に協力してくれない限り、放棄は成立しません。
放棄による免責には「登記」が不可欠
共有持分を放棄すると、固定資産税や管理義務などの負担から解放されると考えがちですが、実際には登記が完了しなければその効力は及びません。法務局での登記を通じて、正式に持分が移転されて初めて、義務からも免れます。
逆にいえば、いくら「放棄した」と伝えても、相手が協力せず登記ができなければ、納税通知書は元の持分者に届き続けるのです。
安易な放棄はトラブルの原因になる
放棄は一方的にできる手続きではなく、他の共有者との合意や登記手続きが必要です。ときには放棄された共有持分の引き受けを他の共有者が拒否することもありますし、放棄をめぐって感情的な対立が深まるケースも少なくありません。
さらに、民法第1条第3項にある権利濫用の禁止の原則により、「責任だけ他人に押しつけて逃げようとする放棄」は、後から争点になる可能性もあります。放棄はあくまで、法的手続きに基づいて慎重に進めるべきものです。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)
それでもいち早く共有持分を放棄した方がいいケース
共有持分の放棄には手間や費用がかかる上、放棄したからといってすべての問題が解決するとは限りません。しかし、それでも「できるだけ早く手放すべき」と判断されるケースも存在します。
具体的には、以下4つのシチュエーションです。
- ケース①:持分の売却が困難である
- ケース②:持分を相続財産として残したくない
- ケース③:管理負担・維持コストだけが重くのしかかっている
- ケース④:共有者との関係が悪化しており協力が見込めない
それぞれ、個別に解説します。
ケース①:持分の売却が困難である
共有不動産の売却に際しては、共有者全員の合意が必須です。もし、共有者の中で一人でも売却に反対する意見がある場合、不動産の売却は進められません。
このような場面で共有者間の意見が分かれると、不動産の管理や今後の取り決めに関するトラブルが生じることも想定されます。そのような煩雑なトラブルを回避したいと考えることから、持分の放棄という選択をする人も少なくありません。
ケース②:持分を相続財産として残したくない
共有持分には、賃貸や売却といった有効な活用方法が考えられますが、一方で遠方の土地や利用の難しい農地・山林など、特定の利用目的が難しい場合があります。そうした不動産を持ち続ける意義を見いだせないケースも考えられます。
共有持分は、遺産相続の対象となるため、保持していると将来の相続時に子どもたちにその負担が継承されていきかねません。子どもたちに不必要な負担を背負わせないため、早期の段階で共有持分の放棄を選択することも推奨される場面があります。
ケース③:管理負担・維持コストだけが重くのしかかっている
共有持分を保有しているだけでも、固定資産税や管理費といった維持コストが継続的に発生します。特に築年数の古いマンションや利用価値の低い空き地では、賃料収入や活用の見込みが乏しい一方で、支出だけが積み重なる状況に陥りやすくなります。
また、修繕積立金や清掃費なども共有者全員に分担義務が課されるため、単純に「使っていないから払わなくていい」というわけにはいきません。こうしたケースでは、もはや資産ではなく「負債」としての側面が強まり、早期の持分放棄が現実的な選択肢となることも少なくありません。
関連記事:共有不動産の管理費用の分担方法とは?費用を払わない共有者がいる場合の対応手段について
ケース④:共有者との関係が悪化しており協力が見込めない
共有名義の不動産では、他の共有者との連携が必要不可欠です。しかし、そもそも関係が良好でない。あるいは感情的な対立や疎遠状態が続いている場合には、協議そのものが成立しないこともあります。
売却や活用の話し合いが進まず、合意形成も難航する中で、ストレスや精神的負担ばかりが増していく。このような状況では、もはや物件の将来性を論じる以前に「関係性から解放されたい」というニーズが先立ちます。早めに共有関係を抜け出す手段として、持分放棄は極めて有効な選択肢となるでしょう。
共有持分の放棄に関わる税金・費用
共有持分の放棄は「意思表示」だけで終わるものではなく、実際には税金や登記手続きに関する費用が発生します。放棄を検討する際には、こうした金銭的な負担も把握しておくことが重要です。
ここでは、主に「登記関連費用」「贈与税」「固定資産税」の3つに分けて、具体的に解説します。
登記関連費用(登録免許税+司法書士報酬)
共有持分を放棄する際には、その持分を他の共有者に「移転登記」する必要があります。このとき課されるのが登録免許税です。放棄は贈与扱いとなるため、「固定資産税評価額 × 2%」が税額の目安になります。
(参考:国税庁「登録免許税の税額表」)
例えば、評価額が500万円の持分であれば、登録免許税は10万円となります。また、登記手続きを司法書士に依頼する場合は、報酬として5〜10万円前後の費用がかかるのが一般的です。
相手方とのやり取りや書類の作成、法務局への申請まで含めて対応してもらえるため、実務上は専門家のサポートを受けるケースが多いでしょう。
関連記事:共有持分の「登記費用」はいくら?計算方法や手続きについて解説
贈与税(持分を受け取った側に課税)
持分の放棄とは、他の共有者に無償で不動産の一部を譲渡する行為ともいえます。そのため、放棄された持分を受け取った側には贈与税が発生する可能性があります。
贈与税は、年間110万円を超える贈与を受けた場合に課税対象となり、共有持分の評価額によって税額が決まります。
<一般贈与財産用(一般税率)>
| 課税価格範囲(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | – |
| 200万円超〜300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超〜400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超〜6,000万円以下 | 30% | 65万円 |
| 6,000万円超〜1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超〜1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
ただし、誰に放棄するか、親族か第三者かによっても税務上の取り扱いが異なります。複雑な場合は、税理士に確認のうえ対応するのが無難です。
関連記事:共有持分を贈与する際の「贈与税の計算方法」をわかりやすく解説!
固定資産税(放棄が未登記の場合は負担継続)
共有持分を放棄しても、その内容が登記簿に反映されていなければ固定資産税の納税義務は継続されます。市町村の課税は登記情報をもとに行われるため、「放棄した」と口頭や書面で伝えていても、登記が済んでいなければ課税通知は届いてしまいます。
そのため、持分放棄後は速やかに登記手続きを完了させることが不可欠です。もし放棄に応じてくれる相手が見つかっても、登記をしなければ一方的な放棄にすぎず、現実の負担からは解放されないままです。放棄の意思表示だけで安心せず、必ず法的手続きまで完了させましょう。
関連記事:共有名義の「固定資産税」は誰が払うべき? 滞納した場合や支払いたくない場合はどうなる?
共有持分を放棄するにはどうすればいい?基本の流れと注意点
共有持分を手放すには、ただ「放棄します」と伝えるだけでは足りません。法的に効力を持たせるためには、他の共有者に放棄の意思を伝え、共有持分の移転登記を行う必要があります。特に「先に放棄した者が有利」とされるような状況では、早めの対応が後々の負担軽減につながります。
ここからは、共有持分の放棄に必要な基本的な流れと注意点を、できるだけ簡潔に整理します。
Step1.他の共有者へ放棄する意思を伝える
まず、他の共有者に口頭で放棄意思を伝えます。その後、確実な記録として内容証明郵便を利用して再度意思表示を行います。事前に口頭で伝えないと、突然の内容証明郵便によって関係が悪化することがあるため注意が必要です。
内容証明の内容は重要なので、弁護士や司法書士に相談することが推奨されます。
Step2.共有持分移転登記ををする
放棄を完了させるには、登記上の名義変更(=共有持分の移転登記)を正式に行うことが不可欠です。これにより、法的にも持分の権利義務が他者に移り、固定資産税や管理費の負担から解放されます。
この手続きには、他の共有者の協力が前提です。受け取り側が拒否すれば登記は進まず、放棄が成立しません。相手の同意を得られるよう、事前に話し合いや条件交渉をしておくことが現実的な対応策です。
なお、登記にあたっては専門知識が求められるため、司法書士に依頼するのが一般的です。費用や必要書類の準備についても、専門家に確認しておくと安心です。
共有者が非協力的でも持分は放棄できる?
共有持分の放棄は、他の共有者の同意がなくても「意思表示」自体は成立します。しかし実務上は、放棄後に「登記をどう進めるか」がネックになります。
たとえば、他の共有者が放棄された持分の受け取りや登記に協力しない場合、放棄した側は依然として名義上の所有者とされ、固定資産税などの責任も残り続けかねません。
このような状況では、不動産登記法第63条第1項に基づき、「登記引取請求訴訟」を提起することで対応可能です。これは、協力しない共有者に代わって、裁判所の判決で登記を完了させる手続きです。
(参考:e-Gov 法令検索「不動産登記法」)
訴訟には以下の書類を用意しなければなりません。
- 訴状
- 登記原因証明書類(協議書や放棄通知など)
- 相手方の住民票や登記簿謄本などの添付資料
- 内容証明の写し
裁判という手段は、協力が得られない場合のやむを得ない選択肢ですが、手間や時間、費用の負担も避けられません。共有者との関係がすでに悪化している場合には、専門家に相談しながら、冷静かつ法的に筋の通った対応を検討していきましょう。
共有者間の関係が悪ければ、放棄よりも専門業者への買取依頼も検討しよう
共有者との信頼関係がすでに崩れており、合意形成が困難な状況では、共有持分の放棄手続きが思うように進まないこともあります。
とくに、他の共有者が放棄を受け入れず、登記手続きに協力しない場合、前述したように最終的には登記引取請求訴訟に踏み切らざるを得なくなるリスクもあります。
こうしたトラブルを回避したい場合、共有持分を専門に取り扱う買取業者へ売却するという選択肢も有効です。買取であれば、共有者の同意が不要なうえ、現金化までのスピードも速いため、精神的な負担を大きく軽減できます。
共有持分に悩みを抱えている方は、放棄だけにこだわらず、売却という現実的な解決策も視野に入れて検討してみましょう。
<訳あり物件の買取専門業者に相談するメリット>
- 共有者の同意が不要なケースもある
- 共有者とのトラブルを回避できる
- 現金化までのスピードが早い
- 再建築不可や事故物件などにも対応してくれる
- 登記手続きもサポートしてもらえる
関連記事:共有持分の買取サービスを利用するメリットとは?業者選びのコツも合わせて紹介
放棄が難しい共有持分は「ワケガイ」にご相談ください

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や再建築不可物件など、一般的に売却が難しい不動産を対象とした買取サービス「ワケガイ」を提供しています。
共有者間での関係悪化や、売却の合意が得られないといったケースでも、当社では共有者全員の同意がなくても買取可能な場合があります。
また、共有不動産にかかわる煩雑な登記や手続きも、司法書士・弁護士と連携してスムーズに対応し、最短1日での現金化も可能です。誰にも相談できずに悩みを抱えている方も、まずはお気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
実際問題として共有持分の放棄は、状況によっては確かに「早い者勝ち」になり得ます。特に他の共有者が非協力的であり、持分を引き受ける人がいなくなると、放棄自体が不可能になりかねません。そのため、状況が悪化する前に早めの判断を下す必要があります。
ただし、放棄の意思だけで終わるわけではなく、登記や税金、費用の負担、他者との合意形成など、クリアすべき課題も多くあります。まずは自分の状況に合った選択肢を整理し、無理のない方法で共有状態の解消を目指しましょう。