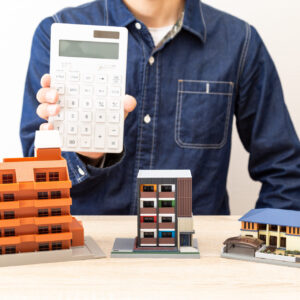共有不動産を複数人で所有している中で、共有者の一人が自分の持分の一部だけを他人に譲渡したいというケースでは、「他の共有者の同意が必要なのか」「登記はどうすればいいのか」といった実務的な問題が発生します。
その際に重要となるのが「共有持分の一部移転登記」です。共有持分の一部移転登記とは、共有者が持つ持分の“中の一部”を別の人に移すための手続きで、売買や贈与などが原因となることが一般的です。
この登記手続きは、一般的な所有権移転登記や相続登記とは異なる独自の注意点があり、誤った方法で進めると、後のトラブルの原因になりかねません。
そこで本記事では、共有持分の一部移転登記の基本から、手続きの流れ、他の登記との違い、リスクと代替手段までを実務に即して解説します。
目次
共有持分の一部移転登記とは
共有持分の一部移転登記とは、不動産を複数人で共有している場合に、そのうちの一人の「持分の一部だけ」を別の人に譲渡する際に行う登記のことを指します。例えば、ある土地を兄弟2人で2分の1ずつ共有している状態で、兄の持分のうち4分の1だけを弟に渡す場合、この手続きが必要になります。
通常の所有権移転登記が「不動産全体の所有権を移す」のに対し、この登記では「持分の中の一部のみ」を対象とする点が大きな特徴です。
つまり、不動産の権利関係を一部だけ変えるという極めて限定的な移転であり、非常に繊細な対応が求められます。
一部移転登記の定義と必要性
一部移転登記とは、登記簿上で共有者が有する持分のうち、その一部だけを他人に移転することを記録する手続きです。この登記を行うことで、誰がどれだけの割合の権利を持っているかを明示し、不動産の法的な所有関係を正確に示すことができます。
この手続きが必要になる主な理由は、以下のようなケースです:
- 相続人の一部が持分を他の相続人にまとめたいと考える場合
- 共有者同士で持分割合の見直しをしたい場合
- 特定の共有者にだけ経済的利益を移したい場合(例:贈与)
また、法的には持分の一部でも第三者に譲渡することは可能であり、登記をしておかないと、その権利移転は対外的に主張できません。万が一トラブルが発生した際、「口約束」や「契約書」だけでは不十分で、登記簿に反映されていなければ、第三者に対して自らの権利を主張できないのです。
そのため、たとえ少額の取引であっても、一部移転登記を行っておくことは、後々の紛争予防にもつながります。
実際、共有不動産をめぐるトラブルの多くは「誰がどれだけの権利を持っているのか」が曖昧なまま放置されてきた結果として起こっているのです。
一部移転登記とその他の移転登記との違い
一口に不動産の移転登記といっても、その内容や目的は大きく異なります。中でも「一部移転登記」は、共有状態の中で特定の共有者が持つ“持分の一部だけ”を移すという、かなり限定的で繊細な手続きです。
それに対し、持分をすべて移す場合や、相続・贈与などを原因とする登記では、対象となる権利や法的な背景がまったく異なります。
一部移転登記を検討している方の多くは、「ほかの登記とどう違うのか」「自分のケースにはどれが適しているのか」といった疑問を持っているはずです。以下では、代表的な三つの登記との違いについて詳しく見ていきます。
持分全部移転登記との違い
持分全部移転登記は、その名のとおり、共有者が保有する持分すべてを第三者や他の共有者に移すための登記です。
登記完了後には、元の共有者の名前は登記簿から完全に消え、新たな所有者がその持分全体を引き継ぐことになります。
これに対して一部移転登記では、持分の“ごく一部”だけが移転され、元の共有者も引き続き登記簿上に残ります。
例えば、4分の1の持分を持つ共有者が、その中の8分の1だけを他人に渡すようなケースがそれに該当します。このように、両者では登記後の権利構造に大きな違いがあります。
相続による移転登記との違い
相続による移転登記は、被相続人の死亡を原因として、その不動産の権利が相続人に移ることを登記簿に反映する手続きです。
基本的には、法定相続分や遺産分割協議に基づいて、登記名義を相続人へ移します。
一方、一部移転登記は生前の契約や意志によって行われる任意の登記であり、相続のような不可抗力的な要因とは性質が異なります。
また、相続登記は被相続人の全財産をめぐる広範な権利移動の一部であることが多いのに対し、一部移転登記は特定の不動産・特定の持分だけを対象とする限定的な手続きです。
贈与による単独移転登記との違い
贈与による単独移転登記は、ある人が自己の不動産全体(または共有持分全体)を他人に無償で譲り渡す場合に行う登記です。
典型的なのは、親が子に自宅を贈与するようなケースで、贈与契約書と登録免許税の納付をもって登記がなされます。
これに対して一部移転登記では、「共有者の持分の一部だけを贈与する」という点で複雑性が増します。持分の一部を第三者に贈与すること自体は可能ですが、他の共有者の意向や今後の管理・利用計画にも影響が及ぶため、より慎重な対応が求められます。
共有持分の一部移転登記を行うメリット
不動産の共有は、相続や贈与の過程で発生することが多く、当初は問題がなくとも、年月が経つとともに管理や売却の意思決定が複雑化することがあります。そうした事態を防ぐためにも、一部移転登記は柔軟な調整手段として機能します。
例えば、次の2つのメリットが代表的です。
- 相続税対策ができる
- 持分割合の調整ができる
それぞれ個別に解説します。
相続税対策ができる
共有持分の一部を早い段階で子や孫に贈与することで、相続時にかかる相続税の圧縮につながる可能性があります。
これは「生前贈与」の一形態として活用されるケースで、課税対象となる財産を少しずつ分けていくことで、各年度の基礎控除を活かしながら負担を軽減できます。
例えば、評価額2,000万円の土地を全額相続させる場合と、毎年数百万円ずつ贈与して持分を移していく場合とでは、課税対象や税率に差が出ることがあります。
もちろん贈与税の課税にも注意は必要ですが、節税効果を得やすいのは分割して贈与する方法です。このような計画的な一部移転登記は、長期的な相続設計の一環としても有効。
相続発生後に慌てることなく、家族間であらかじめ財産を整理しておける点でも、実務的なメリットは大きいといえるでしょう。
持分割合の調整ができる
共有者の間で持分のバランスが悪い場合、例えば「実際に管理している人がごく一部しか持分を持っていない」といった状況は珍しくありません。そうしたケースでは、一部移転登記を用いて適正な割合に調整することが可能です。
これは特に、相続によって「法定相続分どおり」に共有が始まった場合に有効です。相続時には平等に分けたつもりでも、後になって一人が固定資産税を支払っていたり、リフォーム費用を負担していたりすると、不公平感が生まれることがあります。
そのようなときに、負担に応じた形で持分を調整すれば、納得感のある共有関係に改めることができます。
このような持分の調整は、後々の売却や管理・処分時の意思決定にも良い影響を与えます。明確な役割と権利の分担があってこそ、共有不動産は円滑に機能するといえるでしょう。
共有持分の一部移転登記の具体的な方法
一部移転登記は、法的には単純に見えても、実際にどうやって行うかが分かりづらい手続きの一つです。
特に、売買と贈与という2つの代表的な方法によって、手続きの流れや必要書類が異なる点に注意が必要です。
ここでは、「どのような場面でどの方法を選ぶべきか」といった視点も踏まえながら、それぞれの方法について詳しくみていきましょう。
売買による持分の一部移転
売買による一部移転は、金銭のやり取りを伴う正規の取引として行われるため、契約書の作成や売買価格の設定が重要になります。一般的には、共有者間で行われることが多く、例えば親族間で持分を買い取るなどの形で活用されます。
この場合、必要書類としては以下のようなものがあります。
- 売買契約書
- 登記原因証明情報(契約の内容を証明する文書)
- 登記申請書
- 登記識別情報(旧権利証)または本人確認書類
- 固定資産評価証明書
また、売買が成立すれば、通常の所有権移転と同様に課税対象となり、登録免許税や不動産取得税が発生することがあります。金額が小さい場合でも、法的には通常の売買と同じ扱いになるため、しっかりと準備することが求められます。
贈与による持分の一部移転
贈与による移転は、金銭の対価を伴わずに無償で権利を移す方法です。家族間でよく使われる方法で、例えば親が子に対して持分の一部を贈与するなど、将来的な資産承継を見据えた対応として選ばれることが一般的です。
必要書類は、売買と似ていますが、登記原因証明情報として贈与契約書が必要になります。形式的には次のような書類が求められます。
- 贈与契約書
- 登記申請書
- 登記識別情報または本人確認書類
- 固定資産評価証明書
なお、贈与税が課税される場合があるため、受贈者側の課税関係も確認しておく必要があります。贈与額が110万円を超える場合は贈与税申告が必要になるため、事前に税理士などに相談するのが望ましいでしょう。
共有持分の一部移転登記の手続きの流れ
共有持分の一部を売買や贈与によって移転する場合、その内容を登記簿に反映させる「一部移転登記」が必要になります。
登記は、不動産の権利関係を第三者に対して公的に主張できる唯一の手段であり、正確かつ適切に行うことが求められます。
とはいえ、登記手続きには専門的な知識が必要な場面もあり、初めての方にとっては戸惑う部分も少なくありません。ここでは、一部移転登記を自分で進める際に必要な基本的な5つのステップを順を追って紹介します。
- 手順①:必要書類を準備する
- 手順②:登記申請書を作成する
- 手順③:法務局へ申請する
- 手順④:登録免許税を納付する
- 手順⑤:登記完了後の確認をする
売買・贈与いずれの場合でも共通する流れを中心に解説していますので、全体像の把握にお役立てください。
手順①:必要書類を準備する
まず最初に行うべきは、登記に必要な書類の準備です。一部移転登記では、不動産の所在地や取引内容にかかわらず、以下のような書類が基本的に必要となります。
| 書類名 | 内容 |
| 登記申請書 | 登記の目的や理由、当事者情報などを記載 |
| 登記原因証明情報 | 売買契約書・贈与契約書など、権利移転の原因を示す書類 |
| 登記識別情報 | 売主または贈与者の権利証に相当する情報 |
| 印鑑証明書 | 当事者双方の実印を証明(3ヶ月以内) |
| 固定資産評価証明書 | 登録免許税の算出に使用 |
| 住民票または戸籍附票 | 住所や氏名に変更がある場合に必要 |
書類に不備があると、登記が受理されず差し戻しになることもあります。特に契約書の不備や印鑑証明の期限切れなどはよくあるミスなので、細部まで確認しておきましょう。
手順②:登記申請書を作成する
必要書類をそろえたら、次に登記申請書を作成します。これは法務局に提出する最も重要な書類のひとつで、誰がどんな目的で登記を行うのかを明記する必要があります。
登記申請書には以下のような情報を記載します。
- 不動産の表示(地番、家屋番号など)
- 登記の目的(一部移転登記)
- 原因とその日付(売買・贈与などとその日付)
- 移転する持分の割合(例:3分の1のうち6分の1 など)
- 当事者の氏名・住所
- 添付書類の一覧
フォーマット自体は法務局のウェブサイトや窓口で入手できますが、内容に誤りがあると受理されない可能性があるため、記載例を参考にしながら丁寧に作成しましょう。不安がある場合は、登記相談窓口や司法書士にチェックを依頼するのも一つの方法です。
手順③:法務局へ申請する
申請書と添付書類を揃えたら、管轄の法務局へ提出します。不動産が所在する土地の管轄法務局に出向く必要があり、郵送でも受付は可能です。受付時間や混雑状況を事前に調べておくとスムーズです。
提出の際には、以下の点にも注意してください。
- 書類に不足がないか
- 印紙の貼り忘れがないか
- 本人確認書類が適切か
なお、窓口提出の場合は、その場で簡易な内容確認をしてくれることが多く、初めての方には安心です。提出後は「受付票」が渡され、登記完了予定日が記載されます。通常は1〜2週間程度で処理されますが、繁忙期や補正がある場合はさらに時間がかかることもあります。
手順④:登録免許税を納付する
一部移転登記を行う際には、登録免許税の納付が必要です。
税額は、移転対象となる不動産の「固定資産評価額」に移転持分の割合をかけた金額に、所定の税率(通常2%)をかけて算出されます。
【計算式の例】
固定資産評価額:1,000万円
移転持分:2分の1 → 500万円相当
税率:2%
→ 登録免許税:10万円
この税額は、登記申請書に貼り付ける「収入印紙」によって納付します。印紙は法務局や郵便局、法務局近くの売店などで購入可能です。なお、税額計算を誤ると登記が受理されないことがあるため、評価証明書に基づいて正確に計算しましょう。
(参考:国税庁「登録免許税の税額表」)
手順⑤:登記完了後の確認をする
登記が完了すると、法務局から「登記完了通知」が届きます。これを受け取った後は、登記内容が正しく反映されているかを登記簿で確認しましょう。オンラインの登記情報提供サービスや、法務局窓口での登記事項証明書の取得によって確認可能です。
確認するポイントは以下のとおりです。
- 所有者欄に新しい共有者が追加されているか
- 移転した持分割合が正確に記載されているか
- その他の登記情報に誤りがないか
また、登記識別情報(いわゆる「新しい権利証」)は、新たに共有者となった人に対して交付されます。これは今後売却やさらに登記を行う際に必要となる重要書類ですので、紛失しないよう保管してください。
一連の確認を終えることで、ようやく登記手続きが正式に完了したといえます。
共有持分の一部移転登記を行うリスクとは?
一部移転登記は法的に可能な手続きである一方で、実行にあたっては一定の注意が必要です。
権利関係がさらに複雑になったり、他の共有者との摩擦を生むなど、結果として状況を悪化させてしまうこともあります。
実務上よくみられるリスクとしては以下のとおりです。
- 共有者との関係が悪化することがある
- 持分だけを買い取る人が見つかりにくい
- 売却後の不動産の管理が難しくなる
それぞれ個別にみていきましょう。
共有者との関係が悪化することがある
共有持分の一部を他人に譲渡することで、既存の共有者との信頼関係が損なわれる可能性があります。
特に、譲渡先がまったくの第三者だった場合、「なぜ相談なしに他人と共有することになったのか」といった感情的な対立が起こりやすくなります。
共有者の一人が意図せず新たな共有者と関わることになることで、話し合いの場に緊張が走り、物件の利用や将来的な売却方針にも支障が出かねません。
持分の一部であっても、他の共有者にとっては「知らない人と土地や建物を共同で所有する」という大きな心理的ハードルとなります。
そのため、譲渡を検討する際には、事前に他の共有者へ説明をし、理解を得る姿勢が極めて重要です。対話を怠ったことで関係が壊れ、解決が長期化するケースも少なくありません。
持分だけを買い取る人が見つかりにくい
不動産の通常の売却と異なり、「持分だけ」の不動産を購入する人は非常に限られています。例えば、3分の1の持分を譲渡しようとしても、購入後すぐに単独で住めるわけでも、自由に売却できるわけでもありません。
不動産の持分は、あくまでも「全体に対する権利の割合」であり、物理的に特定の区画を独占できるわけではないため、使い勝手が悪く、一般の投資家や居住希望者には敬遠されがちです。
そのため、実際に持分を売却しようとしても、買い手が見つからない、あるいは著しく低い価格での売却を余儀なくされるということもあり得ます。持分売却を進めるのであれば、市場価値や売却可能性を冷静に見極めたうえで、慎重に判断する必要があります。
売却後の不動産の管理が難しくなる
持分を一部譲渡した後も、残された共有者が不動産の管理を続けていくことになります。この際、新たな共有者との関係性が不安定である場合、日常的な意思決定が難しい状態に陥ります。
例えば、建物の修繕や固定資産税の負担、入居者の募集など、実務的な判断を共有者全員で行う必要がある状況で、価値観やスタンスが異なる相手と意見を一致させるのは簡単ではありません。
特に、譲渡先が投資目的の第三者であった場合、「費用は出したくないが利益は受け取りたい」といった立場をとることもあり、実質的に管理業務が立ち行かなくなるおそれもあります。共有関係の継続には、信頼関係だけでなく、意思疎通の土台が不可欠です。
共有持分の一部移転登記を避けるべきケース
共有持分の一部を譲渡できるからといって、すべてのケースで実行すべきとは限りません。むしろ、その選択が問題を複雑化させてしまう場合もあります。
例えば、以下のようなケースでは一部移転登記ではなく、他の手段を検討すべきです。
- ケース①:持分の放棄を検討する場合
- ケース②:共有名義の解消を希望する場合
それぞれ個別に解説します。
ケース①:持分の放棄を検討する場合
不動産を所有しているだけで、経済的な負担(例:固定資産税、管理費)が生じているケースでは、「持分を売る」よりも「放棄する」ほうが合理的なこともあります。
特に、地方にある利用価値の低い土地などでは、買い手がつかない一方で、持っているだけで維持費がかさむといった状況も少なくありません。
このような場合、一部移転登記を行っても現実的な解決にはつながらず、むしろ手間や費用だけがかかってしまいます。相手が見つからず登記もできないという悪循環を防ぐためにも、「不動産を手放す」という判断を検討すべき場面もあるのです。
なお、持分の放棄は一定の条件下で成立しますが、他の共有者の同意や手続き上の配慮も必要となるため、実行前に専門家への相談が望まれます。
ケース②:共有名義の解消を希望する場合
そもそも共有状態そのものを終わらせたいと考えている場合には、一部の持分を移転するのではなく、「共有名義を解消する」方向で検討すべきです。
例えば、他の共有者の持分をすべて買い取って単独所有とする、あるいは共有物分割請求によって不動産を売却し、代金を分け合うといった方法が考えられます。
一部移転登記はあくまで「共有状態を前提としたままの持分調整」に過ぎず、根本的な問題の解決にはなりにくいのが実情です。
将来的に売却やリフォーム、賃貸活用を視野に入れている場合、共有状態を維持すること自体が足かせになるケースもあります。
共有持分の問題を解決する代替手段
共有不動産は、複数人が権利を持つことで意思決定が難しくなり、利用や処分に関するトラブルを引き起こしやすい資産です。共有者の一部が売却に反対していたり、管理費の負担に差があったりすると、実質的には身動きが取れなくなることもあります。
こうした状況で「一部移転登記」を行って共有関係の調整を試みることは一つの方法ですが、そもそも共有状態自体を解消したい、あるいは関係を断ち切りたいというニーズも多く見られます。
そこで、共有状態を根本的に見直すための3つの実践的な代替手段をご紹介します。
- 持分の全部移転による単独所有化
- 共有物分割請求による解消
- 専門業者への持分売却
持分の全部移転による単独所有化
もっともシンプルで根本的な解決策は、他の共有者が持つ持分をすべて取得し、自分ひとりで単独所有にする方法です。
この場合、他の共有者と合意して売買や贈与などの形で持分を譲り受け、登記を「持分全部移転登記」として行います。
単独所有になることで、不動産の利用・処分に関する全権限を持てるようになります。
例えば売却やリフォーム、賃貸なども自分の判断だけで進められ、他の共有者に説明・同意を求める必要がなくなるため、将来のトラブルを大幅に軽減できます。
共有物分割請求による解消
共有者間で話し合いがまとまらない場合、最終手段として「共有物分割請求」という法的手段を取ることができます。これは民法に定められた制度で、共有関係を解消したい共有者が裁判所に申し立てを行い、強制的に不動産の分割処分を図るものです。
分割の方法には主に以下の3種類があります。
| 分割方法 | 内容 | 特徴 |
| 現物分割 | 土地や建物を物理的に分けて単独所有にする | 実務上は困難なことが多い |
| 換価分割 | 不動産を競売または売却して代金を分ける | 裁判所が選択しやすい |
| 代償分割 | ある共有者が物件を取得し、他の共有者に代償金を支払う | 当事者の資力と合意が前提 |
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)
代償分割は、実際には「不動産を欲しい人が買い取り、他の共有者には代金で応じる」という柔軟な形で、共有状態を一気に解消できるメリットがあります。ただし、代償金を支払う側の資力や意思が必要であり、共有者全員の合意が得られるケースでないと実現は難しい点もあります。
専門業者への持分売却
共有関係を自ら解消するのが難しい場合は、自分の持分を第三者、特に「共有持分の買取を専門とする業者」へ売却するという方法もあります。
こうした業者は、共有状態にある不動産でも価値を見出し、将来的な買取や権利調整を見越して買い取ってくれる存在です。
通常の不動産市場では、持分だけの売却は買い手が見つかりにくいため、売却価格が大きく下がる傾向にあります。
しかし専門業者は、共有状態の処理ノウハウを持っているため、相場に近い価格での買い取りやスピード感のある手続きが可能です。
この手段は「早期に現金化したい」「共有関係から早く抜けたい」と考える人にとって、精神的にも経済的にも大きなメリットがあります。
ただし、買い取り後に他の共有者との関係に影響が出ることもあるため、事前に説明や調整をしておくとトラブルを避けやすくなります。
共有持分も「ワケガイ」なら煩雑な手続きなしで現金化が可能です!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や再建築不可、空き家などの“訳あり物件”を専門に取り扱う不動産買取サービス「ワケガイ」を提供しています。 共有不動産の一部だけを手放したいと考えても、通常の不動産会社では取り扱いを断られるケースがほとんどです。特に持分だけの売却は、買主を見つけにくく、交渉や契約が思うように進まないことが多くあります。
ワケガイでは、共有者全員の同意がそろっていなくても、単独での売却に対応可能です。司法書士や弁護士と連携し、複雑な登記や調整も当社が代行いたしますので、スムーズかつ安心してご相談いただけます。共有状態にお悩みの方は、お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
共有不動産を巡る問題は、当事者の関係性や物件の活用方針によって非常に複雑になります。中でも、一部だけの持分移転は、権利関係が細分化されることで、管理や売却の判断が一層困難になるリスクをはらんでいます。
そのため、登記による権利の明確化だけでなく、「本当に共有状態を続けるべきか」という視点も含めて、根本的な解決策を検討することが重要です。
持分調整や単独所有化、共有物分割、さらには専門業者への売却といった複数の選択肢を視野に入れ、自身の状況に適した現実的な対処を進めましょう。