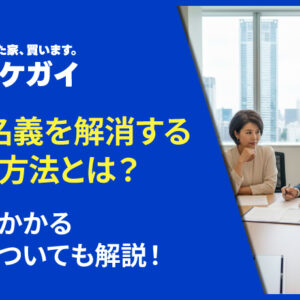こんにちは。ワケガイ編集部です。
親子で住宅を購入する際、資金面の理由から共有名義にするケースは少なくありません。しかし親が亡くなったときには、相続人間での持分処理が複雑になり、相続登記や税金、売却の同意などで思わぬトラブルが生じることがあります。
その際に重要となるのが「親子共有名義の仕組みと相続への影響」です。親子共有名義とは、親と子がそれぞれ不動産の権利を持ち合う形態のこと。正しく理解していないと、相続時に大きな混乱を招く恐れがあります。
そこで本記事では、親子共有名義のメリット・デメリット、親が死亡した場合の相続手続き、必要な書類や費用、さらには生前にできる対策までを詳しく解説します。
目次
親子共有名義とは?
親子で不動産を購入する場合、登記の名義をどのようにするかは大きな検討事項です。そのなかでよく利用される形態のひとつが「共有名義」です。
単独所有とは異なり、親子で共同出資した場合や、贈与税の課税を避けたり住宅ローン控除を利用するために持分を分ける場合に、共有名義が選ばれることがあります。
ただし共有名義のままでは「相続の際に持分が細分化して処分が難しくなる」「売却時に共有者全員の同意が必要になる」など、実務上の負担が増えかねません。
そこで、まずは共有名義の仕組みと持分割合の考え方を整理していきましょう。
共有名義の仕組みと持分割合
共有名義では、不動産の権利を「持分」という形で分割し、各人がその割合に応じた権利を持ちます。購入代金の半分を親が負担し、残りを子が負担した場合には、それぞれ2分の1ずつの持分が登記されるのが一般的です。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)
持分割合は出資額に応じて決められるのが原則であり、登記簿謄本にも明確に記載されます。
この仕組みは公平である一方、持分の扱いには制約が発生します。不動産を売却する際には原則として共有者全員の同意が必要になりますし、リフォームや担保設定なども同様です。
単独所有であれば自由にできる行為も、共有名義では他の持分権者の合意を得なければ進められません。
したがって「誰がどれだけの負担をしたのか」を明確にしておくだけでなく、将来の利用や処分の場面で足並みが揃うかどうかも考えておく必要があります。
関連記事:共有持分の不動産を売却する方法とは?売却費用やよくあるトラブルを紹介!
親子共有名義が選ばれる背景(住宅ローン・贈与税対策など)
親子で共有名義にする大きな理由のひとつは、住宅ローンの利用です。子どもだけでは借入額が不足する場合に、親と収入を合算してローンを組む「ペアローン」や「収入合算型ローン」があります。
このとき、融資の条件として親子双方の名義を登記するよう求められるケースも存在します。単独では実現できない住宅取得を可能にする手段として、多くの家庭で採用されています。
もうひとつの要因は「節税」です。
実際、親が全額を負担して子ども名義で登記を行うと、贈与とみなされ高額な贈与税が課される場合があります。そこで、実際に負担した金額に応じて持分を設定することで「不自然な名義移転ではない」と税務署に説明でき、贈与税を避けやすくなるのです。
親が資金援助を行いつつも贈与と判定されないようにする工夫として、共有名義が選ばれるケースは多々あります。
このように、共有名義は住宅ローンや税金の観点から合理的に思える面があるものの、相続や処分の段階では大きな課題を抱えやすいため、事前にデメリットも理解しておきましょう。
関連記事:親子の共有名義で住宅購入はあり?メリットや注意点を解説
親子共有名義で親が死亡した際に必要になる書類
親子で共有していた不動産を相続する際には、登記や協議を行うためにさまざまな公的書類を揃える必要があります。
特に相続登記では、誰が相続人であるか、どのような経緯でその地位を承継するのかを証明できなければ、法務局に申請しても受理されません。
ここからは、相続手続きにおいて基本となる戸籍関係の書類について取り上げます。
- 被相続人(亡くなった親)の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票・印鑑証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印付き)
- 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
それぞれ個別にみていきましょう。
被相続人(亡くなった親)の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
まず必要となるのが、亡くなった親の戸籍をすべて揃えることです。戸籍謄本は、亡くなった時点での親の身分関係を示す書類で、死亡の事実を証明する資料となります。
しかし、それだけでは不十分であり、親の出生から死亡までの戸籍を一貫して確認できるようにしなければなりません。
本籍地を移した場合や婚姻・転籍をした場合には、古い戸籍が除籍謄本や改製原戸籍として残っています。これらをすべて収集しなければ、相続人を確定することができません。
実務上は、法務局で相続登記を申請する際に「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍一式」が求められます。つまり途中が抜け落ちていると、相続人を網羅できないと判断され、申請が却下される可能性があります。
相続人全員の戸籍謄本
次に必要なのが、相続人全員の戸籍謄本です。これは「誰が法定相続人なのか」を証明するために不可欠な資料です。被相続人の戸籍で相続人の候補を確認した上で、それぞれの相続人について戸籍謄本を取得し、親子関係や配偶者関係を裏付けます。
もし、子どもが結婚して別の戸籍に移っているなら、その新しい戸籍謄本を用意する必要があります。
相続人全員の戸籍謄本を揃えることで、法務局や金融機関に対して「相続人の範囲に漏れがない」ことを示せます。これは遺産分割協議を進める際にも重要で、後に「相続人の一人が協議に参加していなかった」と判明すると、協議自体が無効になる恐れがあります。
したがって、最初の段階で戸籍を正確に収集しておくことが、その後の手続きを円滑に進める上では必須です。
相続人全員の住民票・印鑑証明書
相続登記の手続きを進める上で、相続人全員の住民票と印鑑証明書も必要になります。住民票は、現在の住所を証明する役割を果たし、登記簿へ記載する際の情報源となります。
法務局では、登記簿に相続人の正確な住所を記載するため、この書類を提出しなければなりません。
一方、印鑑証明書は遺産分割協議書に押印した印鑑が、確かに本人の実印であることを証明するために求められます。
遺産分割協議は相続人全員が参加して成立するものですが、協議書に記載されている合意内容が本当に当人の意思に基づいたものかどうかを、第三者である法務局が形式的に確認する必要があります。その際に活用されるのが印鑑証明書です。
これらの書類は、住民票が市区町村役場で取得できるのに対し、印鑑証明書は事前に印鑑登録をしていないと発行してもらえません。
遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印付き)
親子共有名義の不動産を相続するとき、相続人の間で誰がどの持分を取得するかを決める必要があります。その合意内容を文書化したものが遺産分割協議書です。この協議書がなければ、相続登記を申請することはできません。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。誰か一人でも欠けてしまうと効力が認められず、登記手続きが進められません。特に親子共有名義のケースでは、亡くなった親の持分を誰が引き継ぐのかをはっきりさせる必要があります。
遺産分割においては「子どもの一人がすべてを相続するのか」「兄弟姉妹で分けるのか」といった点を協議し、明文化しておかなければ不動産の権利関係は確定しません。
不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
不動産の権利関係や価値を明確にするために、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書の取得も必要です。
登記事項証明書は法務局で入手できるもので、その不動産の所在地、地番、所有者、持分割合、抵当権の有無などが記載されています。相続登記を申請する際には、対象となる不動産がどのような状態にあるかを確認するため、提出が求められます。
固定資産評価証明書は、市区町村が発行するもので、その不動産の課税標準額が記載されています。
これは登録免許税を計算する基礎資料として使われるため、登記申請の際に必ず必要となります。課税標準額は固定資産税の算定にも用いられているため、相続後に納税義務を引き継ぐ上でも参考になる情報です。
両者はそれぞれ役割が異なるものの、相続登記ではセットで提出を求められるのが一般的です。
特に共有名義の不動産では、登記事項証明書によって誰がどの程度の権利を持っているかが明らかになり、固定資産評価証明書によってその価値を基準に費用を計算することができます。
親子共有名義で親が死亡した場合の相続の手順
親子で共有していた不動産を相続する際には、決まった流れに沿って手続きを進める必要があります。具体的には、以下の5ステップです。
- 手順①:死亡の事実を証明する戸籍謄本を取得する
- 手順②:相続人を確認する
- 手順③:遺産分割協議を行う
- 手順④:相続登記を申請する
- 手順⑤:税務申告や納税を行う
次項より、個別にみていきましょう。
手順①:死亡の事実を証明する戸籍謄本を取得する
相続手続きの起点となるのは、被相続人である親の死亡を公式に証明することです。法務局や金融機関では、単に死亡届を提出しただけでは足りず、戸籍謄本を通じて法律上の事実を確認します。
実際には「死亡の記載がある戸籍」だけでは不十分で、出生から死亡まで連続した戸籍を揃えることが求められます。
本籍を移している場合、古い戸籍が「除籍謄本」や「改製原戸籍」として残っています。これらもすべて収集することで、相続人の範囲を正しく示せるようになります。途中の戸籍が抜けていると、相続人の一部を把握できない恐れがあり、法務局では登記申請を受理しないのが通常です。
手順②:相続人を確認する
戸籍を揃えたら、次に行うのは相続人の確定です。相続人が誰であるかを明らかにしない限り、その後の遺産分割協議や登記は進められません。民法では、配偶者は常に相続人となり、子ども、直系尊属、兄弟姉妹といった順序で範囲が定められています。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)
相続人を確定する作業では、被相続人の戸籍だけでなく、相続人それぞれの戸籍謄本も必要です。これによって親子関係や婚姻関係が証明され、相続人としての地位が裏付けられます。
注意が必要なのは、過去に認知した子や、前婚の子どもがいる場合です。被相続人の出生から死亡までの戸籍を丁寧に確認することで、そうした存在も明らかになります。
手順③:遺産分割協議を行う
相続人が確定したら、次に進めるのは遺産分割協議です。これは、不動産を含めた遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合う手続きです。親子共有名義の不動産では、亡くなった親の持分を誰が引き継ぐのかを決めることが大きな焦点となります。
兄弟の一人が引き継ぐのか、複数人で新たに共有するのか、あるいは売却して現金で分けるのか。選択肢はいくつかありますが、いずれにしても相続人全員の合意がなければ有効な協議とはなりません。
協議の内容は「遺産分割協議書」として文書化し、全員が署名・押印します。これが後の相続登記に必要となるだけでなく、後日トラブルが起きたときの証拠にもなります。
注意すべきは、一人でも合意しない相続人がいれば協議は成立せず、家庭裁判所で調停や審判を求めるしかないという点です。共有名義の不動産は権利関係が複雑なため、協議が長引きやすいのが実情です。
手順④:相続登記を申請する
遺産分割協議がまとまったら、次は不動産の名義を変更する相続登記を行います。登記簿の所有者欄に亡くなった親の名前が残ったままでは、売却や担保設定などの取引は一切できません。
相続登記は2024年4月から義務化されており、原則として相続発生から3年以内に申請しなければならなくなりました。期限を過ぎると過料の対象となる可能性があるため、協議が整ったら速やかに登記を済ませることが大切です。
(参考:東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)」)
申請にあたっては、遺産分割協議書や戸籍謄本一式、固定資産評価証明書などを添付し、法務局に提出します。手続きを司法書士に依頼する人も多く、専門家を通せば必要書類の確認や記載内容の誤りを防ぐことができます。
手順⑤:税務申告や納税を行う
相続登記と並行して確認すべきなのが税務上の手続きです。相続税が発生する場合、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を行わなければなりません。
(参考:国税庁「相続税の申告と納税」)
基礎控除の範囲内であれば申告不要ですが、都市部の不動産など評価額が高い場合には課税対象となることもあります。さらに、不動産を売却して現金化する場合は譲渡所得税がかかりかねないのです。
相続で取得した不動産をすぐ売却するケースでは、取得費加算の特例などを活用できるため、節税効果を得られることがあります。
名義人の親が死亡した場合の不動産相続で発生する費用
親子共有名義の不動産を相続する際には、一般的な相続に共通する税金のほか、このケース特有の負担が加わることがあります。具体的には、以下のものが挙げられます。
- 相続税
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 固定資産税・都市計画税
- 司法書士報酬
- 税理士報酬
- 遺産分割協議書の作成費用
- 不動産鑑定費用
- その他の実務費用
特に注意すべきは税金関係で、手続きの順序を間違えると余分なコストが生じかねないため、きちんと把握しておきましょう。
相続税
親の持分が相続財産となるため、その評価額が基礎控除を超える場合には相続税が発生します。不動産の評価額は「相続税評価額」に基づいて算出され、路線価や固定資産税評価額を参考に決まります。
(参考:国税庁「相続税の税率」)
共有名義のケースでは、被相続人の持分割合に応じた金額が課税対象となります。
仮に、2分の1を親が所有していた場合、その半分の評価額が相続財産として加算されます。相続税は現金一括納付が原則のため、不動産のまま相続すると納税資金の確保が課題となりやすい点に注意が必要です。
延納や物納といった制度もありますが、利用条件は厳格ですので、早めに納税計画を立てておくことが求められます。
登録免許税
相続登記を行う際には登録免許税がかかります。税額は「不動産の固定資産税評価額×0.4%」が基本です。共有名義の一部を承継する場合でも、亡くなった親の持分に対して課税されるため、登記を避けることはできません。
(参考:国税庁「登録免許税の税額表」)
例えば、固定資産税評価額が2,000万円で、親の持分が2分の1だった場合、その1,000万円に0.4%を掛けた4万円が登録免許税となります。相続人が複数いるときには、相続人の数にかかわらず合計でこの額を負担することになります。
司法書士に依頼する場合は報酬も必要となるため、実際の負担額はさらに大きくなる点を念頭に置いておくべきでしょう。
不動産取得税
相続そのものには不動産取得税はかかりません。ただし、共有名義を整理する過程で贈与や売買を用いた場合には課税される可能性があります。
「親の持分を生前贈与して子が単独名義にしていた」「相続発生後に兄弟間で売買契約を結んで名義を移した」といったケースなどが該当します。
不動産取得税は固定資産税評価額に原則4%を乗じて計算されます(住宅用の場合は特例で3%)。高額になることもあるため、「相続では非課税だが整理の方法によっては課税される」と認識しておきましょう。
(参考:総務省「不動産取得税」)
結果的にどの手段を取るかで税負担が大きく変わるため、事前にシミュレーションを行うことが望まれます。
固定資産税・都市計画税
不動産を所有している限り、毎年の固定資産税や都市計画税は相続人に引き継がれます。納税通知書は市区町村から送付され、通常は年4回の分納または一括納付で支払います。相続した不動産が空き家のまま放置されている場合でも課税は続くため、維持管理ができない物件は思わぬ負担になることがあります。
さらに「特定空き家」と認定されると固定資産税の軽減措置が外れ、税額が数倍に跳ね上がるリスクだって存在します。利用予定がない不動産をそのまま相続すると、将来的な税負担が重くのしかかるため、早い段階で活用方法や処分を検討しておく必要があります。
(参考:国土交通省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」)
司法書士報酬
相続登記は個人でも申請できますが、必要書類の収集や記載方法が複雑で、誤りがあると法務局から補正を求められます。
そのため、多くの人が司法書士に依頼しています。司法書士報酬は案件の難易度や不動産の数によって変動しますが、相続登記1件あたり数万円から十数万円が相場です。
親子共有名義の場合、複数の持分や相続人が絡むため、単独名義の登記よりも手間が増えやすく、費用が高めになることもあります。安心して進めたい場合には、専門家に依頼する費用も含めてあらかじめ予算を考えておくとよいでしょう。
税理士報酬
相続税の申告が必要な場合、税理士への依頼が現実的な選択肢になります。相続税の計算は不動産評価や特例の適用可否など判断が難しく、自己判断では過大申告や申告漏れのリスクが高まります。
税理士報酬は申告の有無や遺産の規模によって異なり、数十万円規模になる可能性だってあります。特に不動産を含む相続は評価の方法によって税額が大きく変わるため、専門知識を持つ税理士に任せる価値は高いといえます。
費用はかかりますが、結果的に節税につながるケースもあるため、単なるコストではなくリスク回避の投資として考えるべきでしょう。
遺産分割協議書の作成費用
遺産分割協議書は自分たちで作成することも可能ですが、書式や記載内容に不備があると法務局で受理されない場合があります。そのため、司法書士や行政書士に作成を依頼するのが安全といえます。
費用は依頼先や内容の複雑さによって異なりますが、数万円程度が一般的です。親子共有名義の不動産は持分の扱いを明確にしなければならず、兄弟姉妹が複数いる場合には記載内容が複雑化しやすいのが特徴です。
適切に作成された協議書は後のトラブル防止にも役立つため、必要に応じて専門家の力を借りるのが無難です。
不動産鑑定費用
不動産の正確な評価が必要になる場合には、不動産鑑定士に依頼することがあります。特に、遺産分割協議で「持分の価値」を現金換算する必要があるときや、税務上の評価額に納得できないときに鑑定が活用されます。
鑑定費用は物件の規模や用途によって幅がありますが、数十万円程度になってしまいます。
親子共有名義では持分の評価が問題となることが多いため、鑑定費用が発生しやすい点が特徴です。公平な分割や円滑な協議のために必要な出費と位置づけられます。
その他の実務費用
相続手続きでは、印紙代や郵送費、各種証明書の発行手数料といった細かな実費もかかります。戸籍謄本や住民票は1通数百円程度ですが、出生から死亡までの戸籍をすべて揃えると数千円から1万円以上になることもあります。また、固定資産評価証明書や登記事項証明書も取得のたびに手数料が必要です。
こうした費用はひとつひとつは小額ですが、全体として積み重なれば一定の負担になります。大きな税金や専門家報酬に目が行きがちですが、こうした実務的な支出も見込んでおくと、予算の見積もりに狂いが生じにくくなります。
親が存命の内にできる共有名義不動産の相続対策
親子で共有している不動産は、一見便利に思えても、相続が発生すると処理が複雑になりやすいのが特徴です。
親が元気なうちに将来を見据えた準備をしておくことで、相続時の混乱や不要な税負担を避けられます。そのための方法としては、以下の3つが存在します。
- 遺言書を作成して相続人の意思を明確にしておく
- 生前贈与を活用して共有名義を解消する
- 親子間で売買契約を結んで単独名義にする
それぞれ個別に解説します。
遺言書を作成して相続人の意思を明確にしておく
相続で最も混乱を招きやすいのは、相続人同士の意見がまとまらないケースです。特に不動産は現物を分けにくく、持分割合や利用方法を巡って争いになりやすい財産といえます。こうした事態を避けるには、親が生前に遺言書を作成しておくことが効果的です。
遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。公正証書遺言は公証役場で作成され、偽造や紛失の心配が少なく、家庭裁判所の検認も不要です。費用はかかりますが、確実性の面で優れています。
一方、自筆証書遺言は自宅で作成できる手軽さがありますが、形式の不備で無効になることもあるため、近年では法務局に保管できる制度が利用されるようになっています。
いずれの形式でも、遺言書に「親の持分を誰に相続させるのか」を明確に記しておけば、相続発生後に遺産分割協議を巡って長期化するリスクを減らせます。
生前贈与を活用して共有名義を解消する
親子共有名義のデメリットは、親が亡くなった後に不動産の処分や利用で相続人全員の同意が必要になる点です。
この不便さを解消する方法のひとつが、生前贈与による持分の移転です。親の持分を子に贈与すれば、単独名義となり、将来的な相続の手間を大幅に減らせます。
ただし、生前贈与を行うと贈与税の課税対象となるため注意が必要。贈与税には基礎控除(年間110万円)が設けられており、その範囲内であれば非課税となります。
また、「相続時精算課税制度」を利用すれば、2,500万円までの贈与が非課税で認められ、超過分は一律20%で課税されます。制度を使い分けることで、負担を抑えつつスムーズに名義を移せるのです。
(参考:国税庁「相続時精算課税の選択」)
親子間で売買契約を結んで単独名義にする
もうひとつの方法として、親子間で売買契約を結ぶケースがあります。これは親が持つ持分を子が購入し、登記を変更することで単独名義にするものです。売買契約を用いると、贈与とみなされにくく、税務上も合理的に処理できるのが利点です。
ただし、売買代金のやり取りを実際に行うことが前提で、形式だけの売買は認められません。さらに、売買契約で名義を移す場合には不動産取得税や登録免許税が発生します。贈与よりも税負担が重くなる場合もあるため、実際に選ぶかどうかは慎重に検討しましょう。
親子共有名義で親が死亡した場合に相談できる専門家
相続に関する手続きは法律、税務、不動産取引が入り組んでおり、一人で対応するのは容易ではありません。
特に親子共有名義の不動産では、相続人の数が増えたり持分の評価が難しかったりと、通常より複雑になる傾向があります。こうした状況では、専門家に相談して手続きを進めるのが現実的です。以下では、代表的な相談先とその役割を紹介します。
司法書士:相続登記や名義変更の手続き
司法書士は、相続登記や名義変更を専門とする法律家です。前述のとおり相続登記は2024年から義務化されており、親の持分を相続人へ正しく移転するためには必ず行う必要があります。
(参考:東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !~」)
必要な戸籍や固定資産評価証明書の収集、申請書の作成などは複雑ですが、司法書士に依頼すればスムーズに手続きが進みます。共有名義特有の「複数人への名義移転」にも慣れているため、実務上の負担を大きく減らせます。
弁護士:遺産分割や相続トラブルの対応
相続人間で合意が得られず遺産分割協議がまとまらない場合、弁護士が関与します。調停や審判に発展したときに代理人となるのは弁護士だけであり、法的な助言を受けながら交渉を進められる点が大きな強みです。
共有不動産を売却するかどうか、誰がどの持分を引き継ぐかといった争点は感情的な対立を招きやすく、弁護士を通じて冷静な話し合いを行うことが解決への近道となります。
税理士:相続税・贈与税の申告と節税対策
相続税の申告が必要な場合には税理士のサポートが不可欠です。不動産の評価額をどのように算定するかで税額は大きく変動します。共有名義の場合、持分評価を巡って判断が難しいことも多いため、経験豊富な税理士に依頼する意義は大きいといえます。
さらに、生前贈与を含めた節税シミュレーションを行うなど、長期的な視点でのアドバイスも期待できます。
不動産会社:共有不動産の売却や買取相談
不動産会社は、相続した共有不動産を現金化したいときに相談先となります。共有者が多く利用や管理が難しい場合、売却によって問題を解決するのが現実的な方法です。
ただし、持分のみを売却する場合は市場での流通性が低く、価格が下がりやすい点に注意が必要です。複数の業者に査定を依頼し、最適な条件で売却を進めることが望ましいでしょう。
不動産鑑定士:不動産や持分の評価額算定
相続人の間で公平な分割を行うためには、不動産の正確な評価が必須。不動産鑑定士は法律に基づいた評価を行う専門家であり、共有持分の価格を算定する際にも活用されます。
鑑定結果は税務申告や遺産分割協議の根拠資料としても用いられるため、相続人の納得を得やすいという利点があります。特に不動産の評価額を巡って意見が割れた場合には、不動産鑑定士の判断が解決の糸口となります。
「ワケガイ」なら共有持分も短期で買い取りいたします!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有名義や事故物件など売却が難しい不動産の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。
一般的な不動産会社では扱いづらい共有持分や再建築不可の土地、空き家、ゴミ屋敷といった物件も、独自のノウハウと全国対応のネットワークにより、スピーディに買取可能です。
これまで最短1日での契約や高額一括決済の実績もあり、時間や手間をかけずに資産整理を進めたい方にご利用いただいています。法的リスクや権利関係が複雑なケースでも、専門家と連携しながら対応いたしますので安心です。まずはお気軽に無料査定をご活用ください。
FAQ:親子共有名義に関するよくある質問
Q1.共同名義のまま死亡したらどうなる?
共同名義の所有者が亡くなると、その人の持分は相続財産となり、相続人全員で承継します。つまり「亡くなった親の持分=複数の相続人の共有」となるため、名義人がさらに増えてしまうこともあります。
結果として売却や利用の際にはより多くの同意が必要になり、手続きが煩雑化する傾向があります。
Q2.親子共有名義の変更はどうすればいいですか?
共有名義の変更は、不動産登記の手続きを通じて行います。具体的には持分を贈与、売買、相続などの方法で移転し、その後に法務局で登記を申請します。
親の持分を子へ移す場合は贈与や売買を選ぶことが多いですが、税金や登記費用がかかるため、事前に負担やメリットを比較して決める必要があります。
Q3.共有名義の人が亡くなったらどうなる?
共有者の一人が亡くなると、その持分は法定相続人に引き継がれます。例えば父と子で2分の1ずつ所有していた場合、父の持分は母や子どもたちが相続し、新たな共有関係が生じます。このときに遺産分割協議を行い、誰がその持分を取得するのかを決めなければ、名義が複雑になり管理や処分が難しくなります。
Q4.親子共有名義のデメリットは?
親子共有名義は、住宅ローンを組みやすい、贈与税を避けやすいといった利点がありますが、相続時には不便が目立ちます。親が亡くなると持分が細分化し、登記や売却に相続人全員の同意が必要になります。そのため利用や処分が難航することがあり、結果的に資産価値を活かしづらくなるのが大きなデメリットです。
まとめ
親子共有名義は一見便利に思えても、親が亡くなると相続登記や税務処理、売却の同意などで複雑な手続きが待ち受けています。特に複数の相続人が関わる場合、協議が整わずに不動産の利用や売却が停滞することも当然あります。
こうした事態を避けるには、事前に遺言や生前贈与で対応策を講じておくこと、また相続発生後は速やかに相続人を確定し、登記や税務申告を進めることが大切です。
迷ったときは司法書士や弁護士などの専門家へ相談し、状況に応じた最適な解決策を取るようにしましょう。