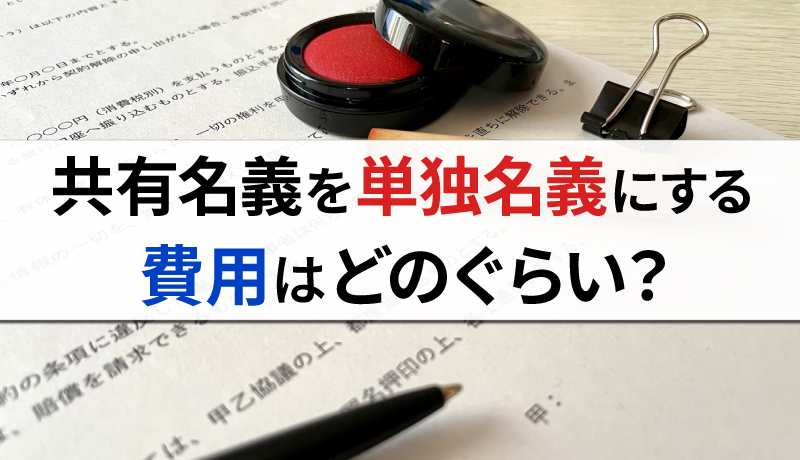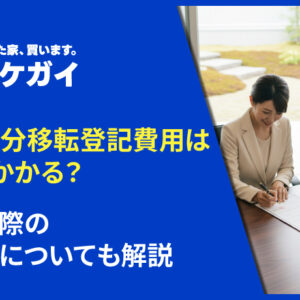こんにちは。ワケガイ編集部です。
兄弟で相続した不動産を共有名義のままにしておくと、「売却したい人」と「残したい人」で意見が分かれるなど、合意形成が難しくなるケースがあります。その際に問題となるのが共有名義不動産のリスクといえます。
共有名義不動産とは、複数人が同じ不動産を共同で所有している状態を指します。
一見公平に見えますが、実際には「売却や活用の同意が得られず計画が止まる」「第三者に持分を売られて関係が複雑化する」「相続をきっかけに名義人が増えて処分できなくなる」といった問題が生じます。
そこで本記事では、兄弟間で共有名義不動産を所有し続ける際に起こり得るリスクと、その背景について詳しく解説します。
目次
兄弟で共有名義不動産を所有し続けるリスクとは
一見すると「兄弟で仲良く所有していれば問題ない」と思われがちですが、共有名義のまま長期間放置すると、さまざまな不利益が生じる可能性があります。
意思決定の難しさや想定外の売却、さらに相続をきっかけとした名義人の増加など、現実的に起こり得るリスクは少なくありません。
ここからは代表的な3つのリスクを取り上げて解説します。
- 売却や活用の意思決定がスムーズに進まない
- 片方が勝手に持分を第三者へ売却するリスクがある
- 相続で名義人が増え手続きが複雑化する
それぞれ個別にみていきましょう。
売却や活用の意思決定がスムーズに進まない
共有名義の不動産は、売却や賃貸、リフォームなどの重要な判断を行う際に、共有者全員の同意が必要です。
兄弟の一方が反対すれば、たとえ他の共有者が賛成していても計画は進みません。実際には「早く売って現金化したい人」と「思い出があるから残したい人」で意見が割れることが多く、話し合いが停滞しやすいのです。
結論が出ないまま放置すれば、固定資産税や維持費が積み重なり、空き家の劣化による資産価値の下落にもつながります。共有名義のままでは、活用のチャンスを逃すリスクが常に伴うといえます。
片方が勝手に持分を第三者へ売却するリスクがある
共有者は、自分の持分だけを自由に第三者へ売却できます。そのため、兄弟の一人が資金繰りのために持分を売却すれば、見知らぬ不動産業者や投資家が突然新しい共有者になることもあります。
こうした第三者は収益化や早期換金を重視することが多く、強引に売却を進めようとするケースもあります。
その結果、兄弟間だけでは解決できたはずの問題が複雑化し、裁判による共有物分割請求や競売に発展する可能性も否定できません。思わぬ相手と共有関係を持たざるを得ない点は、大きなリスクといえます。
相続で名義人が増え手続きが複雑化する
共有者の一方が死亡すると、その持分は相続人に承継されます。たとえば兄の持分が配偶者や子どもに分散すると、共有者の人数は一気に増えます。
人数が増えれば売却や活用の合意形成がますます難しくなり、連絡が取れない相続人がいれば手続きが進まないこともあります。世代をまたぐごとに名義人はさらに細分化し、「誰がどのくらいの権利を持っているか」が把握できない状態になることさえあります。
その結果、処分できないまま固定資産税や管理費だけを負担する「塩漬け不動産」と化すリスクがあります。
関連記事:兄弟で不動産を共有するのはNG?共有状態を避ける方法も紹介
兄弟で共有名義から単独名義に変更する5つの方法
兄弟で不動産を共有している場合、そのままにしておくと将来的にトラブルの原因になりかねません。そこで有効なのが単独名義への変更です。
その方法は以下のものが挙げられます。
- 方法①:持分を贈与する
- 方法②:持分を売買する
- 方法③:持分を放棄する
- 方法④:持分を交換する
- 方法⑤:裁判所の共有物分割請求を利用する
選択肢によって必要な手続きや税金の負担がことなりますので、それぞれ個別にみていきましょう。
方法①:持分を贈与する
兄弟間で持分を無償で譲り渡すのが「贈与」です。流れとしては、まず贈与契約書を作成し、法務局で所有権移転登記を申請する必要があります。
手続き自体は比較的シンプルですが、贈与税には留意しておくべきです。
贈与税には基礎控除額110万円がありますが、不動産の持分評価額は高額になりやすく、多くの場合で課税対象となります。
(参考:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)
さらに、贈与税は累進課税が適用されるため、金額が大きくなるほど税率も高くなり、数百万円単位の負担になることもあります。特に兄弟間の贈与は配偶者控除や親子間の相続時精算課税といった特例が使えないため、節税メリットがほとんどありません。
したがって、贈与を選ぶ場合は税額を事前に試算し、資金的に対応できるか確認しておきましょう。実務では司法書士に登記を、税理士に税務相談を依頼すると安心して進められます。
関連記事:親子共有名義の不動産は生前贈与するべき?注意点について徹底解説!
方法②:持分を売買する
もう一つの方法は兄弟間で持分を売買することです。これは一方が相手の持分を買い取る形で単独名義にする方法で、売買契約書を作成して代金を授受し、登記を行います。
贈与と異なり、対価のやり取りがあるため「税務署から不自然に見られにくい」「お互いに不公平感が少ない」といった利点があります。
ただし売却する側には譲渡所得税が課される場合があり、取得費や譲渡費用を差し引いた利益に課税されます。買い取る側は登録免許税を負担する必要がありますし、購入資金を準備しなければならない点が大きなハードルです。
住宅ローンの利用を検討することも可能ですが、金融機関によっては親族間売買を認めない場合もあるため、事前に確認が必要です。
売買は公平性が確保しやすい一方で、資金面の準備が求められます。実行する際は、税負担と資金計画の両面から慎重に検討しましょう。
関連記事:共有持分の売却は「買取」「仲介」のどちらにするべき?
方法③:持分を放棄する
兄弟の一方が自分の持分を放棄し、残った共有者が単独名義となる方法です。シンプルに見えますが、実際には「持分放棄」という登記手続きを行う必要があります。
形式上は無償で持分が移転するため、贈与に近い扱いとなり、受け取った側に贈与税が課税される可能性が高いのが実情です。
特に不動産の持分は評価額が大きいため、基礎控除額110万円を超えて多額の贈与税が発生するケースも少なくありません。
また、持分放棄を行う場合でも、法務局に申請するための書類(登記原因証明情報や印鑑証明など)を揃える必要があり、専門的な知識が求められます。税務上の扱いについてはケースによって異なることもあるため、税理士に確認してから進めるのが安心です。
「お金をもらわないから簡単」と考えがちですが、実際には思わぬ税負担や手続きの複雑さがあるため、慎重な判断が求められます。
方法④:持分を交換する
兄弟で複数の不動産を相続している場合に有効なのが「交換」です。一例を挙げると、一方が土地の共有持分を放棄する代わりに、もう一方が別の不動産や資産を譲るといった方法です。
交換契約書を作成し、法務局で登記申請を行う必要があり、公証役場で公正証書化しておくと将来のトラブル防止につながります。
ただし、交換は「等価交換」が原則とされていますが、実際には資産価値に差がある場合が多く、その差額を金銭で調整する必要があります。
この差額部分については譲渡所得税が課税される可能性があり、また登録免許税も発生します。さらに評価額をめぐって兄弟間で不公平感が生まれやすいため、第三者である不動産鑑定士などの専門家による評価を利用することが望ましいでしょう。
(参考:国税庁「土地や建物を売ったとき」)
公平性を保ちながら整理できる点がメリットですが、税金や評価の問題を丁寧に詰める必要があります。
方法⑤:裁判所の共有物分割請求を利用する
兄弟間でどうしても合意が得られない場合の最終手段が、裁判所に共有物分割請求を申し立てる方法です。これは民法で認められた権利で、裁判所が不動産の分け方を判断します。
分割の方法には、以下の3つがあります。
- 現物分割:物件を実際に分けて、それぞれが単独所有とする方法
- 代償分割:一方が不動産を取得し、他方に代償金を支払う方法
- 競売分割:物件を競売にかけ、得られた現金を分ける方法
ただし、この手続きには時間と費用がかかり、結果的に希望どおりの形にならないことも多いです。特に競売分割では市場価格より安く処分されることが一般的で、共有者全員が損をする可能性もあります。
それでも、兄弟間の話し合いがまとまらず、膠着状態が続く場合には有効な手段です。利用する際は弁護士に依頼し、費用対効果を踏まえて慎重に判断することが大切です。
兄弟で共有名義から単独名義に変更するための手続きの流れ
単独名義にする方法を決めたら、次は実際の手続きに進む必要があります。流れを把握していないと、途中で書類不足や手戻りが発生し、余計な時間と費用がかかることになります。
ここからは、実際の手続き方法を解説します。
- 手順①:共有者間で合意内容を決定する
- 手順②:契約書を作成する
- 手順③:必要書類を準備する
- 手順④:登記申請を行う
- 手順⑤:税金や費用を納付する
次項より、個別にみていきましょう。
手順①:共有者間で合意内容を決定する
最初に行うべきことは、兄弟間で「どの方法で単独名義にするのか」を明確に決めることです。贈与にするのか、売買にするのか、それとも持分放棄や交換にするのかによって、必要な手続きや税金の負担が大きく異なります。
そのため、安易に「贈与でいいだろう」と決めるのではなく、税金や費用を試算したうえで話し合う必要があります。
また、単に方法を決めるだけでなく、「金額をいくらにするか」「税金や登録免許税は誰が負担するか」といった条件も取り決めておかなければなりません。
こうした合意内容は口頭で済ませず、後日のトラブルを防ぐために必ず書面に残すようにしましょう。ここで丁寧に合意を固めておけば、後の手続きがスムーズに進みます。
手順②:契約書を作成する
合意が固まったら、次は契約書を作成します。方法に応じて必要となる契約書は異なり、贈与なら「贈与契約書」、売買なら「売買契約書」、交換なら「交換契約書」が必要になります。
契約書は自分たちで作成することも可能ですが、法的に不備があると登記申請が通らないこともあるため、専門家に作成してもらうようにしましょう。
特に高額な不動産が関わる場合には、公証人役場で公正証書にしておくと法的効力が強まり、より安全です。契約書は単なる形式的なものではなく、兄弟間の信頼関係を守るための大切な証拠となります。
手順③:必要書類を準備する
合意や契約が整ったら、次に登記申請に必要な書類を準備します。基本的に必要となるのは以下のような書類です。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 固定資産評価証明書
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑証明書
- 契約書(贈与契約書・売買契約書など)
これらは登記の内容や方法によって追加される場合もあります。例えば、相続に伴う変更であれば戸籍謄本や遺産分割協議書が必要になることもあります。
書類の一部は市区町村役場で取得し、法務局に提出する際に原本を添付しなければならないケースもあるため、早めに準備しておくことが大切です。司法書士に依頼すれば、必要な書類リストを作成してもらえるため、漏れや不備を防げます。
手順④:登記申請を行う
書類が揃ったら、いよいよ法務局に登記申請書を提出します。申請は自分で行うことも可能ですが、登記の申請書式は複雑で、少しでも記載内容が誤っていると補正や却下の対象になることがあります。
そのため、一般的には司法書士に依頼して申請を代行してもらうケースも多々あります。司法書士は契約書や必要書類をチェックし、登記原因証明情報の作成から申請まで一貫して行ってくれるため安心です。
また、登記が完了すると法務局から「登記完了証」が交付されます。これを受け取ることで、正式に単独名義への変更が完了したことを確認できます。ここまで進めば、名義上はトラブルが起きにくい状態に整理されたといえます。
手順⑤:税金や費用を納付する
登記が完了したあとには、税金や諸費用を期限内に納付しなければなりません。代表的なものは以下のとおりです。
- 登録免許税(固定資産評価額に応じて算出)
- 贈与税(贈与による場合、基礎控除110万円を超えると課税対象)
- 譲渡所得税(売買による場合、利益が出たときに課税)
- 司法書士報酬や契約書の印紙税などの実費
税金は発生する原因や金額がケースごとに異なるため、事前に試算しておくことが大切です。納付を怠ると延滞税や加算税が課される可能性があるため、必ず期限内に納めるようにしましょう。
共有名義から単独名義に変更する際にかかる費用・税金
兄弟間で共有名義を整理して単独名義にする場合、避けて通れないのが費用や税金です。登記手続きに伴う税金のほか、方法によっては贈与税や譲渡所得税が発生する可能性もあります。
具体的には、以下のものが挙げられます。
- 登録免許税
- 贈与税
- 譲渡所得税
- 司法書士報酬
- その他実費
それぞれ個別にみていきましょう。
登録免許税
不動産の名義を変更する際には、法務局で登記申請を行う必要があり、その際に納めるのが登録免許税です。
税額は「不動産の固定資産評価額 × 税率」で計算されます。税率は移転の原因によって異なり、相続による名義変更なら0.4%、売買や贈与などの場合は2.0%が原則です。
| 内容 | 税率 |
|---|---|
| 所有権の保存 | 0.4% |
| 売買または競売による所有権の移転 | 2% |
| 相続または法人の合併による所有権の移転 | 0.4% |
| その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) | 2% |
(参考:国税庁「登録免許税の税額表」)
仮に、固定資産評価額が1,500万円の不動産を兄弟間で売買する場合、登録免許税は30万円(1,500万円 × 2.0%)となります。
相続や贈与などで税率が異なるため、自分のケースにあてはめて計算する必要があります。また、土地と建物を同時に移転する場合にはそれぞれに課税されるため、思ったより負担が大きくなる点にも注意が必要です。
贈与税
兄弟間で持分を無償、または著しく低い金額で譲り渡す場合には、受け取る側に贈与税が課されます。贈与税には基礎控除110万円がありますが、不動産の持分評価額は高額になりやすく、多くのケースで控除額を超えて課税対象になります。
贈与税は累進課税制度が採用されており、贈与額が大きくなるほど税率も高くなります。
<一般贈与財産用(一般税率)>
| 課税価格範囲(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | – |
| 200万円超〜300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超〜400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超〜6,000万円以下 | 30% | 65万円 |
| 6,000万円超〜1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超〜1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
(参考:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)
仮に、評価額が1,000万円の持分を無償で譲り渡したとします。この場合、基礎控除110万円を差し引いた890万円が課税対象となり、数百万円単位の贈与税が発生する可能性があります。
さらに注意すべきなのは、兄弟間の贈与には「相続時精算課税制度」や「配偶者控除」といった特例が利用できない点です。
そのため親子間の贈与に比べて節税メリットがなく、税負担はより重くなります。贈与を選ぶ場合には、税理士に相談し、事前に正確な税額を試算してから進めることが大切です。
譲渡所得税
兄弟間で持分を売買する場合、売却した側に「譲渡所得税」が課されることがあります。これは不動産の売却益に対して課される税金で、単純に売却金額が課税対象となるわけではありません。
取得したときの費用(購入価格や相続時の評価額など)や、売却にかかった仲介手数料・測量費などの諸経費を差し引いた「利益部分」に課税されます。
税率は所有期間によって以下のように異なります。
| 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計 | |
| 短期譲渡所得(5年以内) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期譲渡所得(5年超) | 15% | 5% | 0.32% | 20.32% |
(参考:国税庁「短期譲渡所得の税額の計算」/「長期譲渡所得の税額の計算」)
例えば相続で取得した土地を短期間で売却すると税率が高くなるため、譲渡益が出やすく注意が必要です。なお、譲渡損失が出た場合は課税されません。
譲渡所得税は計算が複雑なため、事前に税理士に試算してもらうと安心です。特例控除や相続に伴う特別ルールが使えるケースもあるため、必ず確認してから売却を進めることをおすすめします。
司法書士報酬
登記手続きや契約書作成を自分で行うことも可能ですが、法務局の申請は専門的な知識が必要であり、一般の方にとっては負担が大きいのが実情です。そのため多くのケースでは司法書士に依頼することになります。
司法書士報酬は、登記の内容や物件数、難易度によって金額が変わります。一般的には5万〜10万円程度が目安ですが、贈与登記と売買登記を合わせて行う場合や、必要書類が多い場合にはさらに費用がかかることもあります。
また、書類取得の代行や登記完了後の書類送付などを依頼する場合には、実費と合わせて請求されます。
「自分で手続きをした方が安い」と考える方もいますが、記載ミスや添付書類の不足によって法務局から補正を求められると、手間が増えて結果的に時間もコストも余計にかかることがあります。確実に進めたいなら、司法書士に依頼することが安心です。
その他実費
共有名義を単独名義に変更する際には、税金や司法書士報酬以外にも細かな費用が発生します。代表的なものは以下のとおりです。
- 契約書に貼付する印紙税(贈与契約・売買契約など)
- 固定資産評価証明書の取得費用(数百円〜数千円)
- 登記事項証明書(登記簿謄本)の発行手数料(1通600円程度)
- 住民票や印鑑証明書の取得費用
これらは1つひとつは小額ですが、複数の書類を揃えると数万円程度になることもあります。特に契約書の印紙税は契約金額によって変わり、数千円から数万円まで幅があるため注意が必要です。
こうした実費は意外と見落とされやすく、後から「思った以上に費用がかかった」という声も少なくありません。単独名義化を検討する際は、これらの細かな費用も含めて全体の予算を見積もっておくことが大切です。
兄弟で共有名義から単独名義に変更する際の注意点
単独名義への変更方法はいくつかありますが、どの方法を選ぶかによって発生する税金や費用、さらには兄弟間の関係性への影響まで変わってきます。見落としや誤解があると、後から予期せぬトラブルを招くこともあります。
そのため、単独名義変更する際には以下の点に留意しましょう。
- 方法ごとの税負担を事前に把握する
- 不動産の評価額を公平に算定する
- 契約内容を必ず書面に残す
- 兄弟間の感情的対立を避ける工夫をする
- 司法書士や税理士など専門家に早めに相談する
それぞれ個別に解説します。
方法ごとの税負担を事前に把握する
不動産を単独名義にする場合、贈与、売買、持分放棄などの方法がありますが、それぞれにかかる税金の種類と金額は大きく異なります。
実際に、贈与を選ぶと、基礎控除110万円を超える部分に贈与税がかかり、数百万円単位の負担になることも珍しくありません。
一方、売買では譲渡する側に譲渡所得税がかかり、買う側には登録免許税の支払いが必要です。持分放棄の場合も、結果的に贈与と同じ扱いになり、受け取った側に贈与税が課税される可能性があります。
このように方法によって税負担が変わるため、「安く済むと思って選んだ方法が、実は一番税金が高かった」というケースもあります。事前にシミュレーションを行い、税理士など専門家に確認してから選択することが、余計なトラブルを防ぐ第一歩です。
不動産の評価額を公平に算定する
兄弟間で金銭授受が伴う場合、注意しなければならないのが不動産の評価額です。評価額を適正に算出しないまま進めてしまうと、兄弟の一方に「高すぎる」「安すぎる」という不公平感が残り、関係悪化の原因となります。
さらに、税務署に不自然と判断されれば、贈与とみなされ余計な税金を課されるリスクもあります。
評価額は、固定資産税評価額を基準にしたり、不動産会社に査定を依頼したりして客観性を確保することが大切です。可能であれば複数の査定を取り、兄弟間で納得感のある金額に調整することが望ましいでしょう。
特に市場価格と大きな乖離がある取引は後々問題になりやすいため、第三者の専門家を介して透明性を確保することが安心につながります。
契約内容を必ず書面に残す
兄弟間のやり取りは「信頼関係があるから口約束で大丈夫」と思いがちですが、これは大きなリスクといえます。
不動産の名義変更は金額が大きく、税金や将来の相続にも影響します。口頭合意だけでは「そんな約束はしていない」と言われたときに証明ができず、トラブルの火種となります。
そのため、どの方法で単独名義にするか、金銭の授受があるのか、税金や手続き費用を誰が負担するのかといった内容を必ず契約書に明記し、署名・押印を行って残しておくようにしましょう。契約書は自作することも可能ですが、誤りがあると法的効力が弱まる可能性があります。
確実性を高めるためには、司法書士に確認してもらったり、公証人役場で公正証書にしておくと安心です。
兄弟間の感情的対立を避ける工夫をする
不動産の単独名義化をめぐる話し合いは、金銭や権利が絡むため、感情的な対立に発展しやすいものです。特に相続で受け継いだ家や土地は思い入れが強く、「売りたい兄」と「残したい兄弟」で意見がぶつかることは珍しくありません。
感情が優先されると、冷静な判断ができなくなり、結果的に手続きが進まなくなることもあります。
このような場合には、第三者を交えることが有効です。司法書士や税理士、不動産業者などの専門家を同席させれば、客観的な立場から合理的な解決策を提示してもらえます。また、専門家が入ることで兄弟双方が「公平に扱われている」と感じやすくなり、不必要な疑心暗鬼を避けることにもつながります。
大切なのは「相手を説得する」のではなく、「どうすれば双方が納得できるか」を一緒に考える姿勢を持つことです。
司法書士や税理士など専門家に早めに相談する
不動産の登記や税金の計算は複雑で、一般の方が独力で対応しようとするとミスが生じやすい分野です。登記申請の記載内容が不十分だと法務局から補正を求められ、時間がかかるだけでなく、最悪の場合はやり直しになることもあります。
税務処理に関しても、贈与税や譲渡所得税の扱いを誤ると、追徴課税やペナルティを受ける可能性があります。
そのため、早い段階で司法書士や税理士に相談することをおすすめします。司法書士は契約書作成や登記申請をサポートし、税理士は税負担のシミュレーションや申告を代行してくれます。
専門家に依頼することで費用はかかりますが、安心感と手続きの確実性を得られる点でメリットは大きいです。「自分でできるかもしれない」と悩む時間を減らし、専門家に任せることでスムーズに単独名義化を進めることができます。
兄弟での話し合いが難航したらどうすればいい?
不動産の共有名義を単独名義に変更する際、兄弟間で意見が対立することは珍しくありません。売却か活用か、税負担をどう分けるかといった具体的な条件が絡むと、感情的な対立に発展しやすいのです。
そのまま膠着状態が続けば、固定資産税や維持費だけがかかり続け、資産価値を下げる原因にもなります。
ここからは、話し合いが行き詰まったときに有効な対応策を3つ紹介します。
第三者を交えて話し合う
まず検討すべきは、当事者だけでなく第三者を交えて話し合う方法です。親族以外の信頼できる友人や、利害関係のない第三者が加わることで、感情的な衝突を避けやすくなります。
特に兄弟間の相続や財産分与では「昔からの関係性」が影響して冷静な話し合いが難しくなることがあります。第三者が間に入ることで、意見を整理し合意形成をスムーズに進められる場合があります。
不動産や税務の専門家に相談する
司法書士や税理士、不動産業者といった専門家に相談することも有効です。専門家は法律や税制に基づいて中立的にアドバイスをしてくれるため、「どの方法を選べば一番公平か」「税金を抑えるにはどの選択肢が現実的か」といった疑問を解消できます。
また、専門家の助言を根拠として話し合いを進めれば、兄弟のどちらか一方の意見に偏ることなく、公平性を保った条件を提示できるため、行き詰まりを打開しやすくなります。
家庭裁判所の調停を利用する
どうしても合意が得られない場合には、家庭裁判所の調停を利用する方法があります。調停では、裁判官と調停委員が中立的な立場で兄弟間の話し合いをサポートし、妥当な解決策を導いてくれます。
合意に至れば調停調書が作成され、これは判決と同じ法的効力を持ちます。費用や時間はかかりますが、感情的な対立が深まり関係修復が難しい場合には、法的に整理する手段として有効です。
「ワケガイ」なら名義変更前でも買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有名義や再建築不可物件、空き家や事故物件など、一般の市場では売却が難しい不動産を専門に扱う買取サービス「ワケガイ」を提供しています。
全国対応の豊富な実績を活かし、複雑な事情を抱えた物件でもスピーディに現金化が可能です。
最短で査定から数日以内に契約・決済まで進められるため、「すぐに手放したい」「維持費やトラブルの負担を減らしたい」と考える方にも安心してご利用いただけます。まずはお気軽に無料査定をご活用ください。
共有名義から単独名義への変更でよくある質問
ここからは、兄弟での共有名義を単独名義へ変更する際によく寄せられる質問を取り上げ、具体的に解説します。
兄弟から土地を買うと税金はかかりますか?
兄弟から持分を買い取る場合には、主に「譲渡所得税」「登録免許税」「印紙税」が関わります。売る側には利益が出れば譲渡所得税が課され、買う側は不動産評価額に応じた登録免許税を負担します。契約書には印紙税も必要です。
兄弟間だから税金が安くなるわけではなく、むしろ贈与と判断されないように適正価格で売買契約を結ぶことが大切です。
共有名義の固定資産税は誰が払うのですか?
固定資産税は原則として共有者全員に納税義務があります。ただし、実際の納付書は代表者一人に送付され、その人がまとめて支払うケースも多々あります。
公平に負担するためには、持分割合に応じて按分し、兄弟間で精算しておくことが望ましいです。放置すると「払った・払わない」で感情的な対立につながるため、事前にルールを決めておくと安心です。
共有者が死亡した場合、単独名義にするにはどうすればいいですか?
共有者が亡くなると、その持分は相続人に承継されます。単独名義にするには、まず相続手続きを経て誰が持分を引き継ぐかを確定させ、そのうえで持分を買い取る、放棄してもらう、贈与してもらうなどの方法で整理する必要があります。
名義人が増えると合意形成が難しくなるため、相続発生後は早めに対応することが必須といえます。
共有名義から単独名義への変更は自分で手続きできますか?
法務局への登記申請は本人でも可能です。ただし、贈与契約書や売買契約書の作成、登記原因証明情報の添付、税務申告など専門的な知識が必要で、不備があれば手続きがやり直しになることもあります。
手間やリスクを考えると、司法書士や税理士に依頼した方が安心です。自分で行う場合は、必要書類を漏れなく準備し、法務局の相談窓口を活用しましょう。
まとめ
兄弟で不動産を共有名義にして所有し続けることは、一見公平な解決策に見えても、長期的には多くのリスクを伴います。
合意が得られず売却や活用が進まない、第三者が共有者として介入しトラブルが拡大する、相続で名義人が増えて事実上動かせなくなるといった事態は現実に起こり得ます。
こうした状況を避けるには、できるだけ早い段階で単独名義化や処分方法を話し合い、契約内容を文書で残すことが大切です。
また、税務や登記の複雑さを踏まえて専門家の助言を受けることも有効です。問題を先送りせず、将来を見据えて具体的な行動を取りましょう。