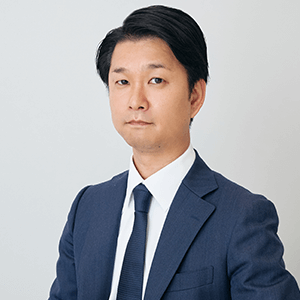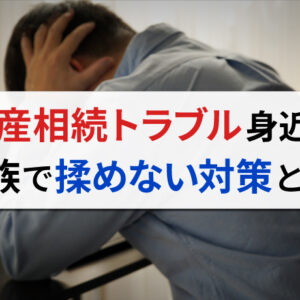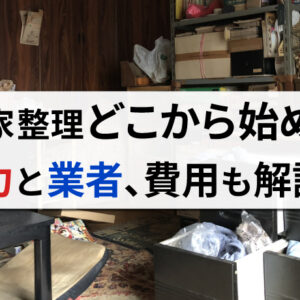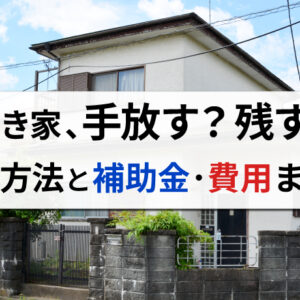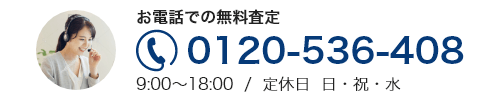について今すぐご相談できます。
お電話する
そのままでは売却が難しい再建築不可物件ですが、間口が接している道路が4m未満の幅であるなら、セットバックを実施すれば、再び建築可能な状態にできます。
セットバックとは、都市計画や防災上の観点から、特定の土地を道路として提供することを指します。これにより、道路の拡張や新たな道路の確保が可能となる一方で、土地所有者にはさまざまな影響が生じます。
今回は、セットバックの概要に加え、そのメリットや必要費用について解説しますので、ぜひお役立てください。
目次
セットバックとは
「セットバック」とは、建築物を道路の中心線から一定の距離だけ後退させることを指します。具体的には、道路中心から2m土地を後退させることで、建築基準法の接道義務が満たされる手法。
特に、接道の対面が川や線路のような場合には、その反対側の境界から4m後退させる必要があります。
歴史を振り返ると、日本での建築制約は「建築基準法第42条」によって、道幅4m以上の道路に対して、土地の間口が2m以上接していなければ建築が認められないと定められていました。
しかしながら、建築基準法が改訂される前に建てられた既存の建物の中には、この基準を満たしていないため再建築ができないものも多く存在します。このような制約下での再建築を可能にするのが、セットバックの役割です。
建築基準法第42条2項には、「セットバックを活用して接道幅を確保すれば、それを道路として扱う」という内容が記述されています。このように、セットバックを利用して形成された道路部分は「みなし道路」や「42条2項道路」として認識され、その土地の所有権は元の土地所有者に帰属します。
しかし、このセットバックされた部分は、道路としての利用のみを目的とし、フェンスや門扉を勝手に設置することは許されません。
関連記事:再建築不可物件の救済処置とは?再び建築可能な状態にするための方法を解説
斜線制限を緩和にも活用される
セットバックは、ただ接道義務を満たすためだけでなく、道路の斜線制限を緩和する目的でも用いられることがあります。
斜線制限とは、日照や通風を確保し、建築物が周囲に圧迫感を与えないように、建物の高さを制限するための規則です。
この斜線制限において、敷地と道路の境界線からの距離が基準となり、建築物の高さが決まります。セットバックを適用して道路の幅を拡張することで、許容される建築物の高さが増加し、より大きな建物の建築が可能となるのです。
セットバックのメリット
セットバックを行うメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
- セットバック後の道路は非課税
- 防災対策になる
次項より、個別にみていきましょう。
セットバック後の道路は非課税
物件の所有者として、固定資産税や場合によっては都市計画税など、様々な税金の支払い義務があります。
しかし、セットバックによって形成された道路部分は「公共道路」として扱われることが多く、これにより課税対象外となる可能性が高まります。
注意点として、セットバック後の道路部分を非課税とするためには、管轄する役所への非課税申請が必須です。申請の際、以下の書類を用意する必要があります。
- 土地の登記簿謄本
- セットバックしたエリアを明確に示す地積測量図
- 役所から指定された申告書や関連書類
防災対策になる
セットバックを行うことで、道路の物理的な幅が拡がり、通行人や車の流れがスムーズになります。この制度が導入された背景には、消防車や救急車などの緊急車両が迅速に通行できるスペースを確保するためという考えがあります。
従って、セットバックは単なる土地利用の制約だけでなく、都市の防災対策としての重要な役割も果たしているのです。
セットバックのデメリット
一方で、セットバックにはデメリットも存在します。具体的には、以下のとおり。
- 土地部分が狭くなる
- 費用を支払わなければならない可能性がある
- セットバックした道路は自由に使えない
それぞれ、詳しく解説します。
土地部分が狭くなる
セットバックを行うと、所有する土地の有効利用面積が減少します。これにより、物件の使い勝手や土地の活用価値が変わる可能性があります。
費用を支払わなければならない可能性がある
セットバックに伴う工事費用は、多くの場合、土地の所有者が負担することが求められます。ただし、自治体によっては、セットバックの補助金制度が設けられている場合もあるため、事前の確認が必要です。
セットバックした道路は自由に使えない
セットバックによって形成された道路部分は、所有者が完全に自由に利用することはできません。所有権は維持されるものの、道路部分としての役割を果たすため、塀や門扉はもちろん、移動が困難な大きな石などを設置することも制限されることがあります。
セットバックの流れ
セットバックの流れは、以下のように大別されます。
- Step1.公図の入手
- Step2.必要書類の提出
- Step3.測量・事前協議
- Step4.建築確認の申請
各ステップについて、詳しくみていきましょう。
Step1.公図の入手
セットバックの手続きを始める前に、まず所有する物件の接道幅を正確に知ることが重要です。
これを確認するためには、公図を取得する必要があります。公図は、物件が位置する地域を管轄する役所の対応部署で入手可能です。この公図を基に、具体的な接道状況を把握しましょう。
Step2.必要書類の提出
公図の確認を通して、接道義務が満たされていないことが明らかになった場合、セットバック工事を進めることとなります。
この際、セットバック工事を行う前に、各自治体に提出する事前協議書の準備が求められます。事前協議書のフォーマットや入手方法については、各自治体の公式ホームページに詳しく掲載されていますので、参照しましょう。
Step3.測量・事前協議
事前協議書が自治体に受理されると、続いて自治体による測量と事前協議が進められます。セットバックに関しては、「現況測量」と「境界確定測量」の2つのタイプの測量が要求されるケースが多々あります。
特に、再建築が難しい物件の場合、隣接する土地との境界が時間の経過で不明瞭になっている可能性があるため、注意が必要です。事前協議では、工事の詳細やセットバック後の道路部分の管理についてなど、具体的な内容を共有・確認することになります。
Step4.建築確認の申請
事前協議が無事終了し、セットバックの詳細が確定したら、次は建築確認の申請を行います。
申請を進める際には、建築確認申請書の他に、事前協議の結果をまとめた協議書の提出も必要。この審査が通れば、セットバックの実施が正式に認められることとなります。
セットバックで必要な費用
セットバックで必要な費用としては、以下のとおりです。
- 土地の測量費
- 道路整備費
それぞれ、詳しく解説します。
土地の測量費
セットバックを進める際、土地の測量は欠かせないプロセスです。隣地との境界線が明確な場合、現況測量のみで対応できるため、分筆登記費用を含めた全体のコストは20万〜30万円程度となることが多々あります。
しかし、境界線が不明瞭な場合や、セットバック後の道路を自治体へ寄贈する場合など、境界確定測量が追加で必要となります。この場合の費用は、おおよそ50万〜70万円程度になることを予算内に考慮しておきましょう。
道路整備費
セットバック後の道路部分は、適切な使用のために舗装作業が必要です。舗装にかかる費用は、整備する面積の大きさにより変わりますが、概算で1㎡あたり5,000円程度が一般的です。
さらに、この舗装作業において、重機の導入や撤去が必要となる場合があり、この関連費用も約5万円程度が見込まれます。
セットバックでは自治体の補助制度も活用しよう
セットバックは、都市の防災を強化するという社会的な側面も持っています。そのため、多くの自治体はセットバックの取り組みを支援するための補助制度を設けています。
セットバックの導入にはそれなりのコストがかかるため、自治体の補助や助成制度をうまく利用することで、経済的な負担を軽減できる可能性があります。
ただし、補助を受けるためには、役所による調査が必要な場合があるなど、いくつかの条件や手続きが求められることも。そのため、計画の初期段階からこれらの情報を確認し、適切に手続きを進めるよう心がけましょう。
セットバック物件を購入する際の注意点
セットバックされた物件を購入する際には、以下の点に留意しましょう。
- セットバック部分は敷地面積から除外され、私的利用もできない
- 固定資産税の非課税申請を行う
次項より、個別に解説します。
セットバック部分は敷地面積から除外され、私的利用もできない
セットバック部分の土地は、建ぺい率や容積率を算出する際に敷地面積から除かれます。建ぺい率とは、敷地の全体面積に対する建物の面積の比率を、容積率は敷地面積に対する建物の全階の面積の比率を示すものです。
これらの率は、都市計画や地域の制限に基づいて上限が設定されています。そのため、セットバックが必要な物件においては、通常の土地に比べて建てられる建物の面積が制限されることが一般的。
もし既存の建物がセットバック部分を含めて建設されていた場合、新たに建てる建物は以前のものよりも狭くなることが想定されます。
建て替えの際は、前の建物のサイズと比較して過度な期待をせず、新しい敷地面積を基準に計画を立てることが重要です。
セットバックされた部分は、基本的に公共の道路としての性質を持つため、私的な利用は認められません。例えば、門や塀の設置、駐車スペースとしての利用などは、法的に禁止されています。セットバック後の土地利用を考慮して、計画やデザインを行う必要があります。
固定資産税の非課税申請を行う
セットバックにより公道としての性質を持つ部分は、私的利用が制限されるものの、所有権は変わりません。この土地部分について、固定資産税や都市計画税が課されるのは不合理といえるでしょう。
幸い、これらの税金は、正式な手続きを踏むことで免除される場合があります。しかし、自動的に免除されるわけではなく、自治体への非課税申請が必要となります。
詳しい手続きや要件については、各自治体の窓口、特に建築指導課などで確認し、適切に申請しましょう。
まとめ
セットバックを実施すれば再建築不可物件を建築可能な状態にできるだけでなく、本来満たしておくべき接道幅を確保し防災性を向上させられます。
セットバックは、都市計画や防災の観点から必要とされる措置であり、多くの土地所有者が直面する可能性がある課題。セットバック部分の土地は建築計画や税金の面で特別な取り扱いが求められ、その詳細を把握することは、土地利用や建物計画を進める際の重要な手続きといえます。
一方で、セットバックでは多額の費用を負担しなければならない点がネックとなりますので、自治体が実施している助成金なども有効活用しましょう。
本ブログで情報発信を行っている「ワケガイ」は、訳あり物件を積極的に買い取っている専門業者です。所有物件についてお悩みの方は、訳あり物件の買取に特化したワケガイに、ぜひお問い合わせください。
| 運営団体 株式会社ネクスウィル 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 |