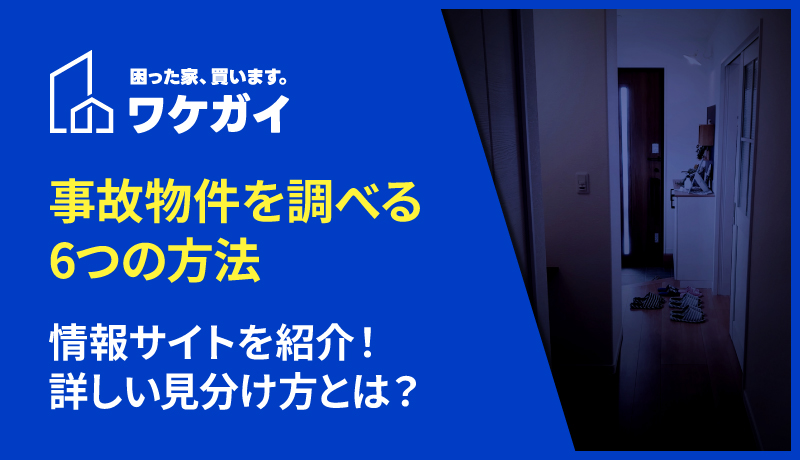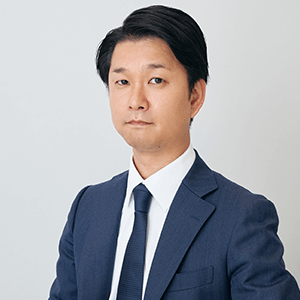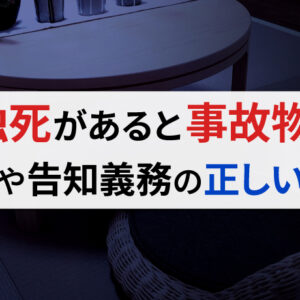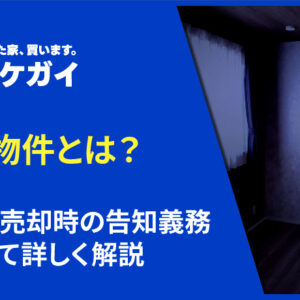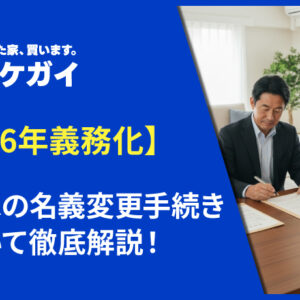こんにちは。ワケガイ編集部です。
賃貸や購入を検討している物件が「事故物件だったらどうしよう」と不安に感じる方は少なくありません。事故物件は過去に事件や事故があったことから、心理的に抵抗を感じる人が多く、できれば避けたいと考えるのが一般的です。
しかし、不動産業者から必ずしも告知されるとは限らず、契約後に後悔してしまうケースもあります。こうしたトラブルを防ぐためには、事故物件を自分で調べる方法を知っておくことが大切です。
本記事では、事故物件の調査に役立つサイトや具体的な確認方法、隠れ事故物件を見抜くためのポイントまで詳しく解説します。
について今すぐご相談できます。
お電話する
目次
事故物件とは?まず知るべき基本知識
事故物件という言葉を耳にしたことはあっても、実際にどのような状態の物件を指すのか、明確に答えられる人は少ないでしょう。特に賃貸や購入を検討している立場であれば、事故物件の定義を曖昧なままにしておくと、契約後に思わぬ後悔を招きかねません。
ここからはまず、事故物件に当たるケースと、法律上どのように扱われているのかを整理しておきましょう。
事故物件に該当するケース例(例:自殺・他殺・孤独死・火災)
事故物件と呼ばれるのは、過去に人の死や事件、火災などが発生し、その履歴が物件に心理的な影響を与えると考えられるケースです。代表的なのは自殺や他殺ですが、それだけではありません。
例えば、住人が長期間発見されずに亡くなった孤独死も、発見の状況によっては事故物件として扱われます。
また、火災で住人が死亡した、あるいは重大な損傷を受けた建物も心理的瑕疵のある物件として認識されることが多いです。ここで注意したいのは、必ずしも「人が亡くなった」ことだけが基準ではないという点です。大規模な事件が起きた現場や、過去に放火などの犯罪行為が絡んだケースも対象になる場合があります。
こうした情報は契約書や重要事項説明で伝えられることがありますが、その基準は統一されていません。つまり、事故物件かどうかの判断は曖昧な部分があり、買い手や借り手が慎重に確認する必要があるのです。
<事故物件とみなされやすいケース例>
- 室内での自殺や他殺事件が発生した物件
- 長期間発見されなかった孤独死があった物件
- 住人が火災で死亡、または大きな損傷を受けた建物
- 放火や暴行事件など犯罪行為が絡んだ物件
- 大規模な事件や事故の現場として報道された物件
事故物件の「告知義務」とは?法律で定められた基準と期間
事故物件を語る上で避けて通れないのが「告知義務」です。宅地建物取引業法では、不動産会社や仲介業者は契約前に物件に関する重要な事実を伝えることが義務付けられています。
そのなかには、心理的瑕疵にあたる事故物件の情報も含まれます。
ただし、すべての事故歴が永久に告知されるわけではありません。国土交通省が2021年に出した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、賃貸物件において、自然死や日常生活の中で起きた病死などは原則として告知しなくても良いとされました。
また、自殺や他殺といった事件性のある死亡でも、事故から3年が経過すると告知義務が免除される目安とされています。
一方、購入の場合はより厳格で、事故から時間が経っても買い手への説明が求められるケースが多いのが現状です。こうした基準を理解していないと、「事故物件だと知らずに契約してしまった」というトラブルにつながる恐れがあります。
告知義務の内容と範囲を知ることは、事故物件を避けたい人にとって欠かせない前提知識です。
(参考:国土交通省「『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』を策定しました」)
【無料で可能!】事故物件かどうか自分で調べる6つの方法
事故物件かどうかを見分けるために、必ずしも有料の調査会社に依頼する必要はありません。契約前に少し調べるだけで、事故物件の可能性を判断する材料は手に入ります。
ここからは、誰でもできる代表的な調査方法を紹介します。
- 調査方法①:周辺住民や管理会社に直接確認する
- 調査方法②:過去のリフォーム・修繕履歴を調べる
- 調査方法③:特定ワードでネット検索してみる
- 調査方法④:家賃が相場より安い理由を調査する
- 調査方法⑤:不動産会社に聞いて確かめる
- 調査方法⑥:建物名の変更や履歴をチェックする
それぞれ個別にみていきましょう。
調査方法①:周辺住民や管理会社に直接確認する
最も直接的な方法が、近所の人や管理会社に話を聞くことです。事故物件であるかどうかは、公式な書類や不動産業者の説明だけでは分かりにくいこともありますが、近隣に住んでいる人は意外と詳しい情報を知っていることがあります。
特にマンションの管理人や管理会社は、建物内で起きた出来事を把握していることが多く、過去に事件や事故があったか尋ねる価値があります。
聞き込みといっても大げさなものではありません。内見の際に「過去にトラブルがあった部屋はありますか?」と軽く声をかける程度でも十分です。
ただし、こうした質問は聞かれた側にとってデリケートな話題でもあるため、言い方には注意が必要です。あからさまに「自殺はありましたか?」と尋ねるよりも、「前の入居者が退去した理由をご存知ですか?」とやんわり切り出す方が、相手も答えやすくなります。
調査方法②:過去のリフォーム・修繕履歴を調べる
物件のリフォーム履歴を確認するのも、事故物件かどうかを推測する手がかりになります。事故後の部屋は、床や壁を張り替えたり、水回りを交換したりと大きな修繕が入ることが少なくありません。
通常の経年劣化とは違うタイミングで大規模な工事が行われている場合、背景に事故がある可能性を疑う価値があります。
管理会社やオーナーに「最近リフォームされていますか?」と尋ねるだけでも、工事内容や時期を教えてもらえることがあります。また、分譲マンションなら管理組合の議事録や修繕履歴に工事の記録が残っていることもあります。
もちろんリフォームが直ちに事故物件を意味するわけではありませんが、家賃や物件の条件と照らし合わせることで判断材料になります。
調査方法③:特定ワードでネット検索してみる
事故物件を調べる上では、当然インターネットを使った調査も有効です。物件名や住所とあわせて「自殺」「事件」「火事」などのキーワードで検索してみると、ニュース記事や掲示板の書き込みが見つかることがあります。
特に地元のニュースサイトやSNSは、過去の出来事が記録として残っていることが多く、思わぬ情報源になることもあります。
検索する際は、漢字と平仮名の両方で試すなど、表記を変えて調べるのもコツです。「○○マンション 自殺」だけでなく「○○マンション 事件」や「○○マンション 火事」など複数のワードを組み合わせると、より幅広い情報が拾えます。
もちろんネット上の情報は真偽が不明なものも含まれるため、見つけた内容を鵜呑みにせず、不動産会社など他のルートでも確認して裏付けを取ることが大切です。
調査方法④:家賃が相場より安い理由を調査する
家賃が周辺の物件と比べて極端に安い場合、そこには理由があることも珍しくありません。立地や築年数、設備面で大きな差がないのに、家賃だけが目立って低い場合は、過去の事故や事件が影響している可能性を考えたほうがいいでしょう。
事故物件は心理的な敬遠感から入居希望者が集まりにくく、オーナーが空室を避けるために相場よりも安い家賃を設定しているケースが少なくありません。
確認する際は、同じエリア、同じ間取り、築年数が近い物件と比較することがポイントです。不動産ポータルサイトや賃貸情報サイトを活用すれば、複数の物件の家賃を並べて比較できます。
少し調べるだけでも相場の感覚が見えてきますし、家賃が低い理由を推測しやすくなります。もちろん家賃の安さが必ずしも事故物件を意味するわけではなく、例えば日当たりの悪さや交通の便など他の理由も考えられます。
調査方法⑤:不動産会社に聞いて確かめる
最もシンプルで確実なのは、担当している不動産会社に直接聞いてみることです。宅地建物取引業法では、仲介業者には事故物件であることを契約前に伝える義務があり、質問された場合に虚偽の説明をすることは許されていません。
内見の際や問い合わせ時に「この物件に心理的瑕疵はありますか?」と率直に質問するのが基本です。言葉にしにくいと感じるかもしれませんが、業者にとっては日常的に受ける質問のひとつで、特別なことではありません。
なお、告知義務がないケース(例えば賃貸で事故から3年以上経過した場合)もあるため、必ずすべてが伝えられるとは限りません。
調査方法⑥:建物名の変更や履歴をチェックする
意外と見落とされがちなのが、建物名の変更履歴です。マンションやアパートの名前が過去から変わっている場合、イメージを刷新するためにリネーミングされた可能性があります。
もちろん、単純にオーナーが変わっただけということもありますが、中には事故や事件があったことをきっかけに名前を変更したケースも存在します。
確認する方法としては、過去の不動産広告や販売資料を調べてみるのも手段の1つです。不動産ポータルの古い掲載情報や、ネット掲示板、ストリートビューの過去画像が役立つ場合もあります。こうした情報を集めると、「数年前まで別の名前で募集されていた」「急に名前が変わった」という動きが見えてきます。
事故物件について調べられるサイト一覧
事故物件を見極めるとき、ネット上で公開されている情報を活用すれば無料で調べられます。代表的なサイトとしては、以下のとおり。
- 大島てる
- UR賃貸住宅
- JKK東京
- 成仏不動産
- レインズ(※業者用)
各サイトについて、個別にみていきましょう。
大島てる
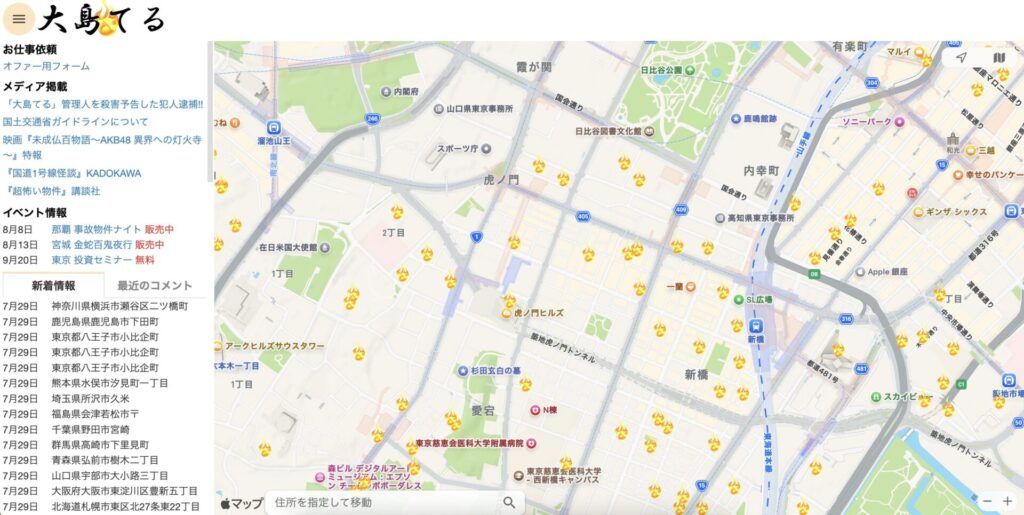
(出典:大島てる)
事故物件を調べるサイトといえば「大島てる」を思い浮かべる人も多いでしょう。地図上に火のアイコンが表示され、事件や事故が起きた場所をひと目で確認できるのが特徴です。
ユーザーが投稿した情報が中心ですが、新聞記事やニュースをもとにした記録もあります。掲載内容には「○年に自殺」など具体的な出来事が書かれていることもあり、調査の出発点として使いやすいサイトです。
ただし、投稿内容はあくまで一般ユーザーによるもので、情報が古いまま残っていることや、確定していない噂が含まれていることもあります。見つけた情報は鵜呑みにせず、不動産会社や他の調査方法とあわせて確認する姿勢が必要です。
UR賃貸住宅

(出典:UR賃貸住宅)
独立行政法人都市再生機構(UR)が運営する「UR賃貸住宅」のサイトでは、募集している物件情報を確認できます。URの物件は礼金や仲介手数料が不要な点がよく知られていますが、実は告知事項ありの部屋が掲載されることもあります。
つまり、事故物件であっても正直に「告知事項あり」と明記された状態で募集されるケースがあるのです。
サイト上では「特記事項」や「備考欄」をよく見ることで、事故物件かどうかを把握できることがあります。URは公的機関の管理物件なので、情報の信頼性も高いのが魅力です。
JKK東京

(出典:JKK東京)
東京都住宅供給公社(JKK東京)の公式サイトも、都内で公社賃貸を探す人にとっては便利な存在です。URと同様、JKKも管理している物件については「告知事項あり」かどうかを正確に表示する運用がされています。事故物件である場合は、契約前にきちんと伝えられるため、安心して調べられます。
JKK東京の物件は主に東京都内に限られますが、信頼できる情報源として、事故物件かどうかを確認したいときには候補に入れておきたいサイトです。
成仏不動産

(出典:成仏不動産)
「成仏不動産」は、事故物件専門の不動産会社が運営するサイトです。事故物件を隠すのではなく、正面から取り扱うことを掲げており、売却や活用の相談窓口のサービスも提供しています。
サイトには事故物件の紹介記事や、実際に取り扱った事例が掲載されているため、事故物件の流通実態を知るのにも役立ちます。
レインズ(※業者用)
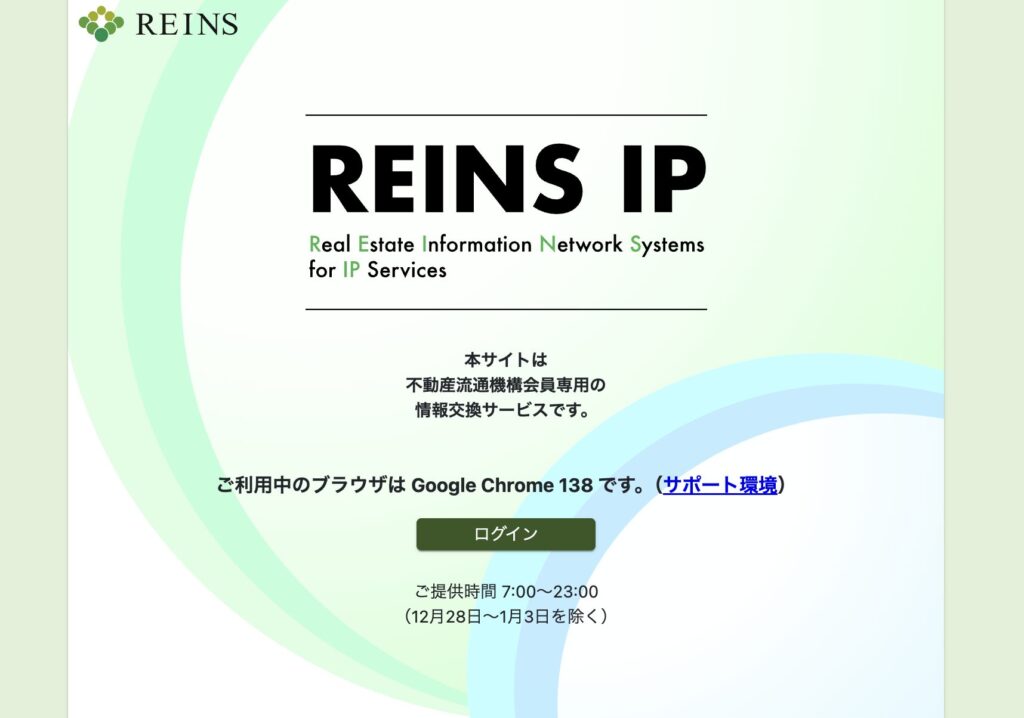
(出典:レインズ)
「レインズ(REINS)」は、宅建業者が物件情報を共有するために使う専用システムです。本来は不動産会社向けで、一般の個人が直接アクセスして詳細を確認することはできません。
しかし、レインズに登録されている物件情報は業者を通して提供されるため、「この物件はレインズでどう扱われていますか?」と質問すれば、不動産会社から確認してもらうことが可能です。
【要注意】調べても事故物件と見抜けないケースとは
事故物件を調べる方法はいくつもありますが、どれだけ入念に調べても分からないケースが存在します。ここからは、見抜くのが難しい代表的な3つのケースを紹介します。
ケース①:告知義務がない3年以上前の事故物件
宅地建物取引業法では、物件に関する「重要な事実」を告げることが義務付けられています。しかし、この告知義務は無期限に続くわけではありません。
国土交通省のガイドラインでは、賃貸物件の場合、自殺や事件があったとしても事故から3年以上が経過すれば、心理的瑕疵の告知義務は原則免除されると示されています。
つまり、過去に悲しい出来事があった物件でも、年月が経てば事故物件として扱われなくなる可能性があります。入居者にとっては知りたい情報でも、法律上は伝えなくても良い扱いになるのです。
購入の場合はより厳格で、事故から年数が経っても告知することが求められる場合がありますが、それでも全ての事実が伝わるわけではありません。調べても情報が出てこないのは、こうしたルールが背景にあるのです。
(参考:国土交通省「『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』を策定しました」)
ケース②:本来告知すべきなのに隠される事故物件
もう一つの問題は、告知義務があるのにわざと伝えないケースです。不動産業者や貸主が告知を怠るのは明らかに違法行為ですが、残念ながらゼロとは言い切れないのが実情です。
理由は単純で、事故物件だと告知すると借り手や買い手が減り、空室期間が長くなったり売却が進まなかったりすることを恐れているためです。
宅建業法違反として行政処分を受けるリスクがあるにもかかわらず、隠す判断をする貸主がいないとも限りません。このような場合、入居者側は不動産会社やオーナーからの説明だけを鵜呑みにするのではなく、複数の調査方法を組み合わせて確認する必要があります。
ケース③:事故履歴がリセットされた「ロンダリング物件」
さらに厄介なのが「事故物件ロンダリング」と呼ばれる手口です。これは事故物件に一時的に従業員や知人を住まわせ、入居者がいたという事実を作った上で、「次の入居者には事故物件とは告知しなくてよい」と主張するものです。
宅建業法の解釈としてはグレーゾーンですが、現実にはこうした手法が使われることがあります。短期間の入居であっても「事故後に人が住んだ」という事実を盾に告知義務を免れる狙いです。入居希望者にとっては、こうした物件を外見から見抜くことは非常に難しいため、複数の方法で調べたり、担当者に詳細を尋ねるなど、慎重な姿勢が求められます。
事故物件を相続・購入するのはやめた方がいい?
事故物件を前にしたとき、「価格が安いから」と安易に購入したり、相続したからといってそのまま持ち続けたりする判断には注意が必要です。
事故物件には目に見える損失だけでなく、時間をかけてじわじわ効いてくるリスクがあります。ここからは特に深刻になりやすい二つのリスクについて解説します。
リスク①:資産価値の低下リスクが高い
事故物件は一般の物件よりも低く評価されがちです。購入直後から市場価格が安く見積もられ、将来売却を検討しても、希望価格での取引が成立しにくい傾向があります。
買い手にとっては心理的な抵抗があるため、内見の段階で候補から外されることも珍しくありません。
相続したケースでも同様で、財産分与の場面では他の相続人から「処分しにくい物件だから自分は欲しくない」と敬遠されることが多く、分割協議を難しくします。
さらに、事故物件は長期的に持っても資産価値が回復する見込みが薄く、固定資産税や管理費といった維持費だけが重なっていきます。価格が下がるだけでなく、手間やコストがかさむ点も大きな負担となるのです。
リスク②:入居者が見つかりにくい
賃貸運用を考えている人にとっても、事故物件には厳しい現実があります。心理的な抵抗感を持つ人が多く、「事故物件でも構わない」と思う入居希望者は限られているのが実情です。
その結果、家賃を下げて募集せざるを得なくなったり、長期間空室のままになることが珍しくありません。
仮に入居者が決まったとしても、短期で退去するケースが多いのも課題です。何らかの理由で気持ちが落ち着かず、数カ月で解約する入居者もいます。こうなると、家賃収入が安定せず、物件を維持するだけのコストのほうが大きくなってしまう可能性があります。
「貸せばなんとかなる」と思って手を出すと、予想以上の空室リスクに悩まされることになるでしょう。
リスク③:周囲の評判や心理的負担が残る
事故物件の大きな問題のひとつは、地域社会に残る記憶です。過去に事件や事故があった物件は、どれほど時間が経っても近隣住民の間で話題に上ることがあります。
購入者が自分で住む場合、挨拶回りをしている時に「あそこは昔…」と耳にするだけで気持ちが沈んでしまうことも珍しくありません。近隣住民が悪意を持っているわけではなくても、ふとした一言や視線が居心地の悪さにつながることがあります。
さらに、自分や家族がその場所で暮らすうちに、過去の出来事を無意識に思い出してしまうこともあります。
昼間は平気でも「夜になると気になる」「特定の部屋に入れない」といった心理的負担は数値で測れませんが、日常生活の質に確実に影響します。安く買えたとしても、こうした無形のリスクは思った以上に大きく、後悔を生む要因になりやすいのです。
リスク④:将来的なトラブル発生の可能性
事故物件を所有するということは、その後の取引で「説明する立場」になることを意味します。将来、売却や賃貸に出すとき、過去の事故や事件を相手に告げる義務が生じます。これを怠ると契約解除や損害賠償請求といった法的トラブルに発展するおそれがあります。
さらにやっかいなのは、この責任が時間を経ても消えにくい点です。賃貸であれば事故から数年経過すれば告知義務が緩和されることもありますが、売却の場合はより厳格で、相当な年月が経っても説明責任を求められることがあります。
こうした義務を抱えたままでは「いつか売ろう」と思っても相手が見つからず、結局は維持費だけが重なり続ける負の資産になりかねません。事故物件を持つということは、目先の値段以上に長期的な責任を背負うことだと理解しておく必要があります。
事故物件をすでに相続・購入してしまった場合の対処法
気づいたときにはすでに事故物件を相続していた、あるいは購入してしまった──そんな状況に立たされたとき、感情的に動くと選択肢を狭めかねません。
重要なのは、まず現状を正確に把握し、冷静にできることを考えることです。対処法は一つではありませんが、特に最初に検討しておきたい4つの方法を紹介します。
- 対処法①:事故物件であることを受け入れて活用方法を検討する
- 対処法②:リフォームや用途変更でイメージを一新する
- 対処法③:事故物件専門の不動産会社に売却を相談する
- 対処法④:税務・法務の専門家に相談してリスクを最小化する
次項より、個別にみていきましょう。
対処法①:事故物件であることを受け入れて活用方法を検討する
所有してしまった以上、「事故物件である」という事実を受け入れるところから始めましょう。自分で住む予定がある場合は心理的なハードルが高いかもしれませんが、それでも使い道を限定せずに考えることが大切です。
例えば、賃貸に出すという選択肢があります。事故物件は敬遠されやすいため、家賃を相場よりやや低めに設定する必要がありますが、条件を調整すれば入居者が見つかるケースは多いです。
特に、価格重視で部屋を探す人や、事情を理解したうえで借りる層を狙えば、空室を長期化させずに活用できます。
また、事故物件の扱いに慣れた専門業者に相談し、どの層にアプローチするか、募集方法をどう工夫するかを一緒に考えてもらうのも良い方法です。無理に隠すのではなく、情報をきちんと開示しながらターゲットを絞ることで、活用の幅が見えてきます。
対処法②:リフォームや用途変更でイメージを一新する
心理的瑕疵の大きな課題は「過去のイメージ」が物件にまとわりつくことです。これを和らげる上では、リフォームや用途変更という選択肢があります。
壁紙や床材の張り替え程度ではなく、間取りを変更するほどの大規模リフォームを行えば、見た目や雰囲気は大きく変わります。「同じ部屋」という印象を薄められれば、借り手や買い手の心理的な抵抗を減らす効果が期待できます。
さらに、住宅用途にこだわらず、シェアハウスや事務所、アトリエといった別の用途に転用することも考えられます。利用目的を変えるだけで求められる条件が違い、住居としては敬遠される部屋でも、新しい使い道が見つかることがあります。
こうした工夫をすれば、「使えない物件」だと思っていた不動産が再び価値を持ち始める可能性があるのです。
対処法③:事故物件専門の不動産会社に売却を相談する
自分で住むことも貸し出すことも難しい場合、事故物件を専門に扱う不動産会社への売却を検討するのが現実的です。一般的な市場では事故物件は敬遠され、買い手が見つかるまでに時間がかかるうえ、価格も大きく下がりがちです。
しかし、専門会社は事故物件の取引経験が豊富で、事情を理解したうえで対応してくれます。
こうした業者は、事故物件の買取後にリフォームして販売したり、賃貸用として活用するノウハウを持っています。そのため、相場を踏まえた価格でスピーディーに買取を進めるケースが多いのです。特に、維持費の負担を減らしたい、相続した物件を早く手放したいという場合には心強い選択肢といえるでしょう。
対処法④:税務・法務の専門家に相談してリスクを最小化する
事故物件を所有すると、売却や賃貸の際に告知義務を背負うことになります。これを怠ると契約解除や損害賠償請求といった法的トラブルに発展する可能性があります。
こうしたリスクを減らすためにも、不動産に詳しい弁護士や税理士といった専門家に早めに相談しておきましょう。
特に相続で得た事故物件は、税務面でも複雑です。相続税の申告や、場合によっては相続放棄や限定承認といった手続きを検討することもあります。こうした判断を誤ると、後々大きな負担となりかねません。
専門家に状況を伝え、どの方法が最も安全で負担の少ない道かを一緒に考えてもらうことで、事故物件を持つことによる将来のトラブルを最小限に抑えられます。
「ワケガイ」なら事故物件も短期で買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり物件の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。共有持分や再建築不可の土地、長く放置された空き家やゴミ屋敷、さらには事故物件など、一般の不動産市場では売却が難しい物件も幅広く取り扱っています。
これまで全国で数多くの買取実績を重ね、最短1日で現金化を希望されるケースにも対応してきました。査定から契約、決済までの流れもスピーディで、余計な仲介手数料もかかりません。時間や手続きの負担を軽くしたい方にとって、シンプルかつ安心できる選択肢です。
事故物件や訳あり不動産をどうするか悩んでいる方は、まずはお気軽に無料査定をご活用ください。
事故物件を調べる方法に関するよくある質問
事故物件はバレる?聞かれたら答える義務はある?
宅地建物取引業法では、不動産会社や仲介業者に事故物件であることを告げる義務があります。ただし、個人オーナーが自ら貸す場合は、同じような法的義務が明確ではない部分もあります。
とはいえ、入居者に「事故物件ですか」と尋ねられた場合、後から隠していたと分かるとトラブルに発展する可能性があります。無用な争いを避けるためにも、分かっている範囲の情報を正直に伝えることが最善といえます。
事故物件は内見のときに教える必要はある?
事故物件に関する告知は、宅地建物取引士が行う「重要事項説明」の段階で伝えることが原則です。つまり、内見のときに自動的に教えてもらえるとは限りません。
内見時に不安があるなら、「この物件に心理的瑕疵はありますか?」と質問して確認するのが確実です。業者にとっては日常的な質問であり、遠慮する必要はありません。
スーモなどポータルサイトで事故物件は見分けられる?
スーモやホームズといった大手賃貸ポータルには、事故物件専用の検索機能はありません。物件詳細の備考欄に「告知事項あり」と書かれるケースもありますが、すべての物件がそう記載されるわけではないため、掲載情報だけで判断するのは難しいのが実情です。
事故物件の可能性を確認するなら、「大島てる」などの外部サイトを併用し、複数の不動産会社に尋ねるなど、情報源を増やして調べましょう。
まとめ
事故物件は心理的な抵抗感が大きく、知らずに契約してしまえば、引っ越し後に後悔するだけでなく、売却や解約に伴う金銭的な負担にも直結します。
リスクを回避するためには、不動産会社の説明だけに頼らず、自分でも積極的に調査する姿勢が必要です。本稿で紹介した大島てるなどの専門サイトで過去の事故情報を探す。あるいは周辺住民や管理会社にさりげなく確認するといった行動が後の安心につながります。
さらに、契約直前には必ず「心理的瑕疵はありますか」と質問し、重要事項説明の内容をしっかり確認してください。「調べる→質問する→確かめる」という3ステップを意識することで、事故物件を避け、納得のいく結果に繋げましょう。
運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |