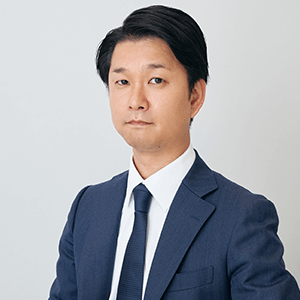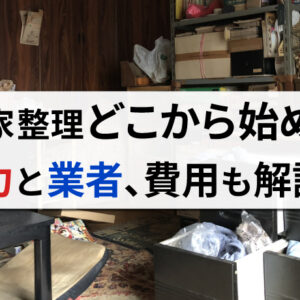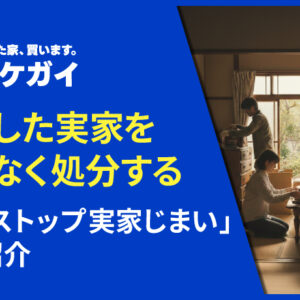こんにちは。ワケガイ編集部です。
相続や転勤などで空き家を所有したものの、固定資産税や維持費だけがかかり続けてしまうケースでは、大きな経済的負担や老朽化による近隣トラブルといった問題が発生します。
その際に選択肢となるのが「空き家ビジネス」です。空き家ビジネスとは、使われていない住宅や土地を有効活用し、収益を得たり地域の価値を高めたりする取り組みのことです。民泊や賃貸、駐車場経営、さらにはレンタルスペースなど多様な形が存在します。
そこで本記事では、空き家ビジネスの基本的な仕組みから、代表的なビジネスモデル、メリット・デメリット、成功のポイントまでを幅広く解説します。
について今すぐご相談できます。
お電話する
目次
空き家ビジネスとは?
空き家をただ持ち続けるだけでは、固定資産税や管理費といった出費が重なり、所有者にとって負担となります。しかし見方を変えれば、放置されていた建物や土地は「新しい収益源」へと変えられる可能性があります。
空き家ビジネスは、使われなくなった住宅や土地を再活用し、収益を生み出す手法です。民泊や賃貸住宅、駐車場経営などの身近な事例から、地域の観光資源として古民家を活かす試みまで、多様なモデルがあります。
社会的課題を解決しながら利益を得ることができるため、重要度は年々高まっています。ここからは、その背景と注目される理由を見ていきましょう。
全国的に拡大する空き家問題
総務省の調査によると、日本の空き家は増加の一途をたどり、2023年時点で全国で900万戸を超える規模に達しています。人口減少と高齢化の影響で、相続や転居の後に利用されないまま残される住宅が多いことが背景にあります。
(参考:総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果」)
地方では特に深刻で、誰も住まなくなった家がそのまま朽ち果て、景観や治安への懸念を招いている地域も少なくありません。空き家を放置すれば、倒壊や火災といった危険性が増し、近隣住民とのトラブルにつながることもあります。
さらに固定資産税の負担は続き、所有者は費用面でも悩まされます。こうした状況が広がるなか、空き家を「社会の課題」として捉える動きが強まり、行政や民間が協力して新たな活用策を模索するようになっているのです。
なぜ空き家活用が注目されるのか
空き家を活用することが注目を集める背景には、二つの側面があります。ひとつは経済的な側面で、所有者が維持費や税金だけを負担するよりも、賃貸や民泊として収益化した方が合理的だという点です。
駐車場やトランクルームなど、比較的低コストで始められる事業もあり、個人が参入しやすい環境が整ってきました。
もうひとつは社会的な側面です。
使われていない住宅をリノベーションして店舗やコミュニティ施設にすれば、地域に人の流れを取り戻すきっかけになります。地方創生や観光振興の文脈で、空き家を新しい価値に変える事例が各地で生まれているのもそのためです。
個人の利益と地域全体の課題解決を両立できる点こそが、空き家活用が広く注目される理由といえるでしょう。
空き家を使ったビジネスモデル10選
空き家を活用したビジネスにはさまざまな形があります。ここからは代表的なモデルを取り上げ、それぞれの収益性や初期投資の規模、運営の難しさや市場の広がり方に注目して解説していきます。
- 民泊経営
- 空駐車場経営
- カフェ経営
- シェアハウス経営
- 収納スペース事業
- 賃貸経営
- サテライトオフィス
- 介護施設
- コワーキングスペース
- バイクガレージ
単なるアイデア紹介ではなく、実際に取り組む上でどのような点に着目すべきかもセットでみていきましょう。
空き家を活用した民泊経営
訪日外国人の増加や国内旅行の多様化により、インバウンド客が増えている昨今、民泊は依然として高い需要を見込めます。空き家を改装して宿泊施設にすれば、賃貸よりも高い収益を見込めることも少なくありません。
(参考:e-Gov 法令検索「住宅宿泊事業法」)
特に観光地や都市部のアクセスが良い地域では、稼働率が安定すれば利回りは大きく伸びるでしょう。
一方で、民泊新法による営業日数の制限や、近隣住民とのトラブルを避けるための運営体制が求められる点は注意が必要です。
初期投資はリフォーム費用や家具・設備の導入に加え、消防・保健所の基準を満たすコストも発生します。こうしたハードルをクリアするため、運営代行サービスを利用して収益化を図るオーナーも増えています。
市場規模は今後も観光需要とともに拡大が期待されますが、法規制や管理コストを考慮に入れて計画を立てることが大切です。
関連記事:空き家を使った民泊の始め方とは?費用や手順についてわかりやすく紹介
空き家を活用した駐車場経営
建物を解体して更地にした上で駐車場として活用する方法は、空き家ビジネスのなかでも比較的手堅い選択肢となります。コインパーキング形式にすれば利用単価は高くなりますが、精算機や舗装工事などの初期投資がかかります。
対して、月極め駐車場であれば整地や簡易な区画整理だけでも始められ、初期費用は抑えられるものの、収益性は地域の需要に大きく左右されます。
運営の難易度は低めで、日常的な管理の負担も少ない点は魅力です。ただし、立地条件によっては空き区画が長期化しやすく、思ったように収益が上がらないケースもあります。
都市部や駅周辺では安定した需要が見込める一方、地方では採算が合いにくい場合もあるため、市場調査を徹底する必要があります。リスクを抑えつつ安定収入を狙うなら、駐車場経営は検討に値する活用法といえるでしょう。
空き家をリノベーションしたカフェ経営
空き家をリノベーションしてカフェとして経営する方法は、収益だけでなく地域活性化の観点からも注目されています。古民家や築年数のある住宅を改装したカフェは、独自の雰囲気やストーリー性が生まれやすく、SNS映えを狙った集客が可能です。
初期投資は内装工事や厨房設備の導入に加え、耐震補強や水回りの改修といったコストが発生するため、数百万円単位の資金を見込む必要があります。
運営難易度は高めで、飲食業の経験やスタッフの確保、安定した集客戦略が必須。収益性は立地やコンセプトに大きく左右され、観光地や人通りの多いエリアでは成功例も多いですが、地方や郊外では固定客の獲得が課題になります。
単なる飲食店経営ではなく、地域コミュニティの場として位置づけることでリピーターを増やし、持続的な事業に育てていくことが求められます。
空き家を使ったシェアハウス経営
若年層や外国人労働者を中心に一定の需要があるのがシェアハウスです。空き家を複数の個室と共有スペースに分けることで、低家賃で提供しながら安定した収入を得ることができます。
初期投資は個室化のためのリフォームや共有設備の整備などで数百万円程度が目安となり、賃貸経営に比べればやや高めです。
運営難易度も高く、入居者間のトラブル対応や生活ルールの設定、清掃管理などの手間が発生します。収益性は稼働率に直結するため、ターゲットを学生、外国人、単身社会人など明確に定め、需要に合ったエリアで展開することが大切です。
都市部では高稼働を維持しやすく市場性がある一方、地方では入居者募集に苦戦する場合も少なくありません。空き家を住宅として再活用するなかでも、オーナーの運営力が試されるビジネスモデルといえるでしょう。
空き家を使った収納スペース事業
近年需要が伸びているのがトランクルームや収納スペース事業です。空き家の内部を仕切り、収納専用のスペースとして貸し出すことで、比較的安定した収益を得られます。
初期投資は改装費用とセキュリティ設備の導入程度で済むため、他の事業に比べれば低コストで始めやすいのが特徴です。運営難易度は低く、入居者管理や日常的なメンテナンスは限定的ですむことが多いでしょう。
ただし収益性はエリア特性に左右されやすく、都市部では需要が高く単価も上がりやすい一方、地方では採算が合わないケースもあります。
市場性としては、ライフスタイルの多様化や住宅の狭小化により今後も拡大が予想されますが、地域の需要を正しく見極めることが前提となります。低リスクで始めたいオーナーに適したモデルといえるでしょう。
空き家を貸し出す戸建て賃貸経営
空き家をリフォームし、戸建て賃貸として貸し出すのは最もオーソドックスな方法です。ファミリー層やペット飼育を希望する層から一定の需要があり、安定した家賃収入を見込めます。
ただし、築年数の古い物件は水回りや屋根、外壁といった大規模修繕が必要になる場合があり、初期投資がかさむ可能性があります。収益性はリフォーム費用と賃料設定のバランスに左右され、利回りが低下しやすい点には注意が必要です。
運営難易度は低めですが、空室期間が長引くと収益計画が崩れるリスクもあります。市場性としては、都市近郊では依然として需要が強く、地方でも学校や駅に近い立地であれば安定した入居が期待できます。
空き家を比較的堅実に活用したい人にとって、戸建て賃貸は王道の選択肢といえるでしょう。
空き家をサテライトオフィスとして運営
企業のリモートワークや分散型勤務が広がるなか、空き家をサテライトオフィスとして整備する動きが注目されています。特に地方自治体では、企業誘致による雇用創出や移住促進を目的に、補助金や助成制度を設ける例もみられます。
収益性は、オフィス利用契約を結ぶことで安定した賃料収入が見込める一方、需要は地域差が大きい点に注意が必要です。初期投資はインターネット環境や空調、会議室設備の整備に加え、耐震・防火基準を満たすための改修費用がかかります。
運営難易度は低めで、企業と長期契約を結べれば安定性は高まりますが、利用者が少ないエリアでは採算が合いにくいこともあります。地方と都市をつなぐ働き方が広がるなか、自治体との連携を活用すれば事業性を高められるモデルです。
空き家を介護施設として経営
高齢化が進む日本では介護施設への需要が年々高まっています。
ただし、空き家を大規模に改装し、小規模多機能型施設やデイサービス拠点として運営する方法は、社会的意義が大きい一方で、事業性の観点からは高いハードルがあります。初期投資はバリアフリー化や耐震補強、入浴設備の導入などで数千万円単位に及ぶことも少なくありません。
また、介護報酬制度を利用するためには各種の認可や指定を取得する必要があり、行政手続きに時間と労力を要します。
さらに、慢性的な人材不足が課題となる介護分野では、スタッフの確保と教育が経営を左右します。収益性は安定しているものの、運営難易度は高く、長期的な視点で取り組む必要があります。
地域の高齢化率や行政支援の有無を踏まえ、慎重に計画することが欠かせないモデルです。
空き家をコワーキングスペースとして運営
リモートワークの普及に伴い、コワーキングスペースは都市部だけでなく地方でも需要が高まっています。空き家をリノベーションしてデスクやWi-Fi環境を整えれば、比較的低コストで開業可能です。
収益性は会員制や時間貸しなど料金体系によって異なり、安定した利用者を獲得できれば継続的な収入が見込めます。
ただし、立地によっては集客に苦戦することもあり、ターゲットとなるフリーランスやリモートワーカーがどの程度存在するかを見極める必要があります。運営難易度は中程度で、清掃や設備管理のほか、利用者同士の交流イベントなどを企画すれば差別化につながります。
市場性は今後も拡大傾向にあり、特に「ワーケーション」需要が伸びる地域ではチャンスが広がっているといえるでしょう。
空き家を活用したバイクガレージ経営
都市部を中心に一定の需要を持つのが、バイク専用のガレージ経営です。バイク利用者は盗難や風雨による劣化を避けるため、安全な保管場所を求めています。
空き家の敷地や建物を改装し、専用スペースとして月極で貸し出せば、固定的な収入を得ることが可能です。
初期投資はシャッターやセキュリティ設備の設置、簡単な区画工事程度で済む場合が多く、比較的低コストで始められます。運営難易度は低めで、入居者管理や設備点検が中心となり、日常的な対応は少なくて済みます。
市場性はニッチながら安定しており、大都市圏では特に高い需要が見込めます。大きな収益を狙うモデルではありませんが、限られた空きスペースを活かし、着実に収益を積み上げられる点が特徴です。
空き家を解体して土地のみで行うビジネスモデル5選
建物をそのまま活用するのが難しい場合でも、空き家を解体して更地にすれば新たな収益モデルを展開できます。特に都市部や人の往来が多い地域では、土地ならではの活用方法に安定した需要が見込めます。
ここからは代表的なビジネスを取り上げ、収益性や参入のしやすさを解説します。
- コインパーキング経営
- トランクルーム・コンテナ設置事業
- 貸し農園・市民農園として運営
- 太陽光発電事業
- 資材置き場・車両置き場として貸し出す
次項より、詳しく解説します。
コインパーキング経営
更地活用の代表格といえるのがコインパーキングです。都市部や駅周辺では駐車需要が高く、稼働率次第では安定的な収益を生み出せます。
収益性は立地に大きく左右され、オフィス街や繁華街では高回転が期待できます。
一方、郊外では利用が伸びにくく採算が合わない場合もあります。初期投資は舗装工事やライン引き、精算機の設置などが必要で数百万円規模になることもありますが、オーナーが土地を提供し、運営会社が設備投資や管理を行う「一括借り上げ方式」を選べば、負担を抑えて安定収入を得ることも可能です。
運営難易度は比較的低く、利用者対応はほとんどありません。市場性としてはカーシェアやレンタカー需要とも結びつき、今後も一定の需要が続くと考えられます。
トランクルーム・コンテナ設置事業
住宅事情の変化から収納ニーズが高まり、トランクルームやコンテナ型収納事業は拡大を続けています。空き地にコンテナを並べ、収納スペースとして貸し出す方式は、建物を建てるよりも初期投資が抑えられる点が魅力です。
設置費用やセキュリティ設備の導入を合わせても比較的低コストで始められ、短期間で事業化が可能です。収益性はエリアによって差があり、都市部や住宅密集地では需要が高く、高利回りを狙える一方、地方では利用者が限られ採算が難しい場合もあります。
運営は契約管理や巡回点検が中心で難易度は高くなく、清掃や修繕も限定的です。市場性としてはライフスタイルの多様化に伴い、一定の拡大が見込まれる分野であり、土地を有効に使いたいオーナーに適したモデルといえるでしょう。
貸し農園・市民農園として運営
都市部に住む人が週末だけ農作業を楽しむ「貸し農園」は、趣味需要に支えられて安定した人気があります。空き家を解体してできた土地を区画ごとに分け、利用者に貸し出す仕組みは、初期投資が少なく済む点が特徴です。
必要となるのは水道の確保や土壌整備、簡易な区画分け程度であり、大規模な建設工事は不要。収益性は利用料の設定に依存しますが、都会からのアクセスが良い郊外であれば需要が見込め、年間契約で安定収入につながります。
運営の難易度は低めですが、農業経験がある管理人を置く、あるいは収穫体験イベントを開催するなど、付加価値を加えることで競合との差別化が可能です。
市場性としては健康志向や自然回帰の流れも追い風となり、地方創生や観光と組み合わせれば発展性のあるモデルといえるでしょう。
太陽光発電事業
広さのある更地を活用するなら、太陽光発電事業という選択肢があります。土地にソーラーパネルを設置し、発電した電力を売電することで収益を得る仕組みです。
初期投資はパネルや設備一式の導入に数百万円から数千万円規模が必要で、参入ハードルは高めでしょう。
ただし、国の再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)を利用すれば、一定期間は安定した売電収入が得られるため、長期的に見れば収益性は比較的高い事業といえます。運営難易度は低く、日常的なメンテナンスは業者に委託できるため、オーナー自身の負担は少なめです。
市場性は再生可能エネルギー需要の高まりで堅調ですが、近年は買取価格の下落や新規認可の厳格化も進んでおり、計画段階で収益予測を慎重に立てることが不可欠です。長期安定収入を目指す土地活用として有力なモデルといえるでしょう。
資材置き場・車両置き場として貸し出す
建設業者や運送業者を対象に、土地を資材置き場や車両置き場として貸し出す方法は、都市部だけでなく郊外でも一定の需要があります。特に建設現場が多い地域や物流拠点に近いエリアでは、安定した利用が期待できます。
初期投資はほとんどかからず、整地や簡易フェンスの設置程度で始められるため、土地活用のなかでは低コストの部類に入ります。収益性は利用料設定に依存しますが、長期契約を結びやすいため安定的な収入を得やすい点が強みです。
運営難易度も低く、管理は基本的に区画の確認や利用者との契約対応程度にとどまります。
市場性としては、都市開発や物流需要が続く限り安定したニーズがありますが、立地条件による差が大きいため、貸し出し先の業者を事前に確保できるかどうかが成功の分かれ目になります。
空き家ビジネスのメリット
空き家はそのままでは維持費や固定資産税の負担が続くばかりですが、工夫次第で新たな価値を生み出す資源に変わります。空き家をビジネスに活用することで得られる代表的なメリットとしては、次のものが挙げられます。
- 遊休資産を収益源に変えられる
- 初期費用を抑えて参入できる
- 地域活性化につながる
次項より、個別にみていきましょう。
遊休資産を収益源に変えられる
相続や転居などで所有することになった住宅は、誰も住まなければ「負担」になりがちです。固定資産税や維持管理費だけが出ていき、資産としての価値は年々下がってしまいます。
空き家ビジネスの大きな利点は、この遊休資産を収益を生む存在に転換できる点です。
空き家をリフォームして賃貸住宅にすれば安定した家賃収入が得られますし、立地によっては民泊やシェアハウスのほうが高い収益を見込める場合もあります。駐車場やトランクルームといった用途なら大規模な改修が不要なため、比較的短期間で収益化が可能です。
所有者にとっては「費用がかかるだけの空き家」が「利益を生む資産」に変わることで、経済的な安心感を得られるでしょう。
初期費用を抑えて参入できる
不動産ビジネスというと大きな投資が必要なイメージを持つ方も多いですが、空き家を活用する場合は比較的低コストで参入できるケースもあります。すでに土地と建物を所有しているため、新たに不動産を購入する費用が不要だからです。
特に駐車場経営やコンテナ設置型のトランクルームなどは、数十万円から数百万円程度の投資で始められる例もあります。また、古民家を簡易的に改修してレンタルスペースとして貸し出すといった形であれば、工事費用も抑えられるでしょう。
もちろん全面的なリノベーションを行う場合は相応の資金が必要ですが、活用方法を選べば「小さく始める」ことが可能です。大きなリスクを抱えず、段階的に収益を伸ばしていける点は、他の投資商品にはない魅力といえます。
地域活性化につながる
空き家ビジネスは所有者の利益にとどまらず、地域社会にも好影響をもたらします。放置された住宅は景観を損ねたり、防犯上の不安を与えたりする存在ですが、店舗やコミュニティ施設として生まれ変われば、人の流れが戻り地域に活気が出ます。
古民家をカフェにリノベーションすれば観光資源として注目され、周辺の商店街にも波及効果をもたらします。
また、シェアハウスや子育て支援施設として活用することで、住民同士の交流が増え、地域全体の結びつきが強まります。
こうした取り組みは自治体の支援対象となることもあり、補助金や助成制度を活用できる場合もあります。空き家を活用することが、所有者にとっての収益化であると同時に、地域課題の解決策として機能する点は大きな魅力です。
空き家ビジネスのデメリット
空き家を活用することで収益や地域への貢献を期待できる一方、現実には負担やリスクも存在します。ここからは、空き家ビジネスを検討する際に多くの人が直面しやすい代表的な課題を解説します。
- 初期投資や維持管理コストがかかる
- 法規制や許認可のハードルがある
- 経営ノウハウや運営スキルが求められる
以下より、個別にみていきましょう。
初期投資や維持管理コストがかかる
空き家を活用するには、必ずしも「すぐに貸せる」状態ではありません。築年数の経過した物件は、屋根や外壁、水回りなどの修繕が必要となるケースが多く、リフォーム費用は数百万円単位に及ぶこともあります。加えて、家具や設備を整える費用も発生します。
事業化した後も、固定資産税や保険料、清掃や修繕といった維持管理コストは継続してかかり続けます。収益が安定するまでの期間は赤字を抱える可能性があるため、投資額と予想収入のバランスを慎重に見極めなければなりません。
初期投資を抑えられるモデルもありますが、十分な資金計画がないと、せっかくの空き家ビジネスが経済的な負担に転じてしまいます。
法規制や許認可のハードルがある
空き家を事業に活用する際には、用途によってさまざまな法規制が関わります。民泊であれば「住宅宿泊事業法」に基づく届け出が必須で、消防法や建築基準法も遵守しなければなりません。
(参考:e-Gov 法令検索「住宅宿泊事業法/消防法/建築基準法」)
飲食店やカフェに改装するなら、保健所の許可や衛生基準への対応が不可欠です。こうした法規制は事業の安全性を確保するためのものですが、手続きや改修に時間と費用がかかる点は大きなハードルとなります。
さらに自治体によって独自の条例がある場合もあり、全国一律で考えることはできません。許認可を得られないことで計画が頓挫するケースもあるため、事業を始める前に地域の規制や行政窓口での確認を欠かさないことが求められます。
経営ノウハウや運営スキルが求められる
空き家ビジネスは「空き家を貸せば終わり」ではなく、事業として継続的に運営していく力が必要です。賃貸であれば入居者募集や契約管理、民泊なら清掃や宿泊者対応、カフェやシェアスペースなら集客やサービスの質を維持する努力が求められます。
こうした運営には、経営の基本知識やマーケティング感覚、顧客対応のスキルが必要でしょう。不動産管理の経験がない人にとっては学習コストが大きく、思うように収益を上げられないリスクもあります。
専門業者に一部を委託する方法もありますが、その分コストは増えるため、オーナー自身がどこまで関わるかを見極めなければなりません。資産を動かすだけではなく「経営者」としての意識が問われる点は、空き家ビジネスならではの難しさといえるでしょう。
空き家ビジネスで儲けを出すためには何が必要?
空き家を活用して事業を始めても、必ずしも収益が上がるわけではありません。成功するためには、思いつきではなく現実的な計画と準備が必要です。
空き家ビジネスで収益を確保する上では、以下の視点が求められます。
- 立地条件と需要の見極め
- 初期投資とランニングコストの管理
- 法規制や許認可の確認
- ターゲットに合わせた活用方法の選定
- 集客力を高める運営ノウハウ
- 補助金や税制優遇の活用
次項より、個別にみていきましょう。
立地条件と需要の見極め
空き家ビジネスの成否を大きく分けるのは立地です。観光地や駅の近くであれば民泊やカフェ、都市部の住宅街であればシェアハウスや収納スペース、郊外で広い土地があるなら駐車場や農園といった形が適しています。
つまり、ビジネスモデルは物件の立地と需要に応じて選ぶ必要があります。需要を見誤ると、改装や設備投資をしても利用者が集まらず赤字に陥ることも珍しくありません。
収益化を目指すなら、地域の人口動態や観光客数、競合施設の有無を調査し、どのような需要が存在するのかを冷静に見極めるようにしましょう。
初期投資とランニングコストの管理
どれだけ魅力的なビジネスモデルでも、費用がかさみ過ぎれば採算は合いません。空き家の改修費や設備導入費はもちろん、開業後に発生する固定資産税や清掃費、光熱費といったランニングコストも含めて収支を見積もることが大切です。
特に築古物件の場合は、当初の見積もり以上に修繕費がかかることもあり、余裕を持った資金計画が必要になります。収益性を高めるには「初期投資を抑えつつ、継続的なコストを最小限にする工夫」が不可欠です。
例えば駐車場や収納スペースのような事業は人件費がほとんどかからず、コストを抑えて安定した収益を狙えます。
法規制や許認可の確認
空き家を事業に活用する際には、必ず法律や条例の確認が求められます。具体的には、以下のように、それぞれの法令に基づく指定を受けなければ運営できません。
- 民泊:住宅宿泊事業法、消防法」
- 飲食店:食品衛生法、保健所の許可
- 介護施設:介護保険法
さらに自治体ごとに独自の条例を定めている場合も多く、想定していた用途が認められないこともあります。法的な要件をクリアするには、事前に自治体や専門家へ相談し、必要な手続きや改修内容を確認しておくことが不可欠です。
許認可を軽視すると、後になって営業停止や追加費用の発生につながるリスクがあり、収益化どころか大きな損失を抱える恐れがあります。
ターゲットに合わせた活用方法の選定
空き家ビジネスで成果を出すには、誰に向けて提供するのかを明確にした上で活用方法を選ぶことが大切です。
実際、観光地であれば短期滞在者をターゲットに民泊やゲストハウス、大学や専門学校の近隣であれば学生向けのシェアハウスが適しています。
逆に、ファミリー層が多い地域では、戸建て賃貸のほうが安定的な需要を見込めるでしょう。ターゲットを誤ると、せっかく改修しても利用者が集まらず、投資が無駄になりかねません。
収益化を目指すなら「立地とターゲットの一致」が最も大きなポイントになります。空き家をどう活用するかを考える際には、地域の人口構成やライフスタイルの傾向を分析し、具体的な利用者像をイメージした上で事業計画を立てることが求められます。
集客力を高める運営ノウハウ
どれだけ立地条件が良くても、利用者がその存在を知らなければ事業は成り立ちません。
空き家ビジネスを成功させるには、集客の工夫が必要です。インターネット上での広告や予約サイトへの掲載はもちろん、SNSを使って施設の魅力を発信する方法も効果的です。
特に民泊やカフェ、コワーキングスペースなどは写真や口コミが利用者の意思決定に大きく影響するため、情報発信の質が収益を左右します。また、地域のネットワークを活かして自治体や観光協会と連携すれば、集客の間口を広げることが可能です。
運営ノウハウとは単に利用者対応にとどまらず、プロモーションやブランディングを通じて利用者に選ばれる存在になることです。安定的な稼働率を維持するためには、集客力を磨き続ける姿勢が必須です。
補助金や税制優遇の活用
空き家ビジネスは初期投資や運営コストが負担になることがありますが、国や自治体の制度をうまく活用すればリスクを軽減できます。
空き家再生に関する補助金やリフォーム費用の一部を助成する制度、さらには耐震改修や省エネ改修を行った際の減税措置などが用意されています。
また、地域活性化を目的とした交付金や、子育て支援施設・高齢者施設などに用途を転換した場合の助成制度も存在します。こうした制度は地域によって内容が異なるため、自治体の窓口や公式サイトで最新情報を確認しましょう。
補助金や税制優遇を適切に利用すれば、投資のハードルを下げながら事業をスタートでき、収益性を高める後押しとなります。
ビジネス目的での活用が難しい空き家は専門業者への買取依頼がおすすめ
空き家の中には立地条件が悪かったり、老朽化が進んでいたりして、事業としての活用が難しいものも少なくありません。改修費用が高額になれば採算が合わず、投資回収ができないリスクもあります。
そのような場合、専門業者に直接買取を依頼するのは有効な選択肢です。ここからは、直接買取を利用することで得られる主なメリットを紹介します。
直接買取のメリット①:早期に現金化できる
不動産仲介を通じて売却する場合、買い手が見つかるまでに数か月から年単位で時間がかかることがあります。これに対して、買取業者なら査定から契約、決済までがスピーディーに進み、数週間で現金化できるケースも珍しくありません。
相続直後で維持費をかけたくない場合や、早急に資金を確保したいときに大きな安心につながります。
直接買取のメリット②:仲介手数料が不要
通常の不動産売却では仲介会社に手数料を支払う必要がありますが、買取業者への直接売却ではその費用がかかりません。手取り金額を減らす要因が一つなくなるため、資金計画を立てやすくなります。
大きな利益が出ない物件であっても、余計なコストを省けるのは所有者にとって大きな利点です。
直接買取のメリット③:老朽化や訳あり物件でも売却可能
空き家の中には、老朽化が進んでリフォーム費用が莫大になるものや、相続トラブルなどで買い手がつきにくい「訳あり物件」もあります。
一般の市場ではなかなか売れない物件でも、買取業者は再生や転用のノウハウを持っているため、そのまま引き取ってくれるケースが多いです。所有者が自ら修繕や手続きをしなくても済む点は安心材料となります。
直接買取のメリット④:手間をかけずに売却できる
不動産を通常の市場で売る場合、これに対して、買取業者に依頼すれば査定から契約までを一括で進めてもらえるため、所有者の負担は最小限で済みます。
遠方に住んでいて管理が難しい場合や、多忙で売却手続きに時間を割けない人にとっては大きなメリットといえるでしょう。
関連記事:空き家の買取価格を上げるコツとは?相場や業者選びのポイントを解説
「ワケガイ」なら空き家も短期で買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や再建築不可の土地、事故物件や空き家など、市場で売却が難しい不動産を専門に扱うサービス「ワケガイ」を提供しています。通常の仲介では買い手が見つからない物件でも、私たちは直接買取によりスムーズな取引を実現できます。
最短1日で現金化できるスピード感と、全国対応の実績を強みに、幅広いケースに対応しています。老朽化や管理が難しい物件をそのままの状態で手放せるため、相続や維持コストで悩む方にとって有効な解決策となります。
煩雑な手続きも専門スタッフがサポートいたしますので、まずはお気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
空き家を放置すれば、資産価値の低下や税金の負担、近隣からの苦情といったリスクが高まります。一方で、民泊や駐車場、シェアスペースなどの空き家ビジネスに取り組めば、収益を生み出しながら地域社会にも貢献できます。
ただし、成功には立地条件や需要の見極め、法規制の確認、費用対効果の計算もきちんと行うようにしましょう。
すぐに活用が難しい場合は、専門業者への売却という選択肢も有効です。空き家を所有している方は、現状を正しく把握し、自身の状況に合ったビジネスモデルや出口戦略を選び、将来のリスクを軽減できる方法を実践していきましょう。