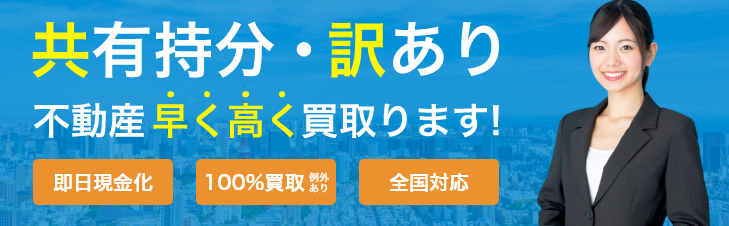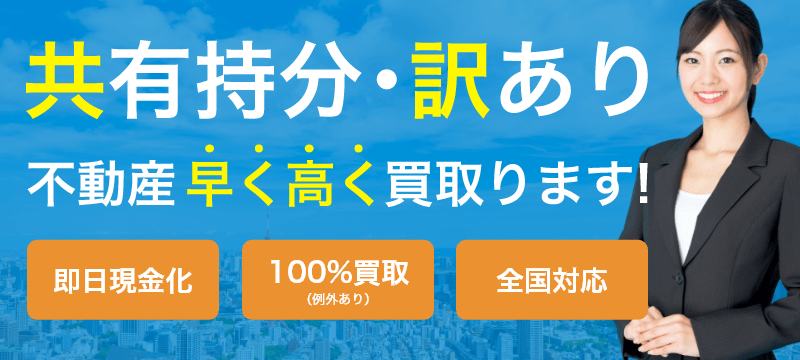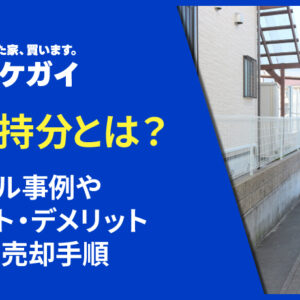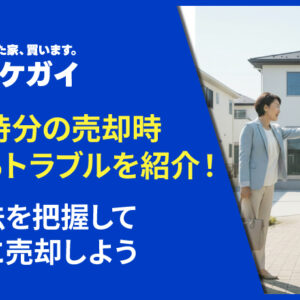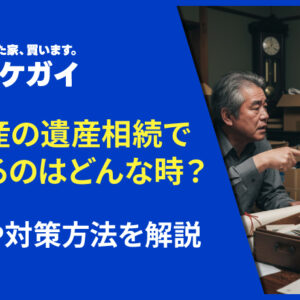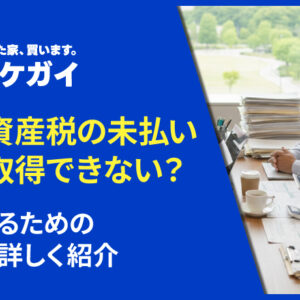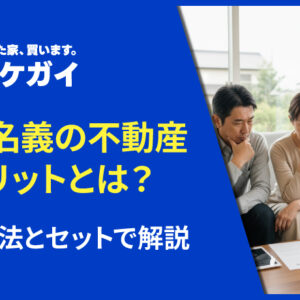相続や離婚などをきっかけに、不動産を複数人で共有しているケースは少なくありません。しかし、共有状態のままでは売却や活用がしづらく、他の共有者との意見の違いによるトラブルも発生しやすくなります。その際に検討すべきなのが「共有持分の売却」です。
共有持分とは、不動産全体ではなく、個々の所有者が持つ権利の割合を指します。基本的に、自分の持分であれば他の共有者の同意なしに売却が可能ですが、事前の交渉を怠るとトラブルにつながるケースもあります。
この記事では、共有持分不動産の基礎知識から、売却できるかどうか、売却方法や相場、必要な費用や書類、起こりやすいトラブルとその回避策までをわかりやすく解説します。共有持分の売却を検討している方はぜひ参考にしてください。
目次
- 共有持分不動産とは?
- 共有持分の不動産は売却できる?
- 共有持分不動産は他の共有者に勝手に売却されることはある?
- 共有持分を売却する方法
- 共有持分の土地を売却する方法
- 自分の持分を売却した場合の相場はどのくらい?
- 共有持分の不動産売却にかかる費用
- 共有持分の不動産売却に必要な書類
- 連絡が取れない共有者がいる場合はどうやって同意をとる?
- 同意なしで共有持分不動産を売却するリスク
- 共有持分不動産の売却で起こりうるトラブル
- 共有持分不動産の売却におけるトラブルを避ける方法
- 「ワケガイ」なら訳あり物件も短期で買取可能!
- 共有持分の売却に関するよくある質問
- 共有持分不動産の売却をする際はトラブル防止のために同意を取るのがおすすめ!
共有持分不動産とは?
共有持分とは、不動産のような財産を複数人で共同所有する際に、それぞれの所有者が持っている権利の割合を指します。
例えば、一つの土地を兄弟2人で所有している場合、どちらかが「持分2分の1」というように、どれだけの権利を持っているかを明確にしなければいけません。
持分は登記簿に記載されており、法的な所有権の証明となります。共有持分の所有者は、自分の持分に対してのみ自由に売却や贈与ができますが、全体の不動産を単独で処分(売却・賃貸・建て替えなど)はできません。
また、共有状態のまま放置してしまうと、将来的に相続が発生し、共有者が増えていくことでトラブルや権利関係の複雑化が生じる恐れもあります。その際には、共有持分の整理や買い取り、分割などが必要です。トラブルを防止するうえでは、共有持分について正しく理解しておきましょう。
関連記事:共有持分の所有者(共有者)ができること、できないこととは?
共有持分が発生するケース
共有持分は、特別な事情がなくても日常的に発生する可能性があります。代表的なケースは以下のとおりです。
| 相続 | 親の不動産を複数人の子どもで相続した場合、それぞれの相続分に応じて共有持分が生じます。 |
| 贈与 | 親が子に不動産の一部を贈与した場合など、持分だけを移転する形で共有が発生します。 |
| 離婚による財産分与 | 夫婦で共同購入した不動産を離婚時に分け合い、双方が持分を持ち続けるケース。 |
| 共同購入・投資 | 友人や親族と資金を出し合って不動産を購入する場合、出資割合に応じて持分が設定されます。 |
これらのケースはいずれも珍しいことではなく、多くの人に起こり得るものです。だからこそ、共有持分の仕組みやリスクを正しく理解しておくことが重要になります。
共有持分の不動産は売却できる?
不動産を共有している場合、「自分の持分を勝手に売却できるのか?」「他の共有者の同意は必要なのか?」と疑問に思う方は多いでしょう。
結論から言えば、自分の持分だけであれば単独で売却できます。ただし、全体の不動産を売却する場合や大きな改築などを行う場合には、共有者全員の同意が必要です。
自分の持分だけなら単独で売却できる
民法第206条および第251条に基づき、共有者は自分の持分を自由に処分できる権利を持っています。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)
しかし、売却の方法によっては、共有者との合意が求められるケースもあります。たとえば、共有者全員で不動産を売却する場合は、全員の合意が必要になります。また、買主が共有状態を嫌がる場合は、売却が難しくなることも考えられます。
そのため、共有持分の売却を検討する際は、他の共有者の意向や不動産の状況を確認し、最適な売却方法を選ぶようにしましょう。必要に応じて買取専門業者を利用することで、スムーズな売却が実現しやすくなります。
共有不動産でできる行為と必要な同意の目安
| 行為 | 具体例 | 必要な同意 | 法的整理(要点) | 注意点 |
| 保存行為 | 雨漏り修繕/倒壊防止の補修/老朽フェンスの付替えなど | 単独で可 | 共有物の保存は各共有者が単独で可 | 緊急性が高い場合は特に単独可が明確。費用負担は後で清算を検討 |
| 管理行為 | 短期賃貸の締結/共用部の清掃・点検契約/駐車区画の運用など | 持分の過半数 | 共有物の管理は持分多数決 | 契約期間が長期・実質的に用途を縛ると“変更”に近づく点に注意 |
| 変更・処分行為 | 建替え・大規模改築/用途転換(住居→店舗)/不動産全体の売却など | 全員の同意 | 共有物の変更・処分は全員一致が原則 | 反対者がいる場合は協議・調停・(最終的に)分割手続の検討 |
共有持分の単独売却は買い手が限られる
理論上は自分の持分を自由に売却できますが、実務上は大きな制約があります。
| 買主が限られる | 持分だけを買いたい個人は少なく、実際の買主は他の共有者や専門業者に限られることが多い。 |
| 価格が安くなりやすい | 共有状態のままでは利用価値が制限されるため、売却価格は相場より低くなりがち。 |
| 新たなトラブルのリスク | 見知らぬ第三者が共有者になることで、意見の食い違いや訴訟リスクが高まる。 |
そのため、共有持分の売却を検討する際は、「売れるかどうか」だけでなく「売った後にどうなるか」も踏まえて慎重に判断することが大切です。
共有持分不動産は他の共有者に勝手に売却されることはある?
共有持分不動産を知らないうちに売られてしまうのでは?と不安に思う方もいるでしょう。
結論からいえば、不動産全体を勝手に売却されることはありません。不動産全体を処分するには、共有者全員の同意が必要だからです。
しかし、注意すべきは、各共有者が自分の持分だけを第三者へ売却できるという点です。民法では共有者に「持分を自由に処分する権利」が認められているため、知らずに持分が売られることは十分に起こり得ます。
共有持分を売却する方法
共有持分を売却する方法は一つではありません。ここからは、共有持分を売却する方法について紹介します。共有持分の売却を検討している方は、それぞれの概要を把握しておきましょう。
他の共有者に持分を売却する
他の共有者に自分の持分を買い取ってもらうのは、共有持分の売却方法として一般的です。共有者同士であれば、物件全体の利用目的や売却後のトラブル回避を考慮しやすいため、話し合いも進みやすくなります。
売却後に共有状態が解消されるため、不動産の管理や運用がスムーズに進めやすいというメリットもあります。
メリット
- 物件全体の利用目的を共有しているため交渉がまとまりやすい
- 売却後に共有状態が解消され、管理や活用がスムーズになる
注意点
- 他の共有者に資金的余裕がない場合、買い取ってもらえないこともある
共有者全員で第三者に売却する
共有者全員の合意が得られれば、不動産全体を第三者に売却できます。この方法は不動産全体を一括で売却できるため、高値で売却しやすく、買い手もつきやすいのがメリットです。
売却代金は、持分割合に応じて各共有者に分配されます。しかし、共有者の中に売却に反対する人がいれば、第三者への売却は難しくなるでしょう。
メリット
- 不動産全体を一括で売却できるため、相場に近い高値がつきやすい
- 買主にとっても共有関係のない物件の方が安心できる
注意点
- 共有者の一人でも反対すれば実現できない
- 売却代金は持分割合に応じて分配される
買取業者に売却する
共有持分の扱いに慣れている専門の不動産買取業者に売却する方法もあります。共有状態のままでも買い取ってくれる業者も多く、他の共有者との調整が難しい場合や、早期に現金化したいときに有効です。
しかし、共有状態のままの不動産は流動性が低く、買取価格は一般の相場よりも低くなる傾向があります。それでも確実に売却でき、手間を省けるという意味ではメリットが大きいといえるでしょう。
メリット
- 他の共有者の同意が得られなくても売却可能
- 最短数日で現金化できるスピード感
注意点
- 市場価格よりも安くなる傾向(相場の5〜7割程度)
- 業者選びを間違えると不利な条件を押し付けられることもある
共有持分の土地を売却する方法
土地の場合は、自分の持分に相当する範囲を明確に分割して、単独名義にしたうえで売却する必要があります。これは分筆と呼び、土地全体を物理的に区分けし、それぞれを単独所有とする方法です。
分筆が可能かどうかは、土地の形状や面積、接道条件などによって判断され、実務では測量士のような専門家の協力が必要です。分筆後は共有状態が解消され、自由に売却できるようになります。
自分の持分を売却した場合の相場はどのくらい?
共有持分のみを売却する場合、不動産全体の売却と比べて価格が低くなる傾向があります。その理由は、持分だけでは利用価値が制限され、流動性が低くなるため、買主が限定されるからです。
一般的に、共有持分の買取価格は「不動産全体の市場価格 × 持分割合 × 40%〜70%」の範囲内で決まります。例えば、物件全体の市場価格が5,000万円で、自分の持分が50%だった場合、買取価格は1,000万〜1,750万円程度となる可能性があります。
相場が低くなる要因として、以下の理由が考えられます。
| 利用価値が限定される | 持分だけでは単独で住む・貸すといった利用が難しい |
| 交渉リスクを考慮される | 他の共有者との調整が必要になるため、買主はリスクを価格に反映する |
| 買主が限られる | 主に他の共有者や買取業者が対象となり、市場が狭い |
持分のみでは第三者にとって活用が難しいことや、他の共有者との交渉が必要になるリスクがあることが挙げられます。共有持分不動産をできる限り高く売りたい場合には、まず他の共有者に売却を検討してみましょう。
関連記事:共有持分の売却相場っていくら?価格の決まり方も交えて解説
共有持分の不動産売却にかかる費用
共有持分の売却には、通常の不動産売却と同様にさまざまな費用がかかります。以下が代表的な費用になります。
- 印紙税
- 登録免許税
- 司法書士報酬
- 仲介手数料
売却価格からこれらの費用を差し引いた金額が実際の手取りとなるため、あらかじめ費用の内容を把握しておくことが大切です。それぞれの費用について、詳しく解説します。
関連記事:共有持分の放棄にかかる費用はどのくらい?放棄する人、取得者別に具体的に紹介
印紙税
売買契約書を作成する際には、印紙税が必要です。契約書に貼付する「収入印紙」として納めるのが印紙税であり、契約書の記載金額に応じて税額が決まります。
例えば、契約金額が100万円を超え500万円以下であれば印紙税は2,000円、500万円超1,000万円以下であれば1万円となります。
印紙税の負担は、売主・買主のそれぞれが自分の保管分について印紙を貼るのが一般的です。ただし、契約内容や慣習によっては、売主がまとめて負担する場合や、双方で費用を折半する場合もあります。
(参考:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」)
登録免許税
不動産の所有権が移転する際には、法務局での登記手続きが必要であり、その際に登録免許税が課されます。税率は、本則は不動産の固定資産評価額の2.0%ですが、令和9年3月31日までの軽減措置により1.5%が適用されています。
共有持分を売却する場合は、売却部分に応じた固定資産評価額を基に税額が算出されます。登録免許税は原則として買主が負担することが多いですが、契約内容によっては売主側が負担する場合もあります。
(参考:国税庁「登録免許税のあらまし」)
司法書士報酬
登記手続きは自分で行うことも可能ですが、司法書士に依頼するのが一般的です。その際にかかるのが司法書士報酬です。
報酬額は依頼する司法書士や不動産の所在などによって異なりますが、相場としては3万円〜7万円程度が目安となります。共有状態のまま持分を移転する登記や、分筆登記を行う場合など、手続きが複雑になると報酬額が高くなる傾向にあります。
仲介手数料
不動産会社に売却を依頼した場合は、契約が成立すれば仲介手数料が発生します。宅地建物取引業法により上限額が定められており「売却価格の3%+ 6万円(消費税別)」
例えば、売却価格が1,000万円であれば、仲介手数料は36万円(税抜)となります。共有持分の場合でも、不動産全体の価格ではなく、売却する持分に応じて手数料が算出されます。
共有持分不動産の売却にかかる主な費用一覧

共有持分の不動産売却に必要な書類
共有持分を売却する際も、通常の不動産売却と同様に複数の書類が必要です。手続きをスムーズに進めるためにも、事前に必要書類を揃えておく必要があります。以下より、共有持分の不動産売却に必要な代表的な書類を解説します。
権利証(登記識別情報)
不動産を売却する際には、所有者であることを証明する「権利証」または「登記識別情報通知書」が必要です。
登記識別情報は、不動産の登記完了後に法務局から発行される書類で、オンライン登記の導入以降は紙の権利証ではなく登記識別情報が主流になっています。
これがなければ、原則として所有権移転登記ができないため、厳重に保管しておきましょう。
土地測量図・境界確認書
共有持分が含まれる土地の場合、売却前に土地の「境界」を確認する必要があります。特に土地全体の売却や分筆を行う場合には、測量図や境界確認書が必要となります。
これらの書類は、隣接地とのトラブル防止にもつながり、共有者間や第三者との取引において客観的な根拠として機能します。測量作業は隣地所有者への立ち会い依頼などで1〜2か月かかることが多いため、早めに準備を始めましょう。
身分証明書・住民票
不動産の売買契約を締結する際には、宅地建物取引業法に基づき、契約当事者の本人確認が行われます。そのため、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の提出が必要です。また、登記の際には住所が確認できる住民票も求められます。
(参考:e-Gov 法令検索「宅地建物取引業法」)
登記簿上の住所と現住所が一致していない場合は、住所変更の経緯を証明する書類が必要です。通常は「住民票の除票」や「戸籍の附票」で確認します。
印鑑登録証明書
売買契約書や登記申請書には実印を押印することが一般的であり、そのためには印鑑登録証明書の提出が必要です。
印鑑登録証明書は、市区町村の役所で発行されるもので、原則として発行から3ヶ月以内のものが有効とされます。売買契約書への捺印も行いますので、実印そのものも忘れずに用意しておきましょう。
連絡が取れない共有者がいる場合はどうやって同意をとる?
共有持分を売却する際、共有者と連絡が取れないと手続きが滞る可能性があります。特に、相続で共有者が増えたり、長年疎遠になっている場合、同意を得るのが難しくなります。
まず、共有者の所在を調査しましょう。住民票や戸籍の附票を取得すれば、過去の住所変更履歴を確認できます。また、固定資産税の納付通知書や登記情報を調べることで、現在の住所がわかることもあります。どうしても見つからない場合は、探偵業者や弁護士に相談する方法も検討しましょう。
それが終われば、内容証明郵便を送付して売却の意思を伝えます。相手が返信しなくても、正式に通知した記録が残るため、後のトラブルを防ぐのに有効です。
連絡が取れない共有者がいると売却が難しくなりますが、適切な手続きを踏めば、スムーズに進められる可能性があります。
関連記事:共有者が行方不明の場合の対処方法について詳しく解説
関連記事:共有名義人が認知症になったら、不動産は売却可能?成年後見人制度とセットで解説
同意なしで共有持分不動産を売却するリスク
共有持分は他の共有者の同意なしに売却が可能ですが、同意を得ずに売却することでさまざまなリスクが生じる可能性があります。
売却後にトラブルが発生すると、想定外の時間や費用がかかることもあるため、事前にリスクを把握し、適切な対策を講じなければなりません。ここからは、同意なしで共有持分を売却するリスクについて解説します。
共有者との関係が悪化しかねない
共有持分を第三者へ売却すると、新しい共有者が加わることで他の共有者の意向が通らなくなる可能性があります。投資目的の買主が共有者となった場合、賃貸や建て替えなどの方針が大きく変わることもあるため、トラブルにつながりやすくなります。
また、共有者の意向を無視して売却を進めると、関係が悪化して協力が得られなくなるかもしれません。将来的に不動産全体を売却したくなった際に、スムーズに話が進まなくなる可能性が高まります。
新しい共有者とトラブルになる可能性がある
共有持分を第三者に売却すると、今まで顔見知りだった共有者に代わって第三者が共有者として加わることになります。新たな共有者が利益を優先して、裁判を起こすかもしれません。
不動産投資家や買取業者が買主となる場合は、共有状態の解消を目的として、共有物分割請求訴訟(裁判)を起こされるリスクがあります。訴訟になると、費用や時間がかかるだけでなく、最終的には不動産が競売になるケースもあるため注意が必要です。
不動産全体の売却がしづらくなる
共有者が複数存在し、その中に第三者が加わると、不動産全体を売却する際の調整が困難になります。全体売却には原則として共有者全員の合意が必要なため、新たに加わった共有者によって交渉がまとまらない事態も考えられます。
長期間にわたって売却できなくなるかもしれません。不動産を売却するうえで、共有している状態というのは障害になりやすいといえるでしょう。
共有持分不動産の売却で起こりうるトラブル
共有持分を売却する際には、通常の不動産売買とは異なるトラブルが発生しやすいのが実情です。以下では、代表的なトラブル例について解説します。
他の共有者との関係が悪化する
共有持分の売却は、他の共有者の同意なしに単独で可能な行為ですが、事前に話し合いをしないまま売却すると、関係性が悪化する恐れがあります。法的に問題がなくても、「勝手に売った」と感じられ、信頼関係にひびが入るケースは少なくありません。
今後の共同利用や管理にも支障が出る可能性があるため、売却前には説明や相談を行うのが望ましいでしょう。
希望通りの価格で売却できない
共有持分は市場での流動性が低く、購入希望者が限られるため、希望通りの価格で売却できないケースも多くあります。共有者間で対立がある場合や、物件の利用制限が厳しい場合は、買い手が見つからない可能性も高まります。
買取業者に強引な営業をされる
共有持分を売却しようとすると、専門の買取業者からしつこく営業を受けることがあります。強引な手法で売却を迫ってくる業者も存在するため、誠実な対応をしてくれる業者を選定しましょう。
共有物分割請求訴訟を起こされる可能性がある
第三者が共有持分を取得した場合、他の共有者に対して「共有物分割請求訴訟」を起こすことがあります。詳しくは後述しますが、不動産全体の売却や単独名義化を目的とした法的手段であり、時間や費用面での負担が大きくなってしまうので注意が必要です。
みなし贈与になる場合がある
共有持分を他の共有者や親族に売却する際、時価より大幅に安い価格で取引すると、その差額が「贈与」とみなされ、贈与税が課される可能性があります。
例えば、本来1,000万円の価値がある持分を500万円で売却した場合、差額の500万円が贈与と判断されるケースです。
贈与税は税率が高く、想定外の負担になる恐れがあるため、売却価格を決める際には必ず不動産会社の査定や専門家の意見を参考にし、適正価格での取引を行いましょう。
相続で共有者が複雑化する
共有状態をそのまま放置していると、相続のたびに共有者が増えるという問題が生じます。例を挙げると、2人で持っていた不動産をそれぞれが子ども3人に相続させると、次の世代では6人の共有状態になります。さらにその次の世代に相続されれば、共有者は倍々で増え、所有権の分割割合も細かく複雑になっていきます。
共有者が増えると、
- 売却や活用のための合意形成が極めて困難になる
- 連絡が取れない相続人が出てくる
- 管理責任や固定資産税の負担割合を巡って争いが起きやすくなる
といったリスクが高まります。
こうした「負の遺産」とならないためにも、早めに共有状態を解消することが大切です。
共有持分不動産の売却におけるトラブルを避ける方法
共有持分の売却におけるトラブルを避けるうえで、注意するべきポイントは主に3つあります。共有持分の売却を検討している方は、それぞれ把握しておきましょう。
訳あり物件の買取専門業者に依頼する
共有持分の売却は通常の不動産売却とは異なり、専門的な知識が求められます。一般の不動産会社では、共有持分のみの売却に対応していなかったり、適正な査定を受けられないケースも少なくありません。
そのため、共有持分の売却に特化した専門業者を選ぶことが求められます。こうした業者は、共有持分特有の問題を熟知しており、他の共有者との関係性や潜在的なリスクを考慮した査定を行うことができます。
また、専門業者に依頼することで、共有者との交渉や権利関係の整理、法的手続きのサポートも受けられるため、スムーズな売却が実現しやすくなります。
売却後のサポートを徹底して行う
共有持分の売却は契約が成立すれば終わりではなく、売却後に共有者との関係悪化や法的トラブルが発生するケースも考えられます。
例えば、他の共有者が「知らないうちに売却された」と感じた場合、関係性が悪化し、最悪の場合は訴訟に発展する可能性もあります。また、新しい共有者が加わることで、物件の管理方針や使用ルールが変わり、他の共有者との摩擦が生じることもあります。
こうしたリスクを回避するためには、売却後のサポート体制が整っている業者を選びましょう。
関連記事:共有不動産の売却でも「確定申告」は必要?やり方と注意点について紹介
持分の買取を他の共有者に依頼する
第三者に売却する前に、まずは他の共有者に持分の買取を打診するのもおすすめです。共有者同士での売買であれば、トラブルのリスクが大幅に低下し、共有状態を解消できます。
「相手方に不動産を有効活用する意志がある」「相続で得た持分である」場合なら、買取に応じてもらえる可能性があります。公平な価格での交渉を心がければ、円満に取引を終えられます。
共有状態を解消したいなら「共有物分割請求訴訟」も検討する
共有持分の売却を進めたいものの、他の共有者の同意が得られない場合や話し合いが難航するケース も少なくありません。そのような場合に、共有状態を解消する手段の一つとして「共有物分割請求訴訟」 を検討できます。
共有物分割請求訴訟とは、裁判所の判断によって共有不動産の分割・処分を決める法的手続きです。裁判では、以下のような分割方法が検討されます。
- 現物分割:不動産を物理的に分割する方法
- 換価分割:売却して売却代金を共有者間で分配する方法
- 代償分割:他の共有者が買い取る方法
ただし、訴訟には時間と費用がかかるため、まずは共有者との協議や専門家への相談を行うことが望ましいでしょう。訴訟を視野に入れる際は、弁護士などの専門家と相談し、最適な方法を選択しましょう。
関連記事:共有物分割請求とは?請求方法や流れを解説
「ワケガイ」なら訳あり物件も短期で買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分をはじめとする売却が難しい不動産を専門に買取するサービス「ワケガイ」を運営しています。共有不動産の売却では、他の共有者の同意が得られない、権利関係が複雑、一般市場での売却が難しいなど、多くの課題が発生しがちです。
ワケガイでは、こうした訳あり不動産をスムーズに売却できる仕組みを整えており、最短1日での現金化も可能です。さらに、弁護士や司法書士との連携により、権利関係の整理や売却手続きをサポートするため、トラブルを未然に防ぎながら安心して売却を進められます。
共有持分の売却にお困りの方や、できるだけ早く現金化したい方は、お気軽に無料査定をご活用ください。
共有持分の売却に関するよくある質問
ここからは、共有持分に関してよくある質問とその回答を紹介します。トラブルを避け、納得のいく取引を行うための参考にしてください。
Q1. 共有持分不動産はどのような場合に発生する?
相続によって不動産を複数の相続人で受け継いだ場合に発生しやすい所有形態です。夫婦や親子で住宅を購入した際に出資割合に応じて共有とするケースや、不動産の共同購入をした場合などにも共有持分が発生します。
Q2. 共有持分の所有者に認められている権利とは?
共有者には、自己の持分割合に応じて不動産の利用や管理に関与する権利があります。また、持分を単独で売却する権利も法律上認められています。
Q3. 共有持分は早めに解消した方が良い?
基本的に、共有状態は早めに解消しておいた方が望ましいとされています。共有状態が長期化すると、管理の意思決定が複雑になったり、他の共有者との関係性が悪化したりするため注意が必要です。
Q4. 他人と不動産を共有するのは避けるべき?
他人と不動産を共有するのは避けるのが無難です。価値観や目的が異なる相手との共有では意見が食い違いやすく、思うように活用できなくなる恐れがあります。
Q5. 共有持分不動産の売却の相談はどこにすればいい?
共有持分の売却は、通常の不動産取引に比べて専門的な知識や交渉力が求められるため、相談先選びを慎重に行いましょう。適切な窓口を選ぶことで、スムーズに売却できるだけでなく、将来的なトラブル防止にもつながります。以下が主な相談先になります。
共有持分の買取専門業者
他の共有者の同意が得られない場合や、早期に現金化したい場合には、共有持分を専門に扱う買取業者への相談が効果的です。こうした業者は複雑な権利関係にも精通しており、交渉や手続きを代行してくれるため、安心して売却を進められます。
不動産仲介会社(共有持分に対応しているところ)
仲介会社を通じて第三者に売却する方法もあります。全体売却や高値売却を目指す場合に有効ですが、共有者全員の合意が必要になるケースが多いため、事前の話し合いが求められます。
弁護士・司法書士などの専門家
共有者間の対立や相続問題など、法的な課題が絡む場合には弁護士や司法書士に相談しましょう。共有物分割請求訴訟など、裁判を視野に入れる場合も専門家のサポートが不可欠です。
Q6. 共有持分不動産は同意なしで売却できる?
自分の持分であれば、他の共有者の同意なしに単独で売却が可能です。これは民法で認められている権利です。
ただし、同意を得ずに売却すると、共有者との関係悪化や新しい共有者とのトラブルにつながる恐れがあります。将来的に不動産全体を売却したい場合にも支障が出やすいため、できる限り事前に共有者と話し合っておくことが望ましいでしょう。
共有持分不動産の売却をする際はトラブル防止のために同意を取るのがおすすめ!
共有持分の売却は、法律上、他の共有者の同意がなくても可能ですが、売却後のトラブルを避けるためには慎重に進める必要があります。共有者との関係悪化や買主が見つかりにくいといったリスクを回避するためには、事前の交渉や市場相場を把握しなければなりません。
また、共有持分のみの売却は流動性が低いため、通常の不動産売却と比べて価格が下がる傾向があります。スムーズに売却を進めるためには、買取専門業者を活用し、適正な査定を受けるようにしましょう。