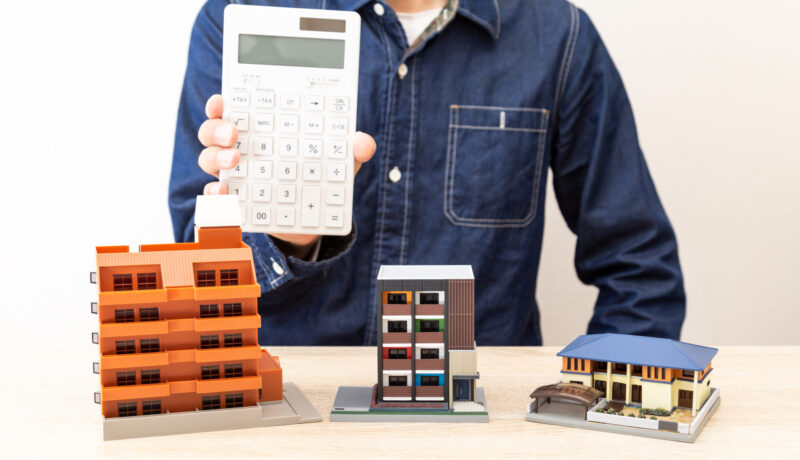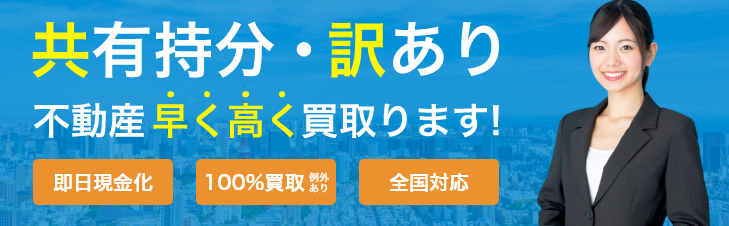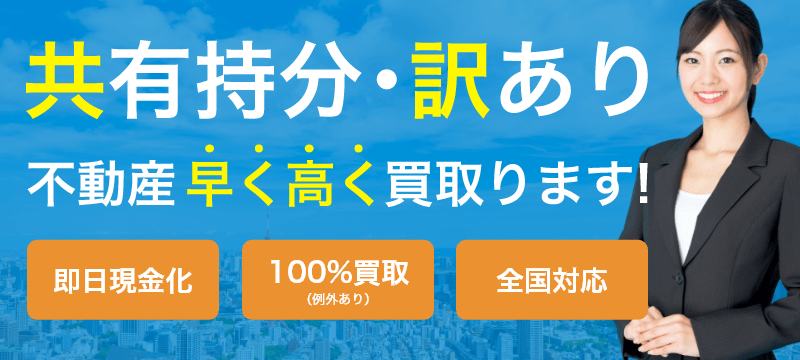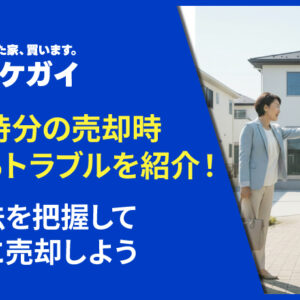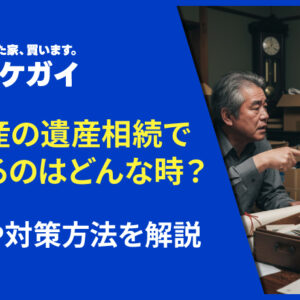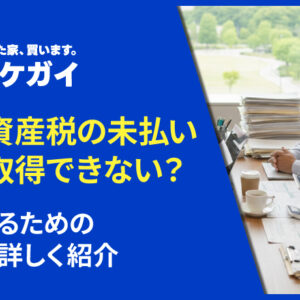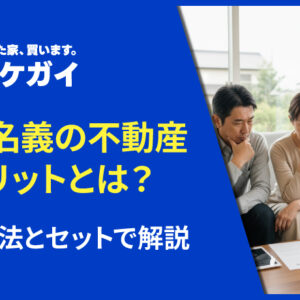他の共有者の経済状況が悪化し、共有不動産の一部が競売にかけられそうな状況にある場合、「自分には関係ないと思っていたのに、突然不動産に影響が出るのではないか」と不安を感じる方は少なくありません。
そのようなときに正しく理解しておきたいのが「競売の仕組み」です。競売とは、債権者が債権回収のために裁判所を通じて物件を強制的に売却する法的手続きのこと。共有不動産でも、一部持分が対象となることで影響を受ける可能性があります。
そこで本記事では、競売の基本的な仕組みとリスク、特に他の共有者の持分が競売対象となった場合に起こりうる事態について、整理・解説していきます。
目次
不動産の競売(けいばい)とは
不動産の競売とは、債務の返済が滞った場合に、債権者が裁判所を通じて不動産を強制的に売却する法的手続きです。任意での売却とは異なり、所有者の意思にかかわらず手続きが進むのが特徴です。
競売の対象は、本人名義の不動産だけでなく、共有名義の持分も含まれるため、自分に借金がなくても他の共有者の債務によって競売が始まる可能性もあります。
また、競売物件は市場価格よりも安く売却される傾向があるほか、見知らぬ第三者と共有状態になるなど、思わぬリスクも抱えることになります。
こうした競売は、大きく分けて「強制競売」と「担保不動産競売」の2種類に分類されます。
強制競売とは
債務名義(確定判決や公正証書など)に基づいて、債権者が裁判所に申立てることで実行される競売です。
主にカードローンや未払いの貸金など、抵当権が設定されていない債権が対象となります。担保がなくても強制的に不動産が差し押さえられ、売却されるのが特徴です。
担保不動産競売とは
住宅ローンの滞納など、抵当権が設定された不動産に対して行われる競売です。金融機関などの抵当権者が債権回収のために申立てを行い、裁判所の手続きによって物件が強制的に売却されます。対象物件は市場よりも割安で売却されるケースが一般的です。
関連記事:共有持分が差し押さえられた場合の対処法とは?強制執行の影響も踏まえて詳しく解説
他の共有者の持分が競売にかけられた場合のリスク
では、共有持分が競売にかけられた場合はどのようなリスクがあるのでしょうか。具体的には、以下のとおりです。
- 第三者と共有状態になる可能性がある
- 共有物分割請求訴訟を提起されかねない
次項より、詳しく解説します。
第三者と共有状態になる可能性がある
共有持分が競売にかけられると、その持分を不動産ブローカーなどの第三者が落札する可能性があります。この場合、残された共有者は見知らぬ第三者と不動産を共有することになります。
第三者との共有関係は、これまでの生活や不動産の利用に大きな支障をきたす恐れがあります。例えば、不動産の管理や処分に関する意思決定が困難になったり、新たな共有者から不当な要求をされたりする可能性があるのです。
特に、不動産ブローカーが落札した場合、高額での持分買取りを迫られる。あるいは、逆に安価での持分譲渡を要求されたりすることも考えられます。
このような状況は、残された共有者にとって非常にストレスフルで、財産的にも不利益を被る可能性が高いでしょう。
共有物分割請求訴訟を提起されかねない
第三者が共有持分を取得した場合、その第三者から共有物分割請求訴訟を提起される可能性があります。共有物分割請求訴訟とは、共有関係の解消を目的とした法的手続きで、裁判所を通じて共有物の分割方法を決定します。
この訴訟が提起されると、残された共有者の意思に関わらず、不動産の分割や売却を強いられる可能性があります。
訴訟の結果、「現物分割」「代償分割」「換価分割」のいずれかが命じられますが、多くの場合、競売による換価分割となります。これにより、不動産全体が競売にかけられ、市場価格よりも低い価格で売却される可能性が高くなります。
また、訴訟にかかる費用や時間的負担も大きいため、残された共有者にとっては大きなリスクとなります。
関連記事:共有持分の「換価分割」とは?メリット・デメリット、選択すべきケースを紹介
他の共有者の持分が競売にかけられるケース
共有持分が競売にかけられるのは大きくは次のケースです。
- ケース①:共有者が自己持分を担保に借入をしていた
- ケース②:住宅ローンを滞納して自己破産した
以下より、詳しく解説します。
ケース①:共有者が自己持分を担保に借入をしていた
共有者の一人が自己の持分を担保に借入をしていた場合、その借入の返済が滞ると、担保となっている共有持分が競売にかけられる可能性があります。共有持分を担保にする場合、他の共有者の同意は必要ありません。
そのため、他の共有者が知らないうちに、共有者の一人が自己の持分を担保に借入をしていることもあります。
例えば、夫婦で共有している不動産で、夫が妻に知らせずに自分の持分を担保に借入をし、返済が滞った場合などが該当します。このような事態が発生すると、他の共有者にとっては寝耳に水の状況となり、突然、見知らぬ第三者と共有関係になる可能性が生じます。
そのため、共有者間で定期的に経済状況を確認し合うなど、事前の対策が重要です。
関連記事:共有持分を担保にお金を借りるには?不動産担保ローンのにおける共有不動産の取り扱いについて
関連記事:共有持分への抵当権設定は問題ない?注意点についても解説!
ケース②:住宅ローンを滞納して自己破産した
住宅ローンを滞納した場合、共有不動産全体が競売にかけられる可能性があります。特に、夫婦で共同名義の不動産を購入し、ペアローンを組んでいる場合に注意が必要です。
ペアローンとは、夫婦がそれぞれ別々に住宅ローンを組む方法で、互いに連帯保証人になるケースが多々あります。
この場合、どちらか一方がローンの返済を滞納すると、その人の持分だけでなく、不動産全体が競売にかけられる恐れがあります。例えば、夫がローンを滞納した場合、妻が自分の分をきちんと返済していても、不動産全体が競売にかけられる可能性があります。
そのため、共有者同士で常に返済状況を確認し合い、一方が返済に困難を感じた場合は早めに対策を講じることが重要です。金融機関との交渉や任意売却の検討など、さまざまな選択肢を考える必要があります。
債権者に競売を取り下げてもらうことはできる?
競売が申し立てられた後でも、債権者との交渉次第では競売を取り下げてもらえる可能性があります。ただし、これはあくまでも「債権者の任意」による判断であり、どのケースでも成立するとは限りません。特に他の共有者の持分が対象となっている場合、関係者が多くなるため判断も複雑になります。
競売の取り下げが検討される場面としては、債務の一括返済や、任意売却によって競売より高額での回収が見込まれるときが典型です。
つまり「競売より得られる金額が上回る」ことが交渉成立の前提条件です。
一方で、現実的には次のようなケースでは交渉は難航しやすく、取り下げは期待できません。
<競売の取り下げ交渉が現実的に難しいケース>
- 債務額が大きく、一括返済の目処が立たない
- 債務者が自己破産を予定している
- 開札(落札)期日が迫っている
- 債権者が複数存在し、全員の同意を得るのが難しい
こうした事情を踏まえると、取り下げ交渉は「実現性のある代替案(任意売却や一括返済)が揃って初めて検討される選択肢」であると捉えるのが現実的です。可能性がゼロとは言い切れないものの、早期に動き、債権者との交渉材料を整えておくことが最低条件といえるでしょう。
他の共有者の持分が競売にかけられた後の対処法
一方で、競売にかけられてしまった場合は以下の対応をとりましょう。
- 自分が競売で落札する
- 落札者の持分を買い取る
- 自身の持分を専門業者に売却する
- 共有物分割請求訴訟に備える
競売後の対応方法についても、詳しく解説します。
自分が競売で落札する
競売が避けられない場合、残された共有者自身が競売に参加し、対象となる共有持分を落札する方法があります。
この方法のメリットは、見知らぬ第三者との共有状態を避けられることです。また、競売価格は市場価格よりも低いことが多いため、比較的安価で持分を取得できる可能性があります。
ただし、この方法を選択する場合は、十分な資金力が必要です。また、競売は入札制のため、必ずしも落札できるとは限りません。さらに、競売手続きに関する知識や経験も必要となります。
そのため、この方法を検討する際も、弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。専門家のアドバイスにより、適切な入札額の設定や手続きの進め方を決定することができます。
落札者の持分を買い取る
落札者の持分を買い取る方法は、元の共有状態を回復するための直接的な対処法です。この方法のメリットは、見知らぬ第三者との共有関係を解消し、不動産の管理や利用に関する自由度を取り戻せることです。
しかし、落札者が売却に応じるかどうかは不確実です。特に、不動産ブローカーが落札した場合、高額での買取りを要求されることがあります。交渉に際しては、不動産の市場価値や共有持分の特殊性を考慮した適正価格を提示することが重要です。
また、資金面での準備も必要となります。金融機関からの借入れや、親族からの援助なども検討するとよいでしょう。交渉が難航する場合は、弁護士を介して進めることで、より有利な条件を引き出せる可能性があります。
競売の取り下げ交渉を債権者に行う
他の共有者の持分が競売にかけられた場合、債権者との交渉によって競売を取り下げてもらうことは理論上可能です。しかし、実際には債権者が競売を取り下げるケースは稀であり、取り下げには一定の条件が求められます。
主な条件としては、債務の一括返済や任意売却の完了が挙げられます。債権者は、競売によって債権回収を図るため、これらの条件が満たされない限り、競売の取り下げには応じないことが一般的です。
また、競売の取り下げが可能な期限は、開札日の前日までとされています。この期限を過ぎると、取り下げは原則として認められません。そのため、競売の取り下げを検討する場合は、早期に債権者との交渉を開始し、必要な手続きを迅速に進めることが重要です。
自身の持分を第三者に売却する
他の共有者の持分が競売にかけられ、第三者が新たな共有者となった場合、共有関係の継続が困難になることがあります。
そのような状況では、自身の持分を第三者に売却することで、共有関係から離脱する選択肢があります。
共有持分の売却は、通常の不動産取引よりも難易度が高く、買い手を見つけるのが困難なケースも珍しくありません。その場合、共有持分の買取を専門とする業者も存在し、これらの業者を利用することで、比較的スムーズに売却が進む可能性があります。
売却を検討する際は、複数の業者から査定を受け、条件を比較検討することが重要です。また、売却後の税務処理や法的手続きについても、専門家の助言を受けながら進めることをおすすめします。
関連記事:共有持分の買取サービスを利用するメリットとは?業者選びのコツも合わせて紹介
他の共有者の持分が競売にかけられる前にできること
ここからは、所有不動産が競売にかけられる前にとっておくべき、以下の対応方法について紹介します。
- 債務者の債務を返済する
- 任意売却の手続きをする
それぞれ詳しく解説します。
債務者の債務を返済する
債務者の債務を返済する方法は、最も直接的で確実な対処法です。残された共有者が資金的に余裕がある場合、債務者の債務を肩代わりして返済することで、競売を回避できます。この方法のメリットは、現状の共有関係を維持できることです。
ただし、債務を肩代わりする際は、必ず書面で合意を交わし、将来的なトラブルを防ぐ必要があります。また、債務者の返済能力や今後の経済状況も十分に考慮する必要があります。
さらに、債権者との交渉により、一括返済ではなく分割払いの可能性を探ることも有効です。債権者にとっても、競売よりも確実に債権回収ができる可能性が高いため、交渉の余地は十分にあります。
任意売却の手続きをする
任意売却とは、債権者の同意を得て、競売にかけられる前に不動産を自主的に売却する方法です。
任意売却のメリットは、競売よりも高値で売却できる可能性が高いことです。前述のとおり、競売では市場価格の5〜7割程度で取引されることが多いですが、任意売却であれば市場価格に近い金額で売却できる可能性があります。
また、売却までの時間も競売よりも短縮できる場合が多いです。
ただし、任意売却を行うためには、全ての共有者の同意が必要です。また、債権者との交渉も必要となります。任意売却を検討する際は、不動産専門家や弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
専門家のサポートにより、スムーズな売却手続きと、できる限り高値での売却を目指すことができます。
関連記事:共有持分を任意売却する方法を徹底解説!メリット・デメリットについても詳しく紹介
「ワケガイ」なら競売リスクのある物件も柔軟に対応可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、複雑な権利関係を抱える不動産を専門に扱う買取サービス「ワケガイ」を提供しています。
共有持分が第三者に渡ってしまったケースや、他の共有者の持分が競売にかけられてしまった物件でも、売却の道を閉ざす必要はありません。
私たちは、そうした難易度の高い不動産についても、士業と連携した調査や法的手続きを通じて、売却までを一貫してサポートしています。
時間的・精神的な負担を減らし、円滑な現金化を目指すなら、お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
他の共有者の借金やローン滞納によって、知らない間に自分の住まいが第三者と共有状態になったり、望まない形で不動産が売却される。こうした競売のリスクは、予期せぬタイミングで突然やってきます。
不動産競売は、法的に粛々と進行するため、早い段階で「競売の仕組み」と「自分に起こり得る影響」を把握しておくことが重要です。とくに共有者の債務状況に不安がある場合は、定期的な確認や、任意売却などの事前対策も検討しておきましょう。
いざというときに慌てないよう、リスクと対処法を冷静に把握し、準備を整えておくことが、財産と暮らしを守る上では大切なのです。