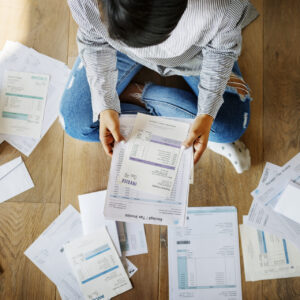相続や離婚、売買などにより不動産の共有持分を取得した場合、「名義を変えないまま放置していたらトラブルに発展した」というケースも少なくありません。こうした事態を防ぐために必要なのが共有持分の移転登記です。
持分移転登記とは、共有名義の不動産において持分の一部を第三者に移転する際に行う名義変更手続きのこと。これを怠ると、税金の請求が前の所有者に届いたり、将来的な相続や売却がスムーズに進まなかったりするおそれがあります。
そこで本記事では、持分移転登記が必要となるケースや手続きの流れ、かかる費用、移転を放置するリスク、登記に関する注意点までを網羅的に解説します。
目次
持分移転登記とは
不動産が1人の名義(単有)ではなく、2人以上の名義で登記されていることを「共有」といいます。つまり共有持分とは、それぞれが持っている所有権の割合のこと。
持分移転登記は、共有持分が他の人に移ったときに名義変更をする手続きを指します。移転登記をすることで、登記簿に載っている共有者の名前の変更が可能です。
単なる「所有権移転登記」との違い
不動産の所有権が移るときは「所有権移転登記」を行います。所有権が移る不動産が共有名義である場合は、所有権移転登記に加えて「持分移転登記」が必要です。
不動産を単独で所有しているのであれば所有権移転登記を、共有であればさらに持分移転登記が必要になると認識しましょう。
関連記事:共有持分の不動産を売却する方法とは?売却費用やよくあるトラブルを紹介!
持分移転登記が必要となるケース
持分移転登記をしなくてはいけないのはどのようなケースでしょうか。代表的なものとしては、以下のとおりです。
- ケース①:共有持分を相続した
- ケース②:離婚による財産分与で共有持分を得た
- ケース③:共有持分の贈与を受けた
- ケース④:共有持分を売買した
- ケース⑤:共有持分を放棄した
- ケース⑥:共有物分割請求により代償分割が選択された
ここからは、それぞれについて個別に解説します。
ケース①:共有持分を相続した
被相続人が共有名義の不動産を所有していた場合、その持分は相続の対象となり、相続による所有権移転登記が必要です。相続人が1人であればその人への単独登記、複数人で相続する場合は、その人数分の共有状態になります。
なお、もともと不動産が単独名義だったものを、遺産分割協議などの結果、複数人で分けることになった場合も、新たに共有状態となり、登記が必要です。
関連記事:共有名義不動産を相続するのは危険?よくあるトラブルや手続き方法を解説
関連記事:共有持分の相続放棄って?具体的な手順を徹底解説!
関連記事:共有持分は相続するべき?分割方法やトラブルの回避方法を解説
関連記事:遺産分割協議書とは?共有持分を遺言書なしで相続する場合に必要な理由
ケース②:離婚による財産分与で共有持分を得た
夫婦共有名義の不動産を離婚後に一方の単独名義にする際は、夫婦共有名義の不動産を離婚後に一方の単独名義にする際は、財産分与による持分移転登記を行う必要があります。住宅ローンが残っている場合は、勝手に登記変更を行うとローン契約違反になる恐れがあるため、必ず事前に金融機関に確認をしましょう。
また、登記上の持分と実際の貢献度が異なるケースもあり、財産分与の取り決めに基づいて持分変更を行うことが重要です。
関連記事:離婚時に共有持分はどのように財産分与したらいい?取り扱いの方法を詳しく解説
ケース③:共有持分の贈与を受けた
親から子へ、夫婦間、あるいは兄弟間などで共有持分を贈与した場合には、贈与による所有権移転登記を行う必要があります。贈与は無償で財産を譲る行為であるため、贈与税の課税対象になる可能性がある点にも注意しましょう。
関連記事:共有持分になっている土地を贈与する場合に知っておくべき税金関係の基礎知識
ケース④:共有持分を売買した
他の共有者や第三者との間で、共有持分を売買した場合にも、売買による所有権移転登記を行います。たとえば、他の共有者の持分を買い取って自分の単独名義にしたいときなども該当します。
なお、第三者に売却する際には、他の共有者に対して持分の買取りを優先的に申し出る「共有持分の優先取得権」(民法上の「共有者間の持分譲渡に対する通知」)を行うことが望ましいです。
関連記事:共有持分とは?売却をする方法やよくあるトラブルを紹介!
関連記事:親子の共有名義で住宅購入はあり?メリットや注意点を解説
ケース⑤:共有持分を放棄した
共有持分を放棄すると、民法第255条に基づき、その持分は他の共有者に帰属します。この場合、法的には「持分放棄」ですが、登記上は「贈与」とみなされ、他の共有者に対して贈与による所有権移転登記を行う必要があります。
したがって、実務上は放棄=贈与として扱われ、贈与税の対象になる可能性もあるため注意が必要です。
関連記事:共有持分の放棄で課税される税金とは?贈与税・不動産取得税の扱いを詳しく解説
ケース⑥:共有物分割請求により代償分割が選択された
共有物分割請求とは、共有関係を解消するために、他の共有者に金銭等で補償を行い、単独所有とする方法です。裁判や調停により代償分割が決まった場合には、裁判所の判決や和解調書に基づく所有権移転登記を行います。
分割方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3つがありますが、代償分割では不動産を取得する者が他の共有者に金銭で補償するため、その後の名義変更手続きが必要です。
関連記事:「代償分割」とは?共有持分の分割方法方法として選ぶべきケースを解説
持分移転登記を行うタイミングはいつ?
共有持分の移転登記を行うタイミングは、その取得原因によって異なります。
たとえば、売買によって共有持分を取得した場合は、残代金の支払いと同時に登記手続きを行うのが一般的です。このときは司法書士が立ち会い、売主に残金が支払われた時点で、登記に必要な書類を預かり、速やかに移転登記を行います。
売主が登記手続きに協力しない場合、契約違反(債務不履行)とされる可能性もあり、損害賠償や契約解除の対象となるため注意が必要です。
一方、相続や贈与、離婚による財産分与などの場合は、金銭の授受にかかわらず、できるだけ早めに移転登記を済ませることが望ましいとされています。
特に、相続による取得は、2024年4月から登記申請が義務化されており、取得を知った日から3年以内に登記を行わないと過料(10万円以下)の対象となるため注意が必要です。
持分移転登記の手順
共有持分を取得した場合でも、所有者としての権利を正式に持つためには「移転登記」が必要です。単有名義の不動産と同様、共有持分の移転登記も法務局で行います。
手続きの流れは以下のとおりです。
- 手順1:必要書類を準備する
- 手順2:登録免許税を算出・納付する
- 手順3:申請書類を法務局に提出する
それぞれ個別に解説します。
手順1:必要書類を準備する
登記には、以下のような書類が必要です。状況によって求められる書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。
【登記に必要な書類(一例)】
- 登記申請書(法務局HPからダウンロード可能)
- 住民票(共有持分を取得する人のもの)
- 登記原因証明情報(売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議書など)
- 印鑑登録証明書
- 固定資産評価証明書(市区町村で取得)
- 委任状(代理人に依頼する場合)
また、相続による取得であれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など、相続関係を証明する書類も必要になります。
手順2:登録免許税を算出・納付する
登記を行うには、登録免許税(=固定資産評価額×税率)の納付が必要です。共有持分の場合も、評価額に応じた税額を算出し、収入印紙で支払います。税率は通常2%ですが、相続などの場合は軽減措置があるため注意が必要です。
手順3:申請書類を法務局に提出する
書類が揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。郵送または窓口での提出が可能ですが、提出時に不備があると再提出になるため、事前の確認が推奨されます。
法務局の審査が無事に終わると、「登記識別情報通知書(いわゆる新しい権利証)」が交付されます。これが届けば、登記手続きは完了です。共有持分の正式な権利者として法的に認められたことになります。
持分移転登記で発生する可能性のある費用
移転登記をする際には、以下のような費用の支払いが必要です。
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 必要書類の取得費用
- 司法書士への報酬金
次項より、詳しくご紹介します。
登録免許税
登記にかかる手数料のような税金であり、登記申請の際に法務局に支払う必要があります。金額は不動産の「固定資産税評価額 × 登録免許税率」をかけて算出されます。
(参考:国税庁「登録免許税の税額表」)
持分移転登記の場合、持分割合も計算に含まれるため注意しましょう。
登録免許税率は下記の通りです。
| 相続人による相続の場合 | 4% |
| 贈与の場合 | 2% |
| 遺贈の場合 | 2% |
| 離婚による財産分与の場合 | 2% |
関連記事:共有持分移転登記費用はいくらかかる?登記の際の注意点についても解説
関連記事:共有持分にかかる税金一覧!計算方法や控除制度もセットで徹底解説
不動産取得税
贈与や売買によって共有持分を得た場合、不動産所得税がかかります。金額は、「固定資産税評価額 × 不動産取得税率」となります。不動産取得税率は下記の通りです。
| 税率 | 標準税率本則4%<税率の特例> 住宅及び土地3%(令和6年3月31日まで) |
| 課税標準及び税額の特例 | <住宅・住宅用地の特例>
新築住宅→1,200万円を控除 中古住宅→住宅の新築時期により最高1,200万円を控除
150万円又は床面積の2倍の面積(200m2限度)に相当する土地 の価格のいずれか大きい額に税率を乗じて得た額を減額 <住宅用地・商業地等の特例>
|
(参考:総務省「不動産取得税」)
この費用は登記時に必要な訳ではなく、共有持分取得した翌年に納付書が送られてくるタイミングで支払います。離婚時の財産分与や相続の場合、不動産取得税はかかりません。
関連記事:共有持分を取得した場合にかかる「取得税」とは?節税対策もセットで解説
必要書類の取得費
住民票や印鑑証明書を取得するためには、各種書類の取得費用が必要です。また相続の場合、戸籍謄本が必要になることもあります。
| 住民票 | 300円程度 |
| 印鑑登録証明書 | 300円程度 |
| 固定資産税評価証明書 | 300円程度 |
| 戸籍謄本 | 450円程度 |
取得費用は自治体によって異なる場合があるため、確認しましょう。
司法書士への報酬金
持分移転登記は自分で行うことも可能ですが、司法書士に依頼するケースも多々あるでしょう。費用は依頼先によって異なりますが、相場は1件3~8万円となっています。
複数の共有持分移転を行う際には、件数分の費用が必要になる場合もあります。依頼前に金額を確認しておくといいでしょう。
持分移転登記しないで放置するリスク
移転登記をしないままにしておくと、どのようなことが起こるのでしょうか。考えられるリスクとしては、以下が挙げられます。
- リスク①:固定資産税の請求が前の共有者に届いてしまう
- リスク②:不動産を担保に融資を受けられない
- リスク③:相続が発生すると関係者が複雑になる
それぞれについて、個別に説明します。
リスク①:固定資産税の請求が前の共有者に届いてしまう
不動産の固定資産税は、毎年1月1日時点の登記上の所有者に課税されます。移転登記をしない限り、法的には前の所有者が引き続き納税義務を負うため、税通知や納税書類が前の共有者に送られてしまうことになります。
一時的な遅れであれば事情を説明して対応することもできますが、長期にわたり移転登記を怠ると、税務処理や名義人間の関係に支障をきたし、トラブルに発展する可能性もあります。
リスク②:不動産を担保に融資を受けられない
登記が移転されていない場合、法的には所有者が変更されていない状態と扱われるため、不動産を担保に金融機関から融資を受けることはできません。共有持分であっても、登記された名義人でなければ権利を証明できず、担保提供や売却、賃料請求などの処分行為も制限されます。
そのため、事業資金や生活資金の借入れを検討している場合、速やかな登記が重要となります。
リスク③:相続が発生すると関係者が複雑になる
移転登記をせずに共有持分を相続したまま放置していると、次の相続が発生した際に、新たな相続人が増えることで権利関係が複雑化します。
たとえば、当初1人に相続されたはずの持分が、その人の死去により配偶者や子どもに再び相続され、共有者が細分化されてしまうおそれがあります。
結果として、権利者全員の合意が取れずに売却や共有物分割が困難になるなど、後々のトラブルに発展する可能性が高まります。
持分移転登記に関する注意点
共有持分の移転登記は、法律上の権利を確定させるうえで欠かせない手続きです。しかし、見落としやすい落とし穴もいくつか存在します。
ここからは、登記を行う前に知っておきたい注意点を詳しく解説します。
注意点①:未登記では法的な所有者と認められない
共有持分を相続・売買・贈与などで取得しても、移転登記をしなければ法的には所有者とは認められません。登記簿に名前が記載されていない以上、売却や担保設定といった処分行為を行う権限も得られず、不動産を有効活用することができません。
また、将来的に相続や共有者間でのトラブルが発生した際も、「自分の権利」を主張できない状況に陥るリスクがあります。共有持分の取得が完了した時点で速やかに移転登記を行うことで、所有者としての地位を確立し、法的リスクを回避できます。
注意点②:取得原因により税負担が変わる
取得原因ごとの登録免許税率や不動産取得税の有無についてはすでに解説したとおりですが、実務上の注意点としては「手続きにかかる費用が想定より大きくなりがち」という点です。
たとえば、贈与であれば贈与税や登記にかかる費用が高額になることもあり、売買の場合も税率が2%と高めに設定されています。
こうした税負担に加え、司法書士への報酬や必要書類の取得費用も発生するため、登記前にはトータルコストを必ず試算しておきましょう。不安がある場合は、早い段階で専門家に相談しておくのが安心です。
注意点③:ローンがある場合は金融機関の承諾が必要
対象の不動産に住宅ローンが残っている状態で持分移転登記を行う場合、金融機関の承諾が必要となります。
ローン契約には、担保となる不動産の所有者が変更された場合の通知義務や承諾条件が定められていることが多く、勝手に登記手続きを進めると契約違反となり、ローン残債の一括返済を求められるおそれもあります。
特に、離婚や贈与などで一方が持分を手放すケースでは、慎重な確認が不可欠です。事前にローン契約書を確認し、必要に応じて金融機関に連絡を入れるなど、登記手続きとローンの条件を両立させる準備をしておきましょう。
「ワケガイ」なら共有持分の売却も短期で対応可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり不動産の専門買取サービス「ワケガイ」を提供しています。
共有持分や共有名義の不動産は、売却時に全共有者の同意が必要であるなど、取引が難航しやすい物件です。特に相続や離婚を経て共有者が増えていたり、連絡がつかない共有者がいたりすると、思うように売却が進まず、手続きが長期化してしまうこともあります。
ワケガイでは、共有持分だけの単独買取にも対応しており、複雑な事情を抱える物件でも豊富な実績があります。司法書士や弁護士と連携し、スムーズな売却をサポートいたします。共有名義の整理にお困りの方は、お気軽に無料査定をご活用ください。
関連記事:【2025年版】共有持分の買取業者のおすすめ厳選5社!今買取をお願いするべき専門業者とは?
まとめ
共有持分の移転登記は、不動産の持分を取得した際に「法的な所有者」として認められるための重要な手続きです。これを怠ると、固定資産税の誤請求や、相続時のトラブル、融資不可といった問題が生じかねません。
登記には一定の費用や書類準備が必要ですが、長期的に見れば、将来的なトラブル回避や円滑な資産管理においては不可欠な行為といえるでしょう。とくに取得原因によって課税や必要手続きが変わるため、事前の調査や専門家への相談も視野に入れておくべきです。
共有持分を得たら、放置せず、できるだけ早めに登記手続きを進めるようにしましょう。