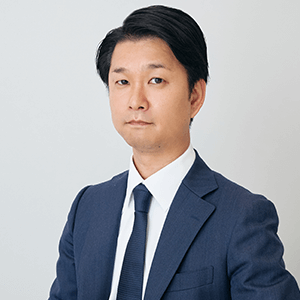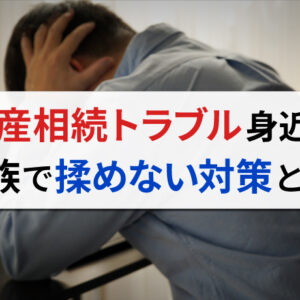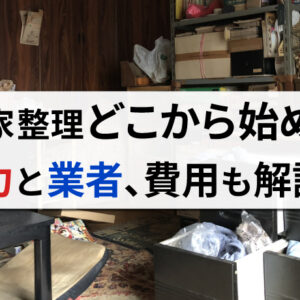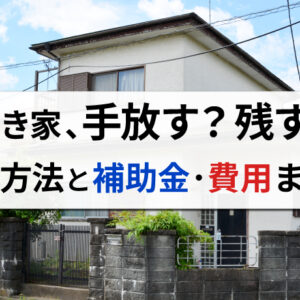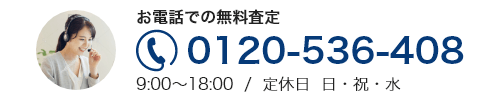について今すぐご相談できます。
お電話する
所有者不明土地は所有者の探索に多大な手間がかかるため、利用意向があっても土地を活用することが難しかったり、公共事業や災害からの復興事業を進めるにあたって妨げとなってしまったりするなどの課題があります。
このような課題を受け、所有者不明土地問題を解決するために、国も少しずつ具体的な取り組みを打ち出してきました。
今回は、「所有者不明土地の解決方法」の一翼を担う特別措置法の詳しい内容と、その後新たに行われた法改正について、実際の土地活用事例も紹介します。
目次
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法)」とは
この特別措置法は、所有者不明土地を「公共的目的」のもとに利用できるようにするための新制度として、大まかに3つの観点から作られました。
- 所有者不明土地を円滑に利用する仕組み
- 所有者の探索を合理化する仕組み
- 所有者不明土地を適切に管理する仕組み
以下より、それぞれ個別にみていきましょう。
所有者不明土地を円滑に利用する仕組み
利用に反対する所有者がおらず、建築物(簡易な構造で補償額の算定が容易なものを除く)が無く、現在利用されていない所有者不明土地であるという場合、以下の2つの仕組みを利用できるようになりました。
- ①:これまでに比べ合理的かつスムーズになった手続き
- ②:地域住民等のために創設された新たな事業(地域福利増進事業)
まず、①についてですが、公共事業、例えば道路建設などの際に、土地収用法の特例として、国や都道府県知事が事業の合理性を確認。収用委員会の代わりに都道府県知事が判断を下すことが許され、従来の審理手続きが省略され、土地取得や移転の手続きが効率化されました。
次に②について述べると都道府県知事は、公共の利益やその他の要因を考慮し、市町村長の意見を取り入れ、一定の期間公示した後、土地の使用権(最大10年)を設定する権限を持ちます。
これにより、所有者不明の土地に小さな公園や農産物の直売所を設けるなどの利用が可能になりました。
ただし、もし所有者が明らかになり、土地を返還するよう求められた場合、期間が終わった後には土地を元の状態に戻す必要があります。異議がなければ、10年以上の延長も検討される可能性もあるでしょう。
関連記事:所有者不明土地とは? 現状と支障になっている事例の紹介
所有者の探索を合理化する仕組み
原則として、登記簿や住民票、戸籍といった公的な情報をもとに調査を行いますが、固定資産の税務記録やインフラ関連の情報など、さまざまな有益なデータを行政が活用することが許されるようになりました。
加えて、情報の取得方法も改善され、特定の親族や詳しい情報を持つ住民からの情報提供の範囲を明確にしたことで、調査がより合理的になりました。
所有者不明土地を適切に管理する仕組み
土地の適切な管理が求められる場合、地方自治体の責任者は家庭裁判所に、財産の管理者を任命するよう求めることが可能になっています。
これらの新しい手段や制度を通じて、所有者不明の土地の有効活用への道が広がり、それまでの手間や時間のかかる手続きを大幅に効率化できるようになったといえるでしょう。
所有者不明土地問題のさらなる解決方法とは?
以上の動きに加え、令和3年には「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が公布されました。
これらの法律は、所有者不明土地を「利用しやすく」することと、「更なる発生を防ぐ」という2つの観点から総合的に民事基本法制の見直しをはかったものです。
所有者不明土地を利用しやすくする
土地利用に関する改革として、共有、財産管理、そして相続に関する制度のルールが大きく見直されました。
これにより、所有者不明土地の有効活用が促進されることが期待されています(令和5年施行予定)。
所有者不明土地そのものを発生しにくくする
まず、土地の「登記義務化」が導入され、相続や住所変更に関連する土地の登記が義務付けられるようになりました(令和6年施行予定)。
このほか、もし相続などで得た土地が不要であれば、「所有権放棄」という新たな制度を利用して、土地の所有権を国に譲渡することが可能となりました(令和5年施行予定)。
近年、土地を単なる資産と見なす価値観が変わりつつあります。そのため、この新制度は、不要な土地を放置せず、効果的に活用するため上では非常に大切です。
関連記事:「所有者不明土地」の主な課題とは?注目すべき3点を解説
所有者不明土地法の円滑な運用に向けた先進事例構築推進調査
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が施行されたことで、公共の広場や施設として所有者不明土地を利用する「地域福利増進事業」が立ち上げられました。
国土交通省は、所有者不明土地問題への対策として、NPO、民間事業者、地方公共団体の先進的な活動を一部支援しています。この取り組みの中心的な目的は、成功例や知見を全国に共有し、所有者不明土地の効果的な利用や管理を推進すること。
具体的な支援内容としては、所有者の探索や事業計画の策定、関係者との意見交換会の開催などがあり、一つの地域に対しては最大300万円の予算が確保されています。
毎年度、公募を基に7地区程度が選ばれ、令和3年度では、6つの取り組みが支援の対象として選出されました。
================
■北海道 旭川市 (NPO)
市内に点在する管理不全状態の所有者不明土地の内の1箇所について、地域福利増進事業によって、児童や高齢者等が利用する地域の公園としての整備を検討する。
■新潟県 南蒲原郡 田上町 (一般社団法人 福祉関係)
竹が繁茂し、管理不全状態となっている所有者不明土地について、地域福利増進事業による竹林の適正管理、緑地としての整備を図ることで、竹林を活かしたイベント等を通じた地域交流や青少年育成の場としての活用を検討する。
■千葉県 八千代市 (一般社団法人 まちづくり関係)
住宅地内の道路脇の木が生い茂る管理不全状態の所有者不明土地を地域福利増進事業によって適正に管理し、災害時に備えた通路等としての確保を検討する。
■東京都 八王子市 (NPO)
住民の高齢化が進行する住宅団地内において、点在する管理不全状態の所有者不明土地について、生活環境の改善、地域の防災性の向上、高齢者の交通利便性の向上に資することを目的として、地域福利増進事業によりソーラーシェアリング等の再生可能エネルギーを推進する土地利用を検討する。
■兵庫県 川西市 (任意団体)
20年以上前に発生した火災の瓦礫が放置され、雑草繁茂や不法投棄、強風・豪雨等に伴う近隣への悪影響が発生するなど、管理不全状態の所有者不明土地について、地域の防災性の向上、 生活環境の向上等を図るため、地域福利増進事業による防災空地や地域の菜園(公園)等の整 備・適正管理の方法を検討する。
■鹿児島県 奄美市 一般社団法人 (まちづくり関係)
相続人の中に行方不明者がいる所有者不明土地について、障がい者の就労支援や育児支援に資する社会福祉施設等、地域の生活利便向上を図るための地域福利増進事業を検討する。
================
(出典:国土交通省「令和3年度 『所有者不明土地対策の推進に向けた先進事例構築モデル調査』支援対象一覧」)
これらの取り組みをみると、所有者不明土地の現状とそれに対する取り組みの幅広さを感じることができます。民間の力を活用し、多様なアイディアを取り入れることで、所有者不明土地問題への新たなアプローチが生まれているといえるでしょう。
利用されていない土地の具体的な活用事例
さらに、これまで利用されていなかった土地を活用して地域の活性化に寄与することができた事例も、日本全国に既にできつつありますので、ここでいくつかご紹介します。
================
■北の屋台(帯広市)
わずか19台ほどの車しか駐車されていなかった駐車場スペースを利用し、街の活気を取り戻すべく屋台村を展開。
地元の商工会議所青年部等のメンバーの働きかけで、土地に水道・電気・ガス等の設備を整備し屋台形式のまま飲食店としての許可を取得。年間3億円超の売上げを記録するほどの地元の人気スポットとなった。
■わいわいコンテナプロジェクト(佐賀市)
街中の空き地や駐車場を借り、中古のコンテナを利用した図書館等や芝生の広場を設置。
8ヶ月間で約1万5千人が来場するほどの賑わいをみせた。
社会実験としてプロジェクトが行われた後は、地元Jリーグチームの市内拠点として活用されている。
■まちなか防災空地整備事業(神戸市)
普段は広場やポケットパーク(公園)等、地域の交流の場として利用しつつ、災害時には防災活動の場として活用できる防災空地を整備。密集市街地において火災時の延焼を防止する目的で老朽木造建物を除却し、その跡地を活用。
================
このほかにも、「築年数の古い団地において空き家や空き地が生じた際、地元の不動産業者がまず隣地の居住者等に隣地取得を働きかけた例」「保育園の立て替え中の仮園舎の用地として、自治体が既に保有する公有地を活用するといった取り組み」などもあります。
まとめ
日本の土地政策は、長い間、バブル期の地価の急上昇を抑えるための「適正かつ合理的な土地利用」を中心に形成されてきました。その後、バブルが崩壊すると、人々が安心して生活できる「土地の有効利用」の推進が重要なテーマとして前面に出てきました。
しかし、我々は現在、社会の大きな変容期を迎えており、人口の減少、都市集中、それに伴う空き地や空き家、さらには所有者不明土地問題といった新しい課題に直面しています。
近い将来を見据えると、土地価値の二極化、我が国の急速な高齢化、予測困難な自然災害が増加するなか、土地政策の方針や関連する法律、特に土地基本法や民事基本法制などの改正が求められています。
これらの改正から、国が所有者不明土地の管理や活用を如何に重視しているかを読み取れるでしょう。
所有者不明の土地が日本全土に点在している現状を考えると、その原因や特徴、管理の状態などは多岐にわたり、一律の解決策を見つけるのは難しいかもしれません。しかし、適切な法制度やガイドラインが確立されれば、その土地をクリエイティブに活用する方法は無限に存在します。
過疎化が進行する地域を再生する手段として、土地の再活用により観光資源を創出し、地域の活気を取り戻す取り組みは、非常に有望です。その可能性は、まさに計り知れないものがあると感じられます。
このような法制度の改革をきっかけに、全国での成功事例を増やし、所有者不明土地問題を段階的に解決する方向に進むことが期待されています。
本ブログで情報発信を行っている「ワケガイ」は、訳あり物件を積極的に買い取っている専門業者です。所有物件についてお悩みの方は、訳あり物件の買取に特化したワケガイに、ぜひお問い合わせください。
<参考>(※URL最終閲覧2024年1月24日)
法務省 「令和3年民法・不動産登記法改正、 相続土地国庫帰属法のポイント」https://www.moj.go.jp/content/001360808.pdf
法務省 「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
国土交通省 「所有者不明土地法の円滑な運用に向けた先進事例構築推進調査」https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/kanteishi/totikensangyo_tk2_000124.html
国土交通省 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する 特別措置法(所有者不明土地法)について」https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001352323.pdf
国土交通省 「改正土地基本法と今後の土地政策について」https://www.cbr.mlit.go.jp/yochibu/chuburenkeikyo/pdf/r2totikihonhou.pdf
国土交通省 「所有者不明土地を取り巻く 状況と課題について」https://www.mlit.go.jp/common/001201306.pdf
| 運営団体 株式会社ネクスウィル 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 |