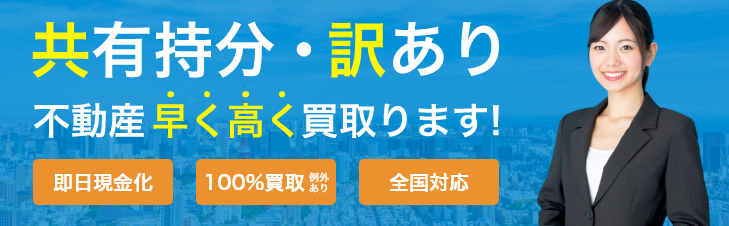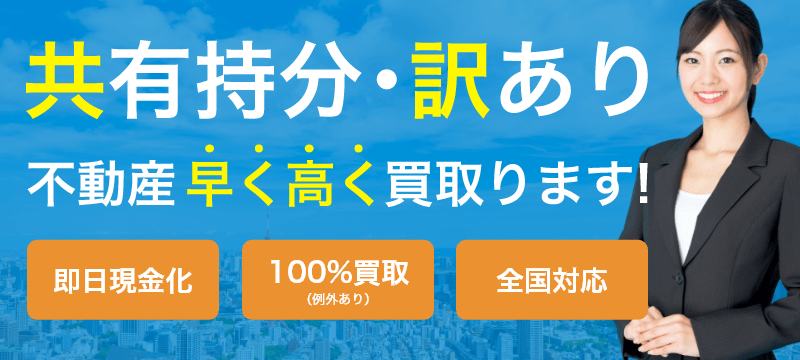共有持分の譲渡とは、複数人で所有する不動産の権利の一部を他者に移転することです。相続や離婚などで共有不動産を処分したいとなった場合、権利を手放すための方法の1つとなります。
ただし、共有持分を適切に譲渡しないと、将来的なトラブルや税務上の問題が発生するリスクがあります。
本記事では、共有持分の譲渡の方法や手続きの流れなど、共有持分の譲渡に関する重要ポイントを詳しく解説します。共有不動産の問題解決に向けた第一歩として、ぜひご活用ください。
目次
共有持分の譲渡とは
そもそも共有持分とは、1つの不動産を複数の人が共同で所有している状態において、各所有者が持つ権利の割合を指します。
例えば、親から相続した土地を兄弟で共有する場合や、夫婦でマンションを購入した場合などが該当します。共有持分は、不動産の物理的な区分ではなく、所有権の割合を表すものです。
共有持分の特徴として、各共有者は自身の持分に応じて不動産全体を使用する権利を持ちますが、不動産の処分や大きな変更には他の共有者全員の同意が必要となります。また、固定資産税などの費用負担も持分に応じて行われます。共有持分は登記簿に記載され、各共有者の権利割合が明確にされます。
共有状態は法律上「一時的な権利状態」とされており、将来的には単独所有や区分所有などに移行することが想定されています。
共有持分の譲渡は、この一時的な状態を解消するための1つの方法なのです。
共有持分を譲渡するメリット
共有持分を譲渡することには、いくつかの重要なメリットがあります。
まず、共有関係から抜け出せるため、他の共有者との意見の相違や管理の煩わしさから解放されます。特に相続で予期せず共有状態になった場合や、離婚後の財産分与の際などに、この点は大きな利点となります。
また、譲渡によって得られる金銭的利益も重要なメリットです。不動産の価値に応じた対価を得ることができ、その資金を他の用途に活用できます。特に、維持費や固定資産税の負担が重い場合、これらの支出から解放されることも経済的なメリットと言えるでしょう。
さらに、将来的なトラブルの予防にもつながります。共有状態が長期化すると、相続や売却の際に複雑な問題が発生する可能性が高まります。早期に譲渡することで、こうしたリスクを回避し、不動産の効率的な活用や管理を促進することができます。
加えて、税務面でのメリットも考えられます。例えば、贈与による譲渡の場合、計画的な贈与を行うことで相続税の軽減につながる可能性があります。また、売却による譲渡の場合も、適切なタイミングで行うことで税負担を最適化できる可能性があります。
共有持分を譲渡する際の3つの方法
共有持分を譲渡する方法には、「売買」「贈与」の2つの選択肢が存在します。それぞれ個別にみていきましょう。
方法①:売買
共有持分の売買は、自身の持分を金銭と交換に他者に譲渡する方法です。この方法は、共有者間での売買や第三者への売却が可能。売買による譲渡の利点は、譲渡者が対価を得られることです。
ただし、共有持分の売却価格は通常の不動産売却よりも低くなる傾向があります。これは、共有状態特有の制限や将来的なリスクが価格に反映されるためです。売買契約を結ぶ際は、他の共有者への事前説明や了解を得ることが望ましく、トラブル防止につながります。
<売買のメリット>
- 持分を売却することで、現金化が可能
- 共有関係から抜け出し、管理や税金の負担をなくせる
- 共有者間での売買が成立すれば、手続きがスムーズ
<売買のデメリット>
- 共有持分のみでは市場価値が低く、希望額で売却しにくい
- 共有者の同意がないと売却先によっては関係が悪化する可能性がある
- 買い手が見つからない場合、売却に時間がかかる
関連記事:共有持分の不動産を売却する方法とは?売却費用やよくあるトラブルを紹介!
関連記事:共有持分を売却した際にはどのような税金がかかる?
方法②:贈与
贈与は、共有持分を無償で他者に譲り渡す方法です。主に家族間や親族間で行われることが多く、相続税対策の一環として活用されることもあります。
贈与の利点は、譲渡手続きが比較的簡単で、受贈者の同意さえあれば成立する点です。ただし、贈与税の課税対象となる可能性があるため、税務面での検討が必要です。また、贈与契約書の作成や登記手続きなど、法的な手続きは確実に行う必要があります。
<贈与のメリット>
- 売却とは異なり、共有者間で合意しやすい
- 親族間で持分を整理するのに適している
- 共有関係を解消しつつ、財産の引き継ぎができる
<贈与のデメリット>
- 贈与税の課税対象となるため、税負担が発生する可能性がある
- 贈与契約書の作成や登記手続きが必要
- 受贈者が共有持分を引き継いだ後の管理負担を考慮する必要がある
方法③:交換
交換は、共有持分を他の不動産や財産と交換する方法です。特に、相続によって兄弟姉妹が複数の不動産を共有している場合や、他の共有者が自分の持分と引き換えに単独所有を希望する場合に用いられることが多くなります。交換により、双方が納得できる形で不動産の整理が進められる点が特徴です。
交換する財産の価値が等価であれば、追加の金銭負担は発生しません。ただし、価値に差がある場合は、その差額を補填する「交換差金」を支払う必要があります。また、交換の対象となる財産の評価を適切に行わなければ、不公平な取引となる可能性があるため、慎重に進めることが重要です。
さらに、交換の場合でも譲渡所得税が発生する可能性があります。これは、交換した不動産の価値が取得時よりも上がっていた場合、差額が「譲渡益」として課税対象となるためです。そのため、交換を行う際は、事前に税務面の影響を確認しておくことが必要です。
<交換のメリット>
- 共有者間でスムーズに持分の整理ができる
- 現金を用意せずに、不動産の権利を調整できる
- 共有関係を解消しつつ、双方にとって公平な取引が可能
<交換のデメリット>
- 交換対象の財産の価値評価を適切に行う必要がある
- 交換差金が発生する場合、金銭的な負担が増えることがある
- 交換による譲渡所得税が発生する可能性があるため、税務対策が必要
共有持分の譲渡に関わる税金
共有持分を譲渡する際には、次の税金が課税されることも留意しておきましょう。
- 不動産取得税(※売買・贈与・交換の場合)
- 譲渡所得税(※売買・交換の場合)
- 贈与税(※贈与の場合)
以下より、詳しく解説します。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を取得した際に、その不動産の価格に応じて課税される地方税です。共有持分を購入したり、贈与を受けたりした場合にも課税対象となります。
不動産取得税の税率は、原則として課税標準額(固定資産税評価額)の4%です。ただし、2024年3月31日までは、土地と住宅については3%に軽減されています。
(参考:総務省「不動産取得税」)
共有持分を取得した場合、取得した持分割合に応じた課税標準額に税率を乗じて税額が計算されます。例えば、評価額1,000万円の不動産の50%の共有持分を取得した場合、500万円に税率を乗じた額が不動産取得税となります。
なお、一定の要件を満たす住宅や土地を取得した場合は、課税標準の特例措置や税額控除が適用される場合があります。
不動産取得税は、不動産の取得から通常3〜8ヶ月後に、都道府県から納税通知書が送付されます。納付期限は、納税通知書が届いてから60日以内です。
関連記事:共有持分を取得した場合にかかる「取得税」とは?節税対策もセットで解説
譲渡所得税
譲渡所得税は、共有持分を売却して利益(譲渡所得)が生じた場合に課税される税金です。譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算されます。譲渡所得税の税率は、所有期間によって異なります。
<所有期間が5年を超える長期譲渡所得の場合>
- 所得税15%(復興特別所得税0.315%を含む)+ 住民税5% = 計20.315%
<所有期間が5年以下の短期譲渡所得の場合>
- 所得税30%(復興特別所得税0.63%を含む)+ 住民税9% = 計39.63%
(参考:国税庁「短期譲渡所得の税額の計算」「長期譲渡所得の税額の計算」)
ただし、居住用財産の譲渡所得に関しては、3,000万円の特別控除が適用される場合があります。この特別控除は、共有者それぞれに適用されるため、共有持分の譲渡においても有効に活用できる可能性があります。
また、譲渡所得が発生した場合、確定申告が必要となります。申告期限は、譲渡した年の翌年の2月16日から3月15日までです。
贈与税
贈与税は、共有持分を無償で譲渡(贈与)した場合に、受贈者(贈与を受けた人)に課税される税金です。
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額(年間110万円)を差し引いた額に対して行われます。
贈与税の税率は、贈与を受けた財産の価額によって異なり、10%から55%の間で段階的に上昇します。ただし、直系尊属(親や祖父母など)からの贈与の場合は、特例税率が適用され、最高税率が45%になります。
(参考:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)
共有持分の放棄の場合も、他の共有者の持分が増加することから、贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。
なお、贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。
関連記事:共有持分の贈与税を節税する方法とは?具体的な対策を紹介
共有持分の譲渡における注意点
共有持分を譲渡する際には、次の点にも留意する必要があります。
- 他の共有者との関係を調整する
- 住宅ローンや担保設定を確認する
- 共有物分割請求訴訟に備える
それぞれ個別に解説します。
他の共有者との関係を調整する
共有持分の譲渡を円滑に進めるためには、他の共有者との関係調整が求められます。まず、譲渡の意向を他の共有者に事前に伝え、理解を得ることが大切。この際、譲渡の理由や譲渡後の不動産の取り扱いについて、明確に説明することが望ましいです。
他の共有者から反対意見が出た場合は、丁寧に話し合いを重ね、互いの立場を理解し合うことが重要です。場合によっては、譲渡の条件や時期の調整、あるいは他の共有者への優先的な譲渡の提案など、柔軟な対応を検討することも有効です。
また、共有者間で将来的な不動産の管理や処分に関する取り決めを文書化しておくことで、後々のトラブルを防げるでしょう。例えば、共有者の一人が持分を譲渡する際の手続きや、他の共有者の優先買取権などを明確にしておくことが有効です。
譲渡所得が発生したら確定申告を行う
共有持分を売却した場合、売却益が発生すると譲渡所得税が課される可能性 があります。そのため、確定申告を行う必要があるか事前に確認 しておくことが重要です。
- 売却価格が取得費を上回る場合、譲渡所得が発生し、課税対象となる
- 譲渡所得税は不動産の所有期間によって税率が変わる(短期譲渡と長期譲渡で異なる)
- 特別控除や繰越控除が適用されるケースもあるため、税理士に相談するのも有効
申告漏れがあると追徴課税の対象になるため、売却後は税務処理を適切に行いましょう。
住宅ローンや担保設定を確認する
共有持分に住宅ローンが残っている場合や、担保として設定されている場合、勝手に売却や譲渡を行うことはできません。そのため、事前に金融機関や担保権者と相談し、譲渡の可否を確認することが必要 です。
- 住宅ローンが残っている場合、売却代金で完済する必要がある
- 抵当権が設定されている場合、金融機関の同意がなければ譲渡できない
- 共有者がローンの連帯保証人になっている場合、譲渡後も保証義務が残るケースがある
ローンや担保の問題を整理せずに譲渡を進めると、金融機関とのトラブルにつながる可能性があります。契約前にしっかりと確認し、必要な手続きを行いましょう。
このように、共有持分を第三者に譲渡する際には、譲渡先の選定、既存の共有者との関係構築、信頼できる買取業者の選別、税務処理、ローンや担保の確認 という5つのポイントを意識することが、後々のトラブルを避けるために不可欠です。
共有物分割請求訴訟に備える
共有物分割請求訴訟は、共有関係の解消を目的として提起される訴訟です。他の共有者との話し合いが難航した場合や、第三者に譲渡した結果として提起される可能性があります。
この訴訟に備えるためには、まず自身の持分や不動産の状況に関する証拠書類をしっかりと保管しておくことが重要です。「登記簿謄本」「固定資産評価証明書」「不動産の維持管理に関する記録」などが該当します。
また、共有不動産の利用状況や各共有者の寄与度についても、できる限り客観的な記録を残しておくことが有効です。これらの情報は、訴訟において自身の主張を裏付ける重要な証拠となります。
さらに、訴訟に発展する前に、調停や和解などの裁判外紛争解決手続き(ADR)の利用を検討することも有効です。これらの手続きは、訴訟に比べて柔軟な解決が可能であり、共有者間の関係悪化を最小限に抑えられる可能性があります。
関連記事:共有物分割請求とは?請求方法や流れを解説
譲渡以外の共有持分の解消方法
共有持分を整理する方法は、売買や贈与、交換だけではありません。共有状態を解消する手続きとして、「放棄」や「共有物分割」という選択肢もあります。これらの方法を適切に活用することで、
共有関係による制約をなくし、よりスムーズに不動産を管理・活用できるようになります。
共有持分の放棄
共有持分の放棄とは、自身の持分を手放し、他の共有者に帰属させる方法です。 他の共有者の同意を得る必要がないため、個人の判断で手続きを進められる点が特徴です。
ただし、放棄した持分は国庫に帰属するわけではなく、他の共有者の持分割合に応じて自動的に配分される 仕組みになっています。そのため、放棄によって持分を取得した共有者が「贈与を受けた」とみなされ、贈与税の課税対象になる可能性があるため注意が必要です。
また、放棄をしたからといって、ただちに不動産の管理義務や固定資産税の支払い義務から解放されるわけではありません。共有持分の放棄を考える場合は、事前に他の共有者と話し合いを行い、税務や管理責任の問題を整理しておくことが重要です。
関連記事:共有持分は放棄できる?具体的な手順や発生する費用をチェック!
共有物分割
共有物分割とは、共有状態を解消し、各共有者が単独で所有権を持つ形にする方法です。 共有者全員の合意が得られれば、円満に共有関係を解消できますが、合意が難しい場合は裁判所に分割を請求することも可能です。
分割には以下の3つの方法があります。
- 現物分割:不動産を物理的に分割し、それぞれが単独所有とする。土地の分筆などが代表的な例。
- 換価分割:不動産を売却し、得られた売却代金を共有者間で分配する方法。共有者同士の意見がまとまらない場合に有効。
- 代償分割:一部の共有者が他の共有者の持分を買い取り、単独所有とする方法。共有関係を整理したい場合に適している。
共有物分割を行うことで、共有関係による意思決定の遅れや管理の煩雑さを解消できます。どの分割方法を選ぶかは、共有者間の合意や不動産の特性に応じて慎重に検討する必要があります。
関連記事:共有持分の「換価分割」とは?メリット・デメリット、選択すべきケースを紹介
関連記事:「代償分割」とは?共有持分の分割方法方法として選ぶべきケースを解説
「ワケガイ」なら共有持分の売却もスムーズに対応可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分をはじめとする訳あり不動産の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。通常の不動産市場では売却が難しい共有持分も、当社の専門的な知識と豊富な実績を活かし、迅速かつ適正な価格での買取を実現しています。
共有持分の売却は、単独所有の不動産とは異なり、共有者間の調整が必要だったり、市場価値が低く評価されやすかったりするため、一般の不動産会社では買い手が見つかりにくいケースが少なくありません。
ワケガイでは、こうした問題を抱えた共有持分の買取に関する無料査定を行っており、最短1日で買取価格の提示が可能です。
共有者との関係や売却の進め方に悩んでいる方も、お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
共有持分の譲渡は、共有状態を整理し、不動産を有効活用する手段のひとつです。
しかし、売却価格が低くなりやすい、税負担が発生する、共有者間の合意形成が難しいといった問題もあるため、慎重な判断が求められます。
譲渡を検討する際は、まず 売買・贈与・交換のいずれの方法が最適かを判断し、税金や契約のポイントを事前に確認することが重要です。
また、確定申告やローンの残債、抵当権の有無など、見落としがちな点についても事前に整理しておきましょう。
共有者間のトラブルを防ぐためにも、譲渡契約の内容を明確にし、必要に応じて専門家に相談するのが賢明です。適切な方法で譲渡を進めることで、不要なリスクを避けながら、円滑な不動産活用を実現しましょう。