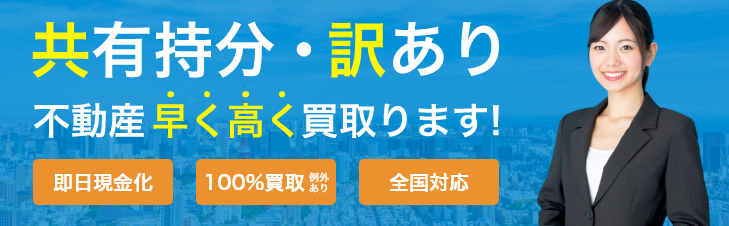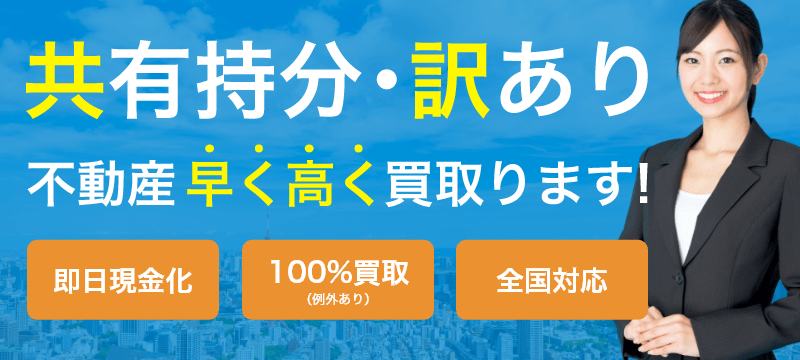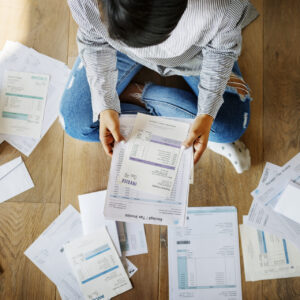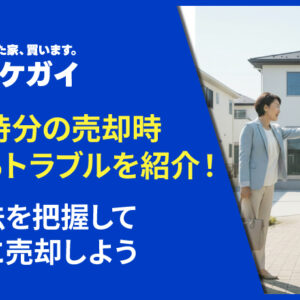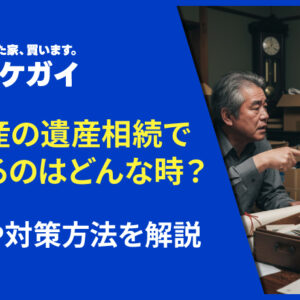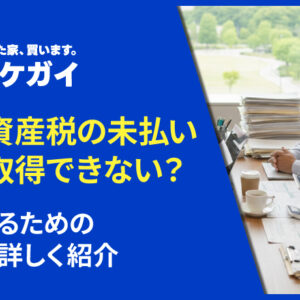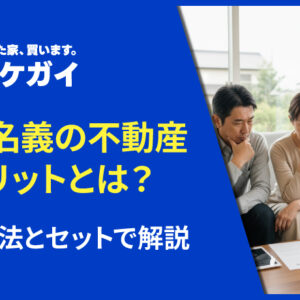親子共有名義で保有している不動産を生前贈与するべきか迷っている方は少なくないでしょう。生前贈与すれば、基本的に相続税は発生しません。そのため、節税効果が高いように思えます。
しかし、正しい方法で生前贈与を行わないと、贈与税が高額になるため注意しなりかねませんません。
本記事では、親子共有名義の不動産の生前贈与について詳しく解説します。親子共有名義の不動産の取り扱いに悩んでいる方は、ぜひお役立てください。
目次
生前贈与とは

生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産の一部を家族や親族などに無償で譲り渡す行為を指します。通常は現金や預貯金、不動産、有価証券、車などの資産が対象となります。
生前贈与は、相続におけるトラブルの回避や、相続税対策を目的として行われます。しかし、生前贈与は、贈与税の対象となるため、金額によっては申告と納税が必要です。
一定額までであれば非課税となる制度も整っており、うまく活用すれば税負担を抑えられます。節税目的で生前贈与を行う場合は、どのように活用するかが重要になるといえるでしょう。
また、生前贈与を行う際には、贈与する相手との合意が必要であり、後に争いにならないように契約書を作成しておく必要もあります。
共有持分とは

共有持分とは、一つの不動産を複数の人が共有している状態において、それぞれが所有している権利の割合を指します。
不動産を共有している場合、各共有者は不動産全体に対して自分の持分に応じた権利を有しており「土地の2分の1を所有している」といった形で表現されます。
共有者は自分の持分について自由に売却や譲渡を行えます。しかし、物件全体の利用や処分には他の共有者との協議が必要になることが多く、トラブルの原因になるケースも少なくありません。
共有持分を生前贈与するメリット

共有持分を生前贈与するメリットは主に4つあります。それぞれ詳しく解説しますので、共有持分の取り扱いに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
相続に関するトラブルを事前に防止できる
共有持分を生前に贈与することで、相続発生時のトラブルを未然に防ぐことができます。相続人同士で共有不動産の分割方法について意見が分かれたり、感情的な対立が起きたりするケースは珍しくありません。
生前贈与で共有持分の行先を明確にしておけば、遺産分割協議を避けられますので、スムーズな相続に繋がるでしょう。
相続税の対策になる
生前贈与は、相続税対策としても有効です。
暦年贈与の基礎控除により、1人につき年間110万円までの贈与は課税されません。この仕組みを踏まえて毎年少しずつ共有持分を移転していけば、将来の相続財産を減らすことができ、相続税の負担軽減につながります。
相続税の課税対象額を抑えられる可能性が高まり、家族の税負担を軽減できます。
(参考:国税庁「相続税」)
贈与する相手を選べる
生前贈与であれば、共有持分の贈与先を自分で選ぶことができます。例えば、将来的にその不動産を有効活用しそうな子どもに持分を集中させることで、将来的な管理や売却の意思決定がスムーズになります。
贈与先の選定により、意図した不動産の活用計画を実現しやすくなるのもメリットの一つです。
贈与後の不動産の活用がスムーズになる
贈与によって共有者が整理されれば、不動産の活用がよりスムーズになります。共有者が少数になったり、同じ方向性を持つ家族間で共有状態を形成できたりすれば、売却・賃貸・建て替えなどを行う場合も対応しやすくなるでしょう。
共有持分を生前贈与するデメリット

共有持分の生前贈与にはメリットだけでなく、デメリットも存在します。詳しく解説しますのでメリットとデメリットを比較した上で、生前贈与するべきか判断しましょう。
共有関係が複雑になる可能性がある
共有持分を生前に贈与すると、共有者が増えてしまい、不動産の管理や意思決定が煩雑になっていきます。不動産の取り扱いそのものが困難になりやすいのは、生前贈与を行うデメリットといえるでしょう。
不動産の評価や登記に費用がかかる
生前贈与で共有持分を移転する場合、登記手続きに登録免許税や司法書士報酬といった費用が発生します。詳しくは後述しますが、不動産の評価額が高い場合や、複数の持分に関わる手続きが必要な場合には、思わぬ出費になりかねません。
相続時に特別受益とみなされる可能性がある
生前に共有持分の贈与を受けた場合、相続の際に「特別受益」として扱われる可能性があります。
特別受益とは相続人の間で公平な相続を実現するための制度であり、共有持分の贈与を受けた相続人は、遺産分割の際にその分を考慮され、他の財産の取得分が減らされたり、金銭で調整を求められたりすることがあります。
贈与された側が不利な立場に立たされることもあるため、事前に相続人間で合意を取っておくことが大切です。
贈与税が発生する可能性がある
生前贈与には、一定額を超えると贈与税が課されます。年間110万円を超える贈与には贈与税の申告が必要になります。不動産を贈与する際には、課税の基準となるのは固定資産税評価額であり、評価額が高いほど税負担も大きくなります。
特例の活用や相続全体を見据えた贈与方法を検討する必要があるため、税理士に相談の上で節税対策を講じることが大切です。
親子共有名義の不動産を生前贈与する方法

親子共有名義の不動産を生前贈与する方法は、主に4つあります。次項より個別に解説しますので、生前贈与を行う際にお役立てください。
親の持分を子供に贈与する
親が所有する持分をそのまま子供に贈与するのが、一般的な生前贈与の方法です。この場合は贈与契約書を作成し、法務局で贈与登記を行う必要があります。贈与額が年間110万円を超える場合には贈与税の申告も必要となるため、事前に税額の試算もしておきましょう。
数年にかけて段階的に贈与する
一度に多額の贈与を行うと高額な贈与税が発生する可能性があるため、数年にわたり分割して贈与するという方法もあります。
毎年110万円の基礎控除の範囲内で贈与を行うことで、贈与税の負担を抑えられます。しかし、不動産持分の一部を毎年贈与するには、その都度登記の手続きが必要になる点に注意が必要です。
相続時精算課税制度を利用して贈与する
親が60歳以上、子供が18歳以上であれば「相続時精算課税制度」を利用して2,500万円までの贈与を非課税で行えます。持分を一括で贈与しても贈与税がかからないというメリットがあります。
しかし、将来の相続時にその贈与分を相続財産に加えて相続税を計算する必要があるため、制度の特徴を理解した上で活用しましょう。
(参考:国税庁「相続時精算課税の選択」)
共有物分割後に贈与する
親子で共有している不動産を、一旦分筆などで分割し、それぞれの持分を明確にしたうえで、親の持分を子供に贈与する方法もあります。共有状態を解消してからの贈与であれば、将来的なトラブルのリスクを減らせます。しかし、分筆や測量には費用と時間がかかる点には注意が必要です。
生前贈与を行う際の注意点

生前贈与を行う際には、特に贈与税について注意しなければいけませんが、他にも留意すべき要素があります。ここでは、生前贈与を行う際の注意点について解説します。
共有持分を「放棄」した場合も贈与税がかかる?
共有持分の放棄とは、自身の持分を手放し、他の共有者に帰属させる行為を指します。例えば、相続で取得した実家の共有持分を、兄弟姉妹の誰かに譲りたい場合などに行われます。放棄の手続きには、他の共有者への意思表示と登記の変更が必要です。
共有持分の放棄は、他の共有者にその権利を無償で譲ることと同義とみなされるケースが多くあります。例えば、親が自分の持分を放棄し、その結果子供の持分が増えるような場合は、「持分の贈与」として課税対象となるかもしれません。持分の放棄を行う前には、税理士など専門家に相談し、税務上のリスクをしっかり確認しましょう。
親子共有名義の不動産を生前贈与する際は贈与税について理解しておく必要がある
親子間で共有している不動産の持分を贈与する場合、贈与税が発生する可能性があります。贈与税には、毎年110万円までの基礎控除がありますが、それを超えた部分には税率がかかり、金額によっては高額になることもあります。
また、贈与を受けた子供が贈与税を納税する義務を負うため、負担の大きさに注意しなければなりません。加えて、不動産の評価額が市場価格ではなく固定資産税評価額などによって決まる点にも留意が必要です。
贈与前には税額シミュレーションを行い、家族全体で納税負担について理解しておきましょう。
共有持分になっている土地を贈与する場合に知っておくべき税金関係の基礎知識
共有持分における贈与税

共有持分の贈与は、不動産の一部所有権を他者に無償で譲渡する行為です。この行為には贈与税が課されますが、その計算方法や適用される特例について正しく理解することが求められます。そこで、共有持分における贈与税について詳しく解説します。
共有持分を贈与した場合の贈与税
共有持分を贈与した場合、受贈者は贈与された持分の時価相当額に対して贈与税を納める必要があります。
例えば、時価1億円の不動産の20%の共有持分を贈与された場合、2,000万円分の贈与を受けたことになります。この金額から基礎控除額110万円を差し引いた1,890万円が課税対象です。
贈与税の計算においては、過去3年間の贈与累計額も考慮されます。したがって、共有持分の贈与を計画する際には、過去の贈与実績も含めて慎重に検討する必要があるでしょう。
配偶者間での共有持分の贈与と配偶者控除
配偶者間での共有持分の贈与には、特別な控除制度が設けられています。これは「配偶者控除」と呼ばれ、一定の条件を満たせば最大2,000万円まで非課税となる特例です。
この制度を利用することで、夫婦間での資産移転を効率的に行えます。配偶者控除の適用条件には、婚姻期間が20年以上であることや、贈与される財産が居住用不動産またはその取得資金であることなどが含まれます。ただし、この特例は一生に一度しか使えないため、適用させるタイミングは慎重に選びましょう。
(参考:国税庁「配偶者控除」)
共有持分の贈与と放棄の税務上の違い

共有持分の贈与と放棄は、一見すると似たような行為に思えますが、税務上では大きな違いがあります。税務上の取り扱いの違いを理解して、より適切な資産管理を行いましょう。
贈与と放棄の違いによる取得費の取り扱い
贈与と放棄では、取得費の扱いが大きく異なります。贈与の場合、受贈者は贈与者の取得費を引き継ぎます。つまり、贈与者が当初購入した価格や、それまでにかかった諸経費が取得費として認められます。
一方、放棄の場合は、放棄された時点の時価が取得費となります。ただし、相続税法上のみなし贈与として扱われる場合は、概算取得費(売却価格の5%)が適用されることがあります。
(参考:国税庁「取得費が分からないとき」)
将来の譲渡所得税への影響
贈与と放棄の違いは、譲渡所得税にも影響します。贈与の場合は、贈与時に贈与税が課され、その後の売却時にも高額な譲渡所得税が課されるため、二重課税の問題が生じる可能性があります。
一方で、放棄の場合は、放棄時の時価が取得費となるため、売却時の譲渡所得は比較的小さくなるのが一般的です。ただし、みなし贈与として扱われる場合は、概算取得費の適用により譲渡所得が大きくなる可能性もあります。
このような違いを踏まえ、長期的な視点で税負担を考慮し、贈与と放棄のどちらを選択するかを慎重に判断しましょう。
共有持分の贈与税対策

共有持分の贈与にはさまざまな税務上の課題がありますが、適切な対策を講じることで税負担を軽減できます。ここからは、代表的な以下2つの方法について解説しますので、贈与税対策を行う際の参考情報としてご活用ください。
暦年贈与を活用する
暦年贈与は、毎年の基礎控除額(110万円)を活用して、複数年にわたって少額ずつ贈与を行う方法です。この方法を用いれば、一度に大きな金額を贈与する場合に比べて、贈与税の負担を大幅に軽減できます。
例えば、1,000万円の共有持分を贈与する場合、10年かけて毎年100万円ずつ贈与すれば、基礎控除の範囲内で贈与税を完全に回避できます。
ただし、この方法は長期間にわたる計画的な実行が必要であり、贈与者の健康状態や将来の資産価値の変動などのリスクも考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を利用する
相続時精算課税制度は、60歳以上の親から20歳以上の子への贈与に適用できる特例制度です。この制度を利用すると、2,500万円までの贈与を非課税とし、それを超える部分に対しても一律20%の税率が適用されます。
共有持分の贈与にこの制度を適用すれば、高額の贈与でも税負担を抑えることが可能です。さらに、将来の相続時に贈与財産と相続財産を合算して相続税を計算するため、相続税の節税効果も期待できます。
ただし、この制度を選択すると、その後は通常の贈与税の基礎控除が使えなくなるなどのデメリットもあります。共有持分の価値や家族の状況などを総合的に考慮し、この制度の利用が適切かどうか判断する必要があるでしょう。
共有持分贈与の具体的な手続き

共有持分の贈与は、以下の3つの手続きで行うことが可能です。それぞれ詳しく解説しますので、共有持分の贈与を行う際の一助となれば幸いです。
手順①:贈与契約書の作成
共有持分の贈与を行う際は、贈与契約書を作成する必要があります。贈与契約書には、贈与者と受贈者の氏名、贈与する財産の詳細、贈与の時期、さらには贈与の目的などを記載します。特に共有持分の場合、対象となる不動産の所在地や登記簿上の表示、贈与する持分の割合を明確に記す必要があります。
契約書作成の際は、法的な有効性を確保するため、できるだけ具体的かつ明確な表現を用いることが重要です。また、贈与者と受贈者の署名捺印も忘れずに行いましょう。
手順②:不動産登記
贈与契約が成立したら、次は不動産登記の変更手続きを行います。この手続きは、贈与された共有持分の権利を第三者に対抗するために不可欠です。登記手続きは、司法書士に依頼して実施するのが一般的です。
登記手続きの際は、共有者全員の同意が必要となる場合がありますので注意しましょう。事前に他の共有者との調整を行い、スムーズに手続きを進めるようにしてください。
手順③:贈与税の申告
最後に贈与税の申告手続きを行います。申告期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。この期間内に、受贈者が贈与税の申告書を提出し、納税を行う必要があります。
申告に必要な書類には、贈与税の申告書、贈与契約書の写し、不動産の評価額を示す資料などがあります。不動産の評価は原則として路線価方式で行いますが、実際の取引価格が評価額を下回る場合は、精通者の意見価格を用いられます。
贈与税の計算は複雑なため、税理士に相談しましょう。特に高額な贈与や、配偶者控除などの特例を適用する場合は、専門家のアドバイスを受けることで、適切な申告と納税が可能となります。
共有持分を手放す際に発生する贈与税以外の税金

共有持分を手放す際には、贈与税以外の税金が発生する可能性もあります。
次項より、共有持分を手放す際に発生する税金について解説します。どのような税金が発生するかを理解しておき、正しく納税を行いましょう。
持分売却時の「譲渡所得税」
共有持分を売却して手放す場合に注意すべきなのが、譲渡所得税です。売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡益に対して課税されます。税率は所有期間によって以下のように異なります。
| 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計 | |
| 短期譲渡所得(5年以内) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 (5年超) | 15% | 5% | 0.32% | 20.32% |
(参考:国税庁「土地や建物を売ったとき」)
ただし、居住用財産の譲渡特例など、状況に応じて適用できる軽減措置もあるため、税負担を軽減できる可能性があります。
著しく低い価額での譲渡時の「みなし譲渡所得税」
共有持分を時価よりも著しく低い価額で譲渡する場合、その差額分が贈与とみなされると同時に、譲渡所得税の課税対象となります。
これは「みなし譲渡所得税」と呼ばれ、実際の売却価格ではなく時価で譲渡したものとして計算されます。「みなし譲渡所得税」は、贈与税と重複して課税される可能性があるため、注意が必要です。
所有権移転登記の際の「登録免許税」
共有持分を手放す際、その移転を登記する必要がありますが、その際に発生するのが登録免許税です。通常、売主と買主で折半するケースが多いですが、契約内容によっては全額を負担するケースも存在します。
税率は原則として以下のように定められています。
| 内容 | 税率 |
| 所有権の保存 | 0.4% |
| 売買または競売による所有権の移転 | 2% |
| 相続または法人の合併による所有権の移転 | 0.4% |
| その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) | 2% |
(参考:国税庁「登録免許税の税額表」)
親子共有名義の不動産の生前贈与に関するよくある質問

親子共有名義の不動産の生前贈与に関するよくある質問について回答します。親子共有名義の不動産の生前贈与についてわからない点があるという方は、ぜひチェックしてみてください。
不動産を共有名義にしたまま贈与することはできる?
共有名義のままでも贈与することは可能です。ただし、贈与するのはあくまで自分が保有している持分に限られます。
親が認知症になったら生前贈与はできなくなる?
基本的に、贈与契約は当事者双方の「意思表示」によって成立するため、親が認知症を発症して意思能力がないと判断されると、生前贈与はできません。
成年後見人が選任されていても、贈与は本人の財産を減らす行為にあたるため、家庭裁判所の許可なしには行えません。
生前贈与の後に不動産登記をしないとどうなる?
生前贈与後に登記をしないままにしておくと、法的には第三者に対してその贈与を主張できません。相続や売却の際にも不利益を被ることがあるため、贈与後は速やかに登記手続きを行うことが大切です。
生前贈与と相続ではどちらの方が節税効果が高い?
ケースバイケースですが、基本的には相続の方が節税効果を見込めます。理由として、相続税には基礎控除があり、一定の額までは非課税となるからです。しかし、相続時精算課税制度を活用することで、結果的に生前贈与の方が有利になるケースもあります。
親子共有名義の不動産を生前贈与する際は贈与税の対策が欠かせない

生前贈与は相続税対策として有効ですが、税金の扱いを誤ると大きな負担になりかねません。特に贈与税については、ルールや計算方法を正しく理解していないと、思わぬ負担が発生することもあります。
贈与と放棄は似ているようで扱いが異なるため、それぞれの違いを事前にしっかり把握しておくことが大切です。
また、「暦年贈与」や「相続時精算課税制度」といった制度をうまく活用すれば、税金の負担を軽くできるケースもあります。
共有持分の生前贈与を考えるときは、税理士や弁護士など専門家に相談しましょう。プロのサポートがあれば、生前贈与の手続きや納税などをスムーズに進めることができます。