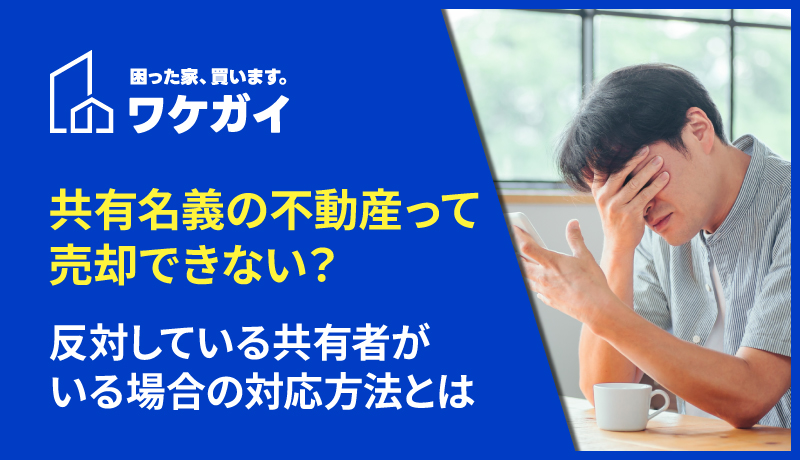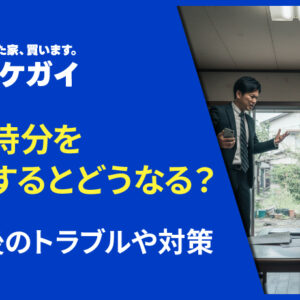こんにちは。ワケガイ編集部です。
相続で取得した不動産や親族と共同で購入した土地では、共有者の一人が売却を希望しても思うように進まないケースがあります。共有名義の場合、売却のためには共有者全員の同意が必要であり、一人でも反対すれば取引が成立しないという問題が発生します。
その際に理解しておくべきなのが「共有名義不動産の売却ルール」です。共有名義不動産とは、複数人が持分割合を持って所有する形態で、法律上の制約や税金の負担が伴います。
そこで本記事では、共有名義不動産がなぜ売却できないのか、売却すべきケースや対処法、専門業者を利用する方法まで詳しく解説します。
目次
共有名義不動産はなぜ売却できないのか?
不動産を売却しようと思っても、共有名義になっているとスムーズに進まないものです。
相続や夫婦・親子での購入などで共有名義が発生することは珍しくありませんが、法律上の仕組みを理解していないと「なぜ売れないのか」が分からず、トラブルの原因になりがちです。
ここからは、共有名義の基本的な考え方や、売却の際に必要となる手続きの違いについて整理していきます。
共有持分とは
共有持分とは、ひとつの不動産を複数人で所有する際に、それぞれが持っている権利の割合を指します。
兄弟が相続で土地を受け継いだ場合に「2分の1ずつ」と記載されていれば、その割合が持分です。この持分は登記簿にも明記され、法律的にも強い効力を持っています。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)
一方で、持分は土地や建物の特定の区画を意味するものではありません。兄が庭を、弟が建物を、といった形で物理的に分かれているわけではなく、不動産全体を共同で所有している状態です。
このため、利用や処分には共有者同士での調整が不可欠となり、売却にあたって大きな制約となるのです。
関連記事:共有持分の不動産を売却する方法とは?売却費用やよくあるトラブルを紹介!
共有持分を売却するには全員の同意が必要
共有名義不動産をまるごと売却したい場合には、共有者全員の同意がなければ契約は成立しません。これは民法上の取り扱いで、不動産という大きな財産を処分するには、所有者全員の意思確認が求められるためです。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)
現実には、一人が売却を希望しても「まだ住みたい」「思い出があるから手放したくない」といった理由で反対する共有者がいれば、取引が止まってしまいます。
特に相続で複数人が共有したケースでは、遠方に住んでいて連絡が取れない、感情的な対立があるなど、同意を得るのが難しいことも多いでしょう。
こうした背景から「共有名義の不動産は簡単に売れない」といわれているのです。
自分の持分のみなら同意なしで売却可能
ただし、自分が持っている持分だけを第三者に売却することは可能です。この場合は他の共有者の同意を得る必要はありません。法律上、自分の所有権を処分する自由は認められているためです。
もっとも、買い手が見つかるかどうかは別問題です。持分を購入しても、他の共有者と共同で利用せざるを得ず、自由に使えないため、一般市場では需要が乏しく、価格も低くなる傾向があります。
表向きは「売れる」とはいえ、条件が限られる点は理解しておきましょう。
共有持分はどんなときに売却すべき?
共有持分を手放すべきかどうかは、人によって状況が異なります。ただし一定のパターンでは、持ち続けるよりも売却したほうが合理的な選択となります。
ここからは典型的なケースを取り上げ「なぜ売却を考えるべきなのか」を解説します。
- 共有者との関係悪化で利用が難しくなったとき
- 自分では利用予定がない不動産を相続したとき
- 管理や維持の負担が大きくなったとき
- 現金化して資金を必要とするとき
それぞれ個別にみていきましょう。
共有者との関係悪化で利用が難しくなったとき
不動産の共有は、理論上は公平な仕組みに見えますが、実際には人間関係が円滑でなければ成り立ちません。
例えば兄弟が相続した家を共有している場合、片方は「すぐに売って現金化したい」と望んでも、もう一方が「思い出があるから残したい」と主張すれば平行線のままです。
意見の不一致が長期化すれば、固定資産税や修繕費はかかり続け、何も決められない状態が続いてしまいます。
このような状態では、不動産が「資産」としての役割を果たさず、むしろ人間関係の亀裂を深める要因となります。
共有者との信頼関係が崩れ、話し合いの糸口が見えないときには、持分を売却することで感情的な対立が解消されるだけでなく、先の見えない不安からも解放される点で、売却は有効な選択肢となります。
自分では利用予定がない不動産を相続したとき
相続によって取得した不動産は、必ずしも生活に役立つわけではありません。遠方の土地や空き家を引き継いでも、使う予定がなければ「管理コストだけを背負う資産」になってしまいます。
特に空き家の場合、放置すれば老朽化が進み、固定資産税の軽減措置を受けられなくなるリスクもあります。
利用の見込みが立たず、維持費が毎年発生するような不動産を抱え続けるのは、将来的に負担となりやすいもの。こうした場合には、共有者と相談して一括で売却するか、あるいは自分の持分のみを売却して整理するほうが現実的です。
資産を現金化すれば、教育費や生活費など別の用途に充てることができ、家計面でもプラスに働くでしょう。
関連記事:実家を共有名義で相続するとトラブルになる?共有不動産の持つリスクについて論考
管理や維持の負担が大きくなったとき
不動産は所有しているだけで維持管理の責任が生じます。特に空き家や利用していない土地では、草刈りや清掃、屋根や外壁の修繕といった作業が避けられません。
年齢を重ねると体力的に対応できなくなり、遠方に住んでいれば物理的にも管理は難しくなります。
結果として放置すれば景観を損ねたり、近隣から苦情が寄せられる事態につながることもあります。行政も近年は空き家対策を強化しており、「特定空家」に指定されれば固定資産税の軽減措置が外れる可能性もあります。
(参考:e-Gov 法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」)
つまり、利用していないのに税負担は増え、資産価値も下がる悪循環に陥るのです。こうした状況を避けるために、管理が難しいと感じた段階で共有持分を売却するのは合理的な選択肢といえます。
現金化して資金を必要とするとき
教育費や老後の生活費、あるいは借金の返済など、まとまった資金が必要になる場面は誰にでも訪れます。共有持分を現金化することは、そのような場面で資金を確保するひとつの方法になります。
特に相続で取得した不動産を利用する予定がない場合、資産を眠らせておくよりも売却して手元資金に変えるほうが有効なケースが多いでしょう。
不動産は現金化に時間がかかるイメージがありますが、共有持分の買取を専門とする業者を利用すれば比較的短期間で換金できる可能性があります。
もちろん通常の市場で売却するより価格は下がる傾向がありますが、それ以上に「すぐに資金を手にできる」という利点は大きいのです。
共有者の合意が得られず不動産活用が進まないとき
不動産を賃貸に出したり、リフォームして活用したりするには、共有者全員の同意が必要です。しかし実際には、活用に賛成する人と反対する人が出て、計画が進まないことも少なくありません。
相続で親族が複数人共有者になった場合、「遠方に住んでいて意思疎通が難しい」「そもそも話し合い自体に応じてもらえない」といった問題もあります。
こうした合意形成の壁に直面したときに検討できるのが、自分の持分だけを売却する方法です。持分だけを買い取る業者に依頼すれば、他の共有者の同意がなくても手続きを進められます。
もちろん、物件全体を売却する場合と比べると価格は低くなる傾向がありますが、動かない状況を変える有効な一手になります。
共有持分のまま不動産を所有し続けるのはやめた方がいい?
一見すると「持っているだけで安心」と思われがちな共有持分ですが、長期間そのままにしておくことで思わぬリスクを抱えることになります。
具体的には、共有持分の所有には以下のようなリスクが存在します。
- リスク①:不動産価値が下がっても柔軟に対応できない
- リスク②:共有者のライフイベントで権利関係が複雑化する
- リスク③:固定資産税や維持費を払い続けるだけになる
- リスク④:賃貸や活用の機会を逃す可能性がある
- リスク⑤:将来の売却時にトラブルが拡大しやすい
次項より、個別にみていきましょう。
リスク①:不動産価値が下がっても柔軟に対応できない
不動産市場は景気や地域の環境によって大きく変動します。価格が下がる前に売却したいと考えても、共有者全員の同意がなければ動けないのが共有名義の大きなデメリットです。
例えば再開発計画が持ち上がり、周囲の土地は需要が高まっているのに、自分だけ売却の決断ができないという状況が生じます。
結果として、好機を逃して資産価値が下がってから売らざるを得なくなる可能性があります。
さらに、リフォームや建て替えといった資産価値を保つための手段も、共有者の意思が揃わなければ実行できないため修繕を先送りにして老朽化が進めば、不動産は売却どころか維持することさえ難しくなります。
つまり、意思決定の遅れがそのまま資産価値の下落につながるのです。
リスク②:共有者のライフイベントで権利関係が複雑化する
共有者が変わらない限り問題はないと思われがちですが、現実にはライフイベントによって所有者が入れ替わることが少なくありません。
相続が典型例で、兄弟二人で持っていた土地が、次の代でその子どもたちに分かれると、所有者は一気に数人から十数人に増えることがあります。人数が増えれば増えるほど意見の調整は困難になり、売却や活用の合意は事実上ほとんど不可能になるでしょう。
離婚によって共有者が変わる場合も、感情的な対立が絡むため協議が難航しがちです。新しい共有者が不動産に関心を持たなければ管理は放置され、逆に権利を強く主張すれば他の共有者との摩擦が絶えなくなります。
リスク③:固定資産税や維持費を払い続けるだけになる
不動産を所有している限り、たとえ使っていなくても固定資産税は毎年課税されます。さらに空き家や土地を放置すれば、草刈りや建物の修繕、火災保険といった維持費も必要です。利用価値がないのに出費だけが積み重なれば、資産ではなく負担へと変わってしまいます。
(参考:総務省「固定資産税」)
特に空き家の場合、放置することで老朽化が進み、行政から「特定空家」に指定される恐れもあります。
そうなると固定資産税の軽減措置が外れ、税額が数倍に跳ね上がる可能性もあるのです。実際に「相続で引き継いだ家をそのままにしていたら、思いがけない出費に悩まされることになった」という例は珍しくありません。
関連記事:共有名義の「固定資産税」は誰が払うべき? 滞納した場合や支払いたくない場合はどうなる?
リスク④:賃貸や活用の機会を逃す可能性がある
共有名義の不動産を活用しようとすると、共有者全員の同意が必要です。
例えば賃貸に出して家賃収入を得たいと考えても、一人でも反対すれば計画は実現しません。リフォームをして資産価値を高めるにしても、費用負担をめぐって対立すれば前に進まないでしょう。
その結果、せっかくの活用機会を逃し、ただ放置されるだけという状況に陥りがちです。不動産は人が住まなければ劣化が早まるため、活用できない期間が長引くほど資産価値は低下します。
つまり、共有者の合意が得られないという理由だけで収益化のチャンスを失い、資産価値を削ってしまうリスクを抱えているのです。
リスク⑤:将来の売却時にトラブルが拡大しやすい
共有名義をそのまま放置すると、時間の経過とともに所有者の数が増えていく傾向があります。
相続が重なるたびに子や孫へと権利が分かれ、数十人単位の共有者が存在するケースもあり、所有者が増えれば増えるほど、売却に必要な同意を集めるのは難しくなります。
さらに、誰か一人でも連絡がつかないと取引が成立しないため、実務上は売却がほぼ不可能になることもあります。仮に連絡が取れても、利害関係が複雑化して交渉が難航する可能性は高いでしょう。
こうした事態を避けるには、問題が大きくなる前に早めの判断を下すことが大切です。長期的に見れば「今は大きな問題がない」と思える段階で売却を検討するほうが賢明といえます。
共有者に反対されて売却できない場合の対処法
共有名義の不動産を売却するには、基本的に共有者全員の合意が必要です。そのため、一人でも強く反対する人がいれば取引は進みません。
しかし、合意が得られないからといって手をこまねいていては、時間とともに不動産の価値は下がり、税や維持費の負担だけが続きます。
ここからは、その際に検討できる具体的な手段を紹介します。
- 共有者との話し合いで合意形成を目指す
- 共有者に持分を買い取ってもらう交渉をする
- 自分の持分だけを第三者へ売却する
- 裁判所に共有物分割請求を申し立てる
- 専門家に相談して解決策を検討する
それぞれ個別にみていきましょう。
共有者との話し合いで合意形成を目指す
最も基本となるのは、まず共有者同士でしっかり話し合うことです。売却の理由を感情的に伝えるのではなく、維持費や税負担、将来のリスクなど、数字や具体的な根拠を示すことが効果的。
例えば「このまま10年放置すると固定資産税だけで○百万円かかる」といった形で、損得の面から理解を得る工夫が必要です。感情面の対立は解決に時間を要しますが、合理的なデータを提示することで折り合いをつけられる可能性は高まります。
共有者に持分を買い取ってもらう交渉をする
どうしても売却に反対する共有者がいる場合、その人に自分の持分を買い取ってもらう方法があります。「売却したい側」「残したい側」で利害が一致しやすいため、交渉がまとまりやすいでしょう。
買い取る側も、他の共有者が減れば自由度が増すため、将来的な利用に有利になります。価格交渉では市場価格にこだわらず、双方が納得できる水準で妥協点を探すことがポイントです。
自分の持分だけを第三者へ売却する
合意形成が難しい場合、自分の持分だけを第三者に売却する方法もあります。民法上、自分の権利は自由に処分できるため、共有者の同意は不要です。ただし一般市場では需要が乏しく、安値での取引になりやすいのが現実です。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)
そこで、共有持分の買取を専門にしている業者を利用することで、比較的スムーズに現金化できる可能性があります。膠着状態を解消する有効な選択肢といえるでしょう。
裁判所に共有物分割請求を申し立てる
話し合いや交渉で合意に至らない場合、最終手段となるのが裁判所に共有物分割請求を申し立てることも検討しましょう。裁判所の判断に基づき、不動産を現物分割するか、競売にかけて代金を分け合うかが決まります。
時間と費用はかかりますが、強制的に共有関係を解消できる手続きです。合意が不可能な状態を打開する最後の手段として覚えておく価値があります。
専門家に相談して解決策を検討する
共有不動産の売却は、法律・税金・人間関係が絡み合う複雑な問題です。弁護士に相談すれば裁判所手続きの見通しを立てられますし、司法書士なら登記の整理をサポートしてくれます。
不動産会社や専門業者に依頼することで、市場での需要や買取価格の目安も把握できます。一人で抱え込まず、第三者の視点を入れることが、解決への近道となるでしょう。
それでも共有持分を売却したいなら専門業者への売却がおすすめ!
共有持分を抱えていると、共有者との話し合いが進まず、不動産を動かせないまま時間だけが過ぎることも多々あります。そんなときに現実的な選択肢となるのが、共有持分を専門的に取り扱う買取業者への売却です。
買取業者に共有持分の売却を相談するメリットには、以下のとおり。
- 専門業者のメリット①:共有者の同意が不要でスピーディーに売却できる
- 専門業者のメリット②:不動産会社や一般市場では売れにくい持分も対応可能
- 専門業者のメリット③:法的な知識やトラブル解決のノウハウがある
- 専門業者のメリット④:現金化までのスケジュールが明確で安心できる
- 専門業者のメリット⑤:秘密厳守で共有者に知られず売却できるケースもある
次項より、個別にみていきましょう。
専門業者のメリット①:共有者の同意が不要でスピーディーに売却できる
通常の不動産売却は共有者全員の同意が不可欠ですが、自分の持分だけを専門業者に売却する場合、他の共有者の同意を得る必要はありません。つまり、家族や親族の反対で何年も膠着していた問題を、自分の判断だけで動かせるのです。
また、専門業者はこの分野に特化しているため査定や契約の流れも早く、数週間から数か月で現金化できるケースもあります。
資産価値が下がる前に手放したい、固定資産税の負担を来年度からは避けたいといったニーズに応えられる点で、スピード感は大きな魅力です。
専門業者のメリット②:不動産会社や一般市場では売れにくい持分も対応可能
共有持分は、一般の不動産市場では買い手が付きにくいのが実情です。理由は単純で、持分だけを購入しても自由に利用できず、他の共有者と利害が絡むためです。
多くの不動産会社は仲介を断るか、仮に引き受けても長期間売れ残るケースも当然あります。
その点、専門業者は共有持分の取り扱いを日常的に行っており、活用や処分の方法を熟知しています。購入後の出口戦略を持っているため、一般市場では敬遠される案件でも取引が成立するのです。
市場に出しても動かない不動産を抱え続けるより、確実に引き受けてもらえる安心感は大きな価値があります。
専門業者のメリット③:法的な知識やトラブル解決のノウハウがある
共有持分の売却は、法律や契約上の制約が多く、一般的な不動産取引に比べて複雑です。例えば「売却後に他の共有者から異議を唱えられたらどうなるのか」「登記の手続きは誰が担うのか」といった疑問は、素人が判断するのは難しいものです。
専門業者はこうした状況に数多く対応してきた経験があり、法律的なリスクを最小限に抑える手続きを整えています。
必要に応じて弁護士や司法書士と連携してくれるため、契約から登記、引き渡しまでを一貫して任せられる点は大きな安心材料といえます。トラブルの芽を事前に摘み取りながら進められるのは、専門性の高い業者ならではの強みです。
専門業者のメリット④:現金化までのスケジュールが明確で安心できる
通常の不動産売却では、買い手探しに数か月、場合によっては1年以上かかることもあります。共有持分はさらに買い手が限られるため、不確実性が大きいのが難点です。
その点、専門業者への売却では、査定から契約、代金受け取りまでのスケジュールがあらかじめ明示されることが多く、先の見通しを立てやすくなります。
教育費や老後資金など、資金を必要とする時期が決まっている場合には、この「いつ現金化できるかが分かる」ことが何よりの安心につながります。市場で買い手を待つよりも、確実に資金を得られるという点が利用者から評価されています。
専門業者のメリット⑤:秘密厳守で共有者に知られず売却できるケースもある
共有名義の不動産は、売却を望んでいること自体を他の共有者に知られたくないという人も少なくありません。「家族関係が悪化するのでは」と懸念したり、「内密に処分したい」という事情を抱えている場合もあるでしょう。
専門業者はこうした利用者の意向を理解しており、秘密厳守を徹底する体制を取っているところが多くあります。契約の進行や連絡方法も配慮され、他の共有者に伝わらないよう慎重に扱ってくれるのです。
もちろんすべてのケースで完全に知られずに済むとは限りませんが、少なくとも通常の市場で広く売り出すよりははるかにプライバシーを守りやすいといえます。家庭や親族との関係を壊したくないと考える人にとって、大きなメリットとなるでしょう。
共有持分をなるべく高くで売却するためのコツ
共有持分は一般的な不動産よりも買い手が限られるため、どうしても価格が下がりやすい傾向があります。しかし事前の準備や工夫次第で、売却額をできるだけ高めることは可能です。具体的には、以下の対策を講じましょう。
- 複数の専門業者に査定を依頼して相場を把握する
- 不動産の権利関係や登記を整理しておく
- 測量・境界確定など不安要素を解消しておく
- 共有者と協力して一括売却できる可能性を探る
- 売却時期や税制優遇を踏まえてタイミングを見極める
それぞれ個別に解説します。
複数の専門業者に査定を依頼して相場を把握する
共有持分を売却する際に最初にすべきことは、複数の専門業者に査定を依頼することです。
一般の不動産売却でも複数社に見積もりを取るのは基本ですが、共有持分の場合はさらに重要になります。理由は業者によって買取条件に大きな差が出やすいからです。
ある業者は再販や活用のノウハウを持っているため比較的高値を提示する一方、別の業者はリスクを避けて低めの金額しか出さないこともあります。ひとつの査定額だけを信じて売却を決めてしまうと、本来より数十万円から数百万円安く手放してしまう危険もあるのです。
査定は無料で受け付けている業者が多いため、複数の意見を集めることで相場の感覚がつかめます。その上で条件や対応の丁寧さも比較すれば、安心して取引できる業者を選びやすくなるでしょう。
不動産の権利関係や登記を整理しておく
もうひとつの大きなポイントは、売却に先立って権利関係や登記を整理しておくことです。
相続で共有持分が発生した場合、登記が未了のままになっているケースも少なくありません。登記が正しく整っていなければ、価格交渉で不利になることが多いのです。
例えば相続登記を済ませていないと「本当に売却できる権利があるのか」と疑念を持たれ、買取額を下げられる要因になります。また、抵当権や差押えの記録が残っている場合も、早めに解消しておくことでスムーズに取引が進みます。
業者から見て「余計なリスクがない状態」に整えておくことが、査定額を引き上げる上で欠かせない準備といえるでしょう。司法書士など専門家に依頼すれば、複雑な手続きも確実に処理できます。
測量・境界確定など不安要素を解消しておく
不動産の売却において、境界が不明確な土地や図面と現況が一致しない物件は、買い手にとって大きなリスクと受け止められます。
共有持分の取引でも同じで、測量や境界確定が済んでいないと「後で隣地とのトラブルに巻き込まれるのではないか」と懸念され、査定額が低くなることがあります。特に、古い相続物件では、登記簿に記載されている地積と実際の土地面積が異なっていることも珍しくありません。
売却前に測量を行い、境界標を設置しておけば、買い手は安心して取引に臨めます。測量費用は数十万円かかる場合がありますが、将来的に数百万円単位で売却額が変わることを考えれば、先行投資として十分に意味があります。
共有者が複数いる場合は費用分担をどうするかが課題となりますが、売却価格の向上につながると説明すれば合意を得やすいでしょう。
共有者と協力して一括売却できる可能性を探る
自分の持分だけを売却するよりも、共有者全員で不動産を一括して売却した方が高値で取引できるのは事実です。理由は単純で、買い手にとって「不動産全体を自由に使える」状態だからです。
共有者同士が協力できるなら、仲介会社を通じて通常の市場に出すことができ、持分売却よりも有利な条件が期待できます。
ただし一括売却には共有者全員の同意が必要です。家族内の意見が割れていたり、遠方の共有者と連絡が取れない場合には現実的に進まないこともあります。
だからこそ、まずは一度真剣に全員で協議し、一括売却のメリットを丁寧に共有することが大切なのです。もし合意が難しいと判断した場合でも、その過程を経ることで「最善の選択肢は持分売却」という納得感も得やすいでしょう。
売却時期や税制優遇を踏まえてタイミングを見極める
不動産の価格は景気動向や需要の変化に影響を受けます。例えば再開発の計画がある地域では、完成前後で価格が大きく動くこともあります。
共有持分を売却する際にも、こうした外部要因を踏まえて時期を選ぶことで、査定額に差が出るのです。
さらに見落とされがちなのが税制面です。相続から3年以内であれば取得費加算の特例を利用できる場合があり、譲渡所得税を抑えられる可能性があります。
(参考:国税庁「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」)
また、居住用財産の特別控除や買い替え特例など、条件に合えば負担を大きく減らせます。単に「早く手放したい」と焦るのではなく、税制優遇を活用できるかどうかを事前に確認しておくことが賢明です。時期を見極めることは、売却益だけでなく手取り額を左右する要素でもあります。
「ワケガイ」なら共有持分も短期で買い取りいたします!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や再建築不可の土地、空き家、ゴミ屋敷、事故物件といった“訳あり不動産”の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています通常の不動産市場では売却が難しいケースでも、ワケガイなら最短1日で現金化が可能です。
全国対応の豊富な実績があり、最大3億円までの即時買取にも対応しており、面倒な手続きや権利関係の整理についても、提携する専門士業と連携してスムーズに進める体制を整えています。
他社で断られた物件も数多く取り扱ってきましたので、まずはお気軽に無料査定をご活用ください。
FAQ:共有名義に関するよくある質問
Q1.共有名義を外す方法はありますか?
共有名義を解消する方法はいくつかあります。最も多いのは、他の共有者に自分の持分を買い取ってもらう形です。相手に資金的余裕があればスムーズに進みますが、そうでない場合は話し合いが難航することもあります。
もうひとつは自分の持分を第三者に売却する方法で、専門業者を利用すれば早期に現金化することも可能です。裁判所に共有物分割請求を申し立てる方法もありますが、競売になると価格が下がることが多いため、慎重に検討する必要があります。
Q2.共有持分を売却するにはどうしたらいいですか?
共有持分の売却は、自分の権利部分を単独で処分できるため、他の共有者の同意は不要です。ただし市場での需要は少なく、一般の買い手が見つかりにくいのが実情です。そのため、共有持分の買取に特化した業者に依頼するケースが増えています。
業者ならば持分だけでも引き取る体制が整っており、契約から現金化までの流れも明確です。価格は通常の不動産より低くなりがちですが、身動きが取れない状況を解消する上では有効です。
Q3.共有名義の家の売却はどうすればいいですか?
家を丸ごと売却する場合には、共有者全員の合意が不可欠です。一人でも反対すれば契約は成立しないため、まずは共有者との協議が出発点となります。全員が同意できれば通常の仲介会社を通して売却が可能で、市場価格での取引が期待できます。
もし合意が難しい場合には、自分の持分だけを売却するか、裁判所に共有物分割請求を行う方法があります。いずれにしても、「家全体の売却」か「持分のみの売却」かで手続きは大きく異なる点に注意が必要です。
Q4.共有名義の土地を勝手に売却できますか?
土地全体を勝手に売却することはできません。売却には共有者全員の同意が必要であり、独断で契約しても無効となります。ただし、自分の持分だけを第三者に売却することは法律上認められています。
この場合でも、買い手は他の共有者と権利を分け合う形になるため、一般の市場では敬遠される傾向があります。現実的には、共有持分の扱いに慣れた専門業者に依頼するのが現実的な選択肢となるのです。
まとめ
共有名義不動産は、単独では自由に売却できないという制約があるため、放置すると資産価値が下がったり費用負担だけが残るリスクがあります。
重要なのは「どのタイミングで売却すべきか」を見極めることと、「共有者との合意形成や代替手段」を冷静に選ぶことです。
共有者との関係が難しい場合でも、持分のみを売却したり、裁判所の共有物分割請求を利用したりする方法は存在します。管理の負担や将来のトラブルを避けるためにも、専門家や専門業者を活用しながら、自分に合った解決策を選び、早めに行動に移しましょう。