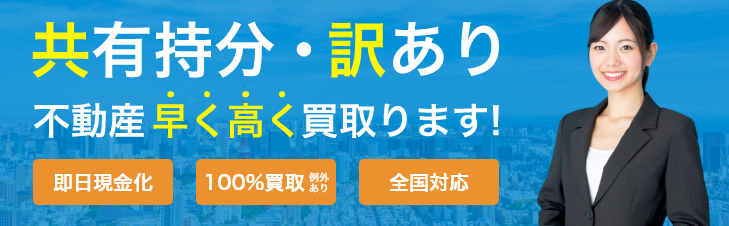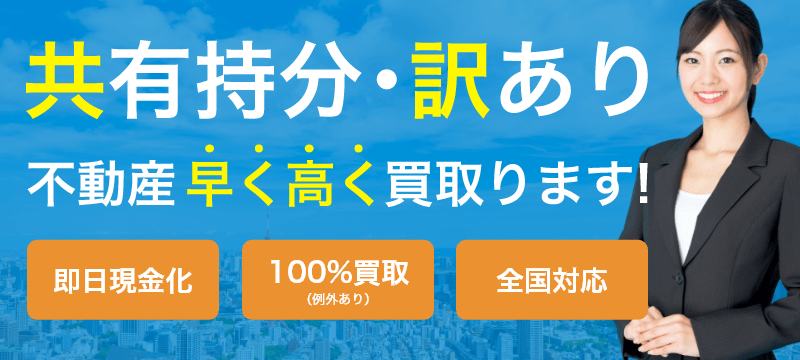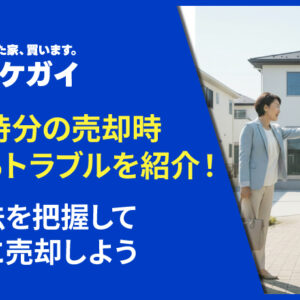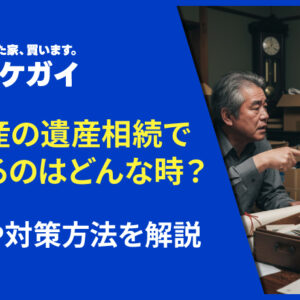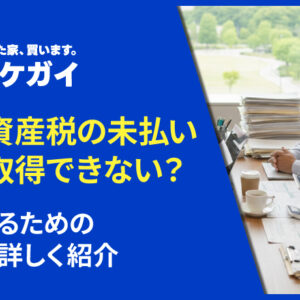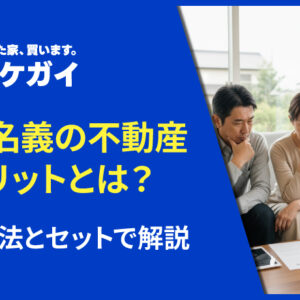相続した土地が自宅や事業用として使われていた場合、「小規模宅地等の特例」によって相続税を大きく減額できるケースがあります。特に、都市部など地価の高い地域で適用できれば、制度の活用が大きな節税効果を得ることが可能です。
ただし、共有持分がある場合は、特例の適用条件や計算方法が複雑になります。たとえば、相続人が複数いる場合には、持分ごとに要件を個別に判断する必要があり、形式的に満たしていても実態として適用できないケースも少なくありません。
加えて、一般的には「3,000万円特別控除を活用しよう!」といわれることも多いものの、そもそもの制度の適用条件自体が厳しいことから、実際には活用できるのは稀な制度でもあります。
本記事では、共有持分がある土地に対して小規模宅地等の特例を適用するための条件や注意点、適用可否の判断基準について、実務的な観点から詳しく解説します。
目次
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例(正式名称:「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」)は、相続税の計算において、被相続人の自宅や事業用の土地の評価額を大幅に減額できる制度です。
この特例は、相続人の生活基盤や事業継続を支援する目的で設けられており、適切に活用することで相続税の負担を大きく軽減できる可能性があります。
特に、地価の高い都市部では、この特例の恩恵が非常に大きくなることがあります。たとえば、被相続人が住んでいた自宅の敷地など、特定の要件を満たす土地については、その評価額を最大80%も減額することが可能です。
【相当厳しい!?】小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例は、相続税の負担を大きく軽減できる制度として広く知られています。しかし実際には、「居住用だから適用されるだろう」といった認識では通用しない、極めて厳格な要件が課されています。
たとえば、被相続人が亡くなる時点での利用状況、相続人がその土地をどう取得したか、取得後も継続して住み続けているかといった点まで問われます。形式的に「同居していた」「相続した」だけでは足りず、細かな条件を一つずつクリアする必要があるのが現実です。
特に、共有持分がある場合は要件の判断がさらに複雑になります。以下では、その点に焦点を絞って解説します。
共有持分がある場合の適用要件
共有名義の土地にも、小規模宅地等の特例は適用可能です。ただし、次のような点に注意が必要です。
まず、特例が適用されるのは、あくまで被相続人の「持分部分」に限られるということ。たとえば、被相続人が300㎡の土地を50%の共有で所有していた場合、特例の対象となるのは150㎡分までとなります。
(参考:国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」)
また、相続人がその持分を取得したとしても、自動的に適用されるわけではありません。取得した相続人が以下の要件を満たす必要があります。
- 被相続人と同居していた(特定居住用の場合)
- 申告期限までその土地に居住し続けている
- 土地の利用状況が、被相続人の生前から要件に合致していた
さらに、相続で共有状態が発生した場合には、相続人ごとに適用要件を満たしているかどうかを個別に判断しなければなりません。同じ土地を複数人で相続したとしても、特例が使える人と使えない人が混在することがあります。
このように、共有持分に対して小規模宅地等の特例を活用するためには、持分割合・利用実態・相続人の状況を丁寧に精査することが不可欠なのです。
共有の取得経緯ごとの「小規模宅地等の特例」の適用方法
共有名義の土地に小規模宅地等の特例を適用する場合、重要なのはその「共有がいつ発生したか」という点です。
被相続人が生前から他者と土地を共有していたケースと、相続によって土地が共有状態になったケースでは、適用される条件や評価の考え方が大きく異なります。
ここでは、それぞれのパターンにおける適用方法や注意点を解説します。
ケース①:生前から共有である場合の適用方法
被相続人が生前から土地を他の人と共有していると、小規模宅地等の特例は被相続人の共有持分に対してのみ適用されます。
たとえば、被相続人と配偶者が200㎡の土地を50%ずつ共有していた場合、被相続人の持分である100㎡分に対してのみ特例が適用可能です。この場合、配偶者が相続人となり、被相続人の持分100㎡を相続すれば、その全てに特例を適用できます。
ただし、共有者との関係性や土地の利用状況によっては、適用できる面積が変わる可能性があります。
また、共有者が被相続人の親族でない場合など、特例の適用条件に影響を与える要素もあるため、個々の状況に応じた慎重な判断が求められます。
ケース②:相続により共有となった場合の適用方法
相続によって土地が共有となったケースでは、各相続人が取得した持分に応じて小規模宅地等の特例を適用します。ただし、各相続人がそれぞれ特例の適用要件を満たしているかどうかを個別に判断する必要があります。
たとえば、被相続人と同居していた配偶者は要件を満たしますが、別居していた子供は要件を満たさない場合があります。このようなケースでは、配偶者の取得した持分には特例が適用されますが、子供の取得した持分には適用されません。
また、相続人全員で1つの物件を共有する場合と、相続人ごとに物件を分けて相続する場合では、特例の適用結果が異なる可能性があります。
そのため、相続方法を検討する際には、小規模宅地等の特例の適用も考慮に入れ、最も税負担が軽減される方法を選択することが重要です。
関連記事:共同相続人とは?相続人との違いや共有不動産のリスクを詳しく紹介
関連記事:相続人不存在の共有持分はどうなる?帰属のルールや必要手続きを丁寧に解説
共有持分に「小規模宅地等の特例」を適用する際の面積の算出方法
小規模宅地等の特例を適用する際、共有持分がある土地では「評価減の対象となる面積」を正しく算出する必要があります。
これは、被相続人や相続人が所有していた共有持分に応じて、評価対象となる面積を按分する仕組みになっています。
具体例として、数値を仮置きした場合の算出方法は以下のとおりです。
<前提条件>
- 土地の全体面積:400㎡
- 被相続人の持分割合:50%
- 評価減の対象面積:400㎡ × 50% = 200㎡
この200㎡に対して、相続人が特定居住用宅地等の要件を満たしていれば、最大で80%の評価減が適用されることになります。
ただし、次のようなケースではさらに複雑な按分が必要です。
- 土地の一部が賃貸に使われている
- 共有者のうち相続人でない人物が含まれている
- 利用状況に差がある(たとえば一部のみ居住、他は空き地)
このようなケースでは、共有持分の割合だけでなく、各人の利用状況や契約内容も加味して評価対象面積を再計算しなければなりません。
正確な面積の算出と適用判断には、相続税に強い税理士の関与が不可欠です。不動産評価や相続税申告の経験が豊富な税理士に早めに相談することで、誤った適用による追徴課税などのリスクを防ぐことができます。
共有持分に「小規模宅地等の特例」適用した事例の紹介
共有持分がある土地に対して「小規模宅地等の特例」を適用する際は、共有の形態や相続の状況によって適用方法が異なります。
以下に、具体的なケースごとに特例の適用可否や注意点を解説します。
例①:被相続人と配偶者の共有名義の場合
たとえば、被相続人と配偶者が300㎡の土地を50%ずつ共有していたとします。このとき、相続の対象となるのは被相続人の持分である150㎡です。
配偶者がこの150㎡を相続する場合、小規模宅地等の特例の適用条件を満たしていれば、原則としてその全てに80%の評価減が適用されます。配偶者には同居や継続居住といった厳しい条件が課されないため、比較的スムーズに特例を活用できるケースです。
ただし、他に相続人がいる場合や、遺産分割の方法によっては条件が複雑になることもあるため、事前の確認が求められます。
例②:被相続人と子供の共有名義の場合
400㎡の土地を、被相続人と同居の子Aが50%ずつ共有していたケースを想定します。被相続人の持分200㎡を子Aが相続した場合、以下のような条件を満たす必要があります。
- 被相続人と同居していたこと
- 相続税の申告期限まで居住を続けること
これらをクリアできれば、子Aが取得した200㎡に対して80%の評価減を適用することが可能です。
一方、別居していた子Bが相続する場合は、通常は特例の対象にはなりません。ただし「家なき子」の要件を満たせば例外的に適用される可能性もあるため、詳細な要件確認が重要です。
例③:相続人間で共有相続する場合
被相続人が生前に単独で所有していた土地(例:300㎡)を、相続によって配偶者と子がそれぞれ150㎡ずつ相続(持分50%ずつ)したケースを想定します。
この場合、それぞれの相続人が取得した持分150㎡に対して、小規模宅地等の特例の適用が「個別に」判断されます。
配偶者は原則として要件を満たすため、150㎡すべてに80%の評価減が適用されるのが一般的です。一方で、子については「被相続人との同居」や「相続税申告期限までの継続居住」といった要件を満たしているかどうかに応じて、適用の可否が分かれます。
また、最初から土地を共有する形で相続するのではなく、地形や利用状況に応じて物理的に分筆して相続することで、それぞれの相続人に適用できる特例の面積が最大化される可能性もあります。こうした分割相続の工夫は、結果として相続税の軽減につながる場合があります。
「小規模宅地等の特例」を適用する際の注意点
小規模宅地等の特例は、制度の概要こそシンプルに見えますが、実際の適用には細かな実務上の注意点があります。特に、土地の利用状況や建物の形態が単純でない場合、計算方法や適用範囲が複雑になることも少なくありません。
ここでは、共有持分のあるケースを含め、特例の活用にあたって事前に確認しておきたい実務上の留意点を整理してご紹介します。
持分と土地利用の不一致がある場合の評価は複雑になる
小規模宅地等の特例を適用する際、持分割合と実際の利用状況が一致していないケースでは、評価や計算が複雑になりがちです。
たとえば、500㎡の土地を被相続人と他の共有者が50%ずつ所有していた場合、被相続人の持分は250㎡になります。しかし、その250㎡すべてが居住用であるとは限りません。以下のような按分が必要になることもあります。
- 土地全体の利用状況が「居住用40%:賃貸用60%」の場合
- 被相続人の持分250㎡にこの比率を適用
→ 居住用:100㎡、賃貸用:150㎡
- 居住用に80%、賃貸用に50%の評価減を適用(上限面積に注意)
このように、持分割合と用途が一致していない場合は、用途ごとの面積をさらに案分して評価減を適用する必要があります。特例の恩恵を過不足なく受けるには、評価明細の作成段階から慎重な判断が求められます。
二世帯住宅は構造と登記状況に応じて判断が分かれる
二世帯住宅のように、被相続人と相続人が一つの建物に住んでいた場合も、特例の適用可否はケースバイケースです。特に、建物の構造や登記の状態によって判断が分かれるため、形式的な「同居」の有無だけでは判断できません。
主な判断ポイントは以下のとおりです。
- 登記が区分所有かどうか
→ 完全分離型で登記も別なら、別々の住宅と見なされる可能性がある
- 生活実態の有無(食事・水回り・玄関など)
→ 実質的に同居していれば、1住宅として認定されるケースもある - 一方が賃貸用として使われている場合
→ 居住用と賃貸用に分けて按分計算が必要
二世帯住宅は「見た目は一軒家」でも、制度上は複数のパターンに分類されます。建物構造・登記内容・生活実態の3点セットで評価されるため、事前の確認が欠かせません。
特例が使えなかった不動産も「ワケガイ」なら買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や相続不動産など、通常は扱いづらい物件を専門に取り扱う買取サービス「ワケガイ」を提供しています。
小規模宅地等の特例は非常に有用な制度ですが、実際には適用条件が厳しく、制度の誤解から相続後に想定外の納税負担や売却の困難に直面する方も少なくありません。
ワケガイでは、こうした“制度の枠に収まらなかった”不動産も含め、全国対応で買取実績を重ねてきました。
相続による共有状態が続いている物件や、名義が整理できていない土地なども対象となります。まずはお気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
小規模宅地等の特例は、相続税を大きく軽減できる強力な制度ですが、実際に適用するためには厳格な条件を満たす必要があります。
特に共有持分がある場合には、面積の按分や相続人ごとの要件の精査など、専門的かつ複雑な判断が求められます。形式的な同居や所有だけでは適用できないことも多いため、「自分のケースで本当に使えるのか」を事前に見極めることが重要です。
制度の誤解による申告ミスや想定外の納税を避けるためにも、早い段階で相続税や不動産に詳しい税理士・弁護士に相談し、正確な評価と方針を立てましょう。