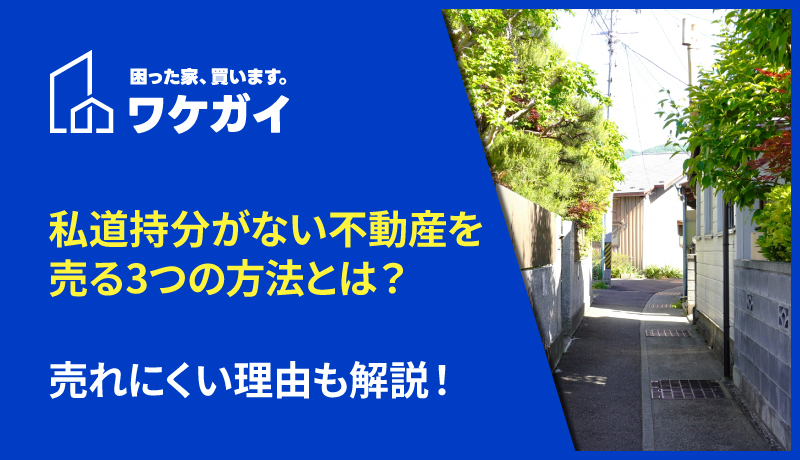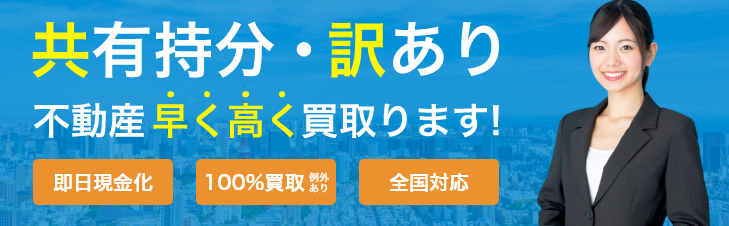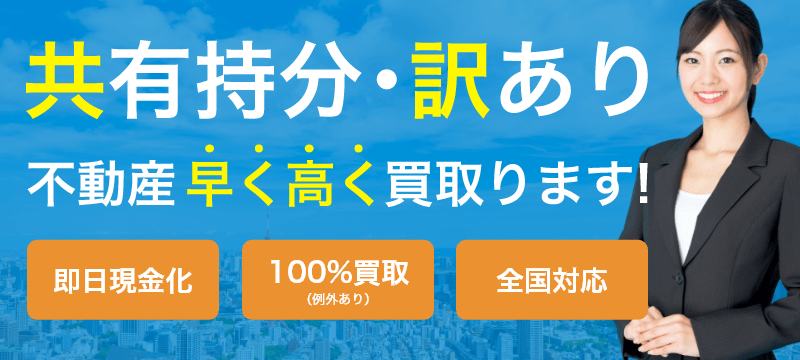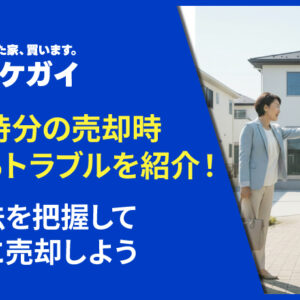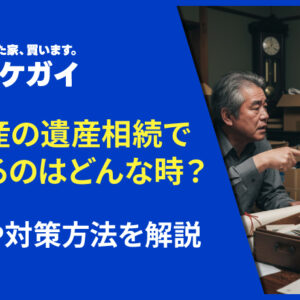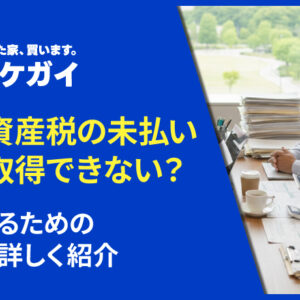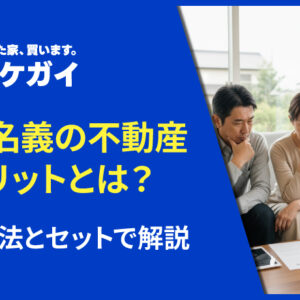私道とは、国や自治体ではなく個人や民間が所有する道路のことを指します。私道に接している土地を所有していても、私道持分がないなら思うように活用できない可能性があります。
そのような事態を避けるためには、「私道持分がない」とはどういう状態か知っておくことが大切です。本記事では、私道持分がない状態におけるリスクと隣接する不動産の売却方法を解説します。
目次
私道とは?

私道とは、個人や法人などの私的な所有者が保有している道路を指します。これに対して、国や自治体が管理する道路は「公道」と呼ばれ、一般に自由に通行できるのが特徴です。
私道は日常的に通行する必要がある道路であるにもかかわらず、舗装の修繕やゴミの収集、インフラ整備といった面で公道と比べて行政のサポートが受けられにくい傾向にあります。
そのため、私道を所有または利用する場合には、権利や管理面の責任についてあらかじめ理解しておくことが大切です。
私道の種類

私道には、主に3つの種類があります。建築基準法に基づいて分類されており、種類によって家の建築や再建築、通行権などに関する影響が異なります。ここからは代表的な私道の種類について解説します。
また、以下の表では私道の種類別の特徴や注意点についてまとめています。あわせてチェックしてください。
| 特徴 | 注意点 | |
| 既存道路 | 古くから利用されている | 整備状況が悪いことが多い |
| 位置指定道路 | 行政から道路として指定されている | 維持・管理は所有者の責任となる |
| 2項道路(みなし道路) | 幅員4m未満の道で既存家屋が並ぶ地域の私道 | 建築時にセットバックが必要 |
既存道路
既存道路とは、建築基準法が施行される前からすでに存在していた私道で、現行の基準を満たしていなくても「みなし道路」として扱われる道路です。
既存道路は、「幅員が狭い」「整備状況が十分でない」場合もありますが、原則として建築許可が下りるため、私道であっても利用価値は比較的高いといえるでしょう。
位置指定道路
位置指定道路とは、建築確認を得るために個人や開発業者が申請し、行政から道路として「位置指定」された私道のことです。幅員や形状などが法の基準を満たしている必要があり、建物を建てるための接道要件として認められています。
位置指定道路には、維持管理の義務が発生するケースが多く、所有者間で補修や管理方法についてあらかじめ取り決めをしておく必要があります。
共有持分になっていることが多いため、将来的なトラブルを避ける上でも契約内容や登記情報をしっかり確認しておきましょう。
2項道路
2項道路は幅員が4m未満の狭い道路を指します。2項道路に面した土地では、道路の中心から2メートル後退して建物を建てる「セットバック」が必要です。
この後退部分は、私有地であっても公共の通行が想定されるため、将来的な活用やリフォームの際には制限がかかる場合があります。
私道持分とは?

私道持分とは、私道(個人が所有する道路)に対する所有権の一部を複数人で持っている状態を指します。例えば、分譲地内の私道が6軒の家に囲まれている場合でそれぞれの家の所有者がその道路に6分の1ずつの権利を持っているようなケースが、私道の共有持分です。
この「持分」があることで、通行や水道工事といった利用を比較的自由に行うことができ、他の共有者に許可を得る必要がないケースも多くなります。一方で持分がないと、通行や掘削のために別の所有者に毎回承諾を求める必要があり、生活や売却に支障が出るかもしれません。
共有型私道
共有型私道とは、道路全体が1つの土地として登記されており、複数の所有者がその土地に対して一定の割合で共有している状態を指します。例えば、私道全体の持分をそれぞれが6分の1ずつ持っているような形です。
私道に対する決定(たとえば舗装工事や水道の引き込みなど)には、原則として全共有者の同意が必要となります。1人でも反対する共有者がいれば工事が進められないケースもあるため、意見の食い違いがトラブルになることも少なくありません。
しかし、共有型の場合は持分が明確に存在しているため、通行や掘削といった権利主張がしやすいという側面もあります。
私道の共有持分で発生するトラブルとは?対処法もセットで詳しく解説
持合型私道
持合型私道は、道路が複数の区画に分筆され、それぞれの土地所有者が別々に私道の一部を単独所有しているケースです。登記上においては「共有」ではありませんが、実態としては私道を共同で利用しているため、やはり合意形成や通行・掘削に関する調整が必要になります。
「目の前の私道は自分の土地」だと思い込んでいても、実は隣人の所有地だったというケースもあり得るため、分筆された持合型私道では、登記上の区分をしっかり把握しておくことが大切です。
私道持分の調べ方

自分が所有する土地に私道持分があるかどうかは、いくつかの方法で確認できます。不動産の売却や建築を検討する際には、持分の有無が大きく影響するため、早い段階で確認しておくことが重要です。以下に主な調査方法をまとめます。
| 方法 | 調査内容 |
| 登記簿謄本(全部事項証明書)を確認する | 私道の地番を特定し、所有者や持分割合を調べることができる |
| 公図を確認する | 接道する道路が私道かどうかを判別できる(地番の有無で判断) |
| 役所で調べる | 建築指導課や道路管理課などで私道の種類や管理状況を確認できる |
| 専門家に相談する | 弁護士・司法書士・不動産会社などに調査を依頼することができる |
書類の読み取りや調査に不安がある場合は、専門家のサポートを受けながら進めましょう。
私道持分がない状態とは?

私道持分がない状態とは、自分の土地が私道に面しているにもかかわらず、その私道に対する所有権を持っていない状態をいいます。例えば、家の前の道路が個人所有の私道で、その持分を自分が持っていない場合が該当します。
私道の通行や掘削は、本来その所有者の承諾が必要な行為です。持分があれば、他の共有者の同意なく通行や工事ができる場合もありますが、持分がなければ一方的に使用することができません。
日常的に通っている道路であっても、他人の土地を無断で使っている状態になっている可能性もあるため注意が必要です。道路の活用や建物の再建築においても制約が設けられるため、私道持分がない状態は大きな問題といえるでしょう。もちろん、自分の土地の資産価値の低下にも繋がります。
私道持分がない不動産が売れにくい理由
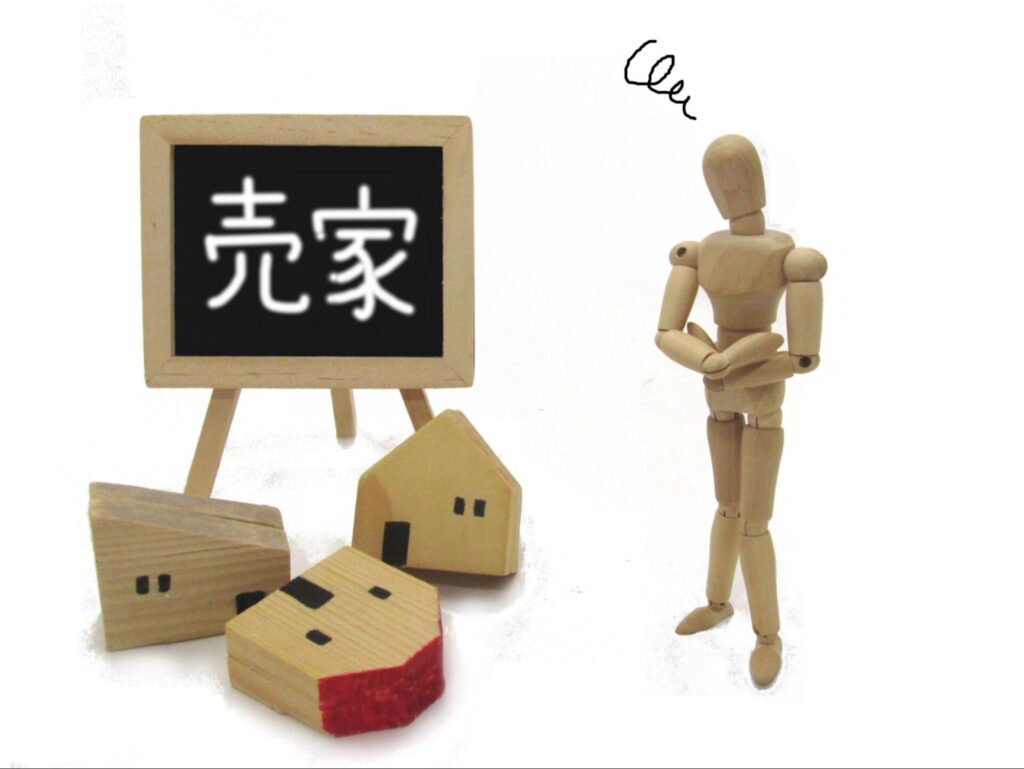
私道持分がない不動産は、いざ売却しようとすると買主がつかないケースが多々あります。以下より、なぜ私道持分がないと売却が難しくなるのかを詳しく解説します。私道持分がない不動産の売却を考えている方は、参考情報としてお役立てください。
通行や掘削に制限がかかる
私道を通行したり、地中にガス管・水道管などのインフラを通したりするには、その道路の所有者の承諾が必要です。私道持分がない場合は、道路に関する権利を持っていないため、通行や掘削に制限がかかってしまいます。
せっかく不動産を購入しても、自由に活用しづらいのが売れにくい要因となっています。
建築・再建築に制約がある
建築基準法では、建物の敷地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが求められています。しかし、私道に接していても持分がない場合、その道路を建築基準法上の道路として扱えず、建築確認が下りない可能性があります。
新築や再建築ができず、実質的に「建て替え不可の土地」とみなされてしまうのも、買い手が見つかりづらい要因の一つです。
住宅ローン審査に通りにくい
私道持分がない不動産は、法律上の不安定さや再建築不可の可能性があるため、金融機関が担保評価を下げやすくなります。その結果、住宅ローン審査が通らない、あるいは融資額が下がるといった事態に発展します。
買主が現金で購入する以外の選択肢が取りづらくなるため、買い手の層が狭まり、売却にも時間がかかりやすいです。初めて不動産を購入する方は慎重になるため、このような物件は敬遠されやすくなります。
私道の維持・管理でトラブルが起こりやすい
私道は公道とは異なり、所有者が維持・管理する責任を負います。私道持分がない場合は、補修や清掃、除雪などの維持管理に関与できない。あるいは費用の負担を巡ってトラブルになることがあります。様々な面で取扱の負担が大きいため、買い手が見つかりづらいのです。
私道持分がない不動産を売る3つの方法

私道持分がない不動産でも、売却できないわけではありません。私道に関する権利関係を整理すれば、スムーズに売却できる可能性は十分にあります。ここでは、私道持分がない不動産を売却するための方法を3つ紹介します。
通行・掘削承諾書を取得してから売却する
私道の所有者から「通行承諾書」や「掘削承諾書」を取得しておくと、買主は不動産の前面道路を通行でき、水道やガスなどのライフラインの整備も可能になります。再建築を希望する買主にとっては、これら書類の有無は重要といえるでしょう。
そのため、承諾書は書面で残し、可能であれば実印と印鑑証明を添えるようにしましょう。不動産会社に相談すれば、ひな形の提供や書類取得のサポートを受けられることもあります。
私道持分を買い取ってから売却する
私道の共有者からその持分を買い取るという選択肢もあります。持分を取得すれば、通行・掘削の権利を正当に主張できるため、売却時におけるアピールポイントとなります。
しかし、私道の持分を所有している人が複数いる場合に、全員からの持分を買い取るのは難しいでしょう。また、売却するつもりがない共有者がいる可能性もあるため、事前にしっかりと交渉しておくことが大切です。
訳あり物件専門の買取業者に売却する
私道持分の取得や承諾交渉が困難な場合は、一般の買主ではなく、訳あり物件を専門に扱う不動産買取業者に売却する方法もあります。こうした業者は、通行・掘削のリスクや再建築制限も織り込み済みで査定を行ってくれるため、交渉もスムーズに進みやすいしょう。
価格は市場相場より下がる可能性がありますが、売却までのスピードが早いというメリットもあります。「早く手放したい」「関係者と交渉したくない」という場合には、有効な選択肢といえるでしょう。
【2025年版】共有持分の買取業者のおすすめ厳選5社!今買取をお願いするべき専門業者とは?
私道持分がなくてもスムーズに売却するためにやっておいた方がいいこと

私道持分がない不動産は、そのままでは売却が難しいと思われがちですが、事前の準備次第で取引のハードルを下げることは可能です。ここでは、私道持分がない不動産をスムーズに売却するための準備について解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
私道の所有者を調べておく
まずは接している私道が誰の所有なのかを明確にしておくことが大切です。法務局で登記簿謄本を取得すれば、所有者の氏名や持分割合を確認できます。また、公図を確認すれば、その道路が私道かどうかを判断できます。
所有者が複数いる場合や、名義人がすでに亡くなっている場合など、交渉の難易度にも関わってくるため、売却の前にしっかり調査しておくことが重要です。
通行・掘削の実態を整理しておく
どのように私道を使用しているのかも把握しておきましょう。具体的には、自動車での通行が可能か、水道・ガスなどの配管はどのように引き込まれているかなど、生活に直結するポイントを整理しておいてください。
これらの情報は「この家で安心して暮らせるかどうか」を見極める上で、重要な判断材料となります。必要な情報をきちんと示すことで、信頼を得やすくなり、取引もスムーズに進められるでしょう。
承諾書の取得可否について事前に確認しておく
実際に通行や掘削を認めてもらうには、私道の所有者からの「承諾書」が必要になることがあります。売却をスムーズに進めたいのであれば、あらかじめ所有者に対し、承諾に応じてもらえる可能性があるかどうかを確認しておくとよいでしょう。
私道を共有しているなら知っておくべき権利と売却時の注意点とは
私道持分に関するよくある質問

私道持分に関するよくある質問について回答します。私道持分の不動産の取扱に悩んでいる方は、ぜひチェックしてください。
公道と私道を見分ける方法とは?
確実な見分け方は「法務局で登記情報を確認する」ことです。市区町村の道路台帳で確認できる場合もあります。台帳上で市区町村が管理していれば公道。個人または法人の所有であれば私道となります。
私道の所有者になるメリットとは?
私道の所有者になると、その道を通る権利が得られます。場合によっては、他の住人から通行料や工事費の負担を求めることも可能です。
私道の所有者になると固定資産税がかかる?
私道でも「不特定多数が自由に通行している」と市区町村に認められれば、非課税となるケースもあります。しかし、原則として土地である以上、固定資産税の課税対象になります。
私道持分は登記が必要?
原則として、私道の持分を正式に取得した場合には登記を行うべきです。登記されていないと、自分が所有している証明ができず、売却や相続などの場面でトラブルの原因となります。
「ワケガイ」なら私道持分がない不動産も短期で買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、再建築不可や共有持分付きなど、権利関係が複雑な不動産の買取に特化したサービス「ワケガイ」を運営しています。私道持分がない土地は、通行や掘削の問題から売却が進みにくいケースも多く、個人での交渉や対応に限界を感じる方もいらっしゃいます。
ワケガイでは、こうした物件に特有のリスクを踏まえたうえで、査定から契約までを専門スタッフと士業がサポートします。複雑な事情を整理し、最短1日での買取にも対応可能です。ぜひ、お気軽に無料査定をご活用ください。
私道持分がない不動産でも売却することは可能!

私道の持分がない状態は、普段の生活では問題がなくても、不動産を売却したり建て替えたりする際にトラブルの原因となる可能性があります。通行や掘削の許可が必要なケースでは、私道の所有者との交渉が避けられず、スムーズに進まないことも少なくありません。
トラブルを未然に防ぐには、まず自分の土地が接している道路の所有関係をしっかり確認することが求められます。必要に応じて持分の取得や、通行・掘削の承諾書を取り付けるといった準備を進めておくと安心です。
私道の持分があるかどうかは、法務局で登記簿や公図を確認すれば把握できます。将来的に売却や建築を考えている場合は、早めに状況を把握し、対応を考えておきましょう。