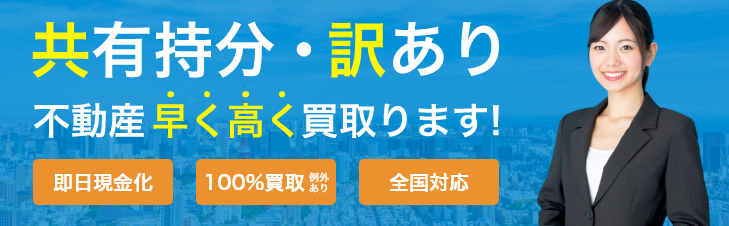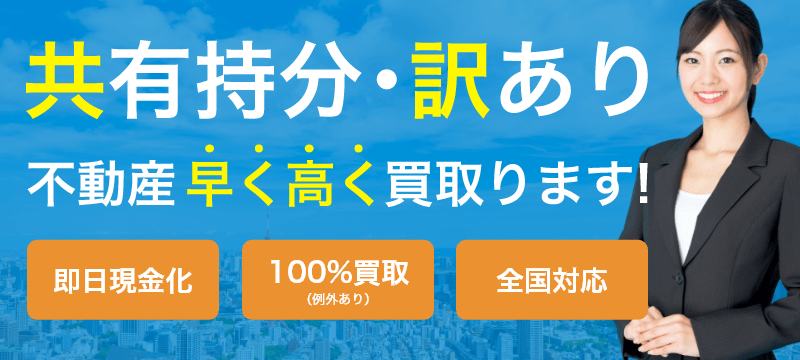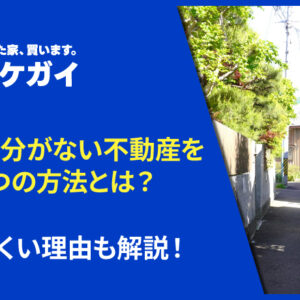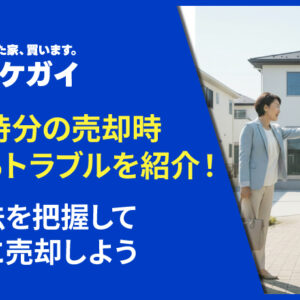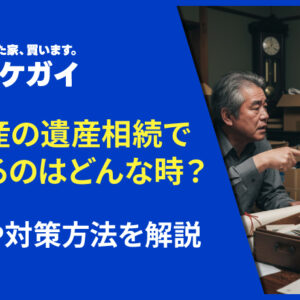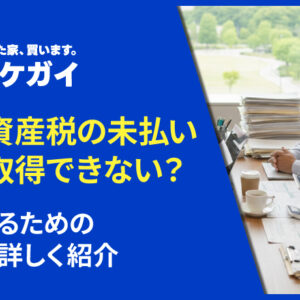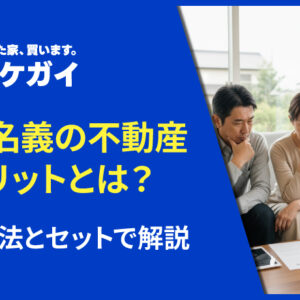住宅地の開発や土地の分割などにより、私道を共有する形態が増えています。しかし、私道の共有持分を持つことで、修繕費用の負担や通行権をめぐるトラブルが発生するケースがあります。その際に問題となるのが私道の共有持分です。
私道の共有持分とは、複数の所有者が1つの私道を共同で所有する形態を指します。共有持分を持つことにはメリットもありますが、さまざまなトラブルのリスクも伴います。
そこで本記事では、私道の共有持分で発生するトラブルと、その対処法について詳しく解説します。
目次
私道の共有持分とは
私道の共有持分とは、複数の所有者が1つの私道を共同で所有している状態を指します。例えば、分譲住宅の敷地に通じる私道を近隣住民数名で共有している場合、それぞれの所有者が持つ割合(持分)が「共有持分」です。
この共有持分には、道路を通行・使用できる権利が含まれますが、同時に管理や修繕、税負担などの義務も発生します。所有者全員で合意が必要な場面も多く、意見の対立や連絡不通などがトラブルの火種になることも。
見た目は普通の道路でも、法的には私有地である点に注意が必要です。
関連記事:私道持分とは?トラブル事例やメリット・デメリット、税金や売却手順までご紹介!
公道と私道の違い
公道と私道は、一見すると区別がつきにくいものの、その性質は大きく異なります。公道は国や地方自治体が管理し、誰もが自由に通行できる道路です。
一方、私道は個人や法人が所有する私有地であり、原則として所有者の許可なく通行することはできません。
公道の管理や補修は行政が行いますが、私道の場合はその所有者が責任を負います。このため、私道の所有者は維持管理の負担を背負うことになります。
ただし、建築基準法上の道路として指定された私道は、公道と同様に誰もが通行できるという特徴があります。
私道には2つの共有形態がある!
私道が複数の人によって所有されている場合、大きく分けて「共同所有型」と「相互持合型」の2つの共有形態があります。
一見すると同じように見えるかもしれませんが、それぞれの仕組みやトラブルの起こりやすさには違いがあります。不動産の売買や再建築、インフラ整備を考える上でも、この違いを正しく理解しておくことが大切です。
共同所有型
共同所有型は、私道全体を複数人で「共有」する形態です。たとえば、5軒の住宅が並ぶ分譲地で、その中央を通る道路を5人全員で所有する場合、それぞれが私道の5分の1の共有持分を持つことになります。
所有者は持分割合に応じて権利と義務を負いますが、私道全体に関する修繕や通行の意思決定には、原則として共有者全員の合意が必要です。そのため、管理や売却の場面では手間がかかることも少なくありません。
関連記事:私道の持分を共有している場合、権利関係はどうなるの?
相互持合型
相互持合型は、私道をいくつかの区画に分筆し、それぞれを個別の所有者が単独で持つ形態です。見た目には一本の道でも、登記上は複数の土地に分かれていて、それぞれ別の所有者に属しています。
この場合、自分の敷地までたどり着くためには、他人の所有する私道部分を通る必要があるため、通行地役権の設定や通行承諾が重要になります。掘削や車両通行などに制限がかかるリスクもあるため、契約関係や登記の有無を事前に確認しておくことが欠かせません。
共同所有型の私道持分のトラブル事例
共同所有型の私道では、複数の所有者がひとつの土地を共有していることから、合意形成や責任分担の難しさがトラブルの原因になることがあります。以下では、よく見られる事例を3つ紹介します。
事例①:共有者が行方不明
私道の共有者のうち、1人が高齢で施設に入っていたり、相続登記が未了で所在が不明になっていたりするケースがあります。通行や掘削の承諾、売却時の合意など、共有者全員の関与が必要な場面では大きな障害となります。
特に、通行承諾書の取得や名義変更を行おうとしても、同意が取れなければ手続きが進められません。こうした場合は、不在者財産管理人の選任や、家庭裁判所への申し立てが必要になることもあり、時間と費用がかかります。
関連記事:共有者が行方不明の場合の対処方法について詳しく解説
事例②:管理を放棄する人がいる
共有者の中には、「自分はあまり通らないから」と私道の清掃や補修といった管理に協力しない人が出てくることがあります。雨水の排水不良やアスファルトの損傷などが放置されると、日常生活に支障が出るだけでなく、私道の劣化による事故リスクも高まります。
それでも全員が所有者であるため、強制的に対応を求めるのが難しいのが実情です。こうした状況が続くと、近隣トラブルや損害賠償請求に発展することもあります。
事例③:費用負担で揉める
私道の補修や舗装、排水設備の工事などが必要になった際、「費用をどのように分担するのか」を巡ってトラブルになることがあります。
持分割合に応じた負担が原則ですが、「あまり使っていないから払いたくない」「前回払ったから今回はパスしたい」といった主張が出ることも。感情的な対立に発展しやすく、話し合いが難航する原因になります。
あらかじめルールを定めた書面を用意しておくことで、予防的対応が可能です。
関連記事:共有不動産の管理費用の分担方法とは?費用を払わない共有者がいる場合の対応手段について
相互持合型私道私道持分のトラブル事例
相互持合型では、形式上は単独所有でも、生活動線や工事のたびに他人の土地を使う必要があるため、トラブルの火種は意外と多く存在します。以下に典型的なパターンを整理します。
事例①:通行を拒否される
相互持合型の私道では、自分の敷地にたどり着くために他人の所有部分を通行する必要があります。しかし、関係性が悪化している場合などには、「勝手に通るな」と通行を拒否されたり、故意に障害物を置かれたりすることもあります。
通行地役権の登記がされていなければ、法的根拠に基づいた通行が難しく、建物への出入りすら制限されかねません。問題を回避するには、通行地役権の設定や承諾書の取り交わしが重要です。
事例②:掘削に反対される
建て替えや新築の際、水道・ガス・下水などのインフラを引き込むために、他人の所有部分を掘削する必要がある場合があります。ところが、私道の持合部分の所有者が掘削に難色を示し、承諾書を出してくれないといったケースがしばしば発生します。
「土地が傷むから」「工事がうるさいから」といった理由で反対され、必要なライフライン整備が進まなくなると、建築計画自体がストップする可能性もあります。
法的には、通行権と異なり掘削を前提とした「掘削権(掘削地役権)」は慣習で当然に認められるものではなく、原則として当事者の合意が必要です。掘削を伴う工事には明示的な承諾書が求められることが多いため、事前の交渉や契約書の整備が極めて重要になります。
事例③:通路に物を置かれる
「この部分は自分の土地だから」と言って、道路の一部に自家用車や植木鉢、自転車などを置かれてしまい、日常的な通行に支障が出るケースもあります。特に幅の狭い私道では、歩行者や車両が安全に通れなくなり、緊急車両の進入にも影響を及ぼすことがあります。
相手が悪意をもって占有している場合でも、通行地役権などの権利関係が明文化されていなければ、法的手段で排除するのは簡単ではありません。
私道の共有持分でトラブルが発生した場合の対処法
私道に関するトラブルは、一度発生すると解決が難しくなる傾向があります。しかし、適切な対応をとることで、問題を最小限に抑えたり、円滑に解決したりすることが可能です。以下に、具体的な対処法を3つ紹介します。
当事者間での話し合う
トラブルが発生した際、まず試みるべきは当事者間での話し合いです。共有者全員が集まり、問題の本質を明確にし、互いの立場を理解し合うことが大切。この際、感情的にならず、冷静に議論する必要があります。
話し合いの結果は、必ず書面にまとめておくことをおすすめします。将来的なトラブルを防ぐため、私道の使用規則や費用負担の方法などを明確に定めた取り決めを作成するのも有効です。
また、通行や掘削に関する承諾書を取り交わしておくことで、後々の紛争を予防できる可能性が高まります。
専門家や行政に相談する
当事者間での解決が難しい場合は、専門家への相談を検討しましょう。弁護士は法的な観点からアドバイスを提供し、交渉や訴訟の支援を行います。
特に、不動産専門の弁護士は私道問題に精通していることが多く、適切な解決策を提案してくれる可能性が高いです。
また、行政への相談も有効な手段の1つです。特に、私道が建築基準法上の道路として指定されている場合、自治体の建築指導課などが助言をくれることがあります。
ただし、行政は個人間の紛争に直接介入することは少ないため、その点は理解しておきましょう。
訴訟や調停による解決を図る
私道の共有持分をめぐるトラブルが当事者間の話し合いで解決できない場合、最終的には法的手続きに進むことも視野に入れなければなりません。
たとえば、補修工事や通行・掘削に関する承諾が得られないケースでは、簡易裁判所への調停申立てや、地方裁判所での民事訴訟が選択肢になります。
特に、共有者の一部が行方不明、もしくは非協力的な場合には、共有物分割請求訴訟や、不在者財産管理人の選任申し立てを行うことで前に進める場合があります。
私道に面した不動産を売却する際のポイント
私道に面した不動産を売却する際は、通常の不動産取引以上に注意を払う必要があります。買主に対して正確な情報を提供し、将来的なトラブルを防ぐためにも、以下の点に特に注意を払いましょう。
権利関係を明確にしておく
売却前に、私道に関する権利関係を明確にすることが極めて重要です。特に大切なのは「通行承諾書」「掘削承諾書」の取得です。これらの書類があることで、買主は安心して物件を購入できます。
通行承諾書は、私道の所有者から通行を許可されていることを証明する書類です。一方、掘削承諾書は、水道やガスなどのインフラ設備を引き込む際に必要な道路の掘削を許可する書類です。
これらの承諾書がない場合、売却そのものが困難になる可能性があります。
建築基準法の確認を行う
私道が建築基準法上の道路として認められているかどうかの確認も欠かせません。建築基準法では、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが、建物を建築するための条件となっています。
(参考:e-Gov 法令検索「建築基準法」)
私道がこの条件を満たしていない場合、建物の建築や増改築が制限される可能性が生じます。
そのため、セットバック(道路中心線から2メートルの線まで後退すること)が必要になることも想定されます。これらの情報は、不動産の価値に大きく影響するため、買主に正確に伝えることが求められます。
関連記事:私道持分がない不動産を売る方法とは? 私道持分がないときの対処法もあわせて解説
「ワケガイ」なら訳あり物件も短期で買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や再建築制限といった複雑な条件を抱える不動産にも対応できる買取サービス「ワケガイ」を提供しています。
私道の共有持分が絡む物件は、掘削や通行の承諾をめぐる合意形成の難しさから、一般の買主に敬遠されやすいのが実情です。とくに、共有者との連絡が取れない・承諾書が取得できないといった問題がある場合、市場流通での売却は現実的ではなくなります。
ワケガイでは、こうした状況も踏まえた上で、法的リスクを整理しながら現実的な売却ルートをご提案可能ですので、お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
私道の共有持分は、一見すると単純な所有形態に思えますが、実際には複雑な問題をはらんでいます。共有者間のトラブルを未然に防ぐためには、事前に明確な取り決めを作成し、お互いの権利と責任を理解しておくことが重要です。
また、不動産の売買時には、私道に関する権利関係を明確にし、買主に正確な情報を提供する必要があります。
私道に関する問題は、法律や建築基準法など専門的な知識が必要となることが多いため、自己解決が難しいケースも少なくありません。
トラブルが発生した場合や、解決の糸口が見つからない場合は、早めに弁護士や不動産の専門家などに相談することをおすすめします。