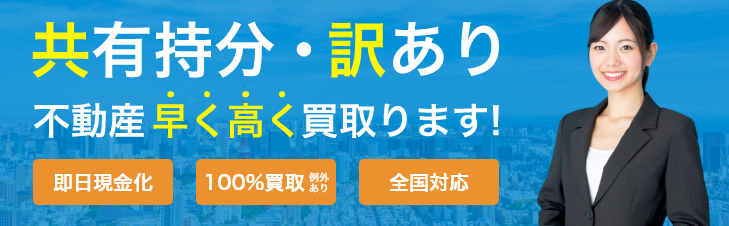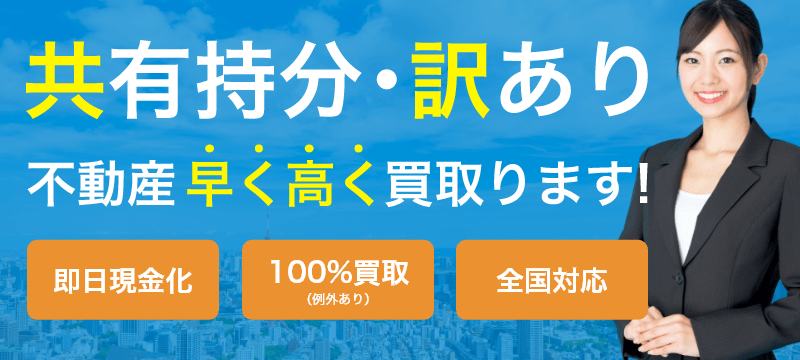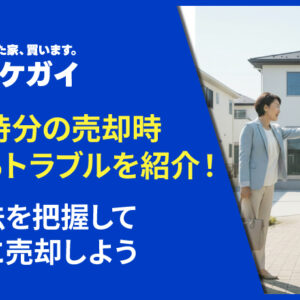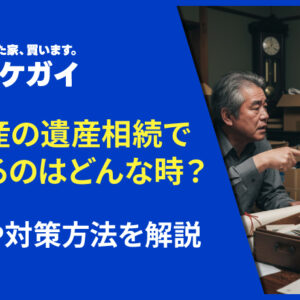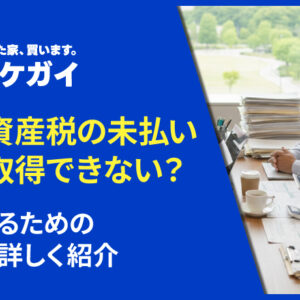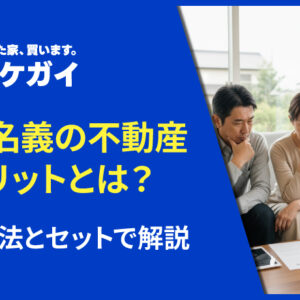親族間の話し合いが難航していたり、思うように不動産を活用できなかったりする場合、共有している不動産を他人に譲渡することが選択肢となることがあります。
しかしその過程では、名義変更の手続きや他の共有者との調整だけでなく、「どのような税金が発生するのか」という点についても慎重な検討が求められます。
とくに、譲渡の方法によって税の種類や課税額が大きく異なるため、事前に整理しておくことが欠かせません。
本記事では、共有不動産の持分を第三者に譲渡する場合に生じる主な税負担について、制度のしくみや計算方法とともに丁寧に解説していきます。
目次
まずは共有持分の特性について知っておこう
共有持分とは、何人かで共有している不動産の所有割合を示すものです。例を出すと、3人の兄弟が実家を均等に相続する場合、その家に対する各人の共有持分は「1/3」となります。
多人数で財産を共有する際には、それぞれの共有持分やそれに伴う各種の権利が発生します。共有持分権者が持つ権利は、「持分が半分なら建物の半分が自分のもの」という具体的な内容ではなく、「全体の不動産に対して半分の権利を持つ」という抽象的な概念となります。
共有持分者に与えられた権利とは?
不動産の所有者は以下の権利を持つことができます。
- 変更(処分)行為…売却や贈与、長期賃貸借など。
- 管理行為…賃貸借契約の締結や利用方法の決定など。
- 保存行為…修繕や明渡し請求、抹消登記請求など。
しかし、共有不動産においては、「単独で実行可能な行為」と「そうでない行為」が存在します。そのため、共有持分は通常の不動産に比べて非常に使い勝手が悪いのです。
例えば、不動産の売却について決定する際、共有持分が大きい者の意見が重視されることがあります。さらには、賃料収入などの利益も、共有持分の割合により分配されるのが特徴です。
共有持分は、相続や贈与、売買などによって譲渡され、その際には税金や手続きなどの規定に従う必要もあります。
共有持分を譲渡する3つの方法
共有持分を他人に譲渡する方法には、主に「売買」「贈与」「交換」の3つがあります。どの方法を選ぶかによって、手続きや税金、後のトラブル回避の観点からも大きな違いが生じます。
以下に、各譲渡方法の特徴をまとめました。
| 譲渡方法 | 概要 |
| 売買 | 金銭を受け取る代わりに持分を譲渡する方法。最も一般的な譲渡手段。 |
| 贈与 | 無償で共有持分を譲渡する方法。親族間などでよく使われる。 |
| 交換 | 自分の持分と他の財産(不動産や金銭など)を交換する方法。双方に譲渡が発生。 |
共有持分は、通常の不動産と異なり「不動産全体に対する一部の権利」であるため、譲渡時には特有のリスクや制限があります。以下の点に留意が必要です。
- 単独では不動産全体を処分できない
- 他の共有者に優先取得権がある場合がある
- 買い手が見つかりにくい
このように、共有持分の譲渡には通常の不動産取引以上に注意が必要です。手続き前に、他の共有者との関係や利用予定も含めて慎重に検討することが大切です。
関連記事:共有持分を譲渡する3つの方法とは?注意点も交えて易しく解説
関連記事:他の共有者から共有持分を取得する方法とは?
関連記事:共有持分の不動産を売却する方法とは?売却費用やよくあるトラブルを紹介!
共有持分の譲渡ではどのような税金が発生する?
では、上記のいずれかの方法で共有持分を譲渡した場合、どのような税金が発生するのでしょうか。ここからは、各ケース別に解説します。
売買で発生する税金
共有持分を売却すると、その売却益に対して譲渡所得税が課税されます。これは「購入額より高く売れた」場合に生じる税金で、5年を超えると長期譲渡所得、5年以下だと短期譲渡所得として扱われ、税率が異なります。
| 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計 | |
| 短期譲渡所得(5年以内) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期譲渡所得(5年超) | 15% | 5% | 0.32% | 20.32% |
譲渡益の算定には、取得費や仲介手数料などの譲渡費用も含めて計算する必要があります。
一方で、買主側には登記に関連する税金が発生します。具体的には、固定資産評価額に基づいて計算される登録免許税や、都道府県から課税される不動産取得税などが挙げられます。
(参考:総務省「不動産取得税」「登録免許税のあらまし」)
特に住宅用地などの場合は軽減措置があるため、取得予定の不動産の条件をあらかじめ確認しておくと安心です。
<売る側が支払う税金>
- 譲渡所得税・住民税・復興特別所得税
→ 最大39.63%、長期譲渡でも20.315%が課税される場合あり
<買う側が支払う税金>
- 登録免許税(固定資産評価額 × 2.0%)
- 不動産取得税(原則4%、住宅用地は特例で3%など)
関連記事:共有持分にかかる税金一覧!計算方法や控除制度もセットで徹底解説
贈与で発生する税金
共有持分を無償で譲渡した場合、税負担が発生するのは「もらった側」です。特に110万円を超える贈与は、贈与税の課税対象となり、金額に応じて最大55%の税率が適用されることもあります。
(参考:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)
贈与する側に課税されることは基本的にありませんが、評価額が高額になると受け手の負担は重くなるため、慎重な判断が求められます。
また、名義変更の際には登録免許税も発生します。不動産の固定資産税評価額に基づいて2.0%が課税され、贈与税と合わせると高額になることもあります。
<贈与する側が支払う税金>
- 原則なし
<贈与を受けた側が支払う税金>
- 贈与税(例:500万円の贈与で約76万円)
- 登録免許税(固定資産税評価額 × 2.0%)
評価額や関係性(親子・配偶者)によって特例措置が使える可能性もあります。事前に税理士に相談するのが安心です。
関連記事:共有持分を贈与する際の「贈与税の計算方法」をわかりやすく解説!
交換で発生する税金
共有持分の「交換」は一見すると単なる名義変更のように見えますが、税務上は「時価での売買」として扱われます。そのため、交換する双方に税金が発生します。
具体的には、自分が手放した不動産に譲渡益があれば譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)がかかり、同時に新たに取得した不動産に対しては登録免許税や不動産取得税が課税されます。
<交換する双方が支払う税金>
- 譲渡所得税・住民税・復興特別所得税
→ 譲渡益が出た場合に課税。短期なら最大39.63%、長期でも20.315%。 - 登録免許税(交換で取得した不動産の固定資産評価額 × 2.0%)
- 不動産取得税(原則4%、住宅用地などには軽減措置あり)
交換は「双方に売却・購入が同時に発生する」とみなされるため、税務処理も双方が必要になります。負担を明確にするためにも、交換前に譲渡益の有無や固定資産評価額を確認し、双方で合意形成をしておきましょう。
関連記事:共有持分の「交換」とは?共有関係を解消する方法を詳しく解説
「売却」で共有持分を譲渡したなら確定申告が必要
共有持分を売却して譲渡益が出た場合には、翌年の確定申告が必要となります。たとえ持分だけの売却であっても、譲渡所得が発生すれば、その旨を税務署に申告しなければなりません。
申告期間は、売却した翌年の2月16日から3月15日まで。普段は会社で年末調整を受けている方でも、このような不動産取引がある年には、個別に申告書を作成する必要があります。
注意したいのは、「利益が出ていないから申告は不要」と思い込まないこと。譲渡益は、「売却額から取得費・譲渡費用を差し引いた残り」で判断されます。帳簿上で損が出ている場合も、計算の過程で必要な書類が求められるため、準備は怠れません。
共有持分の売却は、一見すると小さな取引に見えるかもしれません。しかし税務上はれっきとした「不動産譲渡」であり、正確な手続きと申告が求められます。早めの情報収集と、必要であれば専門家への相談も視野に入れておくと安心です。
関連記事:共有持分はどのタイミングで売却するべき?高く売るための勘所も紹介
関連記事:共有名義人が認知症になったら、不動産は売却可能?成年後見人制度とセットで解説
確定申告のために用意しておくべき書類
共有持分の売却で譲渡益が発生した場合、確定申告を行うには一定の書類をそろえる必要があります。とくに「取得費」や「譲渡費用」がわかる資料が重要です。申告の際は以下のような書類を準備しましょう。
- 売買契約書(共有持分を売却した際のもの)
- 購入時の契約書や領収書(取得費の確認)
- 不動産仲介業者への支払い明細(譲渡費用)
- 登記事項証明書・固定資産税評価証明書
- 確定申告書B・譲渡所得の内訳書
状況により、相続税の申告書や遺産分割協議書が必要になることもあります。不明点がある場合は、税務署や税理士に早めに確認しておくのがおすすめです。
関連記事:共有不動産の売却でも「確定申告」は必要?やり方と注意点について紹介
売却の際に節税で使える特例とは
共有持分の売却で譲渡益が出た場合、そのまま課税されてしまうと、多くの納税負担が生じることがあります。ですが、条件を満たせば節税につながる特例制度も用意されています。
とくに知られているのが、「3,000万円の特別控除」です。これは、自宅(居住用財産)を売却した際、譲渡益から最大3,000万円を差し引くことができる制度。売却した物件に実際に住んでいたこと、一定の期間内に売却されたことなど、細かい要件をクリアする必要はありますが、適用されればかなりの節税が見込めます。
また、「軽減税率の特例」も有効です。こちらは、所有期間が10年を超えている住宅に限り、譲渡益の一部について通常より低い税率(所得税10%、住民税4%)が適用される仕組みです。
なお、こうした特例は共有持分の売却でも適用される可能性がありますが、実際に適用できるかどうかは、物件の利用状況や登記名義、持分の取得経緯などによって異なります。税務署への事前相談や、税理士への確認を通じて、適切な申告と節税対策を検討しておきましょう
共有持分を手放したい方は「ワケガイ」にご相談ください!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分をはじめとする訳あり不動産の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。
共有不動産の譲渡には、税金や申告の手続き、他の共有者との調整といった煩雑なプロセスが伴うため、「持分を手放したいけど、どう進めればいいのかわからない」とお悩みの方も少なくありません。
ワケガイでは、そうした共有持分の取り扱いに精通した専門スタッフが査定から売却手続きまでを一貫してサポートいたします。
全国対応で、共有持分のみのご売却も可能です。共有関係に悩まれている方は、お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
共有不動産の持分を他者に譲渡する場合、選択した方法によって発生する税金が大きく異なります。売買では譲渡所得税、贈与では贈与税、交換では双方に課税が及び、加えてすべてのケースで登録免許税や不動産取得税の発生が想定されます。
こうした税制は細かい条件により優遇措置が適用されることもあり、制度を知らずに手続きを進めると、想定以上の税負担を抱えるリスクも否定できません。
共有持分の譲渡を円滑に進めるためには、まず「どの方法で譲渡するか」を明確にし、あわせて課税対象となるかどうかを事前に確認することが重要です。
可能であれば、税理士や司法書士といった専門家の意見も取り入れながら、納税準備と書類の整理を進めていきましょう。