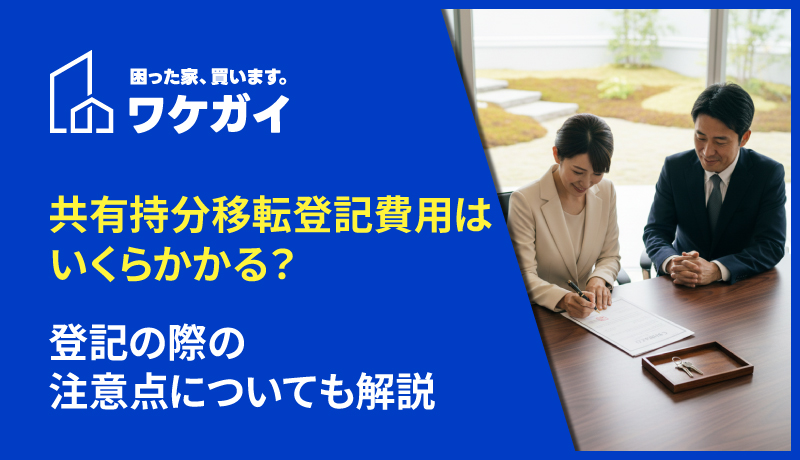共有持分の不動産は自由に売却したり、活用したりするのが難しい所有形態です。そのため、共有持分の移転を行い、共有状態を解消したいと考える方は多いでしょう。
共有持分の移転を行う際には、共有持分移転登記費用がどれくらいかかるかを事前に把握しておくことが大切です。本記事では、共有持分移転登記において発生する費用について解説します。共有持分の移転を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
共有持分の移転登記とは?

不動産を1人で所有していない場合は、登記上に複数人の名前が記載され、共有という状態になります。不動産の所有者が持っている権利の割合を示すのが共有持分です。
共有持分移転登記とは、共有持分を別の人に渡す際に行う手続きのことです。共有持分移転登記を行えば、不動産登記簿に記載されている共有者の名義を新しい所有者へ変更できます。
不動産の権利が移る際には、基本的に所有権移転登記が必要です。所有者が複数いる共有名義の場合は、所有権移転登記だけでなく共有持分移転登記も求められます。不動産を1人で保有している場合と比べると、登記にかかる手間が大きくなるといえるでしょう。
共有持分の移転登記の種類

共有持分の移転登記には主に5つの種類があります。それぞれ詳しく解説しますので、共有持分の移転登記を行う際は、参考情報としてお役立てください。
所有権移転登記
所有権移転登記は、不動産の所有権が別の人物に移ったことを正式に登記簿上で記録する手続きです。例えば、共有持分を売却した場合や贈与、相続などが発生したときに必要となります。
登記を行えば、新しい所有者が第三者に対して自分の権利を主張できるようになります。共有者の一部の持分を移す場合でも、法務局での登記が必要です。
建物表題登記
建物表題登記とは、新たに建物を建てたときに初めて法務局に登記する手続きを指します。この登記を行うことで、建物の存在が公的に認められ、登記簿上に物件として登録されます。
共有名義で建てられた建物についても、持分割合を含めて登記が為されます。通常は建築完了後1か月以内に行う必要があり、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。
抵当権設定登記
抵当権設定登記は、不動産を担保にしてローンを組む際に、担保関係を登記する手続きです。共有持分についても、各共有者が自分の持分にのみ抵当権を設定できます。
銀行のような金融機関が返済不能時に権利を行使できるようにするために、抵当権設定登記は必要になります。他の共有者の同意は不要ですが、同意がないと担保評価の観点から借入が難しいのが実情です。
地目変更登記
地目変更登記は、土地の用途が変わった際にその地目を変更するために行われます。土地を駐車場や住宅用地に転用するなどのケースで必要になります。
共有名義の土地でも、地目変更がある場合には共有者全員の申請または同意が求められます。登記がなされていないと、固定資産税の算出や売却時の評価にも影響を及ぼす可能性があります。
所有権保存登記
所有権保存登記は、まだ登記簿に所有者が記載されていない不動産について、初めて所有者として登記する手続きです。新築物件や、未登記の土地・建物が対象となります。共有持分で所有している場合は、それぞれの持分割合を含めて保存登記を行います。
共有持分の移転登記で発生する費用
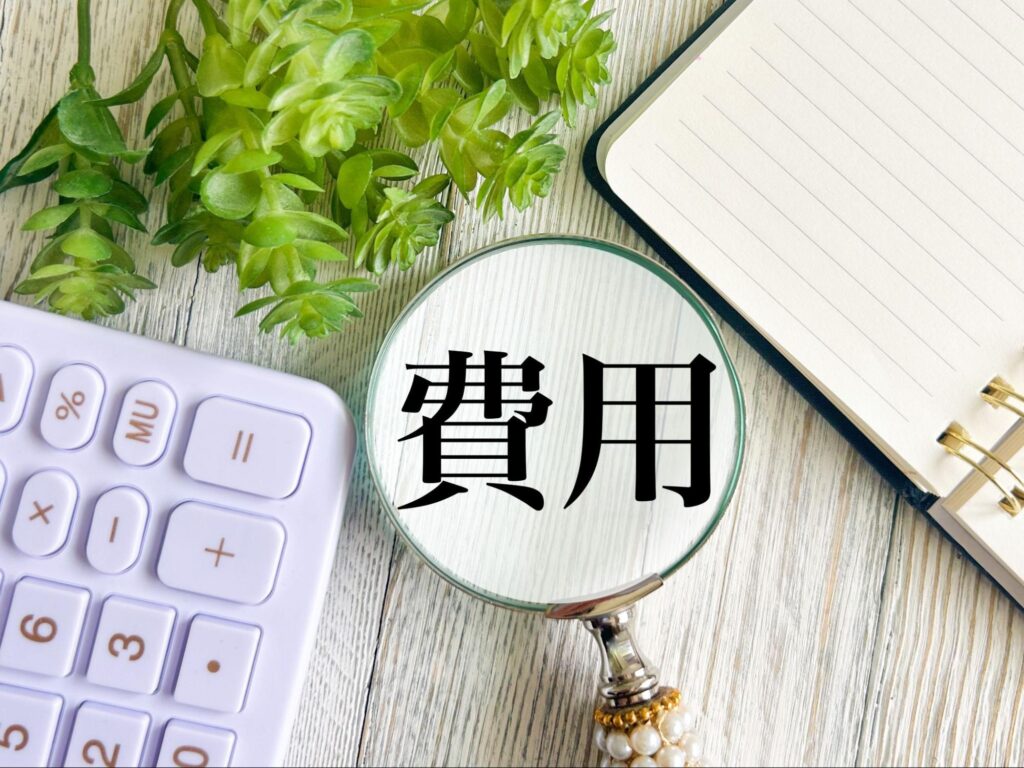
共有持分の移転登記の際は、多種多様な費用が発生する可能性があります。ここからは、共有持分の移転登記で発生する費用について解説します。共有持分の移転登記を行う際は、事前に「どれくらいの費用がかかるのか」を正しく理解しておきましょう。
登録免許税
登録免許税とは、共有持分を移転する際に法務局に納める税金です。売買や贈与、相続などのケースによって税率や課税標準が異なります。売買の場合は不動産の評価額に対して2%が課税されます。移転の原因によっては軽減措置が適用されることもあります。
(参考:国税庁「登録免許税のあらまし」)
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した際に発生する都道府県税で、取得後半年〜1年以内に課税通知書が届きます。課税額は評価額の3%が基本ですが、居住用や一定の条件を満たす場合は軽減措置が受けられる可能性があります。相続で取得した場合には、非課税となるため覚えておきましょう。
(参考:総務省「不動産取得税」)
印紙税
印紙税は、売買契約書や贈与契約書など、文書を作成する場合に課される税金です。契約金額に応じて税額が決まり、数百万円〜数千万円の売買契約では1万円〜数万円程度の収入印紙を貼付する必要があります。電子契約の場合、印紙税が不要になることもあります。
(参考:国税庁「印紙税」)
相続税
共有持分を相続で取得する場合には、被相続人の財産全体に対して相続税がかかります。共有不動産の評価額は通常、路線価などを基に按分して算出されます。適用要件は厳しいですが、配偶者控除や小規模宅地等の特例などを利用すれば、相続税が軽減できるケースも多いです。
(参考:国税庁「相続税」)
譲渡所得税
売却によって利益が出た場合は、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。所有期間が5年を超える不動産を売却した場合は長期譲渡所得となり、税率が下がるのが特徴です。取得費や譲渡費用を差し引いて計算されます。
(参考:国税庁「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」)
贈与税
共有持分を無償で他人に渡す贈与にあたる場合は、贈与税が発生します。基礎控除額は年間110万円までで、それを超えると課税されます。親から子に共有持分を贈与する場合は、相続時精算課税制度を活用すると、負担の軽減が可能です。
(参考:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)
司法書士への費用
登記申請を専門家に依頼する場合は、司法書士への報酬が発生します。費用は案件の内容や地域によって異なりますが、数万円〜十数万円程度が一般的です。金銭面の負担はかかってしまいますが、書類作成や登記所とのやり取りを一任できるため、一般的には司法書士を利用するケースが多いです。
土地家屋調査士への報酬
登記に伴って測量や建物の表示登記などが必要な場合には、土地家屋調査士への依頼が必要になります。未登記の建物や地目変更を伴う場合に発生し、費用は数万円〜数十万円が相場です。
必要書類の取得費
住民票、印鑑登録証明書、固定資産評価証明書など、公的書類の取得にはそれぞれ数百円〜千円程度の費用がかかります。手続きに必要な書類を揃える際に、郵送費が発生する可能性もあります。
共有持分にかかる税金一覧!計算方法や控除制度もセットで徹底解説
共有持分の移転登記を行わないとどうなる?
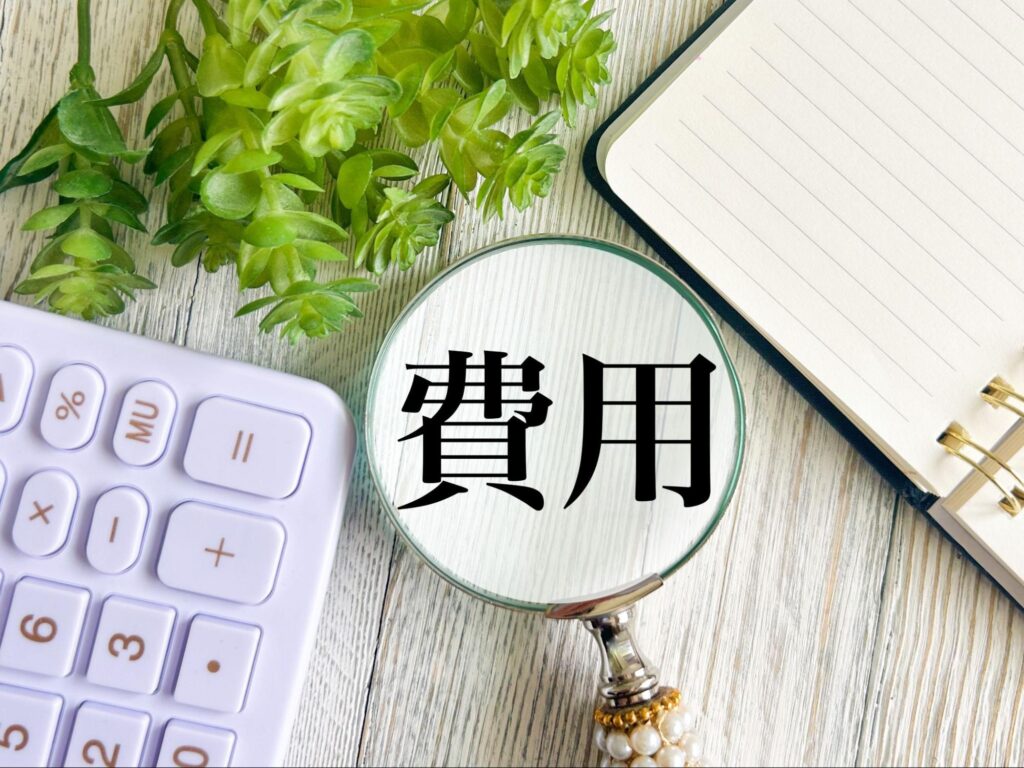
共有持分の移転登記は「名義変更」にあたる手続きです。そのため、正しく実施しなければ様々なリスクが発生する可能性があります。ここでは、共有持分の移転登記を行わなかった場合に生じる問題について解説するので、しっかりとチェックしてください。
第三者に所有権を主張できない
不動産の登記制度は、「誰がどの不動産をどれだけ所有しているのか」を公に示すためのものです。売買や贈与が成立していたとしても、登記をしていなければ、その権利を第三者に対して主張できません。
自分が買い取ったつもりの共有持分が、登記上はまだ旧所有者のままであれば、その旧所有者が他人に勝手に売却した場合でも、権利が主張できない可能性があります。「契約書があるから大丈夫」と思っていても、トラブルに発展するケースは少なくありません。
トラブルや訴訟リスクが増す
登記をしないまま時間が経つと、不動産の所有者が曖昧な状態になり、後々のトラブルの原因になります。例えば、他の共有者が知らないうちに第三者に持分を売却した場合、登記がなければ自分の主張が通りにくくなります。
相続や離婚などのタイミングで、口約束の取り決めが原因で紛争が発生するかもしれません。訴訟に発展すれば時間がかかるだけでなく、金銭面の負担も発生してしまいます。精神面の負担も大きいため、登記は必ず行うようにしましょう。
税務処理や不動産取引に支障が出る
不動産の名義が登記簿上と一致していないと、税務手続きが複雑になります。固定資産税の通知が旧所有者に届き続けたり、譲渡所得税の申告で必要な証明書が揃わなかったりといった問題が発生する可能性があります。
また、登記が完了していない不動産は売却が難しくなりがちです。不動産の活用や処分をスムーズに行うためにも、早めの登記は欠かせません。
共有持分の移転登記を自分で行う手順

共有持分の移転登記は手続きが複雑で時間がかかります。しかし、司法書士に依頼せずに自分で登記を行うことも可能です。ここでは、共有持分の移転登記を自分で行う際の手順について紹介します。自分で対応したいと考えている方は、参考情報としてお役立てください。
必要書類を揃える
登記の根拠となる「登記原因証明情報」は、登記申請時に必ず添付しなければならない書類です。登記原因証明情報には、どのような事情で持分が移転したのかを法務局に対して明らかにする役割があります。
不備があると登記が却下されたり、補正を求められたりする可能性があるため、記載内容や書式にも十分注意が必要です。持分移転登記別の代表的な添付書類は、以下の通りです。
| 登記の原因 | 必要書類の例 |
| 売買 | 売買契約書の写し |
| 贈与 | 贈与契約書の写し |
| 相続 | 遺産分割協議書 相続関係説明図 戸籍謄本(被相続人および相続人) |
| 財産分与 | 離婚協議書 調停調書または審判書の写し |
登記原因証明情報は登記申請の根拠となるため、不備があると受理されない可能性があります。記載内容や書類形式に問題がないか、事前にチェックしておくことが重要です。
登録免許税を計算・納付する
登記を自力で行う場合でも登録免許税は必須です。金額を正しく計算し、必要な分の収入印紙を法務局または郵便局などで購入し、登記申請書に貼り付けて納付します。ミスがあると受付自体ができなくなるため、税率や評価額の確認はしっかり行いましょう。
法務局に登記申請する
書類が揃って登録免許税も納付できたら、管轄の法務局に申請します。原則は窓口持参または郵送による受付で、申請書類一式に不備がないかが審査されます。登記は「通ったら終わり」ではなく、登記完了証や新しい登記識別情報を受け取って初めて完了となります。
登記内容や記載ミスによる補正通知が来るケースもあるため、申請後もしばらくは連絡が取れる状態にしておきましょう。
共有持分の一部移転登記はやめた方がいい?注意点や費用についてわかりやすく解説
共有持分の移転登記を行う際の注意点

共有持分の移転登記を行う際は、4つのポイントに注意する必要があります。それぞれ詳しく解説しますので、共有持分の移転登記を行う際は、必ずチェックするようにしてください。
手続きが複雑なためミスが起こりやすい
共有持分の移転登記は、通常の不動産登記と比べて提出書類や記載内容が多く、手続きが煩雑です。売買・贈与・相続といった登記原因によって必要書類や記載方法が異なり、些細なミスでも登記が却下されることがあります。
持分の割合や他の共有者との関係性も登記内容に大きく関わるため、念入りに確認しながら手続きを進めることが大切です。
司法書士事務所によってかかる費用が異なる
登記手続きを司法書士に依頼する場合、その報酬は事務所によって異なることがあります。登記の難易度や案件の規模、地域による物価差などが影響し、数万円から十数万円の幅があるため、複数の事務所で見積もりを取って比較するのがおすすめです。
また、報酬だけでなく、対応の丁寧さや書類取得のサポート体制も選定のポイントになります。
共有持分移転登記に関係する当事者を正しく把握できない場合がある
共有不動産の場合、登記簿に記載されている持分所有者全員が関係者となります。しかし、「登記簿が古いものである」「相続登記が未了のまま放置されている」といったケースでは、実際の共有者が不明だったり、亡くなっている共有者の相続人が登記されていなかったりします。
こうした場合には、相続登記の手続きから着手する必要があり、時間も費用も余分にかかる可能性があるので注意しましょう。
登記の理由によって申請者が異なる
移転登記の申請者は、登記の原因によって変わります。例えば「売買」による登記の場合は買主が申請人となるのが一般的ですが、「贈与」や「相続」の場合には受贈者や相続人が申請することになります。
申請人の誤認によって手続きが進まないケースもあるため、登記原因を明確にしたうえで、誰が申請を行うべきかを事前に整理しておくことが大切です。
「ワケガイ」なら共有持分のみでも買取いたします!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や複雑な権利関係を抱える不動産を専門に扱う買取サービス「ワケガイ」を運営しています。
「他の共有者と連絡が取れない」「持分だけ売りたいが買い手が見つからない」といったケースでも、全国対応・最短即日での買取が可能です。法律や税務の問題が絡む場合も、提携する専門士業と連携しながらサポートいたします。お気軽に無料査定をご活用ください。
共有持分移転費用は高額になるケースもあるので注意!

共有持分の移転登記には、登記原因や方法に応じて多様な費用がかかります。固定資産税評価額を基準とした登録免許税は金額が大きくなりやすく、加えて税務上の課税(譲渡所得税や贈与税など)が発生するケースもあります。
登記を専門家に依頼する場合は金銭的な負担がかかりますが、知識がないまま自力で手続きを進めると、申請ミスや補正によってかえって時間や費用がかさむことも珍しくありません。そのため、なるべく自力で対応しようとはせずに、専門家に相談して手続きを進めましょう。