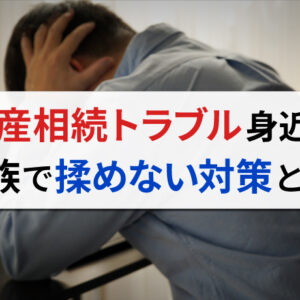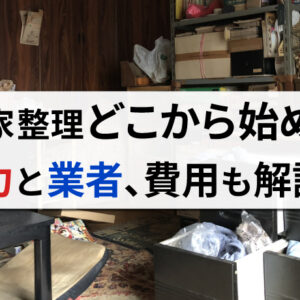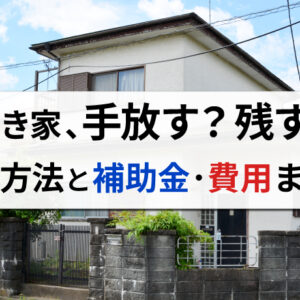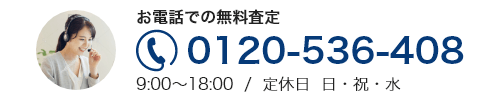について今すぐご相談できます。
お電話する
日本の土地取引や土地の形成には、様々な背景や事情が絡んでいます。特に、「囲繞地」と呼ばれる土地は四方を土地に囲まれた袋地を取得し、生活拠点として活用する場合には、該当する物件から公道に出るために囲繞地通行権を設定する必要があります。
本稿ではそんな囲繞地の通行料について、通行料の相場や囲繞地通行権が無償になるケースについて解説しますので、ぜひお役立てください。
目次
囲繞地通行権とは
袋地に隣接している土地を「囲繞地」と称します。対する「袋地」とは、四方を他の土地に囲まれ、公道に直接接していない土地を指します。
囲繞地通行権は、袋地の住人が公道へと出る際、囲繞地を利用して通行することができる権利。この権利は、日本の民法において明確に定められており、具体的には210条から213条が関連する規定として存在しています。
====================
【民法第210条】
1、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通 行することができる。
2、池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
【民法第211条】
1、前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2、前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる
【民法第212条】
第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。
【民法第第213条】
1、分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2、前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
====================
通行料の設定で必要な「囲繞地通行権の契約」
囲繞地通行権は、袋地の所有者にとって重要な権利として民法によって保護されています。ただし、この権利を行使する際には、囲繞地の所有者への通行料の支払いが必要となることもあり、それは民法第212条により規定されています。
その通行権を実際に行使する場合、囲繞地の所有者の生活の不便を考慮し、以下のような項目を含む契約を双方の間で結ぶことが望ましいでしょう。
- 通行料
- 通行する範囲
- 通路の位置と幅
- 通行する時間帯
- 通行方法
長い期間にわたり契約なしで無償で通行していた場合、通行料を後から請求することは困難です。したがって、囲繞地の所有者として、通行料を正式に受け取る意向がある場合、きちんとした契約書を結ぶことを強く推奨します。
囲繞地の通行料の算出方法
囲繞地を利用して通行する権利、すなわち囲繞地通行権を行使する際、袋地のオーナーは通行料を囲繞地の所有者へ支払う義務が生じます。これは日本の民法によって規定されています。
しかしながら、民法内では「通行料の具体的な金額」をどう設定すれば良いのかに関する詳細な基準は明示されていません。そのため、通行料の金額は事例ごとの状況や双方の話し合いによって決められることが一般的です。
通行料を設定する前のステップとして、袋地のオーナーは囲繞地の所有者と協議を進め、「どの部分を通路として使用するか」や「通路の幅をどれくらいにするか」などの基本的な取り決めを行うことが求められます。
このような契約においては、通常、「賃貸借契約」や「使用貸借契約」の形式が取られます。具体的な契約内容として、以下の点について合意する必要があります。
- 通行料
- 通行する範囲
- 通路の幅・位置
- 通行する時間帯
- 通行の方法
- 通行契約の期間
以上を踏まえた上で、囲繞地の通行量を算出する方法としては以下の3パターンが考えられます。
- 計算方法①:近隣の相場から算出する
- 計算方法②:近隣の駐車場から算出
- 計算方法③:土地鑑定評価を基準にする
以下より、個別にみていきましょう。
計算方法①:近隣の相場から算出する
「近隣の相場を参照しての算出」は、囲繞地通行権に関連する通行料を設定する際の主流な方法として知られています。
このアプローチには、2つの方法が存在します。1つ目は、「近隣に同様の囲繞地が存在する場合」に、その地域での通行料の実態を基に設定する方法。もし、直接的な比較地点が見当たらない場合でも、宅建士や土地家屋調査士といった専門家への相談を通じ、参考事例を得ることが可能です。
通行料に関する協議が困難な場面で、裁判所が介入するケースでも、一般的には近隣の事例が参考にされるケースも多々あります。
もう1つは、「近隣に明確な通行料の基準がない場合」です。このケースでは、不動産鑑定士に評価を依頼し、得られた評価額を通行料の基準とする方法がとられます。ただし、専門家による評価は、費用や時間がかかるため、早めに手続きを行いましょう。
計算方法②:近隣の駐車場から算出
近隣の相場を調査するには専門家の助けが必要となり、そのためのコストが発生します。そこで、より簡便な方法として、近隣の駐車場料金を参考にするアプローチが取られることもあります。
最寄りの月極駐車場の料金を基準に、通行の幅や条件を考慮して通行料を決定する方法。一般的には、通行路の幅は建築基準法で定められた2mが基準となります。この幅は、多くの駐車場の車両1台分のスペースとほぼ同じであるため、参考にしやすいのが特徴です。
計算方法③:土地鑑定評価を基準にする
適切な通行料を導き出すもう一つの方法として、不動産鑑定士に土地の鑑定評価を行ってもらい、その結果を基準にするアプローチがあります。この方法での算出は、土地価格と直接リンクするため、鑑定額が高ければ、それに応じた通行料を設定できることが期待されます。
しかしながら、通行料に明確な相場が存在しないため、最終的な判断は難しい場合もあります。また、鑑定評価はコストが高く時間もかかるため、余裕をもって検討しなければなりません。。
囲繞地通行権が無償となるケース
囲繞地通行権は無償となってしまうケースがあります。具体的には、以下のとおり。
- 元から通行料が無料であった
- 分筆や譲渡で袋地となった
- 共有物分の分割処理により袋地となった
- 競売のかけられて袋地となった
次項より、個別にみていきましょう。
元から通行料が無料であった
土地が相続や売買契約を経て新たな所有者に移ったとしても、以前から袋地の通行が無料で行われていたならば、その無料の通行状態は継続されます。
このシチュエーションでは、「囲繞地通行権」ではなく「通行地役権」として認識されます。事前の口頭合意だけで十分であり、以前からの無料通行状態が保持されるので、同じ条件での通行が可能です。
分筆や譲渡で袋地となった
もともと公道に面していた土地が、分筆や譲渡を経て部分的に他者の所有となり、その結果袋地として存在するようになった場合、袋地のオーナーは囲繞地を通行する権利を無償で主張できます。
この状況下では、囲繞地のオーナーが通行料を要求することはできません。これは民法第213条に基づいています。しかし、もし袋地の所有者が通行料を支払う意向があり、双方がその合意に至るのであれば、その合意が尊重されます。
共有物分の分割処理により袋地となった
複数の権利者が共有の土地を所有していたが、後にそれを分割し、その結果として袋地が発生した場合も、囲繞地を通る際の通行料は基本的には発生しません。
土地が共有から分割された際に、囲繞地通行権が誕生することとなり、民法第213条により通行料は無料とされます。
ただし、双方が通行料の支払いに関して合意することは可能。しかしながら、共有権を有していたのは親族同士であることが多く、実際に通行料に関する交渉が行われるケースは稀です。
関連記事:袋地の不動産は再建築できない? 袋地のデメリットと対処法を解説
競売のかけられて袋地となった
土地が競売の結果として袋地になった場面においても、囲繞地を通行する際に通行料を支払う必要は基本的には発生しません。
袋地が競売を通じて成立した場合も、民法第213条に基づき、通行の際に無償での囲繞地通行権が保証されます。これにより、袋地から公道への移動がスムーズに行われることが確保されています。
関連記事:不動産競売とは?入札完了までの流れやリスクをわかりやすく解説
まとめ
袋地に居住する場合、日常生活を滞りなく送るためにも囲繞地通行権は不可欠となります。囲繞地を通行する際の通行料については近隣の事例をもとに算出するのが、袋地が誕生した経緯によっては無償になる可能性もあります。
もし、通行料の支払いについて不安がある場合は、外部専門家のサポートも検討しましょう。
本ブログで情報発信を行っている「ワケガイ」は、訳あり物件を積極的に買い取っている専門業者です。所有物件についてお悩みの方は、訳あり物件の買取に特化したワケガイに、ぜひお問い合わせください。
| 運営団体 株式会社ネクスウィル 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 |