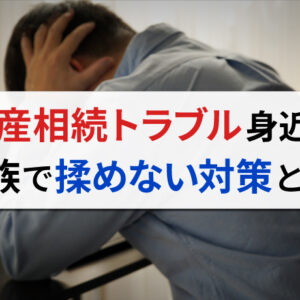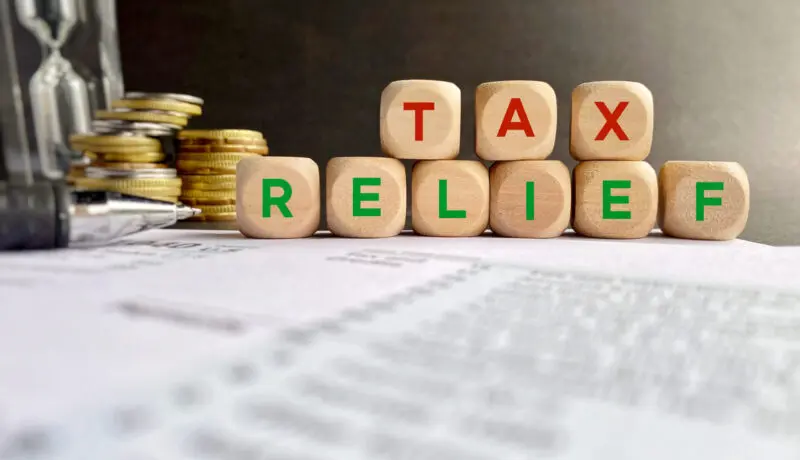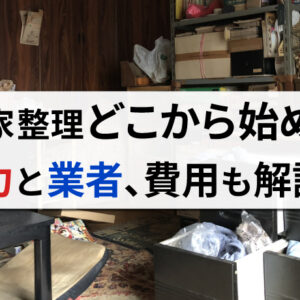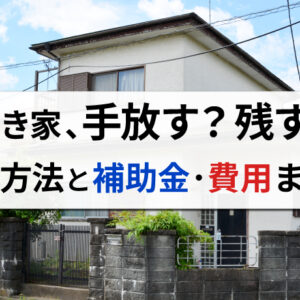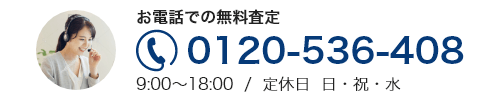について今すぐご相談できます。
お電話する
不動産を相続することは珍しいことではありません。大体の場合がプラスの遺産となることでしょう。しかし、相続した不動産が再建築不可物件だった場合、マイナスの遺産となってしまうことがあります。
そこで今回は、再建築不可物件だと知らずに相続してしまうことのないよう不動産が再建築不可物件かどうか調べる方法とそうした不動産の相続を回避する方法をご紹介します。
相続した際の手続き方法や対処法もあわせて解説しますので、すでに再建築不可物件を相続した方もぜひご一読ください。
目次
相続予定の不動産が再建築不可物件かどうか調べる方法
相続予定の不動産が再建築不可物件かどうか分からない場合も多いでしょう。当該不動産が再建築不可かどうか調べる方法としては、次のものがあります。
- 不動産業者に確認する
- 役所の建築課に確認する
それぞれ、詳しくみていきましょう。
不動産業者に確認する
まず、その不動産を購入した業者、または売却を検討している場合は売却予定の不動産業者に問い合わせるのがよいでしょう。
これらの専門家は物件の歴史や制限について詳しい情報を持っているケースが多々あります。
役所の建築課に確認する
地域の役所、特に建築課や建築指導課では、不動産に関する詳細な情報を提供してくれます。再建築不可物件かどうかを確認するためには、登記簿謄本や建物図面などの必要書類を持参する必要があります。
これらの書類は法務局で入手可能で、オンラインでの手続き後、郵送で受け取れます。ただし、必要な書類は自治体によって異なるため、訪問前に事前に確認することが重要です。
関連記事:再建築不可物件の調べ方とは?必要書類や再建築できない場合の対応方法を解説
再建築不可物件を相続するデメリット
万が一相続した不動産が再建築不可物件だった場合、どのようなデメリットが考えられるのでしょうか。具体的には、以下のとおり。
- 建て替えができない
- 売却しづらい
- 固定資産税などの費用がかかる
- メンテナンスの手間がかかる
- 自分の子どもや孫に影響を及ぼす可能性も
それぞれ、個別にみていきましょう。
建て替えができない
再建築不可物件は、一度解体すると再建が不可能な物件を指します。そのため、老朽化や災害で住めなくなった場合、新たに建物を建てることができず、居住の選択肢が失われます。
売却しづらい
再建築不可の性質上、このような物件の市場価値は通常よりも低くなりがちです。結果として、買い手が見つかりにくく、もし売却できたとしても周辺の不動産価格よりもかなり低い価格での取引になる可能性も高いでしょう。
その他、固定資産税やメンテナンスの費用負担、将来の世代への影響も考慮する必要があります。
固定資産税などの費用がかかる
不動産所有者は、再建築不可物件であっても固定資産税を支払う義務があります。これは毎年1月1日の時点での所有者に課税されます。さらに、地域によっては都市計画税の支払いも必要になることがあります。
税金の支払いだけでなく、建物の修繕や損害賠償費用などの追加費用が発生する可能性もあります。例えば、物件の構造物が破損し、それにより第三者に損害を与えた場合、その責任として修繕や賠償責任を負うことになります。
メンテナンスの手間がかかる
空き家として放置された不動産は、周辺住民に迷惑をかける原因にもなり得ます。不法投棄の対象となることもあり、草刈りや木の剪定などの定期的なメンテナンスが必要になることもあります。
これらの手入れは時間と労力を要する上、コストもかかる可能性が懸念されるでしょう。
自分の子どもや孫に影響を及ぼす可能性も
再建築不可物件は、将来の世代にも影響を与える可能性があります。所有者が変わるにつれて、物件の売却がさらに困難になることが予想され、結果的に子孫に経済的な負担や管理の責任を与えることになりかねません。
相続前に再建築不可物件だとわかっている場合の対処法
相続前の段階で(相続予定の)不動産が再建築不可物件だとわかっているのであれば、適切に対処しましょう。具体的には、以下の方法が有効です。
- 遺産分割協議をする
- 相続放棄をする
次項より、詳しく解説します。
遺産分割協議をする
遺言書が存在しない場合、相続人全員で遺産の分割方法について協議する必要があります。協議の前には、遺産の評価額を算定し、被相続人の財産や負債を記した財産目録を作成することが有効。
この過程で、不動産の価値や将来にわたる管理責任についても考慮する必要があります。
協議後は、全員の実印が押された「遺産分割協議書」と印鑑証明書を提出します。ただし、協議書には全相続人の同意が必要で、一部の相続人が反対する場合や連絡が取れない場合は、協議は成立しません。
相続放棄をする
相続放棄は、被相続人の財産や負債を一切承継しない選択を意味します。この手続きを行うことで、相続人は最初から相続権がなかったかのように扱われ、再建築不可物件を含む相続財産の承継を避けられます。
相続放棄には期限が設定されており、「相続を知った日から3ヶ月以内」に手続きを完了する必要があります。必要書類は「相続放棄申述書」などで、これを家庭裁判所に提出し、受理されると放棄が成立します。
自分で手続きする場合の費用は数千円程度ですが、手間がかかるため、専門家に依頼する場合は数万円の費用が発生することもあります。
相続放棄を選択すると、不動産だけでなく、その他の財産や借金などの相続も放棄することになります。これには車や証券、保険など、他の資産価値があるものも含まれます。プラスの遺産が多い場合、放棄するかどうかを慎重に考慮することが重要。
相続放棄を行うと、次に相続権がある人に相続権が移ります。例えば、夫が亡くなり、妻と子が相続人の場合、妻が放棄すると、相続権は夫の両親に移ることになります。そのため、相続権の移動を事前に関係者に伝えるようにしましょう。
代償分割
代償分割は、1人の相続人が財産を取得し、その人が他の相続人に代償金を支払うことで遺産を分割する方法です。これは特に、現物分割が困難な場合に適用されます。
例えば、兄弟のうちの1人が再建築不可物件を相続し、他の兄弟に代償金を支払うという形です。
代償分割を行うためには、相続する財産を取得する人が代償金を支払う能力を持っていることが必要。もし再建築不可物件を相続する兄弟(上記の例では長男)が代償金を支払う能力がない場合、この方法は適用できません。
したがって、代償金を払える財力の有無が、代償分割を検討する際の重要な前提条件となります。
換価分割
換価分割は、遺産を売却し、得た金額を相続人間で分割する方法です。特に再建築不可物件のような不動産の場合、物理的に分割が不可能なため、換価分割が有効な手段になり得ます。
ただし、再建築不可物件は一般的な不動産市場での需要が低く、売却が困難であるケースが多々あります。
そのため、物件を現金化し、遺産分割を実現するのが難しい状況になることがあります。このような換価分割の遅延は、相続人間のトラブルの原因になりかねません。
相続する際の手続き方法
再建築不可物件を含め、被相続人の遺産を相続するのであれば手続きが必要になります。ここからは、相続に関わる諸要素について詳しく解説します。
相続税の申告
相続税は、ある人が亡くなった際、その人の財産を相続または遺贈によって引き継ぐ際に発生する税金です。「相続」は被相続人が生前に財産の分配を決めていない場合に適用されます。一方の「遺贈」は遺言書により財産の分配が明確にされている場合に該当します。
基礎控除額を超える部分にのみ相続税が課税されます。つまり、総財産の金額が基礎控除額以下であれば、相続税は発生しません。
課税対象となる財産には不動産や預貯金、株式などが含まれますが、一定の条件下ではこれらの財産が課税対象外となることもあります。
課税対象となる財産と課税対象にならない財産は、下記のとおり。
【課税対象になるもの】
- 現金や預貯金
- 株式や債券など
- 不動産(土地・建物・山林など)
- 貴金属や宝石・骨董品などの家財
- リゾート会員権やゴルフ会員権
- 著作権や特許権
など
【その他相続税がかかる財産(みなし相続財産)】
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 被相続人から生前に贈与を受けて贈与税の納税猶予特例を受けていた農地など
- 財産を取得した人が被相続人の死亡3年以内に被相続人から財産贈与を受けている場合
など
【課税対象にならないもの】
- 墓地や墓石・仏具など
- 国や公益法人などに寄附した財産
- 非課税枠内で受け取る生命保険金・死亡退職金(500万円×法定相続人数)
など
相続税は、遺産金額から基礎控除額を引き、残りの金額の割合に応じた税率を掛けて算出します。基礎控除額と税率などは下記のとおりです。
【基礎控除額】
- 3000万円+(法定相続人数×600万円)
【税率と控除額】
- 法定相続分に応ずる取得金額1,000万円以下:税率10%(控除なし)
- 法定相続分に応ずる取得金額3,000万円以下:税率15%(控除50万円)
- 法定相続分に応ずる取得金額5,000万円以下:税率20%(控除200万円)
- 法定相続分に応ずる取得金額1憶円以下:税率30%(控除700万円)
相続税の納付期限は、相続発生を知った日の翌日~10ヶ月以内です。
期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税といったペナルティがかかってしまうほか、相続税に関する特例が受けられなくなる可能性があります。
相続税は自ら申告しなくてはいけません。管轄の税務署に申告書を提出しましょう。申告書はホームページからダウンロードできます。
相続登記
不動産の所有者が確定したら相続登記をする必要があります。不動産を売却するとしても、相続登記は必ず行わなければいけません。なぜなら、死亡した方の名義で不動産を売ることはできないため。
相続登記は法務局で行います。「いつまでに申請しなければいけない」という期限はありませんが、早めに登記した方がよいでしょう。
相続後に再建築不可物件だとわかった場合の対処法
相続後に再建築不可物件だとわかった場合、以下の対応が求められます。
- リフォームをして住むか売却する
- 隣地の所有者に売却する
- 隣の土地を購入して再建築する
- セットバックをして再建築する
- 建築基準法第43条ただし書き道路の申請をして再建築する
- 専門の買取業者に売却する
次項より、詳しく解説します。
リフォームをして住むか売却する
再建築不可物件は、解体して再建築することはできませんが、リフォームを通じて利用価値を高めることは可能です。内装や外装の改修、最新設備の導入などにより、住み心地を向上させることができます。
リフォームによって物件の状態を改善すれば、売却時にも買い手がつきやすくなる可能性があります。
隣地の所有者に売却する
再建築不可物件は、通常の不動産市場では売却が難しいことが多いですが、隣接する土地の所有者にとっては魅力的なケースもあります。
敷地の拡大や増築を考えている隣地の所有者に売却を提案するのは有効な戦略です。
隣の土地を購入して再建築する
再建築不可の理由が敷地の幅員不足にある場合、隣接する土地を購入して敷地の幅を増やすことで再建築が可能になる場合があります。
この方法は、隣地の所有者との交渉が必要です。
セットバックをして再建築する
特定の行政庁が指定した道路に面している場合、セットバックを行うことで建築規制をクリアし、建て替えが可能になることがあります。
セットバックは建物を道路から一定の距離後退させることを指し、これによって敷地面積が小さくなるデメリットはあるものの、自治体によってはその費用を補助してもらえる可能性もあります。
関連記事:セットバックって何?物件を再建築可能な状態にするための手順を解説
建築基準法第43条ただし書き道路の申請をして再建築する
建築基準法第43条の但し書き規定により、特定の条件下では幅員4m未満の道路でも再建築が可能になるケースがあります。
これは消防車や救急車の進入が可能な空間が確保されていれば、特例として再建築が許可されるケースがあります。
この場合、地元の役所で相談し、必要書類を提出して申請することになりますが、必ずしも許可が得られるとは限りません。
関連記事:再建築不可物件の救済処置「43条但し書き」の概要をわかりやすく解説!
専門の買取業者にに売却する
一般の市場で売却が難しい場合、専門の不動産買取業者に売却する方法もあります。買取価格は市場価格より低くなる可能性がありますが、迅速な現金化が可能となり、早期解決が望めます。
関連記事:不動産売却はどこの業者にするべき?高く売るための業者選びのポイントを紹介
関連記事:再建築不可物件の買取相場はどのくらい?高値で売るコツも解説
まとめ
再建築不可物件は、無理に建て替えると違法建築となってしまうため気をつけましょう。また、リフォームは可能ですが、床面積が増える増築は不可ですので注意が必要。
再建築不可物件は制限されることが多いため、住むにしても売るにしても難しいことは事実です。相続を回避できるのであれば、それが最善といえます。
すでに相続している場合は、前述した方法の検討とあわせてプロに相談することをおすすめします。客観的な視点と法律などの観点からスムーズに対処してくれるでしょう。
本ブログで情報発信を行っている「ワケガイ」は、訳あり物件を積極的に買い取っている専門業者です。所有物件についてお悩みの方は、訳あり物件の買取に特化したワケガイに、ぜひお問い合わせください。
| 運営団体 株式会社ネクスウィル 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 |