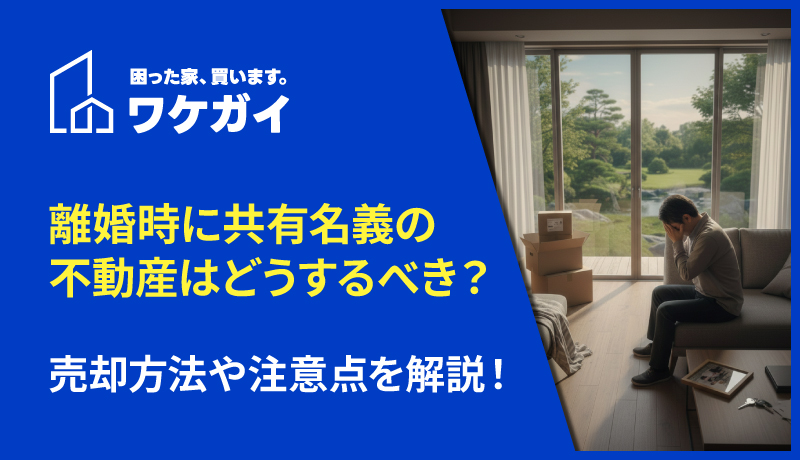こんにちは。ワケガイ編集部です。
離婚に際し、夫婦で共有していた自宅をどう扱うかは、多くの人にとって避けて通れない問題です。特に子どもの養育や生活基盤の継続を考えると、「どちらが住み続けるか」「売却すべきか」などの判断は容易ではありません。
その際、真剣に検討すべきなのが「共有名義不動産の解消方法」です。共有状態のまま放置すれば、後々の売却や管理に支障が出ることも少なくなく、トラブルの火種となりかねません。
共有不動産の扱いは、名義の整理や財産分与、税金の問題など多岐にわたります。そこで本記事では、離婚に伴う共有不動産の売却方法や代替策、注意点などについて実務目線で詳しく解説します。
目次
離婚の際は不動産の共有名義を解消すべき理由とは?
結論からいえば、離婚の際には不動産の共有状態は直ちに解消するのが望ましいといえます。その理由は主に、以下の2つが挙げられます。
- 理由①:不動産を自由に活用・処分できなくなるから
- 理由②:維持費や税金の負担が偏るリスクがあるため
次項より、詳しく解説します。
理由①:不動産を自由に活用・処分できなくなるから
離婚時に共有名義のままでは、売却・賃貸・担保設定などの重要な判断において、共有者全員の同意が必要になります。離婚後に元配偶者と頻繁に連絡を取って意思をすり合わせることは、心理的な負担になるだけでなく、現実的に不可能なケースも少なくありません。
実際には「連絡がつかない」「返信がない」「同意してもらえない」といった状況が長期化し、住宅の活用が滞ったり、売却できずにローンや維持費だけがかさむという悪循環に陥る例も見られます。子どもの学費や転居先の確保といった、新たな生活資金の調達にも影響するため、機動的な資産活用を妨げる構造自体がリスクといえるでしょう。
関連記事:不動産の共有名義はトラブルのもと? 知らないと損する注意点と解消方法を紹介
理由②:維持費や税金の負担が偏るリスクがあるため
不動産には、固定資産税・管理費・修繕費といった継続的なコストがかかります。共有者の一方がその支払いに非協力的だったり、事実上の「音信不通」となっていると、もう一方がすべての費用を負担せざるを得ない状況に追い込まれます。
名義だけ残って実質的には関与しない元配偶者に対して、費用の請求や責任の所在をめぐって争いになるケースもあり、現場では訴訟や調停にまで発展することもあります。特に物件が空き家になっている場合には、防犯・景観管理・近隣トラブルのリスクも高まり、精神的・経済的に重い負担となります。
関連記事:共有名義の「固定資産税」は誰が払うべき? 滞納した場合や支払いたくない場合はどうなる?
離婚時に共有不動産を売却する2つの現実的な選択肢
離婚時に夫婦で共有していた不動産を手放す場合、最も現実的なのが「売却」という選択肢です。ただし、売却と一口にいっても「すべての共有者が同意したうえで不動産全体を売る場合」と「自分の共有持分だけを第三者に譲渡する場合」の2つに大別できます。
ここでは、離婚後の共有不動産の処分方法として代表的な2つの対応策について、それぞれの特徴と注意点を解説します。
選択肢①:自分の持分を元配偶者に買い取ってもらう
元配偶者が不動産にそのまま住み続ける場合、住まなくなる側が自身の持分を相手に売却し、名義を一本化するのが最もスムーズな対応です。この方法であれば、当事者同士の合意さえあれば手続きが進めやすく、不動産全体の売却に比べて負担が少ないというメリットがあります。
また、離婚時に財産分与や養育費の取り決めがある場合には、その一環として共有持分の売却代金を充てることも可能です。ただし、評価額に関して折り合いがつかないケースも多いため、専門の不動産業者に査定を依頼し、適正価格を確認したうえで交渉するのが現実的です。
選択肢②:自分の持分だけを第三者に売却する
「元配偶者が買い取りに応じない」「話し合いが難航している」などの場合、自身の共有持分のみの第三者への売却も検討しましょう。法的には、共有者の同意がなくても自分の持分だけを売ることは認められています。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)
ただし、この方法は共有持分だけでは利用価値が限定されるため、通常の不動産市場では買い手がつきにくく、買取価格も下がる傾向がある点には留意が必要です。また、売却後も共有状態は続くため、新たな共有者(持分買取業者など)と元配偶者との間に新たなトラブルが生じるリスクもあります。
したがって、この選択肢を検討する際は、共有持分の買取に特化した専門業者を活用するなど、慎重な対応が必要です。
関連記事:共有持分の親族間売買は可能?やり方と注意点を解説
関連記事:共有持分の不動産を売却する方法とは?売却費用やよくあるトラブルを紹介!
離婚で共有不動産を売却する際の注意点
離婚によって共有不動産を売却する場合、単に「家を売ってお金を分ければよい」という話では済みません。住宅ローンが残っているか、登記の名義は誰か、利益の分配方法はどうするのか。手続きの途中でトラブルになることも多く、安易に進めると損をしてしまう可能性もあります。
ここでは、離婚後に共有名義の不動産を売却する際に押さえておくべき注意点を具体的に解説します。
売却に伴う税金用のキャッシュも残しておく
不動産売却によって利益(譲渡益)が出た場合、「譲渡所得税」が課されます。離婚に伴う売却であっても、税務上は通常の不動産譲渡と同じ扱いとなるため、利益があれば税負担が生じます。
(参考:国税庁「土地や建物を売ったとき」)
たしかに、「居住用不動産の3,000万円特別控除(マイホームを売ったときの特例)」という制度もあり、一定の条件を満たせば譲渡益を大幅に控除できる可能性はあります。ただしこの特例は、譲渡する側が売却直前までその家に住んでいたことが前提で、離婚後に既に家を出ている・別居していたといった事情があると、適用されないケースも少なくありません。
(参考:国税庁「マイホームを売ったときの特例」)
さらに、共有名義の場合には共有者ごとに申告・課税が発生します。つまり、持分を売却した各人が個別に確定申告を行い、それぞれ納税義務を負うことになります。
そのため、売却後に手元に残る現金のすべてを生活費などに充ててしまうと、翌年の納税資金が足りなくなるおそれがあります。たとえ適用要件を満たしている場合でも、制度の活用には税理士等による事前確認や正確な申告が不可欠です。
住宅ローンが残っている場合、売却には制限がある
住宅ローンが残っている不動産は、原則として金融機関の承諾なく売却できません。抵当権が設定されている場合は、残債を完済しなければ登記変更もできないため、売却益がローン残高を下回ると手続きが頓挫する可能性があります。
離婚後に「売ろうとしても売れない」とならないよう、まずはローンの残債確認と金融機関との協議が必須です。
売却益の分配は「共有持分」ではなく「財産分与」で決まる
婚姻期間中に取得した共有不動産は、たとえ登記上の持分割合が「1:9」であっても、原則として2分の1ずつ分けるのが財産分与の考え方です。登記上の割合と財産分与の割合が異なることに違和感を覚える人も多いのですが、裁判実務でもこの扱いが一般的です。
「持分どおりに分ける」と誤解して交渉すると、不公平感やトラブルの元になります。専門家による中立的な試算を挟んだうえで、分配割合を協議しましょう。
関連記事:離婚時に共有持分はどのように財産分与したらいい?取り扱いの方法を詳しく解説
売却以外の共有不動産の解消方法
離婚に伴って共有不動産を整理する方法は、売却だけではありません。相手との関係性や家の利用状況、感情的な要素などを踏まえると、「売らない選択」が現実的となるケースもあります。
売却を前提としない共有名義の解消手段としては、次の3つが現実的な選択肢です。
- 方法①:共有持分の贈与
- 方法②:共有持分の放棄
- 方法③:家庭裁判所への共有物分割請求の申し立て
それぞれ個別にみていきましょう。
方法①:共有持分の贈与
元配偶者が住宅に住み続ける意向を持ち、自身は完全に関与を断ちたい場合などには、持分を贈与して名義を一本化することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
ただし、持分の贈与は「無償による財産の移転」と見なされ、贈与を受けた側に贈与税が課税される可能性があります。贈与税の非課税枠を超える場合は、申告と納税が必要になるため、税理士への相談が推奨されます。
また、贈与という形であっても、相手がそれを受け入れない限りは成立しません。後から金銭的な請求をめぐってトラブルに発展することもあるため、合意内容を文書化しておきましょう。
関連記事:親子共有名義の不動産は生前贈与するべき?注意点について徹底解説!
方法②:共有持分の放棄
自分の持分を「放棄する」ことで、共有状態を解消しようとする方もいます。これは法的には「共有持分の権利を放棄し、他の共有者の単独所有にする」手続きであり、理論上は成立します。
ただし、放棄は一方的にできるものではなく、放棄の意思表示と、相手がそれを承諾することが必要です。また、持分の放棄が贈与とみなされる可能性もあるため、贈与税の課税対象になることもある点には注意が必要です。
加えて、放棄後の物件の管理責任や固定資産税の納税義務を巡って、「放棄したのに連絡が来る」「完全に縁が切れない」といった問題が生じることもあります。そのため、名義変更や登記手続きを正確に進めておくことが不可欠です。
関連記事:共有持分を放棄した場合に発生する税金とは?
関連記事:共有持分は放棄できる?具体的な手順や発生する費用をチェック!
方法③:家庭裁判所への共有物分割請求の申し立て
話し合いでの解決が難航する場合は、家庭裁判所に共有物分割請求を申し立てることで、法的に共有関係を解消することが可能です。
この手続きには「現物分割(不動産を分けて単独所有にする)」「代償分割(片方が持分を取得し、もう片方に代償金を支払う)」などの方式があり、裁判所が当事者の事情を踏まえて合理的な解決方法を導き出します。
注意点として、裁判所による判断は必ずしも双方の希望に沿うとは限らず、調停や審判の過程で時間と労力がかかることもあります。とはいえ、協議が難航して放置されるよりは、法的に共有状態を整理できる唯一の手段であるともいえるでしょう。
離婚後も「共有不動産」に住み続けることは可能?
結論から言えば、離婚後も共有不動産に住み続けることは可能です。ただし共有名義のまま自分だけが住み続ける場合、将来的な売却や修繕の場面で元配偶者の同意が必要になるなど、意思決定の自由が制限される可能性があります。
また、固定資産税や修繕費の負担についても、居住している側とそうでない側とでトラブルに発展することがあります。
そのため「離婚後も安心して家に住み続けたい」と考えるのであれば、前述したように相手の持分を買い取って単独名義にする。あるいは財産分与として名義変更を行うといった対応は必須。
離婚時の共有不動産の買取は「ワケガイ」にご相談ください!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有名義の不動産や再建築不可物件、空き家などのいわゆる“訳あり物件”を対象にした不動産買取サービス「ワケガイ」を提供しています。
離婚に伴って不動産を処分したいと考えても、共有状態のままでは話が進まず、交渉が難航するケースも少なくありません。そんなとき、当社のような専門業者が間に入ることで、トラブルを避けながらスムーズに売却する道が開けます。
これまで他社で断られたような案件も含め、全国で多数の実績がありますので、まずはお気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
離婚により共有不動産をどう処理するかは、感情的な対立も伴いやすく、対応を誤ると将来にわたって問題を残すリスクがあります。安易に放置せず、売却・持分買取・名義変更などの具体策を早期に検討しましょう。
特に、売却による財産分与を選ぶ場合には、税務面の負担や元配偶者との調整も必要になるため、事前にキャッシュフローや実務負担を見積もっておくことが大切です。また、共有名義のまま居住を希望する場合でも、名義変更や賃貸借契約の整理といった法的手続きが求められるケースもあります。
複雑な判断が求められるからこそ、感情論に流されず、第三者の支援も視野に入れたうえで、自身にとって最適な解決方法を見出すようにしましょう。