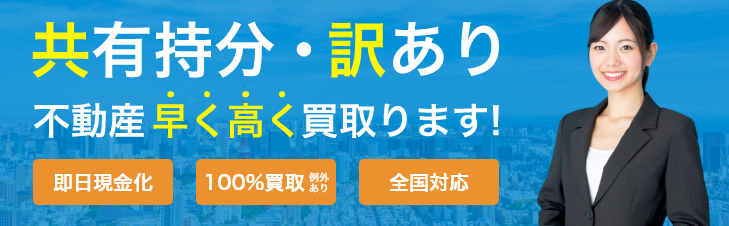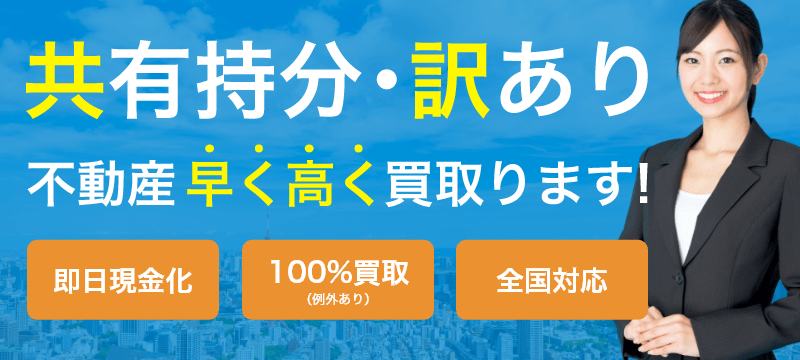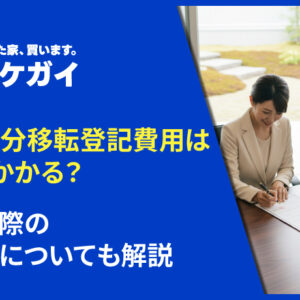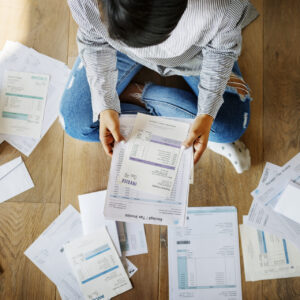こんにちは。ワケガイ編集部です。
共有名義で所有している不動産を売却しようとしたとき、共有者の一人が認知症を発症していると、思わぬ壁にぶつかることがあります。契約には全員の同意と署名が必要ですが、認知症により「意思能力」が確認できない場合、その人の分も含めた売却手続きが進められなくなってしまうのです。
「不動産を早く現金化したい」「相続の準備を進めたい」といった状況で、話が止まってしまうのは大きなストレスでしょう。とはいえ、こうしたケースでも打つ手がないわけではありません。一定の法的手続きを踏むことで、売却を実現できる可能性があります。
本記事では、共有名義人が認知症になった場合に起こる具体的な問題と、そのような状況下でも不動産を売却する方法について詳しく解説します。
目次
共有名義人が認知症になると不動産売却はとても難しくなる
不動産を共有名義で所有している場合、その一部だけでなく不動産全体を売却するには、すべての共有者の意思表示が必要です。たとえ1人が1割しか持っていなくても、同意が得られなければ契約自体が成立しません。
認知症になると、たとえ本人に売却の意思があったとしても、「法的に有効な意思表示ができない」と見なされてしまうため、売却の話し合い自体が頓挫してしまうケースが少なくありません。
さらに厄介なのは、認知症の進行具合や本人の態度によっては、どの時点から「意思能力がない」と見なされるかが曖昧になりやすいことです。不動産の売却が必要とわかっていても、後から契約が無効とされるリスクを考えると、専門家も慎重にならざるを得ません。
こうした理由から、認知症を発症した共有名義人がいると、実質的に不動産の売却は非常に困難になるのです。後戻りができない大きな取引である以上、軽視できない問題といえるでしょう。
共有名義人が認知症になった場合の対処法
不動産を複数人で共有している場合、その共有者のひとりが認知症を発症すると、名義変更や売却などの手続きが極めて難しくなります。とくに本人の判断能力が不十分な状態では、法律上の有効な意思表示ができないため、単純な合意や委任では対応できなくなるのが実情です。
このような場合には、家庭裁判所の関与を得ながら法的な代理制度を活用する必要があります。以下では、実際に取り得る対処法として「成年後見制度の活用」と「特別代理人による共有物分割請求」の2つを紹介します。
「成年後見制度」を利用して不動産全体を売却する
家庭裁判所に成年後見の開始を申請し、後見人が選任されれば、「認知症の人が所有する共有持分の売却」が可能になります。
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力を欠くようになった人の財産管理や法律行為を、代理人(成年後見人)が代わって行えるようにする仕組みです。家庭裁判所に申立てを行い、審判によって成年後見人が選任されることで制度が開始されます。
成年後見人は、司法書士や弁護士などの専門家が選ばれることが一般的です。かつては家族が後見人になるケースも多く見られましたが、近年の運用では、専門職が選任される傾向が強まっています。
成年後見制度が開始され、後見人が選ばれれば、認知症の方の共有持分を含めた不動産全体の売却も可能になります。ただし、成年後見人が売却を実施するには、必ず家庭裁判所の「個別の許可」が必要です。売却理由や金額が妥当であること、売却が被後見人の利益にかなっていることが前提となります。
仮に、共有者が死亡してしまった場合の対処法については、以下の記事でも解説してます。こちらもあわせてご覧ください。
特別代理人に依頼して「共有物分割請求」を申し立てる
認知症の共有者がいる状態では、共有不動産の売却だけでなく、持分の整理や解消そのものも困難になります。このような場合には、家庭裁判所に「共有物分割請求」の調停や審判を申し立てるという手段があります。
ただし、認知症の共有者を巻き込む形で手続きを進めるには、「特別代理人」の選任が必須です。認知症の本人のために一時的に意思決定を行える「特別代理人」を選んでもらうことで、調停や審判における手続きが進められるようになります。
なお、申立てには以下のような準備が必要です。
- 医師の診断書(認知症の程度を証明)
- 特別代理人の候補者(通常は司法書士・弁護士)の選定
- 利益相反の有無の説明(共有者間で売買が生じる場合など)
- 裁判所への申立書類一式(事案の説明を含む)
家庭裁判所は、認知症の共有者にとって不利益が生じないかを厳密に審査した上で、特別代理人を選任します。選任後は、その代理人が認知症の共有者の立場を代弁し、調停または審判の場に参加することになります。
成年後見制度を使った不動産売却の手順
以上2つの方法のうち、より現実的なのは成年後見制度を用いた不動産売却です。
そこで、ここからは共有名義の不動産を売却するために成年後見制度を利用する際の一般的な流れを4つのステップに分けてご紹介します。
- 手順①:家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行う
- 手順②:成年後見人が売却の可否を判断する
- 手順③:家庭裁判所に売却の許可を申請する
- 手順④:買い手と契約し、決済を実行する
次項より、個別にみていきましょう。
手順①:家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行う
認知症などにより共有者が意思決定できない状態にある場合、まずは「成年後見制度」の利用を家庭裁判所に申し立てる必要があります。申立てができるのは、本人の配偶者や四親等以内の親族、市区町村長などです。
申立てに必要な主な書類は以下のとおりです。
<成年後見制度の申立てで必要な書類>
- 申立書一式(家庭裁判所の指定書式)
- 本人の診断書(所定の様式)
- 住民票や戸籍謄本などの添付書類
- 財産目録や収支状況の報告書
申し立て後、家庭裁判所による調査・審理が行われ、通常は数週間から数か月で後見人の選任が決まります。
手順②:成年後見人が売却の可否を判断する
成年後見人が選任された後は、後見人が財産全体を管理する立場となります。不動産の売却に関しても、後見人が「本人(被後見人)にとって必要かつ合理的な判断かどうか」を検討する役割を担います。
具体的には、以下の観点から判断しましょう。
<売却可否の判断基準>
- 売却の目的が本人の生活や介護費用に直結しているか
- 売却後の代替住居の確保が見込まれているか
- 市場価格に見合った適正な条件か
この判断に基づいて、後見人は家庭裁判所に次のステップとなる「売却許可」の申請を行います。
手順③:家庭裁判所に売却の許可を申請する
後見人が売却を適当と判断した場合でも、実際に売却するには家庭裁判所の「個別許可」が必要です。これは、後見制度が本人の財産保護を最優先する制度であるため、売却という重要な判断に裁判所のチェックを挟む必要があるからです。
許可申請では以下のような資料を添付するのが一般的です。
<売却のために家庭裁判所に提出する書類>
- 売買契約書案
- 査定書や相場資料
- 売却理由の説明書
- 買主の情報
裁判所が妥当と認めた場合に限り、売却が許可されます。
手順④:買い手と契約し、決済を実行する
家庭裁判所の許可が下りたら、ようやく売買契約を締結し、決済を行うことができます。この際、成年後見人が売主として署名捺印を行い、本人確認も成年後見人について司法書士が実施します。
登記の際には、「成年後見人による売却」であることを示すため、登記簿にその旨が記載されます。ここまでのプロセスには、申立てから売却完了まで数か月以上かかることが多く、早期の検討と準備が重要です。
成年後見制度を使って不動産売却を行う際の注意点
成年後見制度を利用すれば、認知症などで判断能力を失った共有者がいても、不動産を売却することは可能です。しかし、この制度には特有の制約や手続き上の負担も伴います。特に、家族だけで完結できない部分が多いため、十分な準備と制度に対する正しい理解が求められます。
ここでは、成年後見制度を通じて不動産を売却する際に、事前に把握しておきたい注意点を2つご紹介します。
売却益の使途に制限がかかることがある
成年後見制度を利用して不動産を売却する場合、たとえ後見人が本人の代わりに手続きを行うとしても、売却ごとに家庭裁判所の許可を得る必要があります。これは、成年後見人による不動産処分が、本人の財産に大きな影響を与える行為とみなされているためです。
この許可申請には、「売却が被後見人の利益に資すること」を証明する資料の提出が求められます。具体的には、売却理由書や査定書、購入希望者との契約書案などを揃える必要があり、裁判所の判断によっては許可が下りないケースもあります。
また、家庭裁判所の判断には時間がかかることも多く、希望していたタイミングでの売却ができないことも珍しくありません。買主側の都合とも調整が必要になるため、交渉が成立しても、実際の契約・決済までには一定の期間を要することを前提に計画する必要があります。
こうした事情から、成年後見制度を使った売却には、専門家による事前の見通し確認と、裁判所対応に慣れた司法書士や弁護士の関与が推奨されます。
売却益の使途に制限がかかることがある
不動産売却で得た資金は、基本的に被後見人の財産として管理されます。成年後見制度のもとでは、後見人といえども自由にこの資金を使えるわけではありません。その使い道が被後見人の生活や療養、介護などに明確に資するものでなければ、家庭裁判所から承認を得られない可能性があります。
たとえば、売却益で施設の入所費用を賄うといった使途は比較的認められやすいですが、他の家族の生活費や他人名義の不動産購入資金などに充てることはできません。実際、家族の希望で売却後に別の不動産を購入しようとしても、裁判所が「被後見人にとって必要性が乏しい」と判断すれば却下されます。
このように、売却後の資金運用についても裁判所の監督が及ぶため、家族が柔軟に資金を動かせるわけではない点は理解しておくべきです。
共有名義人の認知症が軽度なときから行っておくべ対応策
共有名義の不動産をめぐる問題は、所有者の一人が認知症を発症すると一気に深刻化します。たとえば、不動産の売却や管理変更には共有者全員の同意が必要となりますが、認知機能の低下によって意思表示ができなくなれば、事実上あらゆる手続きが止まってしまいます。
そのため、本人がまだ判断能力を保っているうちに、将来のリスクに備えた対応を講じておくことが求められます。具体的には、以下のものです。
- 対応策①:認知症発症前に家族信託を締結しておく
- 対応策②:生前贈与で単独名義化を進めておく
- 対応策③:相続時の共有リスクを踏まえた遺言書を用意する
それぞれ個別に解説します。
対応策①:認知症発症前に家族信託を締結しておく
家族信託とは、将来本人が判断能力を失った場合に備えて、あらかじめ信頼できる家族に財産管理の権限を託しておく制度です。不動産を信託の対象とすることで、本人が認知症を発症した後でも、受託者がその不動産を適切に管理・処分できるようになります。
以下のようなケースでは、特に家族信託の活用が有効です。
| 状況 | 家族信託を使うことでできること |
| 本人が軽度認知症の段階 | 判断能力のあるうちに信託契約を結べる |
| 今後の売却や管理を家族に任せたい | 受託者が売却や修繕、賃貸などを対応可能 |
| 相続後の名義トラブルを避けたい | あらかじめ役割を明確にしておける |
家族信託は「本人の意思能力がある段階でしか結べない」ため、症状が軽いうちに専門家と相談しながら契約内容を詰めておくのが望ましいといえます。
関連記事:共有持分の家族信託にメリットはある?トラブル防止に繋がる必要知識を解説
対応策②:生前贈与で単独名義化を進めておく
共有名義が将来的なトラブルのもとになると考える場合は、認知症発症前に生前贈与で持分を整理しておくのも一つの手です。たとえば、兄弟で共有している不動産について、本人の持分を他の兄弟へ贈与すれば、単独名義にまとめることができます。
この対応によって得られるメリットには、以下のような点があります。
- 意思決定が速やかになる(売却やリフォームなどがスムーズに)
- 将来的な管理責任の所在が明確になる
- 相続時に新たな共有者が増えるリスクを回避できる
ただし、生前贈与には贈与税がかかる可能性があるため、金額や贈与時期によっては税負担が大きくなることもあります。事前に税理士等の専門家に相談し、計画的に進めることが大切です。
関連記事:親子共有名義の不動産は生前贈与するべき?注意点について徹底解説!
対応策③:相続時の共有リスクを踏まえた遺言書を用意する
共有名義の問題は、相続発生時の遺産分割によっても起こりやすくなります。たとえば、親が遺言書を残さずに亡くなった場合、子どもたちが不動産を均等に相続し、結果的に共有名義となってしまうケースは珍しくありません。
こうした事態を防ぐには、被相続人本人が判断能力のあるうちに、遺言書を作成しておくことが有効です。とくに以下のような観点から、遺言を準備するメリットがあります。
- 不動産を誰が相続するかを明確にできる(単独相続が可能)
- 管理や売却に関する意思を反映できる
- 共有トラブルの発生を未然に防げる
自筆証書遺言も有効ですが、誤字脱字や不備によって無効となるリスクもあるため、確実性を重視する場合は「公正証書遺言」の利用をおすすめします。相続人同士の関係性が複雑な家庭では、第三者の専門家の関与も含めて準備を進めると安心です。
関連記事:共有持分を遺言書で相続させることは可能?効力や手続きの流れを詳しく紹介
認知症の方がいる共有不動産について「ワケガイ」にご相談ください

当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり物件の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。
共有名義の不動産や、認知症の方が共有者となっている物件の売却は、通常の市場では困難を極めます。とくに、家庭裁判所の許可や成年後見制度の手続きが必要になるケースでは、買い手が見つからずに悩み続ける方も少なくありません。
ワケガイでは、こうした複雑な事情を抱える不動産でも、法的手続きを含めて一括で対応可能です。提携する司法書士や弁護士と連携し、早期の売却実現をサポートいたします。まずは状況のヒアリングから対応いたしますので、お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
共有者が認知症を発症している場合、そのままでは不動産を売却することはできません。成年後見制度を活用することで売却は可能になりますが、自由な判断が制限されるため、資産の活用や処分において柔軟性が失われる側面もあります。
そのため、認知症の進行が軽度な段階で将来のリスクを見据え、任意後見契約や家族信託といった代替手段も含めて、事前の備えを検討することが現実的です。
状況が進行してからの対応はどうしても手間や時間がかかるため、早い段階から家族で話し合いを始めましょう。