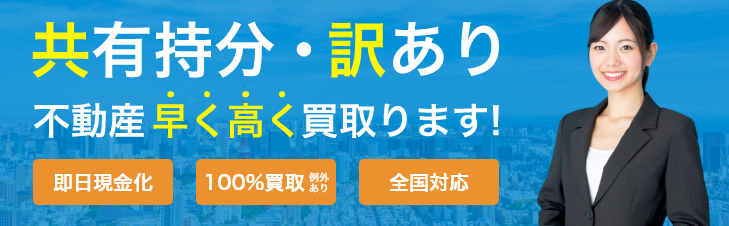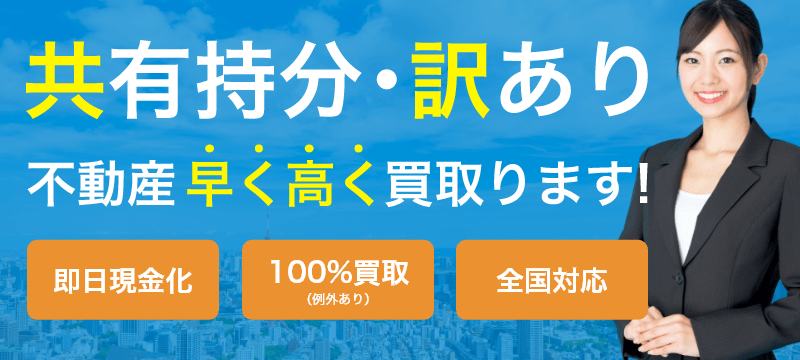こんにちは。ワケガイ編集部です。
共有名義の不動産をリフォームしようとすると、「費用をどのように負担するか」「持分と支出のバランスはどうか」など、共有者間でトラブルが発生しやすくなります。親子や夫婦といった近しい関係でも、「後から贈与とみなされて税金が発生した」「話し合いがこじれてしまった」といった事例は少なくありません。
中でも特に注意すべきなのが贈与税のリスクです。たとえ家族間で合意の上だったとしても、持分割合と異なる費用の負担をすると、その差額が「贈与」とみなされ、税務署から課税される可能性があります。
本記事では、共有持分の不動産をリフォームする際に押さえておくべきルールと、贈与税の計算例やなるべく費用を安く抑える方法について解説します。
目次
共有持分のリフォームに関する基本ルール
共有名義の不動産をリフォームする際は、単独名義のケースと比べて注意すべき点が多くあります。とくに、所有者が複数いることで「誰の同意が必要か」「どこまでの工事なら単独で可能か」といった判断が複雑になります。以下では、共有持分不動産におけるリフォームの基本的なルールを解説します。
軽微な修繕なら単独でも可能
共有物に対して、雨漏りや水道管の補修など、建物の維持に必要な最低限の修繕は、共有者の一人が単独で行うことが可能とされています。これは、民法第252条に基づく「保存行為」とされるためです。
<単独で可能なリフォーム例>
- 壁紙の張り替え
- 配管の修理
- 雨漏り対策
など
ただし、その工事が他の共有者の権利や居住に影響を及ぼす内容であれば、事前の相談や同意を得るのが望ましいでしょう。
大規模なリフォームは共有者全員の同意が必要
一方、間取りの変更、増築、建て替えなどの大規模な工事を行うには、共有者全員の合意が必要です。これらは「変更行為」に該当し、1人の判断で勝手に進めると、法的なトラブルになる可能性があります。
<全員の同意が必要なリフォーム例>
- 2階を増築する
- 台所を移設する
- 外壁をすべて張り替える
など
特に所在不明の共有者がいる場合や、同意が得られない場合は、家庭裁判所に対する「共有物変更の訴え」や「不在者財産管理人の選任」などの法的手続きを検討する必要があります。
贈与税とは
贈与税は、誰かから資産を無料や低額で譲受した際に発生する税金です。特に不動産に関しては、土地や建物が贈与される場合や、住宅購入の際の資金援助を受けた時にこの税が対象となる点に留意しなければなりません。
贈与の総額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して、贈与税が課されるのです。この計算は、毎年1月1日から12月31日の期間で行われるため、「暦年課税」と呼ばれています。
平成27年からは、贈与税の税率は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の2カテゴリーに分かれるようになりました。
特例贈与財産とは、18歳以上で、贈与を受けた年の1月1日時点の状況を基に、直系尊属(例:父母や祖父母)からの贈与として計算される資産のことを指します。
<一般贈与財産用(一般税率)>
| 課税価格範囲(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | – |
| 200万円超〜300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超〜400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超〜6,000万円以下 | 30% | 65万円 |
| 6,000万円超〜1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超〜1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
参考:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」を基に、当社にて作成。
関連記事:親子共有名義の不動産は生前贈与するべき?注意点について徹底解説!
共有不動産のリフォームで贈与税が発生する2つのパターン
共有名義の不動産をリフォームする場合でも、費用の負担の仕方によっては贈与とみなされ、贈与税の対象になることがあります。以下より、贈与税が発生する主な2つのパターンを紹介します。
パターン①:共有者の一人が費用を全額負担する
共有不動産に対して、一人の共有者が持分を超える範囲でリフォーム費用を負担すると、他の共有者に対する「経済的利益の供与」が生じたと判断されます。
一例を挙げると、夫婦で2分の1ずつ共有している住宅を500万円かけてリフォームし、その費用を夫が全額支払った場合、妻の持分(2分の1)に相当する250万円分について、妻が贈与を受けたと見なされる可能性があります。
税務上は、実際の金銭のやりとりではなく「実質的な利益の移転」が重視されるため、「夫婦だから」「親子だから」という理由では贈与税の対象外にはなりません。贈与額が110万円の基礎控除を超える場合は、原則として贈与税の申告・納税が必要になります。
パターン②:費用の負担割合と共有持分割合が一致していない
共有者それぞれが費用を負担したとしても、その割合が登記上の持分と異なっている場合は、その差額分について贈与と見なされる可能性があります。
こちらも例にとって考えてみましょう。兄弟で2分の1ずつ共有する家屋に対して、1,000万円のリフォームを行い、兄が800万円、弟が200万円を支出したとします。
この場合、兄は弟の持分に対して本来負担すべき額(500万円)を大きく上回る800万円を支出しているため、弟は差額の300万円を「経済的利益」として得たと評価され、贈与税の課税対象になる恐れがあります。
税務署は、このような「実態にそぐわない負担割合」に対しても贈与課税を適用する可能性があり、曖昧な口約束や善意の負担が後の税務リスクにつながることも珍しくありません。
【ケース別】共有持分をリフォームした際の贈与税の計算例
共有名義の不動産をリフォームする際、費用の負担割合が共有持分と一致していないと、税務上「贈与」と見なされる場合があります。
特に、夫婦や親子など近しい関係では「贈与のつもりはなかった」というケースが多いものの、税務署は実態で判断するため、申告・納税の必要が生じることもあります。
ここからは、贈与税の課税リスクが高まる代表的な2パターンと、それぞれの贈与税の計算方法を解説します。
ケース①:夫婦で共有名義の住宅をリフォームした場合の計算例
夫婦で共有している自宅をリフォームする際、「どちらか一方が費用を多く負担すること」は少なくありません。しかし、登記された持分割合と実際の費用負担割合が一致しない場合、その差額分が「贈与」とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性があります。
以下のような条件をもとに、具体的に贈与税がどの程度発生するかを見ていきましょう。
<前提条件>
- リフォームの総費用:800万円
- 夫婦の持分割合:夫 2分の1、妻 2分の1(登記済)
- 実際の費用負担:夫が700万円、妻が100万円
- 贈与税の基礎控除:年間110万円
- 贈与税率:一般贈与財産用(夫婦ともに20歳以上とする)
本来、持分割合が2分の1ずつであれば、費用も400万円ずつ負担するのが公平です。しかし、夫が700万円を支出し、妻が100万円しか負担していないため、妻は差額の「300万円」の利益を得たと見なされます。
この300万円から基礎控除110万円を差し引いた 190万円 が、贈与税の課税対象額です。190万円の課税対象額に対し、一般贈与財産用の税率を適用すると、以下のように算出されます。
<贈与税の計算式>
- 190万円 × 15% - 10万円 = 贈与税額 18.5万円
贈与税を回避・軽減したい場合は、最初から「夫400万円・妻400万円」など、持分割合に応じて費用を負担するのが原則です。どうしても一方が多く負担せざるを得ない場合は、あらかじめ契約書や金銭消費貸借契約を結ぶなどの工夫が必要になります。
ケース②:親が共有名義の住宅リフォーム費用を援助した場合の計算例
親からリフォーム費用の援助を受けることは、住宅取得や修繕の場面でよくあることです。しかし、その資金提供が共有名義の不動産に充てられた場合、名義上のもう一方の共有者に対しても「贈与があった」と見なされる可能性があります。
以下のような条件をもとに、具体的にどの程度の贈与税が発生するかを確認してみましょう。
<前提条件>
- リフォームの総費用:800万円
- 夫婦の持分割合:夫2分の1、妻2分の1(登記済)
- 実際の費用負担:夫の親が800万円を夫に援助(夫が全額負担)
- 贈与税の基礎控除:年間110万円
- 贈与税率:一般贈与財産用(夫婦ともに20歳以上とする)
まず、夫は親から800万円の贈与を受けたと見なされます。さらに、夫がリフォーム費用を全額支出し、妻が費用をまったく負担していないため、妻は夫から400万円の贈与を受けたと評価されます。
つまり、このケースでは2つの贈与が発生します。
- 親→夫:800万円の贈与
- 夫→妻:400万円の贈与
いずれも、年間110万円の基礎控除を差し引いた額に対して贈与税が課されます。
<親→夫の贈与税の計算式>
- 800万円 − 基礎控除110万円 = 課税対象額 690万円
- 690万円 × 30% − 65万円 = 贈与税額 142万円
<夫→妻の贈与税の計算式>
- 400万円 − 基礎控除110万円 = 課税対象額 290万円
- 290万円 × 20% − 25万円 = 贈与税額 33万円
このように、一見すると親子間の援助に見える取引でも、配偶者にまで贈与税が課税されるリスクがあります。
贈与額が多額になるほど税負担も大きくなるため、リフォーム費用の支援を受ける場合は、「持分割合に応じた資金の配分」や、「住宅取得等資金の非課税制度の活用」などを視野に入れて計画的に進めましょう。
関連記事:共有持分を贈与する際の「贈与税の計算方法」をわかりやすく解説!
共有持分のリフォームによる贈与税を軽減する方法
共有名義の不動産をリフォームする際、費用負担の偏りによって贈与税が発生する可能性があります。ただし、事前に対策を講じておけば、税負担を抑えることも可能です。
ここからは、贈与税の発生を避けたり軽減したりするために有効な5つの方法をご紹介します。
- 事前に持分を整理しておく
- リフォーム後に持分を引き取って精算する
- 資金提供は贈与でなく「貸付」として契約する
- 非課税制度を活用する
- 贈与額を基礎控除の範囲内に抑える
それぞれ個別にみていきましょう。
事前に持分を整理しておく
リフォーム費用を誰がどれだけ負担するのかが、登記上の持分割合とズレていると、税務上「贈与」とみなされる可能性があります。これを避けるには、あらかじめ持分を調整しておくことが有効です。
具体例を挙げると、建物を夫婦で2分の1ずつ所有していても、夫が全額リフォーム費用を出す場合、夫の持分を6割や7割に増やしておけば、支出に見合った所有となり、贈与とは判断されにくくなります。
この方法をとる場合は、以下の点に注意が必要です。
- 登記変更のため、他の共有者との合意が前提
- 持分の移転には登録免許税(評価額×2%)がかかる
- 評価額が低い築古物件などでは節税効果が出やすい
贈与税の発生を防ぎつつ、登記上も明確にしておきたい場合に、現実的な対策となります。
関連記事:持分移転登記とは?手続き方法や費用、リスクについて解説
リフォーム後に持分を引き取って精算する
リフォーム完了後に費用を多く負担した側が、もう一方から持分を譲り受ける方法もあります。これは現金をやり取りせず、不動産の権利で“代わりに精算”する形です。税務上は「代物弁済」として扱われる可能性があります。
この手法では、次のポイントが判断軸になります。
- 移転される持分の評価額と、実際の費用負担が釣り合っているか
- 代物弁済であることを示す契約書などがあるか
もし評価額と支出額が大きくズレていれば、その差額は贈与とされる可能性が高くなります。逆に、費用と持分のバランスが妥当であれば、課税リスクを抑える有効な手段といえます。
資金提供は贈与でなく「貸付」として契約する
親や配偶者がリフォーム費用を負担する場合でも、それを「贈与」ではなく「貸付」として扱えば、贈与税の対象外となる可能性があります。ただし、形式だけでなく、実質的に貸付と認められることが必要です。
具体的には、以下のような点が確認できれば、貸付として税務上認められやすくなります。
- 金銭消費貸借契約書が作成されている
- 利息や返済スケジュールが明記されている
- 実際に返済が行われている記録がある(通帳など)
これらが不十分な場合、税務署から贈与と判断されるリスクがあります。貸付として扱うなら、契約書の整備と返済実態の記録は欠かせません。
非課税制度を活用する
一定の条件を満たす場合、親や祖父母からのリフォーム費用の援助については「住宅取得等資金の非課税制度」を利用できることがあります。非課税で受け取れる上限額は年ごとに異なりますが、制度を使えば大きな節税につながります。
この制度が使えるのは、以下のような場合です。
- 贈与者が直系尊属(父母・祖父母)
- 受贈者が18歳以上の子や孫
- 対象が住宅の取得・新築・増改築であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税申告を行うこと
なお、「子→親」への援助には適用されない点や、年ごとに制度内容が変わる点には注意が必要です。利用を検討する際は、最新の国税庁サイトで確認しましょう。
贈与額を基礎控除の範囲内に抑える
贈与税には「基礎控除」があり、1年間で110万円までの贈与であれば申告や納税の必要はありません。リフォーム費用の援助も、この範囲に収まれば課税対象にはならないため、少額の支援であればこの制度を利用するのが現実的です。
ただし、以下の点には注意しましょう。
- 年間110万円の枠は「1月1日~12月31日」で集計される
- 他の贈与(学費・生活費など)も合算される
- 複数年に分けた援助は「定期贈与」とみなされる可能性がある
「少額なら問題ない」と安易に考えず、他の贈与履歴も含めて冷静に判断することが大切です。
共有持分でお悩みなら「ワケガイ」にご相談ください!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有名義不動産など訳あり物件の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。
「共有者の一方がリフォーム費用を負担したせいで贈与税が発生してしまった」「工事内容で揉めて売却が進まない」といった、共有持分のリフォームにまつわるトラブルにも対応可能です。
ワケガイでは、共有持分だけを単独で買い取ることも可能で、買取後の処理も専門の士業と連携して進めます。共有名義不動産に関する煩雑な問題を、スムーズに現金化したい方は、お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
共有名義の不動産をリフォームする場合、持分割合に応じた費用負担を原則とし、これを逸脱すれば贈与と見なされる可能性があります。特に、夫婦間や親子間の援助は気軽に行われがちですが、税務上は「善意」では済まされません。
対策としては、「契約書で貸付扱いにする」「贈与額を基礎控除内に収める」「非課税制度を活用する」など、具体的な法的・税務的手続きを事前に講じておく必要があります。
また、金銭のやりとりだけでなく、持分移転の登記や名義変更の有無も税務リスクに影響します。トラブルや課税リスクを未然に防ぐためにも、税理士や司法書士と相談しながら、慎重に手続きを進めましょう。