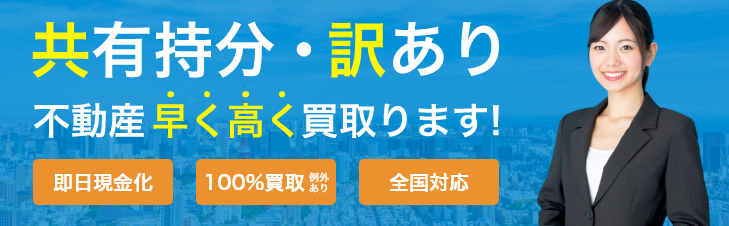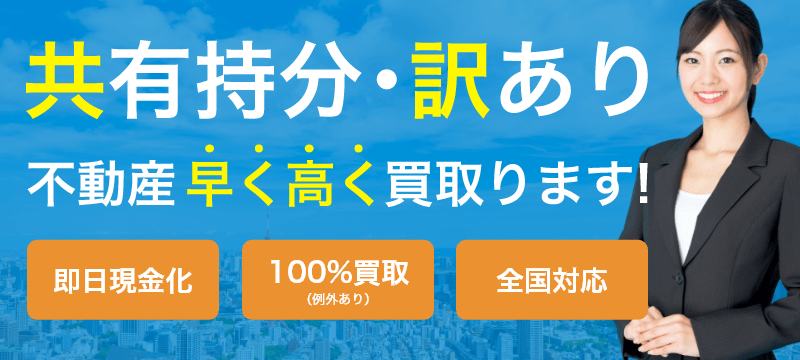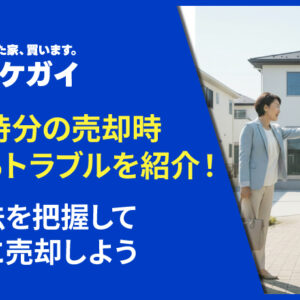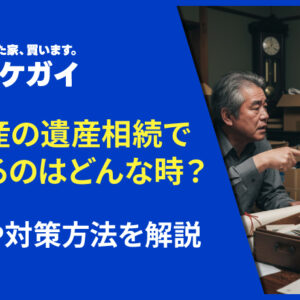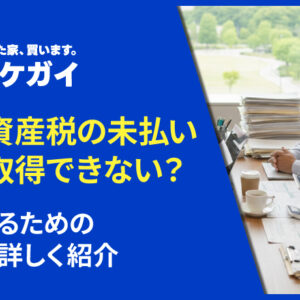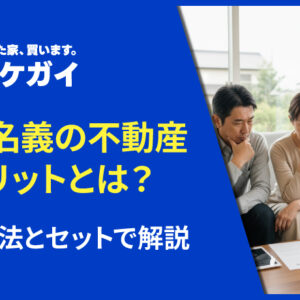不動産の共有持分を親族や配偶者に譲りたいと考えたとき、「贈与税がどれくらいかかるのか」「計算方法はどうなっているのか」といった疑問や不安が生じがちです。
共有持分は通常の不動産とは異なり、分割された権利であるため、その贈与には特有の税務上の注意が求められるもの。その際に正確に理解しておきたいのが「共有持分の贈与税とその計算方法」です。
共有持分の贈与税とは、持分を無償で譲渡した際に受贈者が負担する税金のことで、評価額や贈与の形式によって税額が大きく変わる場合があります。
そこで本記事では、共有持分を贈与する際に贈与税が発生する条件や、具体的な評価・計算方法、節税のポイントまでを丁寧に解説します。
目次
共有持分の贈与税がかかる条件
共有持分を無償で譲り渡すと、その受け手には一定の条件のもとで贈与税が課されることになります。共有不動産であっても、権利の移転が明確になされ、かつ贈与を受けた側がそれを自主的に受け入れている場合、贈与として認定されるのが原則です。
贈与税の課税対象となる主な条件は、次のとおりです。
<共有持分の贈与税がかかる条件>
- 所有権の無償移転があったこと
- 受贈者の意思に基づいて共有持分を受け取っていること
- 贈与された持分の評価額が、年間110万円の基礎控除を超えていること
(参考:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)
この「110万円」という基準は、贈与税における基礎控除額とされており、これを超える贈与について初めて課税が行われます。
評価額が110万円以下であれば、贈与税の申告も納付も必要ありませんが、たとえ1円でも超えれば、その超過分に対して累進課税が適用されます。
とくに共有持分の贈与は、親子や配偶者といった近しい間柄で行われるケースが多く、一定の要件を満たせば「配偶者控除」などの非課税措置が使えることもあります。
関連記事:共有持分になっている土地を贈与する場合に知っておくべき税金関係の基礎知識
関連記事:親子共有名義の不動産は生前贈与するべき?注意点について徹底解説!
関連記事:共有持分をリフォームする際は要注意!贈与税を回避する方法をわかりやすく解説
共有持分の贈与税の計算方法
贈与税の算定は、贈与された共有持分の評価額を知ることから始まります。評価には、固定資産税評価額や路線価といった基準が用いられ、そこに贈与する持分割合を乗じて、課税対象額を導き出します。
具体的な計算の流れは、以下のとおりです。
<贈与税の計算の流れ>
- Step1:固定資産税評価額 × 贈与する持分割合 = 持分の評価額
- Step2:持分の評価額 − 基礎控除110万円 = 課税対象額
- Step3:課税対象額 × 税率 − 控除額 = 贈与税額
たとえば、固定資産税評価額2,000万円の不動産を1/2だけ贈与する場合、その評価額は1,000万円。ここから基礎控除110万円を差し引いた890万円が課税対象となり、贈与税の速算表に基づき税額が決定されます。
なお、税率は課税額の大きさに応じて10%から最大55%まで段階的に上昇します。負担額を左右するのは評価額と課税方式の選択であり、暦年課税と相続時精算課税では大きく取り扱いが異なります。
そのため、実際の贈与に際しては、評価方法や家族関係に応じた特例の有無も踏まえて、早めに税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
(参考:総務省「固定資産税」)
共有持分の「贈与税評価額」の調べ方
前述のとおり、評価額の算出方法には、路線価方式と倍率方式の2つがあります。どちらの方式を使用するかは、その不動産の所在地によって決まります。
それぞれの算出方法について、以下より解説します。
①:路線価方式による算出
路線価方式は、主に市街地の宅地で用いられる評価手法です。国税庁が公表する「路線価」を基に、1平方メートルあたりの土地価格を算出し、それに土地の面積を掛けることで評価額を求めます。(参考:国税庁「路線価」)
ただし、土地の形状や奥行き、接道状況などによっては補正が必要になります。たとえば、奥行きが極端に短い・長い場合には「奥行価格補正」、形がいびつな場合には「不整形地補正」などが適用されることもあります。
共有持分の評価も、不動産全体をこの方式で評価したうえで、持分割合を掛けて算出するという流れになります。
②:倍率方式による算出
前述のとおり、倍率方式は路線価が設定されていない地域、特に郊外や農村部で多く用いられます。この方式では、不動産の固定資産税評価額に対して、国税局が定めた所定の倍率を掛けて評価額を算出します。
算出された不動産全体の評価額に対して、贈与された共有持分の割合を乗じることで、課税対象となる持分の金額が明らかになります。倍率は地目ごと・地域ごとに異なり、また毎年更新されるため、評価の際には最新の倍率表を確認することが大切です。
関連記事:共有持分を評価する方法とは?売却・譲渡時の計算方法を解説
共有持分の贈与税を節税する方法
不動産の贈与税を節税するためには、さまざまな制度や特例を活用することが効果的です。ここでは、代表的な4つの方法を紹介します。
- 相続時精算課税制度を活用する
- 住宅取得等資金贈与の特例を使う
- 配偶者控除(おしどり贈与)を利用する
それぞれ個別にみていきましょう。
相続時精算課税制度を活用する
より高額の持分を一括で移転したい場合には、「相続時精算課税制度」の適用が検討に値します。この制度を選択すると、2,500万円までの贈与が非課税扱いとなり、令和6年以降は基礎控除110万円が追加されるため、最大2,610万円までの贈与が非課税で行えます。
(参考:国税庁「相続時精算課税の選択」)
ただし、一度制度を選択すると撤回ができず、その後の贈与もすべて精算課税方式で扱われることになります。
また、将来の相続時にこの贈与分が相続財産に加算されるという点も見落としてはなりません。共有持分に限定せず、広く資産移転を見据えた設計が求められる制度といえるでしょう。
関連記事:共有持分を遺言書で相続させることは可能?効力や手続きの流れを詳しく紹介
住宅取得等資金贈与の特例を使う
子や孫が自己の居住用住宅を取得するにあたり、資金として共有持分を贈与する場合には、「住宅取得等資金の非課税特例」が利用できる可能性があります。一定の性能や条件を満たした住宅であれば、最大で3,000万円まで非課税となる余地があるため、有効な節税策となります。
(参考:国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」)
もっとも、この制度は共有持分にもそのまま適用されるわけではなく、実際に居住する目的での贈与であること、贈与後すみやかに入居することなど、複数の条件が課されています。形式的な名義移転だけでは非課税の適用は認められない点に、十分注意が必要です。
配偶者控除(おしどり贈与)を利用する
最後に、婚姻期間が20年以上の配偶者間であれば、「配偶者控除」を利用することで、2,000万円までの居住用不動産の贈与を非課税とすることができます。共有持分についても、居住用建物の持分であれば対象となります。
(参考:国税庁「配偶者控除」)
この制度は、将来的な相続税対策としても有用ですが、適用は一生に一度限りです。また、贈与の対象となる不動産に実際に居住していることが要件となるため、形式的な贈与では認められません。節税効果が大きい分、運用には慎重さが求められる制度といえるでしょう。
関連記事:共有持分の贈与税を節税する方法とは?具体的な対策を紹介
共有持分の贈与税の申告手順
共有持分を贈与した場合、その評価額が基礎控除を超えると、原則として贈与税の申告が必要となります。
申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に行う必要がありますが、共有不動産の性質上、登記や書類の準備において他の共有者との連携も欠かせません。
ここでは、実務的な流れに沿って、申告までの一連の手順を整理しておきましょう。
- 手順①:贈与内容の合意と登記手続きの確認
- 手順②:必要書類の収集と整理
- 手順③:申告書の作成と提出
次項より、詳しく解説します。
手順①:贈与内容の合意と登記手続きの確認
まず行うべきは、贈与の合意内容を明文化することです。特に共有持分の場合、贈与者と受贈者の間で交わされた口約束だけでは、後々のトラブルのもとになりかねません。
贈与契約書を作成し、贈与の事実、日付、対象の不動産、共有持分の割合などを正確に記載しておくことが重要です。
あわせて、贈与によって登記の変更が必要となるため、法務局での移転登記手続きも視野に入れます。この時点で他の共有者の承諾は法律上不要ですが、後の管理・処分に支障をきたさないよう、共有者間で情報共有しておくことが望ましいでしょう。
手順②:必要書類の収集と整理
申告に際しては、以下のような書類の準備が必要となります。
- 贈与契約書の写し
- 登記事項証明書(不動産の名義変更が確認できるもの)
- 固定資産税評価証明書
- 評価計算書(路線価図や倍率表など)
- 贈与者・受贈者の戸籍謄本や住民票
特に固定資産税評価額や路線価等に基づいた評価額算出が正確でなければ、過少申告を疑われるおそれがあるため、評価方法には注意が必要です。評価額に迷いがある場合は、早めに税理士や司法書士など専門家の助言を仰ぐべきでしょう。
手順③:申告書の作成と提出
申告書は国税庁の様式に従って作成します。主に「贈与税申告書(第一表)」を用い、贈与財産の種類・価額、贈与者と受贈者の情報、適用する特例の有無などを記載します。
共有持分の場合、評価額は「不動産全体の評価額 × 贈与した持分割合」によって求められるため、該当欄には正確な面積や割合を記載しなければなりません。
また、配偶者控除や住宅取得等資金の特例を用いる場合は、別表の添付が必要となります。
完成した申告書と必要書類一式は、受贈者の納税地を所轄する税務署へ提出します。提出は郵送でも可能ですが、窓口での提出であれば不備の有無をその場で確認してもらえるため、安心感があります。
共有持分の贈与税に関する注意点
不動産の贈与税には、以下のような注意点があります。
- 親子間でも贈与税はかかる
- 登録免許税・不動産取得税も別途発生する
- 7年以内の贈与は相続税の対象になる可能性がある
次項より、詳しく解説します。
親子間でも贈与税はかかる
贈与が親子間や夫婦間など近しい関係で行われる場合でも、税務上は第三者間の取引と同様に扱われます。たとえ相続対策の一環であっても、一定額を超える贈与には課税がなされます。
共有持分においても同様で、たとえば親子で共同所有していた不動産の持分を一方が他方に譲る場合、金銭の授受がなくても「贈与」として扱われ、贈与税の対象となります。特例税率の適用や配偶者控除といった措置があるものの、その適用条件や限度額には注意が必要です。
特に注意したいのは、持分を形式上「放棄」したと見せかけて、実質的に他の共有者の権利を増やすケースです。このような場合も、税務署は贈与と判断する可能性があります。
登録免許税・不動産取得税も別途発生する
不動産の贈与を受けた場合、贈与税以外にも税金がかかることがあります。まず、所有権移転登記を行う際に登録免許税が発生します。この税金は、原則として不動産の固定資産税評価額の2%です。
(参考:国税庁「登録免許税の税額表」)
さらに、不動産取得税も課されます。これは、不動産を取得した際にかかる地方税で、通常は固定資産税評価額の3%(不動産の場合は軽減措置により1.5%)となっています。
(参考:総務省「不動産取得税」)
これらの税金は、贈与税とは別に納付する必要があるため、総額でかなりの負担になる可能性があります。
7年以内の贈与は相続税の対象になる可能性がある
贈与から7年以内に贈与者が亡くなった場合、その贈与財産が相続財産に加算される可能性があります。これは「贈与加算」と呼ばれる制度で、相続税の課税対象を拡大する目的があります。
具体的には、相続開始前3年以内の贈与財産は全額、3年超7年以内の贈与財産はその価額に一定の割合を乗じた金額が、相続財産に加算されます。この制度により、生前贈与による相続税対策が一定程度制限されているのです。
共有持分のように流動性が低く、評価に幅が出やすい財産では、加算による相続税額の変動も無視できません。とりわけ、贈与後に登記を行っていなかった場合や、名義上の変更が未反映の場合には、課税の対象と認定されるリスクもあります。
(参考:国税庁「相続税の税率」)
贈与や放棄で持分整理をお考えなら「ワケガイ」にご相談ください!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や権利関係が複雑な不動産に特化した買取サービス「ワケガイ」を提供しています。
贈与や放棄による整理を検討していても、相手の同意が得られない、税金や登記の手続きが煩雑など、現実には思うように進まないことも多いものです。
ワケガイでは、そうした事情を抱えた共有不動産を、共有者全員の同意が揃っていなくても、持分のみで買取することが可能です。
共有持分の評価や登記、税務面にも精通した専門家と連携しながら、迅速かつ確実な対応を行っております。まずは物件の状況をお聞かせください。
お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
共有持分の贈与は、不動産全体の贈与とは異なり、持分割合に応じた評価と税務処理が求められます。贈与税の負担は、評価額の設定や課税方式の選択によって大きく変わるため、軽視できません。
また、節税を意識するなら、基礎控除や配偶者控除、相続時精算課税制度といった特例制度を戦略的に活用することが重要です。これにより、納税額を最小限に抑えながら、円滑な贈与が実現できます。
贈与は家族間の信頼関係に基づくものである一方で、税務上のリスクも伴います。評価額の算出や税額の見積もりには専門的な判断が必要なため、事前に税理士などの専門家に相談し、適切な対応を心がけましょう。